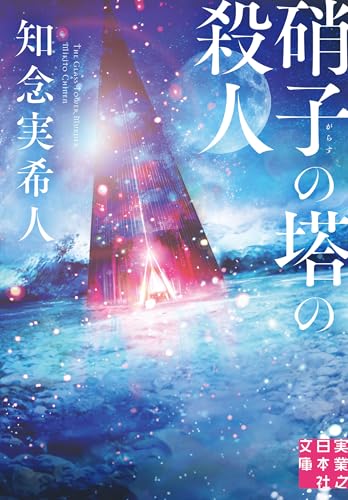この記事は、
【殿堂入り】最強に面白い国内ミステリー小説おすすめ50選【名作選】
【2024最新版】究極に面白い国内ミステリー小説おすすめ50選【最近の新刊】
の二つの記事でご紹介したミステリー小説を、短く簡潔にまとめ、リストにしたものである。
あちらの記事はわたしが作品について長々喋っているので、読むのに時間がかかると思う。
なので、あなたの話はいいから面白いミステリー小説を早く知りたい、という方はこの記事を参考にした方が効率がいいです。


1.綾辻行人『十角館の殺人』
──すべては、あの一行でひっくり返る
孤島の奇妙な館で、ミステリ研の学生たちが一人ずつ殺されていく。外部侵入の形跡なし、つまり犯人はこの中にいる……が、そこに本土パートが絡んできて様子が一変。
名前のトリック、視点のズレ、建物そのものが仕掛けの一部。ぜんぶ《あの一行》に向かって伏線が爆走していく。これが新本格の開幕作だ。
この一作がなければ、新本格という物語は始まらなかった。
 四季しおり
四季しおり記憶を消して何度でも読みたいミステリNo. 1。


2.綾辻行人『時計館の殺人』
──時と空間に閉じ込められる快感
108個の時計に囲まれた洋館で、オカルト集団が降霊術を試みた結果、次々と死体が転がることになる。
閉ざされた館、消えた霊能者、10年前の謎の死、そして現在進行形の殺人。
しかも、時計そのものがトリックに関わってくるという狂気の構造。論理もホラーも全部のせ、本格ミステリのフルコースである。
論理と幻想の完璧なミックス。館シリーズは、ここでひとつの頂点に到達した。



『時計館』は『十角館』の反転構造でもある。どちらを読んでも衝撃は保証付きだ。
3.島田荘司『占星術殺人事件』
──伝説の始発点
娘6人をバラして完璧な女を創る。そんな狂った計画を遺した日本画家が密室で殺され、その後、実際に6人の女性のバラバラ遺体が全国で見つかる。40年以上放置されたこの猟奇事件に、占星術師の名探偵・御手洗潔が挑む。
驚愕のトリック、正攻法のフェアプレイ、クセ強探偵、読者への挑戦状まで完備。本格ミステリが好きなら絶対に外せない一本だ。
この一冊で新本格が始まった。伝説はここから。



常識を疑え、という本格ミステリの鉄則を、トリックの根幹で証明してみせた神作。


4.島田荘司『斜め屋敷の犯罪』
──世界がわずかに傾いたとき、完全犯罪が完成する
北海道の吹雪の中、建物全体が傾いて建てられた奇怪な館「斜め屋敷」で連続密室殺人が発生。足跡、ゴーレム、収集癖、どれもがバラバラに見えて、すべてが「傾き」に集約されていく。
探偵不在の不安定な空間に、終盤ついに御手洗潔が現れ、物理トリックの迷宮を鮮やかに斬って捨てる。舞台とトリックががっちり噛み合った、空間型本格ミステリの極致。
傾いてるのは館だけじゃない。常識も、重力も、読者の感覚もだ。



傾いているという一点だけで、ここまで壮大な論理トリックを作った執念がすごい。
5.『双頭の悪魔』有栖川有栖
──真実はどこで交差する?
豪雨で孤立した二つの村、それぞれで同時に発生した殺人事件。EMCの仲間たちは川の両岸でバラバラに推理を始めるが、互いの情報は一切伝わらない。
読者だけが両視点を追える神のポジションに立ち、三度の挑戦状を経て、重層的な謎と伏線が一気に収束するラストに震える。シリーズ随一の完成度を誇る傑作。
これぞ論理パズルの快感。脳みそが歓喜する。



あらゆる有栖川作品の中で、わたしが一番好きなのがこれ。
6.森博嗣『すべてがFになる』
──密室と論理と天才が、すべてをFに変えるとき
孤島の研究所、隔離された天才博士、そしてウェディングドレス姿のバラバラ死体。すべてが異常で、すべてが理にかなっている。完璧すぎる密室の謎に、犀川と萌絵が挑む。
トリックはシンプルなのに、設定とロジックが異常に強い。真賀田四季という怪物の存在感が、事件と物語のすべてをねじ曲げてくる。
理系ミステリという言葉の意味を根本から塗り替えた、鮮烈すぎるデビュー作。
ミステリは論理だ。でも、それだけじゃ足りないということも教えてくれる。



真賀田四季というキャラクターは、森博嗣自身の全作品において最も神格化されている存在のひとつ。


7.我孫子武丸『殺戮にいたる病』
──狂気の愛と倒錯の論理が交錯する、国産サイコ・ミステリの到達点
若い女性ばかりを狙った連続猟奇殺人。犯人はネクロフィリア嗜好を持つ蒲生稔。彼の「永遠の愛」を求める歪んだ論理、母・雅子の視点、事件を追う元刑事・樋口の視点が交錯しながら、徐々に凶行の全貌へ引き込まれていく。
暴力と性描写は過激だが、すべてが計算され尽くした構成の中にあり、終盤で物語の正体がひっくり返る瞬間は鳥肌もの。ホラーでもサイコでもなく、圧倒的にミステリである問題作だ。
読む人を選ぶが、刺さったときの破壊力は一生モノ。



終盤に訪れるたった一文が、物語全体の認識を根底から崩壊させる。油断すると死ぬ。
8.殊能将之『ハサミ男』
──「おまえは誰だ?」がすべてをひっくり返す
連続猟奇殺人犯ハサミ男が、次の標的に迫ったその瞬間、ターゲットが何者かに自分と同じ手口で殺される。模倣犯を追うことになった本物のハサミ男の一人称視点で進む物語は、読者の認識そのものを裏切るトリックの塊。
語りの構造、違和感の配置、ラストの反転。どれもが見事で、読後しばらく呆然とするタイプの一作。メフィスト賞受賞も納得の、一人称ミステリの金字塔。
「やられた」の快感を味わいたいなら、まずはこの罠にかかってみるべし。



実は、主人公のある一文で気づける人もいる。が、99%は見落とすので安心してくれ。
9.乾くるみ『イニシエーション・ラブ』
──それは恋の話だったはずだった。あのラストまでは。
80年代後半の静岡と東京を舞台に描かれる、大学生と歯科助手のちょっとぎこちない青春ラブストーリー。甘酸っぱくて懐かしくて、まるでトレンディドラマみたいな展開だ。ところが最後の二行ですべてがひっくり返る。
優しい語り、何気ない描写、そのすべてが仕掛けだったと気づいたとき、読者は初めて真相を知ることになる。二度読ませることを前提に組み立てられた、ミステリ的構成の妙が光る傑作。
その恋の名前が「ミステリ」だと気づくのは、読み終えたあとである。



実は絶対に映画化できないと言われていた。なのに映画化された(無事とは言ってない)。
10.道尾秀介『向日葵の咲かない夏』
──その夏、死んだはずの同級生が蜘蛛になって帰ってきた
終業式の日、クラスメイトのS君が首を吊って死んでいた……はずなのに、死体は跡形もなく消え、数日後、彼は蜘蛛の姿で「殺された」と語りかけてくる。小学四年生の語り手・ミチオの目を通して描かれる世界は、どこまでも奇妙で不安定だ。
子どもの純粋さと妄想、曖昧な現実、歪んだ大人たち。じっとりとした違和感が終始まとわりつき、ラストで視界が裏返る。すべてを語りきらない構成が、逆に強烈な読後の余韻を残す一冊。
信じていたものの足元が、ふと崩れるあの感覚が忘れられない。



道尾秀介の出世作であり、彼の「曖昧な現実」というテーマがここで確立された。
11.伊坂幸太郎『アヒルと鴨のコインロッカー』
──途中参加であることの切なさと優しさが、すべてをつなぐ
「一緒に本屋を襲わないか?」そんな奇妙な誘いから始まる物語は、過去と現在、真実と誤解、死と赦しをめぐって交差していく。
まったく無関係に見えた点が伏線となって繋がり、「君は、物語に途中参加しただけなんだ」の一言で景色が反転する構造美。ミステリでありながら、人間のやるせなさと優しさをきちんと描いた、伊坂作品の真ん中にある傑作。
読み終えたあと、「タイトルの意味」が胸に静かに沈んでくる。



大好きな小説が実写映画化すると複雑な気持ちになるが、この作品は映画も素晴らしかった。
12.歌野晶午『葉桜の季節に君を想うということ』
──景色が反転するその瞬間、すべての言葉が意味を変える
霊感商法の調査依頼を受けた成瀬将虎は、自殺未遂の女性・さくらと出会い、奇妙な恋に落ちていく。調査と恋愛、二つの線が交錯し、やがて物語は見えない壁を越えて裏側へ転がる。
読者の先入観を利用した大胆かつ精密な構成、そして最後の一文で世界がひっくり返るあの感覚は、一度読んだら忘れられない。二度読ませる前提で仕込まれた、圧倒的トリックの妙。
「何を読んでいたのか」ではなく、「誰として読んでいたのか」を問われる小説。



タイトルがすでにネタバレ、という説もあるが、読了後にしか意味が届かない構造がすごい。


13.歌野晶午『密室殺人ゲーム王手飛車取り』
──「これはゲームです」と言いながら、人はどこまで本気になれるのか
ネットのチャットルームで、奇妙なハンドルネームの5人が「殺人事件」のシナリオを持ち寄って推理ゲームを楽しむ。が、それは単なる創作ではなく、全員が実際に殺人を犯しているという恐怖のリアルゲームだった。
本格ミステリの伝統トリックを盛り込みつつ、現代という匿名性の空間が孕む倫理の崩壊まで描き切る。誰が誰なのか、何が現実なのか、読み進めるほど混乱し、そして最後に正体が暴かれる快感。
これは現代の名にふさわしい異色作だ。
ミステリの顔をした悪夢のようなゲーム。気づいたときには、もう逃げられない。



続編の『密室殺人ゲーム2.0』『密室殺人ゲーム・マニアックス』もめちゃくちゃ面白いのでぜひ。
14.米澤穂信『儚い羊たちの祝宴』
──その優雅な言葉遣いの奥に、どす黒い悪意が潜んでいる
上流階級の子女たちが集う文学サークル「バベルの会」で起きる五つの事件を描いた連作短編集。どの物語も上品で静謐な語り口なのに、読み進めるほど不穏な気配が立ち上ってくる。
理知と品格に彩られた世界の底に、異常な執着と冷酷な論理が滲み出し、最後には読者の倫理観ごと裏返してくる。毒の盛り方があまりに巧妙で、気づいたときにはもう手遅れだ。
イヤミスという言葉がまだ浸透していない時代に、既にその完成形がここにあった。



全編通して《ある人物》がゆるやかに浮上してくる構成は、何気に超技巧的。


15.米澤穂信『氷菓』
──やらなくてもいいことの中に、たまに一生モノの謎がある
省エネ主義の高校生・折木奉太郎は、好奇心のかたまりのような少女・千反田えるに巻き込まれ、「古典部」でささやかな日常の謎を解いていくことになる。文化祭、図書室、旧校舎、古い文集。
殺人事件は起きない。でも、誰かの胸に残っていた小さな違和感が、いつしか人の記憶や痛みの核心に変わっていく。
『氷菓』という言葉の意味が明かされるラストには、青春の苦さと優しさがきれいに溶け込んでいる。
「日常の謎」という言葉が一般化する前から、その可能性を広げていた作品。



実は原作とアニメで〈あるセリフ〉のニュアンスが微妙に違う。どちらも泣ける。
16.西澤保彦『七回死んだ男』
──ループは味方じゃない。推理だけが唯一の武器だ。
「同じ日を九回繰り返す」という特異体質を持つ高校生・久太郎は、祖父が殺される日に何度も放り込まれ、犯人探しに挑む。死因も状況も毎回変わるなか、少しずつ証拠を集め、仮説を立て直し、論理の糸を手繰っていく。
タイムループSFでありながら、仕掛けの中心にあるのはあくまで本格ミステリのロジック。周回するごとに伏線が刺さり直す構造は圧巻で、「時間」と「推理」の相性の良さをこれ以上なく証明してみせた傑作である。
死に戻り×本格ミステリというアイデアを、1995年の時点でやってのけた先駆的作品。



「繰り返し」がここまで熱くて理詰めだなんて……。
17.貫井徳郎『慟哭』
──正義と狂気、信仰と喪失。その境界が音もなく崩れていく
連続幼女誘拐事件を追うエリート管理官・佐伯と、娘を失い宗教に救いを求める松本。交互に語られる二人の物語は、まったく別の線として進むように見えて、読者の認識ごと終盤に崩れ去る。
騙されたことにすら気づかないまま仕掛けに飲み込まれ、ラストには『慟哭』という言葉の意味を痛感させられる。構成美、心理描写、主題性。すべてが高密度に絡み合った、破壊力抜群の一冊。
これはトリックじゃない。人の良心そのものを撃ち抜く構造でできている。



伏線は、あくまで存在しない違和感として置かれている。気づける人はほとんどいない。
18.筒井康隆『ロートレック荘事件』
──違和感は、最初からずっとそこにあった
瀟洒な洋館「ロートレック荘」に集う美男美女、優雅なバカンス、そして突如始まる連続殺人。王道のクローズドサークルに見えて、その実、読者の目と脳を徹底的に撹乱するトリックが仕込まれている。
視点操作、時制のズレ、情報の省略……どれもフェアすぎて騙されるタイプのやつだ。会話の妙な歯切れの悪さも、唐突な描写も、すべてがラストの一撃のための伏線。
冷酷なまでに構造一本勝負で挑んでくる、筒井流・超異端本格。
騙されたと気づいた瞬間、すべての違和感が一列に並ぶ。



作者自身が「実験的」と語る一作だが、結果としてミステリ界をざわつかせた超本格になった。
19.倉知淳『星降り山荘の殺人』
──これはフェアです、全部提示しています……が、信じていいとは言ってない
雪に閉ざされたキャンプ場で発生した殺人事件。クセの強い面々とともに閉じ込められた星園詩郎は、観察眼を武器にマネージャー杉下とともに謎に挑む。
作中で丁寧に案内される親切設計の推理ゲームは、実はとびきり巧妙な目くらまし。
メタ構造と伏線が精密に組み上げられ、終盤には立ち位置も視点も根こそぎひっくり返される。王道のクローズドサークルをここまで楽しく、ここまで華麗に騙してくれるとは。
油断大敵。フェアを信じる者ほど、いちばん深く落ちる。



全部書いてあるのに、なぜ騙されたのか? 読後、もう一度最初から読んでしまう。


20.江戸川乱歩『江戸川乱歩傑作選』
──エログロも本格も、すべてはここから始まった。
日本ミステリの祖・江戸川乱歩の初期の傑作全部盛りな短編集。「二銭銅貨」「心理試験」など論理派の名作でガッチリつかんでおきながら、「人間椅子」「鏡地獄」「芋虫」では問答無用の変態描写で突き落としてくる。とにかく濃い。
覗き、潜り、狂い、歪み……常識の外側を覗きたいならうってつけ。メタオチも多めで、読み終わっても安心させてくれないのが乱歩流。江戸川乱歩を読むならまずこの一冊から。
美と狂気と変態と論理。探偵小説という言葉を日本に根付かせたのが、乱歩だった。



『人間椅子』の読後、椅子に座るたびちょっと気にしてしまうのは誰もが通る道。


21.泡坂妻夫『乱れからくり』
──偶然か? それとも仕掛けか? 隕石から始まる超精密ミステリ
玩具会社役員が隕石で死亡、というありえない展開から先が本番。からくり屋敷、五角形の迷路、連続殺人。全部が一族の仕組まれた運命に噛み合っていく。
泡坂妻夫の職人芸が冴えわたる、精密機械のように構築された一冊。機構(メカ)好きもミステリ好きも大歓喜。
隕石で始まり、からくりで終わる。これぞミステリの機構美。



泡坂妻夫=手品師でありミステリ作家。つまり、騙しの天才である。
22.青崎有吾『体育館の殺人』
──アニメオタク高校生が、論理ですべてを撃ち抜く
雨の放課後、旧体育館で放送部の部長が刺殺される。舞台はがっちり施錠された密室。容疑者はひとり。警察は早々に決めつけモードだが、卓球部の後輩・柚乃は納得できず、学園にひきこもる変人・裏染天馬に助けを求める。
この裏染天馬こそ、アニメオタクにして論理の申し子。ひとつひとつ証拠を拾い上げ、丁寧に論理を組み立てて、ラストに「読者への挑戦状」まで叩きつけるガチ本格スタイルがたまらない。
古典本格の要素を詰め込みつつ、舞台は学校、探偵は変人。読者への挑戦状まで完備した、ガチガチのフェアな論理バトル。
デビュー作にして鮮烈すぎるフェアプレイ宣言。青崎有吾は最初から覚悟を決めていた。



とにかく、裏染天馬の論理的推理が最高のひとこと。犯人を絞り込んでいく最後の推理シーンは圧巻。
23.東野圭吾『仮面山荘殺人事件』
──すべての顔が外れたとき、真相が姿を現す
雪に閉ざされた別荘に集められた8人。そして突然の銀行強盗による立てこもり。だが発生する殺人は、どう考えてもその強盗の仕業ではない。
外にも出られず、通報もできず、疑念だけが濃くなっていく密室状況で繰り出されるトリックは大胆かつ緻密。
舞台装置も動線も心理の動きもすべてが伏線で、終盤の反転はまさにタイトルに込められた「仮面」の意味を一気に反響させる構造美。純度の高い謎解きの快感が味わえる一作。
騙されたことに気づいた瞬間、もう一度最初から読み直したくなる。



東野圭吾の初期作品がやっぱり好きだ。
24.東野圭吾『ある閉ざされた雪の山荘で』
──演技か、現実か。その一線が吹雪の中で溶けていく
劇団の最終オーディションに参加した7人の男女が、雪に閉ざされたペンションで「殺人劇」の稽古に挑む。だが台本通りにメンバーが消えていくなか、芝居の中のサスペンスが、いつしか現実の不安にすり替わっていく。
虚構と現実、演出と殺意、その境界があいまいになる構成は、劇中劇という形式を見事に活かしたもの。伏線の回収と真相の提示も鮮やかで、ジャンル自体を舞台装置として使い切った意欲作である。
「殺人事件を演じる」が、これほど怖くて面白い舞台になるなんて。



東野圭吾初期の仕掛け系本格ミステリの代表格で、後年の重厚路線とはまた違う顔が見える。
25.西村京太郎『殺しの双曲線』
──「双子がいる」と最初にバラして、なお騙してくる異端の本格
雪に閉ざされた山荘に、謎の招待状で集められた6人の男女。典型的なクローズドサークルと思いきや、冒頭で「双子トリックが使われている」と宣言される異例の展開。にもかかわらず、そこから先で何度も裏をかかれる。
誰が双子なのか、いつ入れ替わったのか、どこに嘘が仕込まれているのか。全ての行動、セリフ、存在そのものがグラグラ揺らぎ出す構造は圧巻。
ミステリの常識に一手かけて勝負してくる、初期西村の代表作である。
ネタをバラしても勝てるってどういうことだよ……と素直に感心する完成度。



トラベルミステリ以前の本格ガチ勢西村京太郎の代表格。
26.貴志祐介『クリムゾンの迷宮』
──このゲームに勝つ条件は、疑うこと。裏切ること。そして、生き残ること
目覚めた場所は、深紅の奇岩が連なる謎の荒野。傍らにあった携帯ゲーム機には「火星の迷宮へようこそ」。記憶を失った主人公・藤木は、他のプレイヤーたちと共に、生死を賭けたサバイバルゲームに巻き込まれていく。
どのルートを選び、誰と手を組むかで未来が変わるゲームブック形式の構造が秀逸で、疑心と暴力と知恵が入り乱れる展開は緊張感のかたまり。
裏切りも死も、すべてゲームのルール内。だがこのルールを作ったのは一体誰なのか。
人間の本性という名の凶器が、最初から最後まで突きつけられている。



ゲームブック形式+バトルロイヤルという構造は、後年のデスゲーム系作品にも大きな影響を与えた。
27.貴志祐介『青の炎』
──守るための殺意。それは希望か、それとも破滅か
湘南の町で母と妹と暮らす高校生・櫛森秀一は、元父親・曾根の突然の帰還によって、平穏な日々を奪われる。警察も法律もあてにならないと知った彼は、自らの手で完全犯罪を実行しようと決意する。
計画立案から犯行、そしてその後の崩壊までを、高校生の視点で克明に描いた倒叙ミステリであり、同時に胸に迫る青春悲劇でもある。
何が正義で、どこからが罪なのか。綿密な犯行計画の隙間に、揺れる感情と未熟さがにじみ出る。冷静に見えても、彼はまだ17歳なのだ。
罪と罰、そのすべてが青く燃える。こんなに切ない完全犯罪があるか。



大好きな作品なんだけど、最後が切なすぎて読み返すのがつらい……。でも読んじゃう……。
28.岡嶋二人『クラインの壺』
──この世界が本物だと、誰が証明できる?
大学生・上杉彰彦は、ある日突然、自作のゲームブックが高額で買い取られ、最新型VRシステム「クライン2」のテストプレイヤーに抜擢される。
触覚・嗅覚・味覚までも再現される仮想世界の中、美少女・高石梨紗とのプレイは順調に見えたが、やがて「今ここ」が現実なのか仮想なのか、境界が溶けていく。
これはゲームなのか、それとも現実そのものがゲームなのか? 五感、意識、自己認識すべてが崩壊していく不安定さが脳を侵食してくる。1989年発表とは思えない先見性と、スリリングな構成の巧さは圧巻。
現実からログアウトしたくなる、超没入型SFミステリ。怖すぎて最高。



岡嶋二人というペンネームは実は2人組作家(井上夢人と徳山諄一)。そのコンビ最終作でもある。
29.岡嶋二人『そして扉が閉ざされた』
──閉じた空間で暴かれるのは、嘘か、真実か、それとも……
旧友の死から三ヶ月後、男女四人が密室状態の核シェルターに閉じ込められる。「娘を殺した犯人は、この中にいる」──そんな一文を残して姿を消したのは、死んだ咲子の母親。頼れるのは互いの証言と、曖昧な記憶だけ。
外には出られない、情報も増えない、でも会話だけは続いていく。この限られたピースで少しずつ浮かび上がってくるのは、意外にも派手な動機やトリックではなく、ゆっくり腐っていた人間関係そのもの。
たった10畳の会話劇、なのに息が詰まるほどスリリングだ。
声を潜めた密室劇にこそ、いちばん深い闇が潜んでいる。



物理的トリックがないのに、最後の言葉の落とし穴で膝をつく読者、多数。
30.鮎川哲也『リラ荘殺人事件』
──カードが告げる次の死、その意味を論理で解き明かせ
芸大生たちが共同生活を送る学生寮「リラ荘」で、スペードのエースを手にした遺体が見つかる。これを皮切りに、トランプになぞらえた連続殺人が発生し、警察はアリバイと証言の迷宮に挑むことに。
犯人の動機や手口よりも、「なぜこの順番で?」「なぜこのカードなのか?」という意味づけと論理構築が作品の主軸。
派手などんでん返しはないが、粘り強いアリバイ崩し、多重解決、丁寧に積み重ねられた推理の組み立ては、これぞ正統派本格という仕上がり。手がかりとロジックの快感が詰まった、骨太ミステリ。
謎を解くとは、こういうことだと教えてくれる一冊。古典の名は伊達じゃない。



今のミステリに慣れた目で読むと、逆にこんなにも地に足がついた推理ものは新鮮に映る。
31.折原一『倒錯のロンド』
──語り手は誰だ、物語は誰のものだ、そして今どこにいる?
盗作されたと訴える青年、復讐の計画、語られる小説原稿、現れる別の語り手。現実と創作、原作者と盗作者、主観と客観の境界が、ページをめくるたびにひっくり返る。誰が語り、誰が見ていて、何が「真相」なのか。
作中作×入れ子構造×倒錯視点のトリプルパンチで、脳内の地面ごと持っていかれる。叙述トリックの名手・折原一の代表作にして、物語という形式そのものが仕掛けになっている一冊。
騙しの快感もここまで来ると芸術。倒錯したまま沈んでいく、その眩暈がたまらない。



叙述好き・メタ好きの終着点として、再読者があとを絶たない迷宮型小説の傑作である。
32.京極夏彦『魍魎の匣』
──「怪異」をロジックで解体する、知の怪物たちの饗宴
戦後東京。バラバラ殺人、少女の転落事故、怪しい宗教団体、そして謎の匣(はこ)。
どこかで繋がっていそうで、どう繋がるのかまったく見えない怪事件の数々を、それぞれ異なる視点を持つ男たちが追い、最後に古書店主にして陰陽師の京極堂が、すべてを理で断ち切る。
「憑き物落とし」とは、怪異に取り憑かれた世界を、知識と論理で正気に戻す儀式のようなもの。その過程で語られるウンチクの嵐も、最後にはとんでもない快感として収束していく。
匣とは何か、魍魎とは誰か、人間とはどこまで狂えるか。すべてを飲み込む濃厚な一冊。
物語を制圧する知の暴力。読んだあと、世界の見え方が変わってしまうレベル。



500ページを超えるウンチクの山が、ラスト数十ページで怒涛の快楽に変わる構成力が異常。
33.高木彬光『人形はなぜ殺される』
──人形が先に殺される。その意味がわかったとき、世界が反転する。
魔術ショーの道具として使われる予定だった人形の首が、鍵のかかった箱から忽然と消える。数日後、その演目に出演する予定だった女性が、首なし死体で発見される。
なぜ犯人は、人間を殺す前に、まるで儀式のように人形を同じ手口で破壊するのか?
怪奇趣味たっぷりの舞台装置に、がっつりロジックが仕込まれているのが本作のすごさ。魔術、黒ミサ、首なし死体……昭和ミステリらしい耽美な雰囲気をまといつつ、トリックそのものは完全にフェアで緻密。
人形を殺すことに意味があると気づいた瞬間、一気に景色が変わる。
怪奇を論理でぶった斬る。その快感を思い出させてくれる一作。



神津恭介の推理が冷酷なまでに鮮やかで、論理と幻想のせめぎ合いが最高に気持ちいいのだ。
34.赤川次郎『マリオネットの罠』
──すべてが仕組まれていた。操られていたのは、誰だったのか?
フランス帰りの青年・修一が、高額報酬と引き換えに訪れたのは、山奥の洋館に住む美しい姉妹の家庭教師という奇妙な職だった。
だがその館には、地下牢に幽閉された三女と、家族にまつわる不穏な秘密があった。幽閉、虐待、当主殺害。連続する死の先に浮かび上がるのは、周到に張り巡らされた「罠」。
赤川次郎のデビュー長編にして、巧妙な伏線とラストの鮮やかな反転が光る原点的傑作。軽妙な文体に潜むゴシックホラー的な陰鬱さと、ミステリとしての完成度が絶妙に交差する。
甘い誘いと、冷たい罠。操られていたのは、こっちのほうだった。



赤川次郎=三毛猫ホームズ、と思っている人ほど、この作品の毒に驚くはず。
35.三津田信三『首無の如き祟るもの』
──首のない死体、歩く祟り神、作中作の迷宮。ホラーと本格がガチで組んだ怪作。
奥多摩の限界集落・媛首村で起きた、首なし連続殺人。首を失った死体が歩いたという証言、祟り神「淡首様」、作中作として語られる元巡査の妻の手記、そして現代の探偵・刀城言耶の論理が交錯する。
ホラーの皮をかぶったバリバリの本格ミステリで、「祟り」と「密室」と「見立て」が全部盛り。怪異っぽさに振り回されつつ、最終的には冷酷なロジックがすべてを叩き潰してくれる。
終盤のどんでん返しの連続は神。
怖いのに、解かずにいられない。理性と恐怖のロンドを、ぜひ最後まで。



「ホラーだと思った? 残念、全部トリックでした!」をここまで高密度でやるのは三津田信三だけ。
36.横溝正史『獄門島』
──俳句、首、火あぶり。やりすぎ三連殺人。
復員兵の金田一耕助が、戦友の遺言を受けて孤島・獄門島へ向かう。「三人の妹が殺される」という不穏すぎるフラグは見事に回収され、しかも殺され方は芭蕉の句に沿った見立て形式。髪切られ、首落とされ、火あぶり。
でも、それがたまらなく美しい。旧家の因習、閉鎖的な村人、祟りめいた空気。金田一シリーズの中でも、とくに横溝らしさが全開の一作である。どこまでが偶然で、どこからが必然か。
終盤で暴かれる真相は、ほとんど呪いの構造解体ショー。それを論理でぶった斬る金田一がまた最高にキマっている。
見立て殺人の美学と陰鬱の極致。横溝ミステリの濃縮還元ジュース。



句に見立てて人が死ぬという発想は、ここから本格ミステリの定番になったとも言われる。


37.二階堂黎人『人狼城の恐怖』
──不可能犯罪×ホラー×新本格の極北。
舞台は伝説の人狼が棲んだ「双子の城」。招かれた10人は密室に閉じ込められ、首なし死体、消失、バラバラ殺人……と、常識外れの連続殺人に見舞われる。
謎は山盛り、解決は後回し。けれど、そのすべてに「論理的解決」を約束するのがこの作品の凄みだ。密室マニア、ゴシックホラー好き、全員集合。
詰め込みすぎ? いや、これが新本格の本気。謎の洪水に沈みながら歓喜せよ。



これぞ本格ミステリの地獄絵図。全4巻・2000枚超。読むこと自体が、ひとつの儀式である。
38.北山猛邦『アリス・ミラー城殺人事件』
──探偵たちの殺し合いと、鏡の国の密室
幻想と論理が交差する「アリス・ミラー城」に、十人の探偵が集められる。ルールは単純、「生き残った者だけがアリス・ミラーを手に入れる」。城はチェス盤のように設計され、探偵たちは駒のごとく次々と消されていく。
『そして誰もいなくなった』を下敷きにしつつ、トリックと構造を二重三重に折りたたんだ異形のミステリ。誰が殺したかより、この世界が何なのかを問われる感覚。
終盤で盤面がひっくり返る瞬間、見えていたはずのものが一斉に反転する。
トリックに殺される探偵たち。読者もまたその一人。



北山猛邦は「幻想世界を舞台にしながら論理で魅せる」という、稀有なスタイルをここで確立した。
39.麻耶雄嵩『翼ある闇 メルカトル鮎最後の事件』
──新本格という名の城に爆弾をぶち込んだデビュー作
中世風の古城・蒼鴉城で発見されたのは、首のない死体。そして切断された足首、鉄靴、甲冑、見立て殺人、蘇った死者など、クラシカルなガジェットが全部盛りで襲いかかる。
挑むは、冷静な論理派・木更津と、異端の名探偵・メルカトル鮎。二人の「解決」がぶつかり合う、壮絶な多重推理バトルが展開する。だが、明かされる真相は常識の外。読者の信じていたものすべてが、最後に裏返される。
これはミステリという名の仮面をかぶった、爆発物である。



綾辻行人が『館』で築いた新本格の城に、麻耶雄嵩は『翼ある闇』で時限爆弾を仕掛けた。そんな構図である。
40.麻耶雄嵩『神様ゲーム』
──神様は転校生の顔をしてやってくる
猫が殺され、人が死ぬ。そして未来を言い当てる転校生・鈴木太郎は言う、「ぼくは神様です」。小学生の芳雄は、街で起きる奇怪な事件と、鈴木の不気味な予言のあいだで揺れ続ける。
神なのか、犯人なのか、ただの嘘つきなのか。予言と現実のズレ、言葉の解釈、子どもたちの純粋さと残酷さ……そのすべてが読む側に刃を向けてくる。
信じること、疑うこと、そして見ることすら試される、恐ろしく冷たい神様の遊び。



子どもの無邪気さを、これほど純粋に恐ろしく描いたミステリが他にあるか?
41.城平京『名探偵に薔薇を』
──メルヘンは血を流し、探偵は孤独に咲く
奇怪な創作童話『メルヘン小人地獄』を模倣した見立て殺人が現実化し、連続殺人が幕を開ける。事件の鍵を握るのは、童話とリンクする不可解な死と、「名探偵」瀬川みゆきの推理。
物語は二部構成。前半は童話×猟奇殺人、後半は毒杯×論理パズル。全貌が明らかになるころには、読者自身の認識すら書き換えられているはずだ。
論理、構造、物語の余韻、どれも高水準。だがその中心にあるのは、決して癒されない傷である。
謎は解けても、心までは救えない。それでも名探偵は推理する。



毒杯を使ったトリックの設計があまりに精緻で、読み終えたあと思わず図を描いてしまった。
42.北村薫『盤上の敵』
──家に帰ったら、そこが戦場だった
猟銃を持った男が自宅に立てこもり、妻を人質に取った。警察に包囲された公然の密室で、夫・純一は犯人との交渉に踏み込み、知略を尽くして盤面を動かしていく。
だがこれはただの人質劇ではない。語られるのは、犯人との戦いだけでなく、過去と嘘、そして夫婦の間に積み重ねられていた見えない何かとの対峙でもある。張り巡らされた伏線と構成の妙、すべてがラストで収束する。
崩れたのは家ではなく、信じていた絆のほうだった。



日常のミステリを得意とする北村薫が、非日常の極限で描いた実験的作品でもある。その実験は大成功した。
43.法月綸太郎『頼子のために』
──愛が殺意に変わるとき、論理はどこまで通用するか?
愛娘を殺された父親が、犯人を突き止め、復讐を遂げ、自ら命を絶った。そう記された手記がすべてを語り終えたはずだった。
だが、名探偵・法月綸太郎は言う。「この物語はまだ終わっていない」と。
調査を開始した瞬間から、事件は二重三重の顔を見せ始める。手記に潜むわずかな違和感。再構築される真相。交錯する父の愛と罪の意識。そして、暴かれるもう一つの地獄。
読後、「最悪の真相」を知ることになる覚悟はしておくべきだ。
これはミステリに見せかけた、愛と狂気の劇薬である。



これほど面白くて、これほど後味の悪いミステリをわたしは他に知らない。


44.宮部みゆき『火車』
──失踪した女は、誰の中にもいる
休職中の刑事・本間は、親戚の婚約者・関根彰子の行方を追うことになる。だが調査の果てに見えてきたのは、自己破産という社会的死を背負い、なお生き延びようとするひとりの女性の足跡だった。
彼女はなぜ、名前も履歴もすべてを捨てたのか。カード社会の歪み、制度の落とし穴、人間の弱さと必死さ。派手なトリックも血まみれの死体も出てこないのに、読み進めるほど心が削られるようなミステリである。
謎を解くことが、誰かの悲鳴をほどいてしまう瞬間がある。



血もトリックも登場しない。それでも「これはミステリだ」と言い切れる、社会派サスペンスの金字塔である。
45.山口雅也『生ける屍の死』
──死んでも死なない世界で、殺人は成立するのか?
死者が蘇る現象が当たり前になったアメリカ。毒殺された青年グリンは、生ける屍となって自分の死の謎と、一族に起きる連続殺人に挑む。だがこの世界では、被害者も探偵も、みんなゾンビかもしれない。
死の意味が揺らぐ中、それでも殺人は起きる。その行為に、どんな意味が残されているのか。本格ミステリとしての完成度は驚異的。
トリックも伏線も、すべてこの特異な設定の中で成立させてしまうのがとにかく凄い。
ジャンルの壁なんて無意味だと思い知らされる。死者の理屈で生の謎を解く、唯一無二のミステリ。



「生ける屍」というタイトルなのに、最も恐ろしいのは完全なロジックという逆説が秀逸すぎる。
46.円居挽『丸太町ルヴォワール』
──真実よりも、魅せる物語で勝て
京都に存在する裏法廷〈双龍会〉を舞台に、名家の御曹司・城坂論語が祖父殺しの容疑を晴らすべく、口先一本で検事と真っ向勝負を挑む。
証拠捏造OK、ウソも詭弁もアリ。裁定者を魅了した者が勝つ、ルール無用の弁論バトル開幕だ。
事件の鍵は、誰も存在を証明できない謎の女〈ルージュ〉。彼女は妄想か、それとも真相か。論語の舌鋒が真実をあぶり出すたび、物語は幾重にも反転していく。
どんでん返ししすぎで脳が湯だつ一冊。



デビュー作にして言葉で殺し合う新本格を打ち出した、円居挽の原点。
47.浦賀和宏『眠りの牢獄』
──地下とネット、二重の監禁はどこへ向かうのか
恋人を昏睡に追いやった階段落下事故。その真相を吐かせるために、若者3人が地下室に閉じ込められる。一方で、ネットでは交換殺人を持ちかける不穏なメールのやりとりが進行中。
閉鎖空間×メール地獄、まったく別物のような2つの「牢獄」は、想像を超えた地点でリンクしはじめる。
誰の話を読まされていたのか。なぜ、あんなにも「切断」にこだわるのか。すべてが繋がった瞬間、ぞっとするほど理にかなった狂気が立ち上がる。
狂ってるのに整合性がある。こんな地獄を、浦賀和宏は本気で設計していた。



浦賀和宏が浦賀らしさに到達した初期の傑作であり、読み返すたびに「どこから狂っていたのか」を考えたくなる作品だ。
48.中山七里『連続殺人鬼 カエル男』
──狂気と法の隙間を縫う、猟奇ミステリの極点
口にフックを刺され吊るされた死体。子供のような字で残された犯行声明。犯人「カエル男」は無差別に殺人を重ね、街はパニックに陥る。
刑事・古手川は正体不明の殺人鬼に挑むが、事件は「刑法三十九条」=心神喪失と向き合う地雷原でもあった。
グロ描写の向こうに浮かび上がるのは、法の限界と正義の曖昧さ。加えて中山七里お得意の怒涛のどんでん返し。一筋縄ではいかないサイコ・ミステリ。
恐怖の先にあるのは、正義の崩壊か、それとも覚悟の選択か。



どんでん返しの名手・中山七里の代名詞を決定づけた初期代表作。ラストの反転に震えてほしい。
49.真梨幸子『殺人鬼フジコの衝動』
──いい人が、どうして連続殺人鬼になったのか?
一家惨殺事件の生き残りだった少女・フジコは、やがて十数人を殺す連続殺人鬼となる。いじめ、孤独、自己否定。
まともに生きようとするたびに、社会は彼女に追い討ちをかけた。物語は記録小説という形式で、彼女の人生と「衝動」の正体を描き出す。
見どころは、フジコの告白が積み重ねる不快さと違和感。それが終盤、一気に裏返る。足元をすくう、はしがきとあとがきの衝撃。騙されたというより、騙されたくなかった自分に気づかされる感覚だ。
悪意は叫ばずに芽を出す。その静けさが、いちばん怖い。



発売当時、読んだら一日気分が悪くなる本と話題になった問題作。
50.高野和明『13階段』
──罪と赦しのあいだで、13段をのぼる。
ある殺人事件で死刑が確定した男・樹原。だが本人には犯行の記憶がない。執行まで残り3ヶ月、元刑務官の南郷と、殺人歴のある仮釈放中の三上が真相を追う。手がかりは「13階段」という謎の言葉だけ。
社会派ミステリとして骨太なのはもちろん、バディものとしても熱い。死刑制度を問う重厚なテーマと、捜査のスリル、そして登場人物それぞれの「罪と贖い」がガッツリ噛み合っていて、読みごたえ抜群。
一段ずつ踏みしめるごとに、足元が揺らぐ。でも彼らは、それでも進む。のぼる。13段目に何があるのかは、最後のページで確認してほしい。
正義も贖罪も生易しくはない。でも、踏み外せない道が、たしかにある。



「13階段」とは、実際の絞首刑台に設置されている階段の数。だからこそ、このタイトルが重い。
51.荻原浩『噂』
──香水と都市伝説が殺意を生むとき
都内で女子高生が殺される事件が発生。切断された足首と額の「R」の文字。その手口は、巷で囁かれる都市伝説〈レインマン〉に酷似していた。事件は「噂」か、それとも「現実」か。
少女たちの間で囁かれる香水「ミリエル」と、そのプロモーションに仕込まれた怪談まがいの設定が、思わぬ方向で現実を侵食していく。
ネットと現実の境界が曖昧になるこの時代、どこまでが虚構で、どこからが殺意なのか。読み進めるごとに背筋が冷えてくる。そして、最後の一行で全身が凍る。
香りで始まり、沈黙で終わる。この一撃は忘れられない。



都市伝説×連続殺人というアイデアは多いが、それを広告戦略と結びつけたのは極めて異色。
52.井上夢人『ダレカガナカニイル…』
──頭の中に誰かが住みはじめた夜から、すべてが狂い始める。
警備員の吾郎は、火災で教祖が焼死した宗教施設の警備中、頭の中に「自分じゃない誰かの声」が響くようになる。
声の主は何者か? あの火事の真相は? 二つの謎が交差し、物語はSFと本格ミステリの境界を飛び越えていく。
「他人が自分の中にいる」という奇想設定を、トリックにも哲学にも昇華させる離れ業。意識とは何か、自分とは誰か。その答えを探すうちに、読み手の境界線も侵されていく。
自分の中の声が、自分を追い詰める日が来るかもしれない。



他人が自分の中にいるという設定は、後の作品や映画でも繰り返し使われるが、ここまで論理的に落とし込んだ例は珍しい。
53.皆川博子『開かせていただき光栄です』
──鋸と詩と腐臭と、18世紀ロンドンの血と知と闇。
舞台は十八世紀のロンドン。解剖教室に運び込まれた、四肢を切断された少年と顔を潰された男。
連続する奇怪な死体に、外科医バートンとその弟子たち、盲目の判事フィールディングが挑む。謎は一人の詩人志望の青年と、ある稀覯本を巡って深まっていく。
科学と偏見が入り混じる時代背景、腐臭の立ちこめる街の描写、社会からはじかれた者たちの連帯感。歴史ミステリでありながら、青春小説でもあるし、知のロマンでもある。
鋸とペンの音が響くたび、人間の尊厳が剥き出しになる。



タイトルは実際に当時、死体を教材にする外科医が使った丁寧語。死者への皮肉とも読める。
54.相沢沙呼『medium 霊媒探偵城塚翡翠』
──霊視 × 論理で挑む、死者の声を論理でつなぐ新感覚ミステリ
死者の魂が見える霊媒師・城塚翡翠と、ロジック担当の推理作家・香月史郎が、幽霊案件をガチの本格推理で解決していく連作短編集。見えても捕まらない。それなら論理で立証しよう、というスタンスが最高にクールだ。
翡翠の「犯人はこの人です」に対して、香月がちゃんとロジックを積み上げて証明していく流れが快感すぎる。
そして何よりラスト。全部ひっくり返る。すべてが伏線だったとわかる瞬間、即ページを最初に戻したくなる。
可愛い顔して、最後に脳天ぶち抜いてくる。これが真の霊媒トリック。



ミステリランキング三冠(『このミス』・本格ミステリ大賞・週刊文春ミステリ)を制した令和本格の代表作。
55.知念実希人『硝子の塔の殺人』
──探偵と犯人が手を組む、禁断の館ミステリ
北アルプスの山奥に建てられた異形の〈硝子館〉に集められた5人の来訪者。だがその中で殺人が発生し、しかも第一の犯人はあっさりと自白する。
ところが事件はそれで終わらなかった。犯人自身も知らない第二、第三の殺人が続く中、探偵・碧月夜との異色のタッグが真相へ迫る。
「犯人と探偵が共闘する」という構図がまず新しい。舞台設定も、登場人物のいかにも感も、徹底的にミステリ趣味を突き詰めた快作だ。
王道の密室ものをやりつつ、構造ではきっちり裏切ってくる。ラストのどんでん返しも鮮烈。
これは反則すれすれのフェアプレイ。ミステリ好きほどニヤけるやつ。



本格ミステリとは何か?という問いへの、知念実希人流の挑発と愛が詰まった一冊。
56.今村昌弘『屍人荘の殺人』
──ゾンビも出るし人も死ぬ。しかもちゃんと密室。
大学のミステリ愛好会メンバー・葉村が、探偵気質の少女・剣崎比留子に誘われて参加した映画研究部の夏合宿。場所は山奥のペンション〈紫湛荘〉。
だが、到着早々、外界ではまさかのバイオテロ発生、ゾンビに包囲されて完全クローズドサークル化。そして館内では、本格的な密室殺人が起きる。
ゾンビパニックと本格ミステリの融合という無茶な企画に見えて、構造もトリックもきっちり設計されているのが恐ろしい。テンポもキレてるし、登場人物もクセが強い。緊張感と笑いと謎が同時進行する中で、剣崎の推理が冴えまくる。
ゾンビ×館×密室。これで面白くないわけがない。



ゾンビ密室殺人という前代未聞の設定で、第27回鮎川哲也賞を受賞した衝撃のデビュー作。
57.夕木春央『方舟』
──密室×水没×犯人当て=読者ごと沈める密室地獄
大学生グループと一般人を乗せて、地下建築「方舟」は地震で密室化。閉じ込められた10人の中で起きる絞殺事件。水は迫り、疑心は加速する。
犯人を見つけて殺すのか? それとも全員で死ぬのか? 出口なき心理戦が始まる。
息もつけぬサバイバル推理の末に待っているのは、希望か破滅か。ラストの展開が、すべてをひっくり返す。
読者の理性ごと沈めにくる、密室パニックの傑作。



終盤の展開がえげつない。単なる犯人当てではなかったことが明らかになる「構造トリック」が秀逸だ。
58.夕木春央『十戒』
──ルールを破れば全員爆死。黙れば、また誰かが死ぬ
無人島に集められた10人に突きつけられる、絶対遵守の〈十の掟〉。「犯人を知ろうとしてはならない」「外部と接触してはならない」。破れば爆発。だが何もしなければ、連続殺人は止まらない。
推理すら禁じられたこの地獄で、〈正しさ〉を問う資格は誰にあるのか。そして最後の一撃は、前作『方舟』を読んだ者すら崩壊させるほどに冷酷だ。
「考えるな、感じろ」の逆を突きつけてくる、恐怖と論理の密室ゲーム。



犯人当てすら禁じるという掟は、ミステリというジャンルへの明確な挑戦でもある。
59.榊林銘『あと十五秒で死ぬ』
──限られた時間の中で、知恵と命が燃え上がる
撃たれて絶命寸前、現れた死神が告げる。「あなたには、あと十五秒ある」。表題作は、そんな“死に損ない”から始まる逆転劇だ。
全編「15秒」をテーマにした短編集で、テレビ予告をヒントに事件を解く話、事故の夢に怯える少女、15秒以内なら首が飛んでもセーフな世界……と、奇抜な設定が揃う。
限られた時間を最大限に使った推理と仕掛けが鮮やかで、一作ごとに印象を焼きつけてくる。
最短距離で最高にスリリングなミステリ、ここに爆誕。



第62回メフィスト賞受賞作。制限時間ミステリの開拓者として一躍話題になった。
60.方丈貴恵『孤島の来訪者』
──殺したいやつがいる。でも、先に殺されたのは“そいつ”だった。
復讐のために幽世島(かくりよじま)を訪れた主人公・佑樹は、いざターゲットに手をかける前に、思わぬ邪魔が入る。
しかもその殺し方が人間離れしていて、妙に不気味。まさか、自分より先に「何か」が仇討ちをしてしまったのか?
復讐者が守る側に回るというねじれた構図が最高だ。殺したいやつの命を守らなきゃいけない。その葛藤がスリルを倍増させるし、謎が謎を呼んでいく展開にもゾクゾクさせられる。
ロジックも伏線もきっちり本格で、ラストの多重どんでん返しも見もの。
殺したいやつが殺されてくれないミステリ、ここに極まる。



ラストの多重どんでん返しは、視点トリックとして鮮やかすぎるのでぜひ体験してほしい。
61.斜線堂有紀『廃遊園地の殺人』
──夢の国で、地獄を見ろ
銃乱射事件で廃園となった遊園地・イリュジオンランド。20年後、元関係者や廃墟マニアが宝探しに集められ、そこで串刺し死体が発見される……という設定だが、本題はそこから。
見どころは、遊園地の各施設を使った異様なトリックと、閉ざされた園内で進行する極限の心理戦。観覧車もメリーゴーラウンドも、すべてが伏線に変わる構成力が見事すぎる。
閉ざされた空間、先の読めない連続殺人、後半で効いてくる切ない人間ドラマ。そして、読者の倫理観を揺さぶるラストの選択肢に注目。
着ぐるみの中に詰まっているのは、夢じゃなくて地獄だ。



終盤、読者にも選択肢が突きつけられる構造が強烈。これは謎解きではなく、倫理の踏み絵である。
62.鳥飼否宇『指切りパズル』
──可愛い動物とアイドルと、連続指切断事件
動物園イベント中に、アイドルの指がレッサーパンダに噛み切られる。奇抜な事故に見えて、実は連続切断事件の幕開けだった。
次々と指を失う関係者たち。その謎を追うのは、警察ではなく、動物をこよなく愛するチーフ警備員・古林。
最大の見どころは、終盤で違和感のピースが見事に組み上がっていく構成力。あのプロローグの意味が反転する瞬間、声が漏れること必至だ。
ふざけた仮面をかぶった本格ミステリ。油断すると指を持っていかれる。



本作の真のテーマは「誰が嘘をついていたのか」ではなく、「誰が本当のことを言っていたのか」だ。
63.東川篤哉『スクイッド荘の殺人』
──笑ってたら殺人、ふざけてるのに本格
探偵・鵜飼と助手・戸村が護衛で訪れた温泉旅館「スクイッド荘」で、雪に閉ざされ殺人事件が発生。次々と明かされる過去の事件、怪しい宿泊客、そしてまさかの第2の死体。
ゆるゆるギャグとガチ推理の合わせ技。殺人現場でもボケ倒す鵜飼&戸村コンビに、警察の珍コンビも加わって、とにかくテンポが軽快。
だが後半、散りばめられた伏線が一本の線に収束していく展開は、しっかり本格の快感。伏線もトリックもキッチリ決まる、東川節炸裂の一冊。
ギャグに油断してると、ラストの推理で頭をぶん殴られる。



軽快な会話劇が続く中、唐突にど真ん中の本格が始まる構成は、東川作品の十八番(おはこ)。
64.東川篤哉『仕掛島』
──笑いと惨劇のジェットコースターへようこそ
遺言執行のため訪れた孤島・斜島で、相続人が殺される。島は嵐で孤立し、幽霊や赤鬼まで出現。探偵・小早川と弁護士・矢野はボケとツッコミを武器に事件に挑む。
前半は軽妙、後半は怒涛。23年前の事件と現在が交錯し、「仕掛島」の名にふさわしいトリックが炸裂する。
ふざけた空気で油断させてからの、超ド級どんでん返し。



前半のほぼコントから後半の怒涛の伏線回収への落差は、まさにジェットコースターのようだ。
65.石持浅海『風神館の殺人』
──復讐計画は、仲間の死で崩れ始めた。
欠陥商品で人生を壊された十人が、企業幹部を一人ずつ裁く。だが最初の殺しの直後、味方のはずの仲間が何者かに殺される。嵐で孤立した館に裏切り者が潜む。状況は一変、疑心と緊張が爆発する。
石持浅海お得意の〈心理戦〉が冴えわたる。誰が裏切ったのか? 誰が次に死ぬのか? 目配せ一つ、沈黙一つが疑惑の種になり、神経をすり減らされる。
密室トリックではなく、言葉と空気で人間を追い詰める。信頼と恐怖が拮抗する空間で、誰が最後に立っているのか。
推理小説の顔をした、心理戦サバイバル。



「犯人はこの中にいる」ではなく、「裏切者は味方の中にいる」。その違いが物語を圧倒的に重くしている。
66.紺野天龍『神薙虚無最後の事件』
──最終巻なのに、探偵が犯人を明かさなかった。
伝説的シリーズの遺作が、まさかの〈犯人不明〉で終わっていた。依頼を受けた大学生・白兎たちは、作中作の謎を読み解くために、名探偵倶楽部で推理合戦を始める。
この「チームで謎を解く」楽しさが本作最大の魅力。次々と提示される仮説のどれもが納得度高く、読者も思わず頭をフル回転させてしまう。作中作の完成度も高く、「探偵vs怪盗vs使徒」という中二病風ガジェットと本格ミステリの融合が良い。
そして終盤、全員の仮説を超える真相が明かされる。
これは、読者すべてが探偵になるための物語だ。



作中作の推理合戦という形式ながら、青春群像劇としてもきちんと熱い。
67.阿津川辰海『入れ子細工の夜』
──読者もまた、仕掛けの一部。
鞄のすり替え、試験問題、覆面レスラー、密室再現ゲーム……4つの中編すべてに多重構造とどんでん返しが仕込まれた、極上の論理ミステリ集。
語りそのものが罠になっていて、読み終えて初めて「やられた」と気づく仕掛けもあり。どれも短編とは思えない濃度で、一作ごとにガツンと脳にくる。
これぞ現代版〈新本格短編集〉の理想形。密度、仕掛け、意外性、全部アリ。



作中人物の視点すら読者への罠に変える、阿津川辰海の語りの魔術が冴えわたる一冊だ。
68.阿津川辰海『透明人間は密室に潜む』
──特殊設定 × ロジックの快感、全部盛り。
透明人間になれる奇病が流行し、透明化した犯人による密室殺人が起きる……という表題作を筆頭に、「全員アイドルオタクの裁判員ミステリ」「超聴力で真相を探る音の事件」「脱出ゲーム中の本物の誘拐」など、ありえなすぎる設定をガチの論理でぶん回す全4編。
どれも飛び道具っぽいのに、トリックとロジックは超本格。こんなの、笑って唸るしかない。
ありえないからこそ成立する、最高にアリな本格短編集。



全編、「これ本当にロジックで解けるの!?」という疑念から始まり、「解けるのかよ!」という歓喜で終わる。
69.芦辺拓『名探偵は誰だ』
──犯人探しじゃない。〈信用できる誰か〉を探す物語だ。
共犯者だらけの食卓で、自分だけが標的かもしれない。そんな異様な状況から始まる短編集。テーマは「犯人は誰か」じゃなく、「生き残ったのは誰か」「名探偵は誰か」「信じていいのは誰か」。
7編すべて、設定もトリックも発想がバラバラなのに、どれもフーダニットとして成立してるのが見事。推理とは、疑うことではなく、信じられる人を見つけること。そんな視点の転換が心地よい。
ミステリって、こんなに自由でいいんだ!と思わせてくれる快作。



名探偵の顔をした誰かを見抜けるかどうかで、読後の印象が180度変わる仕掛けも巧妙だ。
70.片岡翔『その殺人、本格ミステリに仕立てます。』
──人を救うために、偽の殺人を仕組め。
マーダーミステリーの最中、本当に殺人が起こるという噂。それを防ぐため、主人公・風゛とミステリープランナーの豺は「誰も死なせない殺人事件」を本格ミステリの形で演出し始める。
トリックを組み、伏線を撒き、死体を作る。すべては人命を守るため。
だが仕掛けは破られ、次第に空気は凍りついていく。笑いから、推理へ、そして涙へ。ミステリを愛する人間たちが「本格」の力で命を守ろうとする、この構造の美しさよ。
殺人を防ぐために偽の殺人を演出するという、構造そのものがメタ・ミステリの極地。



マーダーミステリー×青春×ヒューマンドラマ×ガチ本格。このジャンル融合はちょっと反則レベルだ。
71.北山猛邦『月灯館殺人事件』
──首なし、密室、吹雪の館。王道の皮をかぶった、メタ本格の怪物。
スランプ中の若手作家が訪れたのは、文筆家たちが集う謎の執筆施設・月灯館。だが吹雪で閉ざされたその場所で、作家たちが次々と殺されていく。首なし、バラバラ、密室。しかも七つの「大罪」に見立てて。
ここまでは王道。だが本作は、むしろ「なぜその形式で殺すのか」が核心になってくる。密室トリックやクローズドサークルのお約束を逆手にとりつつ、作家と作品、ジャンルそのものへの批評を織り込んだ構造は、読者の視点をぐるりと変えてくる。
密室殺人に偽装された、ミステリというジャンルへの問題提起。



同作者の『アリス・ミラー城殺人事件』と並ぶ、ジャンルそのものを舞台化した問題作である。
72.北山猛邦『アルファベット荘事件』
──箱が開いたとき、世界が裏返る。
雪に閉ざされた洋館「アルファベット荘」。A〜Zの文字と謎の箱に囲まれた一夜、10人の招待客の中から、突如バラバラ死体が出現する。呪いか、奇術か、それとも論理か。
密室、足跡なき殺人、幻想めいたトリック。そしてすべてを覆すラストの仕掛け。幻想とロジックのせめぎ合いが美しい、まさに北山ワールドの原点。
この箱の中身は、恐怖と驚きとミステリの快楽だった。



よくある館ものかと思いきや、世界の見え方そのものを問う転倒構造が待ち構えている。
73.村崎友『風琴密室』
──過去と現在、ふたつの密室が重なった。
取り壊し目前の母校に集まった同窓会メンバー。だが台風により閉じ込められた翌朝、屋上プールで死体が見つかる。その密室状況は、10年前に亡くなった兄の事故と酷似していた。
過去と現在、二重の密室。爽やかだった青春は、いつしか不穏な謎へと姿を変える。トリックもロジックも本格派。ふいに差し込まれるホラー要素も効いていて、ただの青春ミステリでは終わらない。
思い出と真実のあいだに潜む闇が、こんなにも沁みてくるとは。



第17回本格ミステリ大賞候補作。トリックの完成度だけでなく、空気の怖さも一級品である。
74.荒木あかね『此の世の果ての殺人』
──地球最後の夏、トランクに死体。
小惑星衝突で人類滅亡まであと2ヶ月。高校生のハルは、運転免許を取るため福岡の教習所に通い続けていた。そんなある日、教習車のトランクから他殺体が見つかる。
「なぜこの時代に、わざわざ人を殺すのか?」
終末世界×青春×本格ミステリ。絶望の中で、命と夢と謎が交錯する。
最後の謎と最後の希望を描いた、静かに沁みるミステリだ。



終末世界でも、謎を解きたくなるのが人間だ。ミステリの根源的欲望がここにある。
75.山沢晴雄『ダミー・プロット』
──死体はひとつ、でも情報はバラバラ。
街のあちこちで発見される、手首・首・胴体。全部ひとりの死体らしいが、誰なのかもわからない。しかも関係者全員、何かしら嘘をついている。偽証、替え玉、別行動……とにかく情報が錯綜しまくる。
だが探偵・砧順之介が、少しずつ混乱に風穴を開けていく。と思ったら終盤、こっちの足元を爆破してくる。アリバイ、視点、構成、全部が伏線。
ミステリーという名の爆弾処理。ニヤけながら爆死せよ。



語られた事実をそのまま信じていると、ラストで地面ごと抜かれる。騙し方が論理的で美しい。
76.松城明『可制御の殺人』
──制御されてるのは、誰の思考か。
親友にすべてを奪われかけた理系女子・千冬が、精密すぎる殺人計画を始める……そんなヤバめの導入からしてインパクト大。でも本当に恐ろしいのは、裏で「人間の行動を制御できる」と信じて実験してる男・鬼界の存在だ。
連作短編の形を取りつつ、どの話でも誰かの善意が歪められていくのがキツい。そして最後に見えてくるのは、「その選択、本当に自分の意思か?」という疑念。
読んだあと、無意識の行動すら信じられなくなる。操作系ミステリの傑作。



「人間はここまで誘導できる」という科学的思考が、ぞっとする形でミステリに応用されていく異色作である。
77.歌野晶午『首切り島の一夜』
──40年前の妄想小説が、血まみれの現実に?
修学旅行の思い出の島で再会した同窓生たち。そこで一人が語り出す。「高校時代、教師を皆殺しにする小説を書いていた」と。酔った冗談と思いきや、その夜から小説通りに人が死に始める。
歌野晶午らしく、過去と現在が交錯し、語りの中に緻密な仕掛けが隠されている。トリックよりも「構成の妙」を味わうタイプの一作だが、最後の一撃はしっかり用意されている。しかも、カバー裏まで伏線。
小説×現実×遊び心。ページの内側も外側も疑ってかかれ。



真相に気づいたとき、タイトルすらも別の意味を帯びてくる……そんなあとから効く毒がある。
78.小川哲『君のクイズ』
──答えとは知識か、記憶か、それとも人生そのものか。
クイズ番組決勝。問題文が始まる前にボタンを押し、しかも正解した男。0文字押しの謎に挑む本作は、ミステリーでありながら、クイズとは何か、人が答えにたどり着くとはどういうことかを掘り下げていく。
犯人探しではなく、「なぜ答えられたのか」を追う展開が新鮮。人生とクイズが交差する構成に、思わず背筋が伸びる。
この一問は、自分自身に向けられていた。



「なぜ殺したか」ではなく、「なぜ正解したか」を追う。それはある意味で、知の犯人探しだ。
79.桃野雑派『星くずの殺人』
──重力のない密室で、首は吊れるのか?
民間宇宙旅行の舞台は、ホテル「星くず」。到着早々、機長の首吊り死体が無重力空間で発見される。だが宇宙でどうやって首を吊る? その不自然な死を皮切りに、隔離された空間で次々と起こる異変。
トリックは超物理的、動機は超人間的。無重力と密室と人間の業が絡み合い、ラストには重力すら捻じ曲がるような真相が待つ。
地球の論理が通用しない中での極限ミステリ。



宇宙ではアリバイの意味が変わる、というテーマの掘り下げ方がスリリングだ。
80.渡辺優『私雨邸の殺人に関する各人の視点』
──探偵なんて、いなければいないほど面白い
密室で資産家が殺され、山奥の豪邸は土砂崩れでクローズドサークル化。よくある展開かと思いきや、このミステリは探偵役がいないところから始まる。
登場人物たちがそれぞれの視点で語り始め、主張は食い違い、誰かが隠してる、誰かが嘘ついてる。読み進めるほど、真相は増えていく。語りのクセもキャラの濃さもクセモノぞろいで、誰も信じられない感じが最高にはらはらする。
一つの事件を何通りにも再解釈させるという構造がとにかく面白くて、視点の迷子にさせられる。
全員容疑者、全員語り手。これぞ、多重視点地獄の醍醐味。



どの語り手も嘘はついていないのに、整合しない世界。このズレが、読む快楽になる。
81.三津田信三『忌名の如き贄るもの』
──死んだはずの少女から始まる民俗ホラー×本格ミステリ
山奥の虫絰村で行われる「忌名の儀礼」。その最中に死んだはずの少女が火葬場で生き返る、という不気味な体験談をきっかけに、言耶は再び因習村へ。だが、再び始まった儀礼の夜、今度は本当に死人が出る。
首虫、角目、奇怪な風習、見えるはずのないもの。次々と襲いかかる恐怖に、「本当に人間の仕業か?」という疑いすら生まれてくる。だが、それでも言耶は解く。異形の闇の中に、冷ややかなロジックが浮かび上がる。
そしてラストの衝撃。この終わり方は、心臓に悪い。
恐怖と論理の狭間で、足を踏み外したら二度と帰れない。シリーズ屈指のオチが待っている。



刀城言耶シリーズの中でも、終盤の精神的破壊力はトップクラスだ。
82.浅倉秋成『六人の嘘つきな大学生』
──内定を賭けた心理戦、疑心と告発の密室バトル
最終選考に残った六人の大学生に課されたのは、「自分たちで内定者をひとり決める」ディスカッション方式。だがその場に突如現れた告発文が、全員の裏の顔を暴き始める。
いじめ、中絶強要、盗撮、差別。明かされる過去に空気が凍りつき、投票の行方は迷走していく。誰が嘘をついているのか。誰が告発者なのか。人間の建前と本音がぶつかり合う議論は、もはや推理ゲームだ。
就活という名の密室で、最後に選ばれるのは誰か?
他人の嘘より、自分の腹黒さにゾッとする。読者参加型の心理ミステリ。



本作を読むと、就活という儀式の異常性が逆にリアルに感じられてくるから怖い。
83.紺野天龍『シンデレラ城の殺人』
──舞踏会のあとに訪れたのは、ハッピーエンドではなく、死刑宣告だった。
王子の密室殺人事件の容疑者は、まさかのシンデレラ。ナイフには彼女の指紋、動機も十分。だがこのヒロイン、魔法の代わりにロジックと屁理屈で真犯人に立ち向かう。
おとぎ話のキャラたちが濃すぎるのに、トリックは本格派。血文字、監視下の密室、すべての謎がラストで鮮やかに繋がる。
魔法よりも論理で魅せる、型破りな逆転シンデレラ裁判劇。



毒林檎の毒性を証明するくだりが超名推理だ。
84.犬飼ねこそぎ『密室は御手の中』
──神の声より、論理の声を信じろ。
新興宗教の施設で起きた密室バラバラ殺人。捜査に挑むのは、女性探偵と14歳の少年教祖。立場も信条も真逆の二人が繰り広げる、熱量高めの推理合戦がたまらない。
密室、宗教、心理戦。全部乗せなのに、ラストは論理で一本締め。論理と論理が火花を散らす会話劇に、読む手が止まらない。
密室も信仰も、ロジックで解体される快感。



宗教施設という閉鎖空間に、密室とバラバラ死体と神託。設定だけでご飯三杯いけるね。
85.似鳥鶏『推理大戦』
──探偵たちの異能バトルが、理詰めで成立してしまう世界。
キリスト教の聖遺物をめぐり、各国が推理で奪い合う異常事態。集うはAI探偵、五感探偵、クロックアップ探偵など、もはやジャンプのバトル漫画かという面々。
奇抜な設定かと思いきや、ロジックはガチ。前半は探偵紹介の連作短編、後半は総力戦。トンデモと本格の融合が、想像以上にスリルがある。異能×本格の融合が、ここまで熱くなるとは。
ぶっ飛んでるのに、本格。この暴力性にハマる。



「能力バトル型本格ミステリ」という新ジャンルを確立した一冊といっても過言ではない。
86.斜線堂有紀『楽園とは探偵の不在なり』
──天使が裁く世界で、なぜ探偵が再び必要とされたのか?
二人以上を殺した者は即・地獄送り。超常の存在〈天使〉が現れてから、探偵は不要な職業になった。犯人を告発するまでもなく、正義は勝手に下されるからだ。
だが、孤島・常世島で起きた連続殺人では、なぜか天使が裁きを下さない。誰かが〈神の目〉すら欺いている。ならば人間が、その謎を解くしかない。
元・探偵の青岸が挑むのは、失われた職能の復権。そして、「探偵がいない楽園」に現れた論理の闘いだ。
天使が沈黙したとき、探偵が蘇る。これはミステリへの愛と意地の物語だ。



「探偵とは、人を裁くためではなく、人を理解するための装置なのだ」と語りかけてくる本格ミステリの傑作である。
87.門前典之『卵の中の刺殺体』
──その白い卵の中にあったのは、芸術のように加工された刺殺死体だった。
池に浮かぶ謎のコンクリート製卵。その中から現れたのは、右目を貫かれた白骨遺体。
奇抜な導入から始まる本作は、そこから山荘での連続密室殺人、家具にされた死体、異様な殺人鬼〈ドリルキラー〉の影と、次々に狂気と謎を加速させていく。
探偵・蜘蛛手は物語の大半で不在。ワトソン役・宮村の視点から進むことで、不安と恐怖が読者にもダイレクトに伝わる構成が効いている。
終盤で蜘蛛手が登場し、すべてをロジカルに解き明かしていく展開は圧巻。グロさと理詰めの快感が共存する、異形の本格ミステリ。
密室と狂気のフルコース。覚悟を決めて読んでほしい。



探偵不在の前半と密室地獄の後半、緩急の構成が巧みで読み応え抜群だ。
88.門前典之『友が消えた夏 終わらない探偵物語』
──首なしの白骨死体が、焼け落ちた合宿所に並んでいた
あまりにも凄惨すぎる過去の事件。それが「解決済み」とされていたはずなのに、名探偵・蜘蛛手の元に届いた一本のボイスレコーダーが、すべてをひっくり返す。
音声記録だけで追う捜査。記憶喪失者の拉致、ストーカー、錯綜する証言。まったく別々に見えた事件が一本の線に繋がっていく展開がえげつない。ラストの畳みかけと、シリーズ屈指のオチはまさに衝撃。
真相が怖いのか、続きを読まされる運命が怖いのか、もうわからない。



門前典之という作家は、絶対もっと読まれるべきだと思っている。こんなに面白い作品ばかりなのに。
89.米澤穂信『可燃物』
──沈黙は謎を焼き尽くすか
雨の夜に起きた不可解な放火事件。燃えたのは紙でも木でもなく、なぜか「生ゴミ」だけ。意味不明な放火の動機を、無口すぎる警部・葛がわずかな手がかりから見抜いていく。
全5編の短編に共通するのは、「理屈では説明できない違和感」をロジックで逆転してみせる知的スリル。葛の一言が、すべての謎を焼却処分していく快感。
しゃべらない警部が、一番雄弁に真相を語っている。ロジックと寡黙さで勝負する、静かなる名探偵の登場。



葛警部の寡黙で冷静な推理は、米澤穂信の新しい名探偵像として異彩を放っている。
90.雨穴『変な家』
──その間取り図に、殺意が潜んでいる
玄関の奥に広がる謎の空間、二重扉で隔離された子供部屋、窓のない浴室。常識では考えられない間取りに潜むのは、偶然ではなく、明確な「意図」だった。
雨穴の『変な家』は、都市伝説×間取り図×仮説ミステリーの新機軸。設計図から真相を読み解くという、建築ミステリ的な醍醐味と不気味さのバランスが絶妙。
後半に進むにつれ、複数の家がつながり、呪術・監禁・殺意が濃度を増していく構成も最高。
怖いのは幽霊じゃない。設計だ。



不気味な間取りだけで、ここまで読ませる作品は他にない。まさに建築トリックミステリである。
91.白井智之『そして誰も死ななかった』
──死んだのに、推理は止まらない。
密室の館、消えた主催者、そして次々に殺されていく五人の推理作家たち。だが彼らは、死んでもなお意識を保ったまま、自らの死の謎に挑み始める。
死者による密室推理合戦という前代未聞の設定を、本格ミステリの論理で真っ向から成立させた怪作だ。
登場人物は全員ミステリ作家、死後の世界でもガチの推理。ぶっ飛んでるのに、なぜかちゃんとロジカル。
ルール無視で理詰め。こんなミステリ、反則でしょ。



原題のオマージュはクリスティー『そして誰もいなくなった』だが、構造的には逆の仕掛けになっているのが面白い。
92.白井智之『名探偵のいけにえ』
──奇跡の町で、名探偵が神に挑む。
ジャングル奥地の楽園で、900人超の集団自殺。それは惨劇の結末にすぎなかった。
物語はその前日、失踪した助手を探して名探偵・大塒がカルトの町に潜入するところから始まる。奇跡信仰が支配する密室空間で、次々と人が死ぬ。それは神の意志か、殺人か。
信仰と理性、救済と破壊がせめぎ合う中、タイトルの〈いけにえ〉が何を意味するかに気づいたとき、背筋が凍る。
これは「名探偵」という存在そのものへの、最も過激な問いだ。



「名探偵とは何か」を、神とカルトと大量死を通じて真っ向から問い直した、白井智之の異端の代表作だ。
93.五十嵐律人『法廷遊戯』
──それはゲームのはずだった。でも、誰かが死んだ。
ロースクールの学生たちがハマっていた〈無辜ゲーム〉。架空の事件を裁く模擬裁判のはずが、現実の殺人と地続きになった瞬間、すべてが狂い始める。
殺されたのはゲームの主催者、逮捕されたのは親友。そして、弁護するのは——自分。信頼、正義、罪の重さ。どこまでが真実で、どこからが欺瞞か。法廷の中で、その境界があぶり出されていく。
青春の皮をかぶった、覚悟と赦しの物語。



著者の五十嵐律人は弁護士でもある。だからこそ、法の隙間と論理の暴力がリアルに伝わってくる。
94.櫻田智也『蝉かえる』
──虫が導くのは、死の謎じゃなくて、生の輪郭だった。
虫マニアの青年・魞沢(えりさわ)。行く先々でちょっとした違和感に出会い、それがいつの間にか、人の痛みや過去の秘密に触れる謎へと変わっていく。
でも、これを「事件」と呼ぶのは少し違う。死はある。でも殺意や悪意じゃなくて、喪失と孤独が根っこにある。
連作短編集のどれもがしみじみと沁みるが、とくに表題作と『ホタル計画』の破壊力は反則級。謎解きもある。でもいちばん響くのは、「わかろうとすること」の優しさだ。
犯人探しじゃない。心に引っかかっていた何かを拾い上げる物語だ。



魞沢は探偵というより共鳴装置だ。だからこそ、謎解きがこんなにあたたかい。
95.須藤古都離『ゴリラ裁判の日』
──その法廷で、愛と命の価値が問われる。しかも、原告はゴリラである。
人語を操り、論理を組み立て、法廷に立つのは、ゴリラのローズ。人間に夫を殺され、たったひとりで国家を相手取る。
荒唐無稽? いや、これは圧倒的リアリティで読者を殴ってくる社会派×法廷ドラマだ。
笑える。でも泣ける。泣けるのに怒りが湧く。そして読み終わるころには、ローズという存在がただのフィクションのゴリラじゃなくなっている。
裁判ものの皮をかぶった、魂の抗議文。完全にやられた。



タイトルは面白い。でも内容は、本気の命と尊厳のミステリだ。
96.大山誠一郎『ワトソン力』
──推理しない名探偵、ここに登場。
和戸刑事は、ごく普通の警察官。推理はできない。でも彼のそばにいると、なぜか他人の推理力が爆上がりする。
そう、これが「ワトソン力」である。事件を解くのはいつも周囲の誰か。本人はポカンとしているのに、事件はスッキリ解決してしまう。
密室殺人にロシアンルーレット、殺人展覧会に迷推理。バラエティ豊かな本格ミステリが7編。全部、他人の推理で解決するのに、なぜか読後は「和戸ってすごいかも」と思ってしまうのがまたズルい。
推理しないくせに好感度だけ爆上がり。



推理しない名探偵という矛盾を、本格ロジックでねじ伏せた快作である。
97.五条紀夫『クローズドサスペンスヘブン』
──成仏したけりゃ、まず犯人を当てろ。
目覚めたらビーチ、でも自分はもう死んでいた。そんな状況で放り込まれたのが「天国」と呼ばれる謎の館。
そこには同じく殺されてきた男女が5人。全員がその事件の被害者で、真相を突き止めないと成仏できない。
納戸から何でも出せたり、新聞で現世の捜査状況がわかったりと、ファンタジー風味の設定をきっちりミステリに落とし込んでいるのが見事。疑心と協力がせめぎ合うクローズドな心理戦も熱い。
死んでも推理、天国でも腹の探り合い。ミステリ好きなら成仏できない面白さだ。



成仏には論理が必要という世界観が、しっかり本格してて驚く。
98.中村あき『好きです、死んでください』
──この島で芽生えるのは、恋か殺意か。
舞台は、孤島で撮影される恋愛リアリティー番組「クローズド・カップル」。6人の男女が疑似恋愛を演じるはずが、密室殺人とクローズドサークルの地獄絵図が幕を開ける。
撮影という建前、恋愛という駆け引き、そしてSNSによる誹謗中傷。現代的な装置が、見事に疑心と悪意を煮詰めていく。誰かが仕組んだ演出に、誰もが壊されていく。
恋と死をリアルに仕掛けた、毒入りの現代ミステリー。甘い顔して刺してくる。



リアリティーショーという仕組まれた密室が、密室殺人と最高に噛み合っている。
99.井上悠宇『不実在探偵の推理』
──しゃべらない。動かない。けど、いちばん頭がキレる。
名探偵アリス・シュレディンガーは、姿も声も他人には見えない架空の存在。だが彼女の推理はガチ。意思疎通の手段はたったひとつ、「サイコロ」だけ。
4つの目「はい」「いいえ」「わからない」「関係ない」をどう使いこなすか。それを読み解く側の知性が問われる、完全ロジック偏重型の異色作だ。
変死体あり、謎の宗教団体あり、眼球オブジェあり。事件のクセも強いが、それ以上に“訊き方”と“読み取り方”が面白い。まさに思考で殴り合うミステリー。
探偵が喋らない分、読者の読解力が試される。まさに頭脳型バトル。



推理は口じゃなくて、ダイスで決める。これが今世紀最もサイレントな名探偵だ。
100.青本雪平『バールの正しい使い方』
──嘘は時に、バールより鋭く心をこじ開ける。
小学生の礼恩(レオン)は、他人の嘘にやたらと敏感な少年。転校を繰り返す中で出会う子どもたちの「嘘」に気づき、それをどうにかして解いていこうとする。だが、見抜くことは正義なのか? 傷つけることと救うこと、その境界線があまりに脆い。
タイムマシンを語る子、友達に嫌われたいと願う子、誰かを殴ったという噂を持つ子。6つの短編はどれも奇妙で、どこか哀しい。そして礼恩の持つバールが、そっと、でも容赦なく、心の奥に踏み込んでいく。
優しさと残酷さが同居する、静かで鋭い児童心理ミステリ。
その嘘は、本当に暴いていいのか? 少年の問いが、こっちの心もこじ開けてくる。



礼恩の優しさは、嘘を暴くのではなく、「なぜその嘘が必要だったのか」を知ろうとする優しさだ。
おわりに


この100作品を読めば、日本のミステリーがいかに多様で、いかに執念深く「真実」を描いてきたかがわかる。
館にも、孤島にも、密室にも、教室にも、ネットの闇にも、謎は潜んでいる。
そしてそれを解き明かそうとする人たちの姿が、いつだって最高にかっこいい。
だからミステリーはやめられない。
だって、この世界にはまだ、解かれていない謎が山ほどあるのだから。