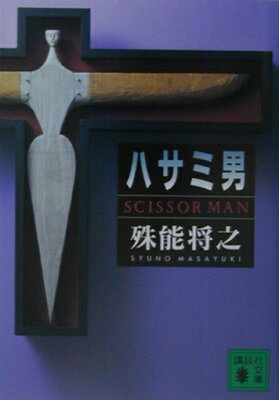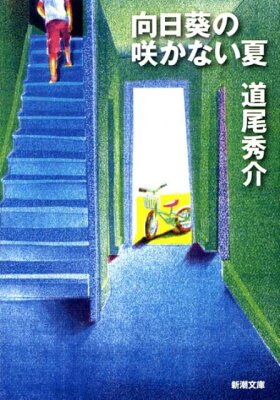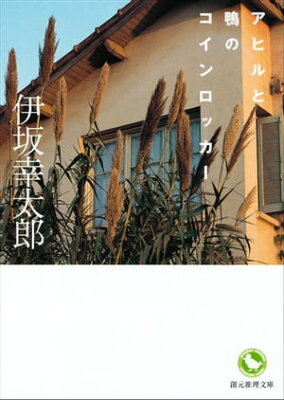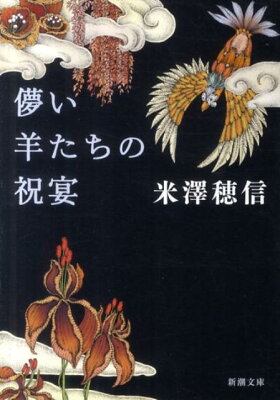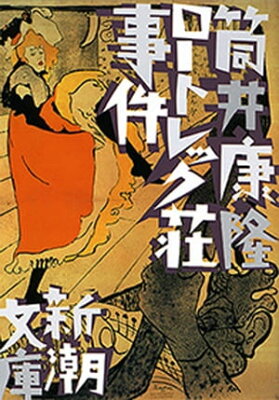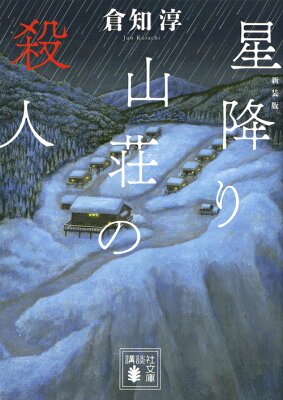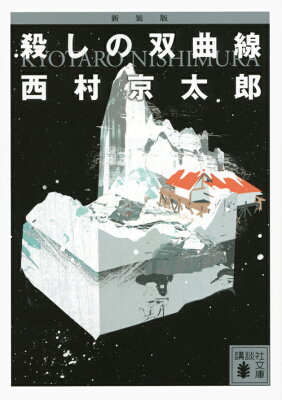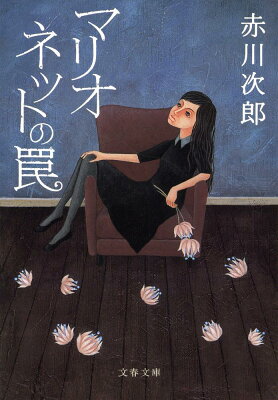名探偵の推理にワクワクして、密室の謎に頭をひねって、最後の一行で世界が反転する。
そんな忘れがたい読書体験をくれるのが、ミステリー小説だ。
中でも日本のミステリーは、ジャンルの幅も深さもすごくて、世界的に見てもかなり独自の進化を遂げてきた。世代を超えて読み継がれてきた名作が山ほどある。
この記事では、ミステリー小説が好きすぎる私が「これは面白すぎる」と心から思った、とにかく面白い国内ミステリー小説を厳選して紹介していきたい。
正直、紹介する作品のほとんどは、ミステリ好きならもう読んでるだろってレベルの有名どころばかり。でもそれはつまり、「殿堂入り」級の名作たちということだ。
「いまさらそんな有名作品すすめられても……」という声が聞こえてきそうなのだが、でも、みんなに読まれてるのにはちゃんと理由がある。それだけ面白いから読まれてきたし、これからも読まれていくということだ。
どの作品も読みやすくてテンポも良いし、「やられた!」と叫びたくなる展開が待っているし、どんでん返しも凄まじい。
ただ一言、
もしこの中にまだ読んでない作品があったら、何も考えずに読んでみてほしい。
それだけだ。
正直、まだ読んでない作品がある人は羨ましい。その衝撃をこれから味わえるのだから。できることなら記憶をまっさらにして、もう一回あの興奮を体験したいくらいだ。
ちなみにルールとしては、「1作家につき2作品まで」「国内ミステリー限定」という縛りを入れている。ジャンルは幅広く選んだ。あと、ランキングはつけてない。全部が1位だと思っているからだ。
ミステリー初心者も、すでに数々のトリックを乗り越えてきた猛者も。
きっと「ああ、これは読んでよかったな」と思える作品に出会えるはずだ。
というわけで、前置きが長くなってしまったが、ぜひ参考にしてもらえたらうれしい。





1.たった一行が、すべてを裏返す── 綾辻行人『十角館の殺人』
九州の孤島・角島には、建築家・中村青司が設計した奇妙な十角館が建っている。彼は半年前、青屋敷の火災で謎の焼死を遂げたとされていた。
大学のミステリ研究会に所属する7人の学生が合宿で島を訪れ、互いを著名な作家の名(エラリイ、ポオ、アガサなど)で呼び合っていた。しかし、メンバーは一人、また一人と殺されていく。外部侵入の形跡はなく、閉ざされた状況下で生存者たちの間に疑心暗鬼が広がる。
一方、本土では元メンバーの江南孝明のもとに、中村青司からの告発状ともとれる手紙が届き、彼は島での過去の事件と青司の謎を追い始める。
島と本土、二つの場所で物語は進行し、ミステリ史上屈指の驚愕の結末へと導かれるのであった。
新本格の幕開けを告げた衝撃

綾辻行人(あやつじ ゆきと)のデビュー作にして、「館シリーズ」のスタートを飾った伝説の一作。それが『十角館の殺人』だ。
1987年、まだ日本の本格ミステリが少し息をひそめていた時代。この一冊が世に出たことで、空気がガラリと変わった。「新本格」の幕がここから開いた、と言っても過言じゃない。
「すべてはここから始まった」
そんなふうに語られるのも納得の、記念碑的な傑作だ。
この作品を語るとき、どうしても触れずにいられないのが、終盤に仕掛けられた《たった一行》の衝撃である。その瞬間、読者が信じていた世界の形がごっそり裏返るのだ。
思わずページをめくり直して、「あのときの描写って……」と確かめたくなる。そうやってもう一度最初から読みたくなるようなトリックと構成の妙が詰まっている。
読み手の目線をまるごとひっくり返す、あの気持ちよさ。読書という体験の中でも、あの感覚はなかなか味わえない。
論理で組み上げた謎解きと、大胆な視点の転換。そういったテクニックが高いレベルで融合していて、今読んでもまったく古びていない。
舞台は、外界から遮断された孤島。その上にそびえるのが、十角形の形をした不気味な館。変わった形の建物というだけでもそわそわするのに、その空間が閉鎖されてて、ひとつ、またひとつと人が死んでいく。自然と肩に力が入る。
登場人物たちは、なぜかお互いを実在の推理作家の名前で呼び合っている。それがまた、現実とフィクションの境界を曖昧にして、不思議な空気を生み出している。誰が誰か、読んでいるうちに混乱してくるが、それすら計算のうちというわけだ。
そしてその背景には、もちろんある。アガサ・クリスティの名作『そして誰もいなくなった』への明確なオマージュだ。でも、ただ真似してるわけじゃない。綾辻行人はそこに、ちゃんと自分だけのスタイルを加えて、見事に超えてきた。
引用とずらし、敬意と反逆。そのバランスの上に、「新本格」の世界観が築かれていく。
本土と島というふたつの視点、名前の使い方、建物そのものをトリックの一部にしてしまう仕掛け。ぜんぶが、終盤の《あの一行》のために組み立てられている。読み終えたあと、そのことに気づいたときのゾクッとする感覚。まさに読む側が試されてるような体験だ。
これは単なる推理小説ではない。読者の認識をゆさぶる、精密に仕組まれた遊戯であり、構造そのものがトリックになっている迷宮でもある。
『十角館の殺人』は、新本格ミステリというムーブメントの原点にして、いま読んでもちゃんと面白い、「読む罠」だ。
未読なら今すぐ。
既読なら、ぜひもう一度。
きっとまた、あの一行に驚かされる。

2.鳴り響く108の時計が、真相への時を刻む── 綾辻行人『時計館の殺人』
鎌倉の森に佇む、無数の時計で埋め尽くされた異様な洋館「時計館」。ここは、美少女・永遠(とわ)が謎の死を遂げて以来、亡霊が彷徨うと噂される場所だった。
永遠の死から10年後、オカルト雑誌編集者・江南孝明、大学のオカルト研究会メンバー、霊能者ら男女9人が、取材と降霊術のため館を訪れる。しかし到着直後から霊能者が失踪し、訪問者たちは次々と不可解な状況で殺害されていく。
館は外部と遮断され、残された者たちは恐怖と疑心暗鬼に陥る。一方、館の外では探偵・鹿谷門実(島田潔)が事件の謎を追う。
永遠の死の真相と現在の連続殺人が交錯し、悪夢の三日間を経て、驚愕の真実が明かされていく。
館シリーズ屈指の複雑な仕掛け
綾辻行人の「館シリーズ」の中でも、群を抜いた完成度を誇るのがこの『時計館の殺人』だ。
ページ数は600超えとけっこうな長編だが、構成がめちゃくちゃ緻密で、トリックもこれでもかと巧妙に仕組まれていて、気づけばラストまで一気読みさせられている。しかも、日本推理作家協会賞まで受賞しているとなれば、本格ファンがスルーする理由なんてどこにもない。
舞台はもちろん、館。今回はその名の通り、108個の時計が不気味に時を刻む「時計館」だ。で、この時計たちがただの飾りかと思いきや、しっかりトリックの一部として機能してくるから油断できない。空間と時間が入り組んだ、この異様な館そのものが、ひとつの巨大な装置として牙を剥いてくる。
密室、アリバイ崩し、そして因縁。本格ミステリでおなじみのガジェットはもちろんフル装備。それに加えて、少女の亡霊とか降霊術とか、ホラー寄りのオカルト要素も自然に混じってくる。論理と幻想の境目がぐらぐら揺れて、何が現実で何が虚構か、読んでる側まで混乱させられるような不思議な体験になるのだ。
伏線もきっちり仕込まれていて、ちゃんと見ていればヒントは全部提示されている。だからこそ、ラストで解決編に入ったときに「そういうことか!」と膝を打つあの感覚が最高に気持ちいい。作家の米澤穂信が「とてもフェア(らしい)」と言っていたのも納得だ。
物語は現在進行形で起きる連続殺人と、10年前の少女の死という過去の事件が並行して描かれる。ふたつの時間軸が交差しながら、やがて一つの真実にたどり着くという流れだ。これがまた見事に決まっていて、構成の妙に思わず唸らされる。
そして終盤。解決編だけで80ページというボリューム。もう怒涛の伏線回収ラッシュで、細部に散らばっていたピースがピタリとハマっていく快感が半端じゃない。論理、恐怖、ひらめき。ミステリで味わいたいすべてが、ここにはちゃんとある。
仕掛けのキレ、構成の妙、そして伏線回収の快感。すべてが高水準で噛み合っていて、まさに「館シリーズのひとつの頂点」と言える作品だ。
一度、時計の針が動き出したら最後。
綾辻行人の仕掛けた時間の迷宮から抜け出すのは、そう簡単じゃない。
3.御手洗潔、ここに誕生── 島田荘司『占星術殺人事件』
1936年、日本画家の梅沢平吉が自宅アトリエで密室状態の中、殺害される事件が発生した。
現場には、彼が遺したとされる手記が残されていた。その手記には、6人の若い処女(自身の娘や姪)の体の一部を使い、完璧な女性「アゾート」を創造するという、常軌を逸した計画が詳細に記されていた。
平吉の死後、手記の計画をなぞるかのように、彼の6人の関係者の女性たちが次々と行方不明となり、体の一部を切り取られた無残な姿で日本各地にて発見される。
この「アゾート殺人事件」は世間を震撼させたが、事件から40数年が経過しても未解決のままであった。この迷宮入りした猟奇殺人の謎に、占星術師にして名探偵の御手洗潔が、友人である石岡和己と共に挑むことになる。
新本格ミステリの原点にして金字塔

島田荘司(しまだ そうじ)のデビュー作にして、名探偵・御手洗潔(みたらいきよし)シリーズの記念すべき第1作。
1980年代後半、綾辻行人らをはじめとする次世代の書き手たちにガツンと影響を与え、本格ミステリの再ブームを巻き起こした火付け役だ。
何がすごいって、やっぱりそのトリックのぶっ飛び具合である。「そんな方法、思いつくか!?」っていうくらいの大技が炸裂する。しかもそれが、単なるドッキリじゃない。ちゃんとフェアプレイの精神に則っている。最初から全部、読者にもヒントは渡されているのだ。
冒頭に出てくる「アゾート創造計画」という謎めいた手記、これがまた厄介だ。難解だし、なんなら不気味だし、「これに何の意味あるのか?」と思いながら読む人も多いはず。しかし、そこが最大の罠なのだ。読者の思考をある方向に誘導するための、見事な仕掛けになっている。
で、事件そのものはというと、バラバラ殺人、不可能犯罪、40年前の未解決事件……盛り盛りの内容。
しかし、それをあざやかに解き明かしてくれるのが、初登場の名探偵・御手洗潔だ。この御手洗がまたクセがすごい。肩書きは「占星術師」だし、変人っぽいがめちゃくちゃ頭が切れる。
そんな御手洗を語るのが、相棒の石岡和己。この石岡の存在がいいのだ。常識人としての視点で、御手洗の破天荒さにツッコミを入れながら物語を支えてくれる。
あとやっぱり嬉しいのが、「読者への挑戦状」があるところだ。シャーロック・ホームズとか、往年のミステリへのオマージュも散りばめられていて、ミステリというジャンルそのものへの愛が詰まっている。ミステリファンとしては、「これぞ本格!」と叫びたくなるような、すべてが詰まった一冊だ。
圧倒的などんでん返し、クセになる探偵、濃厚なミステリ愛。
何もかもが詰まってて、ここからすべてが始まった。
ミステリの扉を開けたいなら、まずはこの一作から。
そう言いたくなるような伝説的な作品だ。

4.世界が傾けば、真実もまた歪む── 島田荘司『斜め屋敷の犯罪』
物語の舞台は、北海道の最北端、宗谷岬の高台に異様に傾いて建てられた西洋館「流氷館」、通称「斜め屋敷」。
この館は、主人の浜本幸三郎の奇抜な発想により、建物全体が意図的に斜めに傾けて建てられていた。雪に閉ざされたクリスマスの夜、館で開かれたパーティーの翌朝、招待客の一人である日下瞬が密室状態の部屋で死体となって発見される。
外部との連絡もままならない吹雪の中、館に集った一癖も二癖もある招待客たちはパニックに陥る。そんな中、第二、第三の惨劇が続き、事態は混迷を深めていく。
この奇怪な連続密室殺人の謎を解き明かすため、名探偵・御手洗潔が現場に乗り込むのであった。
本格ミステリの醍醐味が詰まった舞台設定
本作のいちばんの魅力は、やっぱり「斜め屋敷」という、インパクトありすぎな舞台設定だ。
建物そのものが、最初から意図的に傾いて建てられてる。もうそれだけで、空間がねじれてる感じがするし、読んでいるこっちの感覚もおかしくなってくる。
そこに加えて、密室殺人、雪に残る足跡、ゴーレム、不可解な収集物たち……と、ミステリ好きにはおなじみのガジェットがこれでもかと出てくる。でもすごいのは、そういうバラバラに見える要素たちが、最終的にぜんぶ「傾き」という一つのトリックに結びついていくことだ。これは本当に鳥肌ものである。
斜めの館という発想自体がすでに新本格ミステリっぽいが、その中でもこの作品はかなり挑戦的だ。建築とトリックがここまで直結してる例は、正直なかなかない。空間そのものが謎を語る、そんな異常空間を御手洗潔がスパッと読み解いていく姿は、読んでて惚れ惚れする。
しかも、御手洗が登場するのは物語の終盤なのだ。それまでは警察が右往左往して、登場人物たちが不安や焦りを抱えながら密室の謎に振り回される時間が続く。この探偵不在の構成がまたよくできていて、読んでる側にも妙な無力感と不気味さが伝わってくるのだ。
そしてついに御手洗が登場すると、一気に空気が変わる。彼の強烈なキャラクターと、型破りな推理が、ねじれきった謎をまるごと貫いていく感覚。そこからの展開は、もうカタルシス一直線だ。
この作品は、誰が犯人かという「フーダニット」よりも、「どうやってそんなことが可能だったのか」という「ハウダニット」に重きを置いてる。
で、その中心にあるのが、もうバチバチに緻密で、それでいて大胆な物理トリックだ。物理的な仕掛けの面白さというのは本格ミステリの醍醐味のひとつだが、それをここまで突き詰めてくるとは……と唸らされる。
現実がわずかに傾くだけで、こんなにも世界は歪んで見える。そしてその歪みの中から、美しく構築された謎が立ち上がってくる。そんな作品だ。
トリック重視のミステリが好きな人には、まさにたまらない傑作。
ようこそ、最高に精巧で、ちょっと不安定な「斜めの館」へ。
5.二つの村、二つの事件、一つの真実── 有栖川有栖『双頭の悪魔』
英都大学推理小説研究会(EMC)のメンバー、有馬マリアが、四国の山奥に隠棲する芸術家たちの共同体「木更村」を訪れたまま消息を絶つ。 彼女を案じた江神二郎、アリス、望月周平、織田光二郎らEMC一行は、マリアを連れ戻すべく現地へ向かう。
しかし、村人の頑なな拒絶に遭い、折からの豪雨で木更村と隣接する夏森村を繋ぐ唯一の橋が崩落。江神とマリアは木更村に、アリス、望月、織田は夏森村に、それぞれ取り残されてしまう。
外部との連絡も途絶えた二つの孤立した村で、奇しくも時を同じくして殺人事件が発生する。川の両岸に分断されたEMCのメンバーたちは、互いの状況を知らぬまま、それぞれの場所で事件の真相究明に乗り出すのであった。
緻密な論理と伏線回収の妙が光るシリーズ最高傑作
『双頭の悪魔』は、有栖川有栖の〈学生アリスシリーズ〉の中でも、間違いなくトップクラスに面白い一冊だ。
この作品の最大の特徴は、二つの事件を同時に描いているところにある。
舞台は、外界から隔絶されたふたつの村。ひとつは木更村、もうひとつは夏森村。それぞれの村で起こる殺人事件を、マリア視点とアリス視点の両方から追っていくという、かなり独創的な構成だ。
面白いのは、読者だけが両方の情報を見ることができる、という仕組みで、登場人物たちはお互いの状況をまったく知らない。つまり、私たち読者が神の視点に立てるわけだ。情報の非対称性が効いていて、「これはどうつながってるんだ?」「それとも偶然か?」という感じで、読んでるこっちの頭がずっとフル回転する。
しかも、途中に3回も「読者への挑戦」が出てくる。これはもう、完全にエラリー・クイーンへのオマージュだ。作中でヒントが出揃ったタイミングで「さあ、君も推理してみな!」とばかりに問いかけてくる。自分も探偵になった気分で読めるのが、なんとも楽しい。
そして、江神二郎の推理がまた見事だ。だが、本作では江神が木更村にしかいないので、夏森村の事件はアリス、望月、織田の3人が頑張る。この3人がチーム組んで、地道に話し合って推理していくプロセスが、いわゆる「天才のひらめき」とはまた違っていて、これがめちゃくちゃ面白い。こういうちゃんと考えてる描写が丁寧なのも、シリーズの魅力だ。
そして、やっぱりラスト。香水の匂いだとか、手紙のメモだとか、伏線が全部ピタッと収束していく感覚は、何度読んでも痺れる。複数の動機が絶妙に絡み合っているし、「そういうことか……!」と唸らされるトリックの使い方も見事だ。
本格ミステリ好きなら、「こういうのが読みたかったんだよ!」と叫びたくなるような一作。
構成、論理、人物、全部においてハイレベル。
シリーズ最高傑作と評されるのも納得しかない。
6.孤島、密室、天才、そして── 森博嗣『すべてがFになる』
孤島に建てられたハイテク研究所「真賀田研究所」。そこには、14歳の時に両親を殺害した罪に問われ、以来15年間、完全に外部から隔離された生活を送る天才工学博士・真賀田四季がいた。
N大学工学部助教授の犀川創平と、彼に好意を寄せる同大学の学生・西之園萌絵は、ゼミのキャンプ旅行で偶然この島を訪れることになる。
研究所内を特別に見学させてもらう機会を得た二人だったが、厳重にロックされた四季の部屋から、ウェディングドレスをまとい、両手両足を切断された死体が忽然と現れるという不可解な出来事に遭遇する。
外部との接触が極めて制限された研究所という究極の密室で起きたこの殺人事件の謎に、犀川と萌絵が論理と推理で挑んでいく。
壮大な密室トリック。理系ミステリィの金字塔
『すべてがFになる』は、森博嗣のデビュー作であり、理系ミステリの金字塔とか呼ばれてたりもするが、要するにめちゃくちゃ面白い。
まず舞台がいい。外界から隔絶された孤島の研究所。ここで起こるのが、完全に「ありえない」密室殺人。しかも、被害者はウェディングドレスを着て、両手両足を切断されているというインパクト全振りの導入。
どうしてそんなことに? そもそも、どうやって? というところから、もう完全に物語の中に引きずり込まれる。
そして、この異常な事件の中心にいるのが、天才・真賀田四季(まがた しき)だ。この人がまた規格外で、IQがどうとかそういう次元を飛び越えて、もはや人間じゃないんじゃないかってレベルで浮世離れしている。言ってることもやってることもめちゃくちゃなのだが、なぜか全部筋が通ってて怖い。
トリックは、理詰めで解いていけるタイプだ。物理的な仕掛けとしてはシンプルだけど、設定と情報の配置がうまい。だからこそ、読者が推理に挑みたくなる。で、最終的にすべての謎が「Fになる」というとこに集約していく流れが、もう気持ちいい。
この「F」とは何なのか。読み進めてるとずっと引っかかって、でも答えにはたどり着けない。そして、真相を知ったときに「そういうことか!」となる、あの感覚。やっぱりミステリ読む醍醐味ってこれだよな、と思う。
ただの密室殺人じゃない。ただの天才キャラでもない。論理と哲学が合体して、頭を使いながらゾクゾクできる。そんな珍しいタイプの作品だ。あと、キャラクターの会話もすごく自然で、森作品っぽい知的なテンポが心地いい。
ミステリ初心者にもおすすめできるし、逆に読み慣れてる人こそ、この「F」がどうオチるのか、ぜひ味わってほしい。
事件の鮮烈さ、真賀田四季の異常性、そしてロジックの快感。全部が揃っている。
この一作から、森博嗣ワールドが始まった。
そう考えると、やっぱり凄すぎる出発点だ。

7.理解不能が、理解できてしまう恐怖── 我孫子武丸『殺戮にいたる病』
東京の繁華街で、若い女性ばかりを狙った残虐な連続猟奇殺人事件が発生する。犯行を重ねるサイコキラーの名は、蒲生稔。彼は歪んだ「永遠の愛」を求め、ターゲットを凌辱した末に惨殺するという凶行を繰り返していた。
物語は、犯人である蒲生稔自身の視点、息子の異常な行動に気づき苦悩する母・雅子の視点、そして稔によって親しい女性を殺され、事件を追う元刑事・樋口武雄の視点という、三者のモノローグが交錯する形で進行する。
冒頭では稔が逮捕されるエピローグが描かれ、そこから時間を遡り、彼の犯行に至るまでの心の軌跡、犯行の詳細、そして彼を取り巻く人々の動きが克明に語られていくのであった。
読者の倫理観を揺さぶる衝撃の読後感
この小説、とにかく衝撃がデカい。何がヤバいって、ネクロフィリア(=死体愛好)の性癖を持ったサイコキラー・蒲生稔の「中身」が、徹底的にリアルに描かれているところだ。
しかも表面的な異常性とかじゃなくて、思考や感情の動き、その背後にある執着や妄想まで、こっちの脳内に侵入してくる勢いで迫ってくる。
普通に考えれば「ありえない」「理解不能」と言いたくなるような倒錯の世界なのだが、読み進めるうちに、なぜかその狂った論理に引きずられてしまう。しかも無自覚に。
気がつけば、知らない誰かの夢の中に引き込まれたような感覚になる。不快なのに、目が離せない。気持ち悪いのに、先が気になる。この引力は正直すごい。
で、ここからが大事な話なのだが、この作品、かなり激しい性描写・暴力描写がある。いわゆるエログロというやつだ。
間違いなく人を選ぶタイプの小説なので、気軽におすすめできるかと言われたら、絶対に無理である。読む人の心のどこかに闇を受け止められるスペースがないと、たぶん耐えられない。
でも誤解してはいけないのは、そういう過激なシーンがただの刺激とかショック目的で描かれてるわけではないってことだ。全部が「この異常者がこの世界で存在してる」というリアリティを支えるために、ガチで計算され尽くして配置されている。だから怖いし、だから凄い。
そして構成もめちゃくちゃ凝っている。
犯人である蒲生、彼の母親、そして元刑事という三人の視点が切り替わりながら進んでいくのだが、それぞれの視点が交錯することで、家庭の闇、人間関係の歪み、そして事件の本当の姿が少しずつ浮かび上がってくる。
しかもこの構成自体が、めちゃくちゃ巧妙なカモフラージュになってるから恐ろしい。
物語の終盤、ある一瞬に気づくのだ。「そういうことだったのか?!」と。読んできた話の正体が、ひっくり返る感覚。ここまで来て、ようやく全貌が見える。あの一行は本当に鳥肌モノだ。
あの一撃で、すべてが氷のように冷たく、確実に崩れる。
これはミステリとしてもかなり完成度が高い。ホラーだとかサイコだとか、ジャンルでくくる前に、「作品として圧倒的に強い」というのが正直な感想だ。
読む人は選ぶ。でも、刺さる人には一生ものの傷を残す。
その衝撃、その構築美、その異常なまでの完成度。どれを取っても、日本ミステリ史に残って当然の問題作だ。
怖いけど、読んでよかった。
そう思える人にだけ、そっと手渡してほしい作品だ。
8.その違和感が世界を反転させる── 殊能将之『ハサミ男』
巷では、若く美しい女性ばかりを狙い、殺害後に研ぎあげたハサミを首筋に突き立てるという猟奇的な手口の連続殺人犯「ハサミ男」が世間を震撼させていた。そのハサミ男は、次なる標的として三人目の犠牲者を選び出し、彼女の身辺調査を綿密に進めていた。
しかし、いざ犯行に及ぼうとしたまさにその時、ターゲットの女性が、自分と全く同じ手口で何者かに殺害されている現場に遭遇してしまう。一体誰が、何の目的で自分の手口を模倣したのか? なぜ自分以外の人間が彼女を殺す必要があったのか?
強い疑問と屈辱感を覚えた本物の「ハサミ男」は、模倣犯を自らの手で見つけ出すため、独自の調査を開始するのであった。一方、警察もこの模倣殺人をハサミ男による犯行と断定し、懸命の捜査を進めていた。
読者の固定観念を覆すトリックの妙
まず、掴みが強すぎる。
なんせ連続殺人鬼「ハサミ男」が、自分の模倣犯を追い始めるという導入だ。
追う側と追われる側がごっちゃになるような、普通のミステリじゃまずお目にかかれないスタートダッシュ。初速がバグっている。
でも驚くのは、そこから先だ。この「ハサミ男」というやつは、ただの異常殺人鬼というわけじゃない。理屈っぽく、冷めていて、妙に落ち着いているが、なぜか読んでいて感情が揺れる。
本人は生きることに興味がないっぽいし、死を望んでるようなセリフもある。しかし、なんか、完全に壊れきっていないのだ。
しかも語り口が一人称だから、読者はずっと彼の視点で話を追うことになる。この距離感の近さがクセモノで、気づかないうちに誘導されている。話の流れはそんなに複雑じゃないのに、どこかひっかかる違和感がずっとある。
その違和感が、ラストで炸裂するのだ。
「やられた!」と心から思えるあの瞬間。これを味わうために読んできたと言っても過言じゃない。
ど派手などんでん返しとか、衝撃展開という感じではなく、静かに世界が反転するのだ。しかも、そのトリックが意外とシンプル。構造は複雑じゃないのに、ひっかかる読者が後を絶たない。
それくらい、一人称の語りを使ったトリックの見本みたいな作品だ。
あと、ストーリーを引っ張っているのが「犯人は誰か?」じゃなくて、「おまえは誰なんだ?」という疑問なのもポイントが高い。動機とか過去よりも、視点そのものがテーマになっている。
そんな仕掛け満載のこの作品、第13回メフィスト賞を受賞してるのだが、そりゃそうだよなという感じだ。
今読んでも古びないどころか、むしろ「やっぱこれすごいわ」となってしまう。
正統派ミステリ好きにも、どんでん返し好きにも、構成フェチにも刺さるやつ。
罠にかかる快感をまだ知らない人に、まずはこの一冊を推したい。
9.ラブストーリーは、二行で地獄に変わる── 乾くるみ『イニシエーション・ラブ』
物語の舞台は、バブル景気に沸く1980年代後半の静岡県。当時、恋愛に奥手だった大学生の「僕」(鈴木夕樹)は、友人から人数合わせで誘われた合コンの席で、歯科助手の成岡繭子(マユ)と運命的な出会いを果たす。二人は互いに惹かれ合い、交際を開始。
物語の前半(Side-A)では、ドライブや海水浴など、初々しくも甘い二人の恋愛模様が瑞々しく描かれる。やがて鈴木は就職し、配属先の東京本社へ転勤することになり、マユとは静岡と東京での遠距離恋愛が始まる。
物語の後半(Side-B)では、距離と多忙な仕事によって二人の間に徐々にすれ違いが生じ、鈴木は東京で出会った同僚の石丸美弥子にも心惹かれていく。
一見すると、誰もが経験するような、あるいはどこかで聞いたことがあるような、ごく普通の青春恋愛小説として物語は幕を閉じるかに思われたが……。
「最後の二行」ですべてが覆る衝撃
出だしだけ見たら完全に80年代の恋愛ドラマだ。
舞台は静岡と東京、バブル前夜の大学生とOLのラブストーリー。デートはドライブ、デート中にかかる音楽は松田聖子、ファッションは肩パッド。そんなノリだ。
ちょっと不器用な男子と、魅力的な年上っぽい女子。甘酸っぱい恋のはじまり。
「あ〜こういうの昔のトレンディドラマにあったな〜」という感じで読み進める。
で、油断した頃にぶん殴られる。あの二行で。
冗談抜きで、「最後から二行目」という言葉が帯に書いてあるくらい重要だ。そこ読むまでは完全に良い話。でも、その瞬間に全部ひっくり返る。
あれよあれよという間に、純愛ラブストーリーがあのジャンルへと変貌する。しかもその変貌がめちゃくちゃ鮮やかだ。トリックの完成度が本当に高い。
すごいのは、どんでん返しがただのサプライズじゃないところだ。最初から仕掛けが張り巡らされていて、「あのセリフ」「あの描写」「あの言い回し」……全部トリックの一部だったと後から気づかされる。それで思わず「やられた!」と唸ることになるわけだ。
で、当然のようにもう一回読み直す。二周目になると、登場人物の表情や言葉の裏の意味が見えてくる。「そのセリフって、そういうことだったのかよ……」と何度もなる。一粒で二度おいしいどころじゃない、読後感がまるで別物だ。
この小説、見た目は恋愛、でも中身は完全にミステリ。
ラブストーリーに見せかけたミステリってこういう形もあるのか!という驚きがあるし、ミステリ初心者でも読みやすいから、入門編にもぴったりだ。
ネタバレ厳禁。とにかく最後まで読んでから語ってくれ。
そのラスト2行を味わうまでは、誰にも中身を聞いてはいけない。
で、読み終わったら言いたくなるはず。
「なにこれ、最高かよ」と。
10.あの夏、真実だけが欠けていた── 道尾秀介『向日葵の咲かない夏』
夏休みを目前にした終業式の日、小学四年生のミチオは、学校を欠席した同級生S君の家に届け物をするよう先生に頼まれる。
S君の家を訪れたミチオが目にしたのは、首を吊って死んでいるS君の姿であった。衝撃を受け、その場を離れたミチオが戻ると、S君の死体は跡形もなく消え失せていた。
それから一週間後、ミチオの前に、S君があるものに姿を変えて現れる。「自分は自殺したのではなく、殺されたんだ。犯人を見つけ出してほしい」と彼は訴える。
ミチオは妹のミカと共に、S君を殺した犯人を探し始める。しかし、調査を進めるにつれて、ミチオ自身の記憶や認識の危うさ、そして彼を取り巻く大人たちの奇妙で歪んだ言動が、次々と明らかになっていくのであった。
巧妙なトリックと伏線回収
語り手は小学四年生の男の子・ミチオ。舞台は夏休み。普通なら虫取りとかプールとか、楽しいイベントが詰まっているはずの季節。
しかしこの話、最初からずっと空気が湿っている。不穏という言葉がこれほど似合う夏も珍しい。
何が不穏って、まず死んだはずのクラスメイトが「転生して蜘蛛になった」とか言ってミチオに語りかけてくる。もうその時点で現実と妄想の境界が怪しいし、子どもたちの無邪気さが妙に怖い。周囲の大人たちも、なんか様子がおかしい。全体的に常識のねじがちょっと緩んでいるのだ。
この作品のキモは、「現実と幻想のあいだをずっとふらふらしてる感じ」だと思う。ミチオの視点を通して進んでいくから、読者は彼が見る世界を信じるしかない。でも読み進めていくと「ん? これって本当にあったこと?」みたいな粘ついた違和感が出てくる。
道尾秀介という作家は、この「語りの不確かさ」を操るのがめちゃくちゃ上手い。ミチオの語りが信用できるようでいて、どうもそうでもない。そんな綱渡りの読書体験が、妙に脳に焼きつくのだ。
そして後半、いろんな描写がパズルのピースみたいにハマっていくと、「そういうことか……!」と背筋が冷える。最後のどんでん返しは、ほんとに地面が裏返るみたいな感覚だ。
しかもラストを知ったあとで冒頭を読み返すと、同じ文章がまったく違う顔を見せてくる。あれはズルい。怖いけどすごい。
ただ、これだけは言っておくけれど、読後感は悪い。誰も救われないし、何もスッキリしない。人によっては「なんだこれ」とモヤモヤする終わり方だ。でも逆に、その後味の悪さがこの作品の大きな魅力でもある。いわゆるイヤミスの中でも、トップクラスに記憶に残るタイプだ。
全部が全部、明かされるわけじゃない。でも、だからこそ印象に残る。この不完全さと不条理が、妙にリアルなのだ。
ミステリとして読むもよし、ホラーとして読むもよし。
でも一番大事なのは、「これは子どもの話だけど、子どもだけの話じゃない」ということ。
すべてがきっちり解決するわけではない。
それでも、だからこそ忘れがたい。
この曖昧さこそが、本作をただのミステリではなく、読む人の心に深く刻まれる一冊にしている理由だ。
11.パズルの最後の一片がはまる、その快感── 伊坂幸太郎『アヒルと鴨のコインロッカー』
大学進学のため仙台に引っ越した椎名は、隣人の謎めいた青年・河崎と出会う。彼は椎名に「一緒に本屋を襲わないか」と持ちかけ、その目的は『広辞苑』を奪うことだった。戸惑いつつも、椎名は河崎に巻き込まれていく。
物語は、現在の二人の行動と並行して、河崎の元恋人・琴美や留学生・ドルジが関わる、二年前の悲劇的な出来事も描く。現在と過去の出来事は次第に交錯し、無関係に見えた点が繋がり始める。
やがて、河崎の真の目的、二年前の事件の真相、そしてタイトルの意味が明らかになり、切なくも衝撃的な結末へと収束していくのであった。
伊坂作品ならではの伏線回収を存分に楽しめる
伊坂作品の中でも、これはとびきり美しい構造を持った一作である。
仙台に引っ越してきたばかりの大学生・椎名が、本屋襲撃計画に巻き込まれる「現在」のパートと、2年前に琴美やドルジ、河崎、麗子らが体験した「過去」の出来事が、章ごとに交互に語られていく──この構成だけでもう、伊坂ワールド全開だ。
最初はまったく接点がなさそうに見える現在と過去のふたつの時間軸が、読み進めるうちに少しずつ交差して、最後には一つの真実にぴたりと収束していく。その流れが本当に見事で、構成で魅せる小説の理想形みたいになっている。
過去に起きた出来事が、現在のキャラたちの行動に影響を及ぼしていたことがわかってくると、「あのとき、なぜ彼らは──」という感情が胸を締めつけてくる。この物語の骨組みそのものが、読む人の感情を丁寧に導いてくれるような仕掛けになっているのがすごい。
で、伊坂作品といえば、やっぱり伏線の巧さだ。
さりげない一言や何気ない動作、小道具の扱い方まで、すべてがラストに向けて「そうきたか!」と収束していく。パズルのピースがぴたりとはまっていく快感が、しっかり味わえる一冊だ。
特に印象に残るのが、終盤で椎名が「君は、物語に途中参加しただけなんだ」と告げられる場面。このセリフでそれまでの景色が一気に反転する。自分が読んでいたつもりだった物語の意味がガラッと変わる、あの感覚。最高だ。
誰が主役で誰が傍観者なのか、視点のズレを利用して読者の認識をひっくり返してくるのも、伊坂幸太郎ならではの芸当。まさに物語そのものが仕掛けになっている。
キャラクターたちも個性派揃いだ。飄々とした河崎、流されがちだけどどこか憎めない椎名、優しさと強さをあわせ持つドルジ、そしてミステリアスな麗子。それぞれの会話のテンポが良くて、クスッと笑えるユーモアもありつつ、ふと本質を突いてくるセリフもある。何気ないやりとりひとつ取っても、味がある。
ミステリとしても面白いし、人間ドラマとしても深い。そしてなにより、この作品が好きだと思える気持ちを誰かと共有したくなる。わたしも伊坂作品は全部読んでいるが、『アヒルと鴨のコインロッカー』は確実にトップ3に入る。
物語に途中参加するなんてもったいない。
伊坂幸太郎という作家の芯が詰まった傑作だ。

12.やられた、では終われない── 歌野晶午『葉桜の季節に君を想うということ』
自称「何でもやってやろう屋」の成瀬将虎は、フィットネスクラブで知り合った女性・久世愛子から、高齢者を狙う悪質な霊感商法「蓬莱倶楽部」の実態調査と、それに関わって死亡したとされる身内の死の真相究明を依頼される。
時を同じくして、成瀬は駅のホームで投身自殺を図ろうとしていた麻宮さくらという女性を偶然助け、運命的な出会いを果たす。
調査を進める中で、成瀬はさくらとの関係を深めていくが、蓬莱倶楽部の詐欺被害に遭い人生を狂わされた人たちの存在や、成瀬自身の過去が複雑に絡み合い、物語は誰も予想しなかった意外な方向へと展開していく。
二度読み必至の究極の徹夜本
なぜこの小説が、こんなにミステリファンから熱く支持されてるのか。
理由は簡単。あのトリックだ。人の思い込みを逆手に取って、ど真ん中からきれいに切り返してくる。伏線の張り方がいやらしいくらい巧くて、読んでる最中に「あれ?」と思っても、まんまと引き込まれてしまう。
ラストの一文で、すべてが反転する。見えていたはずの景色が、あっさりひっくり返る。あの快感は格別だ。「二度読まなきゃもったいない」と言われるのも納得だし、実際、仕掛けがわかってても騙されるという声すらある。つまり、構成の精度がバケモノ級ということだ。
ただし、主人公・成瀬将虎のキャラには要注意である。あいつはかなり個性的だ。軽犯罪ギリギリの行動は平気でするし、女関係もだらしないし、口調もなんか鼻につく。まともに共感できる部分がなかなか見つからない。
しかし、実はそこが重要なポイントだったりする。読者の嫌悪感や警戒心をうまく利用して、物語のある部分から視線をそらす。成瀬のうさんくささが、トリック成立のための完璧なカモフラージュになっているのだ。だから「なんかこの主人公ムリだわ」と思った人ほど、作者の術中にどっぷりハマっている可能性が高い。
物語の軸は「霊感商法の調査」なのだが、ヒロインの麻宮さくらとの微妙な恋愛模様や、成瀬のちょっと古風なハードボイルド語りなんかも相まって、かなり独特な味わいが出ている。ジャンルを一言で言い切れない、あの混ざり方が絶妙だ。
前半はややゆるめで、「これはどこに向かってるの?」と感じる人もいるかもしれない。でも、後半に入ってからの回収ラッシュがすごい。一つずつ点と点が線でつながって、最後にはしっかり落ちる。テンポが一気に加速するから、そこまで辿り着けばもう止まらない。
タイトルの詩的な響きとは裏腹に、物語が扱うテーマはかなりシビアだ。読後に残るのは、ただの「やられた!」じゃない。痛みと余韻がずっと引っかかる。トリックの妙と感情の深み、両方をしっかり味わえる作品はそう多くない。
ミステリを読み慣れた人にも、久々に読書で驚きたい人にも、自信を持っておすすめできる。
これはまさに、小説という形式じゃなきゃできないマジックだ。
13.犯人役も探偵役も、全員が罠── 歌野晶午『密室殺人ゲーム王手飛車取り』
インターネット上には、奇妙なハンドルネームを持つ5人の男女が集うチャットルームが存在した。〈頭狂人〉、〈044APD〉、〈aXe〉、〈ザンギャ君〉、〈伴道全教授〉と名乗る彼らは、互いに自作の殺人事件のシナリオを提示し、その謎を解き明かすという高度な推理ゲームに興じている。
しかし、このゲームには恐るべき秘密が隠されていた。彼らが「問題」として提示する殺人事件は、単なる創作物ではなく、出題者自身が現実に犯した殺人だったのだ。
密室、アリバイトリック、ダイイングメッセージ。本格ミステリのあらゆる要素を盛り込んだリアル殺人ゲームは、次第にエスカレートしていく。彼らの歪んだ遊戯は、一体どこへ行き着くのであろうか。
茫然自失のラストまで一気読み
この作品のいちばんの魅力は、なんといっても「ネット上の推理ゲーム」と「現実の殺人事件」がガチでリンクしてしまう、衝撃的な構成にある。
ネット掲示板の匿名空間で、遊び感覚のつもりで語られる「殺人計画」。でもそれが、実は現実でも起きていた……というゾッとする展開。現代ミステリらしい新しさと怖さが、がっつり詰まっている。
ゲームの参加者たちは、犯人役と探偵役をローテーションで演じながら、仮想事件の真相を推理していく。登場キャラたちは、理詰めで攻める本格派から、クセだらけのマニアック系、さらにはミスリードを撒き散らすトリックスターまで揃っていて、プレイヤーごとの個性を見るだけでもニヤけてくる。
昭和〜平成のクラシカルなミステリのノリを、ネット時代に持ち込んで再構築したような仕掛けが実に巧妙で、ベタなのに新鮮。ミステリ好きならこの構造だけでごはん3杯いける。
もちろんトリックも抜かりなし。読者の思い込みや先入観を逆手に取る仕掛けがバッチリ決まっていて、『葉桜の季節に君を想うということ』を彷彿とさせる騙しが炸裂する。
特にあの人物の正体が明かされる場面は最高だ。ハンダごての伏線や進路希望の一言など、「やられた……」となること請け合い。騙されて気持ちいいミステリ、ここに極まれり。
そして終盤の、あのゲーム。この展開には度肝を抜かれる。倫理と現実の境目がグラグラ揺らいでいくなかで、ゲームの仮面がズタズタに剥がれていくスリル。まさかこの読後感で終わるとは思わなかったし、わざと残した曖昧さがまた絶妙なのだ。
でも、単なるエンタメでは終わらないところが歌野晶午の真骨頂。ネットという便利で無責任な空間が、人の良心や境界感覚を麻痺させていく、その怖さが効いてくる。
ただの仮想空間で済まない、現実とのリンクがここまで危ういとは。これは現代ミステリとして、けっこう本気で警告になっている。
サスペンスとしても、構成トリックとしても、社会派としてもめちゃくちゃ優秀。どこから読んでも面白いのに、読み終えた後にグサッと刺さるものが残る。
こんなの、ミステリ好きなら見逃す理由がない。
14.上品な言葉の裏に、毒が潜む── 米澤穂信『儚い羊たちの祝宴』
上流階級の子女たちが集い、読書と夢想に耽る優雅なサークル「バベルの会」。 しかし、その雅やかな世界の水面下では、邪悪な意志が蠢いていた。
物語は、会員である丹山吹子の屋敷で、夏の合宿を目前に控えたある日に起こった惨劇から幕を開ける。その後も、まるで呪いのように、同じ日に吹子の近親者が次々と殺害されていく。
四年目には、更なる凄惨な事件が発生し、バベルの会を巡る五つの事件は、次第にその輪郭を現していくのであった。甘美さすら感じさせる語り口とは裏腹に、 最後に明かされる残酷な真実は、読者の脳髄を冷たく痺れさせる。
これは、米澤流暗黒ミステリの真骨頂を示す連作短編集。
米澤流「暗黒ミステリ」の真髄
米澤穂信のダークサイドが凝縮された、背筋にひびく短編集。それがこの『儚い羊たちの祝宴』だ。
直接的な暴力や血みどろの展開はほぼない。しかし、不穏な空気が最初から最後までずっと漂っていて、読んでいるうちに、どこか精神が削られていくような感覚に陥る。
読後感はめちゃくちゃ重い。救い? そんなもの、どこにもない。でも、その暗さがただの不快じゃない。人の内面の歪みとか、上品な顔をした狂気とか、そういうギリギリの部分をきれいに切り取ってみせるから、怖いのに見てしまう。
印象的なのは、やっぱり登場人物たちの言葉遣いだ。めちゃくちゃ丁寧で上品。育ちの良さがにじみ出ている。でも、その内側で渦巻いてるのは、執着とか、冷酷な合理主義とか、ぞわっとするような感情ばかり。表の顔と裏の本性のギャップがキツい。
舞台は「バベルの会」。上流階級の子女たちが集う、ある種の閉ざされたサロンみたいな場所なのだが、ここで繰り広げられるのが、理性と狂気のせめぎ合いだ。しかも、どの話も美意識とか知性への執着が根っこにあって、そこにほんの少しずつヒビが入って、やがて崩れていく。その過程が丁寧すぎて、逆に怖い。
『バベル』というタイトルの意味もまた皮肉が効いている。美しさや知性を極めようとして築いた塔が、結局は不協和音の果てに崩れていく、そんな感じだ。
そして『祝宴』。これは別に楽しいパーティーの話じゃない。むしろ、登場人物たち自身が祝宴の生贄にされている。そんな黒い皮肉が、物語全体にしれっと染みついてるのだ。
どの話も短いが、めちゃくちゃ後を引くのも特徴だ。ラストで見せる一手が地味に効いてきて、気づいたときには心のどこかがザラつく。読んでるあいだは「きれいで上品なミステリ」っぽいのに、いつの間にかすっかり〈毒〉を盛られている。そんな作品だ。
明るくて気持ちのいいミステリが好きな人には、あまりおすすめしない。でも、上品な文章で描かれる人の黒い部分とか、言葉の裏にある冷たさとか、そういうのが好きな人にはドンピシャだ。
静かに壊れていく人たちの話が好きなら、この祝宴は、忘れられない後味を残してくれる。

15.謎を解くたび、青春が少しずつ色づく── 米澤穂信『氷菓』
神山高校に入学した折木奉太郎は、「やらなくてもいいことなら、やらない。やらなければいけないことなら手短に」を信条とする「省エネ主義者」である。姉の勧めで廃部寸前の「古典部」に籍を置くことになった彼は、そこで運命的な出会いを果たす。
一身上の都合で古典部に入部したという少女、千反田える。 彼女の「わたし、気になります!」という飽くなき好奇心に巻き込まれる形で、奉太郎は、同じく古典部に入部した中学からの友人・福部里志、伊原摩耶花と共に、学園生活に潜む様々な「日常の謎」に挑むことになる。
中でも、えるが伯父から聞き、幼心に涙したという33年前の出来事と、古典部の古い文集『氷菓』に秘められた謎が、彼らの活動の中心となっていくのであった。
日常の謎を解き明かす面白さと、個性溢れる古典部員の魅力
殺人事件なんて出てこない。でも、間違いなくこれは最高のミステリだ。
『氷菓』の魅力は、そんな大事件じゃない事件、いわゆる「日常の謎」を丁寧に掘り下げているところにある。
たとえば、「なぜ教室が密室状態になっていたのか?」「なぜ特定の本だけが毎週借りられるのか?」という、地味な謎。でも、それが気づけばとても気になってくる。
そして主人公・折木奉太郎が、その省エネ主義をかなぐり捨て……るほどじゃないが、持ち前の観察眼と推理でズバッと解き明かしてくれる。このスッキリ感がいい。
古典部メンバーもまた個性的で魅力に溢れている。
やる気なさそうな奉太郎、なのに推理はキレキレ。
「わたし、気になります!」が口癖の千反田えるは、もう天然好奇心のかたまり。
情報収集は任せろな里志、毒舌気味だけど根は真面目な摩耶花。
この4人の掛け合いが、とにかくテンポよくて、読んでて楽しい。会話だけで一生読んでいたいレベルだ。で、これがまた、ただの謎解きエピソード集に終わらない。青春小説としての味わいがすごく濃い。
省エネ主義を掲げてた奉太郎が、えるとの出会いや仲間とのやりとりを通して、少しずつ変わっていく。ほんとに少しずつなのだが、その一歩一歩がリアルで、読んでいて胸にくるのだ。
そして何より、この物語のタイトルにもなっている『氷菓』の謎。こんなに切ない伏線回収ある?というくらい、ぐっとくる。あの場面でタイトルの意味が明かされたとき、優しさと悔しさと、知らなかった誰かの痛みが、ひんやりと胸に残るのだ。
たぶん、奉太郎の省エネとは、生き方そのものだ。できれば関わらずに済ませたい。無駄なことはしたくない。でも、えるのまっすぐすぎる「気になります!」に触れてしまったから、もう、そうもいかなくなってくる。
この小さな変化がたまらなくいい。
そう思えるなら、もうこの作品はあなたに刺さっている。
日常に潜む違和感を拾い上げて、そこから人の心の奥底を掘っていく。
派手じゃないけど、確実に胸に残る。そんなビターで優しい青春ミステリだ。
「世界を鮮やかに見る」って、こういうことかもしれない。
16.同じ一日が九回、真実は一つ── 西澤保彦『七回死んだ男』
高校生の大場久太郎には、奇妙な特異体質があった。それは、彼が「反復落とし穴」と呼ぶ現象で、ある特定の一日を、本人の意思とは無関係に九回繰り返してしまうというものである。 九回目の繰り返しが、最終的に確定する現実となる。
ある年の正月、久太郎は資産家の祖父・渕上零治郎の邸宅での新年会に参加する。祖父が後継者指名を宣言したことで、親族間に不穏な空気が流れる中、久太郎はこの日に「反復落とし穴」に嵌ってしまう。 さらに悪いことに、繰り返される一日の中で、祖父が何者かに殺害されるという事態が発生。
久太郎は、ループする時間を使い、祖父の死を回避しようと奮闘するが、彼の行動によって状況は変化し、殺害方法は変われども祖父の死は避けられない。 果たして久太郎は、九回目のループが訪れる前に犯人を見つけ出し、祖父を救うことができるのだろうか。
SF設定と本格ミステリの絶妙な融合
同じ一日が、何度も繰り返されるとしたら。
それは奇跡のようでもあり、地獄のようでもある。
西澤保彦の『七回死んだ男』は、そんな時間のループに囚われた高校生・久太郎が、殺人事件の真相に迫る話だ。
しかしこの作品、ただの「タイムループSF」じゃない。むしろタイムループそのものが、ミステリのトリックとしてめちゃくちゃ巧妙に機能している。そこがすごい。
物語の軸は、久太郎の家族が殺されるという悲劇の一日。だけど彼には「同じ日を9回繰り返す」という特殊な体質(作中では「反復落とし穴」と呼ばれている)があって、何とかして事件を防ごうとする。1周目でミスっても、次でリカバリ、さらに次で仮説を立て直し……という、地道すぎる推理の積み重ねが見どころだ。
ただ、「時間を繰り返せる=簡単に解決できる」というわけじゃない。むしろ、知ってるのは久太郎だけというこの状況が、本格ミステリとしてめちゃくちゃハードだ。ひとつの証拠にたどり着くまでの試行錯誤がリアルで、読んでいるこっちも一緒に謎に挑んでる感覚になる。
しかもすごいのは、SFっぽい設定なのに、論理は完全にフェア。超能力で「なんとなく真相がわかっちゃいました!」みたいなズルは一切なし。久太郎の推理はきちんと地に足がついていて、ちゃんと論理で解くタイプのやつだ。そういうところが、本格好きにはたまらない。
そして終盤、すべてのピースが揃った瞬間にくる「あーーーー、そういうことか!」という爽快感。あの感覚はやめられない。ループ中に感じてた違和感、登場人物の何気ない行動や言葉、全部が一つの場所にきれいに着地する。この構造の美しさは本当に圧巻だ。
タイムループ×本格ミステリというのは、難しそうに見えて相性が抜群。『七回死んだ男』はその見本みたいな一冊だ。ラストで久太郎がたどり着く正解には、敗北感と同時にちょっとした希望もある。
ミステリ好きも、SF好きも、構造美フェチも、これは読んでほしい。ていうか読んでくれ!
「面白い物語ってこうやって組み立てるんだよ」という、作者からのドヤ顔を真正面から食らう感覚、最高だから。
17.真実とは、救いではなく絶望だ── 貫井徳郎『慟哭』
物語は、二人の男の視点から交互に語られる。一人は、警視庁捜査一課を率いる若きエリート管理官、佐伯。
彼は、世間を震撼させる連続幼女誘拐事件の捜査指揮を執るが、捜査は難航し、警察内部からの嫉妬やマスコミからの批判に晒され、精神的に追い詰められていく。複雑な出自を持つ彼は、家庭内にも問題を抱えている。
もう一人は、最愛の娘を失った深い悲しみから立ち直れず、虚無感を抱える男、松本。 彼は救いを求めて新興宗教「白光の宇宙教団」に傾倒していくが、その信仰は次第に狂気を帯び、取り返しのつかない領域へと足を踏み入れてしまう。
一見無関係に見える二つの物語は、読者の予想を裏切る形で交差し、慟哭の結末へと突き進むのであった。
圧倒的な読書体験と重い余韻
これは間違いなく、ミステリというジャンルが持ちうる構成の暴力を最大限に使い切った作品の一つだ。
何がすごいって、読みながら「完全に騙されていたこと」にすら気づかない。そのくらい自然に、巧みに、物語は進んでいくのだ。
警視庁の刑事・佐伯と、娘を殺されたことで宗教にすがっていく松本。この二人の視点が交互に描かれ、何の疑いもなく「これは犯人と捜査側、ふたつのラインで展開する誘拐事件の話だ」と思い込んでしまう。
で、気づいたときにはもう遅い。終盤の“あれ”で前提が崩壊した瞬間、頭を殴られたみたいにしばらく固まるのだ。これは、仕掛けそのものの完成度も高いが、「その構造があってこそ響くテーマ」があるのがまた凄まじい。
たとえば、「信じること」ってなんなんだろうな、とか。家族を喪ったとき、人はどこに救いを求めるのか。あるいは、正義のために働く側の人が、いつか善悪に揺らぐ瞬間は訪れるのか。
どっちの登場人物も、本当にリアルだ。泣き叫ぶでもなく、ただひっそりと壊れていく感じが、妙に肌に貼りついてくる。
松本が壊れていく過程はキツいし、佐伯の冷静さの裏にある葛藤も深い。どちらも普通の人なのだ。特別な悪意じゃなくて、誰にでもありうる絶望や矛盾が彼らを追い込んでいく。
タイトルの『慟哭』とは、そういう「声にならない悲鳴」のことだ。ただ泣くんじゃなく、心の奥底から搾り出されるような、悲しみの圧力。読後に残るのはまさにそれで、胸の奥にずしんと沈殿する感じだ。
ミステリ好きにとっては、この構成と仕掛けだけでも読む理由になる。
でも、それだけじゃ終わらない。人の弱さ、醜さ、救いのなさ。そういうものを、淡々とした文体でぐいぐい突きつけてくる。
派手などんでん返しじゃない。感情に任せた激情でもない。
それでも、読み終えたあとに膝を抱えてうずくまりたくなるような、圧倒的な読書体験になる。
そのとき心に残るのは、叫びですらなく、ひび割れた沈黙のような音だ。
18.古典の顔をした、構造爆弾── 筒井康隆『ロートレック荘事件』
夏の終わり、木内文麿氏が所有する郊外の瀟洒な洋館「ロートレック荘」には、将来を嘱望された青年たちと、美貌の娘たちが集っていた。
館内は高名な画家、アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレックの作品で彩られ、優雅な数日間のバカンスが始まるかに見えた。
しかし、二発の銃声が惨劇の始まりを告げる。館内で発見された美女の死体。警察が捜査を開始し、館の監視を強めるも、それを嘲笑うかのように、一人、また一人と美女たちが殺害されていくのであった。
閉ざされた館の中で、犯人は一体誰なのか。そして、その目的は何なのか。
SF界の巨匠が仕掛ける驚愕のトリック
『ロートレック荘事件』は、あの筒井康隆が本格ミステリに本気で殴り込みをかけた異色作だ。
「筒井康隆がミステリ?」と思った人こそ、油断は禁物。ジャンルの型にしれっと従ってるように見せて、最終的には読者のアタマを真っ白にしてくるトリックが待っている。
舞台は洋館。登場人物たちは限られた空間に閉じ込められ、次々と殺されていくという、古典的な設定。にもかかわらず、読んでいてなぜか会話が変に感じたり、描写の歯切れが悪かったりする。その違和感がだんだん蓄積されて、最後の最後に「ああそういうことか!」と、物語の構造そのものがひっくり返されるのだ。
情報が曖昧なのには、ちゃんと理由がある。視点操作、時系列トリック、言葉のズレ……あらゆる手段で「読み手の目」を揺さぶってくる。しかもその仕掛けが、けっしてフェアじゃないわけじゃない。むしろ、フェアすぎて見落とすタイプのやつだ。
トリックが解けた瞬間、全編に漂っていた不自然さが一気に一本の線につながる。この快感は、完全にやられた人にしか味わえない。
ただ、筒井康隆らしく、ここにはユーモアも風刺も混ざっている。犯人の動機はあまりに軽くて笑えるし、ミステリで定番の「見取り図」があえて機能しないように描かれてたりして、「お約束」をちょっと鼻で笑ってる感じすらある。
そしてもう一つ特徴的なのは、キャラクターの感情にはほとんど重きを置いていないことだ。ドラマ的な盛り上がりとか、人の悲しみや救いとか、そういうのは皆無。むしろ、トリックがすべてっていう潔さがある。その冷たさが逆に心地いい。
ページ数は少なくて、サクッと読める。でもそのぶん、評価はバッサリ分かれるタイプの作品だ。
「騙された!最高!」と叫ぶ人もいれば、「ふーん、そんなもんか」で終わる人もいる。
ただ、トリックを読むためにミステリを読むタイプの人、つまり、ミステリという構造が好きな人にとっては、この作品は見逃せない。
本格の「型」を一度ぶち壊してから組み直すようなこの一冊は、トリックの魔力に身を委ねたい人に、ぜったい刺さる。
19.フェアに騙される、という贅沢── 倉知淳『星降り山荘の殺人』
広告代理店に勤める杉下は、上司とのトラブルが原因で、社内の芸能部に異動させられる。 彼に与えられた仕事は、女性に人気の文化人タレント「スターウォッチャー」こと星園詩郎のマネージャー見習いであった。
異動早々、杉下は星園と共に、埼玉県奥地の山中にあるオートキャンプ場「星降り高原コテージ村」へと向かう。
キャンプ場の宣伝イベントに集ったのは、オーナー社長とその付き人、人気女性作家と秘書の麻子、UFO研究家、そしてモニター参加の女子大生二人組といった、一癖も二癖もある面々であった。 和やかな雰囲気も束の間、翌朝、参加者の一人が遺体で発見される。
折からの猛吹雪と雪崩により、キャンプ場は完全に孤立。電話も通じないクローズドサークルと化した山荘で、星園は得意の観察眼を武器に、杉下をワトソン役に指名して捜査を開始するが、第二の殺人が発生してしまうのであった。
予測不能な展開と、鮮やかなどんでん返し
この作品について、なによりもまず最初に言いたいのは、作者がめちゃくちゃ親切すぎるということだ。
「そろそろ探偵が登場しますよ」とか、「この会話、伏線なんで覚えておいてね」とか、そんな具合に作者がガンガン話しかけてくる。ナビゲーターかよ、というくらいの親切設計。
だから、つい信じてしまう。
「これはフェアなミステリです」「全部提示されています」なんて言われたら、こっちも「OK、しっかり読んでやるぞ」という気になる。
でもこれが、最大のワナなわけだ。
そう、あまりにフェアを装ってくるものだから、つい油断してしまう。でも実際には、こっちの目を巧妙に逸らしてるだけ。読者に歩かせておいて、落とし穴にはまらせる、あの感じ。うますぎる。
本作のすごいところは、「読者への語りかけ」という親切すぎるメタ構造を、単なるおふざけに終わらせず、トリックの本質にがっつり組み込んでる点だ。しかも、終盤でとんでもないどんでん返しが待ってる。
登場人物の立ち位置、役割、視点の前提……そのあたりを全部ひっくり返してくる。「は? え? そんなことある?」となる。でも、ちゃんと読み返すと全部そこにあったという絶妙なバランス。
舞台は雪に閉ざされた山荘。いわゆるクローズドサークルものの王道だが、重くなりすぎないのはキャラクターの魅力のおかげだ。クセが強めの登場人物たちが、軽妙なやりとりでテンポよく物語を引っ張ってくれる。
会話劇が心地よくて、ついつい読み進めてしまうし、その間にもちゃんと伏線がしれっと仕込まれてるあたり、ほんとに芸が細かい。
倉知淳らしいユーモアと、本格ミステリらしい緻密な構成が高次元で融合してて、「楽しいミステリってこういうことだよな」と思わせてくれる傑作だ。
気楽に読めるのに、最後にしっかり殴られる。
しかもそのパンチは、見えないところからきっちり入ってくるのだ。
20.信じた瞬間、裏切られる── 東野圭吾『仮面山荘殺人事件』
結婚間近に婚約者・森崎朋美を事故で失った樫間高之は、三ヶ月後、朋美を偲ぶため森崎家の別荘に招かれる。そこには高之を含む8人の男女が集まっていた。
その夜、朋美の死が事故ではなく、殺人だった可能性が浮上する。直後、逃亡中の銀行強盗が山荘に侵入し、一同を人質に取るが、さらなる惨劇が発生。参加者の一人が殺されてしまう。
状況から犯人は強盗ではない。通信手段を絶たれた中、残された7人は、見えざる殺意と互いへの疑念に揺れながら、真相に迫ろうとする。
全てを覆す大胆不敵なトリック
閉ざされた山荘に、銃を持った強盗が押し入ってくる。はい、この時点でもう完璧な密室サスペンスだ。しかし本作が本当にすごいのは、そこからさらにもう一段深く仕掛けてくるところにある。
外部との通信も断たれ、脱出も不可能。しかも、立てこもった強盗の中に本当の殺人犯がいるかもしれないという疑惑まで乗っかってくる。もう、ただでさえ密室なのに、登場人物たちの心理まで密室状態だ。
そして東野圭吾といえば、どんでん返し。もちろん今回もキレッキレで、終盤のひっくり返し方は、想像ごとぶん投げてくる勢いだ。
それまでの会話や動きに「あれ?」「なんか変だな」と思わせる違和感が、最後になってすべて回収される気持ちよさ。まさに、伏線ってこうやって張るんだぞっていうお手本みたいなやつだ。
しかもこの小説、全体を通して「誰が本当の顔をしていて、誰が演じているのか」がずっとテーマになっている。まさに『仮面山荘』というタイトルの意味が、あとになってズシンと効いてくるのだ。
舞台となるのは雪に閉ざされた山奥の別荘。ありがちなシチュエーションに見えるかもしれないが、ここまで計算され尽くした舞台装置に仕上げてくるのは、やっぱり初期の東野圭吾は只者じゃない。
1990年発表の初期作だが、完成度は今読んでも十分通用するし、テンポの良さと構成のうまさには脱帽する。社会派要素よりも純粋な謎解きの快感に特化した構成だから、ミステリ初心者にもスッと入りやすいし、トリックにうるさい玄人でも唸る仕掛けがある。
読み終えたあと、「もう一回最初から読んでみたいな……」となるタイプのミステリだ。
トリックと構成の妙、そして物語を信じすぎた読者への軽やかな裏切り。
東野圭吾が本格ミステリに振り切ったらこうなる、という見事な完成形だ。
21.殺人劇は、演技のはずだった── 東野圭吾『ある閉ざされた雪の山荘で』
劇団に所属する男女7人が、新作舞台の最終オーディションに合格し、早春の乗鞍高原にあるペンションに集められる。課題は、「豪雪で孤立した山荘で起こる連続殺人劇」を演じることだった。
だが稽古が進む中で、メンバーがシナリオ通りに次々と姿を消していく。これは演出か、それとも本物の殺人なのか? 疑心暗鬼に陥った残された者たちは、真相を探り始める。
虚構と現実の境界が崩れていく中で描かれる、閉ざされた空間のサスペンス・ミステリー。
劇中劇構造が生む独特の緊張感
オーディション会場に集められた参加者たちが、殺人劇を演じる……というだけでもう面白いが、ここからがこの作品の本領発揮。「演技」なのか「現実」なのか、その境界がとにかく曖昧なのだ。
舞台は雪山の山荘。いわゆるクローズドサークルものの王道だが、今回はその設定自体が演出の可能性もあるっていう、二重三重にメタっぽい構造になっている。
登場人物たちはオーディションの参加者。そのオーディション内容が「殺人事件の再現」という時点で、すでに頭が混乱してくる。何がリアルで、何が台本通りの演技なのか。読み進めているこっちも、まるでオーディションを受けている一人みたいな気分になってくるのだ。
この作品がすごいのは、読者の「これはミステリだよね?」という前提すら揺さぶってくるところだ。つまり、ジャンルの約束をうまく逆手に取ってくる。
クローズドサークルに見えるが、それすら仕掛けかもしれないし、容疑者に見えるあの人も、実はただの俳優かもしれない。物語のすべてが演技かもしれない世界で、読み手は真実にたどり着けるか?というゲームなのだ。
終盤、伏線が一気に回収される爽快感はさすが東野圭吾。台詞の一つ、仕草の一つ、すべてが意味を持っていて、「あれも台本だったのか」「そこにもヒントがあったのか」と、何度でも読み返したくなる。
キャラも立っているし、テンポもいい。文章も軽やかだから、入り口はすごく読みやすいのに、後半になるにつれてどんどん奥行きが出てくる。終わってみると、「誰が犯人か?」ではなくて「この話は、そもそも何だったのか?」という問いに変わってることに気づく。
正統派のミステリ好きにも、メタ構造好きにも、それぞれ響く要素があるはずだ。
まさに、東野圭吾の遊びが光る名作である。
22.宣言から始まる、究極のゲーム── 西村京太郎『殺しの双曲線』
差出人が不明な招待状を受け取り、東北地方にある山荘「観雪荘」に集まった6人の男女。彼らは半信半疑の気持ちを抱きつつも、雪景色の中での滞在を満喫する。しかし、やがてその山荘は外界から隔絶された状況となり、次々と殺人事件が発生するに至る。
アガサ・クリスティの名作『そして誰もいなくなった』を彷彿とさせるクローズドサークルという閉鎖空間の中で、恐怖と相互不信が広がっていく。
物語は、その冒頭において「双子によるトリック」が用いられることを示唆しており、読者はこの前提知識を持った上で、事件の真相と犯人の特定に挑むことになる。
双子トリックの事前提示という挑戦
「双子トリックが使われています」
冒頭でいきなりそう宣言してくるミステリなんて、ほかに聞いたことがない。にもかかわらず、しっかり騙される。それがこの作品のすごさだ。
普通なら、トリックのネタバレは絶対に避けるもの。しかしこの物語では、あえて種明かしを最初に置くことで、推理のベクトルをズラしてくる。「誰が双子なのか?」「どうやって既知のトリックを成立させているのか?」という方向に自然と意識が向かう構造だ。
舞台は雪山の洋館。典型的なクローズドサークルだが、そのお決まりを逆手に取る仕掛けが見事。双子という設定があるだけで、誰が誰なのか、今どっちが動いてるのか、会話の裏に何があるのか。すべてが怪しく見えてくる。
事件は次々に起こる。死体も転がる。会話に仕込まれた違和感や行動のズレも、ちゃんと意味がある。気づくか気づかないかは、観察力と勘次第。とはいえ、仕掛けが露骨じゃないのがうまいところだ。
1971年に発表された作品でありながら、トリックの精度は今読んでもまったく古びていない。むしろDNA鑑定なんてものがなかった時代だからこそ、双子という設定がリアルに効いてくる。テクノロジーに頼らない分、頭脳勝負としての純度が高い。
初期の西村京太郎は、トラベルミステリとはまた違う顔を持っている。これもそのひとつ。定番をきっちり押さえながら、ちゃんと裏をかく。
そんなよくできたミステリを味わいたいなら、外せない選択肢だ。
23.進むか、死ぬか── 貴志祐介『クリムゾンの迷宮』
主人公である藤木芳彦は、一切の記憶を失った状態で、深紅色の奇岩が連なる異様な風景の中で目を覚ます。
傍らに置かれていた携帯用ゲーム機には、「火星の迷宮へようこそ。ゲームは開始された」というメッセージが表示されていた。やがて彼は、同様にこの地に集められた他の参加者たちと合流する。
しかし、そこは生死を賭けた過酷なサバイバルゲームの舞台であったことが判明。誰が敵で誰が味方かも判然としない極限状況下、次々と襲い来る恐怖と対峙しながら、藤木は謎に満ちた迷宮からの脱出を目指す。
これはSF、ホラー、ミステリ、そしてサスペンスの要素を融合させた物語。
読み出したら止まらない、圧倒的な没入感とサバイバル描写
見知らぬ荒野で目覚め、記憶が曖昧なままにゲーム機を手にしている。そんな導入から、すでにイヤな予感しかしない。だがそこから先が、貴志祐介らしい残酷なスリルと緻密な構成のオンパレードだ。
この作品の最大のポイントは、まさにゲームブック式の物語進行にある。プレイヤー=主人公は、携帯ゲーム機の指令に従って進むしかない。選ぶルート次第で遭遇するものも、生死の結末もガラリと変わる。このギミックが面白いだけじゃなく、本気で恐ろしい。
フィールドは深紅の奇岩が連なる異様な景観。正体不明の生物、正体不明の他プレイヤーたち、正体不明のルール。そしてなにより、なぜ自分がここにいるのかすら曖昧なまま、物語は進んでいく。
何もかもが不確かで、誰も信用できない状況。その中で次第にむき出しになっていくのは、人間の本性そのものだ。信頼と裏切り、恐怖と狂気、そして生き残るための合理性がにじみ出してくる。
「人間がいちばん怖い」というジャンルの中でも、この作品はかなりドライだ。怯え、迷い、必死に考え抜く主人公の視点だけで展開する構成だからこそ、感情の揺れがリアルに迫ってくる。
1999年発表ということを忘れるほど、サバイバル描写の密度とテンポがしっかりしている。物語はけっして現実離れしすぎず、むしろ「こういう状況ならありえるかも」と思わせる説得力があるのが怖い。
デスゲームものの元祖とも言われることが多いが、単なる血なまぐさい展開ではなく、人間観察の切れ味が鋭いのが貴志祐介の真骨頂だ。心理的なトラウマスリラーとしても楽しめるし、行動経済学的な思考実験としても面白い。
頭を使うエンタメが好きな人には、これ以上ないほど手ごわくてゾクゾクする物語。
何を信じ、どう動くか。
読んでいるこっちまで試されてるような感覚になる。

24.守るための炎が、すべてを焼き尽くす── 貴志祐介『青の炎』
湘南の海辺の町で暮らす高校生、櫛森秀一は、母と妹との三人での平穏な日々を送っていた。しかしその生活は、10年前に母と離婚した元夫、曾根が突然家に居座り始めたことによって脅かされるようになる。
曾根の傍若無人な振る舞いに家族が苦しむ中、警察や法律といった公的な手段では解決できないと悟った秀一は、自らの手で大切な家族を守ることを決意する。彼は曾根を殺害するという冷徹な意志を固め、完全犯罪の計画を緻密に練り始めるが…。
犯人である秀一の視点から描かれ、計画の立案、実行、そしてその後に訪れる苦悩と計画の破綻が克明に綴られる倒叙ミステリーの傑作。
犯人視点で描かれる完全犯罪の顛末
この物語は、17歳の高校生が殺人を犯すところから始まる。
なぜそんなことを?
その問いに対する答えが、物語全体を貫いている。
主人公・秀一は、家庭という小さな世界を守ろうとして、取り返しのつかない行動を選ぶ。やっていることは完全にアウトなのに、気がつけば感情が彼に寄り添ってしまうのは、彼の中に「守りたい」という一途さが宿っているからだろう。
構成は倒叙ミステリ。犯行の理由から手口、その後の揺らぎまで、すべて秀一の視点で描かれていく。いわゆる「誰が犯人か?」ではなく、「なぜ?」「どう向き合うのか?」を描く話だ。
秀一は周到に準備し、冷静に見えるが、その計画には高校生なりの幼さやほころびが見える。その不完全さが、逆に彼の人間らしさを際立たせる。
日常の描写も秀逸だ。友人との会話、ふとした笑い、淡い恋心。事件の陰にあるこうした場面が、彼の選択の重さと、切なさを倍増させてくる。何気ない一言でさえ、胸を突いてくる瞬間がある。
さらに注目したいのは、作中に散りばめられた文学の引用だ。『山月記』『こころ』『罪と罰』。罪を犯した者の内面を描いてきた古典たちが、秀一の心理と響き合うように語られていく。引用の使い方が説教臭くなくて、自然に物語に溶け込んでいるのも印象的だ。
未成年、家庭内の問題、見えない暴力、法と正義のずれ。現代の抱える歪みが静かに浮き彫りになっていく。だがこの物語は、裁きの物語ではない。悔い、迷い、それでも選ぶしかなかった少年の姿が、まっすぐ描かれている。
ミステリでありながら、倫理小説でもある。正しさと過ちの境界が曖昧になった今だからこそ、心に刺さるのだ。
派手な謎やトリックではなく、「人を殺すとは、どういうことか?」というテーマそのものが重くのしかかってくる。
その答えは簡単に出ない。
でもこの物語は、読む者の心に火を灯す。
それは、消えそうで消えない、「正しさ」という名の炎だ。

25.現実は、すでに侵食されている── 岡嶋二人『クラインの壺』
ゲームブック作家を志望する大学生、上杉彰彦は、自身の作品が高額で買い取られたことをきっかけに、イプシロン・プロジェクトと名乗る謎めいた企業が進める最新鋭のヴァーチャルリアリティ・システム「クライン2」の開発に協力することになる。
K2は、視覚、聴覚のみならず、触覚、嗅覚、味覚といった五感全てを刺激し、現実とほとんど区別のつかない仮想空間を体験させる画期的なマシンであった。上杉は、テストプレイヤーとして美少女・高石梨紗と共に仮想空間での冒険やシミュレーションを繰り返す。
しかし、その没入体験を重ねるうちに、彼は次第に今自分がいる世界が現実なのか、それともK2が生み出した仮想空間なのか、その判別がつかなくなっていく。現実と虚構の境界が崩壊していく恐怖を描いた、SFサスペンスの傑作。
時代を先駆けたVR世界の恐怖
これが1989年の作品? と驚くしかない。いま話題のVRや没入型システムを、すでにここまで描いていたとは。
舞台は五感に干渉する仮想現実の世界。主人公はその「中」に入り、そこで起こる不可解な出来事に巻き込まれていく。
ただの未来ガジェット小説かと思いきや、すぐに足元が揺らぎはじめる。「これは現実なのか?」「今、自分はどこにいるのか?」。そんな感覚が侵食してくる構造だ。
本作が凄いのは、SFとしての仕掛けにとどまらず、哲学やミステリの領域にも深く踏み込んでいるところだ。現実と虚構の境界はどこにあるのか。自己というものは、知覚だけで成立するのか。そんな根源的なテーマが、物語の奥にしっかりと潜んでいる。
とはいえ、頭でっかちな作品じゃない。ミステリとしてもきっちり成立している。不可解な仕様、仮想空間での妙な現象、謎めいた企業の存在。すべてがピースとしてばらまかれ、少しずつ繋がっていく過程はかなりスリリングだ。
そして、なんといってもタイトルの「クラインの壺」。内と外の区別が消えるあの構造体こそ、この作品全体のメタファー。視覚や触覚、理性、直感、あらゆる感覚が反転していくような感覚に襲われる。
ラストまで進むと、もう何を信じていいのかわからなくなる。でも、それこそがこの作品の狙いなのだ。考えている「自分」すら、誰かのプログラムかもしれないという恐怖。それはSFというより、もはや思考実験に近い。
ただし、難解ぶっているわけじゃない。サスペンスもあるし、不気味な空気もあるし、感覚的に引き込まれていく。まさに、思考と体感が同時に揺さぶられるタイプの物語だ。
昔の作品とは思えないほど先鋭的で、VR時代の今だからこそ、あらためて突き刺さる。
「現実とは何か」を考え直す準備ができているなら、迷わず飛び込んでみてほしい。
26.密室にあるのは、記憶と嘘だけ── 岡嶋二人『そして扉が閉ざされた』
裕福な家庭の一人娘であった伏見咲子が、所有する別荘で不審な事故死を遂げてから三ヵ月が経過した。
生前、彼女の遊び仲間であった男女四人(大学生の雄一、女子大生の鮎美、その幼馴染の正志、そして女子大生の千鶴)は、咲子の母親の手によって、地下に設置された核シェルター内に閉じ込められてしまう。
シェルター内には、「娘を殺した犯人は、あなたたちの中にいる」という趣旨のメモが残されていた。
外部との連絡手段を完全に絶たれた極限状況の中 、四人はシェルターからの脱出を試みると同時に、咲子の死の真相を巡って互いを疑い、過去の記憶を辿りながら必死に推理を重ねていくが……。
閉鎖空間での濃密な会話劇と心理描写
登場人物4人が閉じ込められているのは、わずか10畳ほどの核シェルター。そこから一歩も出られないまま、物語は延々と会話だけで進んでいく。
展開は驚くほど地味だ。ドンパチも派手なトリックも出てこない。なのにめちゃくちゃ緊張感がある。
なぜか。ひとことで言えば、「誰も信用できない」からだ。
登場人物たちは、かつての仲間・咲子の死について、互いに「なぜあんなことになったのか」を探り合っている。頼れるのは、4人それぞれの証言と記憶だけ。でも当然、全員が自分に都合のいいことしか言わない。あるいは、本当に忘れてるふりをしてるのかもしれない。だから、話を聞けば聞くほど疑いが深まっていく。
こうなると、もう読む側も「こいつ絶対なんか隠してるだろ」と疑いの目で全員を見てしまう。そして、些細な言葉のズレや矛盾がヒントになる。これはもう完全に安楽椅子探偵スタイルだ。殺人現場にも行かないし、凶器も出てこない。あるのは記憶と証言だけ。逆にそれがめちゃくちゃスリリングだ。
そして、すごいのが構成力である。ひとつひとつの証言が、あとになって意味を持ってくる。ある台詞が、あとで「あれ?さっきと食い違ってない?」となる瞬間の気持ちよさと言ったらもう!
物語の視点もどんどん揺らぎ、犯人の候補も何度も変わる。どこまでが真実で、どこからが嘘なのか、それを見抜けるかどうかは完全に読み方次第だ。
ラストで明かされるのは、明確な悪意や冷酷な殺意ではない。もっとずっと曖昧で、誰にでも起こりうるような「過ち」の連鎖。そこがまたリアルで苦い。そして効く。罪というのは、はっきりしないからこそ、あとを引くのだ。
結末はたしかに出る。でも、スッキリした解決じゃない。むしろ、もやもやが残る。
その余韻が、この作品のいちばんの毒かもしれない。
27.カードに刻まれた死の論理── 鮎川哲也『リラ荘殺人事件』
とある芸術大学の学生寮「リラ荘」には、それぞれに個性的な背景を持つ男女7人の学生が集っていた。
彼らの間には複雑な愛憎関係が渦巻いていたが、ある日、リラ荘近くの崖下で、学生の一人と思われる遺体が発見される。遺体の傍らにはスペードのエースのトランプカードが残されており、これを皮切りに、トランプのカードになぞらえた連続殺人が発生する。
警察による捜査が続けられる中でも犠牲者は次々と増え、残された学生たちは姿の見えない犯人の影に怯えることになる。複雑に絡み合った謎と鉄壁のアリバイに挑む、本格ミステリーの古典的名作。
これぞ本格! ロジックの積み重ねに見立て殺人と多重解決
トリックでドーン! 意外性でビックリ! ……ではない。
むしろこれは、しぶとく、ねちっこく、論理を積み重ねていくタイプの本格ミステリだ。
派手さはない。でも、アリバイ崩し、ダイイングメッセージの解釈、証言の矛盾を拾い上げる地道な作業──そういうのが好きなら、がっつりハマる構造になっている。
物語の軸にあるのは、トランプを使った見立て殺人。犯人がカードを残す理由は何なのか。なぜこの順番で殺すのか。
そういった「意味の解読」が全体に不気味な雰囲気を加えていて、設定としてもギミックとしてもよくできている。クラシックな香りをまといながら、ちゃんと現代的な感覚にも引っかかる絶妙なラインだ。
捜査はやや難航気味で、警察も完璧とは言いがたい。だが、それが逆にいい。警察が頼りないからこそ、物語としての「推理の出番」が生きてくるわけで、これはもはやお約束として楽しむポイントだと思っている。
面白いのは、犯人の計画が最初から最後まで完璧というわけじゃないことだ。ミスもするし、誤算もある。そのせいで事件は複雑化し、ただの連続殺人では済まない展開に転がっていく。トリックそのものよりも、トリックが壊れかけたときのゆがみの描き方が絶妙で、そこに妙なリアルさすら感じてしまう。
伏線の張り方と回収も丁寧で、ラストに向けてピースがはまっていく感覚は、まさにロジック派向けの快感だ。手がかりはしっかり提示されているし、筋道さえ立てば誰だって真相にたどり着けるというフェアプレイ精神も健在。考える楽しさがちゃんと用意されている。
派手さや衝撃よりも、論理の整合性や構造の美しさを愛するタイプに向けて作られている感じがすごくある。
最近の作品にありがちなメタやひねりとは少し違うが、王道の推理する楽しさってやつがしっかり残っているのがうれしい。
古風だけど古くさくない。クラシカルだけど地味じゃない。
案外ありそうでなかなか見かけない、最高峰のミステリだ。
28.読まされる快感、騙される悦び── 折原一『倒錯のロンド』
自身が執筆し、推理小説の新人賞に応募した作品が、何者かによって盗作されたと主張する青年、山本安雄。彼はその盗作者に対する復讐を企てるが、その過程で事態は複雑に絡み合い、二転三転していく。
現実と創作の世界、そして原作者と盗作者という立場すらも曖昧になり、境界線は崩壊。一体、誰が本当の作者で、誰が誰の作品を盗んだのか。物語は作中作という入れ子構造を巧みに利用し、読者を混乱と眩暈の渦へと誘う。
叙述トリックの名手として知られる折原一の初期代表作であり、その複雑怪奇な構成が特徴的な異色ミステリー。
二転三転する予測不能な展開
折原一といえば叙述トリック、というイメージを裏切らない傑作である。
むしろ期待以上。語り手は誰なのか、語られている事実は本当なのか、そのすべてが信用できない。真相を追っていたはずが、いつのまにか物語に読まされている──そんな倒錯した感覚が、ゆっくり効いてくる構成だ。
最大の仕掛けは、入れ子構造にある。物語の中に別の物語が組み込まれていて、そこに「盗作」というテーマが絡んでくる。
これがただのネタではなくて、誰が語り手か、何がオリジナルかという視点を揺さぶる問いにまで繋がっていくあたりが素晴らしい。それに構成そのものが「物語とは誰のものか」というメタな議論を呼び込む仕掛けになってるのも面白い。
当然ながら、ひっくり返しも容赦ない。最初に「Aだな」と思っていたことが、少し進むと「いやBかも」となり、最後には「やっぱりCだった」と全部持っていかれる。この連続の快感こそ、折原作品の醍醐味だ。
視点がどんどん切り替わることで情報の精度が崩れていき、立場すら反転していく展開には、追っていても地に足がつかない感覚がある。信用できない語り、意図的に混乱させてくる構成、どこか演劇的なセリフ回し。すべてが「お前は騙されるぞ」と語りかけてくるようで、それが心地いいのだ。
ただし、登場人物にはあまり共感はできない。どいつもこいつも自己中心的で、自意識の迷路にどっぷり浸かっている。それも含めて、物語全体が倒錯そのもの。善悪や正しさなんてとっくに溶けていて、残っているのは歪んだ欲望とねじれた自我の応酬だ。
結末までたどり着いても、「全部理解できた」とは言いきれない。だからこそ再読したくなる。違和感の正体がわかったときに、もう一段深く潜れるような構造になってるのもいい。
ミステリとしてだけではなく、物語という装置そのものに仕掛けられた罠を味わいたいなら、こういうタイプは外せない。折原一は、やっぱり凄いのだ。
29.理性が怪異を斬る── 京極夏彦『魍魎の匣』
舞台は戦後の東京。ある美少女が中央線のホームから転落する事件が発生する。
時を同じくして、武蔵野では手足が切断された少女の遺体が次々と箱に詰められて発見される連続バラバラ殺人事件が世間を騒がせていた。さらに、人々の信仰を集める謎の宗教団体や、人里離れた山中に現れた巨大な箱型の研究所の存在も明らかになる。
一見すると無関係に見えるこれらの奇怪な事件を、作家の関口巽、元刑事で今は探偵の榎木津礼二郎、そして現職刑事の木場修太郎らが、それぞれの立場と視点から追っていく。やがて彼らは、博識な古書肆「京極堂」の店主であり陰陽師でもある中禅寺秋彦のもとに集う。
そこで事件の背後に潜む「魍魎」の正体と、複雑に絡み合った人々の因縁が徐々に解き明かされていく。膨大な知識と緻密な論理によって憑き物(=謎)を落とす、人気「百鬼夜行シリーズ」の第二弾。
圧倒的知識量と「憑き物落とし」のカタルシス
とんでもなく濃くて、重くて、複雑。でも、それでも読む手が止まらない。
それが『魍魎の匣』という化け物みたいな物語だ。
何がすごいって、まず京極堂の語りだ。陰陽師・中禅寺秋彦が、民俗学、心理学、宗教学、あらゆる知を駆使して怪異をロジカルに斬っていくスタイルは、まさに「知の怪物」。オカルトで説明できそうな事件を、あくまで理詰めで分解していくこの「憑き物落とし」の快感は、他では味わえない。
しかもこの語りは、ただの知識披露じゃない。散りばめられた情報やキーワードが、終盤になるととんでもない形で繋がってくる。最初はバラバラに見えていた断片が、ひとつの巨大な構造物として姿を現したときの衝撃……これは他に類を見ないレベルだ。
事件そのものも強烈である。バラバラ殺人、少女誘拐、謎の宗教団体、そして「匣」。この匣がまた象徴的で、ただの箱じゃなく、人の閉じた精神や狂気を内包するメタファーとして効いてくる。ミステリという枠を飛び越えて、人の心の闇を抉るような視点が全編に張りついてるのだ。
時代は戦後間もない日本。まだ戦争の傷が生々しい空気の中に、土着の妖怪や呪いの概念が混ざってくる。科学と非科学、近代と因習。そのせめぎ合いがこの作品の底流にあって、それがまた不穏で魅力的なのだ。
そして忘れではいけないのが、キャラクター陣の強さだ。京極堂の知性に、関口のぐるぐる思考、榎木津の霊能力(?)、木場の人情。全員クセがすごいのに、なぜか絶妙なバランスで物語を支えている。このメンバーが揃ってこそ、京極堂シリーズは完成する。
1000ページ超えの長編なのに、読み始めたらむしろ物足りなく感じるくらい、熱量がとんでもない。
ミステリ、怪奇、文学、あらゆるジャンルをごった煮にしながらも、すべてを知で制圧していく。そんな唯一無二の体験が待っている。

30.人形は犠牲か、それとも鍵か── 高木彬光『人形はなぜ殺される』
日本アマチュア魔術協会の新作魔術発表会の楽屋裏で、演目『断頭台の女王』に使用される予定だった人形の首が、厳重に鍵がかけられた箱の中から忽然と消失するという不可解な事件が発生。その数日後、その魔術に出演するはずだった女性が首のない死体となって発見される。
切断された彼女の首は現場から持ち去られており、代わりにそこには先日盗まれたはずの人形の首が残されていた。さらにしばらくして、今度は人形が列車に轢かれるという出来事があり、その直後、付近の線路で同様の轢断死体が発見される。
殺人を実行する前に、なぜ犯人は人形を同じ手口で「殺す」のか。この奇怪な連続見立て殺人事件の謎に、稀代の名探偵・神津恭介が挑む。
「人形はなぜ殺される?」タイトルに秘められた謎
この作品の何が最高かって、「人形が殺される」という奇妙な事件が、単なる演出や猟奇趣味じゃ終わらないところだ。
普通なら「人形=被害者の身代わり」みたいなイメージを持つかもしれないが、ここでは違う。人形を壊すこと自体が、犯人の計画にとって必要不可欠な物理操作になっている。つまり、人形が破壊されることがトリックの一部として組み込まれているのだ。
その意味に気づいた瞬間、すべての伏線がピタッとはまっていく。この構成力と発想の鮮やかさは、まさに本格ミステリの真骨頂である。
しかも、ただのロジックだけじゃなくて雰囲気も抜群。魔術、黒ミサ、首なし死体……昭和ミステリ独特の耽美で怪奇な空気感が全体を包んでいて、雰囲気だけで読むミステリが好きな人にもきっと刺さる。だけどそこに甘んじないで、きっちりアリバイ崩しやトリックで攻めてくるのがいい。
こういう「オカルトっぽい事件に論理で切り込む」タイプの話は、個人的にめちゃくちゃ好物なのだが、この作品はその完成度がずば抜けている。怪奇性と論理性のバランスが本当に絶妙なのだ。
そして、探偵役はおなじみ神津恭介。高木彬光が生んだ完全無欠の名探偵。彼が容赦なく論理のメスを入れていく姿はやっぱり痛快だ。論理の切れ味が良すぎて、事件そのものがどんどん解体されていくような快感がある。
ワトソン役の松下研三とのコンビネーションも健在で、重苦しい事件の中にちょっとした軽やかさを添えてくれるのも嬉しいポイントだ。
昭和の時代に書かれたとは思えないほど、トリックは今読んでも新鮮だし、構成もよく練られている。
古典ミステリの名作を掘り起こしたいなら、これは間違いなく読んで損はない一本だ。
31.操られているのは誰だ?── 赤川次郎『マリオネットの罠』
フランス留学から帰国した青年、上田修一。彼は恩師の紹介で、月収百万円という破格の報酬を提示され、長野県茅野の山中にある峯岸家の美人姉妹、絵里子と亜矢子のフランス語家庭教師として住み込みで働くことになった。
洋館で暮らす謎めいた姉妹と無口な使用人たち。修一はどこか不穏な空気を感じながらも、美しい姉妹と高報酬に惹かれて仕事を受け入れる。
ある夜、館の地下に隠された牢獄を発見し、そこに幽閉されていた三女・雅子と出会う。彼女は「ガラスの人形」と呼ばれる繊細な少女で、家族からの虐待を訴える。
修一が彼女を助けようと動き出した矢先、当主が殺され、やがて連続殺人へと発展。峯岸家に渦巻く秘密と欲望の中、修一は逃れられぬ謎に巻き込まれていく。
赤川次郎初期作品ならではの巧妙な伏線と罠
赤川次郎のデビュー長編。テンポのいい語り口、スリリングな展開、そしてラストの鮮やかな反転。すでにこの時点で赤川ワールドが確立されているのがすごい。
物語は、フランス帰りの若者が、奇妙な洋館で家庭教師として雇われるところから始まる。屋敷の中には秘密だらけの家族、監禁された少女、地下牢と、どこかゴシックホラーめいた雰囲気が漂っていて、ライトな文体なのに空気は妙に張り詰めている。このアンバランスさがいい。
登場人物はみんな一癖も二癖もあって、誰を信じていいのかわからない。味方だと思っていた人物が実は……という展開の連続で、事件の真相に近づくほど物語の輪郭が不穏にねじれていく。
そして終盤。物語のタイトルでもある「マリオネット」という言葉が、単なる装飾ではなく、事件の核心そのものだったことが明かされるあたりで、背筋にぞわりとくる感覚が走る。
ああ、罠に嵌められたな、と。
どこまでが偶然で、どこからが仕組まれていたのか。思わず最初のページに戻って、細部を確かめたくなる。伏線はさりげなく、でも確実に張られていて、それが物語の終盤で一気に火を噴くのは爽快のひと言だ。
赤川作品というと「三毛猫ホームズ」シリーズのようなユーモラスでポップなイメージが強いかもしれないが、この初期作品はかなりダークでミステリアス。ホラー寄りの空気感と、本格ミステリ的な構造を高い次元で両立させていて、まさに原点にして異色作とも言える。
いま読んでもまったく古びていない。
軽快に読めるのに中身はずっしり詰まっている。
そんな赤川ミステリーの出発点として、かなり濃い味の一作だ。
32.祟りが歩き、理性が斬る── 三津田信三『首無の如き祟るもの』
奥多摩の山奥にある閉鎖的な媛首村(ひめくびむら)。旧家・秘守(ひがみ)一族が支配するこの地には、首無しの姫「淡首様(あおくびさま)」の祟りをはじめ、首にまつわる不気味な伝承が色濃く残る。
戦時中、一族の双子の妹・織江が屋敷の井戸で不可解な死を遂げ、十年後には双子の兄・長寿郎とその嫁候補たちが首のない姿で次々と殺されるという怪事件が発生する。これらの顛末は、村の元巡査の妻・篤子が記した手記という「作中作」の形で語られる。
そして現代。怪奇作家にして探偵の刀城言耶が、その記録を元に迷宮入りした事件の真相に挑む。首のない死体が歩いたという証言まで飛び出し、ホラーとミステリが交錯する中、やがて隠されていた過去が浮かび上がっていく。
恐怖と謎解きが融合した、ホラーミステリーの超傑作
三津田信三『首無の如き祟るもの』は、横溝正史が好きな人なら、まず間違いなくドハマりするタイプのミステリだ。
舞台は、奥多摩の山奥にある閉ざされた村。旧家の跡目争いがくすぶっていて、地名からしてすでに不穏。そこに「淡首様」という首の祟り神がいて、しかも本当に人が首を失って死んでいくんだからたまらない。三体連続で首が消えるなんて、もうホラーとしか言いようがない。
しかし、ただの怪談では終わらない。そこが三津田作品のすごいところである。
この作品、ホラーと本格ミステリの融合度が異常に高い。たとえば、「首のない者が歩いていた」なんて目撃証言が出てくる。そんな話を出されたら普通はオカルトで終わるが、三津田作品ではそれすらも推理の対象になってくるのだ。
ページをめくるたびに村の空気はどんどん濃くなる。因習、祟り、閉塞感。その中で少しずつ浮かび上がってくるのが、冷徹な論理と緻密な構成だ。怖さと謎解き、どっちも手を抜いてないのが凄まじい。
形式としては「作中作」になっていて、メインの語り手は駐在巡査の妻。つまり、事件の記録が手記という形で残されている。その手記をもとに、シリーズ探偵・刀城言耶が最後に謎を解いてみせるわけだ。
しかし、刀城言耶の出番はほとんどない。冒頭とラストだけ。なのに全部持っていく。あの推理の一撃の破壊力ときたら、まさに暗闇に差し込む光そのものだ。
しかもこの物語、何度も姿を変える。
「なるほどね、そういう話か」と思ったところでひっくり返され、「犯人がわかったかも」と思えばもう一段下に潜らされる。とにかく仕掛けが多層的で、読み終えたあとには「ここまでやるか……」と呆然するくらいだ。
最後の最後まで「そう来るか!」の連発。油断なんて一切許さない。
祟りか?
いや違う。しかし、完全に合理だけでもない。
そのあいだを縫うようにして真相が立ち上がるのが、この作品の最大の怖い部分である。
33.孤島に咲くは、血と俳句の三重奏── 横溝正史『獄門島』
物語は、名探偵・金田一耕助が、復員船の中で息を引き取った戦友、鬼頭千万太(きとうちまた)から託された不吉な遺言を胸に、瀬戸内海に浮かぶ孤島・獄門島へと渡る場面から幕を開ける。
千万太は「三人の妹たちが殺される……おれの代わりに獄門島へ行ってくれ……」という言葉を残したのだ。
かつて流刑地であり海賊の拠点でもあったこの島は、閉鎖的で陰鬱な空気に包まれていた。金田一は、千万太の家族──父の与三松、三人の美しい妹たち、そして従姉妹の早苗と出会う。
やがて、千万太の予言どおり、妹たちが芭蕉の俳句に見立てた方法で次々と命を落としていく。金田一は、因習深い旧家と島の人間模様、戦争の影が交錯する中、連続見立て殺人の謎に挑む。
俳句に見立てた連続殺人という芸術性と猟奇性
横溝正史の代表作は何か?と聞かれて、まず頭に浮かぶのがこれだ。
『獄門島』。タイトルからして不穏すぎるが、中身はもっと恐ろしい。
瀬戸内の孤島。戦後の混乱期。かつては流刑地。もれなく村人は排他的で因習にまみれている。どこを切っても陰湿な空気が漂ってるのに、なぜかページをめくる手は止まらない。もう、この雰囲気がたまらないのだ。
舞台となる鬼頭家には、まさにいわく付きってやつが山ほどある。金田一耕助は戦友の遺言を受けてこの島にやってくるが、早々に首のない死体が出てくる。しかも三人連続という異常な流れ。
しかも、それぞれの殺され方が俳句の一節に沿っている。髪を切られた娘、首を落とされた娘、火に焼かれる娘。やりすぎじゃない?と思いつつ、ここに「見立て殺人」という横溝的美学がしっかり詰まっているのが最高だ。美しいけど、えげつない。でもそれが横溝ミステリの醍醐味である。
殺し方だけじゃない。誰が誰を疑ってるのか、誰が何を隠してるのか、島の誰もが不気味で信用できない。その中を金田一がぽつぽつと歩いて、ぽそっと核心に近づいていく。この探偵、ほんとに胡散臭い見た目してるくせに、推理はキレッキレだ。
終盤の種明かしは「やられた!」というより「そこまでやるのか!?」という感じだ。まさかあの句が、そう繋がってたとは……。もはや事件じゃなくて呪いじゃん、と思わせるほどの仕掛け。それをバッサリと論理で切り裂いていく金田一耕助がかっこいいのだ、これが。
しかも本作、ただのミステリじゃない。金田一がどこか哀しげなのも効いているし、戦後の時代背景とか、鬼頭家の病んだ家系とか、ミステリを超えて人間ドラマとしても読ませてくる。ページ全体に湿度があるというか、気持ちのいい作品じゃない。でも、忘れられない。
いわゆる金田一モノの中でも、陰鬱さ、見立て、連続殺人、旧家、祟り、孤島と、横溝フルコースで詰め込まれているのが『獄門島』だ。
これが好きなら、他の作品も確実にハマる。逆にこれがダメなら、横溝沼は深すぎるかもしれない。
でも、ミステリの原点にある「不可能に見える謎を論理で解く」という快感。それをホラーや民俗的モチーフと掛け合わせて、ここまで美しく仕上げた作品はそうそうない。
『獄門島』にはまさに、横溝ミステリの魅力が全部詰まっている。

34.踏み外せば、奈落── 高野和明『13階段』
物語は、ある夫婦が自宅で惨殺され、金品が奪われる強盗殺人事件から始まる。現場近くで事故を起こし、記憶を失っていた青年・樹原亮が状況証拠で逮捕され、死刑が確定する。
数年後、執行まで残り三ヶ月となった樹原の無実を信じ、弁護士事務所は元刑務官の南郷正二に調査を依頼。南郷は、過去に傷害致死で服役し仮釈放中の青年・三上純一を協力者として選ぶ。三上は罪の償いと報酬のためにこの任務を引き受ける。
手がかりは、樹原が事故後にかすかに思い出した「階段」のイメージただひとつ。限られた時間の中、南郷と三上は記憶の空白をたどり、10年前の事件の真相に迫っていく。
死刑制度の重圧と冤罪の恐怖
死刑囚が記憶喪失、と聞いただけで「面白そう!」と思った人は正解だ。
『13階段』は、江戸川乱歩賞を受賞した社会派ミステリで、ただのサスペンスじゃない。真正面から「死刑制度とは何か」というテーマに挑んだ、かなり骨太な一冊である。
舞台になるのは、死刑執行が迫った男・樹原の冤罪疑惑。問題は、本人が何も覚えていないこと。もう、ほんとに何も。そんな彼を救うべく立ち上がるのが、元刑務官の南郷と、殺人歴のある仮釈放中の青年・三上。このバディがめちゃくちゃいい。
まず、南郷が抱えているのは「死刑を執行した側」としての過去。いまだにその罪悪感を引きずっている。一方の三上は、かつて人を殺したことの贖罪を抱えながら、今度は冤罪の可能性と向き合わされることになる。この二人の関係と成長がすごく熱い。
タイトルの『13階段』というのも、ただの比喩じゃない。これは実際に、死刑執行室へと続く13段の階段のことだ。でもそれだけじゃなくて、登場人物たちが精神的に死に向かって踏みしめていくプロセスそのものでもある。読んでるこっちも息が詰まるような緊張感に巻き込まれていく。
手がかりは、死刑囚の口からかすかに漏れた「階段」という言葉。それだけを頼りに、南郷と三上は当時の事件を再調査する。でも当然、そんなのスムーズにいくわけがない。記憶、証言、立場、すべてが曖昧で、しかも時間はない。タイムリミットが迫る中で、真相に近づく展開はスリル満点だ。
しかも、この作品の魅力はサスペンスのキレだけじゃない。一人ひとりのキャラクターが、それぞれの「罪」と真っ向から向き合っていく。そこがすごくいい。
罪を犯した者は、どう贖えばいいのか。冤罪で死刑になろうとしている男に、本当に救いはあるのか。正義と感情、制度と現実のあいだでぐらぐら揺れる構図が、ずっと頭に残り続ける。
最終的に、三上と南郷が出す答えがどんなものなのかは、ぜひ自分で確かめてほしい。
階段の先に待つのは、絶望か、赦しか。
それでも彼らは、のぼるしかなかったのだ。
35.広まるほど、死は近づく── 荻原浩『噂』
都内の公園で、足首を切断された女子高生の死体が発見される。額には「R」の文字。猟奇的な事件を追うのは、所轄のベテラン刑事・小暮と、警視庁から派遣された若き女性警部補・名島の凸凹バディ。
捜査の中で、この事件が「レインマン」という都市伝説に酷似していることが判明する。雨の日に現れ、少女を攫って足首を切り落とすという恐怖の存在。女子高生たちの間で広まり、誰もがその名を知るが、実在は不明だ。
やがて小暮と名島は、この噂が香水「ミリエル」の販売戦略の一環として仕掛けられたものと酷似していることに気づく。「ミリエルをつければレインマンに狙われない」。そんな不気味な護符としての香水が、少女たちに広まっていたのだ。
噂が事件を生んだのか、事件が噂に便乗したのか。見えづらい女子高生のネットワークと現実の殺人事件が交錯し、捜査は混迷を深めていく。
巧みな伏線と、ラスト一行の衝撃
香水のPRに使われたはずの〈レインマン〉という都市伝説が、気づけば現実の連続猟奇殺人へと姿を変える。この導入だけで、すでに背筋がざわつく。
「女の子を攫って足首を切り落とす」。そんな陰惨な噂が、どうして現実になってしまったのか? そこにネットの即時性、噂の拡散性、そして広告と犯罪の境界がぼやけた今の社会が重なると、作り話で終わるはずのものが、ひどくリアルな狂気に見えてくる。
主人公は、妻を亡くした中年刑事・小暮と、上司でありシングルマザーでもある女性警部補・名島。家族を失った者同士が、事件と向き合いながら、親として、捜査官として、少しずつ言葉を交わしていく。そこに血まみれの事件の合間にも、しっかりと人間の手触りが残っているのがいい。
ミステリとしての作りも緻密で、伏線は丁寧に、でも目立たぬように置かれている。誰がレインマンなのか、どこからが嘘でどこまでが仕掛けなのか。読者も刑事と同じように、暗闇の中で手探りすることになる。
そして、名物とも言われている「ラスト一行の衝撃」。これはもう、騙されたとかそういうレベルじゃない。物語そのものの色が変わってしまうのだ。知ってしまった瞬間、無性にもう一度最初から読み返したくなる。
だからこそ、あまり事前情報は仕入れないほうがいい。
「レインマンって何?」くらいの気持ちでページをめくって、あとはすべて作者に委ねるのが正解だ。
伏線の気配、語られなかった事実、そして最後の衝撃。全部まとめて、体験してほしい。
香りがきっかけだった事件のはずなのに、残るのは恐ろしく鋭い後味だ。
36.花火の下で、私は冷たい── 乙一『夏と花火と私の死体』
ある夏の日、九歳の少女・五月(さつき)は、いつものように遊んでいた親友・弥生(やよい)に、森の木の上から不意に突き落とされ、あっけなく命を落とす。物語は、死んだ少女自身の視点で綴られるという異色の形式で進行する。
五月の意識は、動かぬ自らの体に宿ったまま、弥生とその兄・健(けん)が、自分たちの犯行を隠そうと奔走する姿を静かに見つめ続ける。兄妹は死体を抱えて森をさまよい、隠し場所を変えながら、終わらぬ悪夢のような数日間を過ごす。
夏祭りの夜、花火の音が響くなか、彼らの「隠蔽ごっこ」は次第に破綻し、思わぬ事態へと転がり始めるのであった。
死体が語り手となる、かつてない斬新な設定
乙一デビュー作にして、いまだに語り草になっているこの短編。最大の仕掛けは、何と言っても「語り手が死体」という大胆な構成にある。
殺された九歳の少女・五月の視点で物語が進んでいくのだけど、これが実に不気味で新鮮。感情も行動もない死者の視点だからこそ、妙な浮遊感と、子供らしい言葉の中に潜むゾッとするような異質さが際立ってくる。
中心にあるのは、幼い兄妹による殺人と死体遺棄という重すぎるテーマだ。でもそれが冒険のように描かれているのが、本作の一番怖いところである。健気に、しかしちょっとズレた方向にがんばる兄妹の姿は、純真と残酷の境界線を何度も越えていく。子供の無邪気さとは、時に何よりも冷たい。
特に兄の健。年齢にそぐわない冷静さと計算高さで妹をリードしていくその姿には、サイコパスっぽさすら感じる場面もある。ただ怖いだけじゃなく、ふとした瞬間に兄妹の関係にじんときたりもして、この振り幅が読んでてものすごく気持ち悪い……いや、気持ちいい。
そして、乙一といえばやっぱりオチだ。
この作品も例に漏れず、最後の最後で冷たい刃物を突きつけられるような感覚に陥る。ずっと騙されていた、と気づかされるあの感じ。短編なのに、この余韻の残り方はえげつない。
子供の目線で描かれる世界は、ときに大人の目よりも鋭い。倫理や正義よりも、もっと原始的な感情と反応で動いていく子供たちの姿には、人の根っこみたいなものがちらちら見え隠れしている。
乙一の原点にして、ブラックで静かな傑作。死体の視点という一発ネタに見える構成が、実はずっと生の物語になっているのが、本当に恐ろしい。
37.チェス盤の上で、命が消える── 北山猛邦『アリス・ミラー城 殺人事件』
物語の舞台は、まるで『鏡の国のアリス』が具現化したかのような奇怪な城「アリス・ミラー城」。そこは現実と幻想の境界が曖昧な、巨大なチェス盤を模した異空間だった。
ある日、この城に十人の男女が集められる。彼らはいずれも探偵の肩書を持つ者たち。招待主を名乗る謎の女ルディは、「最後に生き残った者だけがアリス・ミラーを手に入れられる」と告げる。
チェスの駒のように、探偵たちは次々と命を落としていく。誰が仕掛け、なぜ殺すのか。完璧に孤立したクローズドサークルの中、疑心と狂気が城を満たし、ゲームの真のルールが少しずつ明らかになっていく。
すべてが信じられなくなる極限の恐怖と疑心暗鬼の中、探偵たちは生き残りをかけて、この狂気のゲームの謎に挑むのであった。
『鏡の国のアリス』と『そして誰もいなくなった』の奇想天外な融合
北山猛邦といえば、ロジックと幻想が絶妙に絡み合う「物理&特殊設定ミステリ」の使い手だが、その魅力がこれでもかと詰め込まれているのが、この『アリス・ミラー城殺人事件』だ。
物語の舞台は、鏡の国のアリスよろしく、どこか夢のようでどこか悪夢めいた「アリス・ミラー城」。閉ざされた城に集められたのは、名だたる探偵たち。しかし彼らは探偵としてではなく、まるでチェスの駒のように、順番通りに消されていく運命にある。
この設定だけで、もうミステリ好きとしてはワクワクが止まらない。アガサ・クリスティ『そして誰もいなくなった』のオマージュでありつつ、チェス盤のように整然と、そして悪意に満ちた構造で人が消えていくさまは、完全に北山ワールドだ。
しかも、消えていくのが探偵たちっていうのがいい。推理こそが生き残る術であり、沈黙が即ち死を意味するこの世界では、誰もが疑心暗鬼に陥る。味方のフリをして背中を刺すかもしれないし、手を取り合うように見せかけて落とし穴へ突き落とすかもしれない。
どこまでがゲームで、どこからが殺意か。探偵たちの頭脳戦と心理戦は、推理という行為そのものの意味を改めて問い直してくる。
そして終盤、すべてが明かされるとき、私たちは思い知ることになる。
これはやられたな、と。
とにかくトリックの鮮やかさと、その裏で作者が張り巡らせたミスディレクションの巧妙さには、唸るしかない。ラストに明かされるアリス・ミラーの正体、その動機、そして構造全体に隠されていた真実は、確実にページをめくる手を止めさせる。
というより、むしろ、最初のページに戻りたくなる。あの一手が、あの伏線が、すべて繋がっていたのだと確かめたくなるはずだ。
論理と幻想が結び合い、鏡のように世界が反転する。
それはまるで、読み終えたあとも、まだ夢の中にいるような感覚だ。
38.すべてのお約束を疑え── 麻耶雄嵩『翼ある闇 メルカトル鮎最後の事件』
京都近郊の山あいに建つ、中世の古城を模した「蒼鴉城」。
その屋敷を訪れた私立探偵・木更津悠也を迎えたのは、首を切断された屋敷の主・今鏡伊都の死体だった。だが、その首は伊都のものではなく、さらに鉄靴の中では足首が忽然と消えていた。
不可解な死、首なし死体、甲冑、密室、見立て、そして蘇った死者。次々と繰り出される怪事件は、まるで城そのものが仕掛けた迷宮のように、論理と幻想の境界を揺るがせていく。
挑むは二人の名探偵。理知の静けさを湛える木更津と、異才の輝きを放つメルカトル鮎。交錯する推理と、火花を散らす対決の果てに、明かされる真相とは。
常識を破壊する奇抜なトリックと壮大なスケール
これはもう、読み終えた瞬間に「なんじゃこりゃ……!」と椅子から転げ落ちるタイプのミステリだ。
麻耶雄嵩のデビュー作にして、ジャンルごと爆破する勢いの問題作。島田荘司や綾辻行人、法月綸太郎といった新本格の大御所たちが大絶賛したというのも納得で、ただのデビュー作じゃない。新本格の枠をぶち抜いて、ミステリという形式そのものに殴りかかってきてる。
首なし死体、密室、見立て殺人、蘇った死者。クラシックなガジェットをこれでもかと詰め込みながら、出てくる展開はとにかく予測不能。お約束に見せかけて、そのすべてを疑えって構造になっている。
名探偵・メルカトル鮎と、もうひとりの探偵・木更津悠也。どちらも探偵だが、やっていることは全然違う。二人がそれぞれ解決をぶつけ合い、まるで解決のバーゲンセールを浴びせられてる気分になる。
でもその「多重解決」こそが、この作品のキモだ。
一体どれが本当の真相なのか? というより、そもそも真相なんて本当にあるのか?
そんなメタな思索を、私たちに考えさせてくる。
木更津が披露するある密室トリックなんか、あまりの突飛さに思わず笑ってしまう。でも、麻耶雄嵩は本気だ。そのバカバカしさを、ある種の美学として本気で押し通してくる。常識も、現実感も、いったん脇に置かされるのだ。
読者がミステリに期待する「筋の通った真実」とか「名探偵の完璧な推理」とか、そういうものがひとつずつ崩れていくのを、見せつけてくる。なのに、最後まで読む手が止まらない。むしろページをめくるほど興奮してくる。こんな作品は激レアだ。
とんでもなく尖ってるし、クセも強い。でもその過激さが、まさに新本格の熱量を体現している。
ミステリの限界を見てみたい、そんな人にこそおすすめしたい。
39.正しさは、いつも残酷だ── 麻耶雄嵩『神様ゲーム』
小学四年生の芳雄が暮らす神降市では、次々と猫が惨殺される不可解な事件が起きていた。ある日、そんな街に、無表情で「自分は神様だ」と語る転校生・鈴木太郎が現れる。
鈴木は、犯人の名を言い当て、さらに「今度は人が死ぬ」と冷たく予言する。そしてその予言は、驚くほど正確に現実となっていく。
不気味な事件の連鎖、加速する恐怖、そして得体の知れない「神様」の力。芳雄は、信じたい気持ちと抗いがたい疑念の狭間で揺れながら、逃れられない運命に巻き込まれていく。
衝撃的かつ解釈の多様性を生む、問題提起的な結末
この作品、とにかく設定が反則級に面白い。
ある日突然、クラスにやってきた転校生・鈴木。自己紹介で「ぼくは神様です」と言い切るヤバいやつだ。
しかし、ふざけてるのかと思いきや、鈴木は次々と未来を言い当てる。誰が死ぬか、どこで何が起きるか、すべて的中。しかもその予言が、どんどん物騒な事件に繋がっていくのだから、タダ事じゃない。
主人公は小学生の芳雄。彼の視点で、「神様」との奇妙な付き合いと、それに翻弄される日常が描かれていく。最初は猫殺し。そこから連続殺人へ。
神様を信じるか否か。予言に従うか、抗うか。子供だからこそ持ち得る残酷さと純粋さが、物語にすさまじい緊張感を与えてくる。
しかもこれは、ただのジュブナイルじゃない。麻耶雄嵩らしく、仕掛けもロジックも超緻密。言葉と予言の構造そのものが謎解きのカギになっていて、読みながらずっと試されてる感じがある。
鈴木は本当に「神様」なのか? 予言は偶然か、それとも必然か?
ずっとその謎を抱えながら読み進めることになるのだが、終盤の展開がまた凄い。真相が明かされたと思った瞬間、地面がスッと抜ける。解決したはずの事件が、逆に新たな不安を呼び起こす。
そういう意味じゃ、ゲームをしてるのは神様ではなくて、作者の麻耶雄嵩かもしれない。
とにかく読後感がすごい。謎は解かれたようでいて、なにもかも解決していない。「神様の天誅」の意味も、真相の輪郭も、読む人によってまるで違う解釈になるはずだ。
これは、単なるミステリじゃない。
子供の視点と神の視点が交差したとき、人間の理屈がふっと宙に浮かぶような感覚を味わえる。そんな、唯一無二の怪作だ。
納得しかけた瞬間に、さらに深く不可解な謎を突き付けられる。
その読後感こそが、麻耶雄嵩作品の真骨頂だ。
40.童話は血に染まり、推理は薔薇に散る── 城平京『名探偵に薔薇を』
物語は、マスコミ各社に『メルヘン小人地獄』と題された奇怪な創作童話が送りつけられる場面から始まる。
そこには、ハンナ、ニコラス、フローラという三人が順に残酷な方法で殺される様子が克明に描かれていた。やがて童話をなぞるように、現実でも連続殺人が発生。最初の現場には「ハンナはつるそう」という童話の文言が残されていた。
事件の舞台・藤田家に家庭教師として入り込んでいた青年・三橋荘一郎は、大学時代の後輩で、卓越した推理力を持つ若き名探偵・瀬川みゆきに事件解決を依頼する。
物語はこの「メルヘン小人地獄」事件を扱う第一部と、続く「毒杯パズル」の二部構成で展開。不敵な知能犯に、名探偵・瀬川みゆきが鋭い論理で挑む。
二転三転する予測不能なプロットと鮮やかな伏線回収
ひとことで言えば「一冊で二度おいしい」系の傑作ミステリだ。
ただしそのおいしさは、けっこう苦くてグロい。
前半は、猟奇的な童話『メルヘン小人地獄』になぞらえた見立て殺人事件。子どものおとぎ話が残酷な犯罪の設計図になるという展開は、横溝正史ばりの血の香りが漂っている。被害者の死に様、事件の舞台、どれを取っても不穏でグロテスク。しかし、ただのホラーでは終わらない。
後半は一転して論理重視のガチ推理バトルへ。タイトルにもある「毒杯パズル」が動き出すと、一気に世界が塗り替わっていく。
事件の構図ががらりと変わり、前半でバラまかれた違和感や謎が、ひとつずつ意味を持ち始める。見えていなかった裏の物語が浮かび上がる瞬間に、思わず「そう来たか……」と声が漏れてしまう。
しかも、全体がしっかりパズルとして機能している。どんでん返しは何度も来るし、しかも全部が論理的に筋が通っている。第一部で張られていたあれやこれやが、実は全部伏線でしたって回収されていく流れは、ミステリ読みとしてはニヤつかずにいられない。
では全部解決してスッキリかというと、そうでもないのがまた憎いところだ。この物語は、最後の最後にズシンと落ちてくる。真相の先にあるのは、人の業と、名探偵という存在の孤独と哀しさだ。
全てを暴くという行為の、その先に待っている虚無。
犯人の心も、探偵の心も、誰一人として救われないかもしれない。
しかしその切なさと美しさこそが、城平京作品ならではの味わいであり、読後に深く心に残る理由である。
バッドエンドと呼ぶこともできる。
しかし、そのほろ苦い感情こそが、この物語の完成度をさらに高めているのだ。
41.その独白が真実をひっくり返す── 北村薫『盤上の敵』
我が家に猟銃を持った殺人犯が立てこもり、妻・友貴子が人質となる異常事態が発生。警察とマスコミに包囲され「公然の密室」と化した自宅。
夫である末永純一は、妻を無事救出するため、警察の制止を振り切り、犯人との困難な交渉を開始する。緊迫した状況下で、純一は知略を巡らし、絶望的な状況からの逆転を試みるのである。
人質となった妻の安否、犯人の動機、そして純一の取るべき行動とは。息詰まる心理戦と、先の読めない展開が続く。この盤上で、純一は犯人にチェックメイトをかけることができるのであろうか。
それは単なる人質救出劇ではなく、過去の因縁や人間の悪意が複雑に絡み合う、何重にも仕掛けられた罠との戦いでもあった。
日常に潜む悪意と夫婦の絆
これは、派手な爆破やアクションのあるタイプのミステリじゃない。でも、息をのむ緊張感と、心臓をギュッと握られるような結末が待っている。
舞台は人質立てこもり事件。ありがちに見えるが、仕掛けはむしろ冷酷だ。
物語は、犯人と対峙する夫の視点と、妻・友貴子による過去の独白が交互に語られていく。一見、同時進行しているように読める構成がミソで、これが終盤に効いてくる。
「そういうことだったのか……」と気づいた瞬間の衝撃は、まさにジグソーパズルの最後のピースがカチッとはまる快感に近い。
読者の多くが「騙された」と口にするのも納得しかない。ただしこれは、どんでん返しありきの作品じゃない。構成の妙と伏線の張り方、そしてそれを成立させる人物造形がきっちりしているからこそ、このラストは成立している。
ポイントは、友貴子の独白。ただの回想や背景説明ではなくて、むしろこの物語の心臓とも言える部分だ。彼女の抱える秘密と後悔が、事件と地続きで繋がっていくにつれて、どこか怖さすら感じるようになる。
夫婦の物語でありながら、愛とか信頼とかいう言葉では到底片づけられない。
もっと複雑で、もっと歪で、もっとリアル。だからこそ、ぐさりと刺さってくる。
読後にスカッとするかどうかは、人によると思う。
でも少なくとも、心に何かを落としていくタイプの小説だということは間違いない。
42.どんでん返しの先に待つ、愛の地獄── 法月綸太郎『頼子のために』
「頼子が死んだ」
17歳の愛娘を何者かに殺害された父親・西村悠史。警察が通り魔事件として捜査を進める中、悠史は「警察の捜査に疑念を抱き、ひそかに犯人をつきとめて相手を刺殺、自らは死を選ぶ」という衝撃的な手記を残す。
この手記を読んだ名探偵・法月綸太郎は、記述された父の愛と復讐の物語の裏に、さらなる謎が隠されていることを見抜き、事件の再調査に乗り出すのであった。手記に綴られた言葉は全て真実なのか、それとも巧妙に仕組まれた罠なのか。
二重の悲劇の真相を追う綸太郎の前に、驚愕の事実が次々と姿を現す。父が守りたかったもの、そして本当に裁かれるべき罪とは何か。複雑に絡み合う人間関係と心理が、事件をより一層深い闇へと誘う。
父の愛と復讐劇、その手記に隠された驚愕の真相
『このミステリーがすごい!』の上位常連、法月綸太郎シリーズの中でも群を抜いて強烈なインパクトを残すのが、この『頼子のために』だ。
冒頭から度肝を抜かれる。殺された娘の復讐のため、父親が犯人を殺して自殺する──という壮絶な内容の手記から始まる。しかも、その手記はすでに完結した悲劇として提示されるのだ。
読んでいるこっちは、当然「犯人はこの父親」「動機は明確」「結末も出てる」と思い込む。だが、そこから探偵・法月綸太郎が登場し、手記に潜む違和感に気づいた瞬間から、物語はがらりと姿を変えるのだ。
再調査が始まって以降、真相の上書きが次々に発生していく。「あれは違ったのか?」「じゃあこれも……?」と、思考が何度もひっくり返されていく感じは法月綸太郎ならではだ。
終盤のどんでん返しのラッシュも、それが単なるトリック勝負じゃなくて、登場人物の内面や関係性に直結してるからこそ、読後の衝撃が深い。
この作品は、いわゆる「イヤミス」好きにはたまらないやつだ。というか、数ある「イヤミス」の中でもトップレベルの最悪の読後感だ。でも単に後味が悪いだけではなく、もっと複雑で濃厚な感情がうねっている。
怒り、絶望、欺瞞、そして、どうしようもなく純粋な愛。
そう、この物語に流れてるのは「歪んだ愛」なのだ。
しかもそれが、毒とかヘドロとかマグマとか、そういう濃くて重いものとして描かれていて、めちゃくちゃ印象に残る。
探偵役の法月綸太郎も個性的だ。論理重視で、思ったことはズバズバ言うし、情に流されない。でも、感情を突き放した分だけ、物語の悲劇性が際立つのだ。
作者・法月綸太郎自身にとってもこの作品は転機だったらしく、初期の理詰めな作風から、感情や倫理にまで踏み込むスタイルへの橋渡しとなった一冊だと言われている。
どこまでが真実で、どこからが願望なのか。
どの感情が純粋で、どこまでが狂気なのか。
そんな曖昧でねじれた感情が、一滴ずつ、心に沈殿していくような作品だ。

43.金が人生を焼き尽くす── 宮部みゆき『火車』
休職中の刑事・本間俊介は、遠縁の男性から婚約者・関根彰子の捜索を依頼される。彼女は自らの意思で失踪し、徹底して足取りを消していた。
なぜそこまでして姿を消したのか。彼女は何者なのか。本間が過去を辿るうち、謎の鍵はカード社会に取り残された自己破産者の凄絶な人生にあると判明する。
クレジットカードが普及し始めた時代の日本を背景に、借金に縛られた人々の苦悩と、そこから逃れようとする必死の叫びが描かれる。
彰子の足跡は、現代社会の抱える根深い問題へと繋がっていくのであった。
姿なき女性を追う社会派ミステリーの金字塔
借金地獄。自己破産。行方不明の女。
この物騒なキーワードにピンと来た人は、宮部みゆき『火車』の重さをすでに知っているかもしれない。
舞台はバブル崩壊直後の日本。クレジットカードと消費社会が人をどう壊すかを描いた本作は、発表から30年以上経った今でもまったく色褪せていない。
主人公は、ケガで休職中の刑事・本間。親戚の頼みで、婚約者の女性・関根彰子の行方を追うことになるのだが、調べれば調べるほど、その女性の実像は怪しく、そして悲惨なものへと変わっていく。
この作品に、派手なアクションやトリックはない。しかし、聞き込み、資料集め、戸籍の調査……そういった地味でまっとうな捜査が、むしろリアルで、イヤな感じがする。ミステリーというよりは、現代社会の闇を暴いていくドキュメンタリーみたいな感覚だ。
失踪した女性が求めていたのは、何気ない普通の生活だった。でも、それすらも簡単に手に入らない世界が、この作品にはある。
クレジットカード、保証人、アイデンティティの乗っ取り。どれも現実にある話で、だからこそ他人事じゃ済まされない。「これは今の自分にも起こるかも」と思った瞬間から、物語は一気に加速する。
そしてなによりも、宮部みゆきの語りが抜群にうまい。地の文はあくまで冷静、でも会話は自然でテンポがよく、読みやすい。
それでいて読後には、重たい鉛玉を喉の奥に詰め込まれたような気持ちになるのだから、ほんとに恐ろしい。
社会の仕組みが、人間の弱さと結びついたときに何が起こるか。その答えが、この作品には描かれている。
走り出した火車は、もう止まらない。
そして、誰もがその軌道の上にいることを忘れてはいけない。
44.蘇る世界に、絶対の死はあるか── 山口雅也『生ける屍の死』
死者が次々と甦り〈生ける屍〉と化すという怪現象が頻発する20世紀末のアメリカ。ニューイングランドの片田舎で霊園を経営するバーリイコーン一族の青年グリンは、ある日、自らも毒殺され〈生ける屍〉として甦ってしまう。
身体は徐々に朽ちていくものの、生前の意識と記憶は保たれたまま、彼は自身の死の真相と、一族の間で次々と起こる連続殺人事件の謎を追うことになる。
被害者も容疑者も、そして探偵自身も〈生ける屍〉であるかもしれないという、前代未聞の状況下での捜査が始まる。生者の論理と死者の論理が複雑に絡み合い、常識を超えた世界で、グリンは驚愕の真相に辿り着けるのであろうか。
死せる探偵、生ける謎を追う
死者が蘇る。
そんな設定、普通ならファンタジーやホラーに走りそうなものだが、本作はそこをガチで本格ミステリとしてやり切っている。ここがすごい。
というか、「死人が蘇る世界で殺人事件が起こる」なんてそもそも成立するのか? と思うかもしれない。ところがどっこい、この世界では死の定義があやふやだからこそ、殺しが逆に深く、重くなる仕組みになっている。
つまり、「死者が戻ってくる世界でも、人はなお人を殺す」という事に、この物語の全てが詰まっているのだ。
「生き返るなら、殺してもいいのか?」
「死が一時的なものになった社会で、命の価値はどう変わるのか?」
ミステリの皮を被った哲学書だ、という評判も頷ける。
これがまた本格ミステリとしてもちゃんと成立してるからすごい。死んだ人が蘇る世界で、アリバイも動機も再構築される。死が完全じゃないなら、殺人という行為の意味も変わってしまう。その前提を覆された状態で、ちゃんとロジックを積んでいく推理が見事すぎるのだ。
しかも、設定の面白さだけじゃなくて、きちんと推理小説としても緻密。伏線の張り方、情報の出し方、論理的な謎解きの気持ちよさ。ジャンルの垣根を超えながらも、本格としての背骨はビシッと通っている。
主人公のグリンも個性的で面白い。パンクスで、やさぐれてて、でもどこか一本筋が通っていて、彼が世界とどう向き合っていくのか、その視点も物語を面白くしている。
文体もまた独特だ。海外ミステリの翻訳のような、少し浮世離れしてる雰囲気。でもそれがこの異世界感というか、死者が蘇る世界のリアリティに不思議とハマるのだ。
トンデモ設定なのに、読んでるうちに「こういう世界があるかもしれない」と思わせる説得力がある。これはもう、作者の手腕としか言いようがない。
ありえないのにリアル。ふざけてるのに真面目。ミステリなのに問いかけは哲学。
生と死の境界線が溶けていくとき、人間という存在のかたちもまた、曖昧になってゆく。
45.嘘こそ最強の弁論── 円居挽『丸太町ルヴォワール』
京都に古くから存在するとされる私的裁判制度〈双龍会〉。そこで名家の御曹司・城坂論語は、祖父殺害の容疑をかけられる。
論語は自らの無実を証明するため、この特殊な法廷で弁舌の限りを尽くすことを決意。事件当日、屋敷には謎の女〈ルージュ〉がいたと論語は証言するが、彼女の存在を示す痕跡は一切発見されない。
論語は「幻の女」の正体を探りつつ、〈双龍会〉という独特の舞台で、検事役の龍師と華麗かつ熾烈な論戦を繰り広げる。果たして〈ルージュ〉の正体とは。
そして、論語は自らの潔白を証明できるのか。古都を舞台に、虚実入り混じる言葉の応酬が、事件の真相を幾重にも覆い隠していく。
幾重にも仕掛けられた驚愕のどんでん返し
法廷ミステリと聞くと、どうしても裁判所や刑事事件など、固めのイメージを想像してしまう。
でもこの作品は違う。舞台は古都・京都、ルールは「何でもアリ」、そして主戦場は「言葉」だ。
登場するのは、双龍会(そうりゅうかい)と呼ばれる謎の法廷のような場。しかしそこでは、証拠の捏造も、詭弁も、ウソもすべてOK。とにかく「火帝(かてい)」という裁定者を納得させれば勝ち。つまり、真実かどうかではなくて、「どれだけ魅力的な物語を語れるか」が全てなのだ。
この設定がめちゃくちゃスリリングで面白い。読んでいるこっちも完全に観客席にいる感覚だ。論破合戦みたいなやりとりにハラハラして、次の一手が気になって手が止まらなくなる。弁論バトルが、こんなに熱くてエンタメになるとは。
そしてやっぱり凄いのは、怒涛のどんでん返しラッシュだ。ひとつ謎が解けたと思ったら、次の瞬間にはもっとでかい謎が出てきて、「えっ!?」となる。その繰り返し。
作中の『夢から醒めてもまた夢なんだぜ?どれだけどんでん返しするんだよ。馬鹿じゃねぇの!』というセリフが、まさにこの作品の読書体験そのものを言い表している。
キャラも個性があって魅力的。主人公の城坂論語は、論理と情熱のバランスが絶妙。謎の美女ルージュは、色っぽくて危うい。そしてその他の登場人物たちもみんな、言葉を武器に戦っているだけあって、とにかくセリフがキレッキレだ。
ノリはラノベ寄りだが、そのテンポ感が逆にこの「論戦ゲーム」にアクセントを与えていて、読みやすさにも繋がっている。
論理で殴り合って、嘘で人を救って、物語で世界を揺さぶる。そんな一風変わった本格ミステリだ。
ここには、真実よりも美しい嘘に命を懸ける人たちの、切実で滑稽で、そしてちょっと格好いい戦いがある。
46.正体不明の語りがすべてを覆す── 浦賀和宏『眠りの牢獄』
恋人・亜矢子と共に階段から転落し、彼女は5年もの間、昏睡状態に陥ってしまう。そして現在、亜矢子の兄によって、事件当日に彼女の家にいた主人公を含む3人の若者が、地下室に監禁される。解放の条件はただ一つ、亜矢子を突き落とした真犯人を告白すること。
一方、並行して描かれるのは、ストーカー被害に悩む女性・冴子が、インターネットで知り合った正体不明の人物とメールで交換殺人を計画する不穏なやり取りである。閉ざされた地下室での過去の真相追求と、ネット上で進行する新たな殺人計画。
一見、無関係に見えるこれらの「牢獄」は、やがて読者の予測を超えた形で繋がり、衝撃的な真実が明らかになるのであった。
二つの牢獄が交わる時、戦慄の真実が牙を剥く
浦賀和宏の『眠りの牢獄』は、まさに構成美で読ませるタイプのミステリだ。
舞台は核シェルター。終末的な閉鎖空間に集められた若者たち。誰が犯人か、次に殺されるのは誰か。この手のサバイバルシチュエーションものとしての緊迫感は、バッチリある。
でも、それだけじゃない。この密室地獄と並行して描かれるのが、外の世界でひそかに進行する交換殺人計画だ。こっちはメールでのやりとりがメインで、やたらと冷静な語り手が、まるでゲーム感覚で殺人を組み立てていく。
この二つの物語が、まったく別物に見えて、実は……という仕掛けが本作のキモである。
視点は章ごとにくるくる変わる。シェルター側の焦燥と疑念と血。外界側のロジカルで淡々とした殺意。どちらも人間の内側に潜む「見たくないもの」を容赦なくえぐってくる。
しかも、こっちは犯人探しをしてるつもりで読んでいるのに、途中で「あれ?」「誰の話を聞いてたんだ?」と戸惑わされることになる。読者の認識ごとガラリとひっくり返す、あの浦賀節が炸裂するのだ。
何よりすごいのは、すべてが収束していく終盤。
あの「あまりにも異常な切断の理由」は、背筋がガチガチに凍るレベルで怖い。狂っている。でも筋が通っている。でも狂っている。
ただのどんでん返しじゃない。
この動機、この結末、これはミステリじゃなきゃ描けない人間の深淵だ。
綺麗に終わらない。でも、だからこそ忘れられない。
47.法では裁けぬ恐怖── 中山七里『連続殺人鬼 カエル男』
口に巨大なフックを打ち込まれ、マンションの13階から全裸で吊り下げられた女性の死体。
その傍らには、子供が書いたような稚拙な犯行声明文が残されていた。これが、街を恐怖と混乱の渦に陥れる連続殺人鬼「カエル男」による最初の凶行であった。
警察の捜査は進展せず、市民の不安が募る中、第二、第三の犠牲者が同様の手口で発見される。街はパニック状態に陥り、警察への非難の声は日増しに高まっていく。
無秩序に猟奇的な殺人を繰り返すカエル男の真の目的とは何か。その正体は。埼玉県警捜査一課の刑事・古手川は、同僚の渡瀬と共に、この見えざる凶悪犯を追う。
戦慄の猟奇殺人と社会の狂騒。カエル男が仕掛ける悪夢のゲーム
まず、犯人の造形が異常だ。
雨合羽に長靴、子供が書いたような稚拙なメモを残して、残酷な殺人を繰り返す。こんなの、忘れられるわけがない。
グロテスクだが、ただのスプラッターにはならず、読者の好奇心をいい意味でざらつかせてくる。こういう読ませる不快さは、ミステリーにおいてはけっこう貴重だったりする。
でもこの作品、ただの猟奇ものではない。テーマとして据えられているのが「刑法三十九条」だ。要するに、心神喪失だったら罰せられないというアレである。作中でも法医学者が「これは刑法三十九条との格闘になる」と言う場面があるが、これはまさに本作全体に通底する核心なのだ。
「法とは誰のためにあるのだろう?」「異常者に法は通じるのか?」みたいな根源的なモヤモヤを、ずっと心の隅で抱えながら読むことになる。
そして、もちろん中山七里のことだから、どんでん返しはてんこ盛りだ。二転三転どころか、四転五転してくる。伏線の貼り方もうまいし、とんでもないタイミングで爆弾を落としてくるから、油断していると一気にやられる。
どこまでが真実で、どこからが作為なのか。読み終わってもしばらくは、頭の中でぐるぐる反芻せざるを得ない。
怖いけど読みたい。グロいけど止まらない。
そんな矛盾した欲望を見事に突いてくる、極めて中毒性の高い作品だ。
法の目をすり抜ける狂気は、今日もどこかで合羽を着ているかもしれない。
48.社会が生み出した絶望の花── 真梨幸子『殺人鬼フジコの衝動』
十数人を殺害した罪で死刑囚となった女、通称「殺人鬼フジコ」。その名は、日本犯罪史に戦慄と共に刻まれている。しかし、彼女の原点は十一歳の時に経験した一家惨殺事件にあった。フジコはその事件における唯一の生存者だったのである。
悲劇を乗り越え、新たな人生を歩もうとしていたはずの少女は、なぜ、そしてどのようにして、稀代の連続殺人鬼へとその身を変貌させてしまったのか。
物語は、フジコを深く知るある人物が遺したとされる記録小説の形で、謎と狂気に満ちた彼女の生涯を克明に描き出していく。この「記録」という形式自体が、物語に更なる深みと疑念を投げかける。
少女は何故、伝説の殺人鬼になったのか?
これは、読んだあとに本気で気分が悪くなる小説だ。
真梨幸子『殺人鬼フジコの衝動』は、「イヤミス」というジャンルの代名詞的な存在で、読者を徹底的に嫌な気分にさせることに全力を尽くしている。
しかも、そのやり方がものすごく計算されていて上手い。読む手は止まらないのに、ページをめくるたび胃が痛くなる。なのに、やめられない。
主人公・フジコは、一家惨殺事件でただ一人生き残った少女。いじめ、虐待、孤独、自己否定。救いのない現実が積み重なるうちに、彼女の中に何かが育っていく。
そしてある日、それが花開く。真っ黒な、血を吸って咲いたような花が。
殺人を犯すたびに少しずつ正気を失いながら、それでも世間から「いい人」に見られようとする彼女の歪みは、いっそ悲しい。彼女は自分の苦しみを誰にも手渡せなかった代わりに、破壊というかたちで世界に投げ返す。それが衝動なのだ。
構成もめちゃくちゃ巧い。フジコの視点や、記者の記録、関係者の証言、手記などが複層的に組み込まれていて、ずっと「真実っぽい何か」の上を歩かされる。
そして終盤、読者を突き落とすかのように、はしがきとあとがきがすべてをひっくり返す。この冷たさと容赦のなさは、気持ちが悪くなるほどだ。
ラストの仕掛けも衝撃だが、それ以上に刺さるのは、怪物は最初から異形だったのか、それとも、世界がそう育てたのかという問いだ。
答えは出ない。しかし、あまりにも静かに壊れていったその姿に、目が離せなくなる。
そして気づく。
悪魔の種は、土の中で音もなく芽を出すことに。
49.その声は、誰のもの?── 井上夢人『ダレカガナカニイル・・・』
警備員の西岡吾郎は、山梨県の小さな村に拠点を置く新興宗教団体「解放の家」の道場を警備していた。しかし、その初出勤の夜、施設は謎の火災に見舞われ、カリスマ的な教祖が焼死するという事件が発生する。
その日を境に、吾郎の頭の中で、まるで自分自身のものではない、得体の知れない「誰か」の声が聞こえ始めるようになったのだ。
自らの意識の中に突如として侵入してきた他者の声に翻弄されながら、吾郎は火災事件の真相と、この声の主の正体という二重の謎を追うことになる。
SFとミステリーが交錯する意識の迷宮
頭の中に「誰かの声」が響く。
そんな突拍子もない状況から始まるこの小説、普通ならオカルトだとか妄想だとかで処理されそうなものだが、ここからミステリーとして成立させてしまうのが井上夢人のすごさだ。
この声は一体誰なのか? なぜ自分の中に入り込んでくるのか?
さらに、かつて教団施設で起きた火災事件とどう繋がるのか?
断片的な情報が少しずつ積み上がっていき、やがてそれが一本の線になる瞬間の快感は、本格ミステリとしても一級品だ。
一方で、この物語はSFでもある。「他人の意識が自分の中に存在する」という奇想設定が、アイデンティティや人格の境界をめちゃくちゃに揺さぶってくる。
思考って誰のもの? 感情って、どこまでが自分?
そんな哲学的なテーマが、物語の裏側でずっと鳴り続けている。思えばこの「声」は、ただのトリックではなくて、ずっと人の輪郭そのものを見つめていたんじゃないかと思う。
そもそもこの作品、かつて「岡嶋二人」として活躍した井上夢人のソロデビュー作というのが驚きだ。語り口は軽妙でテンポがよく、ユーモアもほどよく混じっているのに、やってることはかなり本気のサイコSFミステリである。
宗教団体をめぐる怪しげな雰囲気、思いもよらない方向に転がるプロット、そして主人公と声の微妙な関係性。どこを切り取っても、既存のジャンルに収まらない凄みがある。
最初は奇抜なネタだと思っていた頭の中の声が、読み終わる頃には、もうひとつの自分に思えてくる。
意識の内と外、現実と妄想、他者と自己。
その曖昧な境界線を揺さぶるこの物語は、最後にこう語りかけてくる。
「あなたの中の声は、本当にあなただけのものか?」
50.真実を解剖せよ── 皆川博子『開かせていただき光栄です』
時は十八世紀、場所は英国ロンドン。高名な外科医ダニエル・バートンの解剖教室から、通常ではありえない異様な状態の屍体が発見される。
それは、四肢を切断された少年と、顔を潰された男性の亡骸であった。不可解な屍体はその後も次々と現れ、ダニエルと彼の弟子たちは深い困惑に包まれる。
やがて、治安判事から捜査への協力を要請された彼らは、この連続する奇怪な事件の謎を追うことになる。その背後には、一人の詩人志望の少年が辿った数奇な運命と、ある稀覯本を巡る恐ろしい陰謀が複雑に絡み合っていた。
本作は、解剖学が最先端の科学として注目される一方で、一般社会からは強い偏見と恐怖の目で見られていた、そんな時代の光と影を描き出す。
歴史と科学が織りなす重厚ミステリー
この小説の何が好きかって、18世紀ロンドンの空気がページから立ち上ってくるところだ。
華やかで洗練されたイメージとは裏腹に、そこには腐臭と煙と泥が渦巻く。市場の喧騒、スラムの闇、夜の街角をうろつく解剖用の死体盗りたち。そんなもうひとつのロンドンが、五感に直接訴えかけてくる。
解剖学への偏見、階級制度の硬直、女が教育を受けられない理不尽。そういう「その時代ならでは」の社会の歪みが、物語の土台としてしっかり据えられている。だからこそ、ただのミステリーに終わらず、歴史小説としてもめちゃくちゃ骨太だ。
主役は、外科医ダニエル・バートン。そして、彼を慕う弟子たち(通称バートンズ)、盲目の治安判事フィールディングとその助手アン。このメンツがまたクセ者揃いで、全員が時代からはみ出した人なのだが、それゆえに深い結びつきと情熱が生まれていく。
社会から押し出された者たちが、知と誠意と手術用の鋸で運命に立ち向かっていく。この、はじかれ者の連帯感がいい。泣かせるんじゃなくて、燃える感じだ。
物語の中心には、失踪した詩人、解剖教室に運び込まれる身元不明の遺体、そして一冊の稀覯本。このあたりの絡ませ方も実に巧妙で、ミステリ的な快楽がしっかりある。
しかも、伏線の張り方も回収の仕方も丁寧で、ラストに向けてピースが一気に揃っていくあの流れはかなり爽快だ。
司法の腐敗、科学の未成熟、都市の闇。そういった重たい要素を抱えつつも、芯にあるのは「生きることへの意志」である。
これは、腐敗した街の真ん中で、それでも真実を解剖しようとした人たちの話だ。
おわりに
というわけで『最強に面白いおすすめ国内ミステリー小説50選』をご紹介させていただいた。
50作品すべてが、時代や作風こそ異なれど、それぞれの方法で読者を騙すことに全力を尽くした名作ばかりである。
ミステリーとは、物語の裏側に隠された真実を、登場人物とともにひとつずつ解き明かしていくゲーム。
だからこそ、読み終えたあとに残る達成感と余韻は、他のジャンルにはない格別なものだ。
あなたの「人生ベストミステリー」が、この中に見つかりますように。
そんな願いを込めて。