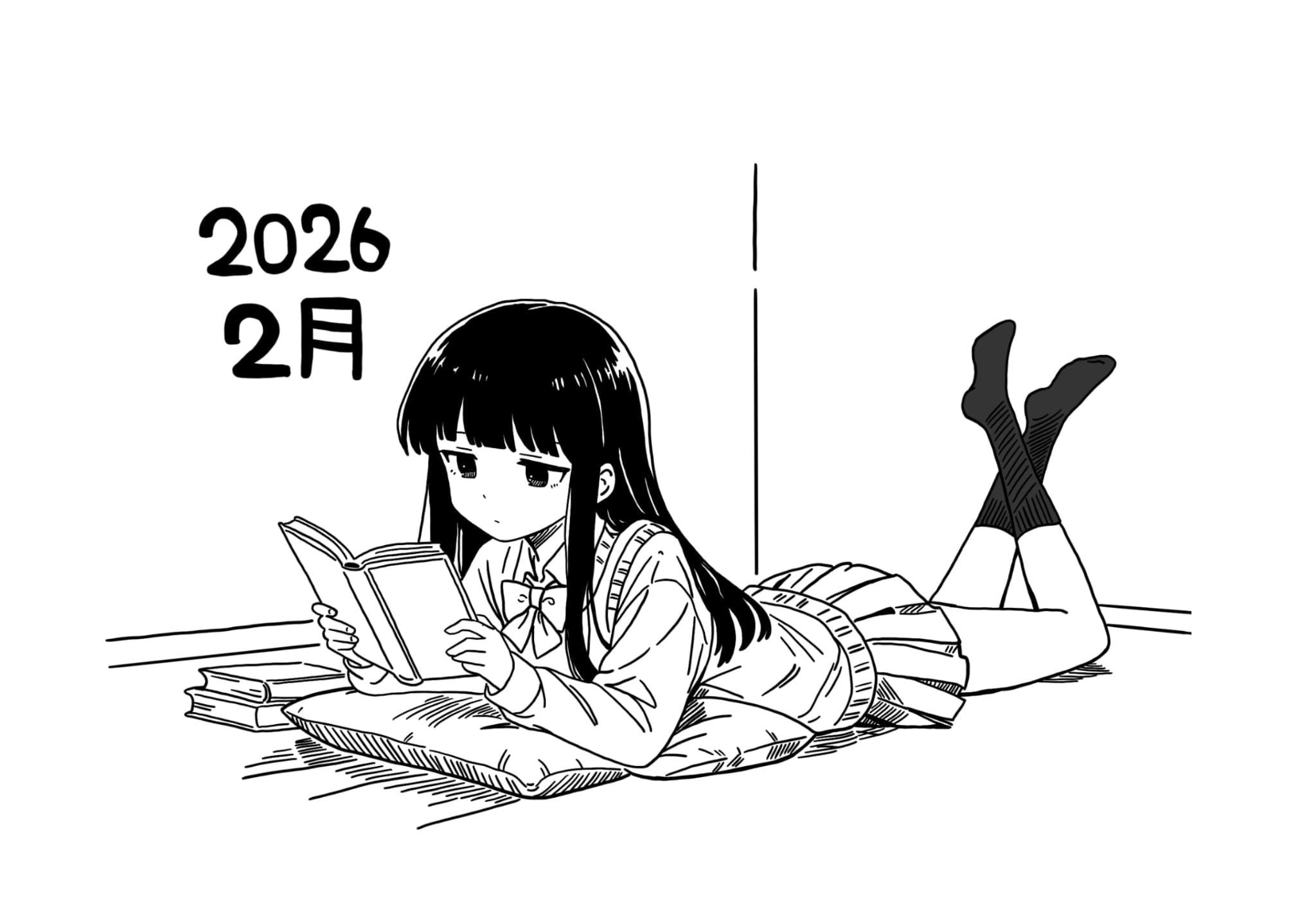ミステリとは「誰が殺したか」を問うもの。
そんな時代は、とうに終わった……とまでは言わないけれど、いまミステリの世界では「特殊設定ミステリ」というジャンルが、かつてない熱狂とともに存在感を高めている。
でもこれは、ただのSFやファンタジーとのミックスじゃない。むしろ真逆。見た目は奇抜でも、中身はバリバリにロジカル。とにかく論理のパズルとしての面白さに全振りした、ストイックなゲームだ。
「特殊設定」とは、要するにその物語の〈世界のルール〉のこと。タイムリープしたり、超能力が使えたり、人間の人格が交換できたり。
設定だけ見るとトンデモ系に見えるかもしれないけれど、だからこそ面白い。
この特殊な世界で、どうやって殺人が可能だったのか? 誰に犯行ができたのか? そこを論理で突き詰めていくのが、最大の魅力だ。
手がかりも変わってくる。普通のミステリなら証拠とか証言が命だが、特殊設定ミステリでは、まず「この世界はどうなっているのか」を理解するところから始まる。
そして、そのルールに沿って論理を組み立てて、犯人を突き止めていくという二段構えの挑戦が待っている。
この記事では、そんな特殊設定ミステリの傑作を40作品厳選した。
記憶、認知、時間、空間、アイデンティティ、世界の在り方。ルールを把握して、攻略法を探して、バグを突くように真相を暴く。まさに、読む謎解きゲームだ。
一冊ごとに常識が崩れ、ページをめくるたびに世界が書き換えられていく。
あなたの論理が、どれだけ異常な世界にも通用するか──その腕試しを、どうぞ。

1.腐りかけの名探偵── 山口雅也『生ける屍の死』
死者蘇生
ピンクの霊柩車で乗り込んでくる主人公がすでに死んでいる、という時点で、もう普通じゃない。
舞台はアメリカの田舎町トゥームズビル。地元を牛耳るのは霊園を仕切るバーリイコーン家。その一族に渦巻く遺産相続と殺意のなか、若きグリンも毒殺されてしまう……が、蘇る。しかも自力で。
でもこの生き返りは、魔法ではない。ちゃんとルールがあって、制限時間つき。時間が経てば、腐る。目玉は落ちるし、関節はギシギシ鳴る。
そんな状態でグリンは、自分の死の真相と、一族に仕掛けられた連続殺人の謎に挑むことになる。
死んでいることがトリックを動かす
この設定はぶっ飛んでいるようでいて、めちゃくちゃロジカルだ。死亡推定時刻のズレ、アリバイの混乱、動機の反転。
「死者が蘇る世界で、なぜ誰かを殺すのか?」という謎がずっと物語の芯にある。その構造自体が、見事に本格ミステリとして成立しているのがすごい。
しかも主人公が探偵であり被害者でありゾンビというのは、いろんな意味で一人三役だ。腐りかけの頭で犯人の動機を考え、崩れそうな体で現場を歩く。もう必死である。でもその必死さが、やけに格好いい。動くたびに肉体が劣化していく探偵なんて、他に聞いたことがない。
文章はやや翻訳調で乾いてるのに、どこか滑稽で品がある。このバランス感覚も絶妙だ。ブラックユーモアは効くし、霊園の描写もどこかおしゃれ。ピンクの霊柩車が似合う世界観ってなに、と思いつつ、気がつけばすっかりなじんでいる。
『生ける屍の死』は、特殊設定ミステリというジャンルの可能性を一気に広げた一作だ。「死んだ人間が主人公です」と言われた時点で読み手の構えを崩しにかかっているが、話が進むほどに、構築された論理と仕掛けの妙に引き込まれる。
派手で、風変わりで、でも骨の髄まで本格。そんな物語が1989年に生まれていたことが、まず驚きだ。
生き返った理由は復讐じゃない。
知りたかっただけだ。自分がなぜ殺されたのかを。
腐っていく体の中で、グリンの目だけは最後まで死んでいなかったのだ。
2.時間が繰り返すのはチャンスか、それとも地獄か── 西澤保彦『七回死んだ男』
タイムリープ
久太郎には変わった体質がある。ある特定の日が、何の前触れもなく9回繰り返されてしまうのだ。
本人は全部覚えている。でも他の人は気づかない。何をしても、9回目の朝にはリセットされる。いわば、人生のやり直しを一人で繰り返す人物だ。
そんな彼が今回ぶち当たるのが、正月の親戚大集合。舞台は祖父の屋敷。空気はギスギス、遺産の話がちらついて、そろそろ誰か刺されそうなムードが漂う。そして案の定、ループ2回目の朝。祖父が死んでいた。
こうなると久太郎に残された選択肢は一つ。祖父を救う。何度でも、何をしてでも。ループを駆使して、犯人を特定し、犯行を防ぎ、悲劇を回避する。
だが、やってみるとこれがめちゃくちゃ難しい。
推理は積み上がり、破綻し、また積み上がる
時間はある。でも足りない。情報を集めるにも限界がある。誰が嘘をついているのか。どうやって殺したのか。そもそも、なぜその日だけループが起きたのか。やればやるほど謎は増えるし、毎回どこかで予定外の展開が待っている。
この作品のすごさは、時間を戻せるから無敵、なんて甘い幻想を一瞬で壊してくるところだ。全能にも見える設定なのに、ちゃんと限界がある。そしてその限界のなかで、どうロジックを組むか。そこがミソだ。
推理モノとして見ると、これはかなりの変化球だ。でも中身はガチガチの本格。ルールはシンプル。
「ループは起きる」「記憶は残る」「世界は毎回同じ」
それだけ。それだけで、こんなにも頭を悩ませる密室劇になるのかと驚く。
犯人の動機も手口も、この設定がなければ絶対に成立しない。でも逆に言えば、この設定だからこそ成立する。そして、そこに持ち込まれるのがSFではなく、純粋な論理。だからこそ面白い。
『七回死んだ男』は、ふざけたようなタイトルからは想像もつかないほどの、緻密で過酷な頭脳戦だ。久太郎の疲労が、読み手のこっちにまで伝染してくる。
それでも彼は走る。9回しかチャンスがないから。
いくらやり直せても、心まで無傷じゃいられない。
でも、やるしかない。人を救うために。
3.中身と身体がバラバラになったとき── 西澤保彦『人格転移の殺人』
人格入れ替わり
地震で逃げ込んだ先が、まさかの「人格入れ替え装置のある実験施設」だった──という出だしからして、すでにただごとじゃない。
西澤保彦『人格転移の殺人』は、SFと本格ミステリを掛け合わせたような、とんでもない密室劇である。
登場人物は6人。全員が、自分ではない誰かの身体に、一定のルールにしたがって次々と乗り移っていく。しかもそれが時計回りという、ゲーム盤のような単純ルールで進行するから、余計に怖い。
ここで起きるのが連続殺人だ。問題は、誰が殺したかだけじゃない。「そのときその身体を使っていたのは誰か?」という、まるでブラックボックスを覗くような謎が加わる。
もう犯人捜しというより、アイデンティティそのものが宙に浮く感覚だ。
身体と中身がズレると、証言もアリバイも壊れる
身体と中身が一致しない世界で、動機もアリバイも証言も、ことごとく曖昧になる。
普通のミステリなら信頼できるはずの材料が、全部ぐらぐらしている。しかも登場人物たちの視点も混乱しているから、「自分がいつ誰だったか」をはっきりさせるだけでもひと苦労だ。
だが、ただのカオスでは終わらない。この作品には、逆転のルールがある。すべての人格は、決められた順番で、決められた身体へと移動する。そのただ一つの法則だけが、全体を貫く唯一の真実になる。
だからこそ、読んでいる側も、証言の断片を拾い上げ、順番を並び替え、パズルのピースを手探りで集めるような感覚に陥っていく。
犯人の動機や目的が明らかになったとき、それはただの犯罪では終わらない。アイデンティティをめぐる葛藤、自己と他者の境界、そして自分という存在はどこにあるのかという、ミステリの枠を越えたテーマが残される。
『人格転移の殺人』は、身体と人格というミステリの基本構造を崩壊させながら、それでも論理だけは手放さない。ぐにゃぐにゃの設定を、カチッとロジックで締めあげてくる構成力がすごい。これは、特殊設定ミステリの最前線だ。
混乱と秩序。破壊と構築。そのせめぎ合いの先に、かろうじて立っている真実の姿。
そこにたどり着いたとき、自分の頭もぐるぐる入れ替わった気分になる。
4.超能力があっても、論理は死なない── 西澤保彦『神麻嗣子の超能力事件簿』
様々な超能力
もしこの世界に超能力者が本当に存在したとして、その能力が事件に悪用されたらどうするか。
「犯人はテレポートしたに違いない」「密室を念動力で開けたんだ!」なんて話になったら、推理小説なんて成り立たないと思っていないだろうか。
……そう思っていた時期が、私にもありました。
西澤保彦の『神麻嗣子の超能力事件簿』は、そんな「超能力=なんでもアリ」という先入観を完膚なきまでに論破してくる。この物語に登場するエスパーたちは、確かに人知を超えた能力を持っている。
でもその力には、重量制限・時間制限・使用条件・副作用……と、現実の科学技術並みにシビアなルールがあるのだ。
超能力=反則、はもう古い
たとえば、念動力で物を動かすには距離の制約があり、予知能力にも精度の限界がある。だからこそ、それを使ってどうやって殺人を成立させたのか?という推理が成り立つ。
主人公はミステリ作家の保科匡緒(ほしなまさお)。超能力は持っていない。でも、誰よりも優れた論理力を持っている。事件の情報は、政府の秘密組織「チョーモンイン」から派遣された超能力専門相談員・神麻嗣子(かんおみつぎこ)と、美人警部・能解匡緒(のけまさお)から伝えられる。
つまり、神麻は超能力のプロ、能解は事件現場のプロ、保科匡緒は頭脳派の安楽椅子探偵という役割分担で、毎回不可能犯罪に挑むというスタイルだ。
例えば、瞬間移動で逃げた犯人。誰も見ていないし、防犯カメラにも映っていない。でも、そもそもその能力は生身の人間は持ち込めないとか、着地地点が不確かとか、ちゃんと制限がある。それを踏まえて、じゃあ本当に瞬間移動だったのか?と考え直す。
つまり、私たち読者はエスパーの取扱説明書を読みながら、ひとつひとつ事件のロジックを検証していくことになる。こんなにファンタジーっぽいのに、むしろ普通の本格ミステリより理詰めとは、どういうことだ。
しかも、主人公が超能力を持っていないのがミソである。彼は常識という武器だけで、非常識な事件に挑む。その構図が気持ちいい。結局謎を解くのは人間の頭脳だろ?という、ミステリの王道をしっかり守ってるのが心地いい。
ハチャメチャな能力バトルじゃない。むしろ超能力という制約があるからこそ、逆にロジカルに組み上がる、異色の超能力×ミステリの融合作品だ。
ミステリファンもSFファンも、論理と想像力のバトルをぜひ味わってほしい。
5.魔法はある。けれど真実は、論理でしか暴けない── 米澤穂信『折れた竜骨』
魔法
12世紀末のソロン諸島。霧の海に浮かぶその島で、領主が殺された。犯人は島の中にいる。だが、誰も殺した覚えがない。
この奇怪な状況に挑むのは、放浪の騎士ファルク。彼が相棒に選んだのは、領主の娘アミーナ。二人は、〈走狗〉と呼ばれる存在の謎に挑んでいく。
魔法と呪いが現実として息づく世界にありながら、『折れた竜骨』はロジックで殴り合う物語である。米澤穂信はこの一作で、魔法があっても論理は死なないという信念を突きつけてきた。
異世界設定がそのままトリックになる快感
この作品のすごさは、ファンタジーを舞台装置として消費するのではなく、そのルールを緻密に設計して、推理の土台にまで組み込んでいる点にある。
たとえば、記憶を失う〈走狗〉の設定は、心理的動揺や矛盾を使った尋問テクニックを封じてしまう。そのせいで、ファルクは限られた証拠と物理的状況から推理を組み上げるしかない。剣を持つが、勝負は思考でつける。
ファンタジーならではの特殊な身体特性や制約も、すべて伏線として活用されている。死なない兵士、呪文の制限、儀式の手順。どれも異世界の雑学で終わらず、殺人と謎解きのギミックとして効いてくる。
物語が進むにつれ、どこか英雄譚のような風格すら帯びてくるが、それは正義のヒーローではなく、知恵と覚悟の物語だ。剣も魔法も使うのに、最大の武器が論理という潔さが気持ちいい。
『折れた竜骨』は、ファンタジーとミステリという交わらなさそうな二つの世界を、本気でくっつけにかかった挑戦作でありながら、その試みがきっちり成功してしまった傑作だ。
竜骨は折れても、真実の芯は折れない。
それを信じて戦う者の物語である。
6.そのクラスにだけ、死がやってくる── 綾辻行人『Another』
呪い
転校してきたばかりの榊原恒一が最初に気づいたのは、クラスの空気だった。
妙にかたく、重い。話し方ひとつに遠慮がにじみ、どこかピリピリしている。そして、教室の隅に座る眼帯の少女──見崎鳴(みさきめい)。
話しかけてみても、誰も彼女のことを話題にしない。存在をなかったことにするように、徹底的に無視している。怖い。
でも恒一は彼女と関わってしまった。その瞬間、バランスは崩れた。
クラス委員長が死ぬ。別の生徒の家族が死ぬ。まるで見えない手で順番に命が落とされていく。これが夜見山北中3年3組にだけ降りかかる、26年前から続く災厄だった。
犯人探しではなく、死んでいるのは誰かという謎
このクラスには毎年、余分な1人が混じってしまう。亡くなっているはずの人間が、誰にも気づかれずにそこにいて、しかもその「死者」のせいで、毎月誰かが死んでいくという。
でも、その「死者」が誰かは、本人にも分からない。記憶も記録も塗り替えられているからだ。これはホラーではあるけれど、やっていることは完全にミステリである。犯人は誰だ、ではなく「死んでいるのは誰だ」という、異形の謎解きだ。
恒一と鳴は、止まらない死を食い止めるため、手がかりを集める。過去の記録、昔の生存者の証言、ささいな違和感。それらをかき集めていくうちに、読んでいるこちらの手にも、真相に近づくヒントが少しずつ積もっていく。
でも本作がすごいのは、仕掛けだけじゃない。中学生という年齢特有の、無防備さ、怖がり方、視野の狭さまで描き込まれていて、だからこそ死の連鎖がリアルに感じられる。決して大人たちが守ってくれるような世界じゃないのだ。
教室の窓の向こうで風が揺れるだけで、何かが起きそうで落ち着かない。そんな感覚がずっと背中に張りついてくる。でも、不思議と目が離せない。
『Another』は、ホラーでもあり青春ものでもあり、そしてがっつり本格の謎解きでもある。しかも、きっちり論理で決着をつけてくるから最高だ。
思い出すたびに、あの教室の空気が肌にまとわりつく。
あの年、あの春、3年3組で何があったのか。
知ってしまったら、もう戻れない。
7.ゾンビと密室殺人が、同じ屋根の下にいた夏── 今村昌弘『屍人荘の殺人』
ゾンビ
ホラー映画を観すぎた夜みたいな、わけのわからない事件だった。
大学のミステリ愛好会に所属する葉村が、ちょっと変わった会長に誘われて、美人の探偵少女・剣崎比留子と共に夏合宿に行くところから物語は始まる。参加者は映画研究会の面々。場所は山奥のペンション「紫湛荘」。
最初はただの合宿だった。少し気まずくて、少し楽しい。
しかし、肝試しの夜、何かが狂い出す。
森の奥から、呻き声。崩れた顔。血まみれの人影。
そう、ゾンビだ。
ゾンビという異常が、謎解きの条件を変える
文字通り死体が歩いてきた。そうなれば全員、当然逃げ込む。籠城するしかない。
外にはゾンビ、内にはミステリ好きたち。サバイバルとパニックと、わけのわからない緊張感に包まれる中、朝が来てみれば、ペンションの一室で人が死んでいた。
扉は内側からロック。窓も開いていない。部屋の中にゾンビはいなかった。
じゃあ、誰が? どうやって? なぜ?
ゾンビと密室ミステリ。まるで相性が悪そうな二つのジャンルを、こんなにも自然に、しかも抜群に面白く融合させてみせたのがこの作品だ。パニックホラーとしてのドキドキ感も本格推理としての謎解きも、どちらも本気。しかも、お互いを邪魔せず、ちゃんと支え合っている。
ゾンビという異常事態は、密室や犯行動機に絶妙なブレを生み出している。だから犯人も普通じゃない。トリックも普通じゃない。しかし、推理はちゃんと筋が通っている。むしろ、論理の力で異常をねじ伏せにいっている。そのバランス感覚がすごい。
そして何より、登場人物たちの空気感がいい。怯えたり、張り合ったり、腹をくくったり。それぞれの反応がリアルだからこそ、状況の異様さが際立つ。なかでも剣崎比留子の魅力は最高だ。この人のキレ味は一度見たら忘れられない。
これはジャンルの境界線を豪快に飛び越えて、でもしっかり着地した、ちょっと変わった、だけど正統派のミステリだ。
ゾンビは脅威だ。
でも、本当に怖いのは、人間の考える力の使い方だったりする。
8.未来は決まっている。でも、それは信じられるのか?── 今村昌弘『魔眼の匣の殺人』
未来予知
「あと二日で、四人死ぬ」
そう言い放ったのは、ある山奥に暮らす予言者の老婆。しかもその言葉を聞いた直後、外界と繋がる橋が燃え落ちた。時も場所も閉ざされた状況で、一行は未来に囚われることになる。
今村昌弘『魔眼の匣の殺人』は、デビュー作『屍人荘の殺人』に続くシリーズ第二弾。今作でも、神紅大学ミステリ愛好会の葉村譲と、美しき探偵・剣崎比留子のコンビが登場する。
今回の舞台は「魔眼の匣」と呼ばれる元研究施設。どこか陰気で、秘密めいていて、いかにも何か起こりそうな場所だ。
四人の死は必然か、仕組まれたものか
物語の肝は、〈予言〉という特殊設定にある。未来があらかじめ提示されているからこそ、緊張感がすさまじい。
死ぬと言われてしまったら、逃れようとするもよし、あえて抗わないもよし。誰が信じていて、誰が操ろうとしているのか。その揺れが、登場人物たちの行動をどんどん歪ませていく。
しかも、次々と本当に死人が出る。しかもちゃんと四人の予兆がついてくる。予言どおりなのか、犯人がそれをなぞっているのか。このあたりの曖昧さが絶妙に効いていて、「どこまでが運命で、どこからが人為か」という謎がずっとつきまとう。
剣崎比留子は冷静で理屈の人間だ。だからこそ、予言のようなあやふやなものと向き合う姿が痛々しくて、そしてかっこいい。論理という刃で、予定調和すら切り裂こうとする姿勢が、今回も冴え渡っている。
前作でゾンビを使って読者の度肝を抜いた今村昌弘だが、今作ではさらに手強い題材をぶつけてきた。ゾンビは外から来る脅威だったが、予言は心の中で効いてくる不安だ。人間の心理を利用するという意味では、より深く、より厄介と言える。
誰かの死が予告されていて、それが避けられないかもしれないとしたら。
そんな状況で、あなたは何を信じる?
これは、見えない刃を巡るミステリだ。
運命に抗おうとするすべての人に、そっと刃先を向けてくる。
9.霊が語り、探偵が裏取りする世界で── 相沢沙呼『medium 霊媒探偵 城塚翡翠』
霊媒能力
この探偵、犯人の名前はもう知っている。
死者から聞いたからだ。
それはミステリとして成立するのか?と疑いたくなる。でもこの小説はその無茶な設定を真正面から受け止め、驚くほどエレガントに論理を立ち上げていく。
登場するのは、霊媒師・城塚翡翠と、推理作家・香月史郎。彼女は霊視で犯人の姿を知っている。でも、その「霊の証言」は証拠にならない。だから香月が、物的証拠や論理でそれを裏打ちしていく。
いわば逆算の探偵。答えありきの推理。でもその分、プロセスは抜群にスリリングだ。
霊媒と探偵、答えありきの逆算推理
トリックを暴くのではなく、霊視の中身を現実に引き寄せていくような不思議な感覚。事件そのものは重い。連続殺人犯がいて、被害者が増え、そして翡翠自身にも魔の手が迫っていく。
でも空気は重苦しくならない。翡翠の柔らかい語り口と、香月のクールな推理がバランスを取り合って、怖さと優しさが同居している。
ただしこの物語は、そこだけじゃ終わらない。ミステリの定番を知っているほど、足元をすくわれる。物語の構造そのものが、一種のトリックになっているのだ。読んでいる側は、まんまと仕掛けられることになる。気づいた時には遅い。すべての前提がひっくり返る瞬間が待っている。
それなのに、どこか読後感は柔らかい。仕掛けの精巧さと、人へのまなざしの優しさが、ぎりぎり共存している。だから、驚いても、笑っても、泣いてもいい。そういう器の大きさがある。
城塚翡翠はただの霊媒師じゃない。香月史郎もただの探偵役じゃない。二人の関係性も事件の真相も、「ミステリってこうでしょ」という思い込みを壊してくる。
いや、壊すというより、横から滑り込んでくる感じだ。あなたがルールだと思っていた枠の外側から、きれいな一手を打ってくる。
犯人がわかっている状態から始まるミステリは、思っているよりずっと深くて、ずっと静かに、心をざわつかせてくる。
10.探偵なんていらない世界で、あえて探偵であること── 斜線堂有紀『楽園とは探偵の不在なり』
ふたり以上殺した者は、天使によって地獄行き
人をふたり殺したら、即・地獄行き。
そんな不条理な法則を天使が地上に持ち込んでから、世界はガラリと変わった。連続殺人は絶滅し、犯罪率は激減……するかと思いきや、「一人まではOK」という妙な倫理が広まり、世の中は別の形で歪み始める。
そんな世界に生きる探偵、青岸焦は、天使信仰にどっぷり浸かった大富豪に招かれ、天使が集う孤島「常世島」へ向かう。孤島、奇妙な館、不穏な空気。どう考えても事件のにおいがする。
でもこの世界では連続殺人は起きないはず。二人目を殺した瞬間、犯人はあの翼の化け物に引きずられて終わるから。
なのに、起きてしまうのだ。連続殺人が。
犯人はどうやってルールを出し抜いたのか
誰かがこのルールを出し抜いた。
なら、考えるしかない。「どうやってやった?」と。
斜線堂有紀の『楽園とは探偵の不在なり』は、トリックと設定の化学反応が猛烈にスリリングな特殊設定ミステリだ。
世界のルールが「天使」という物理現象として成立している以上、そこに嘘はない。だとすれば、犯人はそのスキマを突いたか、天使をも騙したことになる。
この発想だけでもワクワクするが、本作の本当の魅力は、トリック以上に探偵の存在意義を考え直す姿勢にある。
なぜならこの世界は、犯人は基本的に自動で裁かれる。警察も裁判も、そして探偵さえも不要になった。それでもなお、青岸焦は探偵であることを選ぶ。その矛盾が作品の奥行きを広げていくのだ。
犯人は誰か、なぜ殺したのか、どうやって殺したのか。そのすべてに、もうひとつ別の謎が絡んでくる。
なぜ探偵はこの世界で真実を追うのか。
これはミステリを読むという行為自体を、そっと鏡に映してみせるような構造だ。でも決して小難しい話ではない。
青岸の飄々としたキャラ、クセの強い島の住人たち、そして読者に突きつけられる「あなたは何を信じる?」という挑発。すべてが絶妙なバランスで混ざり合って、ただの変わり種では終わらない深みを生んでいる。
探偵が不要とされた世界で、青岸は「だからこそ、探偵であるべきだ」と言う。
誰もが目をそらすなら、せめてひとりくらい、真っすぐ見ていなきゃダメだろ、と。
11.嘘こそが、この世界を救う武器になる── 城平京『虚構推理』
怪異・妖怪
探偵とは、本当のことを見抜く人のことだ。
でも、必ずしもそうとは限らないらしい。
城平京の『虚構推理』に登場するのは、真実を解き明かす探偵じゃない。「嘘」を武器に世界を救う、風変わりな少女・岩永琴子(いわなが ことこ)だ。
彼女は人間と怪異の間でバランスをとる知恵の神。11歳のときに怪異に誘拐され、片目と片足を代償に神職に就くという、とんでもない経歴を持っている。
でもそれよりもさらに驚くのは、琴子が一目惚れした相手、桜川九郎のほうだ。彼は妖怪の肉を食べて不死身になり、しかも複数の未来を試して最善の結果を選べるという、ある意味チートな存在だ。
必要なのは正しさではなく、納得させる物語
そんな二人が対峙するのが、鋼人七瀬。元アイドルの幽霊が都市伝説としてネットで拡散され、人々が信じるからこそ実体化するという、現代的すぎる怪物だ。
琴子が挑むのは、拳でも銃でも魔法でもない。ネット掲示板にいくつもの「もっともらしい嘘の推理」を投稿し、それを議論で磨き上げながら、鋼人七瀬を支える人々の信仰を崩していくという、かなり特殊な頭脳戦だ。
真実はどうでもいい。必要なのは、説得力のある嘘。
この作品の核はそこにある。
ミステリとは普通、誰が犯人で、どうやってやって、なぜそんなことを? と順番に解いていくものだ。でも『虚構推理』はその真逆を突っ走る。「本当のことを言ったって、信じてもらえなきゃ意味がないでしょ?」という、冷静すぎる視点から始まるのだ。
その視点のユニークさだけじゃなく、琴子と九郎の会話劇もまた絶品である。琴子の暴走気味な愛情表現と、九郎のクールすぎる塩対応。そこに漂う妙なテンポ感が、緊張感のある物語の中で思わず笑いを誘う。
この作品がやっているのは、いわば納得させるゲームだ。虚構を編み、世の中の認識を上書きし、怪異という現象そのものを消していく。論理と物語の力を信じる者にしか扱えない、ある種の知的格闘技である。
『虚構推理』は、ミステリであり、ファンタジーであり、ラブコメでもある。そのどれもが本気でぶつかってくるから面白い。
正しさよりも、納得が勝つ世界。
そんな世界で一番頼りになるのは、嘘を語れる頭脳だ。
12.夢で殺されれば、現実でも死ぬ── 小林泰三『アリス殺し』
夢と現実のリンク
アリスになった夢を見たことがありますか?
そう聞かれて「はい」と答える人は少ないと思う。
でも、栗栖川亜理にとってはそれが日常だった。
舞台は現代の日本。亜理はごく普通の大学院生。しかし夜見る夢の中では、「不思議の国のアリス」になっている。そしてその夢が、どうやらただの夢じゃなかったと気づくのに、そう時間はかからない。
夢の中で、ハンプティ・ダンプティが墜落死する。翌朝、現実の大学では博士研究員が屋上から転落して死んでいた。……この二つは、どう考えても繋がっている。
つまり夢の中で誰かが死ぬと、現実でもそのキャラクターに対応する人が死ぬ。
では、夢の中でアリスが死んだら、現実の亜理は?
ナンセンスの国で論理は通じるか
そこからが本番だ。アリスに殺人容疑がかかり、夢の世界では裁判が始まる。しかし相手はあの「不思議の国」の住人たち。
帽子屋、三月兎、チェシャ猫。まともな会話が通じる気配はない。でもそれでも、アリスは戦わなきゃならない。夢の中でも、現実でも。
『アリス殺し』は、ルイス・キャロルのナンセンスな世界を、ぎょっとするほど血なまぐさい殺人事件の舞台にしてしまった異色作だ。ふざけてるようでいて、構成はガチの本格ミステリ。どんなにめちゃくちゃな世界でも、事件は論理で解き明かされなきゃならない。そういう姿勢が、むしろ清々しい。
面白いのは、夢の中のアリス(=亜理)と、現実の亜理の捜査がリンクして進むところだ。夢の中で得たヒントを現実で照らし合わせたり、逆に現実の情報が夢の世界で意味を持ったり。この二重構造に、読んでいてつい引き込まれてしまう。
そして小林泰三の筆致は、さすがSF畑。可愛らしい童話をベースにしながらも、描かれる夢の世界はグロテスクで不気味。甘さのかけらもない。不条理なだけじゃなく、じわりと冷たくて、痛い。
アリスがかわいそう? いや、油断してはいけない。この物語のアリスは、ただ迷ってるだけじゃない。自分の命がかかってるからこそ、考えて、見抜いて、立ち向かう。その姿が、どこか凛としていてかっこいいのだ。
夢か現実か。あっちとこっちの境目が曖昧になる中で、ひとつだけ確かなのは、謎を解かなければ生き残れない、ということ。
可愛さゼロの不思議の国で繰り広げられる、命がけのロジック勝負。
扉の向こうで待っているのは、紅茶でもお茶会でもない。
とびきりシュールでスリリングな、悪夢のようなミステリだ。
13.やり直せる人生に、落とし穴はつきものだ── 乾くるみ『リピート』
時間遡行
主人公の毛利圭介のもとにかかってきた謎の電話。かけてきたのは風間という男で、「一時間後に地震が起こる」と予言してくる。しかもそれが的中する。
この男は、なんと現在の記憶を持ったまま過去に戻る「リピート」をやっているらしい。そして今度は、圭介を含む10人を選んだと言うのだ。
10ヶ月前の世界へ、今の記憶を持ったまま戻れる。そんな夢のようなチャンスに、圭介は迷いながらも乗っかってしまう。
が、当然そんなうまい話で終わるわけがない。
連鎖する死と、疑心のクローズドサークル
時間を巻き戻したあと、彼らの前に立ちはだかるのは、連鎖する死。リピートに参加した仲間たちが、一人、また一人と不審な死を遂げていく。
誰が殺しているのか? というか、そもそも殺人なのか?
舞台は現代日本。でも、物理的な密室じゃない。10人の「リピーター」たちだけが、世界の真相を共有している。この記憶の共有こそが、新しいタイプのクローズドサークルになっているのが面白い。
時間を巻き戻せたからといって、すべてが好転するわけじゃない。むしろ、失敗の記憶を持っているからこそ、執着や後悔、欲望が肥大化していく。人生をもう一度やり直せるなんて、最高の贈り物のはずだったのに。いつの間にか、それが罠になる。
誰が仕掛けた罠か? それとも、自分自身の欲望が仕掛け人なのか?
この物語の怖さは、そこにある。「誰が犯人か」だけではなくて、「この結末を招いたのは誰の選択だったのか」が突きつけられる。
真相が明らかになったとき、ゾッとするのはトリックの巧妙さだけじゃない。人間の欲深さと、自分勝手さと、そしてちょっとした甘さ。それが一つずつ積み上がっていって、取り返しのつかないことになる。
人生にリピートがあったとしても、それはきっと祝福じゃない。
むしろ、二度目のほうが苦いのだ。
14.同じ一日を繰り返しても、殺人は終わらない── 潮谷験『時空犯』
同じ1日を繰り返す
潮谷験の『時空犯』は、ただのタイムループものじゃない。科学と論理でガチガチに組み立てられた、まさに時間を使った密室みたいな作品だ。
私立探偵の姫崎智弘が引き受けたのは、北神伊織博士からの破格の依頼。曰く、2018年6月1日は、すでに千回近く繰り返されているらしい。しかもその日、博士は毎回殺されてしまう。
リセットされる世界。消える証拠。残るのは記憶だけ。これだけで状況としてはかなり詰んでいる。この話が面白いのは、ただ時間が巻き戻るんです、では済まないところだ。
タイムループは状況ではなく装置だ
ループを自覚するには、薬を服用する必要がある。誰にでも記憶が残るわけじゃない。これが絶妙に効いてくる。
記憶を持ったまま犯行を繰り返せる犯人。逆にそれを追うために、探偵たちは何度も同じ日に挑む。もう鬼ごっこというより知能戦だ。しかも舞台は閉鎖空間。
最初のルールさえ押さえてしまえば、そこからは緻密なパズルの応酬だ。誰がどこにいたか、どう動いたか、どこで何が起きたか。1回のループでは足りない。2回目も無理。3回、4回、それでもまだ届かない。しかし、確実に何かが見えてくる。そんな、反復の中に隠された変化こそがカギになっていく過程が熱いのだ。
ループものというのは、つい情緒に走りがちだが、『時空犯』はそこを極限まで抑えて、冷徹な観察とロジックで勝負してくる。その潔さがたまらない。なのにテンポは抜群。殺人が起こるたび、緊張は跳ね上がる。
これは、タイムループという設定を物語の調味料ではなく、トリックの根幹として本気で活かした珍しい一作だ。
時間は止まらない。でもこの一日は、何度でも繰り返される。
それでも犯人は、そこにいる。
そして、論理はすべてを暴き出す。
15.完璧なクラスに、殺意は調和していた── 浅倉秋成『教室が、ひとりになるまで』
能力を使える生徒たち
浅倉秋成『教室が、ひとりになるまで』は、理想的な空間が音もなく壊れていく音を描いた、異色の青春×能力×本格ミステリだ。
舞台は、みんな仲良しという噂で有名な高校のクラス。でもそこで、生徒が立て続けに命を絶つという異常事態が起こる。しかも遺書には、同じような不可解な言葉。
「私は教室で大きな声を出しすぎました。調律される必要があります」
音楽の話じゃない。これは、教室という空間そのものが奏でていた空気の歪みだ。
〈能力〉は凶器か、それとも呪いか
この異変に気づくのが、垣内友弘というどこにでもいる男子高校生。彼は、かつての幼馴染である白瀬美月から驚きの告白を受ける。
「三人とも自殺なんかじゃない。みんなあいつに殺されたの」
ただし、ナイフも毒も使われていない。使われたのは、〈人を自殺させる能力〉。そんなものがあるなら、どうやって止めればいいのか。そもそも誰が犯人なのか。その能力はどう働くのか。
この物語は、その「どうやって」を推理していく話だ。能力バトルでも超常ホラーでもなく、れっきとした論理の物語。与えられた能力は万能じゃない。必ずどこかに抜け穴がある。それを見つけ出して、証明不可能な殺しに論理で立ち向かう。
面白いのは、主人公自身もまた別の能力を持っているということだ。これがチートじゃなくて、逆に苦しみの種にもなるのが上手い。教室という名の密室、能力という見えない凶器、そして笑顔の裏に張り巡らされた圧力。そのすべてに一人で向き合わされる孤独が切ない。
この作品は、謎を解く物語であると同時に、理想を考え直す物語でもある。仲が良いことが正義になる空間。言い返せない空気。壊せない友情。そういうものに馴染めなかった人間が、どうなってしまうのか。
最後の最後まで、じりじりと心理を削るような展開。敵は犯人だけじゃない。空気ごとねじ伏せてくるあの教室自体が、最大の敵かもしれない。
誰も取り残さないクラスで、一人ずつ、ひっそり消えていく。
そのとき初めて気づくのだ。
ここには最初から誰もいなかった、と。
16.名探偵が、裁かれる日が来るなんて── 阿津川辰海『名探偵は嘘をつかない』
転生
探偵とは、何となく正義の味方だと思っていないだろうか。
犯人を見抜いて、真実を突きつけて、みんなの前でカッコよく勝利宣言。そんなお約束の中で生きてる存在だ。
でもこの小説では、そうはいかない。探偵が法廷に立たされて、お前は嘘をついたよな?と真正面から問い詰められる話だ。
『名探偵は嘘をつかない』の舞台は、探偵が制度として存在する世界。つまり名探偵は、警察の下にぶら下がる公的機関というわけだ。
中でも阿津川透は伝説の探偵。難事件を何件も解決してきたヒーロー……だったはずなのに、実は証拠をでっちあげてたんじゃないか?という疑惑が浮上。
当然ながら、世間は大騒ぎ。前代未聞の弾劾裁判が開廷される。
探偵は本当に正義なのか
裁かれる探偵、証言台に立つ元助手、再検証される過去の事件。これがもう、全部ミステリの名シーンを逆再生していくみたいでたまらない。名探偵が「自分の推理で勝手に犯人を決めたんじゃ?」なんて疑われる展開には、読んでる方も動揺が止まらない。
ただこの作品がすごいのは、裁判モノでありながら、きっちり本格しているとこだ。法廷劇のひとつひとつが、過去の密室殺人や不可能犯罪の謎解きになっていて、証言が出るたび「それってどういうこと?」と読み手も再推理に引きずり込まれる。探偵が論理で追い詰められるミステリなんてめったにない。
名探偵というは、真実のためならちょっとズルをしてもOKみたいな空気ある。 でもそれは、本当に許されることなのか。社会の秩序を守るためにウソをつくって、正義と呼べるのか。
読んでいるこっちも、自分の中にある探偵への甘さと本気で向き合わされる。
名探偵は、いつも真実を語る存在なのだと思っていた。
でもそれは、本当だろうか?
17.見えないからこそ、見えてくるものがある── 阿津川辰海『透明人間は密室に潜む』
透明人間
透明人間になんてなってしまったら、殺人において最強じゃないか、と思う。
しかし、ミステリ小説の世界では、むしろそれが最大の弱点になる。そんな逆転の発想でガツンとやられるのが、阿津川辰海の短編集『透明人間は密室に潜む』だ。
タイトルだけ見ると、なんだかSF寄りの奇想ミステリかな?と思うかもしれないが、これがめちゃくちゃ硬派なロジック勝負。
たしかに設定は派手だ。「透明人間病」なんて病気が認知された現代日本、というベースからして、だいぶ飛んでいる。でも、そこで展開されるのは、むしろ超現実的な推理の世界なのだ。
短編それぞれに光る、特殊設定の使い方
たとえば表題作の事件。殺人犯は透明人間。姿が見えないなら、犯行なんてやりたい放題かと思いきや……問題はそのあとだった。
殺したはいいが、現場から出られない。足音、ドアの開閉音、落ちた汗、空気のゆらぎ。見えないという状態には、実はとんでもない不自由が詰まっている。
この作品がすごいのは、そういう特殊設定の弱点を、むしろ事件の根幹に使ってしまうところだ。つまり、設定が味付けじゃない。トリックの根っこそのものに、設定が絡みついてる。
もちろん他の収録作も個性の宝庫。アイドルオタクだけで構成された裁判員裁判で、一体どんな有罪・無罪の判断が下るのかとか、異常な聴力を持つ探偵が耳だけで事件を解いてしまう話とか。読んでいるこっちはずっと「そんなのアリか」と膝を打ったり頭を抱えたりの連続だ。
なのに全部フェア。全部論理的。ちゃんと推理できる。阿津川辰海は特殊設定ミステリのマジシャンかよ!と唸る。とにかく構造の作り込みが丁寧で、変なギミックに頼らず、最終的には考えればちゃんとわかるところに着地させてくるのがほんとうに気持ちいい。
どれも短編ながら、一本一本の濃度が濃い。全体を通して伝わってくるのは、「バカみたいな設定こそ、真剣にロジックで解くのが一番おもしろい」という信念。ふざけた顔で、本気の推理。そんな作品ばかりだ。
そして、肝心の透明人間。
いちばん怖いのは、その存在が見えないことじゃない。
いるかもしれないと思わせてしまう、その不確かさこそが、人の目と心をかき乱していく。
ミステリというのは、やっぱり不自由な世界ほど燃える。
この本はそれを、最高にクールな形で証明してくれた。
18.言葉は銃よりも熱かった── 阿津川辰海『バーニング・ダンサー』
異能力警察
血が煮えたぎる。
文字どおりに。
阿津川辰海『バーニング・ダンサー』は、冒頭からとんでもない熱量で殴ってくる。何しろ、現場に転がっているのは「血液が沸騰して死んだ死体」と「踊りながら全身炭になった死体」だ。やりすぎにもほどがある。
犯人の正体を追う刑事・永嶺スバルは、過去の事件で心がボロボロになった男。彼が異動してきたのは、警視庁に新設された〈コトダマ犯罪調査課〉。名の通り、言葉を力に変える特殊能力者「コトダマ遣い」だけが集められた部署だ。
集められたはいいが、メンツがひどい。交通課から来た姉妹、田舎の駐在あがり、口数だけは多いオタク青年。もはや戦力になりそうなのがスバルしかいない。
異常死体が告げる、ルールの存在
ところがこの世界、ちゃんとルールがある。コトダマ能力は100種類と決まっていて、使うには厳密な条件が必要。つまり、現場に残った異常な死に様は、その能力を使った証拠でもある。
逆に言えば、どのコトダマが使われたかを特定できれば、使える人間も絞れるというわけ。論理的に犯人を追い詰めるミステリの王道が、異能バトルの世界でちゃんと成立しているのが面白すぎる。
そしてこのコトダマ捜査は、いわば能力の逆算だ。痕跡からスキルを割り出し、条件を洗い出し、容疑者の中から「使えるやつ」を炙る。やってることは地味に警察小説、だけど見た目は派手なエンタメ。しかもホワイトボードに情報貼っていく会議シーンまできっちり描かれていて、実はめっちゃ骨太。
そして何よりも圧巻なのは、やっぱり終盤の反転だ。全部わかったと思ったタイミングで、コトダマのルールが牙をむく。証拠もセリフもぜんぶ伏線だったとわかる瞬間、何度でも鳥肌が立つ。
派手で、熱くて、だけどちゃんと論理的で、本格派。
火がついたのは血だけじゃない。
こっちの脳も心も、燃やされっぱなしだ。
19.神様は、救ってくれるとは限らない── 麻耶雄嵩『さよなら神様』
神様が犯人を教えてくれる
麻耶雄嵩『さよなら神様』は、「神様」を名乗る中学生・鈴木君と、彼の隣にいる「僕」が出会う、いくつかの殺人事件を描いた連作短編集だ。だけどこれは、ただの学園ミステリでも倒叙ミステリでもない。
なぜなら、神様は事件が起きるたびにあっさりと犯人を教えてくれるのだ。「あいつが殺した」と。
これはすごく便利だ。しかし、すごく厄介でもある。犯人が最初からわかっているなら、探偵なんていらないじゃないかと、誰もが思う。でも現実はそんなに素直ではない。いくら真実でも、それが証明されなければ誰も信じてくれないし、法にも届かないからだ。
だから僕は、神様から与えられた答えに向かって、証拠と論理を逆算して組み立てていく。これは、ミステリが誇る演繹という技法を、限界まで純化した挑戦でもある。
答えはある。問題は、どう証明するか
しかもそこに立っている神様は、万能で冷酷で、寂しい。鈴木君は一貫して無表情で、どこか他人事のように真実を口にする。彼の視点から見れば、人の嘘も涙も、ただの情報に過ぎないのだろう。
読み進めていくと、ふと立ち止まりたくなる瞬間がある。神様が知っていることは、人間が知るべきことなのだろうか? たとえ正しくても、その真実は、人を救うのだろうか?
そこにあるのは、救済ではなくて、圧倒的な無慈悲。事件が終わっても、すっきりもしないし、晴れやかにもならない。むしろ、真相が明かされたことで、登場人物がより苦しくなっているようにすら見える。
でも不思議と、目が離せない。真実を突きつけるだけじゃ終わらないのが、麻耶雄嵩という作家のすごみだ。読む側も神様の言葉を翻訳する側に立たされて、何を信じ、何を許すのかを考えさせられることになる。
もしあなたの隣に神様がいたとして、あなたはその言葉を、ちゃんと人間の言葉に変換できるだろうか。
正しすぎる真実ほど、人を傷つける。
だから『さよなら神様』なんて、なんとも切ないタイトルがついているのだ。
20.首が飛ぶ村で、理性は通用するのか── 三津田信三『首無の如き祟るもの』
怪談・憑き物
首なし死体と聞いて、どこまで本気で怖がるかは人それぞれ。でもこの小説を読んだら、話は別になる。
戦後の奥多摩にある山村・媛首(ひめくび)村。もう地名からして怪しい。そして登場するのは、首の神様「淡首様」。首が祟る。首が飛ぶ。首がない。読んでるこっちの首まですくみそうになる。
物語の中心になるのは、村の旧家・秘守家で行われる婚舎の集い。跡継ぎとされる青年・長寿郎に、花嫁候補の女性たちが集まってくる──と、そこまではわりと平和な導入だが、あっという間に地獄のフタが開く。
密室で二人の死体。どちらも、首がない。
これが祟りなのか? いや、人間の仕業なのか? という話になる。
怪異と論理が殴り合う瞬間
本作の異常さは、ホラー描写を一切逃げに使わない点にある。つまり、どう見ても超常現象な現場を、ものすごくまっとうに、論理で解き明かしていこうとするのだ。
首のない死体が歩いたという証言まで飛び出すのに、それすら推理の盤面に乗せてくる。普通ならオカルトで処理される場面を、三津田信三は冷酷な構造の中に押し込む。怖いのに、ちゃんと考えさせられる。この両立がとにかく強い。
終盤、探偵・刀城言耶が登場する場面はほんのわずかだ。だが、その一撃で物語の地形が一気に変わる。
重なり合っていた怪談、因習、証言が、一斉に組み替えられる感覚は圧巻のひと言。しかも「合理で全部片づきました」とは言い切らない。その曖昧さが、かえって後を引く。
首が飛ぶのは物理的な意味だけじゃなく、読んでるこっちの理解力も何度か吹き飛ばされる。でも安心してほしい。ちゃんと最後には、理詰めで全部つながるようになっている。
しかもその過程で、人物の入れ替えやら密室トリックやら、古今東西の謎解き要素をぜいたくに盛り込んでくる。怖いけど、ものすごく楽しい。
三津田信三は「ホラーとミステリの融合」なんて簡単な言葉で済ませられない世界を作る作家だ。
この『首無の如き祟るもの』は、その真骨頂。
怖がりながら、推理して、また震えて、でも最後には拍手したくなる。
ぜひ、首を差し出す覚悟で読んでほしい。
首の皮一枚ぶん、濃い読書になるはずだ。
21.死なない竜が死んでいた── 上遠野浩平『殺竜事件』
竜・魔法が存在する世界
不死の竜が殺されていた。
そんなバカな、と思うが、現場にはちゃんと死体がある。しかも密室。しかも刺殺。魔法も科学も使いこなせる世界で、竜だけは絶対に死なないという常識を壊して、事件は始まる。
上遠野浩平の『殺竜事件』は、ハイ・ファンタジーと本格ミステリを無理やりじゃなく、正面から合体させてみせた怪作だ。タイトルはぶっきらぼうだけど、やってることはとんでもなく繊細である。
ファンタジー世界で論理を通すという執念
これはただの異世界ミステリじゃない。不死の存在を、どうやって、なぜ、誰が殺したのか。それをちゃんと論理で解き明かしていく。
魔法という名のなんでもアリをあらかじめ厳しくルール化して、その枠内で推理を成立させてるあたり、作り込みの執念がすごい。
主人公は戦地調停士ED(エド)。争いが起きた地域に派遣されて、ガチで戦って事態を沈めるようなプロフェッショナル。いわば武装探偵。このEDが一ヶ月という期限付きで、犯人捜しの旅に出る。時間制限あり、容疑者は各国に点在。舞台は複雑な魔法と技術が混ざる架空世界。
つまり、「タイムリミット×ロードムービー×密室殺人×不死身の犠牲者」という、ジャンルの全部乗せである。それなのにバランスが崩れないのは、上遠野浩平の筆がブレてないからだ。
世界観は大胆だが、ミステリ部分の構造はびっくりするほどまっとうで誠実。証言、アリバイ、矛盾、動機。きちんと積み上げて、最後は論理でちゃんと崩してくれる。
もちろん、『ブギーポップは笑わない』でおなじみのあの雰囲気も健在。投げやりなようでいて、底の底にはちゃんと哲学がある。人が人を殺すってどういうことか。不死とは何か。命の価値は、殺せるか殺せないかで決まるのか。そんなテーマが、いつの間にかこちらの背中をなでてくる。
ファンタジーだからって、曖昧にはしない。
竜だからって、無敵にはしない。
不死だからって、死なないとは限らない。
そんなねじれた前提に、きっちり筋を通してみせた『殺竜事件』は、派手さよりも構造の美しさで唸らせるタイプの作品だ。
本格ミステリはこんな形でも成立するのだと、この物語は証明した。
22.奇蹟の国で、推理は生き残れるか── 白井智之『名探偵のいけにえ 人民教会殺人事件』
信仰心
密室で人が死んだ。
その状況だけ聞けば、ミステリ好きは条件反射で「どんなトリックだろう」と身構える。
でもその密室が、信仰で物理法則がねじ曲がる村だったらどうだろう?
理屈なんて、そもそも通用しない。そこでは、失った手足が生え、死者すら蘇る。常識なんて、この村には荷が重い。
『名探偵のいけにえ』の舞台・ジョーデンタウンは、南米の奥地にぽっかり存在する信仰の楽園。だがその楽園のど真ん中で殺人が起きる。探偵・大塒(おおとや)は、行方不明の助手・りり子を探しにやってきたはずが、奇蹟信仰の狂騒に飲まれながらも、冷や汗まじりで推理を始める羽目になる。
常識を破壊する、信仰の物理法則
本作がとんでもなく面白いのは、探偵が解こうとする謎が一つじゃないことだ。犯人は誰か? どうやって殺したのか? ……それだけじゃない。この世界で推理は通じるのか?というところから戦わなければいけないのだ。
そして、放り込まれるのが三段階の解決編。信者向けの解決、信仰を逆手に取った解決、そして全てをぶった斬る現実的な解決。どれも成立していて、どれも切実にあり得るのが怖い。この構造自体が、「人は何を信じて、どう生きているのか?」なんてテーマをそのまま投げつけてくる。
そもそも、信じるとは何だろう。正しいことを語るより、相手が信じたくなる物語を提示するほうが、ずっと難しくて、ずっと現実的なのかもしれない。
探偵は、ただの論理マシンじゃない。信仰の海でおぼれそうな人に、意味のあるロープを手渡す存在なのだ。
信じるか信じないかは、読んだ人次第。
この小説は、ミステリの限界を試しにきている。
しかも全力で。
23.世界は何通りでも壊れるし、何度でも殺される── 白井智之『エレファントヘッド』
謎の薬「シスマ」
白井智之という作家はどこまでいくんだ、と読みながら何度も口に出したくなる。
『エレファントヘッド』は、そんなレベルのぶっ飛びを、全ページにわたって真正面からねじ込んでくる怪作中の怪作だ。
物語の始まりは意外なほど穏やかだ。精神科医・象山は、優しい妻と賢い娘に囲まれて、まあまあ幸福な日常を送っている。……にもかかわらず、冒頭から彼の目は冷めている。
家族なんて簡単に崩れる。
そのセリフが呪いのように残り、案の定、その崩壊は理不尽なほど突発的に、そして異常なかたちでやってくる。
自分が複数いる、という悪夢の論理
きっかけは、シスマと呼ばれる謎の薬。服用すれば、意識と存在が分裂し、複数の世界に同時に自分が存在する。
しかもその並行世界、別の時間軸で起きた死因が連鎖して、別の自分も同じように死ぬ。たとえ原因が違っても、結果が一致していれば死は等しく発動するのだ。
これを文字で読んでも「???」となるけれど、作中ではこの荒唐無稽な設定をちゃんと論理で捻じ伏せてくる。そこが白井智之という作家の凄みであり、狂気だ。
殺人事件の真相が一つじゃない。三つも四つも解決編がある。しかもどれも成立している。誰が殺したかも違えば、どう殺したかも違う。なのに全部が真実として成り立つ。これはもう、現実を土台にしたミステリじゃない。物語そのものが、論理で成立する迷路になっている。
登場人物たちは次々と不可解な方法で死んでいく。肉体が破裂したり、内臓をぶちまけたり、残酷なシーンが次から次へと襲ってくるが、それすらも論理的な整合性によって成立している。グロ描写が読みたいわけじゃない。でも、こんなにも仕方なく人が破裂する小説は他にない。
読者は終始、自分の脳みそが削られていく感覚と向き合うことになる。でもそれが快感に変わる。むしろ、快感以外の何物でもなくなってくる。
最終的に明かされる真相は、すごいを通り越してナンダコレと笑いながら崩れ落ちるしかない。
ミステリはこんなところまで行けるんだ。
そんな景色を見せてくれる。
頭を抱えて、でもページを捲る手は止まらない。
これが、白井智之という作家だ。
24.地獄の底でしか、謎は解けない── 白井智之『お前の彼女は二階で茹で死に』
奇病
というわけで、白井智之が続く。この人は特殊設定ミステリの神なので、仕方がない。
タイトルは『お前の彼女は二階で茹で死に』。
なんという言葉の暴力。どこからどう見てもギャグかホラーか、と思いきや、中身はめちゃくちゃ本格的なミステリだ。そして容赦がない。読んでいるうちに、こちらの倫理観も揺さぶられて、なんだかどんどん壊れていく。
物語の主役は、復讐に取り憑かれた刑事・ヒコボシ。彼の妹・リチウムは謎の奇病にかかり、心身ともに追い詰められて命を絶った。
ヒコボシはその元凶たちに合法的に報復するため、猟奇殺人の捜査をしながら裏でこっそり復讐リストを更新している。
奇病が雰囲気ではなく、事件の核になる世界
そしてもう一人の主人公、監禁されている天才女子高生探偵・マホマホ。……倫理観が行方不明になるのも納得だ。
この二人のコンビが、まったくもって普通じゃない。推理ドラマにありがちな刑事と天才探偵のコンビなのだが、今回は刑事が悪人で、探偵が監禁された少女という倒錯ぶり。にもかかわらず、事件解決のプロセスは超まっとう。グロ描写は満載なのに、トリックはきちんと緻密。これが白井智之の真骨頂だ。
さらに面白いのが、世界観の異常性がちゃんとミステリに組み込まれているところだ。舞台は、体がミミズ状に変形する病が蔓延する、いかにも白井ワールドな奇病社会。
しかもその病気はただのホラー設定じゃなくて、事件の構造や犯行動機、トリックにまでがっつり関係してくる。設定がただの雰囲気じゃなく、ちゃんと謎の一部になってるのがすごい。
もちろんブラックユーモアも健在。登場人物の名前は「ヒコボシ」「オリヒメ」。地名は「辺戸辺戸(べとべと)村」。ふざけているようで、笑っていいのか不安になる。でも笑ってしまう。だけどすぐに次のページで誰かの体が変な形に裂けたりする。……やっぱり白井智之はどうかしている。
倫理観は引き裂かれ、胃袋はねじれ、頭はフル回転。
とにかく何か強烈なものが読みたいというときに、この一冊は容赦なく脳を殴ってくれる。
ぐちゃぐちゃで美しい地獄、ここに開幕。
25.嘘のない世界で、最も不誠実な謎を解け── 白井智之『東京結合人間』
嘘をつけない人間
あらすじを読んだだけで一歩引きたくなる人も多いと思う。
でも、引かないで読んだ人だけが見られる景色が、この本にはある。
白井智之『東京結合人間』。タイトルからしてすでに不穏だが、内容はもっとヤバい。なのに、面白い。とてつもなく。
舞台は、男女が物理的に結合して子孫を残す社会。そしてオネストマンという、絶対に嘘をつけない人間が、時々生まれる。
主人公・圷は、そのオネストマン。リアリティショーの出演依頼を受け、孤島に向かうが、クルーが失踪。残された7人のオネストマンのうち、誰かが島の親子を惨殺する。
しかし全員「自分じゃない」と言い張る。いや、言い張るというか、本当に嘘をつけないから、ウソじゃない。
じゃあ、どういうことだ?
嘘が言えないこと自体が最大のトリック
この「嘘がつけない容疑者しかいない」という設定が、本作最大のトリックであり、魅力でもある。
でもこれは、ただの言葉遊びじゃない。物語が進むにつれ、身体構造、感染症、進化、社会構造、果ては昆虫の生態までが、事件の論理を支えるピースとしてぴったりはまっていく。
しかも、前半では東京のアンダーグラウンドで暴れる不良少年たちの物語が展開される。いきなり別の話?と思いきや、後半の島パートですべてが繋がる。忘れていたエピソードが、事件の核心に関わってくる展開がアツい。
読む側も試される。ジャンルの切り替えについていけるか。ルールを見抜けるか。そしてなにより、白井智之の狂気と知性に向き合えるか。めちゃくちゃグロいし、めちゃくちゃロジカルなんて最高だ。
クレイジーな設定と、純度100%の本格ミステリ。その両立がどれだけ難しいか、考えたことあるだろうか?
白井智之は、それを当然のようにやってのける。読み終わったあと、人間はここまで論理的に変態になれるのかと思わされること請け合いだ。
奇想が好きな人、騙されたい人、論理がすべてだと思ってる人。
この本は、そんなあなたの脳を殴りにくる。
でも、悪い気はしない。むしろ、最高に快感だ。
26.世界の終わりに、なぜかミステリが始まる── 荒木あかね『此の世の果ての殺人』
小惑星の衝突
あと三ヶ月で地球が終わる。小惑星テロスが衝突して、全部なくなる。政府も崩壊、警察も機能停止、世の中は崩れていく一方だ。
そんな最中、福岡の教習所に通い続ける23歳の小春。なぜって? 免許が欲しいから。それだけ。
そんな小春が、ある日教習車のトランクから死体を見つける。まるでホラー映画のオープニングみたいな展開だ。でもこの物語は、そこから始まる。元刑事の教官・イサガワと、地球最後の事件に挑むはめになるのだ。
終わりの風景に、推理だけが灯り続ける
世界が終わるとき、人はなぜ人を殺すのか?
この設定は派手なようでいて、めちゃくちゃ丁寧だ。人が狂乱して走り回ったりしない。コンビニはまだ開いているし、車は動いている。だけど、どこか空気が薄い。会話にも、景色にも、人の目つきにも終わりの匂いが染みついている。
本作の真ん中にあるのは、「誰がやったか」ではなく「なぜやったか」というホワイダニットだ。金のためでもなければ、未来のためでもない。明日があるかもわからない世界で、人を殺す意味ってなんなんだろう。そこに挑むのが、この物語の核心だ。
小春とイサガワのコンビもいい。人との距離感がうまくつかめない小春と、どこか破れかぶれで正義感だけは持ってるイサガワ。この二人のやりとりは、乾いた終末世界に少しだけぬくもりを灯してくれる。冗談みたいな掛け合いをしてても、その裏にはずっと時間がないという緊張が流れている。
街は人が消え、看板は剥がれ、テレビも終わった。でも、推理だけはちゃんとある。この状況でまだ真実を追いかける人がいる。その姿勢が、逆に救いに見えてくるのだ。
なによりこの作品、地球最後の殺人事件に、ちゃんと論理と意味を与えているのがすごい。ドラマのためのミステリじゃない。ちゃんと推理として成立していて、読み終えたときに「確かにそうするしかなかった」と納得させられる。
荒木あかねのデビュー作でありながら、この面白さ。受賞も納得。
世界が終わる日、人は何をするのか。
この物語は、その答えのひとつかもしれない。
27.青春頭脳ゲームの最前線── 青崎有吾『地雷グリコ』
特殊な頭脳ゲーム
飄々として掴み所のない女子高生が、頭脳と観察力でエゲツない心理戦を制していく。それだけで、すでにワクワクするじゃないか。
青崎有吾の『地雷グリコ』は、校内のくだらなくて最高にアツいゲームたちを舞台に、論理と思考の限界ギリギリを突き詰めていく青春頭脳バトルだ。
主人公の射守矢真兎(いもりや・まと)は、なんとなく癒し系っぽい見た目だが、ひとたび勝負ごとに巻き込まれると、とんでもない牙を剥く。しかも本人はまったく勝負好きじゃないのが、またいい。
平穏無事を愛する彼女が、なぜか学校の生徒会や強敵たちと、グリコだの坊主めくりだの、変なルール付きの遊びで命懸けの知恵比べをする羽目になるのだから。
日常の遊びが、一瞬で戦場になる
たとえば、表題の『地雷グリコ』。ジャンケンに勝った手数だけ階段を進める、あの懐かしの「グーは3歩、チョキは6歩、パーは6歩」という遊びだ。そこに「相手が地雷に設定した段に乗ったら即失格」というルールが加わる。
それだけでグリコが超おもしろい戦略ゲーになってしまう。心理戦×論理戦×確率論の三重苦のなか、真兎が仕掛ける読み合いは、もはやボードゲーム界隈でバズるレベルだ。
しかもこれが、ただのルール遊びで終わらない。真兎の凄さは、相手の表情や視線、性格や癖を手がかりに、次に何を仕掛けてくるかを見抜いていくところにある。目の前の盤面だけじゃなく、相手の脳内まで読み取って、そのうえで打ち返す。こっちの考えを先読みして、さらにその裏をかく。こんなの将棋のタイトル戦じゃないか。
しかも、扱っているゲームが全て日常の延長線というところが絶妙だ。坊主めくり、神経衰弱、カルタ。誰でも知ってるルールに、少しルールを加えるだけで、ここまでスリリングでハイレベルな戦いになってしまう。
しかも、命はかかってないのに、こっちの緊張感は完全にデスゲームと同等。ある意味、命がかかってない分、心理戦に集中できてめちゃくちゃ怖い。
何よりこの作品の真の魅力は、すべてのルールが「フェア」であることだ。隠された情報やズルい裏技なんて一切ない。勝つために必要なのは、ただ観察すること、考えること、信じること。そのプロセスが、見事なくらい読みやすく、なのに超濃密に描かれているから、頭がフル回転しっぱなしだ。
この物語は誰も死なないし、世界も救われない。でも、知性で勝つことの気持ちよさは、どんなバトルよりも熱い。
日常に仕込まれた地雷原を、笑顔で走り抜ける射守矢真兎の姿は、本当にカッコよすぎる。
28.死んだら、推理が冴えた気がした── 五条紀夫『クローズドサスペンスヘブン』
全員死亡済み
目が覚めたら天国だった。しかも南国リゾート風で、空は抜けるように青くて、海はどこまでも透明。
……ただし、自分は首を切られて死んでいる。
五条紀夫『クローズドサスペンスヘブン』は、登場人物全員がすでに殺されているという突飛すぎる設定から始まる。舞台は死後の世界。西洋館と浜辺しかない空間に集められたのは、自分がどう死んだかを覚えていない5人の男女。
彼らは新聞で毎日1ミリずつ明かされていく生前の事件の情報を手がかりに、自分が誰に殺されたのかを解明していく。全員が被害者、なのに誰かが犯人。
死後世界のルールはフェアプレイ
冷静に考えると絶望的な状況だ。けれど不思議とそうはならない。本作の最大の魅力は、むしろその軽やかさにある。死んでいるのに、全体のムードはどこか陽気。わからないことがあったら、まずは浜辺で水着姿のままミーティング。
疑心暗鬼に陥ってもおかしくないのに、なぜか空気はユルく、少しズレた掛け合いに思わずクスッとさせられる。死者たちがのびのびしてるのが、逆に不気味ですらある。
それでも物語の骨格は、しっかりと本格ミステリだ。毎日届く新聞が情報源として機能し、断片から真相を導くプロセスが読者にも開かれている。つまり、ちゃんと一緒に推理できるのだ。
そして、願った物が出てくる納屋や、死後世界ならではのルールも、ふわっとしたファンタジーに見えて、後半には驚くほど精密な論理の部品として組み込まれてくる。このあたりの設計力は本当にうまいと思う。
キャラもいい。誰もがどこか抜けていて、でもその人なりの悲しみや孤独を抱えている。記憶がないからこそ生まれるやさしさもあるし、それが犯人を推理する過程で、少しずつ揺らいでいく。その小さな感情のうねりが、謎解きのドキドキとは別の切なさを連れてくる。
死んだらすべて終わり──なんて、意外とそうでもないらしい。むしろ、わからなかったことがようやく見えてくることだってある。
生きている間はうまく話せなかった相手と、死後にもう一度だけ言葉を交わせるなら。
そんな天国に、心から拍手を送りたい。
29.メロスは、走る。だが事件も、走る── 五条紀夫『殺人事件に巻き込まれて走っている場合ではないメロス』
物語のパロディ
「メロスは激怒した。必ず、かの邪智暴虐の王を除かなければならぬと決意した」
……はずだった。
でも、花婿の父が羊小屋で刺されていたら話は別だ。走っている場合じゃない。
五条紀夫『殺人事件に巻き込まれて走っている場合ではないメロス』は、あの国民的文学『走れメロス』を土台に、怒涛の本格ミステリを上乗せした、奇跡のような一冊だ。
ギリシャ風世界にそびえ立つのは、格調高い文語調のセリフと、緻密に設計された密室トリック。
そしてそれを駆け抜けるのが、脳筋系熱血男・メロスである。筋肉の張りで風を裂きながら、事件の真相もきっちり割っていく。
ふざけているようで、トリックは骨太
この作品のスゴさは、めちゃくちゃふざけているのに、めちゃくちゃロジカルなところだ。登場人物の名前はイモートア(妹啊)とかギフス(義父ス)とか、読みながらつい噴き出してしまうレベルでユルい。
でもその一方で、仕込まれたトリックはガチの本格派だ。密室殺人、不可能犯罪、アリバイ崩し……そのどれもが、しっかり論理で解けるように組まれている。
そして何より、メロスがいい。怒る。走る。泣く。止まる。推理する。だが、決してぶれない。正義という軸だけを信じて、どんな状況でも突っ込んでいく彼の姿は、ギャグっぽく見えて、実はかなり真っすぐでカッコいい。事件を解決してまた走り出す背中が、なぜだか胸に迫る。
原作を読んだことがあってもなくても楽しめる。むしろ、読んだことがあれば「そんな使い方する!?」と二重に笑えるし、読んだことがなければ、これをきっかけに太宰治に手を伸ばしたくなるかもしれない。
ミステリと文学、笑いと緊張、古典と現代の、奇跡的なドッキングがここにある。
メロスは走る。事件も走る。そして、物語は加速する。
走れ、メロス。
まだまだ、推理は終わらない。
30.何度死んでも、謎は終わらない── 南海遊『永劫館超連続殺人事件』
時が巻き戻る館
タイムループものは山ほどあるが、死ぬと巻き戻るのが魔女の呪いという時点で、これはただのSFじゃないとわかる。
舞台は古びた大屋敷、登場人物は貴族、使用人、探偵に魔女。大正ロマン風のクラシックな装いに、サスペンスとファンタジーと本格ミステリをギュッと詰め込んで、まるで年代物の時計みたいに美しく狂っている。
「魔女が死ぬと、その目を見ていた人間も道連れで一日前に戻される」
これがこの物語のルールだ。しかも、その魔女はなぜか死ぬたびに生き返る。普通ならホラーだが、この世界では理屈で処理されている。
ループがただのご都合展開じゃない。何度も繰り返される殺人は、毎回違う手口で、毎回別の可能性を見せてくれるのだ。
毎回ちがう殺人、毎回ちがう可能性
主人公ヒースクリフは、過去の出来事を少しずつ積み重ねながら、殺人と呪いのルールを解き明かしていく。どこか演劇じみた館の空気と、何度も死を繰り返す魔女の存在が、現実の理屈と幻想の境目をぼやかしてくる。
しかしその曖昧さの中でも、物語の芯にあるのは徹底した論理だ。すべての謎には条件があり、トリックにはルールがある。
しかもこの話、犯人側もループの知識を使ってくる。「タイムリープ殺人犯」という言葉だけで、脳がわくわくする。探偵だけが過去を知ってるなんて甘い設定は許されない。犯人も強い。だからこそ、真相に辿り着くまでの過程が面白い。
誰が嘘をついていて、誰が最初から知っていたのか。最後のループで、「あのセリフ」の意味が反転する瞬間は鳥肌が立つ。
古風で優雅な舞台なのに、物語は冷酷なまでに再起動を繰り返す。謎が解けるまで、終わることを許さない。何度殺されても、何度だって立ち上がる。これは「何かを正しく理解するには、何度も間違えるしかない」という話でもあるのかもしれない。
終わりが決して一度きりじゃないなら、真実もまた一つじゃない。
でも、すべてのルートを辿ったその先にあるたった一つの解が、驚くほど鮮やかに浮かび上がる。
だからこの作品は何度でも騙されたいし、何度でも読み返したくなる。
31.おまえ、ほんとうにおまえか?── 南海遊『パンドラブレイン 亜魂島殺人(格)事件』
人格移植
そこは、海にぽっかり浮かぶ忘れられた島。潮風と鉄の匂いが混ざり合う廃墟。かつて人の中身を別の人間に上書きするという、おぞましい技術が研究されていた場所。
その名は「パンドラブレイン」。そして舞台は、かつて史上最悪の密室殺人鬼〈O〉と、名探偵・霧悠冬真が激突した、あの島、亜魂島(あこんとう)である。
南海遊『パンドラブレイン 亜魂島殺人(格)事件』は、ミステリとSFと青春の全部盛りな作品だ。しかもそれらをチャンポンにするどころか、互いの魅力を底上げしながら絶妙に組み合わせてくる。うっかりしていると、人格すら何層にもズレてしまう。
アリバイも動機も、すべてが「誰だったか」で揺らぐ
物語は、大学のミステリ研究会の面々が亜魂島を訪れたところから始まる。曰くつきの連続殺人事件を現地で追体験するつもりだったが、まさか自分たちが新たな事件の登場人物にされるとは思っていなかっただろう。
島には死体がある。しかも密室で、首を斬られた無惨な姿。再来か? 〈O〉がまた姿を現したのか? それとも別の誰かが、新たな人格をまとって現れたのか?
この物語のキモは、「この人は誰か?」ではなく、「この人の中身は誰か?」という一点にある。見た目も声も記憶も、本当にその人のものか?肉体と魂の結びつきが切り離された世界では、アリバイも動機も、全部が信用ならなくなる。
探偵役は、ミステリ研究会の若者たち。青春の青臭さと好奇心に突き動かされながら、彼らは現実と過去の境界をかき回していく。過去にこの島で何があったのか。そして今、自分たちに何が起きているのか。
登場人物が入れ替わっているかもしれない。
それだけで、あらゆる推理はゼロから見直しになる。どのセリフが誰のものか、どの嘘が本当か。すべてが疑わしく、だからこそ面白い。
この本には、読者の認識をグラグラ揺さぶる仕掛けが山ほど詰まっている。しかし、その揺らぎの中でも論理の筋は一本まっすぐ通っていて、気づいたときには膝を打つしかない。
顔を見ればわかる、なんて時代はもう終わった。
名前を呼んでも、それは誰かの仮面かもしれない。
じゃあ、いったい誰が、誰を、どうやって殺した?
この作品はそんな根本的な謎に、SFとミステリの融合という特異なかたちで挑んでくる。
32.幽霊と少女の、不可能から始まる謎解き── 方丈貴恵『少女には向かない完全犯罪』
幽霊との協力
探偵が幽霊で、助手が小学生。この組み合わせを聞いて、思わず首をかしげたくなる人もいるかもしれない。でも、だからこそこの物語は、驚くほど新鮮で切実で、そしてロジカルなのだ。
黒羽烏由宇は、「完全犯罪請負人」を名乗る男だった。しかしある日、何者かにビルから突き落とされ、気がつけば幽霊に。7日後には消えてしまうという制約つきの存在になってしまう。
そしてそんな彼の姿を唯一見ることができるのが、両親を惨殺された少女・音葉。彼女はあまりにも無力で、あまりにも強い。このバディの誕生だけで、もう物語の半分は成功している気がする。
推理のあとに、もう一度推理が始まる
とはいえ、この作品が本当にすごいのは推理の部分だ。幽霊になった黒羽は、物に触れない。証拠は動かせないし、誰にも声は届かない。
だからこそ、彼の武器は観察と論理だけ。動くのは音葉、考えるのは黒羽。その連携プレイに思わず唸るほど、巧みに物語が展開されていく。
登場する事件も手が込んでいる。例えば、天井に足跡が残された密室殺人なんて明らかに現実離れしているのに、そのトリックは思いがけずシンプルな理屈で解き明かされる。
しかも一度解けたと思ったら、次の章でそれがまるごとひっくり返される。さらにもう一度、より深く、より残酷に。「どんでん返しからのどんでん返し」なんてよくある表現だが、この作品の場合は、それが論理の上できっちり成立しているのがすごい。
そしてこの物語、推理だけでは終わらない。黒羽も音葉も、最初はただの「利用する者」と「される者」だった。でも捜査を重ねるうちに、いつしか彼らの間には確かな絆が生まれてくる。
自分では手を汚せない幽霊と、大人に信じてもらえない少女。二人とも世界から見捨てられたような存在だ。でもだからこそ、彼らはお互いを必要とし、誰よりも信じる。
読み終えたとき、ただ一つ言いたくなる。
このコンビの活躍をまた見たい、と。
ありえないはずのタッグが、どんな大人よりも真っ直ぐに、真実を暴いていく。
そんな清々しさと哀しさが、この小さな名探偵譚には詰まっている。
33.過去と未来、本格とSF、その狭間で── 方丈貴恵『時空旅行者の砂時計』
タイムトラベル
時間は過去に流れない。それが当たり前のルールだ。でも、この物語はそのルールごとひっくり返してくる。
瀕死の妻を救うため、タイムトラベルで1960年の山奥へ飛ぶ男。たどり着いたのは、嵐に閉ざされた山荘、謎の連続殺人、そして土砂崩れで全滅する運命の一族。
加茂が与えられた時間は、ほんの四日間。しかもその先にあるのは、誰がいつ死ぬかすでに分かっているという絶望的なゴールだ。
タイムトラベルというと、どうしてもSF感が強くなりがちだが、この小説は違う。それはもう、限りなくクラシカルな本格ミステリだ。山荘、家系図、因習、見立て殺人、クローズドサークル……お約束のフルコースをど真ん中で出してくる潔さ。
しかしその背後にあるのは、「未来から来た男による過去への逆襲」というドラマチックなねじれだ。
情報は最大の武器であり、時に呪いにもなる
何よりすごいのは、タイムトラベルがただの舞台装置じゃないことだ。ちゃんとルールがある。知っている未来に抗うのは、情報戦でしかない。そしてその情報の中には、これから死ぬ人たちの名前とタイミングまで含まれている。
加茂は誰が犯人かを暴く前に、「どうすればこの悲劇を防げるのか」を考え続ける。犯人と向き合うというより、運命と戦ってるような感覚がある。
だからといって観念的な話に傾くこともなく、謎解きはきっちり緻密だ。誰がどこにいたか、何を知っていたか、どうやって犯行が可能だったのか? 頭をフル回転させたくなる場面が連続してくる。そう、これは感動の物語でもあるけれど、やっぱりガチのミステリなのだ。
そして最後にたどり着く真相は、少しずつ積み上げられたピースがぴたりとはまり、重力のように心に落ちてくる。
未来を変えるというのは、簡単な話じゃない。
だけど、それでも何かが変わったと信じたくなる。そんな物語だ。
34.死が消えた街で起きた殺人── 森博嗣『女王の百年密室』
「死」という概念の消失
未来の都市、ルナティック・シティには、100年間誰も死んでいない。冷凍保存による長い眠りが存在する世界では、「死」とは単なる状態であって、終わりではないらしい。
そんな場所で殺人事件が起きた。だが、事件を捜査しようとする主人公ミチルに、周囲の人々はこう返す。
「だから何?」
ルナティック・シティは、いろんな意味で常識が通じない。誰かが殺されたって、大騒ぎになるわけでもない。悲しむわけでも、怒るわけでもなく、みんな日常をそのまま続けている。
技術が「死」を奪ったとき、人は何を失うのか
そもそもこの都市の住民たちは、殺人の意味そのものがピンときていない。というか、「それって眠らせただけでしょ?」という感じである。そう、ここの人たちにとって死とは一時停止にすぎないのだ。
そんな空気の中で、ミチルはひとりだけ21世紀の常識を引きずりながら事件を追いかけていく。その姿が、もうすでに浮いている。でも、それでも追わずにはいられない。
なぜなら、誰かが明らかにこの街のルールを壊したからだ。物理的な密室ではない。常識という名の密室に守られた犯罪を、どうやって突き崩すかが本作の見せ場である。
しかもただのミステリじゃない。アンドロイド、超技術、社会システム、宗教、死生観、倫理観……とにかく盛りだくさん。それでいて、ちゃんと全部が一本の線で繋がっているのがすごい。殺人事件を軸に、文明そのものの前提を疑うような感覚が、ズバッと突き刺さってくる。
ミステリだが、謎解きだけじゃ終わらない。というか、この本の中でいちばん不思議なのは、「人が死なない世界では、人はどうやって生きるのか」ということだ。事件の真相以上に、そこにこそこの物語の核心があるような気がしてくる。
ミチルが立ち向かうのは、目に見えるトリックじゃない。
「世界そのものが狂っているとき、何が事件と呼べるのか?」という壮大な違和感。
それを丁寧にほどいていく過程が、この小説のいちばんのスリルだ。
35.時間が壊れる音がした── 北山猛邦『「クロック城」殺人事件』
過去・現在・未来を示す時計
巨大な時計が三つ。しかもそれぞれ、過去・現在・未来を刻んでいるというのだから、もうこの時点で何かがおかしい。
そんな時計が壁に埋め込まれた「クロック城」で起きるのは、ただの殺人ではなく、世界の終わりを目前にした、壮大な論理崩壊ギリギリの本格ミステリだ。
まず舞台がすごい。首のない死体が礼拝堂に出現し、眠っていた女性の枕元には生首が並び、誰も行き来できないはずの部屋から人が消える。どう考えても超常現象に片足突っ込んでいるが、そうじゃない。ぜんぶ、筋が通っている。
というか、通ってないように見せかけて、バチバチに通っている。なんというか、騙されて悔しいのではなく「やられた!」と拍手したくなるタイプのやつだ。
圧倒的スケールと、指先のような繊細さ
この作品のすごさは、トリックのデカさと繊細さの同居にある。巨大な物理トリックがドカンと用意されている一方で、語り手のちょっとしたクセとか、文章のリズムの中に細かく仕掛けられた叙述の罠が効いてくる。
いわゆる「読者への挑戦状」ではないが、挑まれてるのは確かだ。目に見えるものと、そこからこぼれていくもの。その両方をすくい上げないと、城の謎にはたどり着けない。
そして、何よりもロマンがある。この作品は、物理と論理のパズルとして完璧なだけじゃない。ゴシックな空間に、古めかしい雰囲気、でもなぜか未来の香りが漂っていて、ずっと不穏。
終末の夜に、崩れていく世界を背景に、歯車の一つひとつがかみ合っていく感覚。なのに、どこか優雅で、冷たくて、きれいだ。
時計の針が三方向に狂っている城。
その中で、ただ一つ確かなものがあるとしたら、それは物語の芯を貫く巨大な理屈だろう。
どれだけ幻想に包まれていようが、最後に残るのは、ちゃんと意味のある答え。
なんかそういうのって、かっこいいと思うのだ。
36.「はい」か「いいえ」か、それがすべて── 井上悠宇『不実在探偵の推理』
存在しない探偵
質問に「はい」か「いいえ」でしか答えない探偵なんてやっていけるのか、と思う。しかし、この作品はやっていけるどころか、バッキバキに事件を解決していくから困る。
井上悠宇『不実在探偵の推理』は、そんな喋らない探偵と、推理を推理する大学生・菊理現(くくりうつつ)の話だ。
探偵は現にしか見えず、喋らず、ただ特殊なダイスで返事をする。出る目は「はい」「いいえ」「わからない」の三択。つまりこの物語の謎解きは、事件を解決するための質問そのものが、最大の謎ということになる。
この形式がめちゃくちゃ面白い。いわばこれは、〈ウミガメのスープ〉を本格ミステリの土俵に引っ張り込んだようなもの。探偵が真相をすでに知っていて、それをどう質問で引き出すかが肝だ。
質問そのものが謎になる
推理のプロセスは、犯人を暴くものじゃない。正しい問いを選び続けること。そこがもう完全にゲーム的で、脳みその回路がカチカチ言い出すレベルで楽しい。
しかもこの探偵、何者かよくわからない。見えるのは現だけ、喋らない、でも推理は完璧。そもそも答えって信じていいのか?……と、物語の裏でずっと不穏な影がちらついているのも面白い。事件の構図だけでなく、推理のシステムそのものを疑わせるメタ構造になっているから、油断していると足元をすくわれる。
しかもキャラ同士の関係性も絶妙で、現と叔父の刑事コンビの掛け合いがなんとも軽妙だ。冷静だけど人間くさい刑事と、論理の迷路に飛び込んでいく学生とのバランスが良くて、ミステリにありがちな探偵の独壇場にならないのもいい。
とにかく、会話がないのに推理劇として成立してることが、まず凄い。いや、成立してるどころかめちゃくちゃ燃える。これだけ制限のある条件で、ここまで論理的に畳み掛けてくる作品はなかなかない。
言葉がないからこそ、すべてが謎になる。だからこそ、答えが光る。
探偵は何も語らない。
ただ真実だけが、転がるダイスの目から滲み出てくる。
37.その15秒で、何をする?── 榊林 銘『あと十五秒で死ぬ』
タイムリミット
「あと十五秒で死ぬ」と言われて、何を思い浮かべるだろう。
遺書を書く? 誰かに電話する? それとも、ただ絶望する?
でもこの小説に出てくる人たちは違う。
彼らは、その15秒をとことん使い倒す。
榊林銘『あと十五秒で死ぬ』は、アイデア一本勝負かと思いきや、どの話もちゃんと理詰めで迫ってくる、骨太の変化球ミステリ短編集だ。
奇抜な設定でも、核にあるのは論理
表題作『十五秒』はまさにタイトル通り、銃弾を受けて崩れ落ちた薬剤師が、死神に与えられた「最後の十五秒」で犯人を割り出し、反撃の一手を打つ。動けない、しゃべれない、残り時間はわずか。
それでもロジックで真実を引き寄せる姿がアツい。スローモーションの中で繰り広げられる推理劇は、時間が止まっているからこその緊張感があって、息が詰まる。
そこからは、同じ「十五秒」というモチーフを軸にしながら、がらっと世界観が変わる。『このあと衝撃の結末が』は、犯人当てドラマの最終回、目を離していたラスト十五秒で登場人物が急死した謎を解くという、メディアと記憶のトリックが光る一編。
『不眠症』では、交通事故の瞬間を十五秒ずつ繰り返す夢に囚われた少女の切ないドラマが描かれる。ジャンルも文体もバラバラなのに、どの話も制限時間と論理が核にあってブレない。
そして、とどめが『首が取れても死なない僕らの首無殺人事件』。もうタイトルからしてヤバいのに、内容も想像以上。十五秒間だけ生きていられる首を、リレー形式で交換しながら生き延びるという、あり得ないけど理にかなった設定。
そんな島で殺人事件が起こる。死んでないのに殺されている、というパラドックスを成立させた上で、ちゃんと推理ミステリとして成立させてくるあたり、正直ずるい。
そしてどの話もただの変わり種じゃなく、きっちりロジックで組み上げられているのがすごい。ミステリとしての信頼感があるから、どれだけ奇抜な設定でも最後までついていけるし、オチの決まり方も鮮やかだ。
たった十五秒で世界がひっくり返る。そんな瞬間を4回も味わえるなんて他にない。まさに才能の目覚まし時計が鳴ったデビュー作だ。
グロさもギャグもロジックも、全部高濃度で詰まっている。
死ぬ15秒前まで推理してやろう、という執念が全編にみなぎっている。
この1冊というか、この作家の存在自体が事件だ。
38.その村は優しすぎて、どこかおかしい── 彩藤アザミ『正しい世界の壊しかた:最果ての果ての殺人』
謎の村
茨の垣根の向こうには、どんな景色が広がっているのか。そんな疑問を抱くまでもなく、「出てはならない」と言われたら、誰もが従うのがこの村だった。
未明もまた、その優しい檻の中で穏やかな日々を送っていた。でもある日、掟を破って外から来た瀕死の少年を村に入れたことで、すべてが音を立てて崩れはじめる。
村を導いていた指導者が何者かに殺され、共同体は一気に猜疑の嵐に包まれる。誰が犯人なのか。なぜこんなことが起きたのか。そして、この〈世界〉とは何なのか。
異物がもたらした、共同体の崩壊
物語の導入は、いわゆる古典的なクローズド・サークル。外界と隔絶された村で連続殺人が起きるという王道ミステリだ。
牧歌的な日常にひとつずつ亀裂が入り、登場人物たちの表情がゆっくりと変わっていく。その過程がじつに丁寧で、まるでビーズを一粒ずつ通していくような手触りのある構成になっている。
密室やアリバイトリックが売りではない。でも推理する愉しさはしっかりあるし、何より人物たちの行動と感情がロジックとして成立しているから、読んでいて気持ちがいい。犯人探しというより、なぜこの殺人が起きたのかという背景の深堀りが、読む手を止めさせない。
この作品がすごいのは、どこかファンタジーにも見える物語が、終盤に向かっていきなりディストピア的な色彩を帯びてくる点だ。その転調がまったく無理なく、むしろ「そうとしか思えなかった」と腑に落ちるよう仕掛けられている。
伏線の回収に関しても、最後に一気に爆発するタイプじゃなく、読み返すことで「あれがそうだったのか!」と何度も感心させられるつくりだ。
物語の終盤で明かされる事実は、犯人の名前なんかではなく、この世界そのものの正体だ。その瞬間、これまで読んできた優しい村は一気に意味を変える。ただの殺人事件ではなかった。共同体の仕組みそのものが歪んでいた。未明が助けた異物ともいうべき少年は、その閉じられた世界に風穴を開ける存在だった。
「正しい世界を壊す」とはどういうことなのか。それは、幸福に見えた共同体の嘘を暴くことなのか。それとも、嘘の上に成り立つ優しさを否定することなのか。
この物語は、そういう重たいテーマをきっちりエンタメの器に落とし込んでいる。
優しくて、残酷で、理不尽で、美しい。
そんな物語に出会いたいなら、この作品は刺さる。
39.夢か現実か、それが問題じゃない── 結城真一郎『プロジェクト・インソムニア』
夢を他人と共有できる世界
殺人は禁止、でも人は死ぬ。
そんな矛盾が成立してしまうのが、結城真一郎『プロジェクト・インソムニア』だ。
設定だけ聞くとサイコホラーかディストピアSFのように見えるかもしれない。でもこれはもちろん、正真正銘の本格ミステリだ。しかも、かなりガチめのやつである。
舞台は、他人と夢を共有できる装置が実用化された近未来。ユメトピアと呼ばれるその夢世界では、自分の願望を〈クリエイト〉という能力で具現化できる。でも、そこで殺人事件が起きてしまう。
いや、そもそもこの世界では「殺人はシステム上できない」という話だったはずでは? しかも、夢で死んだはずの人間が、なぜか現実でも心筋梗塞で死んでいる。一体どういうことだ。
殺人禁止の世界で、人はなぜ死ぬのか
つまりこの話、ざっくり言うと「ルールのある世界で、ルールを守ったまま人が死んでいる。そのトリックを解明せよ」ということだ。
これはもう、探偵側がやることは一つで、ユメトピアという夢の世界のルールブックをひっくり返して、その隙間を突く仕様バグを見つけること。ガジェットがSF寄りでも、やってることはめちゃくちゃクラシカルなロジックバトルなのがアツい。
しかもこのミステリは、ただ論理的に冴えてるだけじゃない。夢と現実の境界線がどんどん曖昧になっていく中で、「自分の見ているものは本当に現実か?」という感覚まで押しつけてくる。このグラグラする感じは、映画『インセプション』とか『パプリカ』が好きなら、問答無用でハマると思う。
終盤には例のやられた系のカタルシスも、もちろんある。ミステリ的に「まさかそんな解釈があったか!」という逆転が入ってきて、最後はスカッと納得。
つまりこの作品、どこを取ってもブレがない。甘っちょろい話じゃなくて、夢というルール付き空間を、どこまでもロジカルに攻め倒す。おすすめしたくなるのも当然だ。
夢の中の殺人事件。でもご安心を。
すべてはルールの中で、論理が解決してくれる。
夢で死ぬのが怖くても、謎を追うのはやめられない。
40.推理は、バグらない── 紺野 天龍『ソードアート・オンライン オルタナティブ ミステリ・ラビリンス 迷宮館の殺人 』
VRゲーム《ソードアート・オンライン》の世界
ゲームの中で死ねば、現実でも死ぬ。そんな世界を知っているだろうか。
あの《ソードアート・オンライン》事件の影で、もうひとつ語られていなかった連続殺人があった。そう、誰にも知られず、迷宮入りしたままの事件が。
紺野天龍『ソードアート・オンライン オルタナティブ ミステリ・ラビリンス 迷宮館の殺人』は、その埋もれた記録を掘り起こす、反則級に面白い異色ミステリだ。
物語は、SAO事件の影で誰にも知られず迷宮入りになったという、連続殺人事件の手記から始まる。舞台は《迷宮館》と呼ばれるダンジョン。
ただのゲーム空間かと思いきや、そこは死んだら現実でも死ぬ、最悪すぎるルールが適用された地獄の舞台だった。
スキルとログが、密室とアリバイに変わる世界
そんな手記を拾ったのが、後継ゲーム《アルヴヘイム・オンライン》で探偵業を営むスピカと「俺」。彼らはその謎を解き明かすべく、再現された迷宮館に足を踏み入れる。
つまり、過去のデスゲーム内殺人を、現代の探偵が追体験する構図だ。探偵と読者が揃って記録の迷路に飛び込む、完全インタラクティブ型のミステリ体験になっている。
そして本作最大のポイントは、舞台がゲームだからといって、ご都合主義には一切ならないことだ。むしろその逆。トリックも動機も、すべてはゲームの仕様とルールの中で、ガチガチに構築されている。
ログは嘘をつかない。でも、どこを見るかで意味は変わる。密室はスキルの範囲で作られるし、アリバイはシステムの穴を突く。現実世界ではあり得ない条件が、逆にこのミステリにだけ許された論理の物差しとして機能している。
さらに面白いのは、構造そのものが二重三重に仕組まれていることだ。プレイヤー目線の事件、手記の中の過去事件、そしてそれを読み解く現在の探偵たち。
この事件の地層を掘っていくうちに、「じゃあそもそもこの手記は本当に信用できるのか?」という超根本的な疑問が湧いてくる。そこから先は、探偵だけでなく読者自身の認識が試される展開が待っている。
SAOの世界観を活かしつつ、ここまで厳密でフェアで、なおかつトリックとして美しい物語をやってのけたのは、まさに快挙。
ログはすべてを記録している。
ただし、その意味に気づけるかどうかは、探偵の腕次第だ。
おわりに 論理で世界をねじ伏せるという快感

イラスト:四季しおり
今回ご紹介した40作品は、特殊設定ミステリがどこまで進化したのか、その到達点をしっかり見せてくれた傑作だ。
奇抜な舞台設定に見えて、やっていることはめちゃくちゃストイック。だからこそ、ロジックで押し切る姿勢がかっこいいのだ。
ここでご紹介した作家さんたちは、SFっぽい設定やファンタジー的な世界観を、単なるギミックとしてではなく、フェアな論理ゲームの土台として見事に使いこなしている。世界観を作り、それに合わせてルールを定め、その中で推理を成立させる。
これはつまり、ミステリ黄金期の精神を、現代的な文脈でちゃんとアップデートしているということじゃないか。
もはや古典的な密室やアリバイものでは満足できなくなった今、新しい謎の形を見せてくれるこのジャンルは、本格ミステリの次なる主役といってもいい。
そして何より、ここには「良質なパズルに挑みたい」という欲望が詰まっている。
世界をひっくり返してでもロジックで解く、そんな作家さんたちがいる限り、ミステリはまだまだ面白くなっていくはずだ。