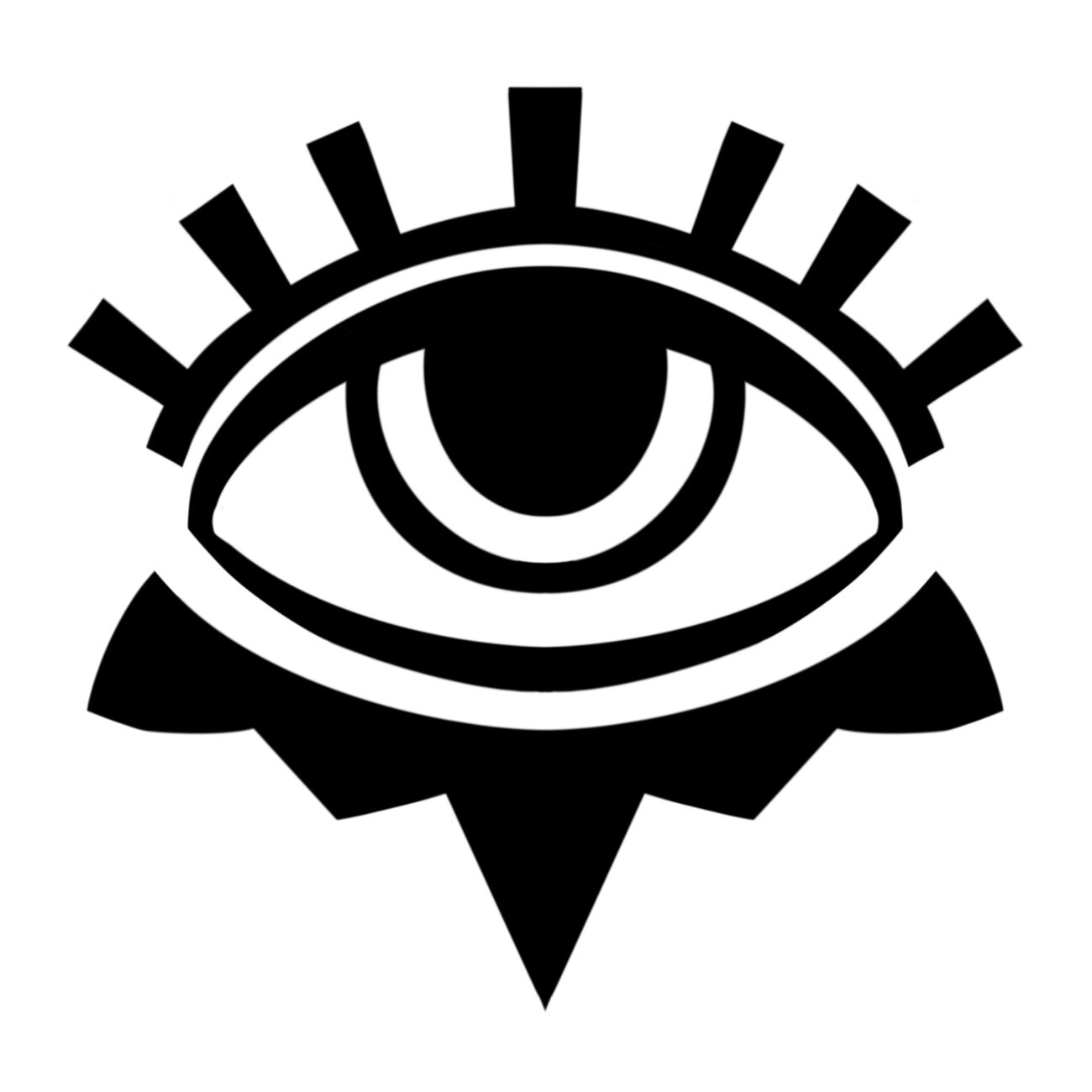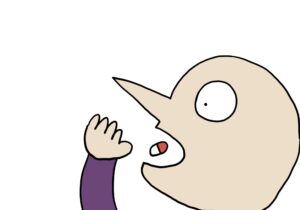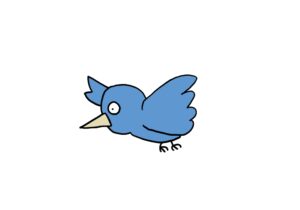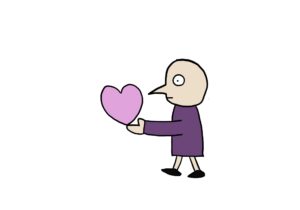N博士はこの一ヶ月で一躍世界の億万長者の仲間入りを果たした。
長年研究してきた透明人間になれる薬を遂に商品化し販売したところ、爆発的なヒットと相成ったのである。
実のところ、この薬は軍隊にだけ提供するという考えもあったのだが、日本出身の生粋の平和主義者である博士はそうしなかった。
彼はまたフランス人の母を持つ生粋の平等主義者でもあったので、誰一人として別け隔てなく薬を提供したいと考えた。
価格は一般的な薬と比べれば保険も効かず高めではあったが、彼は一般市場で販売することを決めた。これが功を奏したのである。
売上好調であるというのは良いことなのだがしかし、製造は自分ひとりで行なっているため、ここ一ヶ月博士は外出できないどころかテレビも見れない忙しさだった。
届くまで時間がかかるので遠いところから先に発送しており、この街の人々に提供できたのはごく最近のことだ。
特許はもちろん取得済みだが、助手を雇えばそこからこの薬の製造方法は外に漏れ出しうる。
博士はアメリカ人の祖父を持つやはり生粋の民主主義者であり、協力者によってこの薬が世界中に広まることは歓迎している。
それでも自分が人生をかけて取り組んできた研究の成果が、簡単に他人のものになってしまうのは悔しかった。
そういうわけで彼は助手一人雇わず黙々と薬を作り続けている。
忙しい彼の食事はもっぱらデリバリーである。今日は木曜日であるから大好物のピザを夕食用に取り寄せている。
博士は薬を型にはめて押し抜く作業を繰り返しながら今か今かと玄関のベルが鳴るのを待っていた。
「ごめんください。ホットピザのDです。ご注文のピザをお届けに上がりました」
「ちょっと待ってくれ。今仕事にかかり切りでね」
博士は自分が待ち設けていたのを知られぬよう、身だしなみを整え、ゆっくりと三分も待たせてから玄関のドアを開けた。彼は見えっ張りなのだ。
配達員のDはドアを開けるなり色紙を博士に突きつけた。
「ボク、アナタのファンなんです!」
博士は自分にもファンが付くまでになったかと誇らしい思いで色紙にサインを書いてやる。
出身地の文化を尊重して筆で書くのが彼流である。Dは目を輝かせた。
「ありがとうございます!宝物にします」
驚いたことにDはそれだけ言って帰ろうとした。博士は慌てて彼を引き止め「ピザはどうしたのかね」と問う。
もちろん控えめに、余裕のある笑みを浮かべて。Dは一瞬考えてハッと目を丸めた。
「ああ! そうでした。すみません。つい舞い上がってしまって。なんと言っても今時の人であるN博士とこうして話すことが出来ているものですから。透明薬、すごい評判ですね」
「やはりそうかね」
博士は鼻高々である。
「はい、もちろんですよ。だって透明人間になれる薬ですよ。みんなの夢ですよ。テレビの取材とかも来てましたよね?」
「まあそうだね。今は忙しくて取材のほとんどは断っているがね。なんと言ってもワタシの目標は求めている人々に出来るだけ早くこの薬を届けることだから。顔を売るのはどうだっていいのさ」
博士は澄まして言った。将来ノーベル賞を受賞した時に金の亡者や自己承認欲求の高い男と言われたくはなかったからだ。
彼はアインシュタインのように生粋の研究者として歴史に名を残したかった。
「さすがN博士です。やっぱり憧れちゃうなあ。実はボクも一錠注文して昨日やっと届いたんですよ。博士と会えた記念にこれから飲んで家に帰ろうと思っています」
Dは博士にピザを渡すとニコリとして錠剤を飲み込んだ。みるみるうちに彼は透明になっていく。自分の偉業を目の当たりにして博士は再び誇りを感じた。
「ばっちり透明になっているよ。ご利用ありがとう。……そうだ、ピザの代金を払わないとね」
そう言って博士が手探りでDに代金を渡し家の中に引っ込もうとした。
すると「そういえば」と彼は急に何かを思い出したらしく、ガッとドアに何かを挟んだ。透明でよくわからないが、おそらく足だろう。
博士が眉をひそめ「なんだい」と聞くとDはそれまでと打って変わったおどおどした調子で弁解を始めた。
箱の中身が注文したシーフードピザではないという弁解であった。
「申し訳ないです。どうしてなのか仕入先から材料が届かなくて。でも、ボクどうしてもN博士に会いたくて電話で本当のこと言えませんでした。ごめんなさい」
「ふむ。残念ではあるがそういうことなら仕方あるまい。こういうことは時々あるのかね」
「いえ、ボクは初めてです。どうやら輸入先の国で暴動が起こった、とかいうことなのだそうですが、ボク、ここのところバイトしかしてないのでよくわからないんですよ」
その後Dは何度も頭を下げて帰っていった。彼が持ってきたソーセージピザは美味しかったが、やはり木曜日はシーフードピザに限ると博士は少し不満げだった。
その日の夜、ようやく仕事が落ち着いた博士は久しぶりにスナックにでも行こうかと考えた。
研究に集中するため完全防音装備を施した室内では外の音が聞こえてくることもないし、このところ会うのはDのような配達員ばかりだったので、そろそろきちんと腰を落ち着けて人と話したかったのである。
そこで思い浮かんだのがスナックのママだったのだ。
彼は三日ぶりのシャワーを浴び、綺麗めの白衣を取り出して身につけた。
ここでも研究者らしいところを見せたかったのだ。白衣にシワなく清潔感があることを確かめると、彼は鏡の前で口ひげを整え外に出た。
外は悲惨な状況になっていた。
まず目に入ってきたのは道路の真ん中で血を流して倒れているDの姿だった。博士は慌てて駆け寄ったものの、彼はとっくに息絶えていた。
頭を強く打ったのが死因らしい。膝や肘があらぬ方向に曲がっているところを見ると、走ってきた車にかなりのスピードで突き飛ばされたようだ。
周りを見ると至るところで火と煙が上がっていた。人々の悲鳴や怒声も聞こえてくる。博士は狼狽えた。一体何が起こっているのだ。
暴動。博士はDの言っていたことを思い出した。急いで携帯を取り出してニュースを見ようと電源を入れる。なかなか立ち上がらないことに彼は苛立った。
「これはこれは博士じゃありませんか。ワタシ探してたんですよ」
聞き覚えのある声に顔を上げてみるとそれはスナックのママだった。博士は一瞬ホッとした直後、ゾッとして体を震わせた。
彼女の顔は涙でぐちゃぐちゃになった化粧で化け物じみており、右手には果物ナイフを持っていたのだ。
博士は声も出ずただ彼女を見つめる。ママは引きつった笑いを浮かべながら右腕を振りかぶった。
「ごめんなさいね、博士。これも世界のためなんです。あの薬のせいで交通事故に遭った夫やテロで死んだ多くの人たちのためなんです。さようなら博士」
それを聞いた博士は、ワタシはどうやらアインシュタインと同じ過ちを犯したらしいと思った。
自分の作った薬がせめて核兵器ほどの被害を人類にもたらさないことを祈り、彼はママの絶叫を聞きながらそっと目を閉じた。
(了)