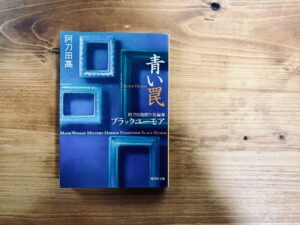読書人生を長く歩いていると、時折「これは特別な宝物だ」と思える本に出会うことがある。
私にとって、それが『ほしのはじまり ――決定版 星新一ショートショート――』だ。
星新一のショートショートは、たしかに文庫で読めるし、図書館にも全集が並んでいる。けれど、この一冊に詰まっているのは単なる再録ではない。
1001編以上の中から、たった54編。選び抜かれ、配置され、語られ、包まれている。
その編集を担ったのが新井素子。星新一に見出されてデビューしたSF作家だ。
しかも、ただ好きな作品を並べただけじゃない。時代を越えて、ジャンルを越えて、星新一という作家を決定版として読ませるための、最良の星座を再構築したのだ。
そう、『ほしのはじまり ――決定版 星新一ショートショート――』(角川書店/2007年刊)は、ショートショートという形式を確立した巨星・星新一の世界を、編集という魔法でまるごと凝縮した奇跡の一冊である。
そしてその錬金術を担ったのが、SF作家・新井素子だというのがまたたまらない。
全作品三回通読から始まった、選書という名のSF
今回、私が、そんな星さんのアンソロジーを編ませていただくことになりました。
大変光栄だし、精一杯気張って、作品選定をしたつもりです。
しかもこの本、厚いし高いよね。
ですので。
新井素子が編むアンソロジーということで、勿論、私が好きな作品を中心に選んだのですが、それだけではなく。これだけ厚くてこれだけ高いんだから。
ある意味、「網羅!」を目指してみました。
代表作と言われるものはいれて、色々な傾向の星さんの作品もできるだけ一作はいれて、読者から見て異色に思われるだろう星作品もいれてみました。(たとえば、えーと、『セキストラ』。これ、星さん御自身はあんまり気にいっていなかったらしいのですが、なんせデビュー作だし、「網羅」っていうなら、外す訳にはいきませんよね。)
『ほしのはじまり』11ページより引用
まず忘れてはならないのが、このアンソロジーを編んだのが新井素子という一点である。
そう、あの口語文体で青春SFを語り、90年代以降は幻想と日常の境界を揺らがせてきた、あの新井素子。彼女が、星新一に見出されてデビューした作家として、没後10年という節目に挑んだのがこの編集企画なのだ。
その情熱のほどは、「星新一の全作品を三回通読した」というエピソードに凝縮されている。1001編を3回。つまり3000回。
しかも読んだだけでは終わらない。彼女は次のような編集プロセスを踏んでいる。
まず「大好きな作品」を抜き出す(これは比較的楽)。
次に「これはさすがに無理」という作品を省く(ここもまあOK)。
最大の地獄が、「好きだけど他にも似た作品がある」ゾーン。
そして当然ながら「絶対に外せない名作」も押さえる。
冷静と情熱、記憶と再読、好みと公平性。これらを同時に成立させるには、単なるファン心だけでは足りない。編者としての使命感と構成センス、そして作家としての目が必要なのだ。
しかも600ページという物理的制約まである。これはもう、ほとんど職人芸の領域である。
テーマ別に読み解く、小宇宙としての54編

収録された54編は、ジャンルの多様性はもちろん、配置の妙も見逃せない。
新井素子が全体構成まで含めて緻密に計算したことが伝わってくる。ここではいくつかの軸で、その選定意図を考えてみよう。
1. 王道にして必修。SFの金字塔たち
まず真っ先に目に入るのが『ボッコちゃん』『おーい でてこーい』『午後の恐竜』といった、星新一の代名詞的作品群。いわば「基本の星」である。
『ボッコちゃん』では、アンドロイドを相手に妄想する男たちの哀れさと皮肉が炸裂。
『おーい でてこーい』は、人類の無責任さと環境破壊の寓話として、今も強烈に刺さる。
『午後の恐竜』に至っては、終末SFなのにこんなに穏やかで幻想的な作品があるのか、と心がざわつく。
これらの作品が導入に据えられていることで、初めて星新一に触れる読者も安心してこの宇宙に飛び込める。まさに「入り口」として完璧な配置である。
2. システム社会と官僚制の風刺
星新一といえば、管理社会を皮肉る天才でもあった。『おみそれ社会』『盗賊会社』『第一部第一課長』などのラインナップは、現代のテクノロジー社会が孕む不条理を、半世紀以上前から予言していたことを証明している。
それでいて、ユーモアがあるから読後感は軽やか。だが、ふとしたときにずしんと来る。この軽くて重い感じこそ星新一らしい。
3. 実存と死、そしてユーモア
『死体ばんざい』や『流行の鞄』なんかは、もうブラックユーモアの極致。死をここまで乾いたまなざしで扱えるのは、星新一ならではだ。
泣き笑いというより、もはや哲学的エンタメの域。笑いながら、「生とは? 死とは?」と考え込んでしまう不思議な時間が流れる。
4. 改変された民話・現代の寓話
『みつけたもの』『ねむりウサギ』などは、ファンタジー系の異色作。ここに新井素子のセンスが出ている。
星新一といえば冷たい未来を描く作家という印象もあるが、こうした童話のような温度感の作品もまた、魅力の一つだ。
しかもそれが1、2作にとどまらず、構成全体に絶妙なバランスで配置されているあたりに、選者の呼吸が感じられる。
『星くずのかご』と自作年譜の衝撃
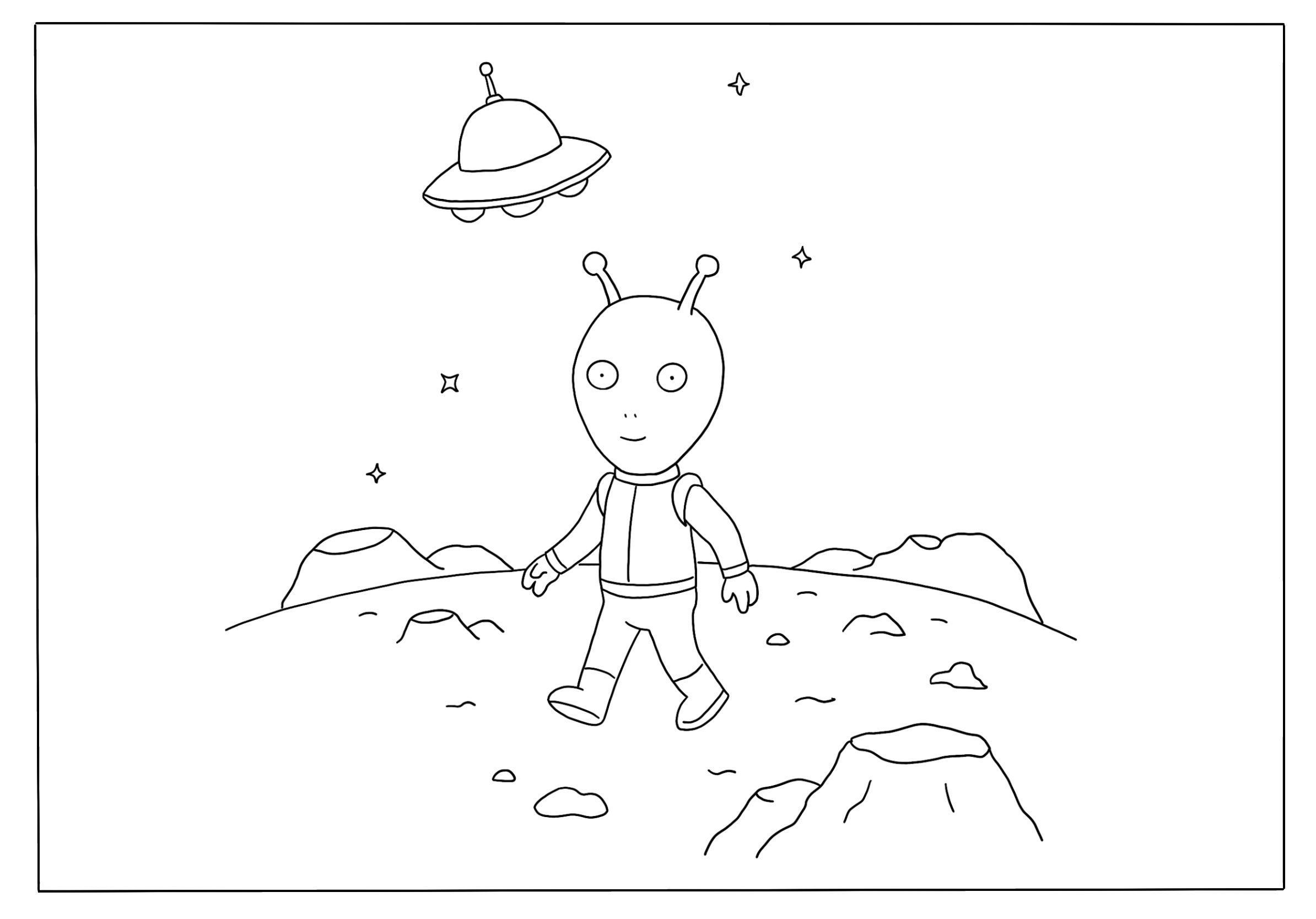
この本が決定版とされる理由のもう一つが、巻末のエッセイ集『星くずのかご』と自作年譜の存在である。ここがまたすごい。
まず『星くずのかご』。これはもともと全集の月報に連載されたもので、普通に生きてたら読む機会がない〈幻の文章〉だ。しかも、ここでは星新一が自分の創作姿勢、生活、ちょっとしたぼやきまで語っていて、作品以上に人となりが見えてくる。
例えば、「自分はSF作家と思っていない」といった発言や、創作に対する職人的姿勢などは、星作品の無機質なトーンの裏にある、深い人間的な迷いを教えてくれる。短編に込めた想像力だけでなく、その裏にある孤独、観察眼、倫理観までもがにじみ出てくるのだ。
そして極めつけは、自作年譜。これは編者や研究者が作った「年表」ではなく、星新一自身が48歳までの自分の人生を振り返った「自己観察記録」だ。
そこには、父・星一との関係、製薬会社の経営失敗、作家としての葛藤など、人生の節々が赤裸々に記されている。読み物としても味わい深く、資料としても超一級品。まさに星新一の裏面を読み解く鍵である。
過去と未来をつなぐアンソロジー
刊行からすでに17年。にもかかわらず『ほしのはじまり』は、いまだに重版され、読まれ続けている。その理由を2つにまとめよう。
入口として完璧すぎる構成
星新一を初めて読む人には、代表作がしっかり網羅されている。そして、昔読んでいたけどしばらく遠ざかっていた層には、愛情こもった編集が刺さる。
つまり、「はじめまして」にも「おかえり」にも効くという、最強のアンソロジーなのだ。
21世紀にも通じる予言性
星新一が描いた未来は、笑えないくらい現実化している。それを、「昔の作品って意外と当たってるよね」で済ませず、「それでもやっぱり面白い」と思わせるのは、構造と語りの妙があるからこそ。
冷たくて温かい。突き放してるのに、どこか人間くさい。そんな語りの温度が、いまの時代にも響いているのだ。
そして新井素子は、それらを「今読むべきもの」として並べ直してみせた。まさに編集の勝利である。
星の海図は、今も輝いている

星新一の作品は、無数の「もしも」を詰め込んだショートショートの宇宙だ。
その宇宙に再突入するための最良の船。それが『ほしのはじまり』である。
54編という数の制約があるにもかかわらず、この一冊には「星新一という作家のすべて」が入っているように思える。
しかも、ただの名作集じゃない。エッセイや年譜を通じて、人間・星新一の息遣いまで感じられる。そういう意味で、この本はアンソロジーというより、星新一というジャンルの再構築プロジェクトと呼ぶべきだろう。
ミステリ好き、SF好き、ショートショート愛好者……どんな入り口からでもいい。
この本を読んだ人はきっと、星新一という名前を過去の作家とは思わなくなる。
それはまさに、星の始まりなのだ。