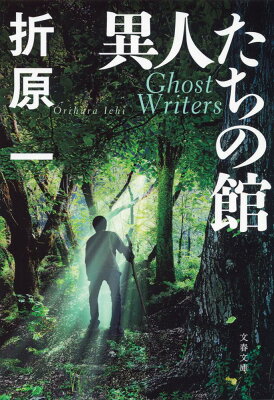叙述トリックの魔術師。
折原一(おりはら いち)を語るとき、この呼び名を避けて通ることはできない。
でも、ただの「意外な結末がすごい人」で終わらせるには、あまりにももったいない。あの人の本当の怖さは、読者の頭の中そのものをひっくり返す、物語づくりの仕掛け屋としてのセンスにある。
物語の外から見ているつもりだったのに、いつの間にか作者の仕掛けた罠の真ん中に立たされている。そんな作家だ。
折原ワールドの武器は、もちろん叙述トリックにある。でもやり方は一種類じゃない。日記や新聞記事、インタビュー記録なんかを混ぜて、真実をわざと断片化する多重文体。作中に小説家を登場させて、物語を書くこと自体を謎にしてしまうメタミステリ。
そして何より、人間の狂気や執着をガツンと描く心理サスペンス。この暗くて不穏な空気が、ただのトリック勝負のミステリとは一線を画している。
折原一のトリックは、単なるドッキリではない。狂気や自己崩壊、現実の揺らぎみたいなテーマを掘るために、必然として仕掛けられているのだ。
読み終わったときに残るのは爽快感より、自分の思い込みが音を立てて崩れていくあの感覚。
この記事では、そんな折原ワールドを味わえるおすすめの10作品をネタバレなしでご紹介したい。
1.伝記を書け?じゃあ、まずは地獄を覗こうか── 『異人たちの館』
売れない作家・島崎のもとに届いたのは、妙に重たい依頼だった。青木ヶ原の樹海で失踪した青年・淳の伝記を、ゴーストライターとして書けという。依頼主は、広大な屋敷に暮らす富豪の母親だ。
広すぎる屋敷、山のような日記と原稿、そしてやけに口をつぐむ関係者たち……。どう考えても一筋縄じゃいかない匂いがぷんぷんする。
言われるまま資料に目を通し、関係者への取材を重ねる島崎だが、調べれば調べるほど、淳は理想の天才像から遠ざかっていく。わがまま、自己愛、トラブルの種。そして必ずそばに現れる異人と呼ばれる謎の存在。
これが何者なのかは誰もはっきり語らないが、その不気味さだけはやたら際立つ。
600ページの助走、その先に待つ最後の一撃
本作の面白さは、なんと言っても折原一という魔術師が仕掛けた、意地悪で精緻な「多重文体」の罠にある。
島崎の視点、淳の自分語り、第三者の淡々とした文章、インタビュー、正体不明の独白……バラバラの断片が次々と差し込まれ、どれも信用しきれない。まるで寄せ集めのピースで完成図が見えないパズルをやらされている気分になる。
しかも、伝記を書く作業そのものがミステリの捜査になっている。新しい証言や資料が出るたびに、組み立てた像は補強されたり崩れたり。いつの間にか「淳に何が起きたか」ではなく、「淳とは何者なのか」に焦点がすり替わっていく。
終盤、異人はただの人物から、ほとんど怪談めいた象徴へと変貌する。屋敷の迷路のような構造と絡み合って、こちらの足元まで不安定にしてくる。
600ページの長旅も、最後の爆弾を炸裂させるための助走だったとわかる瞬間がたまらない。気づけば、島崎と一緒にこの館の奥深くへ迷い込み、出口を見失っている。
結局、誰が嘘をついていて、何が真実だったのか。
最後の一撃を食らったあと、あなたは本当にこの館から抜け出せているだろうか。
 四季しおり
四季しおり折原一自身も、文庫版のあとがきでこの作品を「マイベスト」と評している。
「あなたのマイベストは何ですか?」と聞かれることがたまにある。そういう時、私は決まって『異人たちの館』と答えている。
この作品を書いたのは、四十代前半のもっとも気力充実していた頃であり、その時点における自分の持っているすべてをぶちこんでいるので、個人的には読者に自信を持ってお勧めできるのである。『異人たちの館』P.601 文春文庫版あとがき より引用
2.創作の狂気は輪舞のように── 『倒錯のロンド』
原稿を失くした日から、山本安雄の人生は派手に脱線する。
作家志望の彼が、全力と魂を注ぎ込んだ小説『幻の女』は、不運な事故であっけなく行方不明。ところが数か月後、全く同じタイトルの小説が、新人賞を受賞して華々しくデビューしていた。
作者は白鳥翔。見たこともないその名前に、山本は即座にピンとくる。
「……パクられた!」
そこからの彼は、もう止まらない。証拠を探し、名誉を取り戻そうと、白鳥を執拗に追い詰めていく。しかしその執念は、やがて正義の炎ではなく、妄執と狂気の渦へと形を変えていく。
これは小説か、それとも狂気の伝染か
この作品の面白さは、ただの盗作騒ぎや作家同士の対決にとどまらない。折原一は、物語の土台からして「誰が作者なのか」というテーマを放り込んでくる。
主人公の日記、作中作の原稿、そして作者らしき三人称の語り。これらがぐるぐると入り混じり、まさに「ロンド(輪舞曲)」の名のとおり、読む側の頭をぐるぐる回しにかかるのだ。
誰が真実を語っているのか、本当にこの話を書いているのは誰なのか、読み進めるほどに足場が崩れていく感覚。しかも、心理ドラマとしての破壊力も抜群だ。
嫉妬、承認欲求、被害妄想……そういった感情が雪だるま式にふくらみ、山本の視界を歪ませていく。視点が常に彼の中に固定されているから、現実がどこまで崩れているのか、自分まで巻き込まれてわからなくなる。気づけば、彼の暴走を止めるブレーキなんて、とうの昔に壊れている。
そして極めつけが、あの有名な「あとがき」だ。物語が終わったと思った瞬間、いきなりこちらの肩をつかんでくるような一撃。第四の壁を粉々に壊して、「お前もこのロンドの参加者だ」とでも言うように引きずり込まれる。
ページを閉じても、まだ輪の中で踊らされている感覚が残る。
怖いのは、そこから抜け出そうという気がもう失せていること。
読む、ではなく、巻き込まれる。
それが『倒錯のロンド』だ。
3. 201号室から覗く、歪んだ人生の断片── 『倒錯の死角 201号室の女』
アパートの201号室。この部屋をめぐって、三人の視線が入り乱れる。屋根裏から毎日こっそり覗いているのは、酒浸りの翻訳家・大沢。そこへ引っ越してきたのが、東京暮らしを手紙に書きとめるOL・真弓。
もちろん彼女は、真上から見られているなんて知る由もない。そして三人目は、大沢の知り合いで、なぜか二人の世界に転がり込んでくる、盗み癖持ちの男・曽根。
それぞれが勝手な方向に暴走し、やがてとんでもない事件へとなだれ込んでいく。
日記と手紙が紡ぐ、100%信用できない三重奏
この話は、ただの覗き見ストーリーじゃない。折原一は三人とも「信頼できない語り手」にして、物語を意図的にぐちゃぐちゃにしてくる。
日記や手紙、会話がバラバラのピースみたいに差し込まれ、同じ出来事なのに描写が食い違う。読む側は半ば強制的に探偵役になり、嘘や勘違いだらけの証言の中から真実らしきものを拾い上げることになる。
しかも、この迷路の作り方がいやらしい。人間は、時間や人間関係をつい整理して並べたくなる習性がある。その癖を逆手にとって、作者はズバッと足をすくってくる。
何気なく読み進めていたら、そういうことだったのか!と背筋がひやっとする瞬間が待っている。タイトルの『死角』は、覗き穴の向こうだけじゃなく、自分の頭の中にもあるというわけだ。
湿った空気と、じっと見つめすぎた相手に対して芽生える歪んだ執着。ページをめくるうちに、自分まで屋根裏の暗がりに座っているような気分になる。
もう降りられないし、降りたくもない。この後ろめたい快感こそ、折原ワールドの危険な魅力だ。
4.密室マニア警部、暴走事件簿── 『七つの棺 密室殺人が多すぎる』
埼玉県警の黒星光警部は、とにかく密室が大好きだ。普通の刑事ならただの事件で済ませるところを、「これは立派な不可能犯罪だ!」と勝手に盛り上げ、事態をややこしくしてしまう。
そんな黒星の前に、まるでご褒美のように七つの奇妙な密室事件が現れる。一夜にして合掌造りの家が消えたり、完全に密閉されたプラネタリウムで殺人が起きたり、どれも一筋縄ではいかない案件ばかりだ。
黒星は迷推理を炸裂させたり、時に意外な的中を見せたりしながら、密室パズルに挑んでいく。
これは事件解決の記録ではない。究極の『密室愛』の記録である
タイトルからして、黄金期ミステリの巨匠ジョン・ディクスン・カーへのオマージュ全開。
カーの傑作『三つの棺』をもじったネーミングや、古典作への小ネタがあちこちに散りばめられていて、ジャンルファンならニヤリとするはずだ。折原一はこの手の遊びを心から楽しみ、多種多様な不可能犯罪をこれでもかと詰め込んでいる。
黒星警部は、探偵というより「ミステリに憑かれた人」だ。バッジをつけた熱狂的ファンのようなもので、事件解決より密室愛が優先される瞬間すらある。その暴走ぶりが笑いを生み、同時にミステリファンの自画像のようにも見えてくる。
笑えるだけじゃなく、トリックはどれも本格的。物理的な仕掛けから心理的な誘導、大胆なミスディレクションまで、七つの事件はバラエティ豊かに作り込まれている。
ページをめくるたびに、次はどんなヘンテコな密室が飛び出すのかとワクワクが止まらなくなる。事件そのものは深刻なはずなのに、黒星警部と一緒に「いやあ素晴らしい密室だ!」なんて不謹慎な快楽に浸ってしまうのだ。
古典ミステリへの愛あるいじりと、それを裏切らないガチガチの本格トリック。笑いながら読み進めているうちに、いつの間にかこの密室の沼から抜け出せなくなっているはずだ。
犯人探しもいいけれど、まずはこの贅沢な不可能犯罪のパレードを全力で楽しんでほしい。
読み終えたとき、あなたはきっと、黒星警部のように「もっと密室を!」と叫びたくなっているに違いない。
5.殺人犯の頭の中で暮らすことになりまして── 『叔母殺人事件 偽りの館』
悪名高い殺人事件を追うため、わざわざ現場の洋館に住み込む。そんな危なっかしいことをやってしまうのが、この物語の語り手であるノンフィクション作家の「私」だ。
舞台はレンガ造りの古い洋館。そこで起きたのは、莫大な遺産目当てで叔母を殺した名倉智樹による事件だった。狙いはひとつ。智樹が屋敷のどこかに隠したとされる手記を探し出すこと。やがてそれを手に入れた「私」は、智樹の言葉を通して、犯行に至るまでの毎日を追体験していく。
調査する側とされる側、その境界はこの偽りの館の中で少しずつ曖昧になっていく。
隠された手記。犯人が綴った完全犯罪へのカウントダウン
まず面白いのが、現在の調査パートと、手記による過去のパートが交互に進む作中作の構造だ。
手記はただの証拠じゃない。それ自体が謎の塊で、読む側は常に「これは本当の告白なのか、それとも自己弁護の作文なのか」と揺さぶられる。意図や動機を推し量る作業がそのままスリルになっていく。
もうひとつの面白さは、犯人が練り上げた完全犯罪を、内側からじっくり覗かせるところだ。計画のきっかけ、準備の細部、そして自分は絶対に捕まらないという傲慢さ。
これは犯人探しではなく、どうやって、なぜ犯行に至ったかを追うハウダニット&ホワイダニットだ。読んでいる間ずっと、この完璧そうな計画はどこでほころびるのか?という期待が胸に張りつく。
そして舞台となる偽りの館がまた効いている。事件現場に住みながら犯人の手記を読むという設定は、過去と現在を無理やり近づけ、館そのものに犯罪の記憶を宿らせる。
事件現場で、犯人が書いた手記を読みふける。そんな倒錯したシチュエーションに、気づけばどっぷりと浸かってしまう。智樹が綴る言葉は、告白なのか、それとも読者を欺くための巧妙な罠なのか。
犯人の思考をなぞるうちに、いつの間にか「計画が成功してほしい」とすら願ってしまう自分に驚くかもしれない。そんな風に、読者のモラルを侵食していくのが、折原ミステリの恐ろしくも面白いところだ。
6.ネットの闇に素人探偵が放り込まれるとき── 『叔父殺人事件 グッドバイ』
ある日、叔父がネットで知り合った男女と練炭自殺をした、という連絡が入る。警察はあっさり事件性なしと片づけたが、叔母は真っ向から否定。「これは偽装殺人だ。あんたが調べなさい」と、半ば脅しのように命令してくる。
探偵でも記者でもない、ただの青年である「僕」は、こうして危険すぎる調査に足を踏み入れることになった。
物語の骨組みが覆る折原マジック
たどり着いたのは、自殺サイトという現実の隙間に潜む濃い闇の世界。他の犠牲者の背景を探るうち、叔父が隠していた事実が少しずつ浮かび上がる。
しかし核心に近づくほど、誰かに見張られている感覚が強まっていく。この時点で、事件は「過去を掘り返す作業」から「自分の命を守る戦い」へと変わる。
本作の面白さは、ネット自殺という生々しい題材を折原一流の叙述トリックのカモフラージュにしている点だ。表向きは社会派スリラーのように見せながら、裏では登場人物の正体や動機にまつわる仕掛けが静かに組み立てられている。
しかも視点は、危険に対して無防備な素人探偵。もしかしたら背後に誰かいるという感覚が、推理のワクワク感とスリラー的な恐怖を同時に引き上げていく。
そしてラスト、恒例の折原マジックが炸裂。ひっくり返るのは事件の真相だけではない。語り手や家族について抱いていた認識、物語の構造そのものまで覆される。
最後の一撃を食らったあとの、あの呆然とする感覚。
自分が立っている地面さえ信じられなくなるほどの衝撃は、ミステリ好きなら一度は通っておきたい道だ。
7.このマンションは、日常の皮をかぶった怪物です── 『グランドマンション』
古びた「グランドマンション一番館」は、見た目こそくたびれているが、中身はもっと癖が強い。元〈名ばかり管理職〉の老人、定年後の元公務員、三世代で暮らす女所帯、そして何を考えているのかわからない管理人。
そこに、騒音だのストーカーだの詐欺だの空き巣だのと、ありふれている嫌なトラブルが日々降ってくる。バラバラの小競り合いに見える出来事が、ある瞬間から妙な形で繋がりだし、マンション全体の裏側に潜む、もっとデカくて悪意に満ちた何かが顔を出す。
全ての住人が、一つの罠に囚われている
物語の作りは、いわゆる「グランドホテル形式」だ。章ごとに住人が変わり、それぞれの私生活やトラブルが描かれる。
でもここで面白いのは、住人たち自身が知らないつながりを、読み手だけが少しずつ拾えるようになっているところだ。散らばった伏線をかき集めていくと、マンション全体を貫くひとつの大きな謎が浮かび上がる。
しかも、舞台が身近な集合住宅というところも曲者だ。うるさい隣人、孤独な老人、ちょっと怪しい若者。そんなステレオタイプなイメージを、物語はわざと利用してくる。こちらが勝手に抱いた思い込みをひっくり返される瞬間が、何度もやってくるのだ。この人はこういう人だろう、と決めつけた途端、その前提が粉々になるのが気持ちいい。そして怖い。
そして圧巻なのは物語の膨らみ方だ。最初は近所の揉め事レベルだった話が、少しずつ絡まり合って、気づけばマンション丸ごとを飲み込む陰謀に変貌している。
クライマックスは衝撃的で、どこかシュールですらあり、とんでもない大技まで飛び出す。日常から非日常へのジャンプ、その落差がこの物語の爆発力だ。
章を追うごとに積み重なる違和感。それらが一つに溶け合い、マンション全体を飲み込む巨大な渦へと変わる瞬間は、まさに折原ミステリの真骨頂。
読み終えたあと、ふと自分の家の壁の向こうに耳を澄ませたくなるかもしれない。
だが、そこから聞こえてくる音がただの生活音である保証はどこにもない。
8.二つの事件が、同じ地雷を踏みに行く── 『失踪者』
最初は全く関係ないと思っていた二つの出来事が、少しずつ距離を縮めていく。そんな危うさが、この物語の初手から漂っている。
片方は、女性ライター・五十嵐みどりが追う一家失踪事件。家族全員がある日、まるごと消えたという奇妙な案件だ。しかも数年前に起きた未解決の一家惨殺事件と、不気味なほど似た点を持っている。もう片方は、売れない推理作家の「僕」。
新作のネタを求め、連続通り魔事件の容疑者を勝手に尾行しているうちに、妙な動きに巻き込まれていく。
背筋を冷たく撫でる、実在感のある闇の正体
この二つの線が交わるのはずっと先のこと。最初は無関係に見えるからこそ、それぞれのパートの緊張感がゆっくり膨らむのだ。
みどりの取材は、失踪事件の裏にある重い影を掘り起こし、僕の追跡は、目の前で起こる危うい出来事をリアルタイムで見せつける。章が切り替わるたびに「次はどっちだ」と身構えてしまう。
本作は折原一の「者」シリーズの中でも、現実感の濃さが際立つ一作だ。元ネタの存在を感じさせる設定は、フィクションでありながら生々しい手触りを与え、読み進めるほどにただの作り話ではない感覚を植え付けてくる。その現実感が、後半の仕掛けをより冷たく、鋭く響かせるのだ。
そして最大の魅力はその構成力だろう。ひとつの謎が解けることで、もうひとつの謎が一気に氷解する瞬間が訪れる。二つのプロットが実は同じ闇の両面だったと明かされる終盤は、完全に不意を突かれるのに、振り返れば必然の積み重ねだったと納得させられるわけだ。
別の川を下っていたはずが、気づけば同じ滝つぼに真っ逆さま。そんな爽快さと恐怖が同時にくる。
章をめくるたびに深まる謎。それは単なる娯楽としてのミステリではなく、現実の裏側に潜む闇を覗き見るような、禁断の体験に他ならない。
そして最初から読み返し、そこに仕掛けられた悪意に気づいたとき、この物語の真の恐ろしさが完結する。
9. 15年遅れの手紙が呼び起こす、過去と現在の衝突── 『ポストカプセル』
2001年、全国でちょっとした騒ぎが起きる。届いたのは、15年前に投函された手紙の山。差出人は1985年のつくば科学万博を訪れた人々で、当時のポストカプセル企画によって未来に送られたものだ。
結婚した今となっては気まずい元恋人からのラブレター、亡き親からの別れの言葉、子ども時代の自分から届いた約束。そして、中には脅迫や告白、絶望の叫びといった、笑い話では済まされない代物も紛れ込んでいた。
15年の時差が運んできた、劇薬のような手紙
この小説は、手紙という過去の声を物語の中心に据えた変則的な書簡体ミステリだ。
各章ごとに手紙の送り主と受取人が変わり、それぞれのエピソードが短編のように独立している。しかし、読み進めるうちに、すべての手紙をつなぐ一本の黒い糸が見えてくる。そこに気づいた瞬間、バラバラだった物語が一気に長編ミステリへと姿を変える。
鍵を握るのは〈時間〉だ。手紙が書かれた1985年と、届いた2001年との間には15年という隔たりがある。その間に人は変わり、関係は壊れ、秘密は土の中に埋められたはずだった。そこへ突如として届く過去のメッセージは、平穏な現在を掘り返し、二つの時間をぶつけ合わせる。その衝突がサスペンスを生み、感情をかき乱すのだ。
折原一は、この壮大な設計図を日常のディテールの中に隠している。伏線は何気ないやりとりや些細な描写の中に潜み、最後の章で一斉に姿を現す。その回収の鮮やかさは、仕掛けを愛するミステリファンにとって格別だ。
15年前の自分から届く手紙。それは懐かしさと同時に、触れたくなかった真実をも運んでくる。ページを閉じても、封を切る瞬間のざわめきが頭から離れない物語だ。
過去は変えられないが、過去からのメッセージは現在を塗り替えてしまう力を持っている。
折原一が描き出すのは、そんな言葉が持つ魔力と、時間の壁を越えてくる悪意の正体だ。
10.天井裏からのぞく、作家たちの欲と嘘── 『天井裏の散歩者 幸福荘殺人日記』
著名な推理作家がオーナーを務めるアパート幸福荘は、作家志望者にとって憧れの住処……のはずが、実際は一癖も二癖もある住人たちの巣窟だ。
中でも、美貌の人気少女小説家・南野はるかの存在は、男たちの競争心に火をつける。やがて彼らは、各部屋をつなぐ天井裏を使った覗き見合戦を繰り広げ、ついには密室殺人へと事態は転がっていく。
しかも、彼らが書く原稿の中身と現実の事件が妙にリンクし始め、どこまでが本当でどこからが作り話なのか、境目はどんどんあやしくなる。
『屋根裏の散歩者』への挑戦。古典を解体し、再構築するメタの魔術
タイトルは江戸川乱歩の『屋根裏の散歩者』へのあからさまなオマージュ。
乱歩の持つ覗き趣味や妄執、グロテスクな趣向を受け継ぎつつ、折原一はそこに自分の十八番であるメタフィクションをがっつり組み込む。古典へのラブレターでありつつ、前提をひっくり返す批評でもあるという二重構造が面白い。
最大の特徴は、物語そのものが「現実と虚構の境界」を謎にしていることだ。登場人物は全員作家で、日記や原稿がそのままテキストとして差し込まれる。今読んでいるページが事件の事実なのか、誰かの創作なのか、判断をつけさせない作りになっていて、読み手は常に揺さぶられっぱなし。この不確定さが、妙な苛立ちと興奮を同時に生む。
さらに、文壇や作家志望者への皮肉もたっぷり。プライドだけは天井知らず、嫉妬と承認欲求にまみれた彼らの姿は、笑えるのに少しゾッとする。
タイトルの「殺人日記」は誰のものでもあり得るし、紙の上でなら完璧な殺人くらい誰でもやってしまう。そんなブラックな遊び心が、この話の隅々まで染み込んでいる。
おわりに


折原一というと、派手なトリックばかりが話題になるけれど、本当にすごいのはその奥にある「人間の心のヤバいところ」の描き方だと思う。トリックはゴールではなくて、その深みを覗くための入り口にすぎない。
彼の小説を読むことは、作者が全部の手札を握っているゲームに自分から飛び込むようなものだ。こっちは必死で推理してるのに、最後の最後で鮮やかにひっくり返される、あの感覚がたまらない。
結局、折原ワールドというのは、真実なんて人それぞれで、物語は武器にもなって、現実だって簡単に壊れる世界だ。
だから一度足を踏み入れたら、最後のページを閉じてもずっと頭の中で物語が回り続ける。
読了後に残るあのスリルと眩暈は、きっとずっと消えない。
他の作家さんのおすすめ記事