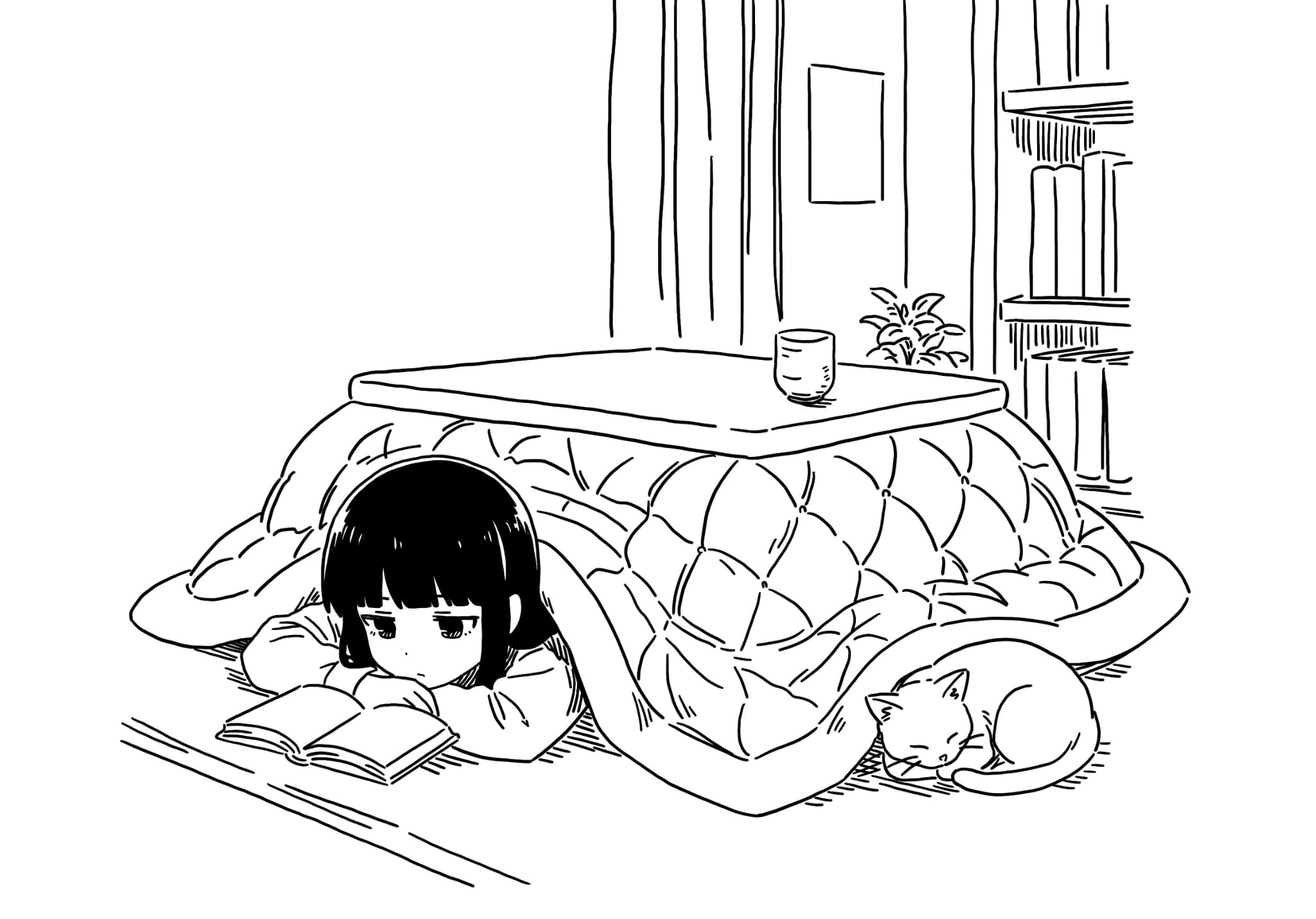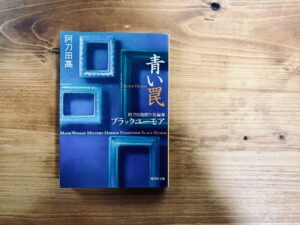現実と虚構の境界がふいに曖昧になる、そんな瞬間。
井上夢人の作品に触れると、だいたいそうなる。これは本当に作り話か? と、読んでるこっちが現実の感覚を疑ってしまうのだ。
もともとは伝説のコンビ「岡嶋二人」の片割れとしてデビューし、のちにソロ作家として活動を開始。そこからの井上夢人は、ある意味でジャンルの枠をぶち壊し続けてきた作家である。
テクノロジーと人間心理、ミステリと幻想、ユーモアと不穏。そのどれもを、器用に、でも決して安易に混ぜることなく、独自のバランスで織り込んでくる。
構成は緻密。けれど、読者を煙に巻くための小手先ではなく、物語の中で自然に「違和感」が立ち上がるように仕組まれている。その違和感がだんだんと濃くなり、やがて一気に襲いかかってくるような、あの感覚。読後に残るのは、「怖い」とも「不思議」とも「泣きたい」とも言い切れない、妙に後を引く何かだ。
殺人事件を通して記憶の迷宮に入り込むような長編もあれば、死者と語り合うような気配を持つ短編集もある。中には「他人の声が頭の中に響く」という、設定だけでご飯三杯いけそうな作品まで揃っている。どれを読んでも、まったく別の顔をしているのに、なぜか「これは井上夢人だ」と直感できるから不思議だ。
というわけで今回は、そんな井上ワールドの異能っぷりを味わえる、代表作から隠れた傑作まで、厳選して10作品をご紹介する。
どの作品にも共通するのは、現実がほんの少しズレていくあの感覚。そして、そのズレを「おもしろさ」として受け入れられるかどうかが、井上作品を楽しむ鍵になる。
覚悟はいいだろうか。次のページをめくった瞬間、現実は少しだけ歪み始める。
だが、それこそが井上夢人の真骨頂だ。
奇妙で、でもどこか親しい裏側の世界が、すぐそこに待っている。
1.愛という名の錯覚、魂という名の牢獄── 『ラバー・ソウル』
「愛すること」と「支配したいと思うこと」は、本当に別物なのか。
井上夢人の『ラバー・ソウル』を読むと、そんなことを考えずにはいられなくなる。最初はただのストーカー事件かと思いきや、物語は次第に軌道を逸れ、倫理と認識の歪みへと突き進んでいく。
中心にいるのは、鈴木誠という男。誠実そうな名前とは裏腹に、彼は社会の隅でひっそり生きてきた人物で、生まれ持った外見のハンディを引きずりながら暮らしていた。
そんな彼が、美しいモデル・美縞絵里と出会い、恋に落ちる。だがその恋は、どこかでねじれ、徐々に所有の欲望へ変わっていく。
多層的な語りの迷宮
この小説の面白さは、事件後の世界から語り始める構造にある。鈴木自身の手記、関係者の証言、警察の聴取記録……それぞれの語りが、鈴木という男を別の角度から浮かび上がらせる。
ある時は哀れに、またある時は気味悪く、そしてふとした瞬間に「自分と似ているかも」とすら思ってしまう。この距離の揺らぎが、実に怖い。
そして終盤、物語は大胆に反転する。どんでん返しというにはあまりに重い真実が暴かれ、世界の前提そのものが壊れていく。その瞬間、鈴木誠という人物がまったく違って見えるようになる。感情移入していたことすら、揺さぶられてしまうのだ。
最後の一文まで読んで、自分がどんな気持ちでいるかを説明するのは難しい。しかし確実に言えるのは、この作品を通して世界の見え方が少し変わったということだ。
愛、幻想、孤独、そして人間の根源的な欲望。井上夢人はそれらを、ひたすら鋭く、しかもどこか美しく描き切っている。
読んでしまったら戻れない。そういう本である。
2.名前のない私たちへ── 『プラスティック』
「自分の名前が使われている」
そう告げられた瞬間、世界の輪郭が揺らぎ始める。
井上夢人の長編小説『プラスティック』は、誰かに「自分」を名乗られているという違和感から始まる、極めて現代的で、ぞっとするほど繊細なサスペンスである。
同姓同名?よくある話? いや、この物語はそこでは終わらない。顔も、暮らしも、日常すらも同じだとしたら。
それはもはや侵略である。
ファイル形式で語られるミステリー
物語は、フロッピーディスクに保存された54個のファイルというかたちで構成されている。
主婦・向井洵子の日記、隣人の監視記録、名もなき男の調査メモ。そのすべてが独白体で綴られ、読んでいる側はあたかも、無断で他人の個人ファイルを開いてしまったような背徳的緊張感と没入を覚える。
しかも、語り手たちは皆「自分のことは正確に語っている」と信じ込んでいる。だが、その中には嘘もあれば、知らずに晒してしまっている真実もある。どの言葉を信じ、どの言葉を疑うか。その選択を迫られ続ける構造こそが、本作の醍醐味である。
物語が進むにつれて、洵子という存在は複数のレイヤーに引き裂かれ、語り手の「私」は不安定になっていく。自分の名前を他人に騙られる不安。それはいつしか、自分自身が自分でなくなるかもしれないという恐怖へと変わる。
『プラスティック』というタイトルの示す通り、この作品における「自分」や「他人」は、表面こそ似ていても中身は簡単に変形しうる、可塑的な存在だ。それはアイデンティティの根源に迫る問いでもある。
そして終盤、すべてのファイルが一本の線につながった瞬間、認識の地盤がひっくり返るような感覚に襲われる。技巧的などんでん返しではなく、積み重ねられた違和感が構造として反転するこの読後感は、ミステリ好きとして快感すら覚える瞬間だ。
この小説の本質は、他人が怖いという話ではない。むしろ、自分自身が揺らぐことの怖さを描いた物語だ。名前、記憶、日常。それらが、実は外から簡単に侵食される仮の皮に過ぎなかったとしたら。
そう考えた時、あなたはきっと、誰かの独白に耳を傾けていたはずが、自分の中にもうひとりの私が語り出している感覚に気づくはずだ。
『プラスティック』とは、そういう種類の物語である。
3.匂いが視えるとき、真実は色を変える── 井上夢人『オルファクトグラム』
匂いに色があったなら、世界はどんな風に見えるのだろうか。
井上夢人『オルファクトグラム』は、そんな突飛な発想を真っ向から物語にしてしまった、異能×サスペンスの意欲作である。
ただの変わった設定では終わらない。これは、嗅覚という最もプリミティブな感覚を武器に、認識と感情の正体に迫っていく、ひたすら硬派で文学的なミステリーだ。
主人公は、姉が殺される現場に遭遇し、犯人に殴られた衝撃で異常な嗅覚を得てしまう青年。彼にとって匂いは、もはや臭覚ではない。目に見える線であり、模様であり、波のように空間に漂うものとなる。
しかもそれは、汗や香水だけではない。怒り、恐怖、愛、嘘。感情の痕跡までもが、色彩を帯びて浮かび上がるのだ。
目に見える匂い、聞こえない真実
物語の構造は非常に丁寧で、上下巻を通じて能力の発現から訓練、そして事件の真相へと向かっていく。序盤はむしろ地味なほどの慎重さで、彼がどれだけ異常な世界を背負ってしまったかがじっくり描かれる。
派手なバトルも特殊部隊も出てこない。あるのは、視覚化された匂いと、それに取り巻かれる心理的重圧だけ。だがそれこそが、本作の一番の魅力でもある。
嗅覚で真実が見えるというのは、感情の裏まで剥き出しになるということでもある。相手の言葉と匂いが食い違えば、そこにあるのは偽りか、あるいは無自覚の本音か。そうした齟齬を見抜けてしまう能力は、同時に孤独をも連れてくるのだ。
犯人との対峙では、ただの追跡劇には終わらない心理戦が展開される。犯人の行動、匂い、動機。どれもが複雑に絡まりながら、最後には一筋縄ではいかない人間の深層が顔を出す。その瞬間、私たちもまた、世界の見え方を変えられてしまう。
「オルファクトグラム」とは、匂いの軌跡、嗅覚の地図。そんな言葉がタイトルに掲げられていること自体が、この作品の詩的な本質を象徴している。匂いは嘘をつかない。言葉が届かなくても、空気には痕跡が残る。
この作品を読み終えたあと、すれ違った誰かの香水に、妙な意味を感じてしまうかもしれない。電車の中でふと、誰かの感情の名残を意識してしまうかもしれない。
それくらい、『オルファクトグラム』という作品は、感覚そのものに干渉してくる。
視覚優位の世界では拾えない「真実」が、こんなにも存在するのか。
そんな驚きを、全身で受け止める作品である。
4.声がする まだ、名前のない誰かから── 『ダレカガナカニイル…』
ひとりきりの部屋で、ふと耳を澄ませたとき、風でもない、テレビでもない、「誰かの声」が聞こえたことはないだろうか。
それが幻聴でも妄想でもなく、自分の中で確かに響いていたとしたら。その存在は、果たして他人なのか、それとも自分の一部なのか。
井上夢人の『ダレカガナカニイル…』は、そんな錯綜した認識を、静かに、大胆に描いてみせる異色の長編である。一見ホラーのようなタイトルに怯んだとしても、中身はむしろ繊細で、どこか愛おしい共生の物語だ。
他人が内側にいるという現象
物語の主人公は西岡という男。宗教施設の警備員という地味な職を経て、火事に巻き込まれ、帰郷を余儀なくされる。
だが、その事件以降、彼の中に異変が起きる。誰かの声が聞こえるのだ。しかも、その誰かはただ喋るだけでなく、意志を持ち、時に体を動かし、ツッコミすら入れてくる。
これがいわゆる共生型人格のような扱いかと思いきや、井上夢人はそこにリアルな生活感と心理的リアクションをじっくりと積み上げていく。西岡が最初に感じるのは恐怖。そして混乱。しかし次第に、この声と共に生きることに慣れ、むしろ少しずつ心を許していくのだ。
物語の面白さは、この声の正体が何なのかを探っていく過程にもある。超常的な力なのか、心の病なのか、それとも別の何かなのか。サスペンス的な構造を取りつつ、徐々に声の過去、西岡とのつながりが明かされていく展開は、ミステリとしてもきっちり楽しめる。
だが、この作品がただの謎解きで終わらないのは、声との関係性がどんどん人間臭くなっていくからだ。かけ合いは時にユーモラスで、とても愛嬌がある。この不気味なはずの共存関係が、いつの間にか微笑ましくすら感じられてくるあたりに、井上作品らしいひねりが光る。
終盤には、事件の真相と声の正体が明かされるのだが、それが単なる驚きではなく、切なさとやさしさを帯びた理解の瞬間として描かれるのがすばらしい。他者と重なりきれないもどかしさと、それでも近づこうとする意志。その狭間に漂うあたたかい不確かさが、物語全体を包み込んでいる。
『ダレカガナカニイル…』というタイトルは、最初はホラーっぽく響くかもしれない。でも読み終わったとき、それがむしろ誰かがいてくれるという小さな救いの証しに聞こえてくる。この小説は、そういうふうに、孤独の輪郭をほんの少しやわらかくしてくれる作品だ。
声がする。
それは、どこかで誰かが、まだあなたとつながっていたいと願っている証なのかもしれない。
5.鏡の奥に眠るもの── 『メドゥサ、鏡をごらん』
男は、自らコンクリートに身を埋めて死んだ。
そばにあったのは一枚の紙片。ただひとこと。
「メドゥサを見た」
それが何を意味するのか。どうして人は、そんな最期を選ぶのか。井上夢人『メドゥサ、鏡をごらん』は、その問いから幕を開けるミステリである。
そしてそれは、単なる謎解きでは終わらない。ホラー、幻想、ロジック、そしてなにより「見ること」の本質を問う、不穏で美しい迷宮なのだ。
物語の核となるのは、奇怪な死を遂げた作家と、その娘と婚約者が残された原稿を手がかりに辿っていく探索劇である。けれどそれは探偵的推理というより、読み進める行為そのものが何かを呼び覚ましてしまうような、儀式に近い体験に変わっていく。
原稿と現実の境界が、静かに崩れていく
この小説の怖さは、直接的ではない。血も叫びもない。なのに、不安が身体の奥にまで染みてくる。
原稿に書かれた内容と現実が徐々に重なり、世界がどこか夢の中のように歪んで見えはじめる。言葉にできない違和感がページごとに蓄積されていき、読者自身が見てはいけないものに近づいていく感覚すらある。
メドゥサとは、視線を浴びた者を石に変える神話の怪物。けれど本作で描かれる「見ること」は、もっと根源的で危険な意味を持っている。対象を理解するための行為ではなく、逆に自分の内側に異物を侵入させる、呪いのような接触なのだ。
鏡を見るとき、人は他者ではなく、自分に出会う。そしてその自分こそが最も恐ろしい存在かもしれない。この感覚を、井上夢人は巧妙に言葉の層で組み上げていく。原稿の中の視点、語り手の視点、読者の視点。それぞれがズレながら重なり、気づけばこちらまで物語の中に取り込まれている。
読み終わっても、何かが解決した感じはない。ただ、理解できないものに手を伸ばしてしまったという感触と、鏡の奥にもうひとつの何かが見えてしまったような、そんな薄ら寒さが残る。
『メドゥサ、鏡をごらん』は、読む行為そのものが呪術になるような一作である。
明確な答えなど求めてはいけない。
鏡の中を覗いてしまった者に残されるのは、正体不明のざわめきだけなのだから。
6.言葉の迷宮で、ふたりはいつまでも── 『もつれっぱなし』
話せばわかる、なんてのは幻想だ。
井上夢人『もつれっぱなし』を読んでいると、人と人との会話がどれほど噛み合わず、どれほどズレ続け、そしてどれほど愛おしいものかを思い知らされる。
この短編集はただ者ではない。というのも、地の文が一切ない。全部、男女ふたりの会話だけ。情景説明も心理描写も一行もなし。にもかかわらず、世界が立ち上がってくる。しかも笑えて、切なくて、ちょっと怖い。
収録作は『宇宙人』『四十四年後』『呪い』『狼男』『幽霊』『嘘』の全6編。どれもタイトルからしてふざけているように見えるが、内容は意外にも緻密で、不思議なリアリティを持っている。というか、あまりにリアルすぎて笑ってしまうのだ。
会話だけでここまでできるのか
例えば『宇宙人』では、女が言い出す。「あのナメクジ、宇宙人よ」。男は当然否定する。が、話はなぜかそっちには進まない。ナメクジがどうとかじゃなくて、ふたりの価値観のズレ、関係性の距離感、そしてお互いが抱えている小さな諦めみたいなものが、会話の端々から浮かび上がってくる。
この、話がどんどんズレていく感覚が全編に通底していて、しかも毎回ちがう形でもつれていく。すごいのは、そのもつれが自然なことだ。喧嘩じゃない。会話として成立している。でもズレている。この微妙なバランス感覚は、地の文なしで表現するには相当な腕がいると思う。
しかも、出てくる男女の名前は明かされない。背景も語られない。けれどなぜか、読み進めるうちに「ああ、たぶんこのふたりは……」と思えてくる。このぼんやりした共通性が、逆に普遍性を生む。
もしかしたらこれは、自分と誰かとの過去の会話のなれの果てかもしれない。言葉がすれ違い、意図が空回りし、それでもどうにか通じ合おうとする。そんな日常のひとコマが、ここにはぎゅっと詰まっている。
そしてどの短編も、どれもオチらしいオチはつかない。大団円も解決もない。ただふたりの言葉がもつれたまま終わる。しかし、そのほどけなさが逆にリアルで、ページを閉じた後もふたりのやりとりが頭の中でこだまし続ける。
『もつれっぱなし』というタイトルは、見事なまでにこの作品集を言い表している。会話は噛み合わない。でもそれでも、人は話す。ぶつかって、すれ違って、それでも話す。
この不器用さこそが、人間関係というものの根っこなんだと、この本は教えてくれるのだ。
笑ってしまうほどバカバカしくて、でもどこか深くて、何より読後に「言葉を交わすこと」そのものを見つめ直させられる。
そんな、不器用で愛おしい会話の標本が、ここには並んでいる。
7.鏡の向こうで、物語が笑う── 『あわせ鏡に飛び込んで』
日常というものは、案外あやふやな構造の上に成り立っている。
井上夢人の短編集『あわせ鏡に飛び込んで』は、その日常の足元に空いた裂け目のような10の物語を集めた一冊である。
90年代前半に執筆された作品とはいえ、今読んでも鮮度がまったく落ちていない。というより、現代の感覚で読むからこそ、この少しだけズレた世界のリアリティがより際立って感じられる。
タイトルがすでに象徴的だ。「あわせ鏡」。二枚の鏡を向かい合わせたとき、そこに映るのは無限の虚像。その虚像に飛び込む、という発想がすでに只事ではない。
現実の皮を一枚だけめくると
収録作は10編。掌編と呼んでも差し支えない短さの中に、不穏さと可笑しさが詰まっている。
『あなたをはなさない』では、恋愛が執着へと変貌する瞬間が、たった数ページで描かれる。甘やかな愛情の裏に潜む支配欲が、皮膚感覚レベルで迫ってくるのだ。言葉にすると陳腐になりがちなテーマを、井上夢人は不気味なほど自然に書き切っている。
一方『私は死なない』は、死んだはずの語り手が淡々と語り続けるという、どこか寓話のような構成。死後の世界というよりは、死そのものが現実に溶け込んでいるような、ひんやりした感触がいい。
『ジェイとアイとJI』では人工知能同士の会話が暴走し、人間の孤独を照らし出す。90年代のテクノロジー観が滲む設定ながら、根底に流れるテーマはむしろ今のほうが刺さる。笑えるのに、背中に冷や汗がにじむ。この温度のねじれが、本作全体を貫いている。
各編の終わり方にも注目したい。明確なオチがある話もあれば、ふわっと終わって読者の思考に投げてくるものもある。だがそれがいい。説明がないぶん、読後に鏡の続きを考える余地が生まれる。つまり、私たち自身がその鏡の中をのぞき込む当事者にさせられるのだ。
物語が終わったはずなのに、どこかに続きがある気がしてならない。誰かがまだ、自分の背後に立っているような気がしてならない。
そんなふうにして、この本は日常の見え方を少しだけズラしてくる。
10の短編のどれもが異なる題材と雰囲気を持ちながら、不思議な統一感があるのは、きっとすべてが現実の外縁をなぞっているからだ。笑ってしまう話も、ぞっとする話も、どれもが「現実のすぐ隣」に手を伸ばしている。
井上夢人の筆致は軽妙なのに、芯がぶれない。だからこそ、この短編集はどこまでも読後に響く。時代の匂いがする描写があっても、それすら味わいのひとつになっている。
気がつけば、あなたもまた、あわせ鏡の中に片足を踏み入れているかもしれない。
ページを閉じたあとも、ふと気になる誰かの視線。
それがあなた自身のものか、鏡の奥からのものか。
それを確かめる術はない。
8.世界が変わった日、ぼくらはまだ人間だった── 『魔法使いの弟子たち』
「死ななかった」というだけで、すべてが変わってしまったとしたら。
井上夢人『魔法使いの弟子たち』は、死の淵から戻った4人の男女が、力を得てしまったことで直面する葛藤と孤独を描いた異色の長編である。
能力バトルでも、救世主譚でもない。むしろこれは、ふつうの人間でいたかった人たちの、もがきの記録だ。
発端は、竜脳炎と呼ばれる致死率100%の新型ウイルス。この絶望的な病から奇跡的に生還した4人、京介、めぐみ、繁、耕三は、それぞれ特殊な力を身につける。
しかしその力は決して万能ではなく、むしろ自分自身の深層とつながっていて、扱えば扱うほど、自分が人間ではなくなっていくような感覚を伴う。
特別になったのではない、逸れてしまったのだ
たとえば京介は「嘘を見抜く力」を得る。だがそれは、誰かを信じるという当たり前の営みを失うということでもある。他人の本音が透けて見える人生は、便利さよりも絶望のほうが多い。ほかの能力者たちも、それぞれ望んでいなかった変化と向き合うことになる。
本作が秀逸なのは、こうした能力の描写がSF的ファンタジーに陥らず、徹底して人間の内面に根ざしている点だ。異能を持つ者がヒーローになるどころか、むしろ社会から浮き、恐れられ、監視される側に回る構図は、現代の不寛容ともリンクしてくる。
「違うこと」への嫌悪。「見たくないもの」を排除する本能。それに晒されるのは、選ばれた者ではない。生き残ってしまった者たちなのだ。
もちろん、物語としての構造もしっかりしている。ウイルスの正体、力の発現メカニズム、社会の動向。これらが緻密に設計されていて、変に煽ることなく、リアルにありそうな空気を作ってくる。SFとしてもサスペンスとしても読みごたえは十分だ。
終盤、4人それぞれが自分の力とどう折り合いをつけるのか、その選択が静かに提示されていく。誰が正しいとか、誰が間違っているとか、そういう話じゃない。ただ、「普通に戻れないまま、これからも生きる」ということの重さが胸に残る。
『魔法使いの弟子たち』というタイトルには、明らかに皮肉がこもっている。彼らは魔法を求めたわけではない。ただ、死ななかっただけなのだ。
なってしまった異能者として、それでも生きていくしかない。世界に拒まれながらも、息をしていくしかない。
力とは何か。人間とは何か。
そして、「変わってしまった自分」とどう向き合うか。
この物語は、そのすべてを真正面から描いている。
9.ぼくらは、ちがう。だけど、ひとりじゃない── 『the SIX ザ・シックス』
子どもたちは、涙すら悟られないように生きてきた。
異なる力を持ったがゆえに、世界と少しずれてしまった6人の少年少女。その孤独と痛みを描いたのが、井上夢人『the SIX ザ・シックス』である。
いわゆる異能バトルものではない。むしろこれは、変わってしまったことに気づいてしまった子どもたちが、それでも誰かとつながろうとする物語だ。
6人それぞれの短編に加えて、彼らのその後を描いた終章という構成。視点は常に子どもたちに寄り添っていて、大人の目線で語られることはほとんどない。だからこそ、彼らの「違うこと」の苦しさが、より鮮やかに響いてくる。
異能は、祝福か、それとも呪いか
この作品に登場する力は、派手ではない。他人の痛みが分かる少年、記憶を読んでしまう少女、音に敏感すぎる少年。むしろ、日常をまともに過ごすには不便でしかない。力があるからすごい、ではなく、力があるからこそ普通ではいられない現実が、ここには描かれている。
そして、彼らにとって初めての「信じていい大人」として現れるのが、飛島という研究者だ。子どもたちを実験対象としてではなく、一人の人間として見つめ、理解しようとするこの存在が、本作の柱になっている。飛島との出会いが、彼らに「誰かとつながってもいいのかもしれない」という希望を芽生えさせていくのだ。
物語のラスト、成長した6人が再び集い、誰かのために自分の力を使う場面は、この物語の核でもある。特別な力を持った子どもたち、という枠組みを超えて、それぞれがそれぞれの人生を選び、歩んでいく。その姿が眩しいほどまっすぐで、どこか切ない。
構成としては短編集でありながら、各話がゆるやかに連なり、最終章でひとつの大きな円を描くようにまとまっていく。登場人物たちの再会はベタな演出かもしれないが、ここまで読んできた人にとっては、ただそれだけで泣きたくなるほどの重みがある。
『the SIX ザ・シックス』は、違っていることを悲劇にしない。ただ、違っていても、生きていていいのだと、やわらかく肯定してくれる。
力があっても、なくても、誰もがどこかで孤独を抱えている。その孤独にそっと手を伸ばすための物語だ。
10.嘘が照らす場所に、本当の救いがある── 『the TEAM ザ・チーム』
世の中には、正しさではどうにもならないことがある。
本当のことだけでは、心が癒せないこともある。
そんな「やさしい嘘」の必要性を教えてくれるのが、井上夢人氏の短編集『the TEAM ザ・チーム』だ。
この作品は、霊視を演じる中年女性と、彼女を支える3人の仲間たちによって織り成される、嘘と真実のあわいに立つ人助けミステリである。
いわゆる霊能力ものと見せかけて、実態は極めて地に足のついた人間ドラマ。奇跡ではなく観察、予知ではなく推理。けれどその結果、確かに誰かが救われていくのだから、これはもう立派なチームものだ。
主人公の能城あや子は、テレビで引っ張りだこのカリスマ霊導師。盲目で難聴、相談料8万円という設定だけで、すでに怪しさ満点。だが実際の彼女は、霊力ゼロの自称インチキ導師。霊視の裏には、情報収集・調査・心理分析をこなすプロフェッショナルたちの存在がある。
霊視は、チームプレイでできている
草壁は地道な調査のスペシャリスト、悠美はハッキングを使いこなす理系女子、そして鳴滝は冷静沈着なマネージャー。この3人とあや子の4人が、《チーム》として裏で仕掛けを整え、表向きは霊能というかたちで人々の問題を解決していく。
とはいえ、この話の本質は、カリスマ導師の活躍や情報戦の妙ではない。むしろ一貫して描かれるのは、「やさしい嘘」の意味と価値だ。
虐待、いじめ、家族の崩壊、詐欺。扱う題材は決して軽くないが、それらに対してチームがとるのは、糾弾でも制裁でもない。本当のことを突きつけるのではなく、信じられる形にして差し出すこと。その構えが、妙に胸に沁みる。
あや子は嘘つきだ。演技もしているし、料金だって高い。でも、彼女の語りにはどこか温かさがある。霊的ではなく人間的な、まっとうなやさしさ。依頼人はその言葉に騙されることで、少しだけ前を向ける。そして私たちもまた、その芝居に心を揺さぶられることになるのだ。
この作品の面白さは、正義や倫理のラインをあえて濁らせている点にもある。やっていることはグレーゾーンもいいところ。だが結果的に人が救われるのなら、それは嘘ではなく、方法なのかもしれない。
短編連作という形式も相性がよく、それぞれに異なる依頼者の人生と、それに寄り添うチームの手口が描かれる。すべての話が明快に収束するわけではないが、そこにまたリアリティがあっていい。
『the TEAM ザ・チーム』は、まるで現代の寓話のような作品である。
人を助けるのに、正しさだけでは足りない。事実を告げることが、時に刃になる世界だからこそ、この偽物たちのやり方が必要になる。
こんなふうに救ってくれる誰かが、現実にもいてくれたら。
そう思わずにいられない。
おわりに この現実が、本当に「現実」だと誰が言える?
井上夢人の小説を読み終えたあと、どこか自分の中で何かがズレているような感覚が残ることがある。
明確な言葉にはしづらい。でも、確かに何かが変わったような、ひっかかりがある。それはもしかすると、世界の輪郭かもしれないし、自分自身の記憶のかたちかもしれない。
だがそのズレ、違和感こそが、井上作品の魔力なのである。
彼の物語は奇抜でありながら、なぜか親密だ。大胆な設定も、風変わりな仕掛けも、読む者の心の奥のほう──不安とか、孤独とか、憧れとか──そういうものを優しく揺らしてくる。テクノロジーと幻想の皮をかぶった、すごく人間くさい小説たち。だからこそ、刺さる。だからこそ、残る。
「現実」にしか見えなかったものが、ふとフィクションのように感じられる瞬間。その逆もまたしかり。そういう感覚の揺らぎを味わえる作家というのは、そう多くはない。
気がつけば、読み終えていた。気がつけば、もっと読みたくなっている。井上夢人という作家の世界から、そう簡単には抜け出せなくなっている。それはむしろ、歓迎すべき囚われだと思う。
現実よりも少しだけ鮮やかで、少しだけ怖くて、でもやたらと魅力的なその世界に、もうしばらく酔いしれてみるのも悪くない。
次に開く一冊が、あなたの「境界線」をやすやすと越えてしまうかもしれないとしても。
現実と虚構の間を、ためらわず彷徨ってみよう。
あの扉は、いつだって開いている。