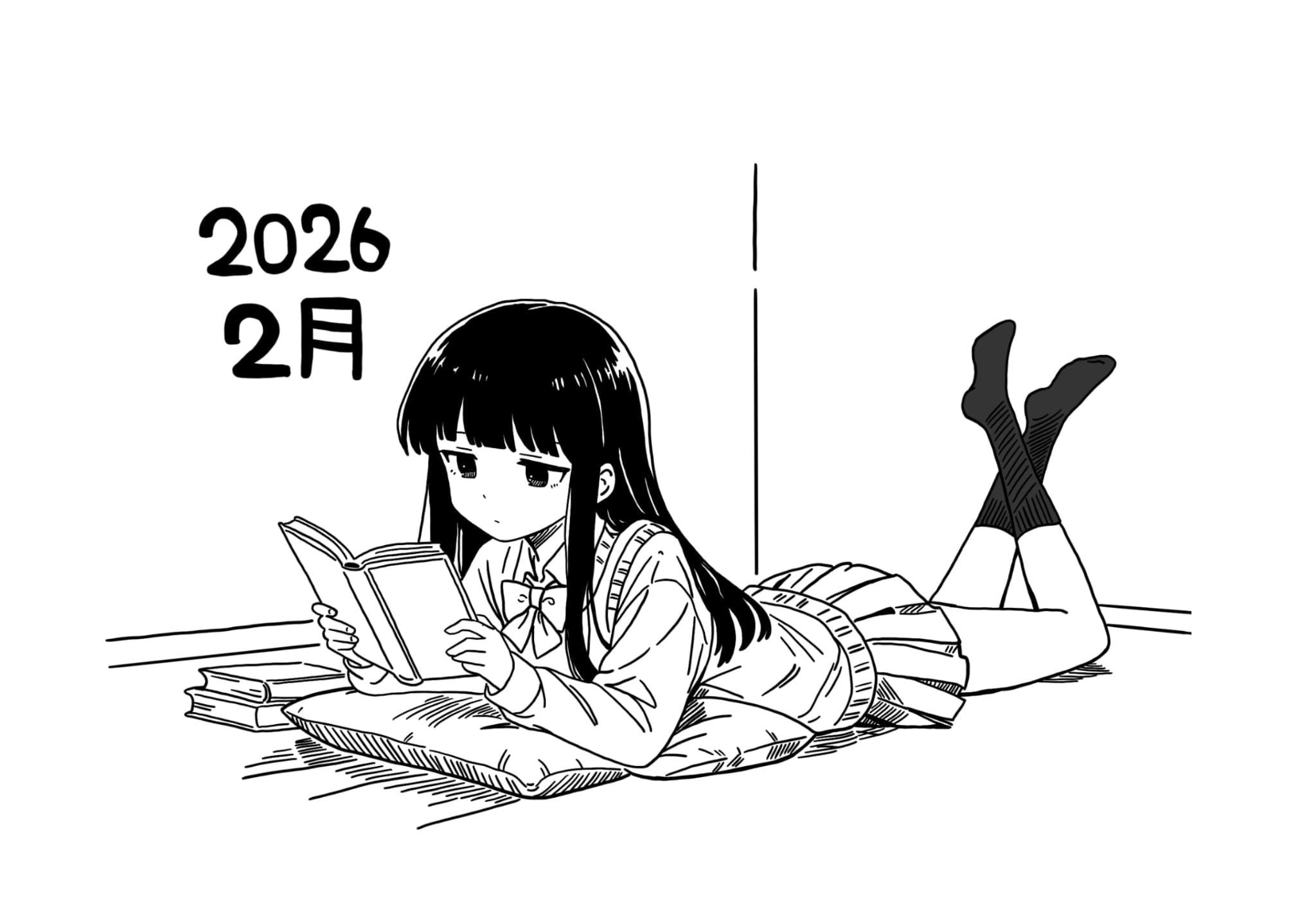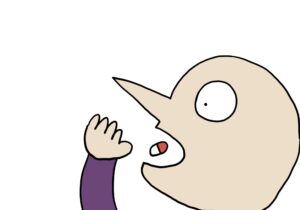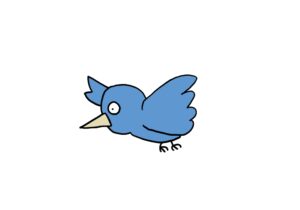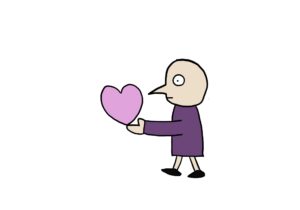オリエント大学で教授を務めるエフ氏、彼はその筋では名の知られた言語学の権威である。
しかし学生時代の彼の成績はビリから数えたほうが早く、決して優秀とは言えなかった。
いや、包み隠さず言ってしまえば落ちこぼれだった。
そのため学者として成功した今でも、己の賢さを鼻にかけるようなことは決してせず、研究者仲間や教え子たちからは慕われ、頼れる存在となっていた。
ある日、講義を終えたエフ氏が大学のキャンパスを歩いていると、ランニングをする集団に出くわした。
ユニフォームからするとテニス部だろうその集団は、颯爽とエフ氏の前を通り過ぎていく。
若いっていいなぁ、などと思いつつエフ氏がしばらく眺めていると、一人だけ遅れて走ってくる者がいた。
前を走っていた先ほどの集団に比べて不格好なそのフォームは、いかにも運動が苦手そうだ。
彼の頭に運動音痴という言葉が思い浮かぶ。
生まれつき運動が苦手な者がいる。
いくら努力をしても、生まれながらにして才能を持つ者にはかなわない。
そんなことをつらつら考えながら、連想ゲームのように味音痴や方向音痴、機械音痴など他の関連した言葉に思考を巡らせてゆく。
言語学者だけあって、こうしたことを考え出すと、無限に発想が広がる。
そこでエフ氏はふと疑問に思った。運動が苦手な者を運動音痴と言う。
ならば勉強が苦手な者を勉強音痴と言わないのはなぜだと。
そこから小1時間ほど考えてみたが、納得のいく答えは出なかった。
ただ運動と対極にある勉強を音痴と言わないのはどうにも不公平である。
そこでエフ氏はこの疑問を論文に書いて発表した。
するとたちまち世間で議論が起こり、多くの賛同者が現れた。
彼に賛同したのは主に学歴コンプレックスを持った若者たちで、頭が悪いわけじゃなく勉強音痴なだけだと言い訳とも開き直りともつかぬ事を言い始めるようになった。
しかし確かによくよく考えてみると、運動音痴があって勉強音痴がないのはおかしい。
おまけに言語学の権威であるエフ氏が間違ったことを言うはずがない。
そんなことからエフ氏の論文をきっかけにして『勉強音痴』という言葉が認められるようになった。
それに気を良くしたエフ氏は次に、恋愛の苦手な者を指す『恋愛音痴』なる言葉を作った。
この言葉によって、大勢のモテない者が救われた。
それからもエフ氏は買物に行くとつい買いすぎてしまう『買い物音痴』——これは買い物依存症に悩む者を救った——やリバウンドを繰り返す『ダイエット音痴』など様々な造語を編み出していった。
それまで深刻に悩んでいた容姿や性格も、ホニャララ音痴と表現すればあら不思議、なんでもないことのように思えてくる。
本来なら欠点のはずが、音痴と言い換えることでその欠点が和らいで思えるのだ。
エフ氏は言語学者の立場から、この風潮をとても喜ばしく思っていた。
音痴を自称するだけでコンプレックスや悩みを吹き飛ばせるのなら、こんなに素晴らしいことはない。
これからも世のため人のため、新しい音痴を生み出してやろうじゃないかと改めて決意した。
その一方で国民たちも、エフ氏の発表を待つまでもなく、様々な音痴を自称するようになっていた。
例えばメイクをしてもしなくても代わり映えしない女子の間では『化粧音痴』なる言葉が流行り、非モテ男子はナンパがうまくいかないのは『ナンパ音痴』だからだと主張、さらに主婦の間では『家事音痴』が家事をサボる言い訳になっていた。
いずれにしても、世の中が明るくなったのは間違いなかった。
それまで勉強ができないだとかモテないだとか悩んでいたのが、生まれつき音痴なだけだと胸を張れるようになったのだから。
こうしてホニャララ音痴は世間に広まり、ごく当たり前に使われるようになった頃。
とあるカップルがドライブデートを楽しんでいた。
ところが助手席の彼女に気を取られた男が人を轢いてしまう。
事故の原因は完全に男の不注意である。
しかし男は慌てるでもなく、ずいぶん落ち着いた様子だ。
数分も経たないうちに事故現場に警官がやってくる。
「この歩行者を轢いたのは君か?」
「はい、俺です」
「何をしたのか分かっているのか?」
「お巡りさん、俺は運転音痴なんですよ」
男が気軽な口調で答えると、警官もそれまでの厳しい表情が一転してのんきなものに代わる。
「ん、なんだ運転音痴じゃ仕方ないな。次からは気をつけなさい」
男は小さく頷いた。
「じゃあ、もう行っていいですか?」
「ああ、いいぞ。運転音痴なんだから、気を付けて運転するんだぞ」
そのまま走り去って行くカップルの車を見送った後、警官は足元を見下ろした。
「ふん、こいつは歩行音痴だな」と被害者を一瞥する。
そしてその場を立ち去ってしまったのだった。
あとに残されたのは、道路に倒れたままピクリとも動かない被害者だけ……。
(了)