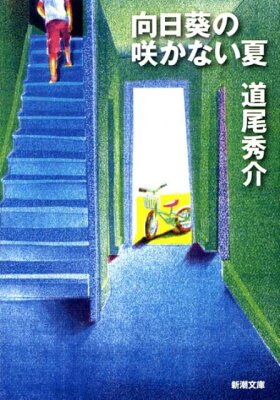一行の描写が伏線になっていて、ラストにたどり着いた瞬間、それまで見えていた風景が全部裏返る。
道尾秀介の小説は、そんな読後のひっくり返しを何度も体験させてくれる。
しかもトリックだけじゃない。そこにあるのは、繊細な心理描写と、痛みを抱えた人間への優しいまなざしだ。
「先が気になる」のに、「読み終わりたくない」。
そんな物語を求めている人には、道尾作品はたまらないはずだ。
ジャンルは幅広い。ホラー、青春、家族ドラマ、日常ミステリ、ちょっと幻想的な話まである。でも、どの物語にも共通して流れているのは、「真実とは何なんだろう?」というテーマだ。
今回は、そんな道尾作品の中から、初めて読む人にも、すでに魅了されている人にもおすすめできる10作品を厳選してご紹介したい。
一度読んだだけでは見えてこないもうひとつの物語が、きっとあなたを待っている。
1.うつくしき詐(いつわ)りの影法師── 『カラスの親指』
誰だって、人生のどこかで間違った角を曲がってしまうことがある。
武沢も、入川も、まひろも、やひろも、貫太郎も。この物語に出てくる連中は、みんなそうだ。転んだまま、立ち上がれずにいた奴らばかりだ。
でも、そんな彼らがひょんなことから肩を寄せ合って、同じ屋根の下で暮らすようになる。詐欺師という、いわば“はみ出し者”たちが、不思議な疑似家族になっていく。
道尾秀介『カラスの親指』は、詐欺を題材にしながらも、根底に流れているのは“優しさ”だ。
詐欺なんて悪に決まってる。しかし、この小説では、その悪の中に、どうしようもなく純粋な悲しみや願い、守りたいものが描かれている。そこがたまらない。
武沢と入川、そして彼らの元にやってきたまひろ、やひろ、貫太郎。五人の共同生活は、騙し騙されの世界とは思えないほど穏やかで、くすっと笑える場面もあるくらい温かい。
壊れてしまった人間たちが、寄せ集まって少しずつ修復されていくような、奇跡みたいな日々が描かれていく。
でも、彼らの中には、それぞれ譲れないものがある。過去に傷つけられたこと、奪われたもの、許せない相手。だからこそ、あるとき彼らは決意する。
「あいつらを、詐欺でひっくり返してやろう」と。
復讐と言えばそうかもしれない。けどこれは、ただの“やり返し”じゃない。自分たちの尊厳を、自分たちの手で取り戻すための、ある種の儀式だ。そしてその手段が詐欺であることが、またこの作品を特別なものにしている。
物語は中盤から一気にギアが入る。そして終盤、すべてをひっくり返すあの〈真実〉。いや、これはもう「トリック」とか「伏線回収」とか、そういう話じゃない。読んだ瞬間、口を開けて固まり、そのあとしばらく天井を見つめてしまう。そういう体験だ。
でも、この作品がすごいのは、ただ読者を騙すだけじゃないところだ。本当に胸に残るのは、トリックの妙でも、構成の巧さでもない。誰かを想ってつく嘘の誠実さ、人と人が寄り添い合うことの意味、つまりは「人間って、悪くないな」と思わせてくれるところだ。
人生は思い通りにならない。選択を間違えることだってあるし、取り返しのつかない過去だってある。
でも、それでも人は、誰かと笑い合える。
同じ鍋を囲んで、ごはんを食べることができる。
過去に折れてしまった心が、もう一度少しだけ形を取り戻すことだってある。
『カラスの親指』は、そんな希望を、〈詐欺〉という仮面の下に隠しながら、そっと差し出してくれる物語だ。
騙されるのも、悪くない。いや、騙されたからこそ、特別なのだ。
2.陽のあたらぬ庭に咲く── 『向日葵の咲かない夏』
夏の終わりには、かならず少しだけ胸が痛む。
あんなに暑かったはずの太陽が、ふいに遠ざかっていくような感覚。蝉の声も、気づけば幻みたいに過去のものになっている。
そんなとき、毎年のように思い出す本がある。
道尾秀介の『向日葵の咲かない夏』だ。
タイトルからして、すでにただならぬ気配が漂っている。向日葵は太陽に向かって咲く花のはずなのに、“咲かない”なんて。
小学四年生のミチオ。夏休みの始まり、終業式の日に訪ねた同級生S君の家。そこで彼が見たのは、首を吊ってぶらさがっているS君の死体だった。
それだけでも衝撃なのに、話はそこからさらにブッ飛ぶ展開になる。死んだはずのS君が、別の“何か”になってミチオの前に現れるのだ。
このあたりで「ん?」と首を傾げる読者も多い。現実なのか、妄想なのか、幻想なのか。境界が曖昧なまま、物語は不穏な空気をたっぷりまとって進んでいく。
S君の依頼は「自分を殺した犯人を見つけてくれ」。ミチオはその依頼を引き受け、調査を開始する。
でもこれは、よくある小学生探偵モノなんかじゃない。むしろ、世界の見え方がまるごと異常で、妙に冷たく、読んでいるこっちまで感覚が麻痺してくる。
この小説のジャンルは一応ミステリーだ。でも読後感は完全にホラー寄り。怖いのは幽霊でも怪物でもない。人間そのものの、壊れ方と不器用さだ。
大人たちは何かを隠している。子どもたちは、無邪気という名の残酷さを携えて、その核心に迫っていく。そしてミチオ自身が、どこかズレていて、どこか冷たい。でも、その歪さこそが、物語全体の奇妙なリアリティを支えている。
トリックの構造も見事だが、それ以上に、なぜそういう結末になったのかという心の闇が、読者をズドンと打ちのめしてくる。
人は、自分の見たいものしか見ない。自分の正しさでしか世界を測れない。
『向日葵の咲かない夏』は、そうした人間の限界を、ミステリの構造の中に巧妙に織り込んでくる。
読み終えたときに残るのは、「謎が解けた!」という快感じゃない。むしろ、「この物語から出られない」という閉塞感だ。
夏は終わった。
しかし、あのとき確かに、陽の当たらない場所に、咲いていた気がするのだ。
一輪の向日葵。
誰かに気づいてもらいたくて、ずっとそこにいた、小さな哀しい花が。
3.鍵は、どこにも見当たらなかった── 『スケルトン・キー』
夜が深まってくると、どうして人は黒に惹かれるんだろう、と思う。
明るい物語も嫌いじゃない。でも、自分のどこかにある陰の部分に触れてくるような話に、不思議と惹きつけられてしまう瞬間がある。
道尾秀介の『スケルトン・キー』は、まさにそんな一冊だ。
初期の道尾作品が持っていた冷たさ。あの静かに壊れていく人間関係や、ぞわっとする違和感。最近の穏やか系もいいが、個人的にはずっと、この黒い道尾の復活を待っていた。
で、これはその「帰還」みたいな一作である。
主人公は、自分をサイコパスだと自認している青年。児童養護施設出身で、良心とか罪悪感とか、そういうものが自分にはないと、はっきり認識しているタイプだ。
そう聞いただけでもう不穏だが、道尾はその設定を全くあざとく使わない。むしろ、異常性を日常の中にぬるっと紛れ込ませてくる。その気持ち悪さが、たまらない。
序盤はひっそりと進む。なのに、どこか引っかかる。違和感がある。読者だけがわかる「ズレ」がある。でも、これがただのサイコサスペンスで終わらないのが道尾秀介だ。
中盤で、あの反転がくる。たった一文で、今まで信じてた全てが揺らぐあの感覚。あれは本当にすごい。気づけば、認識がぐるっと裏返されてる。しかも、それがご都合じゃなくて、しっかり伏線の上に成り立ってるからこそ、読後にめちゃくちゃ納得してしまうのだ。
そして終盤。「スケルトン・キー(万能鍵)」が開けてしまったのは、扉じゃない。人の心の奥底にしまわれた、哀しみや孤独、欲望といった触れてはいけなかったものだ。
開いた先には、救いもある。でも同時に、もう元には戻れないという後味の悪さも残る。誰かが解放された気もするけど、別の誰かは閉じ込められて終わったようにも感じる。そういう複雑な後味を、道尾は絶妙な筆致で描いてくる。
読後、本を閉じたとき、なぜか鉄の扉が音もなく閉じたような気がする。あの鍵は、自分の中のどこに触れたんだろう。そう思ったとき、自然と最初のページに手が伸びる。
「もう一度、確かめなきゃいけない気がする」
これは、そういう物語だ。一度読んだら終わりじゃない。何度でも読み返して、何度でも気づかされる。
道尾秀介の〈黒〉が帰ってきた。『向日葵の咲かない夏』や『骸の爪』が好きな人は、たぶんこの作品にゾクゾクするはずだ。
開ける覚悟があるなら、どうぞ。
でも気をつけてほしい。
その鍵は、あなた自身の閉じた部屋まで開けてしまうかもしれないから。
4.風が、そっと手を伸ばすとき── 『風神の手』
その写真館は、生者のためじゃない。
死者のために写真を撮る、「遺影専門」の写真館だ。
『風神の手』は、そんな少し奇妙な場所から物語が始まる。忘れられた町の片隅、「鏡影館」という名の写真館。しかしここに写るのは、ただの遺影じゃない。
それは、とある〈嘘〉を起点にした、いくつもの人生の枝葉をつないでいく、優しい奇跡の記録でもある。
この小説は、いきなり連作短編集のように進む。女子高生と年上の青年が、ふとした出会いから生まれる甘くて苦い関係。次の章では、少年たちが遭遇する不思議な事件。さらに老いた兄弟の秘密。どれも一見バラバラに見えるが、ページをめくるごとに「これは、さっきの……」となっていく。
そう、これは断片的に進む長編ミステリなのだ。どの章も、それぞれドラマとしてしっかり面白いのに、読み進めるとそれらが少しずつ絡まり、やがて一本の風の道すじとしてつながっていく。
バラバラだった風景が、読み終えたとき「一枚の写真」に収まっているような感覚。いや、「一冊の遺影」と言った方がふさわしいかもしれない。
ここに登場する事件は、誰かが死ぬとか、密室で殺されるとか、そういう派手なものではない。しかし、何気ない言葉、ほんの小さな嘘が、ときに人の運命を変えてしまう。
道尾はずっと〈嘘〉というテーマを書き続けてきた作家だが、本作はその集大成のようにも見える。人を傷つける嘘もある。けれど、誰かの痛みを和らげる嘘もある。それが、未来へと風のように吹いていくことだって、あるのかもしれない。
伏線も巧妙だ。何気なく読み飛ばしていた描写が、別の章でとんでもない意味を持って立ち上がってくる。その瞬間、読者は前の章に戻って再読し始める。まんまとやられるのだ。気づいたときには、もう手遅れ。
でもこれは仕掛け小説である以上に、人の物語だ。人生の終わりに遺された一枚の写真。誰かがほんの少しだけ優しくあろうとしたこと。そこに確かにあった誰かの思い出。そういうものが、嘘や真実や時間を越えて、そっと他人の人生を救っていく。
風神の手は、その象徴なのかもしれない。
ラストの数章は圧巻だ。いくつものピースが迷いなく嵌まっていく。その光景に泣きそうになる。
道尾秀介の優しいミステリが読みたい人に、本作はぴったりだ。もちろん、ちゃんと騙されたい人にも、十分すぎるくらいの仕掛けが待っている。
でも一番の見どころは、やっぱり「人を信じたい」という気持ちの強さだ。
写真に残された姿は、死んでしまった人のためのものかもしれない。
でも、そこに込められた想いは、確かに生きている人の未来を、そっと変えていくのだ。
5.夏が終わる、その少し前に── 『ソロモンの犬』
夏の午後、蝉の声。アスファルトの熱。それらをかき分けて駆け抜けていく、一匹の犬。すべては、そこから始まった。
道尾秀介『ソロモンの犬』は、大学生4人のひと夏の経験を通して、「真実とは何か」「善意とは何か」を語りかけてくるミステリだ。
登場するのは、どこにでもいそうな大学生たち。秋内、京也、ひろ子、智佳。彼らの日常は、ごくありふれていて、ごく穏やかだ。だが、ある日、助教授の幼い息子が飼い犬に殺されるという事件が起きた瞬間、世界の輪郭が少しずつ歪み始める。
はじめは違和感だった。しかし、その違和感が少しずつ大きくなり、やがて物語は、ゆっくりと読者を追い詰めていく。
この作品の怖さは、殺人の陰惨さでもトリックの奇抜さでもない。「誰かの善意」が、別の誰かを傷つけてしまうことのリアルさだ。
読者は途中できっと思う。「ああ、もう犯人分かったかも」と。だが、それすらも著者の仕掛けの一部。読み終えたあと、足元の床がスッと抜けていくような、あの道尾作品ならではの反転が待っている。
それと同時に残るのは、青春特有の鈍さと痛みだ。善悪の判断がグレーに滲み、人間関係の距離感が曖昧なまま事件に巻き込まれていく感覚。あの、若さゆえの無神経さと過剰な真剣さが、リアルで苦しい。
そして、物語の中で鍵を握るのが、一匹の犬。人間の矛盾と迷いをよそに、まっすぐに主を信じるその姿が、とにかく切ない。純粋さとはなにか。信頼とはどこまで成り立つのか。犬はその存在だけで問いを突きつけてくる。
謎を解くための物語、ではない。人を理解するための物語である。どれだけ相手を知ったつもりでも、どれだけ真相に迫ったつもりでも、ほんの小さな思い込みひとつで、すべては崩れてしまう。
終盤、真相が明かされたとき、「そうだったのか」よりも、「あの瞬間の言葉、あれが全部だったのか……」と唸ることになる。
タイトルの『ソロモン』とは、あの賢王のことだ。知恵と裁きの象徴。その名前が示すのは、つまり「誰もが真実を知っているとは限らない」ということなのかもしれない。
何気ない日常に潜む小さな歪み。若さゆえの判断ミス。ほんの一歩の踏み外し。
それらが積み重なったとき、人はどこにたどり着くのか。
その答えを、この物語は淡々と、しかし深く描いている。
6.すべては雨のせいにして── 『龍神の雨』
冷たい雨音が、すべてを覆い隠す夜がある。
言葉にできない痛みも、あの日の怒りも、胸の奥でくすぶる寂しさも、雨が溶かしていく。
道尾秀介『龍神の雨』は、そんな心の水底にまで染み込んでくるような物語だ。
物語の中心にいるのは、添木田蓮と楓。血は繋がっていないが、兄妹として同じ家に暮らしている。対になるように登場するのが、溝田達也と圭介という、こちらも血の繋がらない兄弟。どちらの家庭も、決して幸福とは言いがたい。むしろ、闇や傷を抱えたまま、それでもなんとかやり過ごしてきた、という感じだ。
彼らの人生が交差するなかで、物語は、ただのサスペンスでは終わらないと予感させる。誰かが誰かを騙しているわけではない。でも、誰もが自分自身に嘘をついている。
そこがこの作品の妙だ。事件やトリックの背後に、もっと深くて、もっとやっかいな人の心が見え隠れしている。
たとえば、愛し方がわからないまま大人になった父。傷を黙って飲み込み、頼られたときだけふっと笑う兄。自分の存在理由を見つけられずに揺れる弟。すべてを悟ったようで、実は泣きたがっていた妹。
誰もが、どこか壊れている。でも、だからこそ共鳴する。
この物語のいちばんの魅力は、伏線の巧妙さでも、トリックの鮮やかさでもない。人間という曖昧で不器用な生き物を、驚くほど丁寧に描いているところだ。
雨は単なる背景じゃない。登場人物たちの内側とシンクロしながら、過去も痛みも濡らしていく。読むうちに、雨そのものが語り手になっているような気すらしてくる。
中盤から終盤にかけて、視点が切り替わり、事実の輪郭が少しずつ明らかになっていく。そのたびに、「そうだったのか」と驚かされ、「あれはああいう意味だったのか」と切なさが胸に刺さってくる。
事件を追うというより、「赦し」を探していく物語だ。
なぜ、そんな行動をとったのか。なぜ、心がすれ違ってしまったのか。そうした問いに、派手な答えはない。でも、じんわりと、にじむように、そこに答えのようなものが立ち上がってくる。
ラストには、確かに「救い」がある。もちろん、それは完全な幸福なんかじゃない。でも、生きていくには、十分な希望だ。
タイトルにある「龍神の雨」が象徴しているのは、祟りや伝説なんかじゃない。むしろ、人が過去と向き合うために必要な雨だ。嘘も怒りも後悔も、すべて洗い流す時間の象徴なのだろう。
物語を読み終えたあと、ふと窓の外の雨音に耳を澄ましたくなる。
誰かの嘘の裏にある真実を、もう少しだけ信じてみたくなる。
この物語には、それだけの力がある。
7.騙し絵の中の真実── 『ラットマン』
世界ってのは思ってる以上に歪んでる。まっすぐ見てるつもりでも、視界の端に何かがちらりと映る。
それがただの錯覚なのか、あるいは見てはいけないものなのか。その判断すら、たぶんわたしたちは間違っている。
道尾秀介『ラットマン』は、そんな目の曇りと心のすれ違いを、極限まで追い込んでいくミステリだ。読者の「見る力」「読解力」「思い込みの強さ」すべてを試しにくる。
タイトルの「ラットマン」は、〈騙し絵〉を意味する。つまりこの作品は、最初から「あなたは、どうせ騙されますよ」という前提で書かれてるのだ。
出てくる人物は、誰も嘘をついてない。いや、正確に言えば、誰も嘘をついてるつもりはない。しかし、それでも真相はどこかに隠れている。誰もが何かを誤解していて、そしてわたしたちもその中に巻き込まれる。
主人公・姫川亮。姉が失踪し、姉の恋人が死ぬ。そのふたつの事件が交差し、過去と現在がゆるやかにねじれながら接続されていく。一見すると、家族の問題を抱えた青年が、少しずつ事実に近づいていく話に思える。
しかし、すぐに気づく。
この話、何かがおかしい。
事件そのものよりも、その周囲でうごめく人間の感情の揺らぎ。そこがこの作品の核心だ。
誰かの優しさは本物か? 誰かの沈黙は秘密か、それとも絶望か? 誰かの信頼は、愛なのか、依存なのか?
登場人物の行動には必ず理由がある。でも、その理由が読者に明かされるとは限らない。道尾秀介はそこを容赦なく突いてくる。この作品では、すべての説明が遅れてやってくる。でも、その遅れが、逆にリアルだ。人間というのは、そう簡単に自分の中身を見せたりしない。
ミスリードはある。でも悪意はない。むしろ「あなたが勝手に信じたんでしょ?」とでも言いたげな仕掛け方だ。
読者の側に、勝手な決めつけ、都合のいい読解、目に見えたものだけを信じるクセがある限り、何度でも騙される。
だからこそ、終盤のある視点の回収が効いてくる。その瞬間、読者は自分の目と脳が、いかに偏っていたかを思い知らされるのだ。
伏線はある。でも、目立たない。むしろ「何気ない会話」「一瞬の表情」「空気の流れ」みたいな曖昧なところに、静かに埋まっている。読者が見落とせば、物語は見誤る。
それでも作者は、手を差し伸べてこない。ずっと黙っている。それが怖い。でも、気持ちいい。
読了後、間違いなく最初のページに戻りたくなる。「これは、こんな意味だったのか」と震えながら読み直すことになる。
それこそが、『ラットマン』という騙し絵の完成形だ。
人間の目は万能じゃない。いや、むしろ「見たいものしか見ない」のが人間だ。
『ラットマン』を読み終えたとき、あなたは思うだろう。
「もう道尾作品には騙されない」と。
でも、それはきっと、次の騙し絵の入口にすぎないのだ。
8.影は語る── 『シャドウ』
夕暮れどきの影は、妙に物言いたげで、でも結局なにも語らない。確かにそこに輪郭はあるのに、手を伸ばしても、するっとすり抜けてしまう。
道尾秀介の『シャドウ』は、まさにそんな感触の物語だ。小説というより、影そのものを読まされているような感覚になる。
主人公は小学五年生の凰介。母を亡くし、父とふたりきりの生活が始まる。まだ子ども、されど子ども、という絶妙な年齢だ。
「人は死んだらどうなるの?」
その問いかけが、この物語の始まりであり、終わりでもある。素朴な言葉に見えて、実はかなり根が深い。この一言が、凰介の中に影のように居座り続けることになる。
物語の舞台はどこにでもある町。事件が次々起こるわけじゃない。派手なトリックも、血が飛び散るような展開もない。でも、どこかおかしい。こちらの神経をゆっくり侵食してくる不穏さがある。
友達の母が自殺する。その出来事を境に、凰介の世界は少しずつ歪みはじめる。「平穏に生きていきたい」という願いは、あっさりと、そして理不尽に奪われていく。
しかもこの小説、視点がころころ変わる。凰介だけじゃない。子ども、大人、被害者、加害者。彼らはみんな、自分の言葉で、自分の正しさを語る。そして読み手はそのたびに、揺さぶられる。
「今まで読んできたの、ほんとに正しい話だったのか?」と、何度も立ち止まらされる。
それが道尾作品の怖さであり、面白さだ。
真相が明かされたとき、「そういうことだったのか……」と、思わず息を呑む。でも、それはトリックの鮮やかさに驚くのではない。人間の“見えなさ”。そこに驚くのだ。
そして気づく。
冒頭の「人は死んだら、どうなるの?」という問い。あれは単なる哲学的なお遊びなんかじゃなかった。あの一文が、この物語のすべてだったのだ。
『シャドウ』の読後感は、決して軽くない。でも、ただ重たいだけでもない。
影があるのは、光があるからだ。その事実に、最後の最後でふっと気づかされる。哀しさと、あたたかさが、同じ重さで心に残る。
派手なミステリーに飽きた人にほど、ぜひ読んでみてほしい。仕掛けの巧さはもちろん、心理描写のきめ細かさ、語りの構造、そのすべてが“道尾らしい”。
きっと、あなたの中にある影にも、そっと触れてくるはずだ。
9.声という名の仮面を脱ぐとき── 『透明カメレオン』
人とは、自分の〈声〉をどこまで信じているのだろう。
喋ってる内容だけじゃない。響き、トーン、沈黙、全部ひっくるめて、それがその人自身を伝えてる。
だけど、その声すらも、時に嘘をつく。誰かのために、あるいは自分を守るために。あるいは、何かを隠すために。
道尾秀介の『透明カメレオン』は、ラジオパーソナリティという声の仕事をしている主人公・恭太郎の物語だ。彼は特別な声を持っていた。でも、それが仇になる。目立つくせに、自分を見せない。「声」だけで生きてきた男は、まるで透明なカメレオンだった。
ある日、そんな彼の前に、ひとりの女が現れる。ファンを名乗る恵。彼女が抱えていたのは、とんでもない「計画」。優しさと怒りと、深くて暗い過去が入り混じった、爆弾みたいな女だった。
恭太郎は、知らぬ間に巻き込まれていく。でも、巻き込まれた理由は、彼自身の弱さでもあった。強く拒めなかったのは、優しさゆえか、それとも逃避か。そこがまた、人間くさくていい。
ここから先は、ちょっとした逃走劇になる。でもこの作品は、単なるサスペンスに留まらない。スリリングなのに、やけに切実で、どこか優しい。
道尾作品らしい緊張感はある。しかし、その核心は「事件」じゃない。むしろ問われているのは、「あなたは、自分の輪郭をちゃんと見てるいか?」ということだ。
恭太郎は、自信のない男だ。流されがちで、いつも控えめ。でも彼は、決して空っぽではない。むしろ、空っぽに見せることで、生き延びてきたやつだ。
その彼が、最後に放つ“ひとこと”。その「声」は、誰かを救い、誰かの人生を変える。まさに、透明だった男が“実体”を持つ瞬間だ。
『透明カメレオン』は、他の道尾作品とはちょっと違う。どんでん返しもないし、壮大なトリックもない。あるのは、ひとりの男が「自分自身」とちゃんと向き合うまでのドラマだけだ。
でも、それがめちゃくちゃ沁みる。この静けさは、作家としての「確信」がないと書けないやつだ。
カメレオンは、保護色で身を守る。しかし、ずっと隠れてばかりじゃ、どこにも行けない。恭太郎は、自分の〈声〉で、その殻を壊した。
声という仮面の奥に隠していたほんとうの顔。
そこに触れたとき、きっとあなたも、誰かの声をもう一度、大切に聞きたくなるはずだ。
この物語を読むすべての人に、優しい真実がそっと届きますように。
10.背中に棲むもの── 『背の眼』
誰かの背中を見つめるとき、つい感情を重ねてしまうことがある。
うなだれた肩の丸み、言葉を飲み込んだ沈黙。そこに何かが「見ている」としたら。それはきっと、不安という名の異物だ。
『背の眼』は、そんな得体の知れない気配から幕を開ける。心霊写真に写った、背中の「眼」。それを境に、写真に映っていた者たちが次々と不可解な死を遂げていく。
この設定だけでもう、寒気がする。だが本作の恐ろしさは、ただの怪談では終わらない。現実と地続きの地面から、気づけば読者の足元をすくってくる。ゆっくりと、冷たい手で。
登場するのは、作者・道尾秀介自身をモデルにした語り手と、心霊現象を探究する民俗学者・真備。このふたりのコンビが、霊と科学、信仰と懐疑の狭間を突き進んでいく。
ありがちなオカルト探偵ものに見えて、違う。この物語の魅力は、ホラーとミステリの境界線を、ぶれることなく歩いている点にある。怖さは「幽霊が出るから」ではなく、「なぜ、そう見えてしまったのか」という心の構造に宿っているのだ。
上巻では、やや冗長にも思える会話や回想が続く。だが、油断してはいけない。その何気ないセリフや表情の中に、あとで効いてくる毒がしっかり仕込まれている。
そして下巻。霧が晴れるように、点と点が繋がっていく。もちろんトリックも用意されている。だがそれ以上に印象に残るのは、「心の闇を、誰かに見られたくない」というごく人間的な願いだ。
背中に眼があるという不気味なビジュアルは、単なる怪奇ではない。「見られたくないものがある」という人間の内面と、どこかで呼応している。つまりこの作品は、他者から見られることへの恐怖をグッと突きつけてくるのだ。
タイトルにもなっている『背の眼』は、トリックの中心にあるギミックであると同時に、テーマそのものでもある。見えないけれど、確かにそこにあるもの。見ようとしなければ、決して見えないもの。
これが作家・道尾秀介のデビュー作だというのだから恐れ入る。ホラーに逃げず、ロジックに耽溺せず、その両方に真剣に向き合っている。そしてその語り口は、妙にリアルで人間くさく、読後には「自分の背中」にも何かの視線を感じてしまうほどだ。
シリーズ化された真備シリーズの幕開けとしても、これは非常に強い一作だ。ミステリ好きにもホラー好きにも、まっすぐ突き刺さる。
読み終えたあと、ふと鏡を背にするのが怖くなる。
そんな感覚を味わいたいなら、ぜひこの作品に足を踏み入れてほしい。
おわりに── 物語は、読み終えたあとに始まる
道尾秀介の小説は、「ラストで驚いた!」「騙された!」だけでは終わらない作品ばかりだ。
むしろ、本当の読書体験は、ラストを読んだ“あと”に始まる。
伏線の意味に気づき、思わずページをめくり直す。あのときのセリフが、まったく別の感情をまとって見えてくる。そして、登場人物たちの選択に、不意に胸を締めつけられる。そういう後味こそが、道尾作品の真骨頂である。
今回ピックアップした10作品は、その多面性をしっかり味わえるラインナップだ。
切なさが滲む青春劇もあれば、家族の中にひそむ暗い秘密もある。心をじわりと締めつける心理サスペンスや、幻想をほんの少しまとった語りもある。
どの物語にも共通しているのは、「人はなぜ、そんな選択をしてしまったのか?」という問いへの誠実なまなざしだ。
読み終えたあと、言葉にならない感情が心の中に根を下ろしていく。ページを閉じたはずなのに、まだ物語が終わっていないような感覚。その余韻が、ずっと残る。
どこから読んでもいい。どれを最初に手に取ってもいい。
大切なのは、その物語がきっと、あなた自身の見る目を少しだけ変えてくれるということだ。
あなただけの「もう一度読み返したくなる一冊」が、この中にあると信じている。