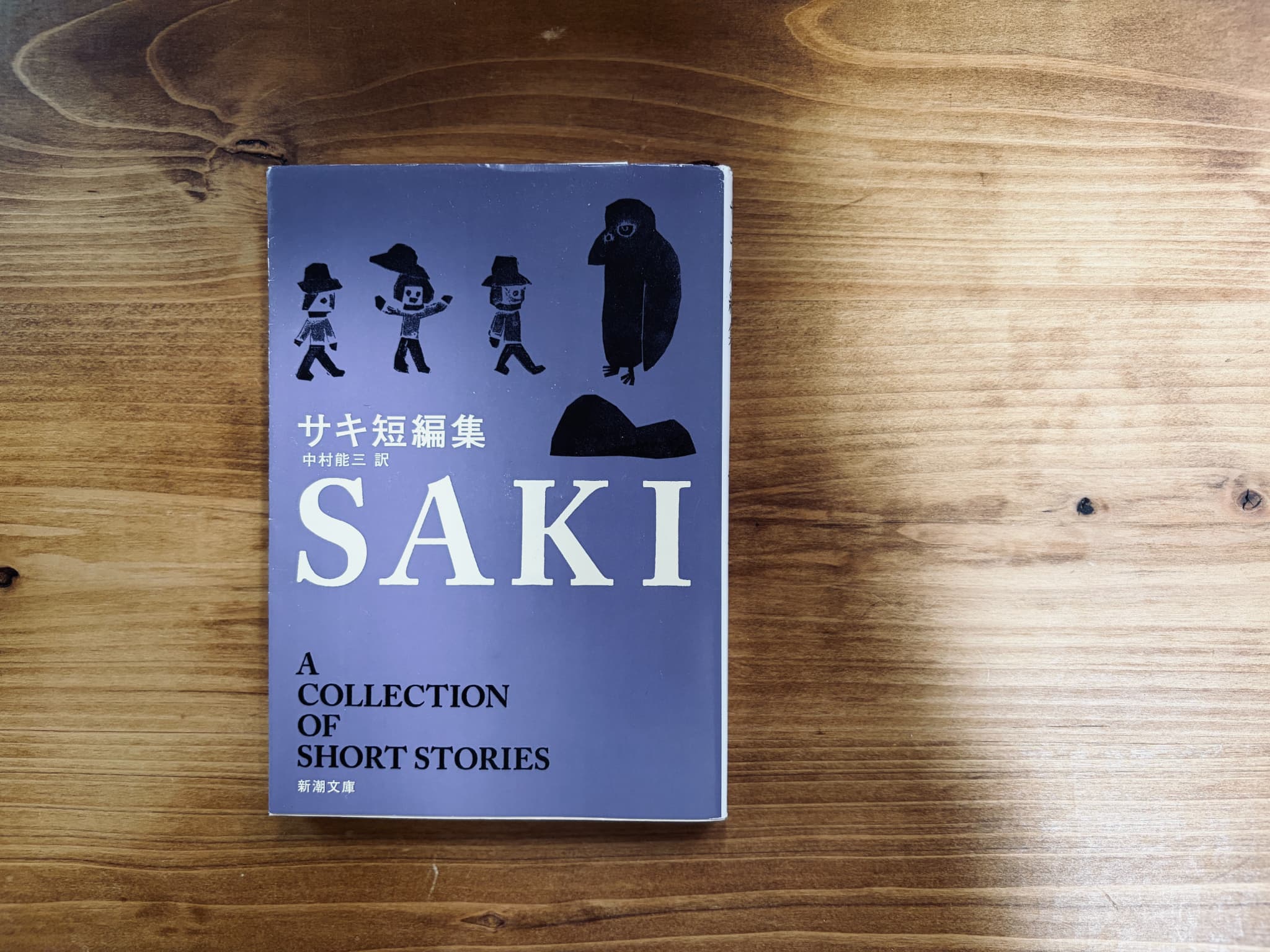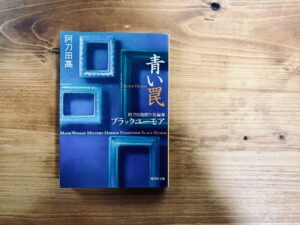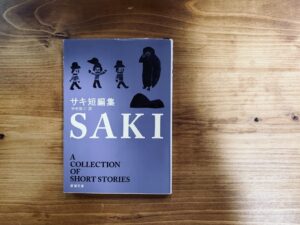ホラーでもない。怪談でもない。
けれど、読んでいると確かに怖い。
ジャンルの枠にきっちり収まる作品もいいけれど、たまにはその枠ごと吹き飛ばしてくるやつに出会いたくなる。
そんなとき脳が勝手に反応してしまうのが、20世紀イギリスの最も分類不能な作家、ロバート・エイクマンの短編だ。
その代表的短編集『奥の部屋:ロバート・エイクマン短篇集(ちくま文庫)』は、読み終えても何も解決しないまま頭を抱えつつ、けれど猛烈に「もう一度読み返したい」と思ってしまう不思議な作品だ。
読み始めたときの期待を裏切るでもなく、かといって応えてくれるわけでもない。それどころか、こちらの予測なんて最初からお見通しで、あざ笑いながら道なき道へ突き落としてくる。
エイクマンの短編群は、そんな読者不在の物語のような空間を持っている。そこにはフェアな謎解きも、感動的な結末もない。
でも、妙に忘れられない。
これってもしかして恋では?
いや、悪夢だろうか。
怪奇小説でもホラーでもない、あるいはその両方

イラスト:四季しおり
まず最初に断っておきたいのは、エイクマンの作品をホラー小説だと思って読むと、たぶん面食らうということだ。
幽霊はなかなか出てこないし、殺人事件もない。バケモノも説明もオチもない。なのに、ページを閉じた後、変な汗をかいている。そんな読書体験を提供してくるのが、この人である。
ロバート・エイクマン(1914-1981)は、もともと怪奇小説を書こうと思っていたわけではないらしい。というより、彼は自作を「Strange Stories(奇妙な物語)」と呼んだ。
怪談じゃないし、モンスターも出てこないけれど、読むと心の奥に変なものが残る、そんな物語たちのことだ。
さらに彼自身は、イギリス国内の運河保存活動に人生を捧げた水路オタクでもある。地図に載らない水路をボートでゆっくり進む、そんな体験がエイクマンの物語の根底にある「場所の記憶」や「時間の歪み」につながっているように思う。
地図に森なんて書いてなかった、でもある、そんな場所が彼の小説では当たり前に現れるのだ。
ちくま文庫版『奥の部屋』はこう読むべし
さて、この『奥の部屋』だが、実は日本では2回出版されている。最初は1997年に国書刊行会から、そして2013年にちくま文庫から。
オススメは断然ちくま文庫版だ。なぜなら、国書版では読めなかった2編の傑作が追加されているから。
収録作は以下の通り(発表年は英語圏での初出)
- 『学友』(1964)
- 『髪を束ねて』(1964)
- 『待合室』(1964)
- 『何と冷たい小さな君の手よ』(1966)
- 『スタア来臨』(1966)
- 『恍惚』(1968)
- 『奥の部屋』(1968)
見ての通り、1960年代中期、エイクマンの創作全盛期に集中している。
いわゆる〈奇妙な味〉が完成された時代だ。

翻訳はすべて今本渉氏によるもので、これがまた絶妙。エイクマンの「言わないことで怖がらせる」文体を、日本語の余白で巧みに再現している。
原文のあの得体の知れない不安が、ちゃんと日本語でも襲ってくる。しかも解説がしっかりついていて、読み終えた後のこれは何だったのか?という放心状態に少しだけ光を当ててくれる。
何も解決しないことがもたらす快感
収録されている7つの短編を簡単に紹介していこう。
『学友』
再会したかつての学友が、別人のようになっていたら? そんな不穏なプロットから始まるのがこの一篇。
語り手は女学校時代の同級生サリーと再会するが、彼女はどこか感情の通わない存在となっており、広大な屋敷には何かが澱んでいる。
この物語では、幽霊が登場するわけではない。それでも読後に残るのは、何かに取り憑かれたような恐怖だ。知性という無機質な存在が、人格を喰っていくさま。蔵書に埋もれて生きる者の孤絶。
そして終盤に現れるよくわからない男の存在が、物語を決定的にねじれさせる。
家というよりも、知識そのものが迷路と化したような不安な読書体験。ミステリで言うなら、あらゆるヒントが出ているのに、真相が組み上がらない感じに近い。
『髪を束ねて』
婚約者とともに田舎の村を訪れた女性クラリンダが、村の閉鎖性と異様な風習に巻き込まれていく。設定だけならありがちな田舎ホラーなのだが、エイクマンの手にかかるとそれはただの恐怖では終わらない。むしろ、そこに満ちているのは生命力と脱構築である。
タイトルの『髪を束ねて』は、女性性の抑圧、理性の象徴のようにも読めるが、物語が進むにつれて、そうしたシンボルがどんどん反転していく。
登場するのは、人なのか獣なのかわからない存在たち、通じているようで通じない会話、そして迷路と呼ばれる謎の場所。
全体を通じて、理性で武装した現代人が、古層の宗教的・性的エネルギーの奔流に飲まれていくような感覚がある。土俗ホラーやフォークホラーの先駆でありながら、エイクマンはそれをあえて神秘化しない。
むしろ生々しい。理性が敗北する瞬間がちゃんと描かれているのがキツい。
『待合室』
仕事帰りに列車を乗り過ごした男が、寒村の駅で次の便を待つことになる。それだけの話なのに、なぜこんなに怖いのか。
舞台は夜の待合室。照明は薄暗く、駅員も頼りなく、男は一人、椅子に座って時を過ごす……はずだった。
この短編の凄みは、「何かが起こる」ことではなく、「起こってしまったかもしれない」という曖昧さを終始漂わせ続けるところにある。しかもそこにあるのは、血の気配や足音ではなく、場所そのものの記憶なのだ。
誰もいない空間に、かつていた誰かの気配が満ちていく感覚。読んでいて、空間そのものが動いているように思えてくる。
現代の都市伝説的なホラーにも通じる、境界空間=リミナル・スペースの不安感を先取りした作品。最も怪談寄りでありながら、最も文学的な後味を残す。
『何と冷たい小さな君の手よ』
ある日、電話が鳴る。出てみると、知らない女の声。
彼女はとりとめもなく語り、語り手である男はなぜかその声に惹かれていく。電話のやりとりはエスカレートし、男はその声の正体にのめり込んでいくが、相手は決して会おうとはしない。
この作品は、声しか存在しない相手との奇妙な関係を描いた、いわば電話版ゴーストストーリーである。だが、そこには霊というよりも、テクノロジーが作り出した空虚がある。過去の時間、断絶された身体、歪んでいく現在。
25年前の記憶が通話の中に入り込み、現在の男の生活はどんどん痩せ細っていく。SNS依存、ひきこもり、音声メディア中毒……現代にも通じる孤立と接続のトラウマを予見していた一作と言ってよい。恋愛や救いの構造がまったく機能しない物語である。
『スタア来臨』
伝説の女優アラベラが地方劇場にやってくる。それだけで地元の人々は沸き立つが、彼女の登場はまるで吸血鬼のように周囲の生命力を奪っていく。スタッフたちは疲れ果て、空気は異様に冷え、舞台は彼女の支配下に置かれていく。
古典的なゴシックホラーの構造を、演劇という人工空間に持ち込んだ実験的作品。アラベラは血を吸わないが、観客の視線と共演者の才能を吸い取って若さを保つ存在のように見える。
物語の舞台全体が、現実なのか演出なのか分からなくなる終盤の展開は圧巻。演技することが呪いとなり、芸術が死に直結するというモチーフは、他の作家にはなかなか真似できない境地に達している。
『恍惚』
語り手の青年は画家志望。ある画家の未亡人を訪ねたことから、奇妙な体験をする。舞台はブリュッセルのアール・ヌーヴォー様式の豪邸。
そこに住むマダム・Aは、美の精霊でもあり、堕落の象徴でもあるような存在。彼女のもとで、語り手は芸術の真の姿を味わうことになる。
この物語は、エイクマンの中でも最も露悪的で倒錯的な一篇だ。美の追求がどこまでも不快にねじれる。観賞ではなく堕落、創作ではなく服従。若者の創造的可能性が、老いた魔女の支配のもとで粉々に砕かれる様は、まさにマゾヒズムの極北。
ラヴクラフトが知ってはならない真実に触れて狂気に至るように、この物語の語り手もまた、芸術の本性に触れて壊れる。しかもそれが、超自然でも神でもない人間の肉体によってもたらされるという地獄。
『奥の部屋』
表題作にして、間違いなく本書の中核をなす傑作。少女レーネがもらった豪華な「人形の家」には、妙な違和感があった。
外見の大きさに比して、内部の部屋数が合わない。つまり、見えない部屋がある。数十年後、レーネはある森の中で、その人形の家とそっくりな屋敷に出会う。
この作品は、象徴と物理が一体となって現れる構造の美しさが際立っている。子ども時代に刷り込まれた何かが、人生の後半に実在として立ち現れるときのぞっとする感じ。人形の家という安全な小宇宙が、いつのまにか監視者に変貌している。
不気味なドイツ語の慣用句、意味のわからない大人の会話、身体に染みついた恐怖。それらが「奥の部屋」という入ってはいけない空間にすべて閉じ込められ、最後にその扉が開く……。でも何があるのかは分からないし、分からないままで怖い。
子どものときに理解できなかったものが、大人になってから現実に現れる。象徴と現実がぐちゃぐちゃになっていく感覚が圧巻。
読んでも理解できないことがご褒美

この作品集を読んで、「結局どういう話なの?」と頭をかしげる人もいるかもしれない。
安心してほしい、私もよくわからない。
だが、そこがいい!
エイクマン作品は、分かる人にしか分からない、なんてケチくさいものではない。むしろ分からないままでも魅了されることが、読む側にとっての最高の体験なのだ。
たとえばミステリでは、犯人が明かされないと怒る人もいるだろう。でもエイクマン作品は最初から「犯人なんていない」し、「事件だったのかどうかも不明」なのだ。なのに、無性に引き込まれてしまう。これはもう一種の美学的拷問である。
エイクマンの技法は、情報のカット、象徴の多義性、夢の論理など、伏線回収に慣れた読者にとっては反則の連続だ。
でも、だからこそ読後に残るのは感情ではなく、感触なのである。ざらざらしてて、どこか湿っていて、でも目が離せない。
終わらない物語、終わらせない体験
ロバート・エイクマンの『奥の部屋』は、読み終えても読了感が来ない本だ。
エピローグがない。カタルシスもない。でも、それこそが彼の作風なのだと思う。読んでいるこちらが、この先を考えざるを得ない構造になっている。
誰の家にもあるかもしれない「奥の部屋」。その部屋にはドアがなく、でも音がする。入れないのに誰かがいる気配がする。
そんな空間が、エイクマンの物語にはいくつも登場する。
そして困ったことに、それは私たちの心のどこかにも確実に棲みついてしまう。
どうか、この本を開くときは注意してほしい。
あなたが本を読んでいるとき、本もまた、あなたの内面にある「奥の部屋」を覗き込んでいるのだから。