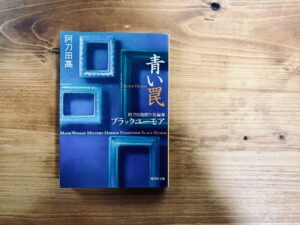ホラー小説には、大きく分けて二種類あると思う。
一つは、どこか遠くの不気味な世界で起きる超常的な恐怖を描くもの。
もう一つは、もっと身近な日常にひたひたと侵食してくるタイプのやつ。
雨宮酔『夢詣』は、まさにその後者、しかもその中でも一線を画するほど、悪夢的で容赦がない。
そしてこの作品の恐怖は、「眠ること」そのものを敵にする。つまり生きている限り、絶対に逃げられないということだ。
「その悪夢を見た者は死ぬ」
いかにもJホラーっぽいキャッチコピーだけれど、問題はその夢が現実にまで影響を及ぼしてくることにある。そうなると、もはやこれは心霊現象ではない。精神科医すら巻き込まれる、知と生理の両方をえぐる物語なのだ。
そんな異質な悪夢の構造が、この作品には驚くほど論理的に描かれている。舞台設定も主人公も現代的で、構成は二人の主人公による二重プロット。にもかかわらず、読後の心に残るのは「因習」と「儀式」、そして「人外の気配」。
つまりこの作品には、最先端と最古代が同居しているのだ。
二本の線が収束するとき、夢は現実になる

絵:四季しおり
この作品の大きな特徴は、二人の主人公による視点の切り替えだ。
精神科医の紙森千里と、オカルトライターの伊東壮太。科学と非科学、論理と直感、冷静な観察と突撃取材。性格も立ち位置も真逆なこの二人が、物語の中でだんだんと交差していく。
千里のパートでは、謎の夢を見た末に死亡した患者たちの存在から話が始まる。彼女はプロの医師として、悪夢なんて非科学的なものを信じない。最初はストレスとか脳の信号とか、そういう方向で原因を探ろうとする。でも、患者の体から人間じゃない血液が見つかった時点で、もうそれどころじゃない。
しかも、その悪夢は彼女自身にも感染してしまう。夢の中で宣告される「順番」が、爆弾のカウントダウンみたいに効いてくる。
一方、伊東は都市伝説〈呪夢〉を追っていて、過去に夢に殺されたという噂のルポライターが残した謎のメモを手がかりに調査を開始する。そこで浮かび上がってくるのが、「夢詣」と呼ばれる儀式の痕跡だ。
千里が巻き込まれ型だとしたら、伊東は突っ込んでいく型の主人公。この二人の動きが中盤で交わり、共闘する展開になるのだが、ここからが本作の加速タイム。サスペンス、ルポ、儀式、夢の密室……とにかく次から次へと怖さの位相が変化していく。
トリックのある本格ミステリというよりは、「謎のルールにどう対処するか」というサバイバル型の構造に近い。ただし、そのルールが理詰めで成立しているから、ちゃんとミステリ脳でも満足できるのがこの作品のすごいところだ。
土着ホラー×現代ミステリ=眠りを媒介にした因習
『夢詣』が面白いのは、都会を舞台にしておきながら、根っこにある恐怖が島の因習であることだ。登場人物たちは夢を通じて、地理的に離れた異界に引きずり込まれる。これはホラーとしてめちゃくちゃ新しい感覚だと思う。
というのも今までの因習ホラー、たとえば京極夏彦や三津田信三のような閉鎖的村落や因習に潜む恐怖は「その場所に行かなければ大丈夫」が基本ルールだった。
でも本作では、行くんじゃなくて行かされる。それも、眠っている間に。地理的な距離とか関係ない。現代人でも、スマホで調べ物しているうちに呪いの存在を知ってしまったらアウト、みたいな構造なのだ。
この『夢詣』というタイトルがまた絶妙で、「詣(もうで)」=神社への参拝、という元々の意味が「夢の中で勝手に参加させられる儀式」に転じている。崇拝じゃなくて強制参加。しかも、祀られているのが神ではなく何か。もう最悪だ。
さらに言えば、この構造はネット感染のようでもある。話を聞いただけで夢を見る。夢を見ると順番が回ってくる。感染ルートは知ることにある。つまり、読者である私たちもまた、感染者候補だ。
ホラーとミステリを融合する手法として、これはとても面白い。トリックではなく、呪術的な因果によって謎が回収されるが、そのロジックが一定のルールに基づいていて、「もし本当なら」と思わせる説得力がある。
そして、その“もしも”が怖いのだ。
気持ち悪さは最大の魅力になる
さて、本作が第45回横溝正史ミステリ&ホラー大賞で「読者賞」を獲ったのはけっこう重要だ。
「読者賞」はプロの作家や選考委員じゃなくて、事前モニターたちの投票で決まる賞。つまり、「とにかく面白かった」「これは止まらなかった」という声が多かったということ。プロの作家や批評家ではなく、一般読者のガチ評価によって支持された作品というわけだ。
「吐き気がする」「ぞくぞくした」「これぞ最恐」。ホラーの文脈で使われるこれらの言葉は、最高の褒め言葉でもある。バッドエンドの美学も、その一つだ。読後に救済がないどころか、絶望が沁みてくる。それでも読み切ってしまう引力がある。
また、タイムリミット型ホラーとしての魅力も見逃せない。『リング』における7日間、『着信アリ』における予告電話。あの「来るぞ来るぞ……」というジリジリとした焦燥が、『夢詣』でも見事に再現されている。
何よりもすごいのは、本作が怖いだけで終わっていないということだ。夢の構造、因習の論理、都市伝説と民俗学の交錯、科学の無力化。すべてが複雑に絡み合い、知ってしまったからこそ怖い構造になっている。
夢という逃げ場のない空間。因習という逃げ場のない呪い。
そこに理性や科学をぶつけても通じない。その恐怖が、私たちの安心できる眠りを破壊してくる。
その夢は、あなたを迎えにくる
ホラーとは、知ってしまったが最後、逃げられないジャンルだ。
『夢詣』は、その原点にもう一度立ち返って、「夢」という最大の密室を見事に舞台化してみせた。
悪夢が心の問題ではなく、肉体と世界をも侵食する感染源となったとき、私たちの眠りは最も無防備な瞬間から最も危険な場所へと変わってしまう。
タイトルの『夢詣』は、夢のなかの恐怖というより、夢のなかでしか行けない異界の祭祀の入り口だ。
その門は、すでに私たちの中に開いている。
眠りにつく前に、この物語を思い出してしまったなら、もう手遅れかもしれない。
どうか、今夜あなたの見る夢が、ただの夢でありますように。