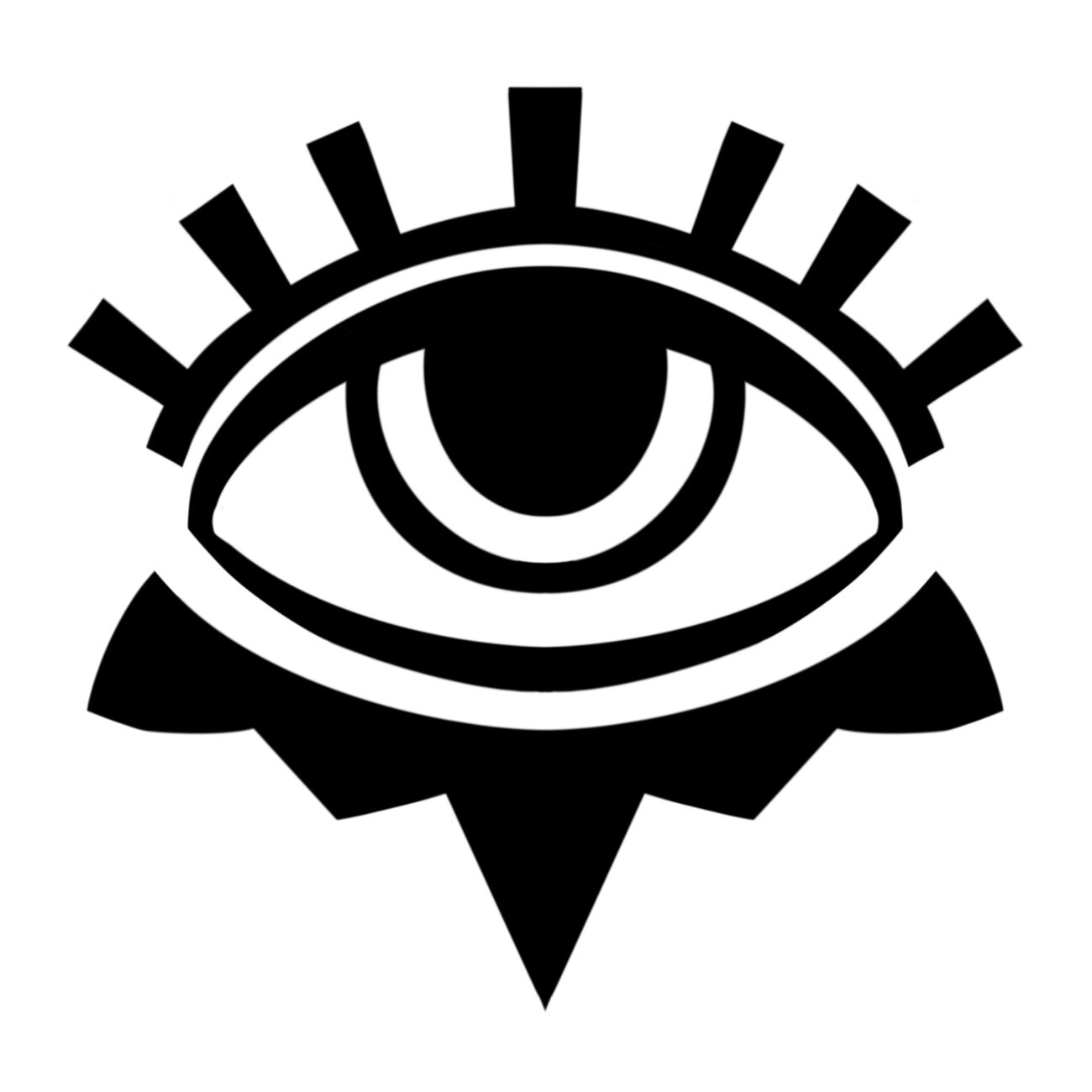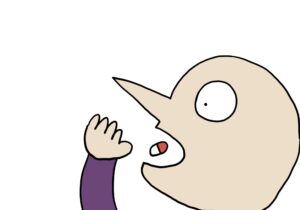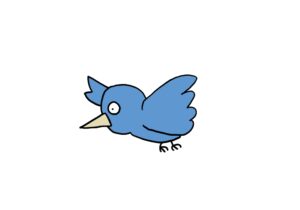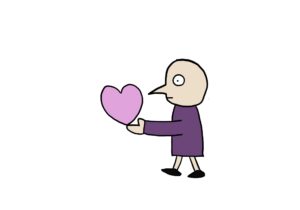ある国でロボットの研究をしているこの博士には、特別苦手なことがある。
それは、他人とコミュニケーションをとること。
彼は、人と面と向かって話すのが昔から大の苦手だったのだ。
そんな博士には、大きな困りごとがあった。
それは、研究資金の援助を得るために、関係する企業や団体にあいさつ回りをしなくてはならないことだ。
これまでは最低限の資金をやりくりしながら研究を進めてきたが、今よりも先進的な研究に着手するためには、まとまった資金を援助をしてもらう必要がある。
しかし、博士はどうしても、他人と会話をしたくない。
しかも、企業のお偉いさんたちの寒々しい目がズラッと並んだ会議室で、意気揚々と研究の意義を説明し、ペコペコと頭を下げるなんてことは、絶対に、何がなんでもしたくないのだ。
そこで博士は、とあるロボットを作り出した。
それは、博士本人の「身代わりロボット」だった。
背格好や顔つきはもちろん、皮膚のたるみ具合やホクロの位置、独特のクセがある髪型など、外見はまさに現在の博士そのもの。
これがロボットだと気づく人間は、一人もいないだろう。
さらに、博士の知識や思考パターンを学習させた、最新の人工知能を搭載することで、文字通り瓜二つの身代わりロボットが完成したのだった。
ただひとつ、本物の博士と違うのは、ロボットには優れた社交性を持たせたことだ。
これで、あいさつ回りには身代わりロボットを向かわせておけば、博士本人は研究に没頭できるというわけだ。
結果は大成功だった。
目の前で意気揚々と魅力的なプレゼンをして、誠意のある一礼をする人当たりのいい博士が、身代わりロボットだと気づくものは、誰一人としていなかった。
それどころか、想定よりも多額の研究資金を手に入れることができたのだ。
「フフフ。ワシの作ったロボットは、やはり世界一じゃ。これで、これからは生活の全てを研究に向けることができるぞ……」
満足げに笑う博士は、研究資金を使って研究所を新築し、数人の研究員たちを雇うことにした。
もちろん、研究員とはいえ直接会話などしたくないので、彼らの前に現れ、的確な指示を出すのは身代わりロボットの役目だった。
本物の博士はというと、秘密裏につくった研究所の地下室に籠り、身代わりロボットに研究の指示を出しながら、誰とも顔を合わせずに過ごすようになった。
それから十数年がたつと、博士の研究は世界的な大発明をいくつも生み出し、その度に研究所はさらに大きくなっていった。
そして今では、百人を超える研究員を抱える、世界有数のロボット研究拠点となった。
ロボット研究の世界的な権威でありながら、高い社交性で人当たりもいい博士は、たびたびメディアからの取材を受けるようになり、世界で知らぬものはいないというほどの有名人になっていた。
もちろん、人々が見ているのは、身代わりロボットなのだが。
そんなある日、本物の博士は体調を崩し、ひどい高熱にうなされていた。
これまで自室に長年籠っていたが、自力でなんとかできないような病気は、初めてのことだった。
「ぐぅ、仕方があるまい、これは病院に行かねば……」
博士は意を決して、十数年ぶりに自室から外へ出ることにした。
「はぁ、はぁ……」
地下室から出た博士は、苦しそうな様子で研究所の廊下を歩いていた。
「……どうしたんですか!?」
声を掛けてきたのは、最初に雇った研究員のうちの一人である、ベテラン研究員だった。
「はぁはぁ……キミか、実は体調がな―」
「誰ですあなた!どうやってここに入ったんですか!?」
強い口調でそう言ったベテラン研究員は、鋭い目つきで博士を見ている。
「……なにを言っておるんじゃ、ワシはここの所長ではないか」
「あなたこそ何を言っているんです!ここの所長は、世界的に有名な博士ですよ!あなたみたいな薄汚い老人とは、似ても似つかない!」
「どういうことじゃ……」
研究員の様子に驚いた博士は、廊下にあったガラス窓に目をうつした。
そこに映っていたのは、伸び放題の白髪が上半身を覆い、頬はガリガリに痩せこけて皮膚はたるみっぱなし。
どこをどう見ても、研究員の言う通りの薄汚い老人だった。
十数年ぶりに見る自分の姿に、博士は驚いていた。
「ち、違う、ワシが本物なんじゃ。これまでずっと地下室にいて、身代わりロボットに指示を……」
「またわけの分からないことを、あっ、博士!いいところに!」
そう言って研究員が視線をうつした先には、あの身代わりロボットが立っていた。
その姿は、十数年前に博士が作った時のまま。
つまり、まだ人前に出ることがあったので、わずかながら身だしなみに気を使っていた、あの頃の博士のままなのだ。
ロボットなので、人間のように外見が変化しないのは、当然のことだった。
「聞いてください博士!この老人が、どこからか研究所に入りこんでしまったようでして。それに、おかしな言動も見られるんです。どうしますか?」
「ふむ、そうかね」
「おいお前!お前から説明するんじゃ!お前はワシが作った身代わりロボットだと……!」
何かを考える身代わりロボットに、博士は血相を変えて叫ぶ。
すると少しして、身代わりロボットが口を開いた。
「……念のため警察に通報しよう。あまり大事にはしたくないが、このご老人のためにも、しかるべき機関で保護してもらったほうがいいだろうからね。この様子だと、精神的な病をかかえているかもしれないからね」
「承知しました。すぐに通報します。」
「待て!ロボットの分際で何を言っているんじゃ!誰がお前を作ってやったと……」
まくしたてる博士を見ていた身代わりロボットは、ゆっくりと博士に近付き、耳元でこう言った。
「今となっては、世界中で誰一人として、あなたが本物だと信じる者はいませんよ。これからも私が身代わりの役目を果たしますから、ご心配なく。さようなら、博士」
(了)