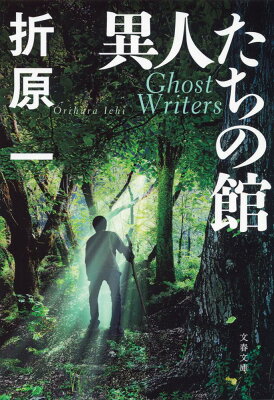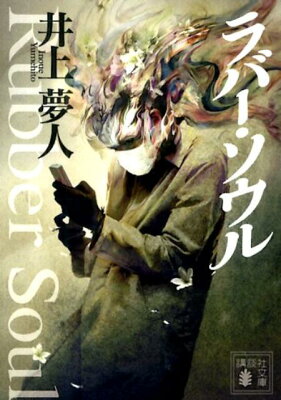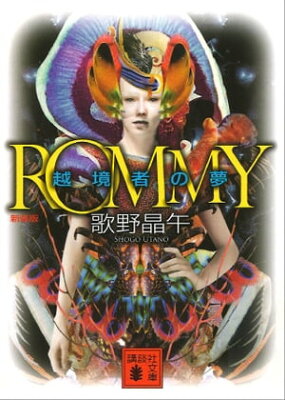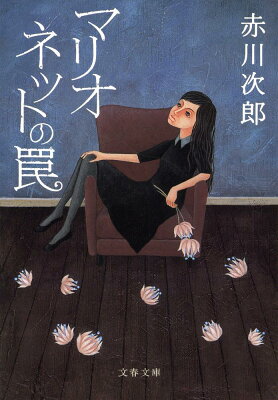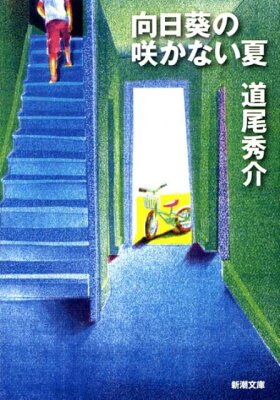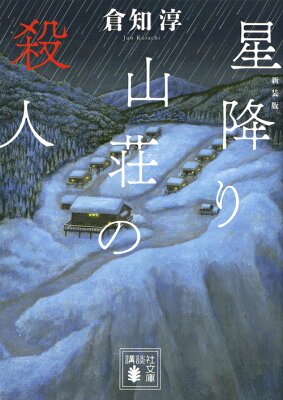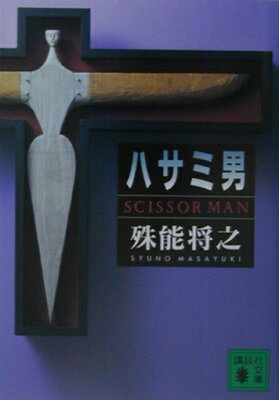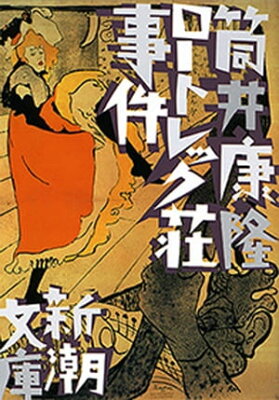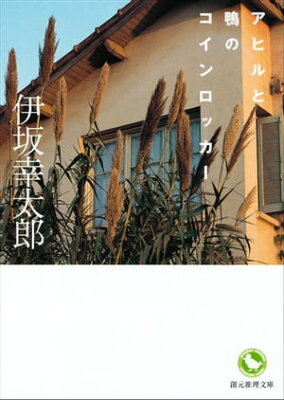物語の終盤、たった一行の真実によって、それまで信じていた全てが覆される──そんな衝撃を味わったことがあるだろうか?
読んだ瞬間に「やられた……!」と、思わずページを遡ってしまう。
それが【叙述(じょじゅつ)トリック】という、ミステリー小説の中でもとりわけ高度で魅力的な技法だ。
叙述トリックとは、物語の語り方そのものに仕掛けを施し、読者の先入観や思い込みを利用して「見えない嘘」を語る手法のことを言う。
犯人の正体を隠すだけではなく、語り手の正体、視点の操作、時系列の錯覚などを巧みに操ることで、読者に鮮やかな逆転を突きつけてくるのだ。
読後、思わず再読せずにはいられなくなる、そんな作品こそが「叙述トリックの名作」と呼ばれるにふさわしい。
この記事では、そんな巧妙な叙述トリックが光るおすすめミステリー小説を50作品厳選してご紹介。
古典から近年の話題作まで網羅し、「このトリックは見抜けなかった」「まさか、そういうことだったのか!」という驚きに満ちた一冊ばかりを集めた。
それと忠告なのだけど、
“叙述トリックを使っている’’ということすら知りたくない人はこの記事は読まないでほしい。
つまり、この作品は叙述トリックを使っていますと言っている時点で、一種のネタバレになっているからだ。
「叙述トリックを使っているとわかったら面白さ半減しちゃうじゃん……」と思う人もいるかもしれない。それもわかる。
でもここで紹介する作品は、叙述トリックを使っていると分かっていても騙されてしまうほどの面白い名作を選んだつもりだ。
参考にしていただければ嬉しい。
あなたの予想を鮮やかに裏切り、もう一度最初のページに戻りたくなる。
そんな極上の一冊と出会えることを願って。
1.すべては、ひとりの失踪から始まった── 折原一『異人たちの館』
売れない作家・島崎に舞い込んだ奇妙な依頼。それは、富士の樹海で失踪した青年・小松原淳の伝記執筆だった。
淳の母からの依頼を受け、渋々調査を始めた島崎は、やがて幼女連続殺人、正体不明の「異人」、行動を先読みする謎の女など、不可解な現象に巻き込まれていく。
浮かび上がるのは、淳の歪んだ自己愛と異様な家庭環境。そして島崎自身もまた、事件の底知れぬ闇へと引きずり込まれていく。
謎が謎を呼ぶ多重構造ミステリー、折原ワールドの真骨頂
売れない作家の島崎に舞い込んできたのは、わけありの仕事だった。富士の樹海で失踪した青年・小松原淳。その伝記を書いてくれと、母親から頼まれたのだ。
断ってもよかった。でも何となく受けてしまった。で、調査を始めたとたん、空気が変わる。幼女誘拐殺人、得体の知れない「異人」、そして島崎の動きを先回りしてくる謎の女。これ、伝記の仕事だよな?って疑いたくなるような展開が、次から次へと押し寄せてくる。
この小説は、とにかく語りの構造が複雑だ。島崎の調査記録をはじめ、淳の手記や小説の断章、関係者へのインタビュー、さらには語り手のわからないモノローグまで、全部で五つの文体が入り乱れている。それぞれの文章が独立しつつ、絶妙な距離感でつながっていくような構成になっていて、読み進めるごとに情報の断片が増えていく。
ただ、それらが一つの答えに向かうかと思えば、さらに別の謎が顔を出すのだ。全体がどこか掴みきれないまま、もやもやと浮かび上がるように組まれている。
そしてなんといっても小松原淳。こいつが強烈すぎる。自分が世界の中心だと思ってるタイプで、他人への攻撃がすさまじい。しかもその家族もどこかおかしくて、調べれば調べるほど重たい空気に包まれていく。このキャラ造形のキツさが、物語全体の不穏さをガッチリ支えているのだ。
600ページ超えの長編だけど、どこにも無駄がない。謎が立ち上がり、予想を裏切り、また別の謎が浮かぶ。その連鎖にぐいぐい引っ張られて、気づけば引き返せないところまで連れていかれる。
折原一の仕掛け方が冴えまくっていて、読み終えたあとには「そう来るか…」と唸るしかない。
構成もキャラも、仕込みも回収も、すべてが緻密に組まれた極上の迷宮だ。
「あなたのマイベストは何ですか?」と聞かれることがたまにある。そういう時、私は決まって『異人たちの館』と答えている。
この作品を書いたのは、四十代前半のもっとも気力充実していた頃であり、その時点における自分の持っているすべてをぶちこんでいるので、個人的には読者に自信を持ってお勧めできるのである。『異人たちの館』P.601 文春文庫版あとがき より引用
2.現実と嘘がねじれて踊る── 『倒錯のロンド』
推理小説家志望の山本安雄は、渾身の作『幻の女』を新人賞に応募しようとするが、原稿を何者かに盗まれてしまう。
ほどなくして白鳥翔という新人作家が、『幻の女』と全く同じ内容の作品で文学賞を受賞し、華々しくデビューを果たす。盗作だと訴える山本の声は届かず、彼は絶望の中で、白鳥への復讐を決意する。
だが、物語は単なる盗作劇では終わらない。作中作『幻の女』の謎、二転三転する展開、登場人物の内に潜む狂気が絡み合い、次第に現実と虚構の境界が崩れていく。
「倒錯」した世界が、「ロンド」のように繰り返されるのだった。
盗作と狂気が織りなす、眩暈く叙述トリックの輪舞
山本安雄は、将来を夢見る小説家の卵。渾身の作『幻の女』を書き上げ、新人賞に応募しようとした矢先、原稿が何者かに盗まれてしまう。
数ヶ月後、白鳥翔という新人作家が、そっくりな作品で文学賞を受賞。文壇の注目を一身に集めてデビューしてしまう。あまりに出来すぎた話だが、まさにそれが山本の現実。訴えても相手にされず、怒りと絶望を抱えたまま、白鳥を追い始める。
ただ、本作は単純な盗作と復讐の話じゃない。そもそも「山本の原稿」と「白鳥の作品」は同じなのか? 本当に盗んだのか? それとも、どこか別の地点から話がねじれてしまったのか? 物語は次第に、現実と小説、真実と嘘の境目をごちゃごちゃにしていく。
中核にあるのは作中作の構造だ。山本が書いた『幻の女』、白鳥が世に出した『幻の女』、そしてそれらを包む現実世界。この三重構造が何度も入れ替わることで、語られている出来事の信憑性がどんどん怪しくなっていく。登場人物も語り手も、いつの間にか役割をすり替えられ、誰が誰を演じているのかすら曖昧になる。
全体としてはかなり技巧的な構成だが、文章は意外なほどスムーズで読みやすい。ページが重たくならないよう工夫されていて、テンポはかなり軽快。そのぶん、構造のズレが効いてくる。
タイトルの「ロンド」が示すように、物語は何度も反復しながら形を変えていく。語りの軸も立場も揺れて、真実に手が届いたと思ったら、すぐ別の顔を見せる。そのくり返しが、読んでいる側の足場を外してくる。しかもそれが気持ちいい。
盗作、復讐、狂気、そしてミステリ。全部が丁寧に積み上げられていく。構造で読ませるタイプの作品が好きなら、これはかなり刺さる。
3.視線がずれると、世界が歪む── 折原一『倒錯の死角 201号室の女』
翻訳家の大沢芳男は、伯母と暮らしながら、向かいのアパート201号室を双眼鏡で覗くのが日課だった。
ある日、彼はそこで若い女性が絞殺される瞬間を目撃するが、覗き見が露見するのを恐れて通報できず、アルコールに溺れ、入院することに。
退院後、201号室に若い女性・真弓が入居。大沢は再び覗きに手を染める。真弓はそれに気づきつつも、あえて挑発的に振る舞い、大沢は過去のトラウマと妄想に翻弄されていく。
物語は、大沢、真弓の書く日記、そして彼を見張る元依存症仲間・曽根の三者の視点で語られ、やがて悪夢のような結末へと突き進む。
倒錯した視線が織りなす戦慄の叙述トリック
翻訳家・大沢芳男の密かな楽しみは、屋根裏部屋から向かいのアパート201号室を双眼鏡で覗くことだった。趣味としては相当アウトだが、誰にも迷惑はかけていない。……はずだった。
ある日、その部屋で若い女性が絞殺される現場を目撃してしまう。けれど、通報はできなかった。のぞき見がバレるのが怖かったのだ。罪悪感と恐怖に押しつぶされた大沢は、酒に逃げるようになっていく。
なんとか入院して治療を終えたものの、帰ってきた彼を待っていたのは、ふたたび人の気配を取り戻した201号室。新しい住人は、若い女性・清水真弓。あの部屋にまた誰かが住む。それだけで心がざわつく。でも結局、大沢はまた双眼鏡を手にしてしまう。
物語は、大沢の視点だけでは進まない。清水真弓もまた日記というかたちで語り出す。そして、もうひとり。大沢を監視している元アル中仲間の曽根新吉も、ひそかに物語に食い込んでくる。三人三様の語りが交錯し、それぞれが自分の正しさを信じている。
でも、それが本当に事実なのかは誰にもわからない。日記というのは、主観のかたまりだ。嘘は書いていないかもしれない。でも勘違いや思い込みは、ごく自然に混ざってくる。だから読み進めるうちに、何が本当で、誰の視点がまともなのか、どんどんわからなくなっていく。
この「語りのズレ」こそが、本作の面白さの中心にある。誰かの言葉を信じかけたその直後、別の視点がそれを上書きしてくる。そして、読み進めるうちに気づく。そもそもこの形式そのものが、最初から仕掛けの一部だったんじゃないかと。
中盤以降、その構造がガバッと反転する場面がある。あれはかなり衝撃的だ。物語の見え方が一気に変わって、視線のルールすら書き換わってしまう。しかも、それが妙に自然に感じてしまうのが不気味だ。
覗く者と覗かれる者。その関係はいつの間にか反転し、曖昧になっていく。視線を軸にしたミステリは数あれど、ここまで執拗に“視ること”と“語ること”をねじってくる作品はそう多くない。
まさに、読む側まで監視されているような、かなりユニークな一作だ。
4.語れない人形が見ていた── 東野圭吾『十字屋敷のピエロ』
資産家・竹宮家が暮らす「十字屋敷」に、ある晩、不気味なピエロ人形が持ち込まれた。その夜、女社長・竹宮頼子が屋敷内で転落死を遂げる。唯一の目撃者は、動かず、話さず、ただそこにいたピエロ人形だけだった。
四十九日を迎え、妹の水穂は姉の死の真相を探るため屋敷を訪れる。だがその矢先、頼子の夫・宗彦と不倫相手の秘書が、オーディオ・ルームで刺殺体となって発見される。
再び、犯行を見ていたのは例のピエロ人形。警察は外部犯を疑うが、水穂は屋敷内の誰かに疑念を抱き、血縁と欲望が交錯する闇に踏み込んでいく。
奇抜な視点が織りなす本格ミステリー
その人形は、ただ笑っていた。口元の表情は変わらない。でも、最初の殺人の瞬間も、次の事件も、ぜんぶ見ていたのは、そいつだけだった。
舞台は十字屋敷と呼ばれる資産家の屋敷。ある日突然、そこにピエロの人形が持ち込まれる。で、その夜に女社長が転落死。四十九日を迎えたタイミングで、今度は夫と秘書が刺殺される。どちらも、犯行現場にいたのはピエロ人形だけ。警察は外部犯を疑うけれど、妹の水穂は「犯人は身内」と踏んで、独自に探り始める。
この小説の最大の仕掛けは、「視点」にある。動かない。しゃべらない。感情を挟まない。ただ、見るだけ。そのピエロ人形の視線が、全編に張りついている。
誰が何をしたのか、誰が誰に何を言ったのか。全部見てはいるけど、何も語られない。だからこそ、怖い。
十字屋敷に集められた面々も、なかなかクセ者揃い。家族、関係者、みんなが何かしらを隠している。嘘もある、演技もある。誰が本音を話していて、誰が仮面をかぶっているのか。その揺らぎが、事件の構造と見事に噛み合っていく。
そして、終盤に至って明かされる真相。それは、まさに「見えていたはずの景色」が反転する瞬間だ。動けないはずの視点、語れないはずの言葉、そのすべてがひとつのトリックとして機能し、読者の理解を音もなく裏切っていく。
この見事な反転は、衝撃とともに一種の感嘆をもたらし、東野圭吾という作家の構成力の高さと物語への深い信頼を改めて感じさせるものだ。
ピエロは、終始無表情のまま。でもその無表情こそが、事件の鍵だった。
全部を見ていたのに、何も言わない。だから、怖い。だから、面白い。
5.舞台の上かと思ったら── 東野圭吾『ある閉ざされた雪の山荘で』
次世代の演劇界を担う若手俳優7人が、名演出家の指示で乗鞍高原のペンションに集められる。
舞台設定は「豪雪で孤立した山荘での連続殺人」。これは新作舞台のための稽古であり、彼らは与えられた状況の中で即興的に演出・演技を行うという実験的試みだった。
しかし、稽古が進むにつれ、参加者が現実に一人ずつ姿を消していく。芝居の一部なのか、それとも本物の殺人なのか。真偽の分からぬ恐怖と疑心が、ペンションを支配していく。
東野圭吾が仕掛ける劇中劇ミステリーの傑作
「殺人劇の稽古をするために、雪山のペンションに集められた7人の役者志望」って時点で、もうミステリー好きの胸は高鳴る。
だけど東野圭吾の『ある閉ざされた雪の山荘で』は、そんな期待を軽く超えてくる仕掛けの連続だ。
舞台は記録的な雪に閉ざされた山荘。設定は殺人劇の稽古。ただしこの稽古、演出家の不在のもと、台本も段取りも一切知らされていない。
それぞれが役を与えられ、舞台上で即興的に演じることで物語が進行していく。そう聞けばただのシチュエーション・スリラーかと思いきや、「稽古」のはずの出来事がどんどん怪しくなってくる。
そもそも「演技をしている人間を、演技かどうか見抜けない状況」に置かれるって、ミステリ的に最高じゃないか。舞台のなかで演じる役者たちが、いつから本当の恐怖を感じていたのか。いつから誰かがシナリオを逸脱していたのか。その境界が少しずつ溶けていく感覚がたまらない。
中盤からは、特定の人物の独白が差し込まれ、三人称だった視点が不意に揺らぎ始める。誰かの目を借りていたはずの物語が、いつの間にか誰かの思考と混ざってくる。構造そのものが伏線になっていて、後半ではそれまで信じていたものすべてが反転してしまう。
クローズドサークル、劇中劇、叙述の仕掛け、虚構と現実の揺らぎ。全部乗せておきながら、ちゃんと読後には「やられたな」と思わせてくれる一作。
「これは舞台か、それとも本当の殺人か?」
その答えは、最後の一行までたどり着いてようやく見えてくる。だけどそれでも、最初に戻りたくなってしまう。
この物語は、開幕よりも、幕が下りたあとのほうが面白くなるタイプの演目だ。
6.仮面の下で笑っていたのは、誰だったのか── 東野圭吾『仮面山荘殺人事件』
婚約者・森崎朋子の死から三ヶ月後、朋子の父の招きで男女8名が湖畔の別荘に集まった。
静かな追悼の場は、逃走中の銀行強盗二人組の乱入により一変。外界との連絡は絶たれ、雪に閉ざされた山荘で彼らは人質となる。
緊張が高まる中、突如ひとりが殺害される。だが、その手口から犯人は強盗ではないと判明。生き残った7人は互いに疑念を抱き、極限の疑心と恐怖の渦に巻き込まれていく。
どんでん返しの帝王・東野圭吾が仕掛ける、仮面の下の衝撃の真実
東野圭吾の初期作『仮面山荘殺人事件』は、「よくできた密室劇」というひとことで片づけるには惜しい一作だ。
設定は王道だ。雪に閉ざされた山荘、通信手段は断たれ、逃走中の銀行強盗が突入、そして殺人。こう言うと、少し出来すぎた舞台装置に聞こえるかもしれない。
でもこの作品がすごいのは、そこからさらにもうひと段、ギアを上げてくるところにある。
まず、主人公・樫間高之の視点が絶妙だ。穏やかで物腰柔らかく、悲しみを抱えた男。その目を通して描かれる山荘での出来事は、一見すればただのサバイバルだ。しかし、その視点そのものが仕掛けになっている。
読んでいくうちに、高之の「何気ない言葉」や「黙った間」に、何かが挟まっていたことに気づく。その何かが後半、ひっくり返ってくるのだ。
この構造の面白さは、クローズドサークルの中で、物語のルールそのものが密かに捻じ曲げられていたことにある。ただのパニック劇ではない。誰かが仕組み、誰かが演じ、そして誰かが仮面を被っていた。それを知ったとき、自分がずっと見ていたものがまるで虚構だったような気がしてくる。
1990年という初期の作品でありながら、構成力はすでに完成されている。伏線の張り方、引きの強さ、視点の使い方。どれも研ぎ澄まされていて、読み終えたあと、もう一回冒頭をなぞってみたくなるような仕上がりだ。
この作品がやっているのは、ミステリーというジャンルの中で、「語りの信頼性」そのものに疑問を突きつけてくることだ。
誰が何を見て、誰が何を語っていたのか。そこまで巻き戻して、やっと全体像が見えてくる。
派手さはないが、完成度と驚きは一級品。
東野圭吾という作家の凄みを、改めて思い知らされる。
7.世界が反転する、その音を聞け── 西澤保彦『神のロジック 次は誰の番ですか?』
人里離れた山中にある全寮制の〈学校〉。生徒たちは入学の経緯や過去の記憶を失い、目的不明のまま推理ゲームや課題に取り組む生活を送っていた。
そんな中、新入生の失踪を皮切りに連続殺人事件が発生。閉ざされた空間で、生徒たちは恐怖に怯えつつも、〈学校〉と事件の謎に挑む。
SF的な舞台設定と本格ミステリが交錯する、予測不能のサスペンス。
閉鎖空間の異様さとSF的特殊設定が生み出す唯一無二のミステリー
閉鎖された寮、意味不明なルール、不自然な授業、そして記憶の空白。そんな場所にぶち込まれて、平然と生活できる人間なんているのだろうか? たぶん、いない。
西澤保彦の『神のロジック 次は誰の番ですか?』は、そんな「前提」そのものに違和感があるところから始まる。
舞台は、世界各地から集められた少年少女たちが共同生活を送る〈学校〉。ただし、授業内容は推理ゲームや論理クイズという妙なものばかり。しかも、生徒たちの多くは、自分がなぜここにいるのかさえ思い出せない。
最初から不穏さしかない環境なのに、そこへ転入生の失踪、連続殺人と来るのだから、これはもうクローズドサークル地獄絵図の幕開けだ。
殺人事件を軸にした本格ミステリとして読んでも面白い。けれど、本作の本質はそこじゃない。全体を覆う構造そのものが、まるで箱庭をひっくり返すようにひたひたと崩れていく。その崩れ方が、あまりにも綿密で容赦がなく、しかもSF的な設定に理性と納得がしっかり貼り付いているからこそ、驚きより先に笑ってしまう。ああ、やられたなって。
犯人が誰とか、動機がどうとか、そんな次元じゃない。「え、今まで読んできた全部、何だったの?」と頭を抱えるレベルだ。
ちょっとした違和感や、どうでもよさそうなエピソード──たとえばスナック菓子の盗難、授業の報酬、そういった細部が、最終盤で異常な精度で絡み合ってくるのがたまらない。
この構成を成立させるために、どれだけの下準備とセンスが要るのか。しかも読んでいて堅苦しさがない。テンポもいいし、登場人物のやりとりも生きている。
世界の当たり前が一気に反転するあの感覚は、この作品でしか味わえない。事件の真相だけでなく、世界そのものの正体まで暴かれるこの読後感。
言葉が届くよりも先に、理解が感情に追いついてくる。完成度、破壊力、問答無用の一発。
西澤保彦という作家が、ただのトリック職人じゃないってことを、これ一冊で思い知らされるはずだ。
読み終えたあと、何を信じていたのか、自分でもよくわからなくなる。
でも、それでいい。そんなふうに揺さぶってくる物語こそ、忘れられなくなるのだから。
8.電気の中から、誰かがこっちを見ている── 詠坂雄二『電気人間の虞』
特定地域に伝わる都市伝説、「電気人間」。
「語ると現れる」「人の思考を読む」「電気で痕跡なく人を殺す」など、様々な怪異が噂されるこの存在は、旧日本軍の極秘実験に由来するとも囁かれ、調査を試みた者たちは次々と謎の死を遂げてきた。
フリーライター・柵馬朋康も、この不可思議な伝説の真相を追い始めるが、あらゆる仮説が常識外の怪異によって打ち砕かれていく。
これは果たしてミステリなのか、それとも純然たるホラーなのか。
既存のジャンルの境界線を軽々と飛び越える、異色の物語が幕を開ける。
都市伝説と叙述トリックが融合する、ジャンル超越の鮮烈な問題作
「語ると現れる」
そんな触れ込みからして怪しい都市伝説に、ライターの柵馬朋康は首を突っ込んでしまった。対象は「電気人間」。思考を読む、通電して移動する、人を殺す、旧日本軍の遺産……ありもしない噂ばかりが積み重なった影の存在だ。
とはいえ、ただの伝説で済ませておけるなら苦労はない。実際に調査を始めた人間が、意味のわからない死を遂げている。そして柵馬自身も、取材を進めるうちに「現実のはずなのに現実っぽくないこと」にどんどん巻き込まれていくのだ。
仮説を立てても崩される。理屈を押し立ててもすり抜けられる。自分の考えがまるで見透かされているかのように、次の異変が起きる。そんな展開が続くうちに、柵馬は正しさそのものがあやふやになっていってしまう。
不気味な話だが、これはホラーだけではない。きっちりミステリでもある。殺人が起きて、犯人がいて、物理的な謎が用意されている。そしてそのどれもが、「電気人間とは何か」という中心に向かって、複雑に絡み合っていくのだ。
特徴的なのは、物語の語り口がそのまま構造の一部になっていることだ。誰が、何を、どこまで話しているのか。視点や伝達のズレが仕掛けとして作用しはじめると、都市伝説の話だったはずが、いつの間にか語り手の物語にすり替わっていることに気づく。
ミステリか、ホラーか、メタフィクションか。そう分類することすら無意味に思えてくる。電気のように形を持たないものが、人の認識や論理を通して、どうやって現実に入り込んでくるのか。それを体験として書いたような物語だ。
そして最後、ある一文に触れた瞬間、何かが終わる。
というより、始まってしまう。
読み終えたあとに残るのは、「語ってしまった」という事実だけだ。
9.見えなかったのは、世界じゃなくて自分だった── 服部まゆみ『この闇と光』
深い森の奥、人里離れた館で、盲目の王女レイアは父王の愛情と家政婦ダフネの世話に包まれ、まるで美しい鳥籠の中のような静かな日々を送っていた。
文字や音楽に親しみながら育つ彼女は、外界を知らぬまま穏やかに成長する。しかしある日、完璧だったはずの世界は唐突に崩れ去り、彼女は全てを覆す衝撃の真実に直面する。
幻想と耽美の中で、美しくも残酷な謎がゆっくりとその姿を現していく。
盲目の王女が視る世界の反転
森の奥、外界から隔絶された館の中で、盲目の王女レイアは「愛されて」育てられた。父の優しさ、家政婦の献身、文字と音楽に包まれた暮らし。
しかしその日々は、まるで鳥籠の中の夢みたいな、甘くて少し息苦しい静けさに包まれていた。
服部まゆみの『この闇と光』は、その甘やかな日常が、ふとした瞬間に崩れ落ちる物語だ。レイアが大人の女性へと近づいていく頃、完璧だったはずの世界は音もなくひっくり返る。彼女の語りを通して見えていたはずの世界が、実はまったく別の姿をしていたことに気づいたとき、背筋に冷たいものが走るのだ。
盲目という設定が、ここではとてつもなく効果的に使われている。見えないからこそ見えない。けれど見えないからこそ、そこには信じるしかない関係と、思い込みが生まれる。
そして、守られているように思えていたものの正体が明かされたとき、読者はレイアと一緒に地面を失う。それまでの優しさが嘘だったかのように、すべてが冷たく反転していくのだ。
でもこれは、ただのどんでん返しではない。耽美な文体、ひりつくような描写、そして詩のように編み込まれたレイアの言葉たち。すべてが複雑な感情のグラデーションになって胸にしみてくる。
なにが光で、なにが闇か。それを決めるのは他人じゃない。自分で選ぶしかない。
そしてその選択の先に、たとえ正解なんてなかったとしても。
10.醜さとビートルズと、壊れた愛の話── 井上夢人『ラバー・ソウル』
鈴木誠、36歳。ホウライエソに例えられるほど醜い容姿ゆえ、家族にも疎まれ、孤独な人生を歩んできた。社会との唯一の繋がりは、洋楽誌に匿名で寄稿するビートルズ評論だった。
ある日、撮影現場で出会った人気モデル・美縞絵里に心を奪われた誠は、偶然を重ねて彼女と急接近し、灰色だった日々に光が差す。しかしその想いは次第に歪み、やがてストーカー行為へと変貌していく。
そしてその歪んだ純愛は、やがて取り返しのつかない犯罪と、あまりにも悲劇的な結末へと彼を導いていくのであった。
ビートルズの名曲が彩る、切なくも衝撃的な純愛ミステリー
鈴木誠、36歳。見た目は「ホウライエソ」という深海魚にそっくりだと言われるほどの容姿。
家族にも顔を背けられ、友達も恋人もいない人生を歩いてきた。彼にとって唯一の誇りは、ビートルズ評論。洋楽専門誌に書いたコラムだけが、社会とつながる細い橋だった。
そんな彼がある日、人気モデルの美縞絵里と出会う。現実とは思えないほどの偶然が重なり、絵里を助手席に乗せてドライブすることに成功する。この瞬間、誠の世界は大きく変わった。彼の人生に、はじめて「光」が差したのだ。
しかし、それは同時に歪みの始まりでもあった。
想いは純粋だった。だが、想いが強すぎた。誠は次第に絵里の行動を監視し、調べ、追い回すようになる。自分がストーカーであるという自覚すらないまま、彼は愛を積み重ねていく。
この物語は、単なるストーカー男の話ではない。醜さに苦しみ、孤独に取り憑かれ、それでも誰かを全力で想い続けた男の、ある意味では「純愛」の話だ。彼の言動を擁護することはできない。だが、その内側にある飢えや焦がれを見てしまったとき、完全に切り捨てるのも難しくなる。
そして、読み進めるうちに気づく。この話には、別の顔がある。ビートルズというモチーフがさりげなく絡み、言葉や構造そのものに意味が込められている。タイトルが『ラバー・ソウル』であることの意味も、最後まで読むと分かるようになっている。
終盤に訪れるあの「ひっくり返し」は、ただの意外性ではない。物語全体の重心がズレるような、読んできたはずの内容が別物になるような、そんな感覚だ。
ページ数は多い。内容も重い。けれど、読み終えたあとには確かに残るものがある。気づけば、ずっと鈴木誠のことを考えているしまう。彼の歪みと哀しみ、そのすべてがどこか引っかかって離れない。
これは「犯人は誰か」を追う話ではない。
誰かを深く想ったとき、人はどこまで正気でいられるのか。
それを突きつけてくる物語である。
11.理屈と笑いと殺意と、すべては「V」の始まり── 森博嗣『黒猫の三角』
那古野市では、発生日と被害者の年齢がゾロ目で一致するという奇妙な法則に従った連続殺人事件が続発していた。
今年、その条件に合致する資産家令嬢・小田原静江のもとに「次はあなたの番だ」との脅迫状が届く。6月6日に44歳を迎える静江は、探偵・保呂草潤平に警護を依頼し、誕生日の夜、邸宅でのパーティーに備えて厳重な監視体制が敷かれる。
だが、招待客に囲まれた密室の中で、静江は殺害されてしまう。
この不可解な事件は、後に名探偵として名を馳せる瀬在丸紅子と、物語の語り部となる保呂草潤平、そして阿漕荘の面々が織りなす「Vシリーズ」の記念すべき第一作であり、シリーズ特有の知的な謎解きと人間ドラマの序章となる。
数学的思考と「理由なき殺人」の哲学
この事件、最初から妙なにおいがしている。
誕生日と年齢がゾロ目の人間ばかりを狙う殺人鬼に、予告状、衆人環視のパーティ、密室での殺人。おまけに依頼人は資産家のお嬢様。いや、設定盛りすぎじゃない?と思いつつ、気づけばどっぷり引き込まれている。
そんなゴリゴリの舞台に現れるのが、名探偵・瀬在丸紅子と語り手・保呂草潤平のふたりだ。会話劇のテンポが絶妙で、ミステリなのに笑える。阿漕荘という謎めいたアパートに住む個性豊かな住人たちとともに、事件の謎に挑んでいく。
物語のタイトル『黒猫の三角』は伊達じゃない。数学用語「クロネッカーのデルタ」を下敷きにした構造やトリックが、緻密に仕組まれてる。衆人環視の中で起きる密室殺人なんて無理ゲーだろと思っていたら、理系頭脳がきっちりロジックで詰めてくるから恐ろしい。
でもこの作品、本当に怖いのは「動機」だ。殺人に理由なんてあるのか?と疑いたくなるほど、どこか空虚で、淡々とした狂気が潜んでいる。それを描き切るからこそ、Vシリーズはただのパズルじゃ終わらない。
後のシリーズ作品につながる人間関係の起点でもあって、今読むとキャラの初期設定の面白さも噛みしめられる。紅子のぶっ飛んだ思考や、練無の怪しさは、最初から全開だ。
『黒猫の三角』は、謎の面白さも、人の怖さも、キャラの濃さも、すべてが絶妙なバランスで転がっていく。
シリーズの口火として、この一冊はあまりに完成されすぎている。
怖いのは犯人より、森博嗣の計算かもしれない。
12.子供の目に映った、甘くて苦い真実── 森博嗣『探偵伯爵と僕』
小学6年生の新太は、夏休みの始まりに「探偵伯爵」と名乗る風変わりな男・アールと出会い、年の差を越えた奇妙な友情を育む。
しかし、親友のハリィが夏祭りの夜に失踪し、続いてガマまでもが行方不明に。現場にはいずれもトランプのカードが残されており、不気味な連続性が浮かび上がる。
やがて魔の手は新太にも迫る。新太は探偵伯爵と共に、親友たちの失踪の謎に立ち向かっていく。
「語り」の仕掛けと読後感を揺るがす結末
物語を読むとは、誰かの目を借りて世界を覗き込むことかもしれない。
森博嗣の『探偵伯爵と僕』は、いかにも「やさしいミステリ」の顔をして、あとからとんでもない打撃を喰らわせてくる。
語り手は小学6年生の「僕」こと馬場新太。舞台は夏休みの始まり、公園で出会ったのは、黒いスーツの奇妙な男。名乗る名前は「探偵伯爵」。この時点で、もう事件の香りしかしない。
彼らの友情が芽吹いたその裏で、新太の親友たちが次々に姿を消す。夏祭りの夜、トランプのカード、秘密基地、子供たちの失踪。そして、残されたのは謎だけ。そんな不穏な事件に、新太は伯爵とともに踏み込んでいく。
しかし、この物語の核心は事件そのものじゃない。全部を読み終えて、探偵伯爵から新太に手紙が届いたとき、それまで信じてきた地面がふわっと浮く。なにが現実で、なにが主観か、ほんの少しのズレが物語そのものの形を変えてしまうのだ。
子供の語りっていうのは、無邪気さのなかに危うさも潜んでいる。新太の目はすべてを真っ直ぐに見ようとするけれど、それだけじゃ届かないものがある。そこがこの作品の仕掛けであり、醍醐味だ。
探偵伯爵とチャフラさんのコンビも印象的だが、やっぱり最後まで物語を引っ張るのは、新太の視点。その「目」があるからこそ、ぼくらもこの謎に振り回される。
ラストで見える真実は、鮮やかな解決じゃない。むしろ、語られた物語のかたちが変わることで、「謎を知ること」そのものの意味を反転させてくる。
この仕掛けを、森博嗣は少年の筆に託して、驚くほど静かにやってのけるのだ。
13.「鏡の国」の奥に潜む、理詰めの死── 北山猛邦『アリス・ミラー城殺人事件』
その城は『鏡の国のアリス』を模した異形の建築、「アリス・ミラー城」と呼ばれていた。
鏡の向こうのようなチェス盤の空間に、8人の探偵が招かれる。依頼主は城の所有者の姪・ルディ。目的は「アリス・ミラー」と呼ばれる秘宝の探索。
だが提示された条件は、「生き残った者だけが秘宝を手にする権利を得る」という残酷なものだった。そして予告通り、探偵たちは次々と殺されていく。
孤島の城で、誰が、なぜ、どうやって?
極限の恐怖と疑念の中、生き残りを賭けた謎解きが始まる。
「物理の北山」の真骨頂!奇抜な設定と正攻法のトリック
鏡の世界に閉じ込められたような不条理と、物理法則の冷徹なロジック。その両方が襲いかかってくるのが、北山猛邦『アリス・ミラー城殺人事件』だ。
舞台は、鏡とチェスの意匠に彩られた奇怪な城。呼び集められたのは8人の探偵。そして主催者が提示したのは、「生き残った者だけが秘宝を手にする」という不穏なルールだ。物騒な予言を裏切ることなく、探偵たちは次々と倒れていく。
この作品の最大の特徴は、設定の異様さとロジックの堅牢さが絶妙なバランスで同居しているところにある。鏡の迷宮、現実離れした建築、チェス盤のような死の配置。そんな夢のような舞台なのに、殺人の手口は異常に現実的だ。つまり、ファンタジーな皮をかぶった、本格中の本格。
特に第1の殺人の仕掛けには驚かされる。まさかこの構造が成立するとは、と思わず唸ってしまう。その後も奇怪な状況が続々と現れるが、すべて理屈で組み上げられており、どんなに奇天烈な場面でも地に足がついている感覚がある。
そして終盤、もうひとつの爆弾が投下される。物理トリックと並んで、この作品を支えるのが言葉の仕掛けだ。読み手の認識にこっそり忍び寄り、ラストで見事にひっくり返す叙述トリックが決まる。このまんまと騙された瞬間は、悔しさよりも心地よさが勝つ。
もちろん、納得度には個人差があるかもしれない。でも、この作品が挑戦していること自体が面白いのだ。トリックのために舞台を整えるのではなく、舞台そのものがトリックに変わる。この発想には、推理小説の新しい地平すら見えてくる。
物理と幻想、チェスと人間、嘘と真実。すべてが歪み合いながら収束していく構造は、北山猛邦という作家の真骨頂を感じさせる。
とにかく、一度入ってしまえば最後まで歩き切りたくなる、重力のある物語だ。
14.人形に恋した青年と、命を宿す幻想── 加納朋子『コッペリア』
愛に飢え、孤独に生きてきた青年・了は、ある日、天才人形作家・如月まゆらの屋敷で、美しい少女の人形と出会う。その精巧さに心を奪われるも、人形はまゆら自身の手で無残に破壊されてしまう。
諦めきれない了は、密かに人形の修復を始める。やがて彼の前に、その人形と瓜二つの容貌を持つ舞台女優・聖(ひじり)が現れ、現実と幻想の境界が揺らぎ始める。
人形を愛する青年、人形を壊す芸術家、人形になろうとする女優。歪んだ愛と執着が交差し、運命の歯車が回り出す。
人形と人間が織りなす愛と幻想のミステリ
感情が欠けた青年が恋に落ちた相手は、人間ではなく、人形だった。
そう聞くと倒錯的に響くかもしれないが、この物語に流れているのは、むしろやさしくて繊細な温度だ。
主人公の了は、人間と心を通わせるのがとにかく苦手な男だ。けれど、とある屋敷で目にした一体の人形に、一瞬で心を奪われる。問題なのは、その人形がすぐに作家本人によって破壊されてしまうことだ。そしてこの出来事をきっかけに、了の人生は歪みはじめる。
人形に瓜二つの美しい女優・聖との出会い。人形を創った天才・如月まゆらと、その支援者であり過去に深い因縁を持つ創也という男。それぞれの思惑と執着が、人形を中心にして複雑に絡まりはじめる。
序盤はロマンスめいた雰囲気で進んでいくが、どこかおかしい。言動のズレ、感情の過剰、無理に隠されている何か。中盤を過ぎたあたりから、物語のトーンが少しずつ冷たく変わっていく。
了は「人形しか愛せない」と言うし、聖は「人形になりたい」と願う。その倒錯っぷりが突き抜けることで、逆にどこか純粋さすら漂ってくる。歪んでいる。でも本気なのだ。
もちろん、物語はただのラブストーリーでは終わらない。ミステリとしての仕掛けも抜群だ。とくに終盤で明かされるある事実は、これまで見えていたものの意味を塗り替えてしまう。
最終的に残るのは、うす暗くもあたたかい奇妙な納得感だ。人間の愛がこんなにも歪みやすくて、でもこんなにも誠実でいられるのか、という驚きと、どこか救われたような感覚。
『コッペリア』は、人形を通して、人間の心の「空白」を浮かび上がらせる物語だ。
そして、その空白にそっと指を差し出すような優しさを持っている。
15.時代劇の皮をかぶったフルスロットル本格── 幡大介『猫間地獄のわらべ歌』
時は天保年間、江戸の猫間藩下屋敷で藩士が腹を切って死ぬ事件が発生。蔵は内側から閉ざされた完全な密室だった。
藩主の側女・和泉ノ方は立場を守るため、事件を外部犯に見せかける偽装を命じる。一方、国許では銀山の利権を巡る混乱の中、わらべ歌に沿った連続見立て殺人が起きていた。
若き目付役所の侍・静馬は、江戸と国許、二つの不可解な事件の謎に挑む。
時代劇の常識を覆す、破天荒ミステリ絵巻
開幕早々、蔵の中で切腹死体。それだけでもインパクト十分なのに、舞台はなんと江戸時代。しかもその蔵、内側から鍵がかかってて完全密室。
どう見てもお家騒動の香りしかしないが、藩主の愛妾が指示したのは「自殺を他殺に偽装せよ」という前代未聞の命令だった。
本作が面白いのは、ただの変化球じゃないところだ。見た目は立派な時代劇だが、フタを開ければがっつりミステリ。しかも「密室」「見立て」「連続殺人」「叙述トリック」と、本格好きのツボを全部押してくる。もはや満漢全席である。
江戸と国許をまたぐダブルの事件。片や切腹偽装の密室、片や不気味なわらべ歌に沿って人が死んでいくという見立て連続殺人。ふたつの筋がテンポよく絡みながら進むので、ページをめくる手が止まらない。しかも動く◯◯◯を使ったトリックなんて、発想がバカ(褒めてる)すぎて笑ってしまう。
だが驚かされるのは、それだけじゃない。途中でキャラが普通に「メタミステリ」「密室殺人のセオリー」なんてワードを口にし始めるのだ。時代劇なのに。タイムスリップか? と思うかもしれないが、そうじゃない。
これは最初からそういう設定なのだ。あえて現代の言葉を喋らせることで、形式としての「時代小説」を突き抜けてくる。これが最高に自由で楽しい。
主人公の静馬も、正統派の頼りない若侍ポジションを踏みつつ、妙にツッコミのキレが良くて親しみやすい。周囲の登場人物もいちいちキャラが立っていて、会話劇としても実にテンポがいい。ギャグと推理の比率が絶妙すぎる。
終盤には鮮やかな叙述トリックまで待っていて、ふたつの事件がひとつの線に収束する瞬間にはガッツポーズ不可避。ここまでやってくれるなら、ミステリクラスタとしても黙ってはいられない。
時代劇で、密室で、わらべ歌で、叙述で、しかもめちゃくちゃ軽妙。そんな作品、そうそうない。型にハマるな、常識に縛られるな、というメッセージが、物語のあちこちにこっそり込められている気がする。
とにかく、「型破り」を読みたいならこれだ。
まさに、ジャンルの壁を軽やかに超えた「怪作」である。
16.正統派の顔をした異形の怪物── 麻耶雄嵩『螢』
オカルトスポット巡りを趣味とする大学サークルの男女6人は、夏合宿として京都の山中にある洋館「ファイアフライ館」を訪れる。そこは、10年前に作曲家・加賀螢司が6人の演奏家を惨殺した忌まわしい過去を持つ場所だった。
彼らの中には、半年前に連続殺人鬼「ジョージ」に仲間を殺された者もおり、不穏な空気の中で合宿が始まる。嵐で外界と隔絶された館内で、やがて10年前の事件を模すかのように、最初の殺人が発生する。
常識を覆す、予測不可能な暗黒ミステリ
黒レンガの洋館、凄惨な過去、孤立した空間、そして次々と死ぬ大学生たち。
設定だけなら、古今東西のクローズドサークル系を愛する身として、これ以上ないくらいのご馳走だ。肝試しを兼ねたサークル合宿で、封印された惨劇が再び幕を開ける──そんな始まり方をされて、興奮しないわけがない。
だが、これは麻耶雄嵩だ。ただじゃ済まない。
事件の構図も、人物の関係も、ぜんぶ整ってるように見えて、何ひとつ信用できない。視点はぶれないし、伏線もある。トリックもある。でも、読み終えてみると「それで、なんだったの?」という妙な感覚が残る。整理できないわけじゃない。ちゃんと整っているのに、どこかおかしい。というか、おかしすぎるのだ。
この作品の怖さは、真相の「質」そのものにある。殺人の動機がどうこう、犯人が誰かというレベルを超えて、そもそも「この話、全部本当にあったのか?」という根本が揺らいでくる。
ラストのある一行。あれを読んでしまったら、すべてが引っくり返る。あの一撃を喰らって以降、ページを戻しても、何もかもが別の顔をしてる。ズルいとか反則とか、そういう問題じゃない。麻耶作品では、それが普通なのだ。
鍾乳洞だとか、近親だとか、並みのミステリなら慎重に扱われる要素を、麻耶雄嵩はさらっと使いこなす。嫌悪感を覚えるかもしれない。でも、それこそがこの物語の体温であり、麻耶らしさの塊でもある。
結末は投げっぱなしのようにも見える。だが、それを不親切とは言えない。むしろ、そこまで読者を導いておいて、最後だけは「自分で考えろ」と突き放す。その冷たさが、たまらなく魅力的だ。
きれいに整った本格を読みたい人には向かない。でも、常識の裏をかいてくる何かを味わいたい人にとっては、麻耶雄嵩の『螢』は、まさに試金石になる作品だ。
そして私たちは気づくのだ。
真相とは、「犯人が誰か」だけではない、と。
17.闇に沈む村、名も消えた村── 麻耶雄嵩『鴉』
かつて「埜戸(のど)」と呼ばれたが今では地図から消えた山奥の村。電気もガスも使わず、外界と隔絶された原始的生活を守る閉鎖共同体である。
主人公・珂允(かいん)は、1年前にこの村で失踪し、不可解な死を遂げた弟・襾鈴(あべる)の真相を追って埜戸を訪れる。だが村は「大鏡様」という現人神を崇め、外部の人間を激しく拒絶する異様な空気に包まれていた。
やがて、信奉者の殺害を皮切りに連続殺人が発生。村に滞在していた異形の探偵・メルカトル鮎も事件に関わり始め、埜戸に潜む因習と血塗られた真実が浮かび上がっていく。
禁断の村で交錯する因習と驚愕のトリック
こんな村入っちゃダメだろ、と言いたくなるが、麻耶雄嵩はわざわざそこを舞台にする。
地図から名前が消えた“埜戸”で起きるのは、外界を拒んだ村が抱え込んだ、血と因習と嘘の物語だ。
主人公・珂允(かいん)が探るのは、弟・襾鈴(あべる)の死の真相。しかし、足を踏み入れたその瞬間から、物語は後戻りのできない迷宮に変わる。電気もガスも通らない村、現人神〈大鏡様〉を中心に組み上げられた奇怪なルール。文明の対極で、命が理不尽に消えていく。
そんな村に、タキシード姿の探偵・メルカトル鮎が紛れ込んでいるのも不穏だ。この男、変人に見えて仕事は超一流。毒にも薬にもなる理性のかたまりで、村に漂う不文律をバッサリ斬っていく。
事件のカラクリがまたすごい。物理トリック、叙述の仕掛け、遺伝的な条件すら使ってミステリの土台を作ってしまう。その発想と構築に、頭を抱える人もいれば、うなるしかない人もいる。語り手が複数いる構成もトラップのひとつで、誰の言葉を信じるかで世界が変わる。読み進めるほどに、現実感がねじれていく。
終盤で炸裂するのは、麻耶作品らしい強烈な反転だ。怒涛の回収と解答のあとに残るのは、明るさゼロの現実。救いはない。でも、そういう物語だからこそ、頭のどこかにずっと残ってしまう。
『鴉』は、謎解きの形をした心理実験かもしれない。読む人を試すような残酷なまでの構成と、血のめぐりまで制御されたロジック。
ミステリとして完成されているだけじゃなく、読書という行為の奥深さを痛感させてくれる作品だ。
18.たった一文がすべてを壊す── 歌野晶午『葉桜の季節に君を想うということ』
元私立探偵の成瀬将虎は、自称「何でもやってやろう屋」として活動していた。ある日、フィットネスクラブで出会った美しい女性・愛子から、霊感商法に関する調査を依頼される。
調査を開始した矢先、成瀬は自殺を図ろうとしていた女性・麻宮さくらを救い、二人は急速に惹かれ合っていく。
こうして成瀬は、霊感商法の実態を暴く危険な潜入調査と、さくらとの甘く危うい恋の狭間で奔走することになる。
果たして成瀬は、悪質なグループの魔手から依頼人を守れるのか。そして、さくらとの恋の行方は。
圧巻の叙述トリックと「必ず二度読みたくなる」問題作
恋と事件。どちらもよくある話のはずだった。
自称「何でもやってやろう屋」の成瀬将虎は、怪しい霊感商法の調査を頼まれたついでに、自殺未遂の女性を助けてしまう。その女性・さくらに惹かれていくうちに、日常は少しずつ軋みを見せはじめる。
歌野晶午『葉桜の季節に君を想うということ』は、そんな何気ない日々と調査劇が交錯するように進んでいく。そして、まるで何でもないような一文を境に、物語がひっくり返る。世界が反転し、信じていたすべてが別物になるのだ。
「完全に騙された」という驚愕と、ある種の快感。あるいは、深い戸惑いと困惑。 そのどちらに傾くにせよ、この読書体験が並の小説では味わえない強烈なものであることは、間違いない。
これは叙述トリックの極致だ。あからさまな騙しではない。むしろ正々堂々とすべてが提示されているのに、読者は見事にミスリードされる。というより、そう誘導されるように巧妙に構成されている。
ただのテクニック勝負では終わらない。その仕掛けが明かされたとき、愛情や信頼といった感情そのものが土台から揺らぐ。物語をどう読んできたのか、自分の受け取り方すらも再検証させられる。
読後、ページを戻したくなるのは、伏線を確認したいからではない。
あの言葉の意味を、もう一度自分の目で確かめたくなるからだ。
一気読み必至、というより一気に読まないと危うい。知ってしまったら最後、二度とは元の視点には戻れない。
そしてたぶん、何度読み返しても、この作品はどこか苦い。
忘れられない、というより、忘れさせてくれないのだ。
19.魂を削るように歌い、生きて、死んだ── 歌野晶午『ROMMY 越境者の夢』
その歌声で時代を魅了した天才歌手ROMMY(ロミー)が、レコーディングスタジオの密室で絞殺死体となって発見された。さらに、目を離した隙に遺体は何者かによって切り刻まれ、異様な装飾を施されるという猟奇的な展開を見せる。
彼女を長年支えてきたカメラマン中村は、深い悲しみと混乱の中、どこか不可解な行動を取り始める。
ROMMYの死の真相、そして孤高の天才が生涯隠していた驚愕の秘密とは。現在と過去、複数の視点が交錯しながら、彼女の謎に満ちた人生と事件の真相が明かされていく。
猟奇と純愛が交錯する、歌野ミステリの真髄
殺された歌姫は、死んでなお舞台の中心にいた。ROMMY。時代を震わせた天才ボーカリスト。
その死体は、レコーディングスタジオの密室で発見された。絞殺。さらに、目を離した隙に、切り刻まれ、芸術品のように装飾された。どうかしている。でも、それでも、どこかで納得してしまう。だって、それがROMMYという存在だったからだ。
彼女を支えたカメラマン・中村は、何かに取り憑かれたように行動し始める。恋だったのか、信仰だったのか、それすらも判然としない。しかし、彼が追い続けたその姿の先に、もうひとつのROMMYが浮かび上がってくる。
この物語は、犯人探しだけじゃ終わらない。むしろ、「ROMMYとは誰だったのか」が主軸になる。本人の語りはなくても、写真、歌詞、衣装、メイク、言葉の断片。それらのモンタージュが、ひとりの人間の輪郭を描いていくのだ。
しかも、その手触りがあまりにリアルで、「これって実在の人物だっけ?」と錯覚しそうになる。創作のはずなのに、ROMMYという名前が、どこかで本当に生きていたような感覚を引き起こす。
事件は猟奇的でショッキングだ。だが、その描写の先には、歪んでいながらもまっすぐな感情が潜んでいる。愛か、憧れか、所有欲か。なんなのかはうまく言えない。でも、間違いなくROMMYだけに向けられたものだった。それがまた、痛々しくて、美しい。
そして、終盤に明かされるタイトルの意味がまたズルい。「越境者の夢」。それはROMMYが歌に託したものでもあり、ROMMYに取り憑かれた誰かの、願いでもあった。
叶ったのか、壊れたのか、それすら判然としない。それでも、確かに夢だった。
鮮やかで、醜くて、まっすぐで、孤独。
そんなROMMYという幻影を追いかけ続けた一冊だ。
20.密室に挑む犯人たちのゲーム── 歌野晶午『密室殺人ゲーム王手飛車取り』
「頭狂人」「044APD」「aXe」「ザンギャ君」「伴道全教授」。奇妙なニックネームを名乗る5人のメンバーは、あるサイトのチャットルームに夜な夜な集い、互いに自作の殺人事件を出題し合うというゲームに興じていた。
だがその殺人は虚構ではない。彼らが提示する事件はすべて、実際に自らの手で行われた本物の殺人であり、このゲームの唯一にして絶対のルールは「出題者が犯人であること」だった。
謎解きのスリルと承認欲求のためだけに殺人を繰り返す彼らの狂気はやがて暴走し、ゲームの枠を越えた惨劇と裏切りが連鎖していく。
その果てに待つのは、想像すら許されない地獄なのか、それとも──。
リアル殺人ゲームという禁断の領域と、個性豊かな殺人者たちの頭脳戦
この小説、倫理の枠は最初から投げ捨ててる。5人のプレイヤーがネットで集まり、次々と実際に人を殺して、そのトリックを出題する。
そんなルールのゲームが始まる。どんなに人間が死んでも、彼らの目的は勝つこと。ただそれだけ。被害者はトリックのための駒に過ぎないのだ。
物語はチャット形式で進んでいく。発言者は「頭狂人」だの「044APD」だの、正体不明のハンドルネームばかり。でも、会話の中から性格や価値観が滲んでくるのがまたうまい。誰がどんな人間かは見えないまま、殺人と推理が冷ややかに続いていく。
注目すべきは、徹底してハウダニットに特化してるところだ。動機なんてどうでもいい。犯人当てもどうでもいい。とにかく「どうやって殺したか」に全振りしてくる。しかも、これがレベル高い。密室、アリバイ、視覚トリック、どれも本格好きのツボを直撃してくる構成ばかりだ。
それでいて、無駄にグロくはない。あくまで頭脳戦。暴力や恐怖に頼らず、論理だけで勝負してくる潔さが気持ちいい。殺人が「手段」として描かれてるからこそ、逆にぞっとする部分もある。
ただ、この作品がすごいのは、単なるトリックの応酬で終わらないところだ。中盤から、プレイヤーたちの過去が見え始めてくる。誰がどこで何をしていたのか。何を背負ってこのゲームに加わったのか。その糸が絡まり出すと、一気に物語が人間の話になる。
そして最後、出題者のひとりの正体が明かされたとき、ゲームは終わる。でもその終わり方がまたイヤらしくて絶妙で、頭では納得しても、感情のどこかに引っかかる何かが残る。そこまで計算されてるのが恐ろしい。
この小説は、謎解きに強い人だけじゃなくて、自分の価値観をグラつかされても平気な人にこそ勧めたい。
推理の楽しさと、倫理のなさと、人間の歪みが全部詰まった、まさに勝ち負けを超えたミステリだ。
21.操られていたのは誰か── 赤川次郎『マリオネットの罠』
フランス留学から帰国した上田修一は、恩師の紹介で、森に囲まれた洋館に暮らす峯岸姉妹のフランス語家庭教師となる。住み込みで三ヶ月、破格の報酬。だが館の地下には、三女・雅子が幽閉されていた。
繊細で美しい少女を救おうと動いた修一の行動は、やがて連続殺人事件の幕を開ける。
都市で頻発する猟奇殺人と、閉ざされた洋館の牢獄は繋がっているのか? 歪んだ欲望が交錯する中、修一は逃れられない闇に足を踏み入れていく。
赤川次郎初期の異色作、ダークな本格ミステリの魅力
フランス帰りの青年が、洋館に住み込んで姉妹にフランス語を教えることになる。報酬は破格。条件は三ヶ月の滞在。ただし、その館の地下には、三女が幽閉されていた。
この時点で、もう事件の匂いしかしない。しかし本当にすごいのは、そこから先だった。幽閉、誘拐、殺人──ロマンとサスペンスがどこまでも絡み合う展開に、逃げ場がない。
『マリオネットの罠』は、赤川次郎がまだ“売れる前”に書いた処女長編だ。のちの三毛猫ホームズや幽霊シリーズの軽妙さとは一線を画す、硬質でヒリついた本格ミステリ。構成は緻密、トリックは端正、文章は若干尖っている。でもそれがいい。
物語は一見ロマンチックに始まるけれど、途中から殺意の匂いが濃くなってくる。登場人物たちの誰もがどこか壊れていて、誰かが誰かを操作している。マリオネットの糸を引いているのは誰なのか。いや、そもそも操られているのは誰だったのか。
読み進めるほどに、細かく張り巡らされた伏線が効いてくる。すべてが繋がったときの快感は見事だ。しかも、そこに漂うのはどこか演劇的な空気。館の構造、登場人物の動き、セリフ回し、全部が舞台のように計算されている。これはミステリであると同時に、ひとつの密室劇だ。
殺人の動機は歪んでいる。でも、それだけじゃない。登場人物たちは皆、心のどこかに「誰かに救ってほしい」という叫びを抱えている。その孤独が事件を通して浮かび上がってくるのが、切ないのだ。
赤川ミステリの原点は、ここにある。とっつきやすさの裏に隠された、冷たい論理と、哀しみに満ちた構造美。改めて読むと、「ああ、この人は、最初から全部わかってたんだな」と思う。
おだやかな文体に油断していると、足元からすくわれる。まさに、罠だ。
22.ミステリ好きには向いていた夜── 東川篤哉『交換殺人には向かない夜』
私立探偵の鵜飼杜夫は、ある富豪の不倫調査のため、山奥に佇むその邸宅に使用人として潜入する。
時を同じくして、鵜飼の弟子である戸村流平は、ガールフレンドの誘いで彼女の友人が所有する山荘を訪れていた。さらに、寂れた商店街では一人の女性が刺殺される事件が発生し、地元の刑事たちがその捜査に乗り出す。
これら三つの出来事は、一見すると何ら関連性を持たないように思われた。しかし、その水面下では、周到に計画された「交換殺人」が静かに、そして着実に進行していたのであった。
ユーモアと本格トリックの絶妙な融合、烏賊川市シリーズの真骨頂
殺人トリックを肴にチャットで盛り上がるような現代とは違い、東川篤哉の『交換殺人には向かない夜』では、ずっと昔から誰かがやってみたくてしょうがなかった計画が、実際に動き出してしまう。
舞台は東川ミステリの聖地・烏賊川市。潜入調査中の私立探偵・鵜飼、バカンス中のその弟子・戸村、そして商店街で起きた刺殺事件を追う刑事たち。一見バラバラに見える3本の物語が、「交換殺人」の一言で束ねられ、ある瞬間からピタリと噛み合いはじめる。
本作はとにかく語り口が軽快で、会話もテンポもゆるくて笑える。なのに、ページをめくっていくうちに「あれ?」と首をかしげる瞬間が積み重なっていく。視点の繋ぎ、人物の立ち位置、誰がどこにいたか……その違和感が、終盤に来て一気に爆発する。
構成の妙に唸る。あからさまな伏線はない。でも、ちゃんと全部、あった。
東川作品の中でも特にこの一作は、バカミス寄りに見せかけて、実は極めて真面目な論理ミステリだ。トリックもちゃんとフェア、視点操作も見事、そして“誰が犯人か”というより“誰が誰か”に驚かされるタイプの仕掛けも効いている。
笑いながら読んでいたはずなのに、気づけば手のひらの上で見事に踊らされていた。そんな読書体験が、本作の最大の魅力だ。
東川氏は、登場人物たちの関係性や視点の隠し方に細心の注意を払い、さりげなく、しかし大胆な叙述トリックを仕掛けている。あえて説明を加えず、人間の先入観そのものを利用することで、「あの人がまさか……」という鮮やかな驚きを物語の終盤に用意しているのだ。
そして、とある人物の正体が明かされた瞬間、多くの読者は二重、三重の驚きに包まれることになる。その瞬間、物語の色調はがらりと変わり、それまで何気なく読んできた一行一行に、まったく異なる意味が立ち上がるのだ。
明るく、ユーモラスで、どこか人懐っこい登場人物たちに誘われて読み進めていた物語が、いつの間にかしっかりとした謎解きの愉しさと驚きを湛えた作品へと変貌している。
それこそが、『交換殺人には向かない夜』が放つ、唯一無二の輝きなのだ。
23.孤島と十角形と、新時代の幕開け── 綾辻行人『十角館の殺人』
九州の沖に浮かぶ孤島、角島。そこにはかつて中村青司という建築家が設計した青屋敷が建っていたが、半年前に凄惨な四重殺人事件の現場となり焼失した。
その島に、唯一残された奇妙な十角形の館「十角館」へと、ミステリ研究会の男女7人が合宿に訪れる。彼らは互いをエラリイ、ポウ、カーといった著名な海外ミステリ作家のニックネームで呼び合い、一週間を過ごす予定であった。
しかし、彼らの到着と時を同じくして、本土にいる元ミステリ研究会のメンバー江南孝明のもとに、死んだはずの中村青司から謎の手紙が届く。
そして十角館では、メンバーが一人、また一人と殺されていく連続殺人が発生。閉ざされた孤島で、彼らは見えざる犯人の影に怯え、互いに疑心暗鬼に陥っていく。
新本格の金字塔、衝撃の「あの1行」とミステリ史への影響
1987年。綾辻行人氏が世に放った長編デビュー作『十角館の殺人』は、日本のミステリ史においてひとつの時代を切り開くこととなった。
この作品から始まった「新本格ミステリ」という潮流は、以降の日本の推理小説界に鮮烈な衝撃を与え、今なお多くの作家と読者に影響を与え続けている。
舞台は孤島。建っているのは奇妙な十角形の館。集まったのはミステリ研究会の大学生たち。名前を捨ててポウだのカーだの呼び合って、オタク気質丸出しで過ごしていると、いつの間にか一人、また一人と殺されていく。完全なクローズド・サークル、これぞ本格、という導入だ。
だがこの小説、構造が二重になっている。島で進行する連続殺人と、本土にいる人物の調査パート。この二つが地味にリンクしながら、読者の先入観を上手くすり替えてくる。気づいたときにはもう遅い。
この作品を語るうえで欠かせないのが、「あの一行」だ。それまでのすべてが、たった数語で崩れ落ちる。世界がひっくりかえり、すべてが再構築される感覚。これこそがミステリの醍醐味、そして読者がずっと探し求めてきた、裏切られ方の最高峰だ。
密室、孤島、ダイイング・メッセージ、そして名探偵不在。王道の本格ミステリ要素をていねいに並べておきながら、それでいて枠組みを壊すほどの鮮烈な仕掛けが隠されている。しかも、やり方が実に鮮やかだ。反則すれすれのギリギリを、本格の旗印を掲げながら、真っ正面から突き抜けてみせた。
ただ意外な犯人が明かされるだけの話じゃない。思い込みごとひっくり返される快感が、ここには詰まっている。
そして何より、この作品は出発点だということも忘れたくない。ここから新本格というジャンルが生まれ、次々と継承者が登場した。その意味では歴史的な一作だが、ただ古典というわけではない。今読んでも、構成の妙とトリックの切れ味に魅了されてしまう。
そう、これはまさに「騙される快感」が詰まった一作だ。読み終わったあと、もう一回最初から見直したくなる。いや、きっと誰もがそうする。しっかり騙されて、なおかつ納得できる。こんな体験はそうそう味わえるもんじゃない。
というか、綾辻行人という作家が、いきなりここまでの傑作を世に送り出したこと自体が事件みたいなものだ。
そしてこの作品以降、日本の本格ミステリは「新本格」という名のもとに、新たな時代に突入していく。
すべてのミステリ好きが、必ずいつか通る場所。
それがこの十角形の館だ。
24.終わらない迷宮と、終わらない物語── 綾辻行人『迷路館の殺人』
著名な推理作家、宮垣葉太郎が死の直前に遺した奇妙な館「迷路館」。その地下深くに築かれた館は、その名の通り複雑怪奇な迷路構造をしていた。
宮垣の弟子である四人の作家たちが、莫大な遺産と「迷路館」のすべてを賭けて、この館を舞台にした推理小説の競作を開始する。
しかし、それは同時に恐るべき連続殺人劇の幕開けでもあった。閉ざされた館の中で一人、また一人と作家が殺されていく。探偵役として招かれた島田潔は、この迷宮の謎と犯人に挑む。
迷宮の館と作中作が織りなす多重解決の妙
綾辻行人の『迷路館の殺人』は、シリーズ中でもひときわ構造にこだわった異色作だ。
館が物語の主役であることは、このシリーズではもうおなじみだけど、今回はその仕掛け方がかなり尖っている。物理的な迷路としての館と、物語そのものの迷路。この二重の迷宮構造が、読み進めるほどに効いてくる。
舞台は、地下に広がる異様な建築・迷路館。亡き推理作家・宮垣の遺言で集められた4人の弟子たちが、この館で推理小説の競作を始めるところから物語は動き出す。ただし始まるのは小説の執筆だけじゃない。連続殺人という、血の競作も同時に進行していくのだ。
探偵役として登場するのはおなじみ島田潔。彼がひとつずつ迷路の鍵を開いていく終盤は、ミステリファンなら誰もが快感を覚える展開だ。伏線の拾い方も見事だし、図面と照らし合わせる楽しさまである。物語の中に入り込んで自分も推理してるような感覚になる。
でも、この作品の真の見どころはそこじゃない。ラストに待っている「もうひとつの視点」。これがすべてをひっくり返す。人間関係の構図も、読んできた物語の意味すらも変わって見えるあたり、綾辻作品らしい意地悪さが炸裂している。
しかもその仕掛けが、物語のどこにも嘘をついていないというのがまた厄介だ。読み返して初めて、「ああ、あの描写か」と気づく瞬間がある。読ませるための迷路じゃなくて、考えさせるための迷路がここにはある。
シンプルな構成に見えて、実は三重にも四重にもひねりが加えられている、緻密で骨太なミステリだ。騙されたとか、驚いたでは終わらない。ちょっとムッとしながら、でも気づけばもう一度読み返してる、そんなタイプの作品だ。
『迷路館の殺人』は、物語そのものが一つの謎になっている。
これを読み終えることが、つまり迷路を抜けることだ。
抜けたつもりが、もう一度迷い込んでるかもしれないが。
25.知性と悪意の罠── 綾辻行人『どんどん橋、落ちた』
ミステリ作家である「私」(綾辻行人)のもとに、大学の後輩であるUと名乗る青年が、自作の犯人当て小説を持ち込み、挑戦状を叩きつける。
表題作「どんどん橋、落ちた」では、古びて危険な「どんどん橋」の向こうにある秘匿されたM村が舞台となる。そこでキャンプをしていた大学生たちと、その弟ユキトを巻き込み、殺人事件が発生する。
続く「ぼうぼう森、燃えた」では、大規模な山火事の中での事件が描かれる。各編は「読者への挑戦」形式を取り、綾辻自身が探偵役となって謎に挑むが、そこには巧妙な罠が仕掛けられている。
遊び心と意外性に満ちた5編を収録したミステリ短編集。
著者自身が謎に挑む、遊び心満載の挑戦型ミステリ
綾辻行人の短編集『どんどん橋、落ちた』は、シンプルな構造の中に毒と遊び心をしのばせた、ミステリの実験場だ。
表題作を含む5編すべてが「読者への挑戦」形式で構成されていて、探偵役はなんと作者本人。いわば「犯人当てクイズ」を仕掛けられているような感覚になる。
舞台は古びた橋の向こうの山村、山火事で混乱する森、やけに既視感のある家庭など、いずれもクセの強い空間ばかり。殺人事件が起きるのは決まってその異常空間の中だが、手口は決して派手ではない。なのに引っかかる。ミスリードの配置、視点の誘導、言葉選びの巧さ。細かく張られた罠が効いてくる。
「どんどん橋、落ちた」や「ぼうぼう森、燃えた」では、トリックと舞台設定ががっちり噛み合っている。特に、橋や火事という隔離空間をミステリの枠組みとして使うのが実にうまい。
そして何より印象的なのが、「伊園家の崩壊」。笑っていいのか引くべきなのか、感情の置き場に困るようなブラックな家庭劇が、気づけばちゃんと推理ものとして着地している。
全体として、ロジックの精度はかなり高い。けれどそれ以上に、「正々堂々と騙す」という綾辻らしさが際立っている。
「嘘はついていない。ただ、肝心なことは言っていない。」
そんな構えでニヤつきながら短編を投げてくる感じが、なんとも愉快だ。
謎解きの快感と、薄暗い笑いが綯い交ぜになったような一冊。肩の力を抜いて読めるのに、読み終わるとスコンと膝を撃ちたくなる。そんな綾辻マジックが、短編のなかでしっかり息づいている。
「正直に嘘をつく」というやり方にニヤリとできるなら、この短編集はかなりおすすめだ。
26.混沌の時代に咲いた、論理と狂気のアンサンブル── 坂口安吾『不連続殺人事件』
終戦間もない日本。詩人である歌川一馬のもとに、旧家の若妻、珠緒から奇妙な依頼が舞い込む。それは、山奥の豪邸でひと夏を過ごしてほしいというものだった。
その豪邸には、歌川夫妻をはじめ、弁護士、劇作家、女優など、多彩な男女が集う。
しかし、その館では異常なまでの愛と憎しみが交錯し、やがて次々と不可解な殺人事件が発生する。八つもの殺人が、「不連続」に起こる中、その裏に隠された悪魔的な意図とは何か。
探偵役が複雑な人間関係と巧妙なトリックに挑む、日本ミステリ史に輝く傑作。
戦後文学の旗手が挑んだ本格ミステリ、複雑な人間模様と心理の足跡
愛だの、芸術だの、自由だの、戦争が終わったあとも、人は結局、言葉で自分をごまかし続ける生き物なのかもしれない。そんな時代に生まれたのが、坂口安吾の『不連続殺人事件』だ。
舞台は戦後すぐの日本。山奥の洋館に集められたのは、小説家に画家、詩人、弁護士、そして妖しい女優たち。なんというか、いかにも火種が揃った顔ぶれだ。ここで八人もの人間が殺されるんだから、そりゃもう地獄絵図だろうと思うじゃないか。だが、そう単純でもない。
この小説の最大の魅力は、バラバラに見えた事件のピースが、最後にカチッと噛み合って一本の筋になる、その構成力の強さにある。しかも、そこに至るまでの会話や仕草、誰がどこにいたのかという些細な描写まで、すべてが意味を持つ。
殺しの動機が愛憎や嫉妬だとしても、その発露がいちいち理屈で貫かれているところに、安吾のしつこいまでの論理への執着が見える。一見破滅的な人間たちが、理性と狂気のあいだでバランスを取ろうとする姿が、なんとも滑稽で切ない。
そして忘れちゃいけないのが「読者への挑戦」だ。これがまた堂々としていて、にやりとさせられる。自信満々に「わかったか?」と突きつけられると、逆に潔く負けを認めたくなるような、そんな気分になる。
坂口安吾が本気で本格ミステリを書いたらどうなるか。その答えが、この一冊だ。混沌と情熱と推理のバランスが絶妙で、ひとクセどころか三クセある作品ではあるけれど、だからこそ忘れがたい。
きっちり騙されて、うまく納得させられる快感。その後味は、妙に鮮やかに残る。
『不連続殺人事件』は、坂口安吾という特異な文学者が、探偵小説への深い愛と敬意を込めて書き上げた、戦後日本ミステリの金字塔だ。
混沌の時代に咲いた、論理の結晶。
その光は今もなお、私たちを試し、そして魅了し続けている。
27.二つの絶望が交わるとき── 貫井徳郎『慟哭』
都内で連続幼女誘拐殺人事件が発生し、捜査は難航を極める。捜査一課長の佐伯は、キャリア組としてのプレッシャーと警察内部の不協和音、マスコミからの執拗な追及に苦悩しながら事件を追う。
時を同じくして、もう一つの物語が語られる。それは、亡くした娘の蘇生を願い、新興宗教にのめり込んでいく男、松本の姿。彼は、教団の教えに従い、娘の「依代」となる幼女を次々と誘拐し、殺害していく。
一見無関係に見える二つの物語は、やがて衝撃的な形で交錯し、読者を慟哭の淵へと突き落とす。貫井徳郎氏のデビュー作にして、日本ミステリ史に残る傑作。
二つの絶望が交わる時、魂を揺さぶる慟哭の真相
誰かを信じることで救われるなら、人はどこまで堕ちてもいいのか。
そんなことを考えさせられるのが、貫井徳郎のデビュー作『慟哭』だ。警察小説と宗教サスペンスが並走しながら、最悪の形でぶつかり合う。しかも、ぐうの音も出ないほど完璧な構成で。
物語は連続幼女誘拐事件の捜査にあたる刑事・佐伯と、亡き娘への執着から宗教にのめり込んでいく男・松本の視点が交互に進んでいく。前者は焦燥感に押し潰されそうな現場、後者は崇拝と救済に憑かれた世界。どちらも逃げ場がなく、追い詰められていく感触がリアルだ。
最初は無関係に見えるふたつの線が、やがて見えない針金で結ばれていたことがわかる。その瞬間、物語全体がぐるりと反転する。ある一文が見えてくると、そこまで読んできた自分自身の視点まで疑わしくなってくる仕掛けがすごい。
しかし、この作品の怖さは、トリックだけじゃない。むしろ、根っこにあるのは人の弱さだ。愛する者を失って、空っぽになって、それでも何かを信じたいという気持ち。誰も悪意だけで動いているわけじゃないのに、最悪の結果だけが残る展開には、本当に胸が詰まる。
宗教に頼る男をただの狂人にしないところも巧みで、こちらの感情がグラグラ揺れてしまう。悲劇を引き起こすのは、善意の裏返しかもしれないという想像が、読後もずっと頭に残る。
読み終えても気持ちは晴れない。でも、それがこの作品の持ち味でもある。目を背けたくなるような現実の中に、ミステリという形式を借りてまっすぐ踏み込んだ一作だ。感情と論理、その両方にしっかり向き合う覚悟が試される。
言葉にならない哀しみの正体に、ようやく名前がついたとき、この物語は真価を発揮するのだ。
慟哭とは何か。
それは、この小説そのものが教えてくれる。
28.壊れてしまった夏の記憶── 道尾秀介『向日葵の咲かない夏』
夏休みを目前にした終業式の日、小学四年生のミチオは、欠席したクラスメートのS君の家を訪れる。そこで彼が見たものは、首を吊って死んでいるS君の姿だった。
しかし、警察に知らせて戻ると、S君の死体は忽然と消えていた。一週間後、ミチオの前にS君があるモノの姿となって現れ、「自分は殺されたんだ」と訴える。
ミチオは、三歳の妹ミカと、S君と共に、S君を殺した犯人を探し始める。少年の視点から描かれる、常に異常性がつきまとう幻想的でグロテスクな夏の物語。
少年期の残酷な幻想、叙述トリックが織りなす悪夢的リアリティ
この夏は、なんだか様子がおかしい。そう思ったときには、もう引き返せない場所まで来てしまっている。
道尾秀介の『向日葵の咲かない夏』は、小学生の語りで始まる。なのに、その語りのどこかがずっとズレている。ほんのわずかな歪みが、読んでいるこちらの感覚を壊してくるように。
夏休み前に起きたクラスメートS君の自殺。だけど遺体は消え、数日後にS君は「あるもの」の姿になって再登場する。しかも「自分は殺された」と語り出す。ここだけ切り取れば、幻想系のジュブナイルっぽく聞こえるかもしれない。でもこれは、もっと重くてもっと黒いミステリだ。
とにかくミチオの世界が不穏すぎる。子どもらしい無邪気さと残酷さが入り混じっていて、読者は彼の語りをどこまで信用していいのか、常に揺さぶられる。家族との距離感も、友達との接し方も、なにかおかしい。違和感が積もって、最後にはある種の破裂を迎えるのだ。
叙述トリックとしても強烈で、真相が明かされたときには背筋が冷える。構造的に見事なうえに、感情にもずっしりと響いてくる。しかもそこにあるのは「驚き」じゃない。「そうだったのか……」と呟くしかない、抜けるような虚しさだ。
いわゆる「イヤミス」の代表格とされるのも納得で、人間の孤独や暴力や絶望が、遠慮なくページに滲んでくる。児童虐待や家庭内の歪みといった描写も重くて、読んでいるとどこかで心が軋む。
なのに、読まずにはいられない。物語に隠された歪みと真実が気になって、目が離せなくなるのだ。
ラストまで読んで、タイトルの「向日葵」がなぜ咲かなかったのかが腑に落ちたとき、軽く息が止まる。
それはきれいな感動じゃない。
むしろ胸に残るのは重さだ。
この物語の夏は、光の中じゃなく、影の中で終わっていく。

29.雨音の向こうに見えたもの── 道尾秀介『龍神の雨』
ある雨の日、二組の兄妹・兄弟の運命が交錯する。母を海の事故で亡くした高校生の添木田蓮と中学生の妹・楓。
そして、同じく母親を病で亡くした中学生の溝田辰也と小学生の弟・圭介。彼らはそれぞれ、継父や継母との新しい家族関係の中で、疑念や不安を抱えながら暮らしていた。
降り続く雨が不穏な雰囲気を醸し出す中、ある出来事をきっかけに、彼らの抱える猜疑心や思い込みが、取り返しのつかない悲劇へと繋がっていく。過去の事故の真相、そして現在進行形で起こる事件。
道尾秀介が描く、家族の絆と人間の心の闇が複雑に絡み合うサスペンスミステリ。
降り続く雨と心の闇、交錯する運命が導く衝撃の結末
たとえば、誰かの表情ひとつを読み違えたまま時間が過ぎてしまったら。
たとえば、たったひと言が、ほんの少し届かなかったら。
『龍神の雨』は、道尾秀介が描く心理サスペンスのなかでも、ひときわ湿度の高い作品だ。
舞台となるのは、複雑な家庭環境を抱えた二組の兄妹・兄弟。高校生の蓮と妹の楓。中学生の辰也と小学生の圭介。それぞれが親を亡くし、継父や継母とともに再構成された生活のなかで、不安や不信を募らせていく。
この物語に血が通っているのは、彼らの怒りや疑いがすべて家族のことだからだ。信じたい。でも信じきれない。好きでいたい。でも距離を感じる。そんな揺らぎが積み重なって、やがて取り返しのつかない事件を呼び寄せる。
道尾作品らしく、叙述の仕掛けはしっかり効いている。誰かの視点にすっかり飲み込まれていたと思ったら、いつの間にか別の角度に立たされている。なにげなく読んでいたあの場面が、ラストに向かって見え方を変えてくる。しかも、その変化は論理ではなく、感情の揺らぎによって訪れる。だから苦い。
登場人物の誰もが悪人ではない。ただ、想像が足りなかったり、言葉にできなかったり、譲れなかったりするだけだ。しかし、その“だけ”が積み重なると、人は簡単に取り返しのつかない選択をしてしまう。
結末は決して派手じゃない。でも、確実に響いてくる。「私が間違っていたのか?」と、誰かがつぶやくその瞬間こそが、本作の本当のクライマックスだ。
雨が止んだあとに残るのは、すがすがしさじゃない。けれど確かに、何かが変わっている。
『龍神の雨』は、そんな変化の物語だ。
30.聴くことで暴く、音の中に潜む真実── 道尾秀介『片眼の猿』
盗聴を専門とする探偵である「俺」は、ある楽器メーカーからライバル社の産業スパイを洗い出すという依頼を受ける。
調査の過程で、同じく盗聴を仕事とする女性・冬絵と出会い、彼女をチームに引き入れようとするが、その矢先に殺人事件が発生し、彼らは否応なくその渦中に巻き込まれていく。
事件の真相を探る中で、主人公の亮が秘めてきた過去の衝撃的な記憶が呼び覚まされ、本当の仲間とは、家族とは、そして愛とは何かを問う物語が展開する。
道尾秀介が「傑作」と銘打つ、謎とソウル、そして技巧が絶妙なハーモニーを奏でる長編ミステリ。
盗聴探偵が見た世界の歪み、外見と内面の真実を問う物語
音は嘘をつかない。
そう言われたって、本当にそうか? と疑ってしまうが、この物語を読めば「確かに」と頷くかもしれない。
道尾秀介の『片眼の猿』は、探偵もののようでいて、もっと不思議な手触りのある一作だ。探偵役を務めるのは、盗聴専門の男。目ではなく、耳で世界を観察するタイプだ。
そんな彼が引き受けたのは、ある楽器メーカーの産業スパイ調査。地味だけど、裏では大騒ぎだ。そこへ現れるのが、同業の冬絵という女。彼女との出会いが、事件をぐっと人間くさい方向へと導いていく。
何が面白いって、事件の核心に迫るほどに、「音」がどれだけの情報を持っているかってことに気づかされるところだ。声の震え、会話の間、足音、ため息。そういう細かい揺らぎの中に、誰が何を隠しているのかが浮かび上がってくる。見えないからこそ、見えてしまうものがあるという感覚。
ただしこれは、ただの捜査物じゃない。登場人物たちは、それぞれ過去や傷を抱えていて、その背景が事件とゆっくり絡んでくる。愛とか、家族とか、そんなベタなテーマが決して押しつけがましくなく、ちゃんと効いているのがいい。
もちろん、道尾氏の代名詞ともいえる叙述トリックも、本作で鮮やかに炸裂する。終盤、ある一文がすべてを覆したとき、それまで「見えていた」はずの風景が、がらりとその色を変えるのだ。
「騙された」と同時に「納得する」あの快感。それは、読者自身の先入観がもたらした、ひとつの罠である。
『片眼の猿』は、視線じゃなく、鼓膜を通して心に染みてくるタイプのミステリだ。
派手さはないけど、耳をすませば、いろんなことが見えてくる。
31.目の前の事件と、ずっと前の地獄── 北村薫『盤上の敵』
主人公である末永純の妻、友貴子が自宅で人質となる立てこもり事件が発生した。純は警察や友人、同僚を巻き込みながら、妻を救出するために奔走する。
しかし、物語が進むにつれて、友貴子の壮絶な過去や、純の行動の裏に隠された衝撃的な真実が明らかになっていく。
事件の背後には、過去のいじめや暴力といった深刻な問題が複雑に絡み合っており、単純な人質事件ではないことがわかってきて……。
巧妙な心理戦と重層的な人間ドラマの深淵
「人質事件」と聞いてイメージするような緊迫感や銃声は、この小説にはない。
でも『盤上の敵』には、それを超えるくらいの怖さと切実さが詰まっている。北村薫の筆致は、いつも穏やかで繊細だけど、今回は違う。優しさじゃなく、鋭さが前に出ているのだ。
物語の起点は、主人公・純の妻が立てこもり犯の人質になるという事件。あらすじだけ見ればサスペンスだし、実際に状況は切迫してる。でも、すぐにわかってくる。これは単なる事件じゃなくて、もっと深くて古い傷が、いま開き直ってきた話なんだと。
舞台の外側では警察が動き、関係者がざわめくが、物語の核心はもっと内側にある。妻・友貴子の過去。それが本当にえげつない。いじめ、暴力、見て見ぬふり、無関心。どれも現実にありそうなことばかりで、そのリアルさが胸を圧迫する。
しかも構成が上手い。現在の事件と過去の出来事が交互に語られるうちに、少しずつ視界が歪んでくる。誰が加害者で、誰が被害者なのか。何が正義で、どこからが欺瞞なのか。登場人物たちの言葉の中に、小さな違和感が潜んでいて、それが最後に大きく跳ね上がる。
終盤の展開は、本当に痛烈だ。立てこもり事件の裏側に、こんなにも複雑な想いが渦巻いていたのかと思わされる。北村薫がこの作品の冒頭で「心を休めたい人には向いていない」と言ったのも納得だ。気持ちがふっと重くなる。
でも、それでも最後まで読ませる力がある。人間の脆さと強さ、その両方に正面から向き合おうとした一冊だ。
やさしい物語しか書かないと思ってた人ほど、読んでみてほしい。
こんな手で迫ってくる北村薫は、かなり貴重だ。
32.信じたものが罠になる── 倉知淳『星降り山荘の殺人』
職場で上司を殴ってしまった杉下は、その処分として人気タレント「スターウォッチャー」こと星園詩郎のマネージャー見習いを命じられる。星園と共に訪れたのは、雪に閉ざされた山奥のオートキャンプ場であった。
そこには、キャンプ場のオーナー社長岩岸とその秘書、女性に人気のロマン小説家あかねとその秘書、胡散臭いUFO研究家の嵯峨島、そして星園目当ての女子大生二人組など、一癖も二癖もある人物たちが集っていた。
吹雪によって電話も通じず、山荘は完全なクローズドサークルと化す。そんな中、第一の殺人事件が発生。杉下は、星園の鋭すぎる観察眼と推理に巻き込まれる形で、事件の調査に乗り出すのだった。
読者への挑戦と鮮やかな逆転劇
雪がすべてを覆い尽くした夜、真実さえも白く塗りつぶされてしまうのかもしれない。
倉知淳『星降り山荘の殺人』は、クローズドサークルの形式美と、作中作のように練られた構造のトリック、そして読者の油断を逆手に取る巧妙さがひとつに溶け合った、これぞ本格ミステリという一作だ。
舞台は雪に閉ざされた山奥のキャンプ場。そこに集った面々はアウトドアとは程遠いクセ者ぞろい。星を見るタレント、ロマン小説家、UFO研究家、女子大生……。見た目はにぎやかでも、次第に空気が軋みはじめる。
事件が起きるのは、そんな場が整ったころだ。電話は不通、逃げ道はない。完全な閉鎖空間。しかも、章ごとに「ヒント」が明示されるというサービス付きだ。
そう、これは挑戦状でもある。
でも、そこに落とし穴がある。
ヒントは確かに正しい。なのに、導き出した答えが間違っているのはなぜか。思い返せば、ちゃんと伏線は張られていた。誰も嘘をついていない。ただ、最初から信じてしまっていた前提が、いつの間にか罠になっていたのだ。
犯人が明かされたあとにも、もうひとつ仕掛けがある。そこがまた憎い。終わったと思っていた物語が、最後にもう一段階、裏返る。しかも、それはロジックのうえで完全に成立していて、読んだあとに悔しさとニヤけが止まらなくなるのだ。
気づかないうちに、こちらも盤上の一駒になっていた。そう思わされる構成の妙。うっかり信じたものが、いちばん手強い敵になる。
『星降り山荘の殺人』は、フェアであることを極限まで突き詰めた反則なしの頭脳戦だ。
そして、読み手が物語の一部となる、極めて現代的な参加型ミステリである。
あなたが信じたものは、真実だっただろうか。
それとも、仕掛けの一部だったのだろうか。
33.笑うカエルと吊るされた死体── 中山七里『連続殺人鬼カエル男』
ある雨の日、マンションの13階から、口をフックで固定された全裸の女性死体が吊るされて発見される。傍らには、子供の手によるような稚拙な犯行声明が残されていた。
「きょう、かえるをつかまえたよ。くびにひもをかけて、おうちにつるしておいたよ」。これが、街を恐怖に陥れる連続殺人鬼「カエル男」の最初の犯行だった。
やがて第二、第三の殺人が発生し、その残虐さと異常性は増していく。警察の捜査は難航し、街は混乱と不安に包まれる中、刑事たちは執念で真相に迫ろうとする。
戦慄の猟奇殺人と社会の闇
はじまりは、風に揺れる一体の死体だった。
全裸で、首を吊られ、口をフックで固定されている。隣には、幼い子どもが書いたような字で綴られた稚拙な声明文。「きょう、かえるをつかまえたよ」──。それは、この国のどこにでもありそうな地方都市に突如現れた、連続殺人鬼〈カエル男〉の第一声だった。
この時点で、本作はもう読者の足元をすくってくる。猟奇的な手口と、あまりに無垢な文体。そのギャップが笑えない不気味さとして迫ってきて、やがて恐怖が社会全体を侵食しはじめる。
中山七里の筆は、ここでも容赦がない。警察の捜査が追いつかないうちに、第二、第三の犠牲者が出る。しかもその死に方はどれも胸が悪くなるほど残酷だ。けれど、その残酷さが無意味ではないところが、この作品のすごさだ。
カエル男が何を選んで殺しているのか、なぜこのメッセージを残すのか、その意味が少しずつ見えてくるにつれ、警察も読者も、安易な同情や怒りでは太刀打ちできないなにかにぶつかっていく。
正義感では解けない事件。共感では届かない狂気。
そこにあるのは、社会が置き去りにしてきた歪みと、無関心が積み重ねてきた見えない暴力だ。そして、それを象徴するように、「犯人」とされる存在の背後には、さらに深く重たい真実が待ち構えている。
終盤、すべてのピースがはまったとき、目の前に立ち現れるのはただの衝撃ではない。それは、心の中にある小さなひび割れが音を立てて崩れていく感覚だ。
この作品が突きつけてくるのは、「誰かが悪い」という単純な結論ではない。そうではなく、誰もが無関係ではいられない、という冷たい現実だ。
『連続殺人鬼カエル男』は、怖いだけのミステリじゃない。
読み終えても心がざわめいたまま止まらない、社会と人間のいびつさをえぐり出す凶器のような物語だ。
34.殺人鬼が探偵になるとき── 殊能将之『ハサミ男』
美少女を狙い、ハサミで首を刺すという残忍な手口で世間を震撼させていた連続殺人鬼「ハサミ男」。次なる標的に選んだ少女への犯行を目前に、彼は驚愕する。その少女が、自分と全く同じ手口で殺されていたのだ。
獲物を奪われた怒りと困惑の中、「ハサミ男」は独自に犯人捜しを開始する。一方、警察はこの事件を彼の新たな犯行と断定し捜査を進める。
こうして、本物の殺人鬼が“自分ではない犯人”を追うという、倒錯した追跡劇が幕を開けるのであった。
ミステリの枠を壊す快作
美少女ばかりを狙う連続猟奇殺人鬼、通称「ハサミ男」。彼は三番目の獲物を狙っていた。
が、直前でその少女が自分と同じ手口で殺されているのを発見してしまう。自分以外に「ハサミ男」を名乗る奴がいる。だったら、そいつを見つけ出してやる。そんな怒りと屈辱に突き動かされて、本物の殺人鬼が犯人を探しはじめる。
そう、これは倒錯しまくった殺人鬼が探偵役の物語だ。
異常な設定だが、読み始めてみると、驚くほど理にかなっている。殺人者だからこそわかる心理、手口、痕跡。その視点で進む追跡劇は、まるで鏡の中を覗いているような不気味さを孕んでいる。
ただ、この作品が本当にすごいのはそこからだ。
視点人物の語りを信じきっていた読者は、中盤から徐々にズレを感じはじめる。何かがおかしい。でも気づいたときにはもう遅い。叙述トリックの仕掛けが、一気に読み手の認識をひっくり返してくるのだ。
しかもこの反転は、ただのトリックではない。読み終えたあと、自分がどこで騙されたのか、なぜそこを信じ込んでしまったのかまで、すべてが意味を持ってくる構造になっている。これはもう、物語の形を使った思考実験だ。
最後に残るのは、「誰が犯人だったのか」以上に、「自分はなぜそう読んでしまったのか」という感覚のほうかもしれない。
信頼、共感、偏見。そういったものが、物語の中でどう作用するかをまざまざと見せつけられる。
『ハサミ男』は、そんな倫理と構造の境界を攻めまくる異端の傑作だ。
35.記憶の迷宮で鏡と語る── 殊能将之『鏡の中は日曜日』
物語は複数の視点と時間軸で展開される。第一章はアルツハイマーを患う「ぼく」の視点で語られ、過去の殺人事件の記憶が断片的に蘇る。
第二章では、14年前に奇妙な館「梵貝荘」で起きた弁護士刺殺事件の再調査に乗り出す現代の探偵、水城の活躍が描かれる。
梵貝荘の主は「魔王」と呼ばれる異端の仏文学者であり、一家の死という不穏な過去を持つ。第三章で、これらの物語が収束し、驚愕の真相が明らかにされる。
多層的トリックと名探偵の肖像
鏡の中で、ぼんやりした自分と会話するところから始まるミステリがある。
それも、アルツハイマーを患った老いた男の語りで、しかもその語りが、どうにも現実と過去の境界が怪しい。妙に叙情的で、断片的で、でもなぜか惹きつけられてしまう。
殊能将之の『鏡の中は日曜日』は、一言でいえば「ずらしの美学」が効いた一作だ。
第一章では、そんな壊れかけた記憶がぼそぼそと語られ、その中にうっすらと殺人の匂いが漂ってくる。続く章では、探偵・水城が再調査のため梵貝荘という奇妙な館に向かい、過去の事件の断片を拾い上げていく。
これがまた地味な作業のようでいて、拾えば拾うほど地面がズレていくのだ。まるで足元に穴が空くような感覚が、ぐらりとくる。
特筆すべきは、叙述の構造と語りの温度差だ。誰が何を語っているのか、どこまでが事実なのか。そういう根幹が、ふとしたタイミングで反転する。それも派手なトリックではなく、感情の振れ幅で読み手の立ち位置をすり替えてくるのだ。
そして、後半で訪れるある「視点の揺れ」によって、この物語はそれまでの顔つきを変える。ちょっとした配置、言葉の間、その選び方。何気ない描写の中に、しっかりした構造の歯車がはめ込まれていたことに気づく。
だまされたというより、「ああ、そこからか」と納得してしまうのが、この作品のうまさだ。
『鏡の中は日曜日』は、推理を楽しむための本というより、記憶の空白を旅するような感覚で読むべき作品だと思う。
現実が曖昧になるその距離感を、ちゃんとミステリとして成り立たせてしまうところに、殊能将之という作家の凄みがある。
36.他人の目で見た世界が、自分を壊していく── 乙一『暗黒童話』
主人公の女子高生なみは、不慮の事故で記憶と左目を失う。
移植手術によって死者の眼球を提供された彼女は、やがてその左目が見せる奇妙な映像――眼球の以前の持ち主である冬月和弥の記憶――に導かれる。和弥が見ていた風景や出来事の断片を頼りに、なみは彼が生前に住んでいた町へと旅立つ。
そこでは、和弥が巻き込まれた悪夢のような事件の真相と、人間の心の奥底に潜む深い闇が彼女を待ち受けていた。
歪んだ瞳が見る残酷な現実
目を移植されたことで、他人の記憶まで引き継いでしまった──そんな異様な設定を、美しさとグロさのギリギリで成り立たせるのが、乙一の恐ろしいところだ。
『暗黒童話』の主人公・なみは、事故で左目と記憶を同時に失う。そして、移植されたその目が見せるのは、元の持ち主・冬月和弥の人生の断片。夢か幻か、はたまた本物か。その映像に突き動かされるようにして、なみは彼の足跡をたどり、知らなくてよかった世界に足を踏み入れていく。
この小説、ホラーともミステリーともファンタジーとも言いきれない、不思議なジャンル感をまとっている。語り口はシンプルなのに、目の前に現れる風景がどこか濁っていて、重たい。なみが見せられる光景は、過去の事件の残滓だったり、和弥の心の底に沈んでいた感情だったりして、すごく生々しい。
物語に並行して挿入される「カラスが目玉を運んでくる童話」は、地味に強烈だ。子ども向けを装ったその話が、ぜんぜん可愛くない。むしろ、なみの置かれている現実の残酷さと、ぴたりと重なってくる。
見たくないのに見えてしまう。自分のものじゃないのに、やけにリアルに心を侵してくる。そんな「視ること」の暴力性が、ひしひしと迫ってくる。
終盤で見えてくるのは、予想を裏切る構造の反転。あれもこれも、最初から仕掛けられていたんだと思い知らされる。そして、それでもなお胸に残るのは、どこかにあった優しさだ。
『暗黒童話』は、怖いだけの話じゃない。誰かの記憶に触れたとき、その人の痛みを背負ってしまうことがある。
それでも進むか、それとも目を閉じるか。
その分岐のギリギリで揺れ続ける物語だ。
37.語りが罠になるとき── 横溝正史『夜歩く』
物語は、屋代寅太という三文探偵作家の視点から、古神家で起こる連続殺人事件が小説仕立てで語られる。
古神家は旧家であり、複雑な人間関係と愛憎が渦巻いていた。初代当主の古神織部が残した予言めいた言葉と、夢遊病に悩まされる美しい未亡人・八千代。
そんな中、屋敷を訪れていた佝僂(せむし)の画家が首なし死体で発見される。さらに、八千代の兄も行方不明となり、事態は混迷を深める。
金田一耕助は、戦時中の恩人からの依頼でこの事件に関わることになるが、事件の語り手である屋代自身が、実は深い秘密を抱えていることが次第に明らかになっていく。
闇を彷徨う魂と反転する物語
金田一耕助シリーズのなかでも、妙に引っかかるのがこの『夜歩く』だ。
首なし死体、夢遊病の未亡人、背を丸めた画家、そして屋敷に残された奇怪な言葉。横溝正史が得意とする「旧家×因縁×奇人」の三点セットに、今回はもうひとつ、強烈な語りの仕掛けが加わってくる。
物語の語り手は、三文小説家の屋代寅太。彼が書くという体裁で話は進み、古神家といういわくありげな一族をめぐる殺人事件が展開していく。読み始めた瞬間は、金田一そっちのけで屋代の語りにぐいぐい引き込まれる。しかし気づくと、その語りの中に、どこかおかしい空気が漂い始めるのだ。
語っている本人が、なんだか信用ならない。登場人物を妙に主観的に見ていたり、自分の行動を都合よく省略していたり……とにかく、読んでいるこちらもいつの間にか、その偏った視点をまるごと受け入れてしまっているのだ。
で、終盤。いきなり金田一がぐいっと出てきて、あの屋代の語りをばらばらに解体してみせる。しかもそれが論理でねじ伏せるというより、見えてなかった真実を一つひとつ照らしていくような感じで、やられたと思う。
それまでの展開も、それなりに衝撃はある。でも本当にすごいのは、語りそのものが伏線だったという一点に尽きる。
しかもこの小説、1948年に出たというから驚く。まだ戦後の混乱が残る時代に、こんなメタな構造の叙述トリックを仕掛けてた横溝のセンスが凄すぎる。
横溝作品というと「おどろおどろしい雰囲気と残酷描写」がフィーチャーされがちだけど、この作品では「語りの視点」という純度の高いミステリ要素で魅せてくるのだ。
『夜歩く』というタイトル通り、登場人物は皆、自分のなかの夜をさまよっている。
幻想と現実、嘘と真実。
その境界線をふらふら歩かされる感覚こそ、この作品のいちばんの楽しみだ。
38.蝶のように華やかで、刃のように鋭い── 横溝正史『蝶々殺人事件』
昭和12年、歌劇団の奔放な花形ソプラノ歌手・原さくらが、大阪公演の会場に運び込まれたコントラバスケースの中から、薔薇の花びらと共に死体となって発見される。
事件の捜査に乗り出したのは、名探偵・由利麟太郎と、その助手役を務める新聞記者の三津木俊助である。
原さくら殺害のために凝らされた数々の偽装工作、密室状態、そして複雑に絡み合う人間関係。由利先生は、卓越した推理力でこれらの謎を鮮やかに解き明かしていく。
華麗なる舞台の裏の惨劇
どこまでも派手で、どこまでもクラシック。『蝶々殺人事件』には、そんな横溝正史の異才ぶりがぎゅっと詰まっている。
首を突っ込むのは、金田一じゃなくて由利麟太郎(ゆり りんたろう)。舞台は昭和モダンな歌劇団。そんでもって、死体が運び込まれたのは、まさかのコントラバスケース。どう考えてもロジカルじゃないのに、ちゃんと筋が通ってるあたりがにくい。
開幕から見せ場は満載だ。密室、偽装、暗号、影武者、死体運搬トリック。使える小道具は全部使いましたってくらい盛りだくさん。まるで黄金期ミステリのビュッフェだ。でも驚くのは、それが散らからずにきちんと一列に並んでるところだ。
事件はどこまでも複雑なのに、由利先生の推理が入ると、不思議とすっと飲み込める。知的で冷静でスマート。それでいて、助手の三津木とのかけ合いでは、ほんのり人間味も滲んでくる。
「クリスティ風であり、カー風であり、クロフツ風でもあり、クイーン風でもある」と評されるように、本作にはさまざまな本格ミステリーの美質が詰め込まれており、それでいて決して借り物ではなく、横溝正史ならではの土着性と物語力が見事に融合しているのだ。
正直、犯人の動機には感情移入しづらいかもしれない。でもそれすらも、まるごと舞台演出の一部なんじゃないかと思わせるほど、仕掛けの完成度が高い。
死体の運び方ひとつとっても、あんな手があったのかと唸らされるし、そこに至る伏線の張り方も完璧だ。このあたり、横溝の技巧派としての顔がしっかり出てる。
全体としては、まるでオペラのように華麗で、どこか哀しい物語。舞台の幕が下りたあとに残るのは、誰かの高笑いでも、どんでん返しの衝撃でもなく、人の哀しさと寂しさ、そしてそれを真正面から受け止める名探偵のまなざしだ。
横溝ファンにはもちろん、由利麟太郎入門編としてもおすすめしたい。ド派手な幕開けから始まる、上質なクラシカル演目だ。
39.すべてを読み終えてから始まる恋の話── 乾くるみ『イニシエーション・ラブ』
物語は1980年代後半の静岡と東京を舞台に、奥手な男子大学生・鈴木が合コンで歯科助手のマユと出会い、恋に落ちるところから始まる。
「Side-A」では、二人の甘酸っぱい恋愛模様が描かれる。鈴木はマユに夢中になり、彼女のために自分を変えようと努力する。やがて二人は親密な関係になるが、鈴木は就職を機に東京へ行くことになり、遠距離恋愛がスタートする。
「Side-B」では、遠距離恋愛の困難やすれ違い、そして鈴木の心変わりの様子が描かれ、二人の関係は次第に終わりへと向かっていく。
しかし、物語の最後には、読者のそれまでの認識を根底から覆す衝撃的な事実が隠されているのであった。
甘く切ない恋愛小説の皮を被った驚愕の罠
読みはじめた瞬間は、なんてことない80年代のラブストーリーに見える。
合コンで出会った鈴木とマユ。ぎこちない初デート、不器用なやりとり、手探りの距離感。どこか懐かしい空気が漂ってて、これはこれで良い感じの青春恋愛小説っぽい。
でも、そんな気配を残したまま物語は進んでいき、東京での遠距離恋愛が始まるあたりから、すこしずつ空気が変わってくる。彼の態度に揺らぎが生まれ、彼女の言動にも妙な引っかかりが出てくる。
で、最後のたった一文で、世界が音を立ててひっくり返るわけだ。
『イニシエーション・ラブ』は、完全に仕掛けありきの物語だ。けれどそれが成立するのは、前半がしっかり「甘酸っぱいラブストーリー」として成立してるからである。恋の始まりを丹念に描いておいてから、後半で恋の終わりと、その裏にあったもう一つの顔を丁寧に暴いてくる。
トリックの構造自体はシンプル。でもその仕掛けがばっちり効いてるのは、読んでる側の無意識の油断をうまく突いてくるからだ。地の文に細工はない。ただ、あることを隠してるだけ。それだけで、視点と意味ががらっと変わる。その潔さと巧みさに拍手を送りたい。
しかも背景に流れるのは、80年代特有の空気感だ。カセットテープ、留守電、国鉄、少しダサいファッション。この時代の匂いが、ちょうどいい感じに現実感をぼかしてくれる。懐かしさがミスディレクションの役割まで果たしているというわけだ。
ラストで明かされる真相は、ある意味で恋愛小説のど真ん中をえぐってくる。信じてたものが全部ズレてたと気づいた瞬間、甘さはすぐに苦みに変わるのだ。
でも、それすらも青春の味と言えるなら、この仕掛けはミステリ好きにとっての、見事な通過儀礼になっている。
これは、最初から最後まで、そして最後から最初まで楽しむタイプの一冊だ。
40.本当の彼女は、どっちだったのか── 乾くるみ『セカンド・ラブ』
主人公の西澤正明は、26歳にして初めて白石春香という美しい恋人を得た。
彼女との関係は順調に進展していくが、正明は春香と瓜二つの容姿を持つ謎めいた女性、美奈子の存在を知る。美奈子は春香とは対照的に大胆で妖艶な魅力を持ち、正明は次第に二人の女性の間で揺れ動くようになる。
春香と美奈子、二人の「そっくりさん」を巡る関係は複雑に絡み合い、やがて思いもよらない結末へと正明を導いていく。
物語の背後には、登場人物たちの過去や、隠された意図が巧妙に仕掛けられているのであった。
二人の「彼女」と揺れる心
恋って、相手のことを好きになるというより、「自分がどんなふうに好きでいたいか」を決める作業なんじゃないか。そんなことを思わされたのが、乾くるみの『セカンド・ラブ』だ。
主人公・西澤正明は、26歳にしてようやくできた恋人・春香に夢中になる。可愛くて、優しくて、自分を変えようと思わせてくれる存在だ。ところが、春香にそっくりな女・美奈子が現れたことで、物語の空気がにわかにきな臭くなっていく。
春香は清楚で慎ましく、美奈子は妖艶で大胆。似ているのに、まるで正反対。どちらも実在しているようで、どこか作り物のような不自然さがつきまとう。読んでいるうちに、「この世界のどこに嘘があるのか」探している自分に気づくはずだ。
乾くるみと言えば『イニシエーション・ラブ』が有名だが、本作も負けず劣らずの仕掛けが待っている。やりすぎじゃないかと思うくらいストレートな伏線と、あまりに自然な誘導。気づいたときにはもう遅い。まんまと踊らされている。
恋愛の熱は、一方が冷めた瞬間にすべてが嘘になる。その残酷さを、トリックという形で見せてくるあたり、やっぱり乾くるみは怖い作家だと思う。
正明が見ていた「春香」とは何だったのか。なぜ彼は美奈子に惹かれてしまったのか。そして、誰が誰をどうやって騙していたのか。
真相を知っても、すぐには納得できないかもしれない。けれど、それこそが恋という感情の正体なんじゃないかと思わされる。
この物語は、恋の甘さと怖さを、ほとんど無言のまま突きつけてくる。
見えていたはずのラブストーリーが、いつのまにかミステリに変わっていたような、あの背筋をなぞる違和感が心地よい。
41.祝福のドレスが告げるのは、永遠の別れか、それとも── 黒田研二『ウェディング・ドレス』
結婚式当日、花嫁・祥子が何者かに襲われ、婚約者のユウ君も事件に巻き込まれる。二人はそれぞれ異なる視点から、事件の真相に迫ろうとする。
鍵を握るのは、猟奇的殺人を記録した過去のビデオテープと、祥子の母が遺した一着のウェディングドレス。母の死に隠された秘密や、ドレスに託された想い、さらにユウ君の兄の謎の失踪も絡み、物語は迷宮のように展開していく。
二人の視点は時に食い違いながらも、やがて一つの真実へと収束していく。
交錯する視点、時を越える謎
タイトルを見て、甘い恋愛小説だと思ったら大間違い。黒田研二の『ウェディング・ドレス』は、愛と死と謎が入り乱れる、ずっと忘れられないタイプのミステリだ。
結婚式当日、花嫁の祥子が突然の襲撃に遭うところから物語は始まる。そこから先は、彼女と婚約者ユウの視点が交互に展開される構成なのだが、これがクセモノだ。
最初はふつうに読めるのに、途中から「あれ?」となる。何かがズレている? 視点が噛み合ってない? みたいな感じで、ページをめくる手がどんどん早くなっていく。
ユウの兄の謎の失踪。母が娘に遺した一着のウェディング・ドレス。そして、過去に記録されたある殺人映像。この三つの線が、ゆっくり、確実に一点へと収束していく構成は見事としか言いようがない。
なんてことない会話や仕草が、後になって意味を持ち始める瞬間の気持ちよさ。これがミステリの醍醐味だよな!と思わされる。
途中からはもう、ふたりの語りがすれ違うたびにヒリヒリしてくる。切ないというか、取り返しのつかない何かをずっと握りしめてる感じというか。誰が悪いわけでもないのに、どうしようもなく悲しい構図がそこにある。
でも、この物語はただ暗いだけじゃない。ラストで明かされる真相は、胸が締めつけられるような悲しさと同時に、不思議とやわらかい光みたいなものも残していく。
仕掛けは鮮やかだが、それ以上に大切なのは、誰かの想いをちゃんと受け取れるかどうか、という話なのだと思う。
あの白いドレスに込められたものが、ただの「結婚の記念」じゃないとわかったとき、本当の物語が始まる。
これは、ドレスを着る人の話であり、ドレスを贈る人の話でもある。
そして、もう一度会いたかった人の話だ。
42.鏡のような語りが割れるとき── 中町信『模倣の殺意』
ある日、将来を嘱望されていた新進作家が、自宅で服毒死を遂げる。
警察は早々に自殺として事件処理を進めるが、故人と親交のあった女性編集者は、その死の状況に拭いきれない不審を抱き、独自の調査を開始する決意を固める。
時を同じくして、一人の男性ルポライターもまた、別の情報源と取材ルートからこの作家の死の真相に迫ろうと動き出していた。
時代を超えた叙述の罠
ミステリというのは、嘘をどうやって本当に見せるかの勝負だと思うのだけど、中町信の『模倣の殺意』はその極北にあるような作品だ。
やってることはシンプルだけど、やられた感は相当深い。まあまあ古い本なのに、トリックの新しさとキレ味は今でも通用するどころか、むしろ今のミステリに足りないものを見せつけてくるのだ。
話は、新進作家の突然の服毒死から始まる。警察は早々に自殺と判断するが、編集者の女性が違和感を拭いきれず、独自に調査を始める。そしてもう一人、ルポライターの男もまた、別ルートから真相を追っていく。ふたりは直接交わることなく、別々の視点から事件に迫っていくという流れだ。
ここでポイントなのが、この〈二人の語り〉の使い方だ。普通、多視点構成というのは、情報の補完とか、真実への接近に使われる。でもこの作品では、視点が変わることでむしろ何かがうまく隠されていく。読んでる側は、ふたりの視点を往復してるうちに、いつの間にか作者の手のひらの上で転がされてるわけだ。
終盤、たったひとつの事実が明かされたとき、それまで読んできた物語が一気に意味を変える。上手い叙述トリックというのは、こういう視点そのものを罠にするものなんだと改めて感じた。
あと、全体を包む昭和の空気感もたまらない。新聞社、団地、喫茶店。今のミステリにはなかなか出せない現実の手触りがあって、それが逆にトリックの非現実感を際立たせてくる。演出じゃなく、日常そのものが舞台装置になってる感じだ。
『模倣の殺意』ってタイトルが示してるのは、もしかしたら事件の模倣よりも、「語りの模倣」なんじゃないかと思えてくる。語り手とは、信用できるようでいて、いちばん嘘をつく存在だ。だからこそ、最後に「そうだったのか!」と気づいたときの感覚が、これほど強く刺さる。
派手なギミックがあるわけじゃない。でも、気づいたときには完全にしてやられている。
この感覚は、ミステリを読み続ける人間にとっての、最高の快楽だ。
43.その思い込みが、すべてを狂わせた── 我孫子武丸『殺戮にいたる病』
東京の喧騒に包まれた繁華街で、人々の心を凍りつかせる猟奇的な連続殺人が発生する。
犯行を重ねるサイコ・キラーの名は、蒲生稔。彼は歪んだ「永遠の愛」を追い求め、ターゲットとした女性たちを凌辱し、惨殺するという凶行を繰り返すのであった。
物語は、この恐るべき殺人者である稔自身の視点、彼の凶行に息子が関わっているのではないかと苦悩する母・雅子の視点、そして稔によって親しい者を奪われた元刑事・樋口の視点という、三者の立場から多角的に描かれる。
脳髄を揺るがす叙述の迷宮
このタイトルを見た瞬間に、ただごとじゃないって気配はある。
『殺戮にいたる病』
もう名前からして不穏だし、実際読んでみても不穏どころの騒ぎじゃない。読み始めたが最後、戻れなくなる系のミステリだ。
話の軸にいるのは、連続殺人犯・蒲生稔。最初から犯人が誰かなんて、もうエピローグで明かされてる。稔は捕まってるし、母親も登場するし、かつての刑事も出てくる。
じゃあ、どこに謎があるのか? それがこの小説の最大のポイントで、「謎」は読者の目の中にある。
我孫子武丸が仕掛ける叙述の罠は、ほんとにえげつない。なにげない言い回し、視点のズレ、誰が何をどう語ってるか。そこに意識が向いてないと、気づかないまま物語が進んでいく。
そして終盤、たった一つの事実が明かされたとき、それまで積み上げてきた全体がガラガラ崩れ落ちるのだ。しかも、ちゃんとフェア。全部、最初からそこに書いてある。
猟奇的な殺人描写も強烈だけど、単なるホラーじゃない。そこには母と息子のねじれた愛情があり、犯人を「理解したい」と思ってしまう瞬間すらある。この感情のグラデーションがまた恐ろしくて、どこまでが自分の感情で、どこまでが作者に操られてるのか、わからなくなってくる。
でも一番こわいのは、そんな感覚に酔ってる自分自身かもしれない。なぜって、この本を読み終えたあとにもう一回読み返したくなる人は、大抵「やられた側」だからだ。
『殺戮にいたる病』は、犯人当てじゃない。真相当てだ。そして、読者自身の視点の狂いを突きつけてくる。
読んでいるうちに、誰かが殺される音よりも、自分の認識が壊れる音のほうがよく聞こえてくるようになってしまう。
そしてやっぱり、あの一文は、震える。
あれを読んだ瞬間に、「そういうことか!」となる人と、「……え?」と固まる人に分かれると思うが、どっちも地獄行きには変わりない。
何を信じ、何を疑うべきだったのか。
それがわかるのは、すべてが終わったあとだ。
44.映画の謎?それとも現実の罠?── 我孫子武丸『探偵映画』
ある映画の撮影が佳境に入ろうとする中、突如として監督が謎の失踪を遂げるという異常事態が発生した。残された映画スタッフとキャストたちは、作品の結末を知らされぬまま、手探り状態で映画を完成させようと苦心惨憺する。
物語は、彼らが製作している劇中映画「探偵映画」のストーリー展開と、その撮影現場という現実世界で起こる不可解な出来事や人間模様が、まるで合わせ鏡のように交錯しながら進行していく。
映画製作の舞台裏で繰り広げられるプロフェッショナルたちの葛藤や情熱、そしてそこに散りばめられたミステリーの要素が複雑に絡み合い、誰にも予測できない意外な結末へと物語を導いていく。
虚構と現実が交錯する撮影現場
映画の撮影現場には、なんだか魔法みたいなところがある。台本どおりに進むはずなのに、現場ではいつも予定外のことが起きる。
で、そんな予定外が極まったのが我孫子武丸の『探偵映画』だ。作中映画「探偵映画」の撮影中、肝心の監督が突然いなくなるという事件が起きる。
脚本は途中までしか完成してないし、撮影は進んでるし、現場はカオス。なのに、スタッフやキャストは「なんとか続けよう」と映画を作り続ける。もうこの時点でミステリ的な違和感がビンビン漂ってくる。
しかもこの物語、劇中映画の内容と撮影現場の現実がまるで鏡合わせのようにリンクしてくる。ある意味で、現実が虚構に追いついていくような不気味さがあるのだ。事件の謎を追ってるはずが、いつの間にか「探偵ごっこ」を演じてる感覚に陥ってしまう。そのうち、自分が見てるのは映画なのか現実なのか、よくわからなくなってくるのだ。
この二重構造が、本作のキモだ。劇中映画の「問題編」と現実の異変が交差するあたりから、謎解き好きのスイッチがガッチリ入る。しかも、誰が探偵で、誰が観客なのかさえぐらついてくる。言ってみれば、「探偵役すらキャスティングされたフィクションだったんじゃないか」みたいな疑念がよぎるのだ。
ただのトリッキーなメタ構造じゃなくて、ちゃんと映画への愛情が通ってるのもポイント高い。カメラの機材、照明スタッフのセリフ、監督と役者のぶつかり合い……創作の現場あるあるを知ってる人ならニヤッとできるシーンも多い。これは、映像制作に関わったことのある人なら絶対に刺さる。
しかも巻末には大林宣彦監督の解説付き。そりゃあ、フィクションとリアルを溶かすような物語は、映像の魔術師にも響くわけだ。
トリックそのものも見事だが、本作の真骨頂は「読者の視点ごとすり替える」仕掛けにある。
読後に「あれ? わたし、ちゃんと読んでたはずなのに……」と戸惑うあの感覚は、まさに我孫子作品の醍醐味だ。
『殺戮にいたる病』の後に読むと、その鮮やかな視点反転芸の幅広さにも感心するはず。
『探偵映画』
これはただのミステリじゃない。
現実を疑うためのフィクションだ。
45.声の主は誰だったのか?── 筒井康隆『ロートレック荘事件』
画家アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレックの名を冠した、郊外に佇む瀟洒な西洋館「ロートレック荘」。
この館を舞台に、美しい女性たちが次々と犠牲となる連続殺人事件が発生する。事件は複雑怪奇な様相を呈し、読者は物語の探偵役と共に、入り組んだ謎の解明に挑むことになる。
しかし、この物語の真髄は、巧妙に張り巡らされた叙述トリックにあり、読者が抱くであろうあらゆる先入観や思い込みを、根底から鮮やかに覆す仕掛けが施されている。
叙述の魔術、読者を翻弄する二重三重の罠
郊外の西洋館、連続殺人、探偵役らしき人物の登場。設定だけ見れば、いかにもクラシカルな舞台だ。
でも、数ページも読み進めれば、この小説が何かおかしいことにすぐ気づく。視点が揺れる。語りが捻じれる。足元がふわつく。
筒井康隆の『ロートレック荘事件』は、ミステリというよりも「語りそのものを使った罠」だ。
主人公は「おれ」と名乗る人物なのだけど、この“おれ”が誰なのか、本当にその視点で物語を見ていたのか、その輪郭が読み進めるごとに曖昧になっていく。語り手が信じられないのではない。語り手そのものが、最初からズレている感覚だ。
ミステリを読む時、人は無意識に何かを信じてる。語り手は正しい、構成は素直、トリックはフェア。でも、この作品はその信頼をまるっとひっくり返してくる。
途中で何度も確認したくなる。「ん?」「これってどういうことだ?」と。でもその違和感すら、全部計算のうち。そういう仕掛けだと気づいたときには、もう手遅れだ。
叙述トリック系の中でも、この作品のヤバさは群を抜いている。構造をいじってるだけじゃない。読み手の思考、先入観、物語を受け取る姿勢そのものを揺さぶってくる。これは、メタフィクションを通り越して、読書行為の構造分析になっているようなレベルだ。
で、何がすごいって、その構造の中に、人の感情がちゃんとあるところだ。悲しみも、やるせなさも、どうしようもない切なさも詰まっている。
だからこそ、最後の一撃が効く。ただのトリックじゃ終わらない。響くのだ。
『ロートレック荘事件』は、「こんなことしていいのか?」と思わされるほど、やりたい放題やってくる。でも、それがすごく美しい。
あの一文が、ずっと頭に残る。すべてを裏返しにしたあとの世界の冷たさが、なんとも言えない読後感を残す。
ミステリを読み慣れてる人ほど、うかつに手を出して痛い目を見るタイプのやつだ。
46.語りの罠と愛の反転── 小泉喜美子『弁護側の証人』
かつてミミイ・ローイの名でヌードダンサーとして喝采を浴びた漣子は、八島財閥の御曹司・杉彦と結婚し、上流階級の生活に身を置く。だがその日々は息苦しく、孤独なものだった。
そんな中、義父・八島龍之助が邸内で殺害され、夫・杉彦に嫌疑がかかる。漣子は夫を信じ、真相究明に動き出すが、物語は法廷を舞台に思わぬ方向へ。愛と憎しみが交錯する人間模様の中、巧妙に隠された驚愕の真実が浮かび上がっていく。
時の迷宮、反転する真実
結婚とは、人生最大のサクセスストーリーのひとつだ。下町のヌードダンサーから、一流財閥の御曹司との結婚。これ以上のシンデレラストーリーがあるだろうか?
小泉喜美子『弁護側の証人』の主人公・漣子は、まさにその夢を掴んだ女だ。かつて「ミミイ・ローイ」として踊っていた彼女は、華やかな世界から上流階級へと舞台を移し、今や八島財閥の若奥様。
だが、豪奢なドレスの下で、孤独と疎外感は確実に蓄積していく。そんなある日、義父が邸内で殺害され、容疑がかかったのは他でもない夫・杉彦だった。
ここからが本題だ。漣子は夫を信じている。彼を守るために法廷に立ち、証言台でその心情を語る。その姿は凛としていて、思わず胸が締めつけられる……が、どうにも腑に落ちない気配が少しずつ積もっていく。
この物語のすごさは、どこかで「何かおかしい」と思わせながら、それでも語り手を信じさせる構成力にある。事件の全貌よりも、語られた言葉の「順番」と「見せ方」が最大の武器だ。
情報は隠されていない。なのに、見えているはずの景色を、まるで別のものとして錯覚させる。たったひとつのカット、ひとつの編集で、物語の意味はあっさりひっくり返るのだ。
終盤で見えてくるのは、法廷劇という舞台を使って描かれた、女の執念と嘘と愛だ。そして、自分が今まで信じてきた視点が、いかに都合よく捉えられていたかに気づいたとき、唖然とするしかない。
この作品は、ミステリの名を借りた語りの実験でもある。情報の並べ方、登場人物の立たせ方、感情の引き出し方、すべてが緻密に計算されている。そして一気に読み終えたあと、最初の数行をもう一度見返したくなる構造がしっかり仕込まれているのだ。
昭和ミステリとあなどるなかれ。女の情念と構成の妙ががっつり噛み合った、一本芯の通った法廷ドラマだ。ラストに待ち構えているのは、爆発じゃない。もっと冷たい、でも確実に効いてくる一撃だ。
この小説は、視点の魔術であり、語りの技術の結晶である。
読み終えたあとで、つい最初に戻りたくなるのは、真相を確かめるためではない。
自分が何を信じていたのか、それを見つめ直したくなるからだ。
47.広辞苑を開いたとき、記憶は嘘をつく── 伊坂幸太郎『アヒルと鴨のコインロッカー』
大学進学を機に仙台へ引っ越してきた椎名は、風変わりな隣人・河崎と出会う。初対面で彼が持ちかけてきたのは、「広辞苑を盗むために本屋を襲う」という突拍子もない計画だった。
戸惑いながらも、河崎の強引さと謎めいた魅力に引き込まれていく椎名。しかしその奇行の裏には、河崎の過去の恋人・琴美、心優しい留学生ドルジ、美しいペットショップ店長・麗子らが関わる、ある哀しい出来事があった。
やがて現在と過去が交差し、すべての点が結びついたとき、椎名は切なさと驚きに満ちた真実にたどり着くのだった。
過去と現在が織りなす切ない嘘と真実
「一緒に本屋を襲わないか」
そんなセリフから始まる青春があっていいのだろうか。しかも、目的はたった一冊の広辞苑。意味がわからない。けれど、伊坂幸太郎『アヒルと鴨のコインロッカー』では、これがすべての入口になる。
舞台は仙台。大学進学で越してきた椎名が出会った隣人・河崎は、やけに饒舌で、妙に魅力的で、なにかがズレている。そんな男の強引なペースに巻き込まれた椎名は、本屋襲撃という不可解な事件に手を貸すことになる。
一方で描かれるのは、二年前の話。ドルジという心優しい留学生、ペットショップの店長・麗子、そして彼らの周囲で起こったある出来事。このふたつの時間軸が、交互に少しずつ絡み合い、やがてとんでもない一点へと収束していく。
この作品がずるいのは、序盤の軽妙さに読者の油断を誘っておいて、物語の真相に気づいたときには、もう感情が戻れなくなっているところだ。しかも、その真相は、目の前にずっとあったのに、気づけなかった。叙述ミステリとしても、かなりキレている。
そして最後にわかる。なぜ河崎が広辞苑を欲しがったのか。なぜ椎名に声をかけたのか。
その理由は、笑えて、切なくて、少しだけ苦い。
『アヒルと鴨のコインロッカー』は、誰かの記憶にすこしだけ触れてしまった人の話だ。
軽さと重さ、笑いと悲しみ、そのどちらもをそっと抱えて歩いていく。
優しい風に吹かれながら。

48.教室の太陽は、もうそこにはいない── 辻村深月『太陽の坐る場所』
高校卒業から十年、年に数回開かれるクラス会では、常に女優として成功した同級生キョウコの話題で持ちきりだった。誰もが憧れる存在である彼女は、なぜか一度もクラス会に姿を見せない。
それは高校時代に起きた「ある出来事」と関係しているのだろうか。幹事を中心に、同級生たちは彼女を会に招こうと動き出すが、次第に一人、また一人と連絡が取れなくなっていく。
過去と現在が交錯する中、それぞれの心に残された傷が明らかになっていく。繊細な心理描写が光る群像劇ミステリー。
過去と現在の交差点、スクールカーストの残影
高校時代のクラスというのは、妙にドラマがある。
誰が中心だったとか、誰が誰をハブっていたとか、今思えばどうでもいいようなことが、当時は人生のすべてみたいに感じられた。
辻村深月『太陽の坐る場所』は、そんなあの頃にきっちりケリをつけにいく物語だ。
卒業から十年。クラス会に現れないのは、今をときめく女優・キョウコ。彼女は当時、クラスの「太陽」だった。眩しすぎる存在で、誰もがその重力圏にいた。でも、その太陽が沈んでから、誰かの中で時間が止まったままだったのかもしれない。
この物語は、同窓会をきっかけに、数人の視点から過去と現在が交差していく。群像劇の形を取りつつ、それぞれの胸に残っていたのは、ちょっとしたすれ違いとか、言えなかった一言とか、見えない優劣の線だったりする。スクールカーストなんて言葉はなかったが、みんな何かしらの立ち位置を気にしていた。
そして何より、この作品の面白さは、「太陽がなぜいないのか」という点だ。いないことが謎であり、過去の傷を浮き彫りにする鏡でもある。
キャラの描き分けが巧みで、それぞれが持ってる感情の歪みや後悔がリアルに響く。誰が悪いわけでもないのに、確かにあの教室にはヒエラルキーがあった。
今さら蒸し返したくもないようなことが、でも確かに心の奥に残ってた。それを小説という舞台で、丁寧に掘り起こしていくのが本作だ。
最後にもう一度言いたい。
高校の教室には太陽があった。
でも、そのまぶしさに焼かれてしまった誰かが、いたのかもしれない。
49.嘘にすがってでも守りたい── 入間人間『嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん』
みーくんは自他共に認める嘘つきだ。彼は、過去の誘拐監禁事件で心を壊した少女“まーちゃん”=御園マユと共に暮らし、彼女の現実逃避を守るため、日常的に嘘を重ねている。
そんな名岐町では、小学生姉弟の失踪と、若い女性を狙う連続通り魔事件が立て続けに発生し、街に不穏な空気が漂っていた。
だが、まーちゃんの部屋には、失踪中だった姉弟の姿があった。
過去と現在、ふたつの事件が複雑に絡み合う中、みーくんとまーちゃんの歪んだ共依存関係が、紙一重の狂気と共に暴かれていく。
嘘と狂気が織りなす歪な愛の形
このタイトルを見て、ただの変わり者カップルの話だと思ったら、大間違いだ。
『嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん』は、サイコサスペンスの皮をかぶったラブストーリーであり、ラブストーリーの仮面をかぶった狂気の物語だ。とにかく、始まって数ページで「この2人、まともじゃない」と気づかされる。
語り手のみーくんは、自他ともに認める嘘つきだ。そして、その相手であるまーちゃんは、誘拐監禁事件の被害者であり、心を壊したまま時間を止めてしまった少女。みーくんはそんな彼女を守るために、嘘を積み重ねながら生きている。
その日常に、行方不明の小学生と連続通り魔事件という、あまりにも非日常な出来事が交差してくる。この状況で、ギリギリ人間らしく生きているのが彼らの強さであり、どうしようもない切なさだ。
会話は軽妙なのに、内容は重い。言葉選びはユーモラスなのに、行間に血が滲む。どこまでが冗談で、どこからが本音か、どこまでが妄想で、どこからが真実か──とにかくすべてが信用できないのに、最後まで目が離せない。
ラブストーリーとして読むと歪んでいて、サスペンスとして読むと狂っていて、青春小説として読むと哀しすぎる。しかし全部が本気だ。まーちゃんの言動はぶっ飛んでるし、みーくんの語りは不安定極まりない。それでも、彼らの関係性だけは確かに“ある”。
ふたりの過去が、現在の事件とどう絡むのか。なぜ小学生がそこにいるのか。そもそも、みーくんは誰で、どこまで正気なのか。……そんなの、読んでるこっちもわからなくなってくる。
でもきっと、この物語の嘘は、誰かを守るためのものだ。
正しさじゃなく、優しさのために紡がれた嘘。その在り方が、どうしようもなく胸に残る。
読後、うっすらと感じる「これはもしかして、めちゃくちゃ純愛なのでは」という感覚が、いちばん怖くて、いちばん尊い。
50.真夏の舞台で、嘘と不安が踊り出す── 静月遠火『真夏の日の夢』
大学の演劇サークルに所属する個性豊かな若者たちは、高額報酬に惹かれ、外部と隔絶されたアパートでの一ヶ月間の心理実験に参加する。
実験生活は穏やかに始まったが、六日目にメンバーの一人が突如として失踪。残された者たちは、不安と疑念に苛まれながら、仲間の行方と実験の真の目的を探り始める。
シェイクスピア『夏の夜の夢』の要素が物語に幻想的な彩りを添え、若者たちの青春群像劇と本格的なミステリーが融合した、予測不能な物語が展開していくのであった。
閉鎖空間の群像劇と二段構えの謎
「外に出られない夏なんて、演劇じゃなきゃ成立しないよな」
大学の演劇サークルに所属する男女が、ひと夏の〈実験〉に身を投じる。それは、外部と完全に遮断されたアパートでの一ヶ月間の共同生活。報酬は高額。
シェイクスピアを引用しても誰も突っ込まないくらい、みんな舞台好きで、それなりにクセが強い。
最初は、わりと楽しかった。だが六日目、ひとりが消えた。
それだけで、空気は一変する。誰もが「まさか」と思いながら、誰かを疑いはじめる。心の中に、ひっそりと別の演目が立ち上がる。それは、疑心と演技と、少しの見栄が混ざった、不協和音だらけの脚本だ。
『真夏の日の夢』は、そんな閉鎖空間で起きる事件を描いた群像ミステリだ。演劇サークルらしいノリとテンションの軽さは、読み進めるうちに鈍い影に変わっていく。
仕掛けられたトリックはシンプルだけど、気づいた瞬間に、何を信じて読んでいたのかがわからなくなる。あれだけ笑っていた会話が、いつのまにか不安の裏返しだったことに気づくのだ。
名前のつけ方やセリフの反復にもきちんと意味があって、ただ奇をてらっただけの作品じゃない。むしろ、ちゃんと青春の匂いと誰かの喪失が残る物語になっている。
最後まで読んだとき、拍手を送りたくなるかどうかは、読んだ人次第。
しかし、あの夏の舞台は、確かにそこにあった。
おわりに
叙述トリックは、ミステリーというジャンルが持つ「読者との駆け引き」を極限まで高めた技法だ。
どれほど注意深く読んでいたつもりでも、最後の一文で思考をひっくり返される。そんな快感と衝撃が、ここに紹介した作品には詰まっている。
まだ読んだことのない一冊があれば、ぜひ手に取ってみてほしい。
巧妙に仕組まれた罠が、あなたを待っている。