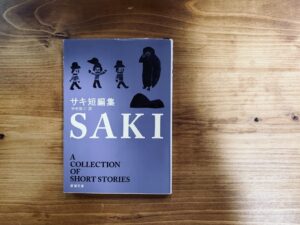スティーヴン・キングが50周年の節目に書いたのが、『フェアリー・テイル』だという事実を、まずどう受け止めればいいのか。
ずっとキングのホラーを読んできた身としては、タイトルからして信じられない。
フェアリー・テイル? おとぎ話? あの『ペット・セメタリー』や『ミザリー』のキングが、そんな牧歌的な響きの物語を書く? 正直、最初は警戒心すらあった。
けれど読み進めていくうちに、そのタイトルが持つ意味がゆっくりと染みこんでくる。これはたしかに「おとぎ話」だ。でも、ディズニー的なファンシーではない。
むしろ、グリム童話の原典のような、死や暴力や人間の業が濃厚に滲む、古くて残酷で、それでも希望の灯を手放さない物語。『フェアリー・テイル』はそういう作品である。
キングのライフワークのひとつ『ダーク・タワー』に並ぶような、いや、それ以上に「今」の彼が描けるすべてを注ぎ込んだような本作は、ホラーからファンタジーへ、現実から異世界へ、痛みから癒しへと連れていく。
その語り口は、かつての『スタンド・バイ・ミー』や『グリーン・マイル』に通じる誠実さと温かさに満ちていて、それでいてやっぱり、キングらしい不穏さと毒も忘れていない。このバランスがたまらないのだ。
17歳の少年と、老人と、犬と、もうひとつの世界

物語の主人公は、17歳のチャーリー。
ある日、近所の〈サイコハウス〉と呼ばれる屋敷で飼われている老犬の鳴き声がしたので近づいてみると、飼い主である老人ボウディッチが怪我をして倒れていた。彼を助けたことがきっかけとなり、交友が始まる。
最初はただのご近所付き合いのようでいて、ボウディッチとその愛犬レイダー、そしてチャーリーの関係は、少しずつかけがえのないものへと変わっていく。
老人の介護を通じてチャーリーが背負うことになる責任と、そこからにじみ出す優しさ。老いていく犬と、それを見守る少年。読んでいて何度も目頭が熱くなるようなやり取りがある。
だが物語はそこで終わらない。ボウディッチは、何かを隠していた。自宅裏の納屋に響く謎の異音。異常な量の金貨。そして、彼の死後に明かされる、とある秘密。
その納屋の扉の先にあるのは、もうひとつの世界──「エンピス」と呼ばれる、呪われた異世界である。
チャーリーは、老犬レイダーを救うために、ひとり納屋の扉をくぐる。異形の怪物が跋扈し、疫病が蔓延し、恐怖によって支配されたその地で、少年は知恵を武器に旅を始める。
物語は、愛する者のために踏み出した一歩が、やがて世界の運命さえも左右する冒険へとつながっていく様を描いていく。
でもその中心にあるのはいつだって、「誰かのために自分を差し出す」という、物語の原初から変わらない倫理である。
暗闇と光のせめぎあい
『フェアリー・テイル』の面白さは、チャーリーが異世界に降り立ってから、さらに加速する。
この「エンピス」と呼ばれる世界の構築が、たまらなく魅力的だ。二つの月が夜空を照らし、灰色の病に侵された住人たちが沈黙の中で生きている。王宮は廃墟と化し、〈飛翔殺手〉なる者に簒奪され、王族は呪いをかけられて宮殿から追放されていた。王都の迷宮では、〈夜影兵〉が警護し、北方の巨人が徘徊していて……。
まるでクトゥルフ神話のような不定形の恐怖と、バローズやブラッドベリに通じる少年冒険譚の高揚が、見事に同居している。
ただし、ここで大事なのは、「少年が世界を救う」という英雄神話にキングがまっすぐ乗っていない点だ。チャーリーは、最強の剣士ではない。天命を背負った勇者でもない。ただ、助けたい存在のために踏み出しただけの、どこにでもいる少年だ。
だからこそ、彼の選択や葛藤に、強いリアリティが宿る。戦う動機も、賢さも、弱さも、すべてが地に足についている。そこにこそ、現代ファンタジーの理想がある。
スティーヴン・キングの現在地と、語り部の覚悟
本作は、キングの作家生活50周年記念作品として書かれた。つまり、若いチャレンジではなく、老境の作家が「何をいま語るべきか」と考え抜いた末の物語である。
かつて『ペット・セマタリー』や『ミスト』で読者の心を容赦なくへし折ってきたキングが、今作で描くのは「それでも世界は信じるに値する」という確信だ。悲劇的な展開はあっても、読後に残るのは深い安心感と、あたたかさ。
愛犬を守りたいと願った少年が、結果として世界を変える。その構図はまるで寓話のようで、今のキングだからこそ描けた優しさに満ちている。
そしてこのおとぎ話には、「語り手」としての覚悟が詰まっている。語り部とは何か。
物語とは何か。誰かを救うために、言葉を紡ぐこと。
それがキングにとっての魔法なのだろう。
これは「物語の力」についての物語だ
この作品を読んで感じるのは、「語ること」そのものへの深い信頼である。
チャーリーは、自らの過去と向き合いながら、異世界で出会う人々の物語を聞き、語り、そして紡いでいく。彼の旅路は、壮大な救済の物語であると同時に、「誰かの声を聞くこと」「誰かのために語ること」の連なりでもある。
その意味で、本作はただのファンタジー小説ではない。これは、語り継がれることで生き延びる「物語の力」そのものに関するメタファーなのだ。
「物語は人を救えるか?」──その疑問に、キングはまっすぐに「Yes」と答えてみせる。
パンデミック下で執筆されたという背景も含めて、本作が「閉塞した現実からの脱出」ではなく、「そこに踏みとどまった上での再生」を描いている点が、とても現代的で誠実であると感じた。
扉はまだ、そこにある

『フェアリー・テイル』は、たしかに異世界冒険ファンタジーであり、ダークなホラーの要素もある。けれど、それ以上に「人生の話」であり、「語りの話」であり、そして「光の話」だった。
スティーヴン・キングが、50年の作家生活の集大成として書いたこの物語は、決して奇をてらったものではない。むしろ、あまりにもまっすぐで、あまりにも普遍的で、だからこそ心に刺さる。
読み終えたあと、自分の中に何かが戻ってきた気がした。
信じること、語ること、守ること。
それは、たとえどんなに暗い世界であっても、希望の灯を絶やさない方法だということを。
もし今、あの裏庭の納屋が目の前にあったら──私は迷わずその扉を開けるだろう。
そしてその先に、レイダーとチャーリーがいてくれたら、きっとこう言うはずだ。
「続きを聞かせてくれ」と。