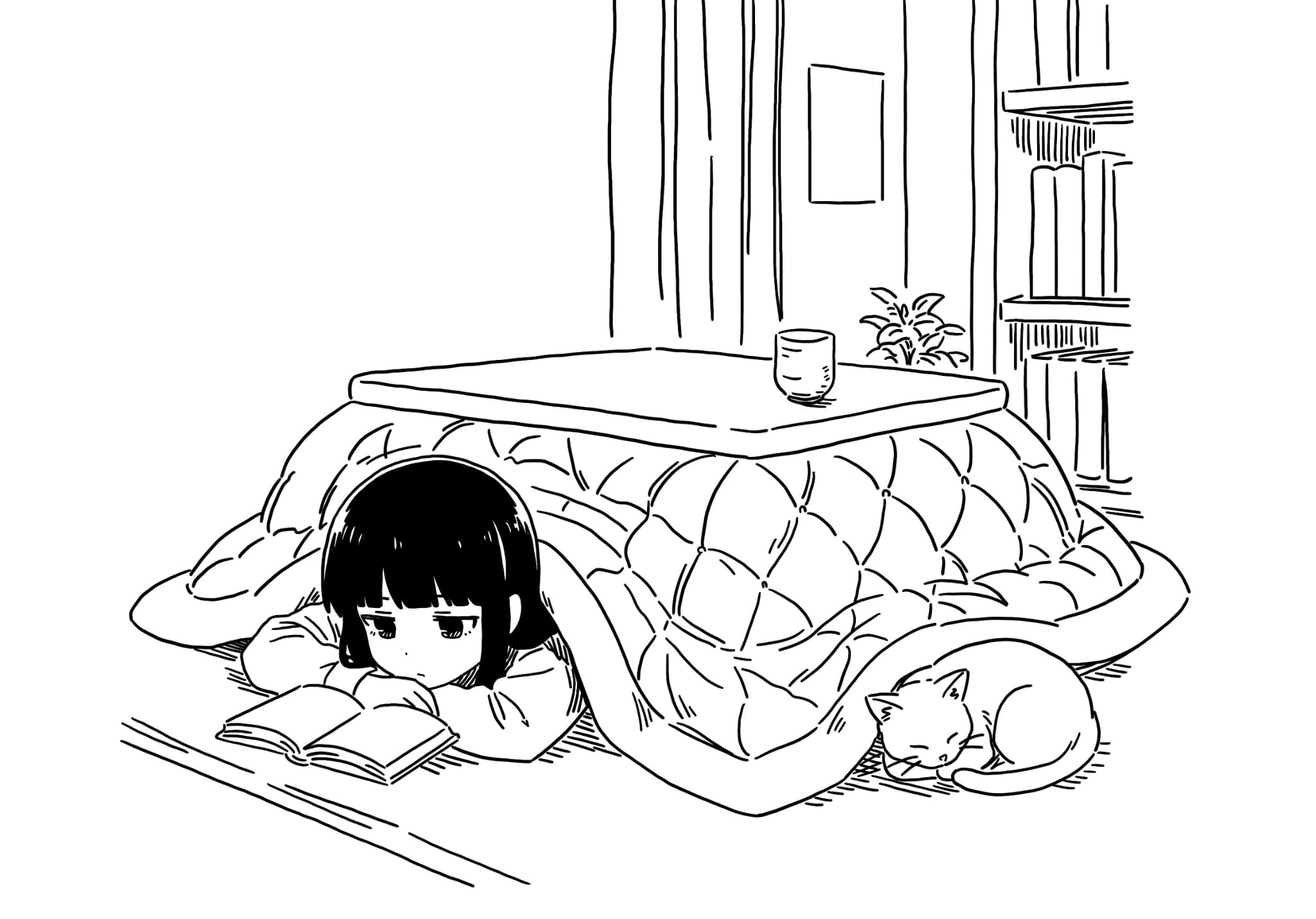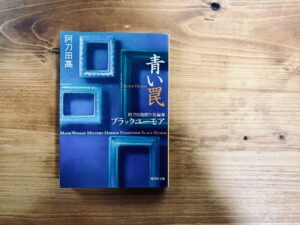「これでもか」と言わんばかりに詰め込まれた不可能犯罪。
山奥の村、古城、病院、雪に閉ざされた孤島……そんなクラシックな舞台で連発される、殺人、連続殺人、そして時にはそれっぽくないものまで殺される。
そう、それが二階堂黎人(にかいどう れいと)の『二階堂蘭子(にかいどう らんこ)シリーズ』である。
このシリーズ、とにかく徹底して本格を突き詰めてくる。舞台は昭和40年代、舞い散る雪、旧家の呪い、消えた足跡、奇妙な遺言、そして無数の死体。まるで横溝×クイーン×ヴァン・ダインを濃縮したような、本格ミステリの博覧会みたいな世界観だ。
そしてその中心に立つのが、傲岸不遜で天才肌、でもなんかカッコいい名探偵・二階堂蘭子。とにかく一度読めば「なんだこの人は……」と唖然としてしまう。
作者の二階堂黎人は「ミステリ原理主義者」なんて呼ばれることもあるが、それも納得。論理、構造、舞台、死に方、探偵の立ち位置まで全部ガチガチに組んでくる。
しかし、それが気持ちいい。「フェアプレイの美しさと、ミステリってこうでしょ?」という全肯定感。私はそこに痺れてしまった。
この記事では、そんな蘭子シリーズをご紹介していきたい。
本格ガチ勢にも、新本格デビュー組にもおすすめできる、蘭子入門の地図として使っていただければ嬉しい。
1.包帯男の狂騒と蘭子のデビュー戦── 『地獄の奇術師』
昭和42年、東京・国立。「十字架屋敷」に現れたのは、包帯ぐるぐる巻きの不審者。その名も「地獄の奇術師」。
見た目もインパクト満点だが、やることもとことん異常。自分を地獄からの使者と名乗り、一族に復讐してやると宣言。以後、屋敷では奇怪な殺人が連続して発生。しかも一つ一つが、旧時代の本格ミステリに出てきそうなゴシック感満載の状況。
警察が右往左往するなか、登場するのが二階堂蘭子。女子高生にして名探偵。ここから、地獄のような謎と推理の応酬が始まる。
圧の強い探偵と、湿度高めの屋敷ミステリ
まずこの作品、とにかく雰囲気の勝利だ。戦後まもない昭和の空気、忌まわしい過去を抱える名家、宗教がらみの秘密、戦争の影、そして包帯に覆われた殺人鬼。
横溝正史にオマージュを捧げすぎて逆に清々しいレベルの世界観が広がる。登場人物もどこかで見たような濃い面々ばかりで、全員が怪しくて信用できない。だが、それがいい。
探偵役の蘭子は、出てきた瞬間から完成された名探偵キャラだ。イキってるとかじゃなく、もう最初から仕上がっている。その傲慢な態度や論理至上主義な姿勢は、好みが分かれるかもしれないが、これがハマると抜け出せない。
ワトソン役を務めるのは、兄の二階堂黎人(作者と同姓同名)。この兄妹のコンビが、後に続くシリーズの基礎になる。
事件の真相にたどり着いたとき、二度驚く。ひとつは、「そこまでやるか」という奇抜なトリックの大胆さ。そしてもうひとつは、蘭子がただの論理マシーンじゃないということだ。
結末は、論理で犯人を倒しておしまい、なんて甘いものではなく、蘭子と黎人の心に確かな傷を残していく。この「傷」が、のちのシリーズ全体に影を落とすことになる。
『地獄の奇術師』は、昭和ゴシックと新本格が全力でぶつかり合ったような、狂騒と情念の幕開けだ。トリックや構成ももちろん楽しいが、それ以上に「雰囲気」と「探偵像の強度」で圧倒してくる。
一発目からフルスロットルで飛ばしてくるこのシリーズ、二階堂蘭子という名探偵の誕生を祝うには、これ以上ない幕開けだと思う。
まずはこの一冊から、その狂騒の旅に出発しよう。
2.血と雪と密室と── 『吸血の家』
「雪の上に残された足跡」と「密室殺人」。このふたつを聞いて、心が躍らないミステリ好きはいないだろう。
そこに「怨霊」「呪い」「遊女の伝説」が加わったらどうなるか?
答えは『吸血の家』に詰まっている。
昭和レトロと和風ゴシックの香りがぷんぷん漂うこの一作は、ミステリの伝統と怪談の恐怖を絶妙にブレンドした、シリーズ屈指の雰囲気勝負作品だ。
パズルと呪術の贅沢セット
舞台は、かつて遊郭を営んでいた名家・雅宮家。24年前に起きた雪中殺人の記憶をなぞるように、再び一家に殺害予告が届く。儀式の夜、起こるのは案の定の殺人劇。密室から発見される第一の死体、そして雪のテニスコートで見つかる、
足跡一つ残さない第二の死体──という、完全に「待ってました」な展開である。
この足跡なき殺人のトリックがとにかく秀逸だ。ギミックの仕掛け方はシンプルだが、発想が冴え渡っている。トリックの一部は、ミステリ好きの間で「忘れたくても忘れられない」と語り草になるほどインパクト大。これをメインに据えつつ、現代編の密室もきちんと用意されているという二段構えで、不可能犯罪好きとしては笑みが止まらない。
そして、事件に挑む名探偵・二階堂蘭子。怨霊だの呪術だのが跋扈する中でも、迷信に惑わされることなく、ひたすらロジックで真相に迫っていくその姿勢がかっこいい。彼女の推理は、ゴシックホラーを理詰めで解体していく快感がある。
また、この作品から本格的に始まる注釈芸も、忘れてはならないポイントだ。ミステリ論、文化小ネタ、ちょっとした毒。とにかく文字通り余白にまで情報が詰まっていて、まるで解説付きの美術展を見ている気分になる。これもまた、二階堂黎人という作家のひとつの「様式美」なのだ。
『吸血の家』は、血の呪いと雪の密室が交差する、極上の館ミステリだ。トリックよし、雰囲気よし、キャラよしの三拍子が揃っていて、シリーズ初期の名作として今なお高く評価されている。
新本格というより、「新怪談本格」とでも呼びたくなるような、ジャンルの境界線ギリギリを攻めた一冊だ。ゴシックなミステリが好きな人には、間違いなく刺さる。
3.黙示録、密室、そして地下迷宮── 『聖アウスラ修道院の惨劇』
霧に包まれた野尻湖のほとり。人里から隔絶された女子修道院で、一人の生徒が塔から転落死し、不可解な暗号文を残す。そしてすぐに、近くの森で神父が全裸・逆さ吊りという衝撃的な姿で発見される。
しかも、桜の木の下で首を切られた状態だ。明らかに異常なこの連続事件が、ヨハネの黙示録をなぞる「見立て殺人」だと判明する頃には、舞台はすでに地獄絵図と化している。
この神聖にして不穏な修道院に足を踏み入れるのが、名探偵・二階堂蘭子と、その兄・黎人のコンビだ。彼らは元同級生からの依頼を受けて事件に挑むが、調査の過程で明らかになるのは、地下に隠された迷宮と、修道院の歴史に潜むある神話的な真実だった。
異教的ともいえる猟奇殺人と、敬虔なキリスト教世界の緊張感。物語のどこを切っても、毒と知識が滲み出てくるような、凄まじいミステリ空間が展開される。
ミステリ好きのための、濃すぎる詰め合わせ
本作の魅力は、とにかく詰め込み具合が異常なところだ。見立て殺人あり、暗号あり、密室あり、地下迷宮あり。極めつけは「髑髏の洞窟」での大探検だ。
昭和40年代という時代設定にもかかわらず、舞台が修道院なので古臭さは皆無。むしろカトリック的な象徴性と、日本的なホラー演出が融合した独特の空気感が味わえる。
事件の構造もかなり豪勢で、ただの殺人事件にとどまらず、聖書の「ヨハネの黙示録」モチーフや、キリスト教的な見立て、象徴、予言が絶妙に絡み合ってくる。読み進めるうちに、「もしかしてこれは、宗教ミステリなのか?」という錯覚すら覚えるが、そこを容赦なく蘭子がロジックでぶった斬ってくれるのがまた気持ちいい。
さらに注目したいのは、蘭子というキャラの「探偵像」の厚みが一気に増している点だ。持ち前の論理力に加えて、神学や修道院史への知識が炸裂し、まさに〈百科事典系探偵〉と化している。その一方で、髪を染めた外見や、ちょっとした毒舌も披露されていて、型にハマらない探偵像として魅力が一段と増しているのもポイントだ。
『聖アウスラ修道院の惨劇』は、クラシカルな本格ミステリの手触りと、宗教サスペンス的なモチーフがガッチリ噛み合った異色の傑作だ。理屈と神秘がせめぎ合い、血と知識がぶつかる修道院ミステリ。
正直、胃もたれするほど濃厚だが、その分、満腹感は保証する。
4.地獄の遺産相続ミステリ── 『悪霊の館』
遺産相続と殺人。これほど相性のいい組み合わせがあるだろうか。西洋館、莫大な遺産、そして複雑な親族関係。そんな古典のフレームに、グロテスクとロジックをこれでもかと詰め込んだのが本作『悪霊の館』である。
舞台は、過去の因縁と悪意が澱のように沈殿した志摩沼家の屋敷。そこに渦巻くのは、家系図をなぞるだけで気が遠くなるような嫉妬と欲望だ。発端は一見ありがちな「特定の婚姻によって遺産が得られる」という遺言。だが当然ながら、そんな条件で誰も幸せにはならない。
やがて起きるのは、密室の中で甲冑に守られた状態で発見された、全裸・首なしという強烈な死体。これでもかという異様さで、序盤から完全に読者の想像力を上回ってくる。
濃厚すぎる王道、そして蘭子への刃
広大な館を舞台に繰り広げられる事件は、次第に「おどろおどろしい雰囲気ミステリ」の極致へと突き進む。密室、時計塔からの転落、毒殺、隠された財宝……ミステリのガジェットがこれでもかと投入され、しかもすべてが意味を持っている。怪奇趣味と論理性、その両立がここまで強引に成功している数少ない作品の一つだ。
そして見逃せないのが、名探偵・二階堂蘭子に訪れる個人的な危機だ。これまでの事件では観察者としての立場を貫いてきた彼女が、今回は犯人の標的になる。つまり、推理の途中で命を狙われる。
この展開によって、物語は一気にスリラーの領域へと踏み込む。シリーズの中でも、この作品以降、蘭子の探偵としての無敵感に陰りが生じ始めるのが興味深い。
『悪霊の館』は、古典本格ミステリへの愛に満ちつつも、その枠組みを過剰な密度と演出で突き破ろうとする暴走列車のような一作だ。館ものが好きなら読まない理由はないし、二階堂作品の中でも蘭子の存在感が際立つ転機となる。
ホラーとミステリの境界線で、首のない死体がこちらを見つめている。
そんな幻覚に襲われながら読むのが正しい姿勢だ。
5.不可能犯罪×ホラー×新本格の極北── 『人狼城の恐怖』
これはもはや「読む」というより、挑む作品である。
二階堂黎人の代表作『人狼城の恐怖』は、文庫本4冊、計3000ページ超。登場人物の多さも異常だし、舞台は双子の巨大な城。密室、見立て、連続殺人、不可能状況……それが次々に雪崩のように襲いかかってくる。
「事件を解く」どころか、「生き残る」ことすら難しい。読者もまた登場人物と同じく、逃げ場のない迷宮に閉じ込められる。
物語の発端は、ドイツとフランスの国境に存在する、二つの巨大な城への招待だ。だがその歓迎は罠だった。一方の城では、首のない死体やバラバラ死体といった凄惨な殺人が続発し、外部との連絡は遮断される。全員が疑い合い、誰が犯人か、誰が人狼か、自分の名前すら信じられなくなる。
体感するパズル地獄
極限の心理戦と、推理すら意味を失いそうな暴力の連続。この作品は、ただの館ものではない。地獄のような孤立空間で行われる知と暴のサバイバルなのだ。
本作最大の特徴は、殺人の「量」である。通常のミステリなら、数件の事件を扱うだけで十分濃厚なのに、『人狼城の恐怖』では、一冊で十数件の事件が次々と起こる。しかもそのすべてが、密室や消失といった不可能犯罪として描かれているから凄まじい。
トリック解明どころか、状況の整理すら間に合わないまま、次の死体が登場する。この「解決の猶予を与えない構成」が本作の真骨頂であり、私たちの頭脳を一撃で叩き潰してくるのだ。
しかも、単なる量の暴力に終わらない。それぞれの事件が丁寧に構成されており、細部まで論理で裏打ちされている。これを成り立たせる作者の頭脳と情熱には、もはや敬意しかない。作者自身が読者に「全部覚悟してから読め」と言っているような、異様なまでの誠意と挑戦状のかたまりだ。
『人狼城の恐怖』は、ミステリが好きなら一度は挑まなければならない作品だと思っている。ミステリというジャンルの限界を押し広げるような、壮絶なまでの実験作を読みたい人には、これ以上ない体験になるはずだ。
読み終えたとき、事件がどう解決したかよりも、あの地獄のような城で自分が何を見て、どこまで耐えたのか。そんな読後感が残る。
そう、本作の真の主人公は、最後まで読破したあなた自身なのだ。
6.名探偵にして宿敵あり── 『悪魔のラビリンス』
名探偵には、倒すべき悪が必要だ。そんな当たり前の事実を、改めて突きつけてくるのがこの『悪魔のラビリンス』。二階堂黎人の蘭子シリーズにおいて大きな転換点を刻んだ作品だ。
なにしろ、ついに出てくるのである。名探偵の宿敵が。その名も「魔王ラビリンス」。ただの怪しいハンドルネームじゃない。本気で探偵と対峙するために生まれた、知能犯の申し子だ。
登場早々、彼は蘭子に挑戦状を叩きつける。推理の力を試すためだけに、列車で殺人を演出し、ガラスの館に密室をこしらえる。自ら手を汚すことなく、舞台装置を整える黒幕タイプ。こいつは間違いなく、本気で名探偵をからかいにきている。
「トリックvs思想」の対決構図
本作は、二編構成になっている。前半「寝台特急〈あさかぜ〉の神秘」では、走行中の列車内で人が消えるという定番中の定番を、図解つきでじっくり料理してくれる。こういう、技術で勝負する列車ミステリを今の時代にやれる作家は、もう本当に限られていると思う。
後半の「ガラスの家の秘密」は、舞台設定も仕掛けも完全に蘭子を挑発するためだけに組み上げられていて、事件の全体像が明らかになるにつれて、ラビリンスという男の変態的なこだわりが浮き彫りになっていく。
ラビリンスは、ただの犯人ではない。殺人を「芸術」と称し、名探偵と「会話」するために犯罪を起こす。これはもう、現実の倫理観からは完全に外れている。しかし、それゆえに、名探偵との間に成立するのは「正義vs悪」ではなく、「論理vs論理」あるいは「トリックvs思想」という次元の勝負になるのだ。
二階堂蘭子というキャラクターも、ここで一気に色づいてくる。知性と傲慢が混ざり合ったその言動は、挑発してくる相手がいることで、より鋭く、より人間的な深みを帯び始める。
この一冊を境に、蘭子シリーズは単発の事件解決型から、宿敵との長期戦へと物語の軸をシフトさせていく。事件そのもののクオリティも高いが、それ以上にラビリンスという存在が、シリーズ全体に火をつけた感がある。
名探偵には謎が必要で、謎には仕掛け人がいる。その当たり前を、濃密に、そして楽しく再確認できる一冊だ。
シリーズの後半戦へ向けた、最初の号砲として最適な導入作である。
7.伝説の宝を賭けた知と狂気の冒険劇── 『魔術王事件』
ミステリの女王と、犯罪界の魔王。その対決が、ついに「宝探し」という舞台に突入したのが『魔術王事件』だ。前作『悪魔のラビリンス』で登場した宿敵・ラビリンスは、今回さらにスケールアップして帰ってきた。
今度の舞台は、由緒正しいが呪われた一族・宝生家。そして、伝説の埋蔵金。まるで横溝正史とルパンとインディ・ジョーンズをごちゃ混ぜにして、不純物として論理をぶち込んだような濃度である。
物語の冒頭から、蘭子はラビリンスの仕掛けた「遊戯」の渦中に巻き込まれる。しかも今回は、単なる密室殺人や消失トリックでは終わらない。呪い、埋蔵金、封印、地中迷宮、そして死体。殺人と宝探しが、等価の重みで語られる展開は、シリーズの中でも異色中の異色だ。
宝、生死、そして神話。すべてがラビリンスの掌の上
ラビリンスの真骨頂は、ただ人を殺すだけで満足しないところにある。彼は、探偵を追い詰め、挑発し、論理のゲームの枠そのものを破壊しようとする。今回の仕掛けも、「知恵の試練」などと名づけられた一連のギミックやトラップが連続し、蘭子たちは殺人現場の分析だけでなく、物理的な罠と暗号、そして家系の怨念にまで付き合わされる羽目になる。
そのうえで、核心に鎮座するのが「魔術王ラビリンス」という称号である。これは単なる厨二ネーミングではない。ラビリンス自身が神格化を意図し、蘭子との勝負を神話の領域に引き上げようとしているのだ。自分を不死身のメフィストフェレスになぞらえ、理性と偶像崇拝の境界線を揺さぶる様は、もはや探偵と犯人のゲームという次元を超えている。
対する蘭子も、もちろん一筋縄ではいかない。どんなにバカバカしく見える罠にも真顔で向き合い、冷静にロジックを組み上げていく姿は、まさに二階堂蘭子の真骨頂。序盤から後半にかけて、理屈のナイフ一本で迷宮を切り開いていくその姿は、論理の勇者とでも呼びたくなる。
『魔術王事件』は、ミステリの骨格を持ちつつ、そこに「宝探し」と「因縁の対決」という少年漫画的スパイスを盛大にぶち込んだ、知と情熱の大冒険譚だ。クローズド・サークルの密室論理に閉じこもっていた蘭子シリーズが、一気に解き放たれるような開放感がある。
そしてその背後には、ラビリンスという怪物がにやりと笑っている。
シリーズの地平を押し広げたこの一作は、いろんな意味で事件であった。
8.双面の怪物か、二重の虚構か?── 『双面獣事件』
「とんでもない方向へ転がり出したな!」
初めて読んだとき、そう思った。
蘭子 vs 魔王ラビリンスという探偵劇にSF・ホラーのスパイスを加えてきた『悪魔のラビリンス』『魔術王事件』に続き、いよいよ「人間の犯罪」の枠すら突破してしまったのがこの『双面獣事件』である。
舞台は南の島々。奄美大島では医療施設が壊滅、隣の島では、四本腕に二つの顔を持つという「双面獣」による大虐殺が報告される。最初から最後までトンデモ展開のオンパレードなのだが、それでも我らが蘭子はブレずに論理の剣を構える。
はたして、これはラビリンスの仕業なのか、それとも戦中に行われた「禁断の軍事実験」の残滓なのか。答えは、最後の最後まで霧の中だ。
ラビリンス編、まさかのモンスターパニック化
まず声を大にして言いたいのは、「これは本当に蘭子シリーズなのか?」という戸惑いが、最初の数十ページで確実に襲ってくるということだ。
密室もアリバイも見立てもどこかへ吹き飛び、出てくるのは「四肢が異常に発達した怪物」と「旧日本軍の極秘兵器計画」。まるでクトゥルー神話と戦争スリラーが混ざったような、ジャンル混濁のカオスが展開されていく。
しかしながら、ここでシリーズの芯が崩壊しているかといえば、そうではない。蘭子はあくまで、論理と観察によって現象に切り込み、「ありえなさ」を「あるかもしれない」に落とし込もうとする。双面獣の存在を信じるでも否定するでもなく、物語はずっと、信仰と知性、神話と現実のせめぎ合いの上に成り立っている。
そこへ、ラビリンスという存在が介在することで、陰謀のスケールが国家レベルへと拡大する。彼の悪意はもはや個人ではなく、歴史や集団心理といった、より深い闇を背後に抱えていることが示唆されるのだ。
『双面獣事件』は、もはや従来のミステリというジャンルで語ることすら無意味かもしれない。でも、だからこそ本作は面白い。理性と妄執、探偵と怪物、虚構と歴史。これらすべてが複雑に絡み合い、奇妙な重力を帯びて読み手を引きずり込む。
ある意味では、蘭子シリーズの中でもっとも「読む体力」が求められる作品だ。が、ハマれば抜け出せない異様な魅力もそこにはある。
探偵と怪物が同じテーブルで論理を語る、その奇妙で崇高な違和感を、ぜひ味わってほしい。
9.蘭子、3年ぶりの復活とシリーズ最終決戦── 『覇王の死 二階堂蘭子の帰還』
3年間の沈黙を破り、ついに二階堂蘭子が帰ってきた。シリーズ最大の宿敵・魔王ラビリンスとの決着をつけるために。そして、その再登場のタイミングがあまりにもドラマチックすぎる。
物語が3分の2ほど進んだその時、彼女は突如として現れ、すべての謎を一気に解き明かしてしまうのだ。探偵というよりも、もはや真相解明のために召喚された女神のような扱い。まさに「帰還」という言葉がこれほど似合うキャラクターもいない。
舞台となる眞塊村は、横溝正史リスペクトのど真ん中を行く因習まみれの閉鎖村。遺産をめぐる陰謀と、村を襲う謎の化物、過去の戦争犯罪、そして遺伝子工学という近未来SF的要素までぶち込まれたてんこ盛り構成で、ジャンルのるつぼと化している。
因習村×遺産相続×SF×最終決戦──詰め込みまくった最終楽章
蘭子が登場するまでの前半は、青木俊治という跡継ぎの視点で進行し、まるで純文学風の心理劇かと思いきや、じわじわと本格ミステリの構図が立ち上がってくる。
そして最大のインパクトは、蘭子が幼い男の子・亜蘭を連れて現れるところだ。彼女はこの3年間、どこで、誰と、何をしていたのか? 亜蘭の父親は誰なのか? そのあたりはまるっと伏せられたまま、読者の好奇心を絶妙にくすぐってくる。
ラビリンスとの因縁を決着させる「最終事件」であると同時に、蘭子自身の新章の幕開けでもあるという二重構造が、作品に奥行きを与えている。
最終決戦にしてはあまりにも情報量が多く、すべてを理解しきるのは難しい。だが、そのめちゃくちゃな密度が、このシリーズに求めていたものそのものだったとも言える。ミステリ的には王道の遺産相続殺人、しかしそこに村の伝承や謎の組織、科学的陰謀、そしてシリーズを貫くライバル対決が絶妙にミックスされるのだ。
『覇王の死』は、すべての伏線を回収しつつ、新たな謎を産み落とすという、実に「蘭子シリーズらしい」完結編である。これが本当に終わりなのか、それとも新章の始まりなのか。どちらとも断言できないまま、最後のページを閉じることになる。
だが一つだけ確かなのは、このシリーズが、間違いなく平成以降の本格ミステリのランドマークだったということだ。
10.謎と狂気が吹雪の中で踊る── 『巨大幽霊マンモス事件』
どこまでも広がる白銀のロシアの大地。そこで隊商が遭遇するのは、まさかの巨大な幽霊マンモス──?
二階堂黎人が描く『巨大幽霊マンモス事件』は、タイトルからしてインパクト抜群の作品である。そしてその中身も、期待通り(あるいは想像の斜め上)を突っ走ってくれる。
この物語は、『ロシア館の謎』に登場した元ドイツ軍人シュペアが語る過去の冒険という形式で描かれており、回想ミステリの体裁をとっている。時代は革命直後のロシア、地図にも載らぬ「死の谷」を目指す一行の旅路。
背景には赤軍、怪しい追跡者、スパイの影……まさにスパイス盛り盛りの冒険譚である。
謎の足跡と巨大な亡霊──雪原に仕掛けられた不可能殺人
しかし、そこはやはり二階堂作品。単なる戦場逃避行に終わらないのが面白い。物語の途中、一行は雪原であり得ない状況の殺人事件に直面する。周囲に足跡はなし、密室もない、でも死体はある。
しかも、現れるのは「巨大な幽霊マンモス」だ。もうここまで来ると、ジャンルがどこに向かっているのかすら曖昧になるが、それがこの作品の魅力でもある。
殺人の謎解き要素はしっかり残っており、二階堂黎人らしいロジカルな種明かしもちゃんと用意されている。ただし、そのロジックの先に待っているのは、「お、おう……」と呆れるか、「なんだこれ最高!」と笑ってしまうかのどちらか。理詰めの正統派ミステリを求めていると驚くかもしれないが、この突飛さを楽しめる人には、むしろご褒美レベルの展開である。
本作は、純粋な本格ミステリというよりは、ミステリの衣を被った風変わりな冒険活劇である。大正時代の探検ロマン、兵士の亡霊、死の谷に眠る伝説の獣……とにかく盛り込みすぎて胃もたれしそうなほどの内容だが、そのカオスっぷりこそが魅力でもある。
理屈よりも想像力。冷静な推理よりも、物語の熱量。『巨大幽霊マンモス事件』は、そんな価値観で読む作品だ。きっちり謎を解いてくれる安心感もあるにはあるが、それ以上に「なんだこの展開……でも笑うしかない」という快感を味わいたいなら、ぜひ吹雪のロシアへ旅立ってほしい。
ただし本作は、短編集『ユリ迷宮』に収められた「ロシア館の謎」の続編であるので、事前に「ロシア館の謎」を読んでおくことを強くオススメしたい。
11.館が消え、骨が砕け、論理が暴れ出す── 二階堂黎人『ユリ迷宮』
長編シリーズでおなじみの名探偵・二階堂蘭子が、短編でも躍動する。『ユリ迷宮』は、そんな蘭子の推理力と作者・二階堂黎人の密室愛が炸裂した、初の短編集だ。
収録作は多彩だが、どれもが古典的ガジェットをこれでもかと詰め込んだ濃密なミステリで構成されている。密室殺人、アリバイ崩し、消失トリック……しかもそれが短編のコンパクトな器に収まっているから、情報密度がとんでもない。まさに「短くて濃い」作品集である。
これぞ二階堂流「超級ロジック」の真骨頂
収録作の中でも伝説的なのが『ロシア館の謎』だ。舞台は吹雪の夜のロシア、革命後の不穏な空気が漂う時代。ある一夜、盗まれた宝石をめぐるスパイたちの駆け引きが行われる中で、なんと館そのものが消える。しかも、跡形もなく。
この短編の、何がすごいかというと、そのアイデアの突き抜けっぷりである。あらすじだけ見ると荒唐無稽だが、そこにキッチリとロジックを通してくるのが二階堂節。ちゃんと説明されるのに「えっ、そんなことアリ!?」と頭を抱えたくなる。
それでいて、ミステリとしての形式美もしっかり守っているから感心するしかない。名作『ロシア館の謎』は、その後の長編『巨大幽霊マンモス事件』にも繋がるスケールを持ち、シリーズの中でも特異な存在感を放っている。
『ユリ迷宮』は、蘭子というキャラクターの多面性を引き出しつつ、本格ミステリの王道と実験精神を両立させた優れた短編集だ。S・S・ヴァン・ダインやアガサ・クリスティーへの目配せも多く、ミステリマニアとしての二階堂黎人の趣味嗜好が詰まっている。
これから蘭子シリーズに入っていく人にも、「濃いめの一撃」を浴びたい人にもオススメできる。短編だからって舐めてかかると、思考力ごと粉砕されかねない。
どの話も骨太すぎて、読み終えたあとに軽く頭がグラつく、そんなミステリ濃度MAXの一冊だ。
12.蘭子が挑む、最悪で最高の短編集── 『バラ迷宮』
シリーズの中でも、これはとにかく「濃い」。二階堂黎人の短編集『バラ迷宮』は、読み終えたあとに「なんだこれ……」と呻きたくなるような、奇怪でグロテスクで、それでいてちゃんと論理的なミステリが詰まっている。
登場する事件はどれも、血と死と皮膚と火と、そんな要素が盛りだくさん。蘭子シリーズの中でも、ここまで演出過多なラインナップは珍しい。
例えば、人間大砲の発射と同時にバラバラ死体が降ってくる「サーカスの怪人」。顔面の皮を剥ぐ連続殺人鬼が登場する「喰顔鬼」。さらには突如として人間が密室内で発火する「火炎の魔」。
どれもが漫画かホラー映画みたいなシチュエーションなのに、ちゃんと推理小説として着地してくるあたり、作者の偏執的なバランス感覚がすごい。
エログロナンセンスとロジックの美学
この短編集の何が面白いって、「おぞましい事件」と「論理的解決」が全然喧嘩してないところである。ふつう、ここまでグロや猟奇に振ると、ロジックが吹っ飛んでしまいがちだ。
だが『バラ迷宮』では、むしろそのグロテスクな状況こそが、トリックの核心になっていたりする。しかも、説明を受けると「……ああ、そういうことか」と納得してしまう程度には筋が通っているからタチが悪い。
江戸川乱歩や横溝正史のような見世物感のあるミステリを現代風に再構成した、というのがいちばん近い感覚かもしれない。気味が悪い。見たくない。でも読んでしまう。そして、ちゃんと面白い。この中毒性は、二階堂作品の真骨頂である。
『バラ迷宮』は、蘭子シリーズの中でも異色作に分類されるだろう。しかしその一方で、本格ミステリが持つ「奇怪な現場の美学」や「見た目に騙される快感」を、最もストレートに味わえる一冊でもある。
グロいだけじゃない、ちゃんとフェアで、ちゃんとロジカルで、なのに脳裏にはグチャグチャした映像が残る。まさに〈美しい悪趣味〉というべき短編集だ。
13.正統派パズル・ミステリへの回帰── 『ラン迷宮 二階堂蘭子探偵集』
シリーズがSFっぽくなったりホラーに足を突っ込んだりしている間も、「やっぱり蘭子には、正統派の謎解きをやってほしい」と思っていた人は多かったはずだ。
そんなミステリ原理主義者たちの願いを真正面から叶えてくれたのが、この『ラン迷宮 二階堂蘭子探偵集』である。収録されているのはすべて中編。つまり、短編のキレと長編の重みのちょうどいいとこ取りなボリューム感で、蘭子が本格ミステリのど真ん中を突き進む姿を堪能できる。
表題作『蘭の家の殺人』は、名画家の遺した因縁の屋敷を舞台にした一編。12年前の不審死と現在の脅迫事件が複雑に絡み合い、3人の元愛人がそれぞれの秘密を抱えて登場するという、香り立つようなお約束がそろったクラシックな構成だ。
これがまた、エラリー・クイーンばりのロジックでしっかり落とし前がつくというのだからうれしい。
中編だからこそ映える、蘭子のロジック芸
やはりこの作品集のポイントは、〈中編〉という絶妙な尺にある。長編のような過剰な設定やサブプロットの混乱がなく、短編では描ききれない人間関係や動機の深掘りができる。
その結果、物語が整理されていて読みやすいのに、しっかり骨太な謎解きが成立しているのだ。特に五重密室を扱った作品では、読んでいて「まだ密室を重ねるのか!」と笑いながらも、ちゃんと理屈が通っていて驚かされる。
ラビリンス編のようなド派手な悪の演出はないが、その分、蘭子本来の論理と直感を併せ持つ知性と、探偵としての品格がじっくりと発揮されている。しかも、過去作を通じて培われた蘭子のキャラクターの深みがあるから、彼女の推理が単なるロジックの積み上げにとどまらない説得力を持つ。
『ラン迷宮』は、シリーズにとって大きな区切りでもあり、新たな始まりでもある。冒険と狂気の時代を経て、蘭子は原点に立ち返り、ふたたび論理の名探偵としてその座に返り咲いた。派手さは控えめだが、ミステリとしての満足度は極めて高い。
地に足のついた、正統派ロジックの香りを楽しみたいなら、ここが次の扉だ。
まとめ 特におすすめな作品

長編作品なら、
1作目『地獄の奇術師 (講談社文庫)』
2作目『吸血の家 (講談社文庫)』
3作目『聖アウスラ修道院の惨劇 (講談社文庫)』
4作目『悪霊の館 (講談社文庫)』
5作目『人狼城の恐怖(講談社文庫)』
は超おすすめ。もうこれは、ミステリ好きなら絶対読んでおきたい傑作だと思っている。
 四季しおり
四季しおり短編集の
『ユリ迷宮 (講談社文庫)』
『バラ迷宮 (講談社文庫)』
『ラン迷宮 二階堂蘭子探偵集 (講談社文庫)』
の3作品はどれもおすすめだ。