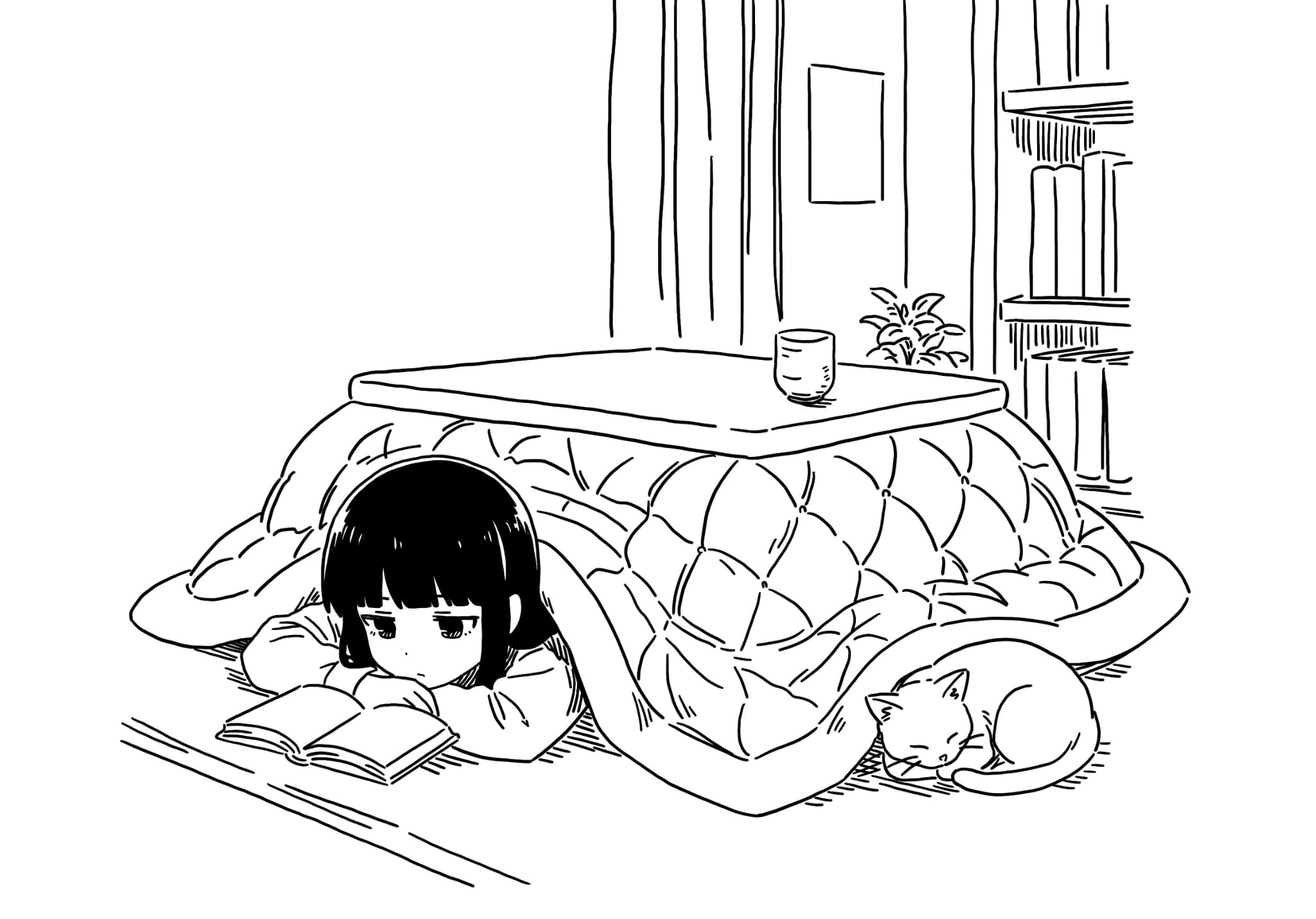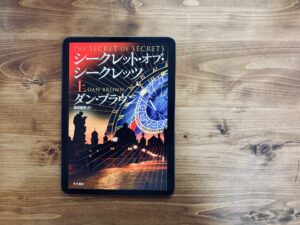エラリー・クイーンについて語るとき、やっぱり初期の「国名シリーズ」は避けて通れない。
舞台のユニークさ、フェアな手がかり、ミステリとしての構造美、そしてあの名物「読者への挑戦状」。これらすべてが揃っていて、黄金時代ミステリの華やかさとストイックさ、その両方を詰め込んでいる。
その中でも、第3作にあたる『オランダ靴の秘密』(1931年)は、「病院」という制度的なクローズドサークルを舞台にして、論理というメスで事件の真相を切り開いていくような一作だ。
タイトルにある「靴」は、まさにこの物語の中心にあるアイテム。最後には犯人を突き止める決め手にもなってくる。
ただの物的証拠としてではなく、「なぜその靴だったのか」「なぜそんな処置がされたのか」という違和感の背後に、ある人物像が浮かび上がってくる。エラリーはそれを、丁寧に論理だけで導き出していく。
クイーンの長編は、このあと心理劇や多重解決といった方向にも進んでいくけれど、この作品はむしろ純度の高いロジックミステリとして、要素をギリギリまで研ぎ澄ました構造の美しさを見せてくれる。
そして何より面白いのは、「病院」という舞台そのものを、ここまで見事にミステリ空間として活かしていることだ。

病院という閉鎖空間における、合理と不穏の交差点

この作品でいちばん面白い仕掛けは、オランダ記念病院という舞台そのものかもしれない。
「病院を舞台にしたミステリ」と聞くと、わりと見慣れた設定にも思えるけれど、本作ではこの空間を、論理的に、かつミステリ的にしっかり機能する迷宮として描いているのがすごい。
特に注目なのが、手術室まわりの空間設計だ。観覧席付きのオペ室、前室、控室、廊下、エレベーター、出入口……。すべての動線がきちんと計算されていて、読んでいる側は作中に登場する平面図を片手に、登場人物の動きをトレースしていくことになる。
こういう図面を見ながら考えるという読書は、ものすごく楽しいものだ。推理というより、パズルゲームに近い感覚。物理的な構造と人物の行動がぴたりと噛み合ったときの快感は、この作品ならではだと思う。
殺人が起きるのは、手術の直前に使われる前室。ある意味、「監視されている密室」だ。しかも犯人は、監視の目をすり抜けて犯行に及ぶ。
変装、時間差、目撃証言……どれもがこの空間設計とガッチリ噛み合っていて、物理的な配置が崩れたら成り立たないトリックになっている。まさに、舞台そのものがロジックになっている構成だ。
さらに、犯人がまねるのは足を引きずる歩き方という身体的な特徴まで含めた偽装。ここに証言の信頼性や、見た目の印象、権威への先入観といった心理的要素も入り込んで、密室トリック以上の深みが生まれている。
靴と論理のダンス
三番目の紐通しの穴から出ている靴紐に、半インチの長さの医療用粘着テープが巻きついていた。テープの表面には汚れひとつない。中ほどに奇妙なへこみができているのが、警視の目に留まった。警視は問いかけるようにエラリーを見た。
「紐が切れたんだろう。クッキーを一枚賭けてもいい」警視が言った。「そのくぼみは、切れた紐をつないだところだ。紐の両端がぴったり接していないんだな」
「肝心なのはそこじゃない」
エラリーはささやいた。
「粘着テープーテープだよ!とてつもなく重要な手がかりだ」
『オランダ靴の秘密』118,119ページより引用
では、この物語のタイトルにもなっている「靴」は、何を意味しているのか。
ネタバレを避けつつ触れるなら、この靴は日常に紛れた決定的な証拠だといえる。
しかも靴そのものより、「靴紐が切れていて、それを粘着テープで繋いでいた」という細かい描写が、物語の後半でとても大きな意味を持ってくる。
なんで、そんな不格好な補修をしたのか?
その絆創膏はどこから手に入れたのか?
そんなことをしたのは、どういう人物なのか?
エラリーは、そういった小さな「違和感」から、犯人の職業や性格、行動範囲にいたるまでを少しずつ読み解いていく。
しかも、こうした情報はすべて作中でちゃんと提示されている。つまり、読んでいる私たちにも同じように考えるチャンスが与えられている。
これこそが「読者への挑戦」の醍醐味だ。
この靴のエピソードが物語っているのは、どれだけ論理の積み重ねで真実に迫っていけるかということ。偶然や暴力ではなく、観察と推理でしかたどり着けない真相。
だからこそ、この作品は本格ミステリの教科書とまで呼ばれているのだろう。
探偵像の生成と、ミステリへの信頼
『オランダ靴の秘密』に登場するエラリー・クイーンは、シリーズ初期らしい若さや未熟さを残しつつ、名探偵らしい論理力もすでに見せている。
鼻眼鏡に文語調のセリフと、少しスノッブな雰囲気をまとった青年だけれど、事件の中ではときに感情的な反応を見せたり、父親である警視に不安をこぼしたりする。そんな姿が、人間らしさとして印象に残る。
個人的には、この時期の少し青さの残るエラリーが好きだ。のちの万能探偵とはまた違った魅力がある。
そしてもうひとつ、本作で忘れてはいけないのが「読者への挑戦状」。
物語の終盤、犯人を明かす前に、クイーンがこんな風に語りかけてくる。
読者への挑戦状
数年前に発表したわたしの最初の探偵小説における例にならって、『オランダ靴の秘密』の物語のこの時点で、読者への挑戦状を差しはさみ……読者諸君が、ドールンおよびジャニー殺害事件を正しく解明するのに欠かせない、すべての関連する事実を現時点で入手していることを、誠心誠意をもってここに断言する……。
『オランダ靴の秘密』373ページより引用
つまり、
「この時点で、あなたにはすべての手がかりが与えられている。さあ、推理してみたまえ」
ということだ。
私はこの挑戦状が大好きだ。ミステリというジャンルに対する絶対的な信頼がなければ、こんなことは書けない。だからこそ、読む側も真剣に受け止めたくなる。
この仕掛けがあることで、物語は見せられるものから「挑むもの」に変わる。読者は推理というゲームに参加し、作品の中に一歩踏み込むことになるのだ。
こうしたスタイルは、のちに日本の作家たち、たとえば綾辻行人や有栖川有栖、法月綸太郎や青崎有吾などにも強く影響を与えていく。
そう思うと、『オランダ靴の秘密』は単なる古典じゃなくて、「ミステリというジャンルがどう形づくられてきたか」を今に伝える、大切な存在でもある。
論理の迷宮に、今こそ挑め

クイーンが描いているのは、「人間の罪」ではなく、「思考の冒険」なのだと思う。
冷たく乾いた印象を持たれるかもしれないけれど、そこには知性と論理に対する深い愛情がある。
もし、感情に頼るサスペンスに少し疲れていたり、「自分の頭で考えて解く」ことが楽しいと感じる人なら──この作品は、考えることでしか得られない爽快感をプレゼントしてくれる。
クイーンは言う。
「すべての手がかりは提示された」と。
あとは、論理の靴を履いて踏み出すだけだ。
靴紐がほどけないように、きちんと結び直してから。