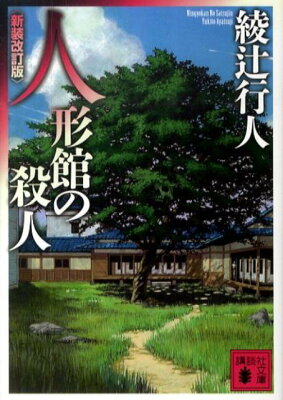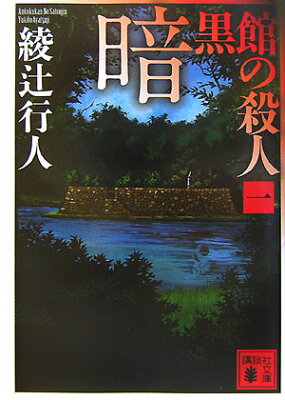〈館シリーズ〉の読む順番(刊行順一覧)
- 『十角館の殺人』(1987年)
──孤島の十角形の館で起きる連続殺人。ミステリ史に残る〈あの一行〉の衝撃。 - 『水車館の殺人』(1988年)
──水車小屋のある洋館が舞台。記憶をめぐるミステリ。 - 『迷路館の殺人』(1989年)
──作家たちが集う迷路のような館。メタ構造も話題に。 - 『人形館の殺人』(1990年)
──不気味な人形と密室の謎。ホラー色も強め。 - 『時計館の殺人』(1991年)
──精緻な館の構造と時間をめぐるトリックが秀逸。 - 『黒猫館の殺人』(1992年)
──「記録」がテーマ。過去と現在が交錯する。 - 『暗黒館の殺人』(2004年)
──シリーズ最長。重厚で幻想的な世界観と謎。 - 『びっくり館の殺人』(2012年)
──ジュブナイル風の短編。少年少女向けながらシリーズ本編とリンク。 - 『奇面館の殺人』(2012年)
──仮面と記憶、アイデンティティがテーマ。シリーズの原点回帰的作品。
あなたはどの館に閉じ込められたい? 館シリーズの正しい歩き方
1987年、一冊の小説が日本のミステリ界を大きく揺さぶった。綾辻行人のデビュー作『十角館の殺人』だ。
ロジックとフェアプレイを大事にする昔ながらの本格ミステリを、現代的な感性でよみがえらせたこの作品は、「新本格ミステリ・ムーヴメント」の始まりを告げた記念碑的な一作だった。
そしてここからスタートするのが「館シリーズ」。綾辻行人はこのシリーズを通じて、本格ミステリに新しい風を吹き込み続けている。
一番の特徴は、天才建築家・中村青司が設計した奇妙な館を舞台にしていること。「十角館」「水車館」「迷路館」…どれも現実にはありえないような建物で、そこに密室や消失トリックが組み合わさって、めちゃくちゃ刺激的な世界が広がっていく。
現在までにシリーズは全9作。
じゃあどこから読むのがいいのか?
結論はシンプルで、刊行順に読むのがベストだ。
というのも、作品ごとにきちんと完結していながら、シリーズ全体で見ると巨大な仕掛けが用意されているからだ。順番通りに進むことで、作品の構造美やシリーズ全体の秘密にガチで向き合える。
この記事では、その読む順番と内容、さらに魅力をざっくり紹介していく。
館の扉は、順番通りに開けていくからこそ面白い。
そこに待っているのは、長く読み継がれてきた名作ならではのご褒美だ。
1.『十角館の殺人』
舞台は孤島・角島に建つ奇妙な十角形の館。半年前には、館の設計者である建築家・中村青司が、島にあった青屋敷の炎上事件で焼死したとされていた。
この島を、大学ミステリ研究会に所属する7人のメンバーが訪れる。彼らはサークルの慣習に従い、互いを著名なミステリ作家のニックネーム(オルツィ、カー、エラリイなど)で呼び合っていた。
やがて、メンバーの一人が殺害され、それを皮切りに、まるで何者かに予告されたかのように次々と連続殺人が発生する。一方、本土では、研究会の元メンバーである江南孝明のもとに、死んだはずの中村青司から奇妙な手紙が届く。
江南は、青司の死や過去の事件に疑念を抱き、調査を開始。孤島での惨劇と本土での謎解き、二つの物語は並行して進み、予測不能な驚愕の結末へと向かう。
新本格の幕開けを告げる、あの一行の衝撃
綾辻行人のデビュー作『十角館の殺人』は、1980年代後半に始まった「新本格ミステリ・ムーヴメント」の出発点としてよく名前が挙がる作品だ。
いま振り返っても、この一作が出たことで日本のミステリの景色がガラッと変わった、という感覚はやっぱりある。
当時の本格ミステリは、悪く言えば少し落ち着きすぎていた。そのタイミングで現れた『十角館』は、新人のデビュー作という肩書きがまったく似合わない完成度で、ジャンルの流れそのものを押し動かしてしまった。ここから何が続いていったかを考えると、その影響の大きさは実感しやすい。
ベースになっているのは、アガサ・クリスティの『そして誰もいなくなった』だ。ただし、やっていることは単なるオマージュにとどまらない。構造やモチーフを借りつつ、別の方向から仕掛け直してくる。この「古典をそのまま再現しない」感じが、新本格らしさの始まりだった。
物語の組み立ても巧い。孤島に建つ十角形の館で起きる連続殺人と、本土で少しずつ明らかになっていく過去の出来事。この二本の線が交互に進み、終盤に向かって静かに距離を詰めていく。片方だけ追っていると見えないものが、合流した瞬間に一気につながる。その構造自体が、もうひとつの仕掛けになっている。
登場人物たちが、有名ミステリ作家の名前をニックネームとして名乗る点も印象的だ。遊び心のある設定だが、それだけでは終わらない。人物の個性をあえて薄くし、先入観を揺らす役割も担っている。このあたりの計算は、かなり周到だと思う。
そしてやはり、話題にせずにはいられないのが終盤の〈あの一行〉だ。この一文が出てきた瞬間、それまで積み上げてきた理解がひっくり返る。伏線や情報の置き方が、全部この一点に向かって並べられていたことに気づいたときの感覚は、かなり強烈だ。
読み終えたあと、自然と最初に戻りたくなる構成力と、はっきり記憶に残る転換点。『十角館の殺人』は、トリックがすごいから有名になった、というだけの作品ではない。
ミステリがまだまだ自由に遊べるジャンルなんだ、という感覚を、最初にわかりやすく示してくれた一作だ。
この作品が特別扱いされ続ける理由は、今読み返してもはっきりわかる。
2.『水車館の殺人』
人里離れた山間に佇む、巨大な三連水車を備えた異形の館〈水車館〉。
館の主・藤沼紀一は、過去の事故で顔に深い火傷を負い、常に白い仮面で素顔を隠している。彼と共に暮らすのは、十九歳で妻となった美少女・由里絵だった。
一年前の嵐の夜、この館では家政婦の転落死、焼却炉からの焼死体発見、そして密室からの人間消失という不可解な事件が連続して起きている。
そして一年後、同じ嵐の夜。藤沼家の人々と、亡き幻想画家・藤沼一成の遺作「幻影群像」に関心を抱く者たちが再び水車館に集まる。そこで、一年前の悪夢をなぞるかのように、新たな殺人が発生。
一年前に消えた男が友人だった探偵・島田潔は、真相を追って水車館へと足を踏み入れるのであった。
横溝正史への憧憬と王道ミステリ
『水車館の殺人』は、日本の伝統的な探偵小説のムードを強く意識した作品だ。とりわけ横溝正史作品に通じる、重たく沈んだ空気や怪奇味が、全体に色濃く漂っている。
舞台は、人里離れた場所に建つ異様な洋館。仮面をつけて姿を見せない館の主、幽閉される美少女、呪われた絵画、そして過去に起きた凄惨な出来事。どれもどこかで見たことのある要素だが、その取り合わせがいかにも「館もの」らしく、クラシック・ミステリ好きには刺さる構成になっている。
物語は、水車館で起こったかつての悲劇と、探偵・島田潔が関わる現在の出来事が交互に語られる二重構成だ。過去と現在、記憶と事実が少しずつ重なり合い、点だった情報が線になっていく。この組み立ては派手ではないが、じわじわ効いてくるタイプの面白さがある。島田潔と一緒に違和感を拾い集めながら、時間を行き来していく感覚が心地いい。
終盤で伏線が一本につながる瞬間の手応えは、本格ミステリらしさのど真ん中にある。派手な仕掛けよりも、積み重ねの妙が効いてくる構成だ。
デビュー作『十角館の殺人』が、強烈なトリックで一気に印象を残す作品だったのに対し、『水車館の殺人』は物語の骨格そのものを丁寧に組み上げている印象がある。全体に落ち着いた佇まいがあり、クラシカルな形式をきちんと踏まえている。
それでも、単なる王道回帰で終わっていないのがこの作品の面白いところだ。ラストに差し込まれる幻想的なトーンが、物語を少し別の場所へ連れていく。論理だけで閉じるのではなく、感情やイメージがふっと広がる終わり方をする。
特に終幕の余情は印象的で、ミステリでありながら幻想譚を読んだような感覚が残る。トリックの瞬間的な驚きでは『十角館』に譲るかもしれないが、物語全体の構築や心理の描写、ラストの詩情では、この作品ならではの魅力がはっきりある。
『十角館』が強烈な一撃でシリーズの幕を開けた作品だとすれば、『水車館』はその世界観に厚みを与えた一作だ。
古典的な探偵小説の雰囲気と、綾辻行人らしい感性が交差することで、「館シリーズ」の輪郭がここではっきりしてくる。
3.『迷路館の殺人』
舞台は、著名な老推理作家・宮垣葉太郎が、自身の死期を悟り、地下に密かに建造した奇怪な館〈迷路館〉。
遺言により招かれたのは、彼の四人の弟子である若手作家たち。彼らは莫大な遺産を懸け、迷路館を舞台にした推理小説を執筆し、その出来を競うという異様な競作に挑むことになる。
だが、そのゲームは同時に、連続殺人の幕開けでもあった。外界から遮断された地下迷宮で、作家たちの書く物語をなぞるかのような「見立て殺人」が次々と起こり始める。
周到な企みと、ミステリというジャンルそのものへの遊戯精神が交錯する、シリーズ第3作。
虚構と現実の迷宮を彷徨う、推理の極致
綾辻行人の『迷路館の殺人』は、「館シリーズ」の中でもかなり毛色が違う。読んでいてまず感じるのは、「これはだいぶ遊んでるな〜」という感触である。
最大の特徴は、メタフィクション的な仕掛けをかなり思い切って前面に出している点だろう。舞台となるのは、とある館に集められた複数の作家たち。彼らは館の中で推理小説を書き始めるのだが、その最中に現実の世界で殺人事件が起きてしまう。そこから先は、虚構と現実の境界が少しずつ崩れていく。
面白いのは、作中作として提示される小説が、単なる本文だけでは終わらないところだ。実在の書籍のように表紙や奥付まで用意されていて、読み進めるほどに「いま自分は何を読まされているんだ?」という感覚が揺らいでくる。この仕掛けが、かなり効いている。
全体の雰囲気は、どこか楽しそうだ。実際、肩に力を入れて構えた本格ミステリというより、作者自身が仕掛けを並べながら「どこまで引っかかるかな」と試しているような軽やかさがある。その一方で、遊びで終わらせないだけの構造もしっかり用意されている。
作中には、見立て殺人や地下迷宮を使ったトリック、先入観を逆手に取る心理的な罠などが次々と登場する。虚構の殺人と現実の殺人が絡み合い、気づけば「どこまでが小説で、どこからが現実なのか」という感覚そのものが揺さぶられていく。この混線状態が、この作品のいちばんの持ち味だ。
正直なところ、途中で「このあたりは見えてきたかも」と思う瞬間はあるかもしれない。だが、『迷路館の殺人』はそこで終わらない。一度きれいに収まったように見せてから、エピローグでもう一段階、視点をひっくり返してくる。
終盤で明かされる、まだ終わっていなかった真実の感触はかなり強烈で、読み終えたあとに「また一枚上をいかれた!」と苦笑いしたくなるタイプの驚きがある。
作中作という仕掛けは、単なる技巧にとどまらず、「語りそのものを疑う」という方向にまで踏み込んでいる。誰が語っているのか、その語りはどこまで信用できるのか。そうした根本的な前提を揺さぶってくる点で、本作はかなり攻めたことをやっている。
『迷路館の殺人』は、謎解きの快感だけを提供するタイプの作品ではない。物語という形式そのものに手を突っ込み、「本格ミステリはどこまで遊べるのか」を試してみせた一作だ。
シリーズの中でも異色作として語られ続けるのは、その実験精神がいま読んでもはっきり伝わってくるからだと思う。
4.『人形館の殺人』
古都・京都。青年画家・飛龍想一は、亡き父が遺した屋敷〈緑影荘〉へ、育ての母・池尾沙和子と共に移り住む。館内には顔のない、あるいは身体の欠損したマネキン人形が無数に置かれ、近隣からは密かに「人形館」と呼ばれていた。
新生活の開始と同時に、想一の周囲では不可解な出来事が相次ぐ。折しも京都では、残忍な通り魔殺人事件が続発。やがて想一のもとにも、正体不明の存在から脅迫状が届き、執拗な嫌がらせが始まる。
追い詰められた想一は、探偵となった旧友・島田潔に助けを求めるが、破局への歯車はすでに回り始めていた。物語は、悲劇的な結末へと緊張を高めながら突き進んでいく。
予想を裏切る変化球
『人形館の殺人』は、「館シリーズ」の中でもかなり毛色の違う作品だ。異色作と呼ばれることが多いのも納得で、これまで当たり前のように使われてきた「隔絶された館」という型を、あえて外してきたところがまず印象に残る。
舞台は孤島でも山奥でもなく、京都の市街地にある一軒の屋敷だ。日常のすぐ隣にぽつんと建つ「人形館」。その内部には、顔のないマネキンがずらりと並んでいて、視線がないはずなのに、ずっと見られているような落ち着かなさがある。この無言の圧が、作品全体の不気味さを支えている。
物語は、街で続く通り魔事件という「外側の恐怖」と、主人公・想一が抱え込んでいく「内側の恐怖」が絡み合いながら進んでいく。嫌がらせや脅迫、説明のつかない不安が積み重なっていく展開は、サイコホラーや心理サスペンスにかなり近い手触りだ。
この作品のポイントは、派手な物理トリックを前に出していないところにある。軸になっているのは、人間の思い込みや認識のズレだ。視点の切り替え、情報の出し入れ、意図的なミスリードが少しずつ積み重なり、終盤でまとめて反転する。この流れがきれいに決まっていて、「やられたな」と感じる人が多いのも無理はない。
読み終えたあとに残るのは、スッキリした解決感というより、胸の奥に沈殿するようなざわつきだ。これまでの館シリーズでは、閉じられた空間は建物そのものだったが、本作ではそれが登場人物の心に置き換えられている。その感覚が、読後もしばらく離れない。
タイトルの「人形館」という言葉も、あとから効いてくる。ここでの「館」は、建築としての形ではなく、記憶や恐怖、執着といった心理の集積として描かれている。この発想の切り替えが、この作品のいちばん面白いところだと思う。
つまり綾辻行人は、この作品で「館」という概念を少し広げてみせた。物理的に閉ざされた空間から、精神的に逃げ場のない場所へ。その一歩によって、「館シリーズ」はクローズド・サークルだけのシリーズではなくなった。
『人形館の殺人』は、舞台設定こそ異なるが、閉塞感や逃れられなさというシリーズの芯はしっかり残っている。シリーズの中でもかなり挑戦的で、その後の広がりを考えると、通過点としても外せない一作だ。
5.『時計館の殺人』
神奈川県鎌倉市の外れ、深い森の中に〈時計館〉と呼ばれる館が建っていた。
館内には古今東西の時計が無数に収集されており、十年前には館主の娘が不可解な死を遂げたという暗い過去を持つ。以来、少女の亡霊が出没するという噂が絶えなかった。
『十角館の殺人』の惨劇を知る数少ない人物の一人・江南孝明は、出版社・稀譚社のオカルト雑誌『CHAOS』の取材班の一員として、この曰く付きの館を訪れる。同行するのは、美貌の霊能者・光明寺美琴や、大学のオカルト研究会の面々。
霊能者による交霊会が開かれた夜、光明寺美琴が忽然と姿を消す。それを合図に仮面の殺人者が出現し、閉ざされた時計館で悪夢の三日間が幕を開ける。
機構と構造が謎と化す、館シリーズの最高到達点
『時計館の殺人』は、「館シリーズ」の中でも完成度が頭ひとつ抜けている作品だ。
時間そのものを巨大な仕掛けとして扱い切った点で、シリーズの中でもかなり特別な立ち位置にある。日本推理作家協会賞を受賞しているのも伊達じゃなく、「シリーズ最高傑作」と推す人が多いのも自然だと思う。
この作品のいちばんのポイントは、館そのものの構造をトリックの中心に据えているところだ。密室や隠し通路といった部分的な仕掛けではなく、建物全体の造りや機能が、そのまま謎として組み込まれている。スケールが一段違う。
舞台となる時計館は円環状の建築で、内部には無数の時計が配置されている。10年前に起きた少女の死、館主が遺した詩「沈黙の女神」、そして止まることなく刻まれ続ける時間。このあたりは雰囲気作りに見えて、実は全部がきっちり意味を持って動いている。読んでいるうちに、空間そのものに翻弄されている感覚になるのが面白い。
物語は二つの視点で進む。館に閉じ込められた江南たちのパートと、外側から事件を追う鹿谷門実(島田潔)のパートだ。館内で起こる連続殺人と過去の出来事が少しずつ絡み合い、情報が丁寧に積み上げられていく。この過程がとにかく気持ちいい。
中でも圧倒されるのが、終盤に用意された鹿谷門実の長い推理シーンだ。かなりの分量があるのに、論理が一切ブレない。散らばっていた伏線が次々と回収され、複雑に見えていた出来事が一本の線にまとまっていく。この感覚は、まさに本格ミステリの醍醐味だ。
ただ、『時計館の殺人』が強く印象に残る理由は、論理の鮮やかさだけじゃない。館に残された詩や、語られなかった死、刻み続ける時間の存在が、物語全体にどこか切なさを残す。謎が解けたあとも、感情の余波がしばらく続くタイプの作品だ。
この作品では、「館」は単なる舞台装置ではない。建物そのものが嘘をつき、時計が真実を隠す。論理のための空間であると同時に、人の記憶や感情を閉じ込める箱としても機能している。
建築と物語、空間と時間、謎と記憶。それらがきれいに噛み合った結果として、『時計館の殺人』は読み手を迷わせ、最後には大きな納得を残す。シリーズの中でも一つの到達点と呼ばれるのは、やはりそれだけの理由があるのだ。
6.『黒猫館の殺人』
推理作家・鹿谷門実と担当編集者・江南孝明のもとに、記憶を失った老人・鮎田冬馬から奇妙な依頼が持ち込まれる。
彼はホテル火災で重傷を負い、過去の一切を失ったという。手がかりは、火災現場から発見された、自身が書いたと思しき一冊の手記だけだった。
手記には、かつて管理人として働いていた北海道・阿寒の森奥に建つ〈黒猫館〉で起きた、奇怪な殺人事件の顛末が克明に綴られていた。内容の真偽も定かでないまま、鹿谷と江南は老人を伴い、手記を頼りに黒猫館を探す旅に出る。
ようやく辿り着いた黒猫館は、手記の記述と微妙に食い違い、過去の事件を示す痕跡も見当たらない。深い森に隠された館で彼らを待ち受けていたのは、世界の見え方を揺るがす衝撃の真実だった。
記憶と手記の迷宮で揺らぐ真実
『黒猫館の殺人』は、「館シリーズ」の中でもかなり異質な一作だ。
読んでまず印象に残るのは、事件そのものよりも、記憶を失った老人・鮎田冬馬と、彼が残した手記の存在。この二つが、そのまま大きな謎として物語の中心に置かれている。
老人は本当に記憶をなくしているのか。それとも、語られている内容自体に何か仕掛けがあるのか。手記に書かれた出来事は事実なのか、それとも作られた物語なのか。鹿谷と江南が北海道の広い風景の中を進んでいくにつれて、こちらも一緒に、その曖昧で落ち着かない依頼と向き合うことになる。
この作品、シリーズの中でもかなり大胆なことをやっている。思い込みを前提に組み立てられた構造が、終盤でひっくり返る瞬間の感触は強烈だ。途中まで当たり前だと思っていた前提が、音を立てて崩れていく。
序盤から散らされている小さな違和感や、手記と現実のあいだに生じる微妙なズレ。それらは読み進めている間は気になりつつも、はっきりとは掴めない。だが後半に入ると、それぞれがきれいに意味を持ち始める。細部がそのまま鍵になっていくあたりは、いかにも綾辻行人らしい組み立てだ。
物語の中で何度か出てくる「鏡の世界」という言葉や、実在する黒猫館と手記に描かれた館のわずかな食い違い。こうしたディテールも、あとから振り返るとかなり重要なヒントだったことに気づく。読後にページを戻したくなるタイプの仕掛けが多い。
この作品で扱われているテーマは、かなりシンプルだ。「語りはどこまで信用できるのか」という一点に集約されている。記憶喪失という設定と、手記という不確かな媒体。その組み合わせが、物語の足場そのものをぐらつかせてくる。
ここでは、事実そのものよりも、「どう語られたか」「どう受け取られたか」が重要になる。情報の正しさより、解釈のズレや誤解に焦点が当てられていて、そのぶん読み手は足元の感覚を失っていく。
そして真相が明かされたときに残るのは、犯人が誰だったか、という話だけではない。視点がひっくり返り、記憶と語りが組み替えられることで、見えていた世界そのものが別の形に変わる。その感覚が、この作品のいちばんの持ち味だ。
『黒猫館の殺人』は、トリックだけで勝負する作品ではない。物語の構造そのものを疑わせることで、「信じること」や「語ること」の不安定さを突きつけてくる。シリーズの中でも好みは分かれるが、強く印象に残る一作なのは間違いない。
7.『暗黒館の殺人』
九州の奥深く、霧に包まれた峠の先に広がる湖。その湖上の小島に、巨大な漆黒の館〈暗黒館〉は聳え立っていた。
そこは、忌まわしい血の宿命と秘密を抱えた浦登家が、外界との接触を断つように暮らす場所だった。
語り手である大学生の「私」は、旧知の浦登玄児に招かれ、この謎めいた館を訪れる。滞在中、「私」は十角塔からの墜落事故、閉ざされた座敷牢、この世ならざる美しさを持つ双子の姉妹、そして奇怪な儀式〈ダリアの宴〉など、異様な出来事に次々と遭遇していく。
一方、建築家・中村青司の関与を知り暗黒館を目指した江南孝明は、到着直後の事故で一時的に記憶を失ってしまう。
浦登一族の忌まわしい秘密と、館内で続発する連続殺人。著者が全力を注ぎ込んだ、ゴシック・ミステリ巨編の幕が、重々しく開かれる。
綾辻ワールドの集大成。幻想と怪奇、そして多層的な謎
『暗黒館の殺人』は、文庫全四巻、2000ページ超えという、見た目からしてただならぬボリュームの作品だ。
正直、手に取った瞬間に少し身構える。でも読み始めてすぐにわかる。これは普通に「読む」小説じゃない。感覚としては、物語の中に沈み込んでいく体験に近い。
前作『黒猫館の殺人』から十二年。綾辻行人が、自分の美意識や趣味を遠慮なく詰め込み、好きなようにやり切った作品だ。ゴシック趣味、異形の存在、土着の因習、狂気に支配された一族、逃れられない宿命の連鎖。館シリーズで描かれてきた要素が、ここでは過剰なほど濃縮されている。
面白いのは、過去作とのつながりがあちこちに仕込まれているところだ。『水車館』に関わる絵画や、『時計館』を思わせる時計といった断片が、さりげなく物語に入り込んでくる。単なるおまけではなく、シリーズ全体をひとつの世界としてまとめ上げる役割を果たしているのがわかる。
舞台となる暗黒館の存在感も、とにかく強烈だ。海に面した断崖に建つその館は、不気味さと幻想性を併せ持ち、読んでいる側の現実感を少しずつ削っていく。浦登一族の狂気、繰り返されるダリアの宴、夢のように連なる描写。その中を進むうちに、現実と幻の境目が曖昧になっていく感覚がある。
もちろん、謎も単純な犯人当てでは終わらない。語り手である「私」の正体、浦登家の血に潜む秘密、過去に起きた惨劇の連なり。それらは一気に解き明かされるというより、絡まった糸を少しずつほどいていくような形で明らかになっていく。
この長さ自体が、実はかなり重要だ。これまで綾辻行人が描いてきたテーマやモチーフ(中村青司の残したもの、反復される館の形式、語りの仕掛けなど)それらをまとめて織り上げるには、この分量が必要だったのだと思えてくる。結果として『暗黒館の殺人』は、シリーズの中心にどっしり腰を据える存在になっている。
この作品は、単に館がもう一つ増えた、という話ではない。そもそも「館」とは何なのか、「語り」とは何なのか。その前提そのものを揺さぶってくる、かなり挑戦的な一作だ。
読み終えたあと、不思議な感覚が残る。まるで自分の中にも、暗黒館の一部が建ってしまったかのような感触だ。
そこにあるのは、忘れられた記憶や影、そして物語というものが持つ底知れなさ。その重さこそが、この作品の読後に残るものだと思う。
8.『びっくり館の殺人』
閑静な高級住宅街の一角に、奇妙な外観と不気味な噂を持つ洋館が建っていた。近隣の子供たちは、その館を「びっくり館」と呼んでいた。
この町に越してきた小学六年生・永沢三知也は、びっくり館に住む同い年の少年・古屋敷俊生(トシオ)と出会う。病弱で外出もままならないトシオと、家庭環境に共通点を持つ三知也は、急速に友情を深めていく。
クリスマスの夜、三知也は同級生の湖山あおい、家庭教師の新名努と共に、館の主であるトシオの祖父・古屋敷龍平の誕生パーティーに招かれる。そこで披露されたのは、龍平による異様な腹話術の人形劇だった。
そしてその夜、密室と化した館の一室で、古屋敷龍平が殺害される。物語は、大人になった三知也が、少年時代のこの事件を回想する形で語られていく。
あのクリスマスの夜、びっくり館で何が起こったのか。
子供向けレーベルからの挑戦。ライトな皮を被ったダークホラー
『びっくり館の殺人』は、「館シリーズ」の中でもかなり立ち位置が特殊な作品だ。というのも、そもそも刊行された場所が違う。
講談社の児童向けレーベル「ミステリーランド」からの書き下ろしで、想定されている対象は小中学生。スタート地点からして、ほかの館シリーズとは明確にズレている。
語り手は小学生の少年で、物語も彼の視点で進む。挿絵も多く、見た目だけなら軽く読めそうなジュブナイル小説に見える。でも、そこで油断すると普通に足を取られるから要注意だ。この作品、見かけよりずっと暗いし、嫌なところを突いてくる。
館の主・古屋敷龍平の異様さや、腹話術人形の不気味さは、児童向けという枠を軽々と飛び越えている。終盤で明かされる真相と結末も含めて、扱っているのはかなり生々しい恐怖だ。人間の奥にある歪みを、妙にまっすぐ差し出してくる。
本格ミステリらしい大仕掛けがあるかというと、そこは控えめだ。その代わり、この作品が狙っているのは、読み終えたあとに残る引っかかりのような感触だ。語り口はやわらかいのに、裏側に何かずっと居座っている。その違和感が、読み進めるほどに効いてくる。
『暗黒館の殺人』が圧倒的な分量と重さで押し込んでくる作品だったのに対して、『びっくり館』はかなりコンパクトで、テンポもいい。けれど、その軽さは手抜きではなく、別の方向への実験になっている。綾辻行人が、違う条件でどこまでできるかを試している感じがある。
探偵役の島田潔(=鹿谷門実)は少し顔を出す程度で、物語の中心にはいない。館の設計者・中村青司も、名前が触れられるくらいだ。そういう意味では、本流というより番外編に近い位置づけになる。ただ、それでも「密室殺人」というシリーズの芯はきちんと残っていて、その解き方には小気味いい工夫がある。
注目したいのは、あえて「子供向けレーベル」で出された点だと思う。この装いを逆手に取って、無邪気そうな外見の中に、かなり不穏な物語を仕込んでいる。若い主人公、素直な文体、挿絵つきの本文。その全部が、警戒心を下げるための下地になっていて、気づいたときにはもう遅い。
「びっくり館」というタイトル自体が、その仕掛けの一部だ。明るくて軽そうな名前の裏に、じっと湿った闇が隠れている。
それに気づくのは、おそらく読み終えてからだ。ページを閉じたあとも、何かがそのまま胸の奥に残る。その感触こそが、この作品のいちばん厄介で、忘れがたいところだと思う。
9.『奇面館の殺人』
東京郊外の山中に建つ〈奇面館〉では、館主・影山逸史によって、年に一度の奇妙な集いが開かれていた。招待された六人の客人は、到着と同時に六種類の「鍵のかかる仮面」を一つずつ与えられ、館内では常に仮面で素顔を隠すことを義務づけられる。
推理作家・鹿谷門実は、自身と瓜二つの容姿を持つ作家・日向京介の依頼を受け、身分を偽ってこの集いに参加。折しも季節外れの猛吹雪により、館は完全な孤立状態に陥る。
その夜、館主・影山逸史が私室〈奇面の間〉で惨殺される。死体は頭部と両手の指を切断され、持ち去られていた。
さらに、客人たちの仮面は何者かによって施錠され、外すことができなくなってしまう。
誰が誰なのかすら判別できない異様な状況の中、疑心暗鬼が館を覆う。前代未聞の条件下で、名探偵・鹿谷門実の困難な推理が始まる。
初期作品への回帰。ゲーム的本格パズル
『奇面館の殺人』は、「館シリーズ」の中でもかなりストレートに本格ミステリをやりにきた作品だ。派手な世界観や情緒に振るのではなく、ひたすら論理と構造で勝負してくる。その意味では、シリーズ屈指のパズラー寄りと言っていい。
前作『暗黒館の殺人』が、ゴシック趣味と物語性をこれでもかと詰め込んだ大作だったのに対し、本作は一気に方向転換している。雰囲気よりも仕掛け、感情よりも論理。『十角館』や『迷路館』を思い出す人も多いはずで、どこか原点に戻ってきたような感触がある。
いちばん目を引くのは、「全員が鍵付きの仮面をかぶり、素顔を隠さなければならない」という設定だろう。顔が見えない、表情が読めない。その状態が続くだけで、空間全体に妙な緊張が生まれる。ここでの仮面は単なる演出ではなく、物語を動かすための中心装置になっている。
誰が誰なのか、本当に目の前にいる人物は本人なのか。殺されたのは本当に館の主人なのか。そもそも犯人は、どの立場にいるのか。仮面が一枚はがされるたびに、それまで立てていた推理が崩れ、また組み直しになる。この強制リセット感が、なかなか手厳しい。
鹿谷門実の推理も、一直線には進まない。可能性を広げては潰し、前提を疑っては組み替える。その過程で明らかになっていく伏線やトリックはよく練られていて、最後にたどり着く結論を知ったとき、「完全にやられた」と思わされる。
この作品では、仮面そのものがテーマでもある。顔を隠すことで、問題は「誰が犯人か」から「誰が誰なのか」へとずれていく。さらに言えば、「被害者とは何か」というところにまで踏み込んでくる。その揺さぶり方が、かなり意地が悪い。
視覚情報がほとんど使えない舞台で、頼りになるのは行動の整合性や言葉の違和感、論理の積み重ねだけだ。勘や雰囲気に逃げる余地はあまりなく、読んでいる側も否応なく頭を使わされる。気軽に読めるタイプではないが、その分、解き切ったときの手応えは大きい。
『奇面館の殺人』は、感情に訴える作品というより、思考に正面から殴りかかってくる作品だ。仮面の奥に何が隠れているのか。その一点を追い続ける時間こそが、この作品のいちばんの楽しみ方である。
あなたも、迷宮へ
綾辻行人の「館シリーズ」は、ただの人気シリーズじゃない。日本の現代本格ミステリの流れを大きく変えた、超重要な作品群だ。
天才建築家・中村青司が作り出した奇妙な館を舞台に、緻密なロジック、大胆なトリック、独特の空気感、そして最後にドカンとくる結末。その全部を一つに融合させたスタイルは、のちの作家たちに大きな影響を与えたし、ジャンルそのものの可能性を一気に広げてしまった。
しかもこのシリーズは、建築を使った謎解きや心理描写に加えて、ときにはホラーっぽい要素まで取り込んでくる。常に「驚き」を用意しているから、長年にわたって人を惹きつけてやまないのだろう。
もしまだ館シリーズに触れてないなら、やっぱり最初の『十角館の殺人』から入るのがオススメだ。
あの迷宮に足を踏み入れた瞬間から、知的なワクワクと背筋がゾクッとする恐怖、そして読後に忘れられない衝撃が、しっかり待ち受けている。