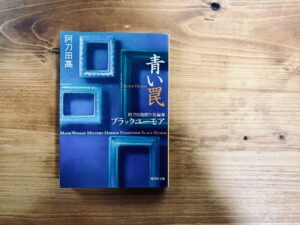梓崎優『叫びと祈り』を初めて読んだときの衝撃は、いまだによく覚えている。
それは単なる面白いミステリではなかった。読み進めるうちに、まるで地図の端っこがぐいっと引っ張られ、世界そのものの形が変わっていくような感覚があった。
収録された短編の舞台はサハラ砂漠、スペインの田舎町、ロシアの修道院、アマゾンの奥地。
どれもミステリの定番舞台とは大きくズレている。でも、そこには間違いなく「謎」があり、「死」があり、「それを見つめる目」がある。
この本の特異性は、トラベルミステリ的な表層を持ちつつ、中身は完全に「異文化と倫理のミステリ」だという点にある。
その土地で、その歴史と文化を背負っているからこそ生まれた必然的な殺人。
そんな重みのある動機を、どうやって読者に納得させるのか?
その仕掛けの中心にいるのが、斉木という変わった探偵だ。
斉木(さいき)という案内人
この作品を読んでいると、名探偵とは別に推理だけが仕事じゃないのだな、と思わされる。
斉木は、国際雑誌社に勤める青年。多言語話者で、何より他者のロジックをきちんと理解しようとする人物だ。
彼は事件を糾弾するために謎を解くわけではない。ましてや、鼻を利かせて犯人をあぶり出すタイプでもない。彼は「なぜそうするしかなかったのか?」を理解しようとする。
舞台がどれだけ遠くても、文化がどれだけ違っても、その土地の言葉で、その土地の常識で、真実に辿り着こうとする。その姿勢が本当に現代的で、ある種、理想的な「探偵」なのだ。
彼は謎を解く翻訳者であり、倫理の旅人である。
5つの土地、5つの謎

さて、ここからは収録された短編5本を順に簡単に紹介したい。
どれも独立した読み切りでありつつ、読了後には全体で一つのテーマに収束していくという連作構成になっている。
『砂漠を走る船の道』
デビュー作にして新人賞受賞作。サハラ砂漠を舞台にした一編。
斉木は塩を運ぶキャラバンとともに、灼熱の砂漠を横断中。水も物資も命綱となる過酷な旅のなか、キャラバンの長が死に、さらに追い打ちをかけるように殺人事件が起きる。
広大な砂漠に密室性なんてあるのか?と思いきや、生き残るためには隊から離れられないという前提が「密室」を作っている。
物理的なトリックとしてもよくできているけど、真に優れているのは「なぜそんなことをしたのか?」という動機にある。
「この殺人の奇異な点は、犯人でも凶器でもない。なぜ砂漠の只中で殺人が起こったか。その動機です」
昨夜の衝突の際に取沙法されたひとつの疑問。これが殺人であるなら、なぜ彼は容疑者が著しく限定される灼熱の砂の海で人を殺すのか。
『叫びと祈り (創元推理文庫)』59ページより引用
その理由が、日本人の常識では到底理解しづらいものであるにもかかわらず、作中で丁寧に文化背景や風土が描かれることで、納得が生まれる。
読後、「自分の常識で人を裁いてはいけない」という当たり前だけど難しいことに気づかされる。まさに旅を通して価値観が広がる体験そのものだ。
『白い巨人』
スペインのラ・マンチャ地方が舞台。ドン・キホーテを思わせる風車の伝説が謎の中心にある。
語り手はサクラ。彼にとってこの地は、過去の恋人アヤコと訪れた思い出の場所であり、彼女が突然姿を消した謎の現場でもある。
旅行に同行した斉木、ヨースケとともに、風車の伝説とアヤコ失踪の謎をめぐって推理が展開される。伝説では、兵士が風車に逃げ込んだ後に消えたという。
現代でも同じように「人が消えた」。その対比が物語に厚みを与えている。
この作品のトリックはシンプルだが、語りの構造が非常に巧妙で、認識そのものに揺さぶりをかけてくる。
サクラの語りはどこまで正確なのか?
そもそも事実とは誰の視点で語られたものなのか?──という、仕掛けも潜んでいる。
人の記憶や認識のズレ、文化的な価値観のすれ違いが生んだ悲劇。それを「謎」として見せるバランス感覚がすごい。
一見ロマンティックな装いで始まるが、ラストにかけて胸に迫る苦さと哀しみが残る作品である。
『凍れるルーシー』
舞台は南ロシアの山奥にある小さな修道院。
そこには250年前の聖人の遺体が安置されており、しかも腐敗せず〈奇跡の不朽体〉とされている。物語はその聖人の正式な列聖(聖人認定)をめぐって、外部から斉木が訪れる場面から始まる。
密室のような空間、崩されるはずのなかった信頼、そして聖人の死体という神聖な存在をめぐる思惑。いくつもの層が折り重なって、ある事件が起きる。
犯人探しというより、「誰の視点でこの状況を見ているか」によって見える景色がまったく変わる構造が面白い。そして、犯人の動機が明かされたとき、正義と狂気の境界が、信仰の中ではいかに曖昧になるかを痛感する。
宗教的な戒律が、いかに人を動かし、罪をも正当化してしまうのか。決して「異常」ではない、その倫理が本当に怖い。
『叫び』
アマゾン奥地。ジャングルの奥にある少数部族の村に訪れた斉木。しかし、その村では疫病が発生していて、人々が死に追いやられていた──というシチュエーション。
その疫病は致死率が極めて高く、発症すれば間違いなく死ぬ。そして村は外部との連絡を絶たれ、もはや隔離された終末世界と化していく。
そんななかで、殺人事件が起きる。自然死ではなく、明確な他殺として。
ここまで追い詰められた状況で、なぜ人は人を殺すのか? 疫病で死ぬのと、殺されて死ぬのと、何が違うのか?
この作品は、シリーズの中で最も生々しく、最も重く、最も読むのがしんどい。しかし、それでも最後まで目を離せないのは、人間の尊厳や倫理が極限状態でどう変化するかを描ききっているからだ。
あまりに過酷で、でもありうる話として心に残る。どこか現実のパンデミックと重なる読後感があり、「祈り」への道を開く一話でもある。
『祈り』
最後の一編は、それまでの騒がしさや緊迫感から一転し、静かな対話劇。ほぼ事件も起きない。
そして語られるのは、とあるクイズ。
「なぜゴア・ドアは祈りの洞窟と呼ばれるのか?」
この問題に斉木が答えることで、これまでの旅、出会った死、異文化での事件、すべてが一本の糸で繋がっていくような構成になっている。
殺人の連作であったはずのこの本が、最後の一編で赦しや祈りというテーマに到達する。その変化が、とても自然で、しかし感動的だ。
タイトルの『叫び』と『祈り』が、この最終話でぴったり繋がるのが見事。派手なトリックはないけれど、心に残る余韻がすごい。
「なぜ」がすべてを変えるとき

『叫びと祈り』は、トリックやどんでん返しで驚かせるミステリではない。けれど、読み終えたときには確実に「考えさせられた」という重みが残る。
特に、「なぜそんなことをしたのか?」という謎(ホワイダニット)に対するアプローチは、他のどのミステリともまったく違う種類の鋭さを持っている。
多くの本格ミステリでは、動機は物語の最後に添えられる味付けのようなものとして扱われがちだ。財産、嫉妬、復讐、正義。いわば物語を閉じるための鍵だ。
でも本作では、むしろ動機が物語そのものを駆動している。「誰が」「どうやって」ではなく、「なぜ?」という動機にこそ心を持っていかれるのだ。
そしてその答えが、私たちの常識とは根本的に異なる論理で語られたとき──たとえば、信仰、儀式、風習、生存のルール──一瞬たじろぎながらも、「それでも、そうするしかなかったのかもしれない」と思わせられてしまう。この納得の構造がすごいのだ。
つまりこれは、殺人事件を使って異文化を描く物語であり、それと同時に、異文化を描くために殺人事件が必要だった物語でもある。
「その文化では、それが当たり前だった」
そう聞くと、一瞬反発を覚える。でも、斉木と一緒に歩いて、その土地の空気を吸って、風土や歴史を目の当たりにしているうちに、少しずつその価値観が肌に染み込んでくる。そして気づけば、自分の中にあった当然という基準が揺らいでいるのだ。
謎を解くことが、誰かを理解することになる。この構造が、読書体験そのものを拡張している。推理というロジックの道筋が、異文化理解という冒険と完全に一致しているという点で、本作はものすごく現代的なミステリだと思う。
しかも、それをきちんとジャンル小説としてやってのけている。論理の整合性、構成の緻密さ、トリックの切れ味、すべてが高いレベルでまとまっていて、どれかに偏ることがない。
だからこそ、読みごたえがあり、読み終えてからも長く残る。
何年か経って、ふと読み返したくなる。そんな本だ。
ミステリ好きなら読まない理由がないし、逆に「ミステリはあんまり読まないんだよね」という人にも薦めたくなる。
だって、物語の力で世界を見せてくれるのだから。
『叫びと祈り』は、ミステリの名を借りた異文化との対話録であり、倫理という名の迷路への地図でもある。
そして、旅はまだ終わらない。