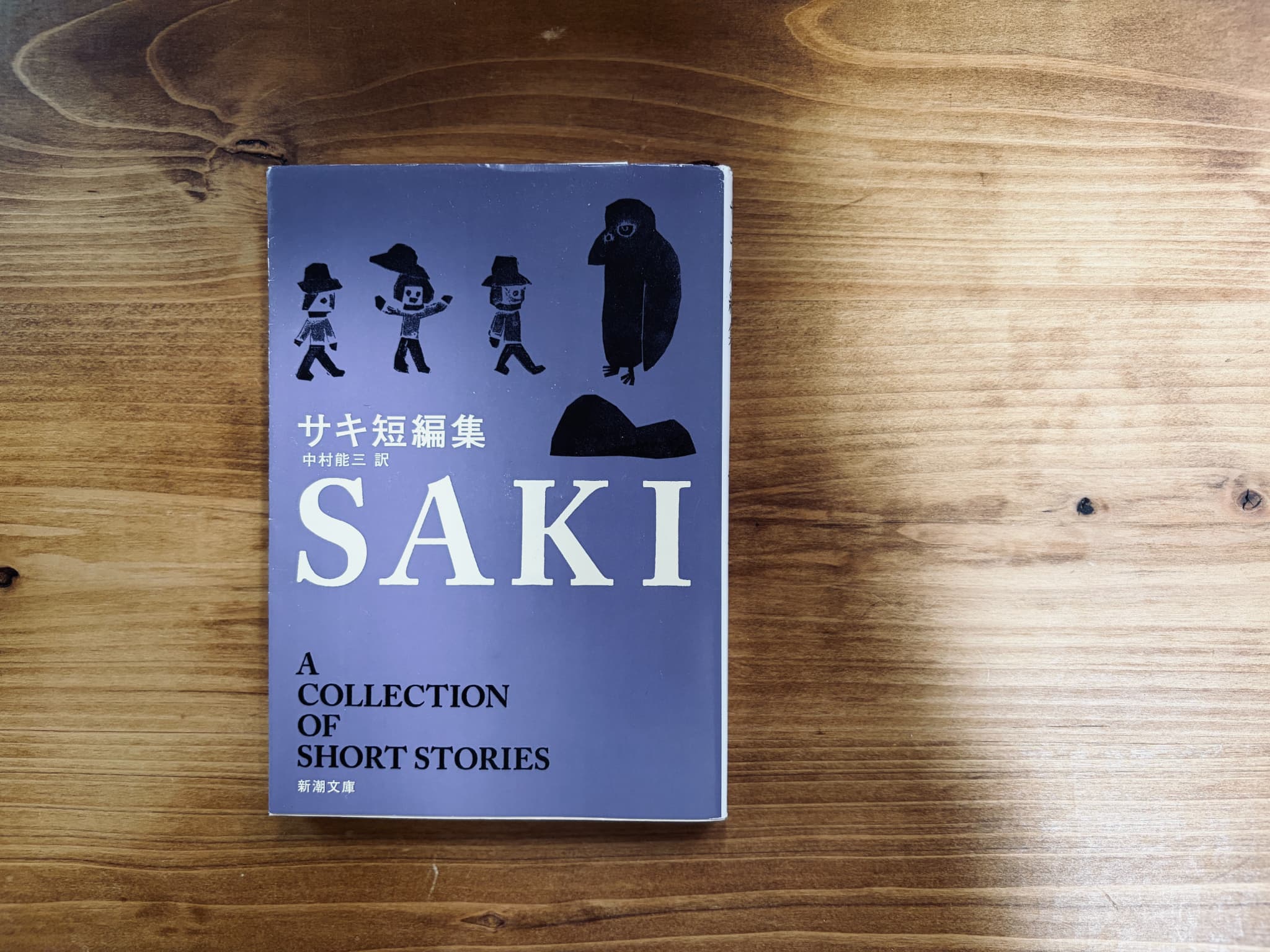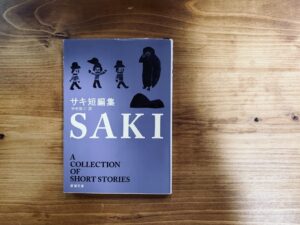怪奇と倒錯の短編ばかりを詰め込んだ、江戸川乱歩の「これぞ変格乱歩のフルコース」とも言える一冊がある。
それが、『人間椅子 江戸川乱歩ベストセレクション(1)』。
収録されているのは、探偵の推理が光る明智小五郎ものではない。怪奇、倒錯、異常心理、視覚と触覚の暴走……。そんな乱歩の裏メニューばかりを並べた一冊である。
読むたびに、現実感が少しずつ失われていく。目の前の椅子が、鏡が、長持が、なんだか不穏なものに見えてくる。
この短編集が持つ濃度は、並のミステリとはまるで別種の魔力だ。
収録作の並びに仕掛けあり

収録作は以下の8編。
- 『人間椅子』
- 『目羅博士の不思議な犯罪』
- 『断崖』
- 『妻に失恋した男』
- 『お勢登場』
- 『二癈人』
- 『鏡地獄』
- 『押絵と旅する男』
トリックを解くためのパズルではなく、読む人の感覚そのものを揺るがすような物語ばかりだ。
構成順にも意味がある。
最初は触覚の侵犯(『人間椅子』)、次に視覚のトリック(『目羅博士』)、そして心理のズレや記憶の混乱(『断崖』『二癈人』)を経て、最後は幻想の異界(『押絵と旅する男』)へ。
まるで五感と現実認識を、段階的に壊していくみたいな体験だ。読んでいて狂気に近づいていく実感があるのに、不思議と心地よい。この倒錯的な快楽こそ、乱歩文学の真骨頂。
感覚をめぐる乱歩の地獄
ここで、私が特に好きな5作品を簡単にご紹介。
1.『人間椅子』 革の下に潜む異物感
乱歩短編と言えば『人間椅子』でしょ、というくらいの傑作。
簡単に言うと、椅子の中に潜む職人が、毎日貴婦人の体温と匂いと重みにうっとりしている話だ。
冷静に考えてめちゃくちゃホラーなのだが、本人はとても幸せそうで困る。しかも本人は、これは愛ですと本気で言ってくる。
視覚が使えない代わりに、触覚が異常に研ぎ澄まされてて、そこがまた生々しくて怖い。階級差と欲望の構造をひっくり返してるのも見事。
革一枚の距離。それはゼロ距離でありながら、永遠に届かない絶対的断絶でもある。
視線ではなく、圧力・温度・匂いで誰かを愛するという発想。乱歩の想像力の異常な方向性に痺れる。
2.『断崖』 会話だけで人は落ちる
男女ふたりが断崖に並んで座り、語り合うだけの物語。でもその会話が、ズレていく。歯車の噛み合わせが狂ったように、言葉が空回りし、裏切りの兆しが浮かび上がる。
登場人物の数も、舞台も、セリフ以外の情報も極限まで削ぎ落としたうえで、ここまでの緊張を与える。ミニマリズムの極みともいえるこの作品は、乱歩の筆致がいかに心理の罠を描くことに長けているかを教えてくれる。
3.『お勢登場』 悪女は即興で殺す
タイトル通りのお勢という女の登場が、すべてを変える。偶然にも夫が長持の中に閉じ込められているのを見つけたお勢は、あろうことかそれを利用して「完全犯罪」を思いついてしまう。
恐ろしいのは、この女性の計画性のなさだ。全ては偶然なのに、彼女の判断力と残酷さがそれを殺人へと導く。倫理をすっ飛ばしてサバイブするこのキャラは、ある意味では現代的ですらある。
4.『鏡地獄』 鏡に魅入られた男の末路
この話の異常さは別格だ。
幼少期の頃から、光の反射や屈折に心奪われた男。彼はただ、自分という存在をあらゆる角度から、余すところなく眺めてみたかっただけなのかもしれない。
けれど、その純粋すぎる好奇心はやがて、彼を奇妙な実験へと駆り立てる。彼が最後にたどり着いたのは……。
この結果は、ナルシシズムが暴走した果ての狂気としか言いようがない。ここにはもはや恐怖やエロスを超えた、感覚の極限がある。
自己と世界の境界が曖昧になる瞬間を、これほどまでに鋭く描いた短編がほかにあるだろうか。
5.『押絵と旅する男』 「あちら側」へ行ってしまった男の、哀しくて美しい幻想譚
乱歩といえばグロテスクで不気味な話を思い浮かべるかもしれないが、この『押絵と旅する男』は少し違う。怖さよりも美しさと哀しさが残る、幻想色の濃い短編である。
舞台は、蜃気楼の町・魚津から帰る途中の汽車の中。「私」は、一枚の押絵を大切そうに抱えた老人と出会う。その絵に描かれていた少女と老人は、まるで生きているかのようで、しかもその老人は、目の前の人物と瓜二つだった──。
語られるのは、かつて浅草十二階の展望台から望遠鏡で誰かを見つめ続けた男の物語。現実の手触りから逃れ、視覚だけの理想へと溺れていくその姿は、どこか現代の「推し活」にも重なる。絵の中の彼女は老いず、汚れず、永遠に完璧なままだ。
たった数十ページなのに、読後の余韻はずっと残る。ふとした瞬間に、あの押絵の視線が、またこちらを見ているような気さえしてくる。
大槻ケンヂによる現代的な解説
この巻のもう一つの魅力は、巻末に収録された大槻ケンヂ氏の解説だ。彼は乱歩の耽美・倒錯・妄想といった要素を、サブカルやオタク文化のルーツとして語っている。
たとえば『押絵と旅する男』で描かれる「2次元の絵の中へ入っていく」願望は、まさに推しの世界に行きたいという現代オタクの感覚そのものだ。
乱歩の作品に登場する変質者たちは、たしかに現代に生きる我々の「偏愛」や「感覚の歪み」とも通じている。
つまりこれは、ただの古典ではない。むしろ現代にこそ響く倒錯の原点として、再発見される文学なのだ。
この椅子に座るのは、あなた自身
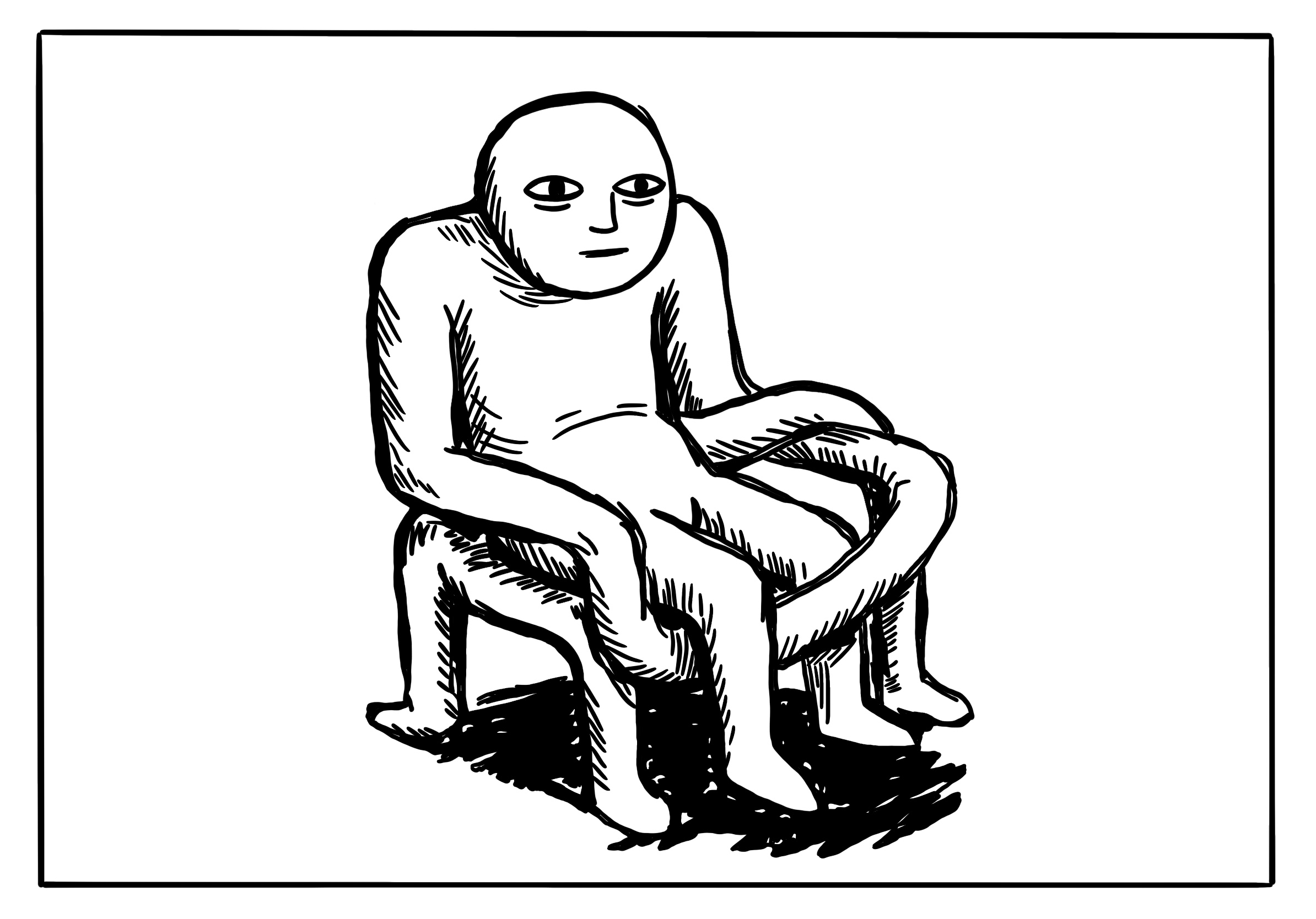
イラスト:四季しおり
この短編集は、乱歩入門としても、乱歩沼への深みとしても完璧な構成をしている。収録作の選び方、並び順、そして巻末の大槻ケンヂ氏による解説まで、すべてが「乱歩の本質はここにある」と語りかけてくる。
探偵も事件もいらない。ここにあるのは、欲望と感覚の迷宮である。
「見る」「触れる」「隠れる」「覗く」といった身体的な行為を通じて、私たちの知覚そのものが揺さぶられる。感覚を信じられなくなること、それこそが乱歩的な恐怖であり快楽なのだ。
たとえば椅子に座るとき。鏡を覗くとき。ふとした瞬間に、背中に何かの気配を感じたり、鏡の中の自分の目線が一瞬だけズレたように思えることがある。乱歩の物語を読むと、そんな違和感が現実の中に忍び寄ってくる。なにげない日常の風景が、ほんの少し異質なものに変わって見えるのだ。
それは決して、恐怖小説を読んだあとのような単純な戦慄ではない。もっと静かで、長く尾を引く、世界がほんのわずかに軋んだ感触である。
乱歩の怪奇は、外から襲いかかってくるものではなく、もともと自分の内側にあったものを引きずり出してくる。その意味で、『人間椅子』の椅子の中に潜んでいたのは、ただの職人ではない。自分自身の奥底にある、誰にも知られたくない欲望や孤独、逸脱の願望そのものなのだ。
この一冊を読み終えたとき、あなたの感覚はすでに変容しているかもしれない。乱歩が仕掛けた異界へのチューニングが完了し、世界が以前より少しだけ違って見える。
椅子に腰かけたとき、鏡をのぞいたとき、すれ違った誰かの視線に、ふと不穏なざわめきを感じたら──それこそが、乱歩の魔法が効いている証である。
異界はどこか遠くにあるものではない。
それは、あなたがいま座っているその椅子の内側に、すでに静かに息をひそめている。