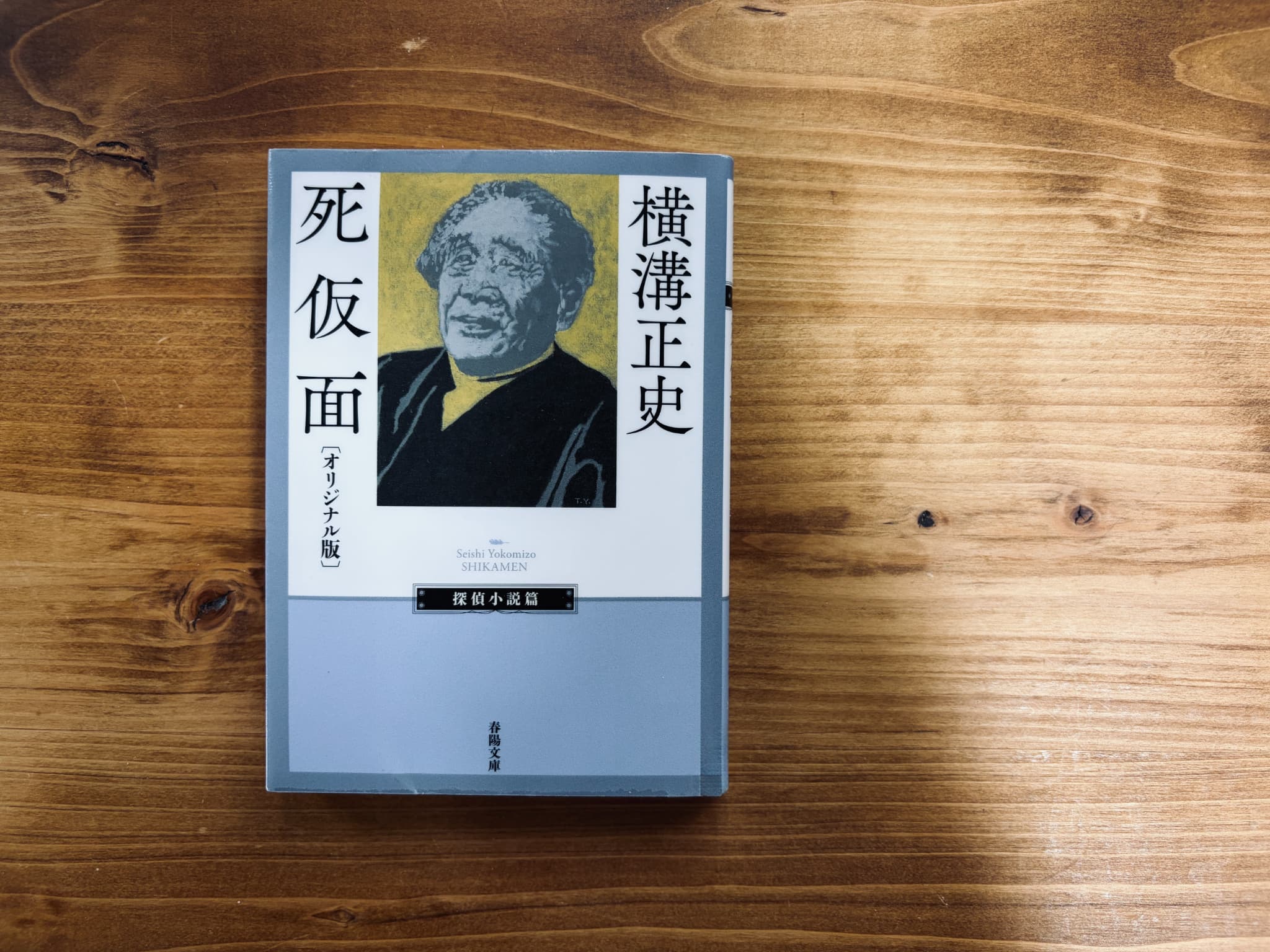「なぜポーは、たった3本でデュパン終わらせたのか?」
ミステリ好きなら一度は疑問に思ったことがあると思う。
探偵小説の元祖、エドガー・アラン・ポー。あの『モルグ街の殺人』で世界初の名探偵オーギュスト・デュパンを登場させた伝説の作家だ。
しかし彼は、そのデュパンをたった3作で放り出してしまった。普通に考えたら、そこからシリーズ化してがっつり稼げそうなものなのに、なぜ?
この「なぜ?」に正面から挑んだのが、本書『謎ときエドガー・アラン・ポー』(竹内康浩 著)である。
副題がすごい。「知られざる未解決殺人事件」。評論本でそんな煽り文句アリかと思ったが、読み進めるうちにわかる。これはただの文学解釈本じゃない。むしろ、文学そのものを事件として再調査する、完全に探偵小説の構造そのものだと気づいた。
特に焦点になるのが、ポーのあまり有名ではない短編『犯人はお前だ』。四十歳という若さで人生を終えたポーが死ぬ前に書いた「最後の推理小説」。
今までパロディ小説だと思われていたこの作品を、「これはもしかして、ガチで誰か殺されてる話じゃないか?」と読み直して、200年間気づかれなかった犯人を暴こうというのが、この本の真骨頂。面白すぎるだろ。
文学探偵・竹内康浩とは何者か?

まず、「この本を書いた人は、どんなヤバい人なのか?」と思ったので調べた。
竹内康浩。東大院卒、現在は北海道大学の文学研究院教授。専門はアメリカ文学、特に探偵小説とエドガー・アラン・ポー。なるほど、筋金入りのポーガチ勢である。
それだけではない。前作『謎ときサリンジャー』では小林秀雄賞を受賞。さらに英語で書いた『Mark X』という本では、アメリカ探偵作家クラブが選ぶ「エドガー賞」の評論部門で最終候補になったというから驚きである。
あのポーの名を冠した賞に、日本人で候補入りなんて、もはやマンガのキャラ設定みたいだ。
そんな彼が今回、満を持してポー本人を捜査対象に選んだというわけである。もう、実績的にも物語的にも完璧な布陣。これは否が応でも期待が高まる。
ちなみにこの人は、いわゆる「陰謀論系の謎とき屋さん」ではまったくない。むしろ真逆。テキストを徹底的に読んで、論理的に読み解く分析屋だ。
本の中でも「アナロジー(類推)じゃなくて、アナリシス(分析)をしようぜ」と主張していて、その姿勢がめちゃくちゃ清々しい。
信頼できない語り手のインパクト
され、ここからが本題である。
竹内氏が本書で取り上げるのは、ポーの短編『Thou Art the Man(犯人はお前だ)』。
従来、この物語は、死体を腹話術で操って真犯人に告発させるという荒唐無稽な展開から、パロディとされてきた。
実際、ポーのなかでもあまり評価が高くなくて、「なんかヘンテコな推理もどきのギャグ小説でしょ」なんて扱われてきた。
でも著者はここでまさかの反転をかける。
「この作品、実はめっちゃ計算された密室トリックなんじゃないの?」という視点で読み直していく。
そして、最大のポイントが「語り手(=主人公)」にある。この語り手、いかにも名探偵っぽく振る舞っているが、語っている内容をよく見ると、いろんなところにおかしな点が出てくるのだ。
その語りに潜む「矛盾」や「違和感」を精密に精読することで、語り手自身に疑惑の目が向けられ、「こいつが犯人なのでは?」という驚きの仮説が提示される。これには、鳥肌が立った。
この構造は、まさにクリスティの『アクロイド殺し』の80年前版。というか、もしこの解釈が正しければ、ポーはクリスティよりずっと早くに「あの禁じ手」をやってのけていたことになる。
『アクロイド殺し』の発表よりも80年早く、あれをポーがすでにやっていたとしたら……?
まさに「文学史の逆転ホームラン」だ。
「評論」のふりした超参加型ミステリ
そして本書がただの評論集で終わっていないのは、読者がちゃんと「捜査に参加」できる構造になっている点だ。
冒頭に『犯人はお前だ』の全文訳が載っている。これをまず読んで、自分の目で現場(=テキスト)を確認しろというスタイルだ。
つまり自分もいつの間にか、もうひとりのデュパンになっている。そこから、竹内氏による再捜査の章に進んでいくと、徐々に視界が変わってくるのだ。
「さっき読んだあの場面は、そういう意味だったのか?」みたいな発見が次々に押し寄せてきて、自然とページをめくる手が止まらなくなる。
構成も「第一章 挑発」「第二章 矛盾」「第三章 未解決殺人事件」……と、完全にミステリの構造。もはやこれは、文学評論の皮をかぶった変則推理小説と言っていい。
そして最終的に見えてくるのが、「ポーはなぜ探偵小説をやめたのか?」という問いの答えだ。
誰にも気づいてもらえなかった挑戦、理解されず笑いものにされた真剣な試み──それに絶望して、筆を折ったとしたら? あまりに寂しいが、なんだかすごく人間くさい話でもある。
しかし、200年経ってようやくその仕掛けに気づいて、丁寧に読み直してくれた人がいた。そう考えると、感動的でもあるし、ポーもちょっとは報われたんじゃないか……そんな風に思えてくる。
『謎ときエドガー・アラン・ポー』は、まさに「読む」という行為そのものがスリルになる、珍しくて面白い一冊だった。
ミステリ好き、文学好き、分析好き、ポー好き、みんなに手に取ってほしいと、素直に思う。
この本は、ポーから私たちへの挑戦状であり、竹内康浩という文学探偵からの、共犯者への招待状である。