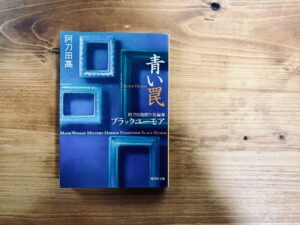恐ろしいミステリを読んでしまった。
読み終えた今も、頭の中が霧に包まれた北関東の山奥から帰ってこれないでいる。
折原一、御年74歳。
叙述トリックの巨匠が、そのキャリアのすべてを叩きつけたかのような超大作『六つ首村』。
572ページというボリュームに、読む前から悦びの吐息を漏らしてしまうわけだけれど、中身はそれ以上に重厚で、そしてあまりにも意地が悪かった。
昭和の亡霊と村が放つ抗いがたい魔力

まず言わせてほしい。
この『六つ首村』というタイトル、そして「横溝正史に捧ぐ」という直球すぎるキャッチコピー。これだけでご飯が進む。
ミステリ好きにとって「村」という空間は、もはや聖域だ。因習、閉鎖性、名家の家督争い、そして過去の惨劇……。
横溝正史が耕し、金田一耕助が駆け抜けたあの「おどろおどろしい世界観」が、令和の現代に、折原一という最高級のフィルターを通して再現される。これに興奮しない人がいるだろうか?
物語の幕開けは、まさに王道中の王道だ。フリーライターの笹村克哉のもとに、見知らぬ義理の姉を名乗る女性が現れ、彼が実は北関東の奥地にある「六つ首村」の名家・白兼家の跡取り候補であることを告げる。
はい出ました、出生の秘密。自分が何者かを知るために呪われた地へと向かう主人公。これぞ『八つ墓村』の寺田辰弥であり、私らが愛してやまない来訪者の物語だ。
しかし、折原一がただの懐古趣味で終わるはずがない。572ページという分量は、単なる描写の積み重ねではなく、読者を迷わせるための距離として機能している。
つまりこの長い物語のどこかに致命的な嘘が隠されている、という作者からの挑戦状だ。
虚構が現実を侵食する、悪夢のような再現ドラマ
本作を唯一無二の傑作に押し上げているのは、中盤から本格化する「再現ドラマ」というメタフィクションの手法だ。これがもう、本当にタチが悪い。
村では30年前に「六つ首村連続殺人事件」という凄惨な事件が起きていて、犯人とされる六彦は今も行方不明。そして現在、その事件をドラマ化するプロジェクトが進行している。
ここからが折原マジックの本領発揮。テキストの中に「再現ドラマの脚本」が挿入され、ト書きと台詞が混じり合い、さらには撮影現場の裏側までが描かれる。
読んでいくうちに、混乱の渦に巻き込まれる。
「いま読んでいるのは、30年前の真実なのか?」
「それとも撮影中の演技なのか?」
「あるいは、現在進行形で起きている新たな殺人なのか?」
このレイヤーの重なりが、あまりにも巧妙なのだ。
特に「復讐劇場」という言葉が示す通り、犯人はこのドラマという舞台装置を、自らの殺人のカモフラージュとして利用してくる。悲鳴が聞こえても「ああ、いい演技だ」とスルーされ、転がっている死体を精巧な小道具だと思い込む。
この「虚構と現実の境界線が溶解していく感覚」は、折原一ならでは。笹村克哉の視点を通して事件を追っているはずなのに、いつの間にか自分自身がカメラのファインダー越しに世界を覗いているような、奇妙な疎外感と不安が常にあった。
顔のない死体と、ロジックが暴くアイデンティティの迷宮
さて、本格ミステリーとしてのガジェットについても語らなければならない。本作のキーワードは、タイトルにもある「首」だ。
伝説によれば、かつてこの地では六人の旅人が首を斬られて殺されたという。そして30年前の事件でも、現在進行形の事件でも、この「首なし」というモチーフが繰り返される。
ミステリにおける「顔のない死体」の機能は、言うまでもなく「個人の特定不可能性」だ。
誰が死んだのか、あるいは誰が生き残っているのか。この匿名性が、入れ替わりや一人二役といったトリックの温床になるのは常識だけれど、本作の捻りは一味違う。
引きこもりの現当主・夢男というキャラクターが、その不気味さを加速させる。誰も姿を見たことがない主。彼は本当に実在するのか? あるいは、消えた犯人・六彦の変り果てた姿なのか?
さらに、物語には「密室」や「瞬間移動」といった不可能性まで出てくる。これらが超常現象ではなく、あくまで論理的な解決を見るという信頼感。それが折原作品の根底にある。
特に「瞬間移動」の謎。双子説、抜け穴説、あるいは叙述トリックによる時間の錯誤……。ページをめくりながら脳内で推理を組み立てる快感。
でも、折原一は読者の思考の裏をかく天才だ。わかったかもしれない!と思った瞬間に、足元の床が抜け落ちるような感覚を何度も体験させてくれる。
騙される快感、そして村ミステリの到達点
電子雑誌『ジャーロ』での長期連載を経て、一冊に纏め上げられたこの『六つ首村』。
連載特有の引きの強さが、単行本化されたことで怒涛のドライブ感に変わっている。正直、一気読みするにはかなりの体力が必要だけれど、それ以上に読んで良かったと思えた。
なぜ、こんなにも騙されることを求めてしまうのだろう。 それは、折原一が描く「嘘」が、単なるパズルのピースではなく、人間の業や、記憶の曖昧さ、そして「悲劇さえもエンタメとして消費してしまう現代社会の歪み」を鋭く切り取っているからだと思う。
30年前の怨念が、現代のメディアという装置を借りて、再び村を血に染める。その結末が提示する景色は、決して明るいものではない。けれど、すべてのパズルがパチリと音を立てて嵌まった時、そこにはミステリーというジャンルだけが到達できる残酷で美しい真実が浮かび上がる。
一度目の読書で、私は物語の「表」を歩かされていたに過ぎなかった。二度目の読書でようやく、その裏側に張り巡らされた膨大な伏線と、巨匠が仕掛けた悪意に満ちた、そして最高に知的な罠の全貌が姿を現す。
この徹底的な敗北感と、それゆえの充足感。
この心地よい混乱の中に、もう少しだけ留まっていたいと思う。