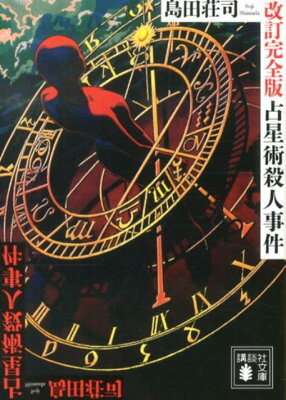島田荘司の『御手洗潔シリーズ』は、正直どれもめちゃくちゃ面白い。
傑作も名作もそろっているし、どこから読んでもある程度は楽しめる。
……でも、結論から言ってしまうと、まず読むべきは『占星術殺人事件』から『御手洗潔のメロディ』までの初期作だ。しかもこの範囲に関しては、絶対に順番通りに読むのが正解。ここを飛ばすと、かなり損をする。
というのも、このシリーズ、ただの一話完結型のミステリじゃない。
天才探偵・御手洗潔と、その相棒・石岡和己のコンビの関係性は、作品ごとに少しずつ変化していく。さらには、過去の事件との繋がりとか、伏線の回収とか、シリーズ全体を貫くある大きな構造まで用意されている。
つまり、発表順で追ってこそ、ちゃんと味わえるようにできてるのだ。
たとえば、『占星術殺人事件』では、いきなり超常現象まがいのバラバラ殺人に挑むという衝撃のデビューを飾るのだけど、ここからどんどんスケールが広がっていく。
科学、歴史、心理学、神話、陰謀論……気づけばミステリを超えた知的エンタメの迷宮に迷い込んでる感じだ。でも、それが成立してるのは、御手洗と石岡という二人の軸がちゃんと存在しているからだ。
あと地味に重要なのが、読者への挑戦状が入っていたり、古典ミステリへのオマージュが散りばめられてたりするところ。このへんは時系列を飛ばして読むと「ん?これってどういう意味?」となってしまうので、やっぱり順番通りがいい。
というわけで、これから御手洗潔シリーズを読むつもりなら、まずは『占星術殺人事件』から『御手洗潔のメロディ』まで。
順番守って読めば、その面白さが倍増するし、終わる頃にはきっとシリーズ全部読みたくなっていると思う。
順番リストと見どころも、続けてまとめておくので、気になる人はそっちもぜひチェックしてみて!
1番目.『占星術殺人事件』
戦慄の御手洗初登場作
昭和初期、日本を震撼させた未解決の猟奇殺人事件があった。それは、高名な画家・梅沢平吉が自宅アトリエという密室で殺害されたことから始まる。
彼の傍らには、恐るべき計画を記した手記が遺されていた。その内容は、占星術の知識を駆使し、六人の若い女性たちの身体の一部を切り取り、それらを合成して完璧な人間「アゾート」を創造するという、常軌を逸したものであった。
手記には、彼の六人の娘たちを含む処女たちの、どの部分を「アゾート」のために使うかまで詳細に記されていたのだ。
平吉の死後、その手記に予言されたかのように、彼の娘を含む六人の若い女性が次々と行方不明となり、やがて日本各地で、それぞれ身体の一部を無残に奪われた姿で発見される。
この奇怪な「アゾート殺人事件」は、戦中戦後の混乱の中で捜査が難航し、解決の糸口すら見えないまま四十数年の歳月が流れた。
そして現代、天才占星術師にして名探偵の御手洗潔が、相棒の石岡和己と共に、この迷宮入りした怪事件の真相究明に挑むのであった。
異常犯罪と名探偵の衝突
『占星術殺人事件』は、島田荘司がぶちかましたデビュー作であり、名探偵・御手洗潔の初登場作でもある。
もうこの1冊で、日本の本格ミステリの歴史が一段階進んだと言っても過言じゃない。
なによりすごいのが、その発想力とトリックのぶっ飛び具合だ。
読み終わったときに残るのは「なるほど」じゃなくて、「マジで!?」という静かな衝撃。しかもその驚きがちゃんと筋の通った論理で支えられてるから、なおさら印象に残るのだ。
冒頭には、気味の悪い画家が残した手記が登場。この文章がまあ長くて難解で、読むのに少し気力がいる。でも、ここがめちゃくちゃ大事なポイントになっていて、読み返したときにゾッとするような仕掛けが潜んでいるのだ。
占星術とか秘教とか、なんか怪しい雰囲気がずっと漂っていて、最初はホラーミステリかと思う人もいるかもしれない。でも、実際にはものすごく緻密に作られた超ロジカルなトリック小説だ。
しかも、事件の真相が明かされるのは、なんと40年以上経ってから。それでも読者をちゃんと納得させられるだけの理屈と説得力があるのは、本当にすごいことだと思う。
この謎を解くのが、例の天才・御手洗潔。占星術師って肩書きのクセに、やってることは完全に論理の鬼。性格は少し変だが、その頭のキレ方は尋常じゃない。
で、そんな彼を語るのが相棒の石岡和己。この石岡くんがまたいいやつで、御手洗の変人ぶりをうまく中和してくれる。二人の掛け合いにはちょっとしたユーモアもあって、重たい事件の中でホッとできる瞬間があるのも嬉しいところだ。
もちろん、この作品の魅力はトリックだけじゃない。事件の背景にあるのは、人間のどうしようもない悲しさや孤独だったりする。最後に見えてくるのは、論理じゃ割り切れない感情の重さだ。
だからこそ、『占星術殺人事件』はただの謎解き小説じゃなくて、ちゃんと心に残る物語になっている。
読み終えたあと、誰かに語りたくなる。
あの驚きも、あの仕掛けも、あの悲しさも、全部含めて「すごかった」と言いたくなる。
星と血で描かれたこの一冊。
ミステリ好きなら、絶対に通っておきたい名作中の名作だ。
2番目.『斜め屋敷の犯罪』
物語の舞台は、北海道宗谷岬の高台に異様な姿で建つ西洋館「流氷館」。その名の通り、館全体が意図的に斜めに傾けて建てられた奇妙な建築物である。
館の主である浜本幸三郎が主催するクリスマス・パーティの夜、最初の惨劇は起こる。招待客の一人が、密室状態の客室で死体となって発見されたのだ。外部からの侵入は不可能、犯人は館内にいる招待客か使用人の誰かに違いない。
そんな中、まるで嘲笑うかのように第二、第三の殺人が、いずれも不可解な密室状況下で発生する。
気味の悪い表情をした招かれざる男の目撃譚や、夜中に響く謎の吠え声、3階の窓から覗く人影など、怪現象も頻発し、館は恐怖と混乱に包まれる。
地元の警察官も捜査に加わるが、事件はますます混迷を深めていく。この連続密室殺人の謎を解き明かすべく、名探偵・御手洗潔が雪深い北の館へと乗り込むのであった。
傾いた館で繰り広げられる本格密室劇
『斜め屋敷の犯罪』は、島田荘司による御手洗潔シリーズの2作目。
これは、いわゆる変な建物ミステリの中でも、かなり異常なレベルのやつだ。
舞台は北海道の離島にある「流氷館」。この館は、わざと傾けて建てられている。冗談じゃなくて本当にナナメ。床も壁も、ドアも天井も全部ゆがんでいる。
で、そんな場所で密室殺人が次々に起きる。どう考えても普通じゃない。
読者としては、最初は「なんだこの変な館?」くらいのテンションで読み始めるのだが、読み進めるうちに、こっちの認識もだんだんおかしくなってくる。斜めの空間で起こる事件、斜めの証言、斜めの視界。読んでる自分の思考までズレてくるのがすごい。
本作が面白いのは、このナナメがトリックの核になってるところだ。ただ奇抜な舞台設定ってわけじゃなくて、建物の構造そのものがミステリの一部としてガッチリ噛み合っている。
事件が起きるたびに間取り図を見返すハメになるし、「あれ?ここってどっちに傾いてたっけ?」みたいな感じで、こっちも自然と捜査に参加させられる。読むというより、巻き込まれるに近い。
そして、事件現場はもちろん密室。しかも一筋縄ではいかない。雪、足跡、施錠、死体。ありとあらゆる「不可能」が、斜めの世界で襲いかかってくる。
登場人物たちもみんな個性的で、それぞれに怪しい。密室の外でも心理戦が進行してて、誰が信用できるのかさっぱりわからない。
そんな中、満を持して登場するのが名探偵・御手洗潔だ。しかも登場は中盤以降。それまで混沌としていた空気が、一気に引き締まる。
御手洗の推理は、まるで水平器だ。傾いた空間に、真っすぐなラインを一本通すように、歪んだ状況を論理で整えていく。これが最高に気持ちいいのだ。
終盤に明かされるトリックは、かなりド派手。でもやりすぎ感は不思議とない。あくまでちゃんとロジックで組み上げられていて、「そう来たか!」と納得できるのだ。しかもちゃんと驚ける。
この驚きと納得を両立させてくるのが、島田荘司のすごいところだ。
『斜め屋敷の犯罪』は、建築と密室トリックをここまで融合させた物理系ミステリの金字塔。
本格派にも、変な屋敷フェチにも、問答無用でおすすめしたい。
3番目.『御手洗潔の挨拶』
さて、ここで短編集をはさもう。
『御手洗潔の挨拶』は、名探偵・御手洗潔が挑む四つの事件を収録した、シリーズ初の短編集。各編で御手洗は、その天才的な推理力と奇抜な発想を遺憾なく発揮し、常人には思いもよらない方法で難事件を解決へと導く。
表題作とも言える「疾走する死者」では、嵐の夜、マンションの11階から姿を消した男が、わずか13分後に遠く離れた場所で走行中の電車に飛び込み死亡するという奇怪な事件が発生する。男の首には絞殺の痕跡があり、全力疾走しても不可能な移動距離の謎が警察を悩ませる。
「数字錠」では、ある少年が関わる事件を通じて、御手洗の意外な優しさや人間味あふれる一面が描かれる。その他、「紫電改研究保存会」ではユーモラスな詐欺事件の顛末が、「ギリシャの犬」では誘拐事件と犬を巡る謎が展開される。
いずれの事件も、奇想天外なトリックと鮮やかな解決が特徴であり、御手洗潔という探偵の多面的な魅力を存分に伝える内容となっている。
多彩なトリックと人間味に満ちた短編集
『御手洗潔の挨拶』は、名探偵・御手洗潔が活躍する短編を四本収録した、シリーズ初の短編集だ。
どの作品もバラエティに富んでいて、重たいのもあれば軽快なものもある。でも共通しているのは、「ああ、御手洗ってこういう人だったんだな」という発見に満ちてることだ。事件よりも、むしろ御手洗という人物をじっくり味わえる構成になっている。
最初の一編『数字錠』は、シリーズの原点とも言える話。ある出来事がきっかけで、御手洗と石岡が出会い、後にコンビを組むことになるのだが、その関係性の芽が静かに描かれている。
事件自体は、ある女性の不可解な死をめぐるもので、いわゆる派手さはない。でも、その陰にある感情の揺れがじわりと効いてくる。御手洗の推理はいつも通りキレッキレだが、どこか「人間の痛み」に寄り添っているような柔らかさが感じられて、読み終わった後に心に残るのだ。
続く『疾走する死者』は一転して、トリッキーで不可能犯罪感満載。島田ミステリの真骨頂とも言うべき、空間と時間の常識を覆す大胆な発想が炸裂する。
一室から忽然と姿を消した被害者が、あり得ないほど遠くで発見されるという不可能状況。この設定がもう既にワクワクさせてくるし、「どうやったらそんなことできるんだよ!」という感じだ。
それを御手洗が論理で切り崩していく流れは、まさに島田ミステリ。読者への挑戦状もついてて、ガチで頭を使いたい人にはたまらない一編だ。
三本目の『紫電改研究保存会』は、ちょっとユーモラスで肩の力を抜いて読める作品だ。変な人たちが変なことを言ってると思ったら、ちゃんと事件の核に繋がってるという、島田流おとぼけ×本格が炸裂している。笑ってたはずが、最後には「おお、そうきたか」と唸らされる。この緩急のつけ方、やっぱり上手い。
最後の『ギリシャの犬』は、都会の地理をトリックに使った異色作だ。誘拐事件のはずが、犬が絡んできて話が妙な方向にズレていく。でもそのズレがちゃんと意味を持っていて、最後にはきっちり納得できる結末に着地するのがすごい。
あと、御手洗が実は犬好きだったっていう描写も地味に良くて、天才探偵の意外な顔にふと癒されたりもする。
そんな感じで、『御手洗潔の挨拶』は、御手洗シリーズの入門としてもバッチリだし、既読組にも「そうそう、こういう御手洗が好きなんだよなあ」と再確認させてくれる短編集だ。
長編とは違うスピード感で人間・御手洗潔にぐっと迫れるし、シリーズを通して読む前の前菜としても、ちょっとしたつまみ食いにも最適。
変幻自在な名探偵の魅力を、ぜひこの短編集で味わってみてほしい。
4番目.『異邦の騎士』
昭和五十年代の東京。ある日、公園のベンチで目覚めた男は、自分の名前も過去も、一切の記憶を失っていた。
途方に暮れる彼に声をかけたのは、偶然通りかかった若い女性・良子であった。行くあてのない男は、彼女の優しさに導かれるように同棲生活を始める。
やがて、男は一枚の運転免許証から、自分の名前が「益子秀司」であること、そしてかつての住所を知る。
しかし、良子との穏やかで幸せな日々に安らぎを見出していた益子は、過去を取り戻すことに躊躇いを覚えていた。そんな中、益子は近所に住む風変わりな占星術師・御手洗潔と知り合い、親交を深めていく。
だが、ある時手にした一冊の日記帳が、彼の運命を大きく揺るがす。そこには、自分がかつて愛する妻子を死に追いやったのではないかという、戦慄すべき過去が記されていたのだ。
絶望と自己嫌悪に苛まれ、破滅へと向かう益子。果たして、彼に仕組まれた罠とは何なのか。
そして、御手洗潔は彼を救うことができるのであろうか。
若き御手洗潔の人間賛歌
『異邦の騎士』は、御手洗潔シリーズの中でもかなり異色の立ち位置にある。
トリック満載の推理モノというよりは、もう少し奥に踏み込んでくるタイプの作品だ。テーマは、記憶、罪、そして愛。とくれば、ただの事件解決で終わる話じゃないのはわかると思う。
物語の中心にいるのは、過去の記憶を失ってしまった男・益子。自分が誰なのかもわからずにぼんやり生きていた彼の前に、良子という女性が現れる。この出会いが、物語を大きく動かしていく。
少しずつ思い出が戻るにつれて、彼の中にイヤな予感が芽を出す。もしかして、自分は誰かを傷つけたんじゃないか。とんでもないことをしてしまったんじゃないか。そういう疑いが胸に居座り始めると、どんな小さな記憶も疑わしく見えてくる。
その苦しさが、すごくリアルだ。犯人捜しじゃないのに、なぜか手に汗握る展開になっていくのは、感情の揺れが丁寧に描かれてるからだと思う。
そして忘れちゃいけないのが、若き日の御手洗潔だ。まだ占星術師として細々とやってる頃の彼は、後年のようなカリスマ探偵って感じじゃない。だけど、どこか飄々としてて、ちゃんと人の痛みに目を向けてくれる不思議な存在だ。益子と御手洗のあいだに流れる空気がすごく良くて、派手なセリフがなくても印象に残る。
音楽がふたりの距離を縮める場面もあって、そこにはほんのりした温度が感じられる。人と人の関係って、こういうささいなきっかけで築かれていくんだなと思えるのがいい。
後半、御手洗が本格的に動き出すと、今までぼやけていた輪郭が一気にくっきりしてくる。謎の構造もすごく緻密で、気づいたら読みながら何度も「あれ?」と立ち止まってしまう。それでいて、ちゃんと腑に落ちる。種明かしのタイミングも絶妙だし、そこに詰まってる感情がまたずるい。
読後に残るのは、犯人が誰だったとか、どうやって殺したかとか、そういう単純な驚きじゃない。「あの人は、どうしてそこまで……」と、ずっと考えてしまうような余熱だ。
島田荘司が「これはミステリじゃない」と言ったのも、わかる気がする。たしかに、これは事件の謎を解くだけの話じゃない。人の心の奥を見に行くための物語だ。
御手洗シリーズの中では少し変わり種だけど、だからこそ、読むタイミングによって印象がまったく変わるかもしれない。
ミステリを超えた場所で、人間の複雑さと向き合いたいとき。そんなときにぴったりの作品だ。
5番目.『御手洗潔のダンス』
名探偵・御手洗潔が活躍する三つの事件と、彼と石岡和己の日常やファンとの交流を描いたエッセイ風の一編「近況報告」を収録した短編集。
「山高帽のイカロス」では、「人間は空を飛べる」と主張していた幻想画家が、アトリエから奇声と共に姿を消し、数日後、地上20メートルの電線上で空飛ぶポーズの死体となって発見されるという奇怪な事件を描く。
「ある騎士の物語」では、十五年前に起きた殺人事件の謎に挑む。当時、容疑者とされた女王とその取り巻きの男たちは、数十キロ離れた場所にいたという鉄壁のアリバイがあった。限られた時間の中で、いかにして犯行は可能だったのか。
「舞踏病」では、月70万円という破格の報酬と引き換えに自宅の二階に住まわせた老人が、夜な夜な一心不乱に踊り続けるという謎の行動の真相を探る。
各編で御手洗は、その卓越した推理力で不可解な謎を解き明かしていく。
空を舞い、踊り、語る、短編ミステリーの妙味
『御手洗潔のダンス』は、短編3本+おまけ1本という構成で、どれも個性が強くてバラエティに富んでいる。御手洗潔の魅力をコンパクトに味わいたいときにはぴったりの短編集だ。
まずインパクト重視で語るなら『山高帽のイカロス』。これは、最初からぶっ飛んでいる。「空を飛ぶ」と豪語していた画家が、まさかの空中死体で発見されるという、完全に意味不明な状況からスタートする。どう考えても現実じゃありえないのだが、御手洗はそこに理屈で挑んでいく。ふわふわした幻想に対して、するどいロジックで一刀両断してくれる感じがたまらない。
次に登場するのは『ある騎士の物語』。これは15年前の事件をめぐるアリバイトリック系の話だ。時間とか距離の計算が絡んでくる、少し複雑なタイプのミステリーだが、そこに騎士というロマンチックな設定が絡んでくるから不思議と読みやすい。トリック自体はかなり強引に感じるかもしれないが、それを押し切るのが島田ミステリってもんだ。
『舞踏病』は、ホームズっぽい日常のなかの奇妙な謎を描いた作品。老人が夜な夜な踊り出すという怖い話から始まって、なんでそんな行動をとっているのかってところに焦点が当たっていく。御手洗と石岡のコンビがワイワイしながら謎に迫っていく流れは、会話劇としても楽しい。
ラストの『近況報告』は、もう完全にファン向けのエッセイ風エピソードだ。御手洗が日本を離れてからの石岡くんの生活とか、熱烈すぎるファンの話とか、肩の力を抜いて笑える話が詰まっている。二人の関係性の空気感もよく出ていて、シリーズをずっと追ってる人にとってはニヤニヤできる内容だ。
短編集という形式だからこそ、それぞれの話のテンポがよくて、どこから読んでも入りやすい。重厚な長編では見えにくかった御手洗の別の一面も垣間見えるし、石岡くんのボヤきも健在で、シリーズのファンには嬉しい小ネタも盛りだくさん。
御手洗シリーズをちょっと休憩がてら楽しむには、かなりおすすめの作品集だ。面白すぎて、読後はちょっと踊りたくなるかもしれない。
6番目.『暗闇坂の人喰いの木』
横浜の元町近くに存在する暗闇坂。その坂の途中に、樹齢二千年とも言われる巨大な楠が聳え立っている。
この大楠は古くから「人喰いの木」として地元の人々に恐れられており、過去にはこの木で処刑された罪人たちの泣き声が聞こえる、あるいは木が人を飲み込むといった不気味な噂や言い伝えが絶えなかった。
その曰く付きの大楠の傍らに建つ古い洋館には、どこか風変わりな一家が暮らしていた。
ある日、探偵・御手洗潔と助手の石岡和己のもとに一人の女性が訪れ、この「人喰いの木」にまつわる奇怪な事件の調査を依頼する。
やがて、大楠を巡る過去の惨劇と、洋館に住む一家の秘密が明らかになっていく。人々の狂気を掻き立てるとされる大楠の呪いなのか、それとも人間の仕業なのか。
御手洗は、この地に根付く暗い伝承と複雑に絡み合った事件の真相に迫るのであった。
闇にそびえる謎の大樹に潜む恐怖と論理
『暗闇坂の人喰いの木』
なんとも不穏でおどろおどろしいタイトルだが、その印象はまるで釣りじゃない。むしろ、物語の隅々にまで異様な空気が充満していて、ページをめくる手を侵食してくるような一作だ。
中心にそびえるのは、樹齢二千年とされる大楠。伝承が幹に絡みつき、土地の人々の記憶や妄想までも吸い込んで、そこにあるだけで何かがおかしいと感じさせる存在感を放っている。
「人を喰う木」という伝説は、眉唾なのか、それとも薄暗い真実を孕んでいるのか。読みながら、信じたくない気持ちと惹かれてしまう興味の間で、何度も視線がその木に引き戻される。
この作品の肝は、オカルトや怪奇じゃない。もっと根の深い部分、人がいかに恐怖に飲み込まれ、理性をねじ曲げていくか、というところにある。大楠は単なる舞台装置じゃなく、人の内面を写す鏡みたいな役割を果たしていて、その描き方がとにかく巧い。
過去の事件が語られるシーンは生々しく、まるで誰かに怪談を囁かれているかのようなリアルさがある。とはいえ、そこはやっぱり御手洗潔シリーズだ。後半になって彼が登場すると、怪異めいた現象の裏側が少しずつ暴かれていく。
どれだけ狂って見えていた世界にも、筋の通った説明が与えられていく過程は、理詰めのカタルシスに満ちている。
特に、御手洗が真相を語り出す場面は圧巻だ。混沌としていた状況が一気に整理され、霧が晴れるような感覚が押し寄せてくる。この瞬間の快感は、カーやクリスティの鮮やかな種明かしにも負けていない。
ただ、読みやすい話ではない。筆致は重めで、登場人物たちの感情や業もずっしりと重たい。でも、その重さがあるからこそ、明かされた真実には美しさと切なさが同居している。
伏線の張り方も、回収のタイミングも見事。すべてが解き明かされたあとに残るのは、理屈で満たされた安心感だけじゃない。どこか胸の奥にひんやりと風が吹き抜けるような、妙に沁みる感覚だ。
人の心の「怖さ」に真正面から向き合いたい人にすすめたい。ただ事件が解決すればいいわけじゃない、その向こう側にある情念まで味わいたい、という人にこそ読んでほしい。
『暗闇坂の人喰いの木』は、恐怖と推理が同じテーブルについた、深くて濃い物語だ。どこかおかしくなりそうな空気のなかで、ちゃんと筋の通った真実が待っている。そのバランス感覚が、たまらなくスリリングだ。
7番目.『水晶のピラミッド』
アメリカのネバダ州に突如として出現した、エジプト・ギザの大ピラミッドを原寸大で再現したガラス製の巨大なピラミッド。
この「水晶のピラミッド」の傍らに建つ塔の最上階、地上30メートルの密室で、男が溺死体となって発見されるという不可解な事件が発生する。現場には冥府の使者アヌビス神を思わせる痕跡が残されており、事件はオカルトめいた様相を呈する。
この奇怪な事件の調査に乗り出したのは、ハリウッド女優となった松崎レオナであった。彼女は、かつて難事件を解決に導いた名探偵・御手洗潔に助けを求める。
物語は、現代のアメリカで起こる事件と並行して、古代エジプトのピラミッド建設の謎や、豪華客船タイタニック号沈没の悲劇といった、壮大なスケールの歴史的エピソードを織り交ぜながら展開していく。
果たして、水晶のピラミッドで起きた密室殺人の真相とは。そして、時空を超えて交錯する出来事の背後に隠された謎に、御手洗潔はいかにして迫るのであろうか。
歴史と謎が交錯する知の冒険
御手洗潔シリーズの中でも、『水晶のピラミッド』はだいぶ異色だ。
密室殺人? 奇妙な死体? もちろんある。しかしこの作品のスケールは、それだけじゃない。
話の発端は、アメリカの砂漠に突如出現した巨大なガラスのピラミッド。透明で、不気味で、どこか美しいこの建築物が、ただの背景にとどまらず、物語全体の謎の根みたいな役割を果たしていく。
そのピラミッドの中で起きるのが、「空中三十メートルの密室で人が溺死する」という前代未聞の不可能犯罪。設定だけで圧倒されるが、読み進めるとそれ以上にヤバいのが、その背後にちらつく歴史や神話の影だ。
古代エジプトの神々、タイタニックの沈没、そして現代の科学技術。そうしたものが縦横に絡み合いながら、「過去と現在」「幻想と論理」「文明と暴力」みたいなテーマがにじみ出てくる。
前半はじっくり進む。御手洗の登場も遅い。だけどその間、描写の密度が異常に濃い。キャラの思考、現場の空気、歴史の背景まで、すべてが丁寧に積み上げられていくから、読む手が止まらない。
ようやく御手洗が登場すると、物語は一気に収束モードに入る。ここからの展開が本当にすごい。あまりにもスケールの大きな謎に対して、御手洗はブレることなく、理と推理で立ち向かっていく。
伏線の拾い方も鮮やかで、細かいパーツが「そう来たか」という形で一気にハマっていく。無理やりじゃない。ちゃんと理屈が通っていて、しかも驚きがある。そのバランスが見事だ。
さらに特筆すべきは、あの松崎レオナが登場する点だ。情熱的でちょっと不穏な彼女と、御手洗のクールさがいいコントラストになっていて、そこに石岡くんの慌てっぷりが加わることで、重たい話のなかに人間的な味がしっかりと生まれている。
読み終わった後に残るのは、単なる「謎が解けた」という快感じゃない。文明って何だ? 歴史って何だ? 人間はどこから来て、どこへ向かうのか。そんなテーマが、ふと頭をよぎってしまう。
『水晶のピラミッド』は、ただの変わり種のミステリじゃない。論理と幻想、科学と神話が、きっちり噛み合って立ち上がる知的な冒険譚だ。
御手洗潔シリーズのなかでも、ひときわ濃くて、異様で、そして忘れがたい一作になっている。
8番目.『眩暈』
物語は、一人の青年が遺した異様な手記から始まる。その青年は『占星術殺人事件』を愛読書としており、彼の手記には、切断された男女の死体が合成され、両性具有の存在として蘇るという、常軌を逸した内容が綴られていた。
窓の外には世界の終末を思わせる荒涼とした風景が広がっているとも記されており、一読しただけでは精神異常者の妄想としか思えないものであった。
この手記は、薬害の影響で奇形児として生まれた大スターの息子・陶太によって書かれたものと判明する。名探偵・御手洗潔は、この手記に記された内容を単なる狂人の戯言として片付けず、そこに何らかの真実が隠されていると直感する。
彼は、この「頭がおかしくなりそうな手記」を手掛かりに、その背後に潜む驚くべき事件の真相究明に乗り出すのであった。
手記に記された恐るべき記述は何を意味するのか。そして、醜悪な現実世界で繰り広げられた事件の真相とは。
御手洗の推理が、常識を超えた謎を解き明かしていく。
二重・三重に折り畳まれたプロットと、パズルの構造美
その物語に足を踏み入れた瞬間、世界がぐらりと傾く。
『眩暈』
タイトル通りの読書体験が待っている。これはただのミステリーじゃない。読者の知覚や感覚までも揺らがせてくる、かなり攻めた一作だ。
まず出てくるのが、謎めいた手記。血と性と死が入り混じったような言葉が並び、読んでるうちに頭がクラクラしてくる。『占星術殺人事件』の亡霊みたいな世界観で、詩のような美しさと狂気がないまぜになって、こっちの現実感覚を揺らしてくる。
この手記、読んでる間は「本当に起きたことなのか?」「これは誰かの妄想なのでは?」と、ずっと判断を保留させられる。その揺らぎがこの作品の最大の仕掛けだ。読者はどこまで信じていいのか、どこまでが事実なのか、読み進めながら自分の基準を問い直す羽目になる。
そこへ御手洗潔が登場する。
あの冷静すぎる頭脳が、この濃厚な手記の異常性をひとつずつ分解していく過程は、見ていて気持ちいい。混沌とした言葉の森に、一本のロープを通してくれるような感覚だ。まさに目が覚めるような推理。
でも、この作品が面白いのは、手記の分析だけじゃない。その内容と現実世界とがリンクし始めたとき、物語はまったく別の顔を見せてくるのだ。
「もしあれが現実だったなら、どうやってやったのか?」
そう思った瞬間から、こっちも完全に罠にハマる。島田荘司の出してくる答えがまた、常識を軽く飛び越えるレベルでぶっ飛んでて、でも納得させられてしまう。奇抜だけど、ちゃんと理屈が通ってる。そこが島田ミステリの強みだ。
あと忘れちゃいけないのが、御手洗の変人っぷりだ。
いきなり「ズールー族の勝利の踊り」を披露する名探偵なんて、他にいない。石岡君との温度差、掛け合い、その全部が絶妙で、ミステリーとしての緊張感の中にいい感じの息抜きが混じっている。
『占星術殺人事件』を読んでいる人なら、ニヤッとできる繋がりにも気づくはずだ。手記、狂気、倒錯、詩的な狂乱。いろんな要素が響き合って、構造的にもめちゃくちゃ凝っている。
結局のところ、『眩暈』というのは、「目に見えてることがすべてじゃないよ」という話だ。現実と幻想の境目があいまいになってくる感覚。それがどんどん加速して、最後には思考の奥まで入り込んでくる。
ミステリーファンにも、スリルが欲しい人にも、そして何より、感覚を揺さぶられたい人にこそおすすめしたい。
言葉が脳をかき乱し、論理が幻想をぶった切る。そういう快感が、ここにはある。
9番目.『アトポス』
虚栄と欲望が渦巻く都ハリウッドで、血で爛れた顔を持つ「怪物」が出没するという噂が広がる。
時を同じくして、著名なホラー作家が首を切断されるという猟奇的な殺人事件が発生し、さらには生まれたばかりの赤ん坊が次々と誘拐されるという不可解な事件が連続する。
一方、女優・松崎レオナは、主演映画『サロメ』の撮影のため、死海のほとりにある「塩の宮殿」に滞在していた。しかし、その撮影現場でもまた、ハリウッドでの事件を彷彿とさせるような惨劇が繰り返される。
甦る吸血鬼伝説の恐怖が、レオナと撮影クルーたちを襲う。前半では、史実にもとづくという身の毛もよだつ吸血鬼事件が詳細に語られ、それがレオナの運命にも影を落とそうとする。
これらの複雑に絡み合う事件の真相を解明すべく、名探偵・御手洗潔が立ち上がる。ハリウッドと死海、二つの場所で起こる怪事件に関連はあるのか。
そして、人々の心を惑わす「アトポス」の正体とは一体何なのであろうか。
血の祭壇に仕掛けられた迷宮
『アトポス』は、御手洗潔シリーズの中でもとびきりヘビーな一作だ。
ページ数も内容もスケールも、何もかもが桁違い。ホラーと歴史ミステリーをぶち込んで、さらにオカルトの香りを漂わせながら、どこまでも真っ直ぐに突き進んでいく。
舞台はなんとハリウッドと死海。アメリカの映画スタジオで起きる猟奇事件と、砂漠の真ん中で展開される惨劇が並行して語られ、読んでいるこっちの頭もどんどん遠くに連れていかれる。
特にインパクトが強いのは、物語の前半に大きく割かれた「血の伯爵夫人 エリザベート・バートリ」のくだりだ。まるで歴史ドキュメンタリーのような密度で、拷問や吸血の描写が延々と続く。これがまた妙にリアルで、不気味で、けれどどこか魅入られてしまう。島田荘司が本気で書く「伝説」ってこうなるんだなと唸らされた。
この血まみれの過去が、現代の奇怪な事件とどう繋がるのか。読者としては、「これは本当に繋がるの?」と思いながら読み進めることになる。
でもそこは御手洗潔の出番だ。中盤以降にひょっこり現れ、例によって論理の剣を振りかざし、オカルトと見せかけた事件の芯をズバズバと突いていく。そのギャップがやっぱり気持ちいい。
タイトルの『アトポス』というのは、「場違いなもの」とか「異物」って意味なのだが、この物語自体がまさに場違いの集合体だ。吸血鬼伝説、古代遺跡、奇怪な死体、奇妙な迷路、映画セット……すべてが異様で奇妙なのに、ラストには不思議とひとつに繋がって見える。
今回のトリックも、相当にぶっ飛んでる。まるで子どもがミニチュアで遊んでるかのような、スケールのおかしな仕掛けが用意されていて、読んだあとに「そこまでやるか!」と笑うしかなくなる。もちろん、そういうバカ真面目な荒唐無稽が、御手洗シリーズの真骨頂なのだが。
事件そのものは複雑で、エンタメ要素もガッツリ。魔都・上海の描写もあれば、映画の内幕話もあるし、グロテスクな描写もてんこ盛りだ。しかも御手洗の出番が遅いっていうお約束も健在。でも、登場してからの彼はやっぱり無双で、混沌の渦を論理の力で切り裂いていく姿には、安心感すらある。
総じて、ミステリーにホラーや歴史やオカルトや映画セットを全部混ぜて、さらに血の伯爵夫人までぶち込んだような、超重量級の御手洗ワールド。
スリルと謎と情報の奔流に、がっつり身を投げ込みたい人向けだ。読むのに体力はいるが、それに見合う読み応えがぎっしり詰まっている。
10番目.『御手洗潔のメロディ』
名探偵・御手洗潔の過去と現在を繋ぐ四つの傑作短編を収録した作品集。各編を通じて、御手洗の天才的な推理力、奇人ぶり、そして人間的な側面が多角的に描かれる。
「IgE」では、何度も不可解な方法で壊されるレストランの便器の謎と、高名な声楽家が探し求める謎の美女の行方という、一見無関係な二つの出来事が、御手洗の介入によって意外な繋がりを見せ始める。
「SIVAD SELIM」では、石岡和己が外国人障害者のためのクリスマスコンサートで挨拶を頼まれ、御手洗にギター演奏を依頼するエピソードが描かれる。ミステリー要素は薄いが、二人の温かい関係性が垣間見える一編だ。
「ボストン幽霊絵画事件」では、御手洗がアメリカの大学に在籍していた頃に遭遇した、自動車工場の看板の一文字だけが執拗に狙撃されるという奇妙な事件と、芸術家失踪の謎に挑む姿が描かれる。
そして「さらば遠い輝き」では、御手洗に想いを寄せていた女優レオナの視点から、彼の近況や過去が語られる。
天才探偵の意外な日常。御手洗潔というキャラクターの奥行き
『御手洗潔のメロディ』は、御手洗潔という人物をいろんな角度から味わえる短編集だ。謎解き、人間ドラマ、友情、思い出話。どれも方向性はバラバラだが、そこに一本芯が通っているのがいい。
『IgE』は、レストランの便器が壊されるっていう妙な事件からスタートする。最初は「なんじゃそりゃ」と思わせといて、どんどん話が広がっていく。声楽家、謎の美女、そして御手洗の鋭すぎる推理が絡んできて、最後は見事に一本の線で繋がる。伏線回収の見事さと御手洗の天才っぷりに、やっぱりこいつすげえなってなる短編だ。
『SIVAD SELIM』は、本格ミステリーというより、御手洗と石岡の関係性を描いたエピソード。クリスマスコンサートが舞台で、石岡がいつも通り振り回されるのだが、そこにちょっとした温かさがあっていい。とくに「鯖の味噌煮」ネタは、読者サービス満点だ。シリーズ追ってきた人にはニヤリとできるシーンが詰まっている。
『ボストン幽霊絵画事件』は、若かりし頃の御手洗がアメリカで起こしたひと仕事。絵画、失踪、看板の狙撃……地味なようで意外と複雑な事件が、あの頃の御手洗らしい観察眼とひらめきで解き明かされていく。海外が舞台なのも新鮮だし、御手洗の原点みたいな雰囲気もあって面白い。
『さらば遠い輝き』は、レオナ視点で語られる御手洗の知られざる顔を描いた作品だ。謎解きはないが、むしろそれがいい。御手洗ってどこか人間離れしてるようで、でもこういう人との繋がりがあって、確かに地に足つけて生きてるんだなと思わせてくれる。石岡との関係性も、あらためてグッとくる描写があって、シリーズの読者には刺さる短編だ。
この短編集は、ただ事件を解く話だけじゃない。御手洗という人物そのものの輪郭を、少しずつ浮かび上がらせるような構成になっている。
シリーズのなかで一休み、というよりも、別の角度から御手洗と向き合うような読後感。ファンにはたまらないし、キャラの魅力を深堀りしたい人にはとてもオススメだ。
まずはここまで!
まだ御手洗潔シリーズにあまり触れていないなら、ここまでをひと区切りにして、まとめて読んでおくのが絶対におすすめだ。
もちろん、読む順番は大事。順不同でも読めないことはないが、人物関係や伏線の面白さがだいぶ損なわれてしまう。
このあと紹介する作品にもいい話はたくさんある。ただ、ここまでに挙げたタイトルは、そのなかでも群を抜いた傑作ばかりだ。ミステリーとしての完成度、物語の厚み、御手洗というキャラクターの描かれ方。すべてにおいてシリーズの核になっている。
まずはこの範囲までしっかり読み切ること。そこから先に進めば、作品ごとの違いや広がりをより深く楽しめるようになるはずだ。
というわけで、次からはシリーズ後半戦。
印象の変化やジャンルの広がりも含めて、ざっくり紹介していこう。
12.『龍臥亭事件』
実は『御手洗潔のメロディ』より前に発表された作品だが、先にメロディを読んだ方が良い。
『龍臥亭事件』では石岡君がメインであり、御手洗は電話のみでの登場。
13.『Pの密室』
御手洗潔がまだ幼稚園児だったときの『鈴蘭事件』と、小学二年生のときの事件『Pの密室』の二編が収録。
子供の頃から天才すぎて笑う。
14.『最後のディナー』
『里美上京』『大根奇聞』『最後のディナー』の3編が収録。
『龍臥亭事件』で出会った犬坊里美が上京してきて石岡君と再会する。このコンビが面白い。
どれもほのぼのしてるけど名作揃い。
15.『ハリウッド・サーティフィケイト』
御手洗潔シリーズに登場する女優レオナが猟奇的殺人に挑む。
御手洗は電話のみの登場ですが、出番が短いからこそ愛おしく思える。
超ハードな事件にグイグイ行っちゃうレオナの魅力がすごい。読めば一発でファンになっちゃうくらい。
16.『ロシア幽霊軍艦事件』
御手洗潔シリーズらしいおどろおどろしさはなし。
ある幽霊軍艦の謎を紐解く壮大な歴史ミステリー。
殺人は起きないのにめちゃくちゃ面白い。
御手洗の天才っぷりがまたよくわかるし、何より物語がいい。
17.『セント・ニコラスの、ダイヤモンドの靴』
『占星術殺人事件」』から間もない頃の御手洗&石岡君の物語。懐かしさを感じる。
御手洗の優しさが光る。クリスマスの時期に読むとなお良い。
18.『魔神の遊戯』
ここにきて、がっつりの、御手洗潔らしい惨忍な事件。
スコットランド、ネス湖畔の村で起こる連続バラバラ殺人。舞台も謎も魅力ありすぎ。
そしてアレをやってくれる。最高。ぜひ読んで味わってほしい。ネタバレに気をつけよう。
19.『ネジ式ザゼツキー』
実は超名作。
記憶に障害を持つ男エゴン書いた物語を読み、御手洗潔が隠された謎を解いていく安楽椅子探偵もの。
絡み合いすぎてワケがわからなくなった謎を解いていくときの爽快感、開放感。うひゃー!と叫びたくなる感じだ。
ああ、島田荘司って天才なんだな、と改めて実感する。
20.『上高地の切り裂きジャック』
『上高地の切り裂きジャック』と『山手の幽霊』の二編が収録。
アクロバットトリック炸裂。
御手洗&石岡コンビのやりとりを見ているだけで楽しい。
21.『龍臥亭幻想』
『龍臥亭事件』の続編。あの八年後、関係者が集まりまた事件が起きる。
なので石岡君が主人公。皆の成長ぶりが伺えて良きかな。
当然トリックが面白い。あっぱれ。
22.『摩天楼の怪人』
御手洗がまだ若かりし頃の事件。
ニューヨーク・マンハッタンにある超高層ビルという密室での事件。どう考えても不可能な謎の数々をキレイに解決していく。芸術のよう。
トリックなんてどうでもよくなるくらい、摩天楼と怪人の世界観が素敵。でもやっぱりトリックすごい。
文庫で720ページをあっという間に読み終わらせちゃう引き込み感。これぞ島田荘司。
23.『最後の一球』
とにかくハートフル。
一人の天才打者と、二流のまま生涯を遂げた投手のアツい物語。
御手洗の活躍や謎解きを期待して読むものではなく、一つの濃厚な小説として読むべし。
ミステリ小説であることを忘れさせる面白さ。
24.『溺れる人魚』
短編集。
人魚繋がりな『溺れる人魚』『人魚兵器』『耳の光る児』『海と毒薬』の四編。
面白いが、初期と比べるとなんか御手洗潔シリーズっぽくないかな。でも、これも島田ワールドの一部なのだ。
25.『UFO大通り』
「馬車道時代」の話。『UFO大通り』『傘を折る女』の中編二編。
やっぱりこの頃の二人が最高にイキイキしてる。ファンにはたまらない一冊。
特に『傘を折る女』が面白い。
26.『犬坊里美の冒険』
タイトルの通り、御手洗シリーズに登場する犬坊里美が主人公の話。
御手洗潔なら秒速で解決しそうな謎だが、そんな天才ではない犬坊里美が奮闘する姿が良いのだ。
油断してたら伏線が見事すぎて驚いた。
27.『リベルタスの寓話』
『リベルタスの寓話』と『クロアチア人の手』の二編が収録。
本気で意味がわからない謎を御手洗が解く。なんだこれ。
『クロアチア人の手』は「んなアホな!!」と叫びたい人は読むことを推奨。
28.『御手洗潔と進々堂珈琲』
若き頃の御手洗が、旅で出会ったエピソードを淡々と語っていく短編集。
ミステリーではなく、御手洗潔という人物の物語。私は大好きな作品。
29.『星籠の海』
映画化もした有名な作品。
御手洗役の玉木宏さんがイケメンすぎてひっくり返った。
いや、確かに私のイメージする御手洗もカッコイイのだが、あれは流石にカッコよすぎた。
30.『屋上』
『屋上の道化たち』が加筆&改題されて『屋上』となった。
これから読むのであれば、『屋上』の方にしよう。
自殺する気が全くない人が、その屋上に登ると飛び降り自殺してしまう、という呪いのような謎に御手洗が挑む。
スーパートンデモトリック。笑うしかない。
「まあ御手洗潔シリーズのトンデモトリックには慣れてきたかな」と思ったらこれだ。
評価が別れるみたいだけど、私は好き。
31.『御手洗潔の追憶』
これまでの御手洗潔シリーズを読んできた人しか楽しめない、完全なるファンブック。
御手洗潔データベース書、的なもの。
32.『鳥居の密室 世界にただひとりのサンタクロース』
クリスマスに起きた密室事件の謎に御手洗潔が挑む。
初期の島田作品ほどではないが、大掛かりなトリックは面白い。
というか今作はトリックよりも人間ドラマに重点をおいた作品。純粋に良い作品でした。好き。
おわりに。
以上が、御手洗潔シリーズのおすすめの読む順番である。
最初にも言ったが、『占星術殺人事件』から『御手洗潔のメロディ』までが、とにかくずば抜けて面白い。まずはそこまでをひと区切りとして、ぜひ順番通りに読んでみてほしい。
もちろん、この先にも魅力的な作品はたくさんあるし、御手洗の新たな一面が見えてくる展開も待っている。ここまで読んで「御手洗シリーズって面白いな」と感じたら、もうあとはそのままどんどん進めばいい。
気づけばシリーズ全部読み終えていた──そんな読書体験になってくれたら、すごくうれしい。
というわけで、長くなったけど、最後まで読んでくれてありがとうございました。
さらに一言。
御手洗潔という人物は、実写化されたり漫画になったり、いろんな顔を持っているのだが、わたし的には『名探偵傑作短篇集 御手洗潔篇 (講談社文庫)』の表紙の御手洗と石岡くんが一番イメージに近いんだよねえ。
この表紙絵、たまりません。
ただし、正直この『名探偵傑作短篇集 御手洗潔篇』を読むのであれば、『御手洗潔の挨拶 (講談社文庫)』『御手洗潔のダンス (講談社文庫)』『御手洗潔のメロディ (講談社文庫)』をそれぞれ読んだ方が良い。
そして、もう一言。
1988年に発表された『切り裂きジャック・百年の孤独 (文春文庫)』は、御手洗潔シリーズとは言われていないものの、実は隠れ御手洗シリーズ。
御手洗好きならぜひ読んでみてほしい。
とはいえ、まずは『占星術殺人事件(講談社文庫)』から。
さあ、御手洗ワールドを堪能しよう!