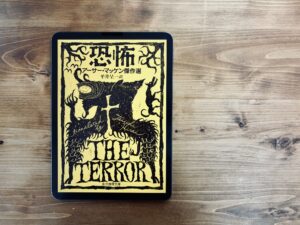アーサー・マッケン。
名前を聞いてピンとくる人はそれなりに怪奇文学が好きなタイプだと思う。
彼の作品は、H・P・ラヴクラフトやスティーヴン・キングにも多大な影響を与えたと言われている。
でも、ラヴクラフトやキングほど広く名が知られているわけではない。
なぜなら、マッケンの恐怖は一筋縄ではいかないからだ。
マッケンのすごさは、いわゆるモンスターとか殺人事件じゃない。日常の風景に、なんともいえない異物感が忍び込んできて、気づいたときには足元がぐらついてる、そんな体験をくれるところにある。
そんなマッケンの世界を、最高の日本語に訳してくれたのが翻訳家・平井呈一。この人は、「マッケン布教の伝道師」であり、「怪奇小説界の吟遊詩人」みたいな存在だ。
平井訳には独特のリズムがある。漢語も多いし、ちょっと古めかしい。でもそれが効く。
マッケンの持つ古代の霧が立ちこめる感じを、日本語でそのまま再現できているというのは、本当にすごいことだ。
『恐怖』という名状しがたい怪異
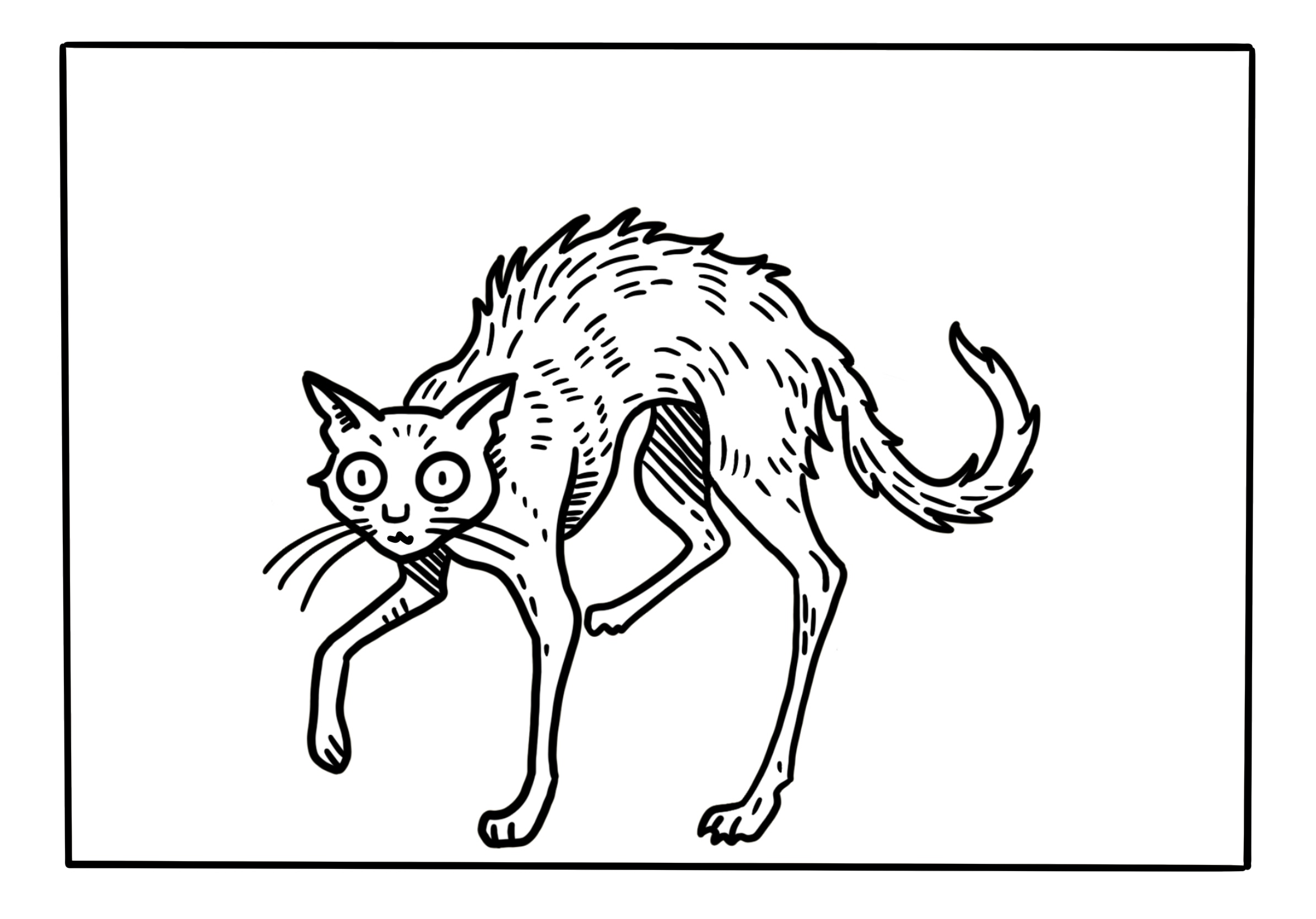
この本の表題作『恐怖』は、マッケンが第一次世界大戦下の1917年に書いた中編小説だ。
これは明らかに、1914年に発表された短編『弓兵』の裏返しとして書かれている。『弓兵』は、英軍を救った幻のアーチャー(モンズの天使)という都市伝説を生み出した作品だが、『恐怖』はむしろ、「自然界そのものが人間に反乱を起こすとしたら」という冷たい逆説を描いている。
物語には、どれもはっきりとした犯人がいない。ただ、人間の支配がどこかで崩れたことだけは伝わってくる。
ここで面白いのは、本作が「犯人は誰か(あるいは何か)」という謎解きの構造を持っている点だ。
創元推理文庫という枠にふさわしく、じつは読者に推理の余地を与えてくる。だが、真相は……あえて言わない。
ネタバレはしないが、読後に抱くのは「ああ、そういう意味だったのか」という論理的納得と同時に、「じゃあ、これは人間に対する何の警告なんだ?」という深い不安だ。
しかもこの構造、たしかにミステリなのに、じつにマッケン的でもある。
つまり、名状しがたさと論理性が同居している。これが読んでいて不気味で面白い。
『パンの大神』『白魔』など、最高に気味が悪くて美しい短編たち
創元推理文庫『恐怖』には、表題作のほかにもマッケンの代表作がぎっしり詰まっている。
たとえば、スティーヴン・キングが「英語で書かれた怪奇小説の最高傑作」と称した『パンの大神』。
これは現代の科学(脳外科手術)と、古代異教の神が出会ったときに何が起こるかを描いた一編で、その終盤の描写は圧巻というほかない。
そして、個人的に一番恐ろしいと思っているのが『白魔』だ。
これは少女の日記という形式で、田園風景の中に潜む「異界」を描いた作品。内容はおとぎ話のように始まるが、読み進めるにつれて、語りの無垢さと背景に潜むとんでもないものの落差が浮き彫りになってくる。
他にも『内奥の光』『輝く金字塔』『生活の欠片』など、ケルト神話や人類学的ホラーをベースにした作品が多く、いわゆるクトゥルー神話系の源流を感じ取ることができる。
現代ホラーやSF、あるいはメタフィクション系のミステリが好きな人にとっても、「こういう発想の原点があったのか」と目から鱗が落ちる一冊だ。
100年前の恐怖が、今なお語られる
マッケンの恐怖は、今読むからこそリアルに感じられる側面がある。
たとえば『恐怖』で描かれる検閲と噂、見えないパニック、自然界の沈黙──これらは、現代のパンデミック時代やSNSの流言飛語を思い出さずにはいられない。
「世界そのものが、私たちに対して口を閉ざし始める」
この静かな絶望こそ、マッケンの描く戦慄の真髄だと思う。
そしてそれを訳出した平井呈一の文体は、漢語の格調と呪術性を兼ね備え、マッケン文学に欠かせない音楽性を与えている。
「怖い」とか「気味が悪い」というより、「精神の深部にノイズが入り込んでくる感覚」が強い。それが平井訳マッケンの魅力だ。
現代の感覚でいえば、ある種のオカルトSFであり、エコロジー・ホラーであり、そして哲学小説でもある。
だからこそ、ラヴクラフトからキング、ボールズ、マーク・フィッシャーに至るまで、後世の作家たちはみな彼を敬意をもって引用し続けてきたのだろう。
あの扉の向こうに、まだ何かがいる
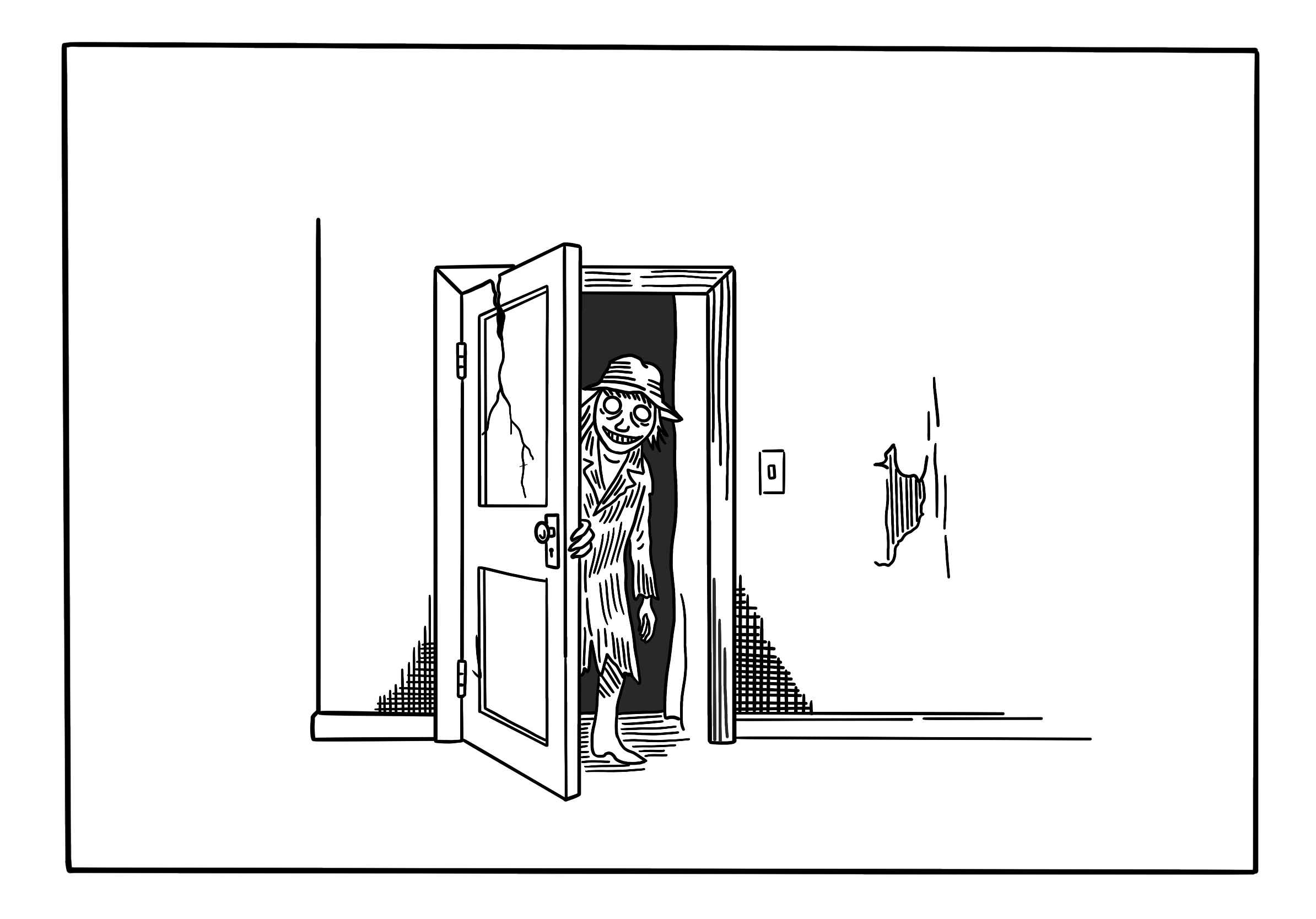
アーサー・マッケン『恐怖』は、単なる昔のホラー小説ではない。
日常のちょっとした違和感、風景のざわめき、世界そのもののよそよそしさにゾッとする、奇妙で美しい体験だ。
白い人がこっちを見ている。
森がしゃべらない。
飼い猫が、急によそ者の顔をする。
そんな場面で「やばい、世界が変わってる!」と思った瞬間。それはすでに、マッケンの魔法にかかっているということだ。
世界のどこかで、いまもアレがひっそり動いているような気がする。
そしてその気配にいち早く気づくのは、たぶん、犬でも猫でもなく、自分自身のなにげない違和感だったりする。
『恐怖』を読んで以来、草むらのざわめきにちょっとだけ耳を澄ませてしまうのは、きっとそのせいだ。