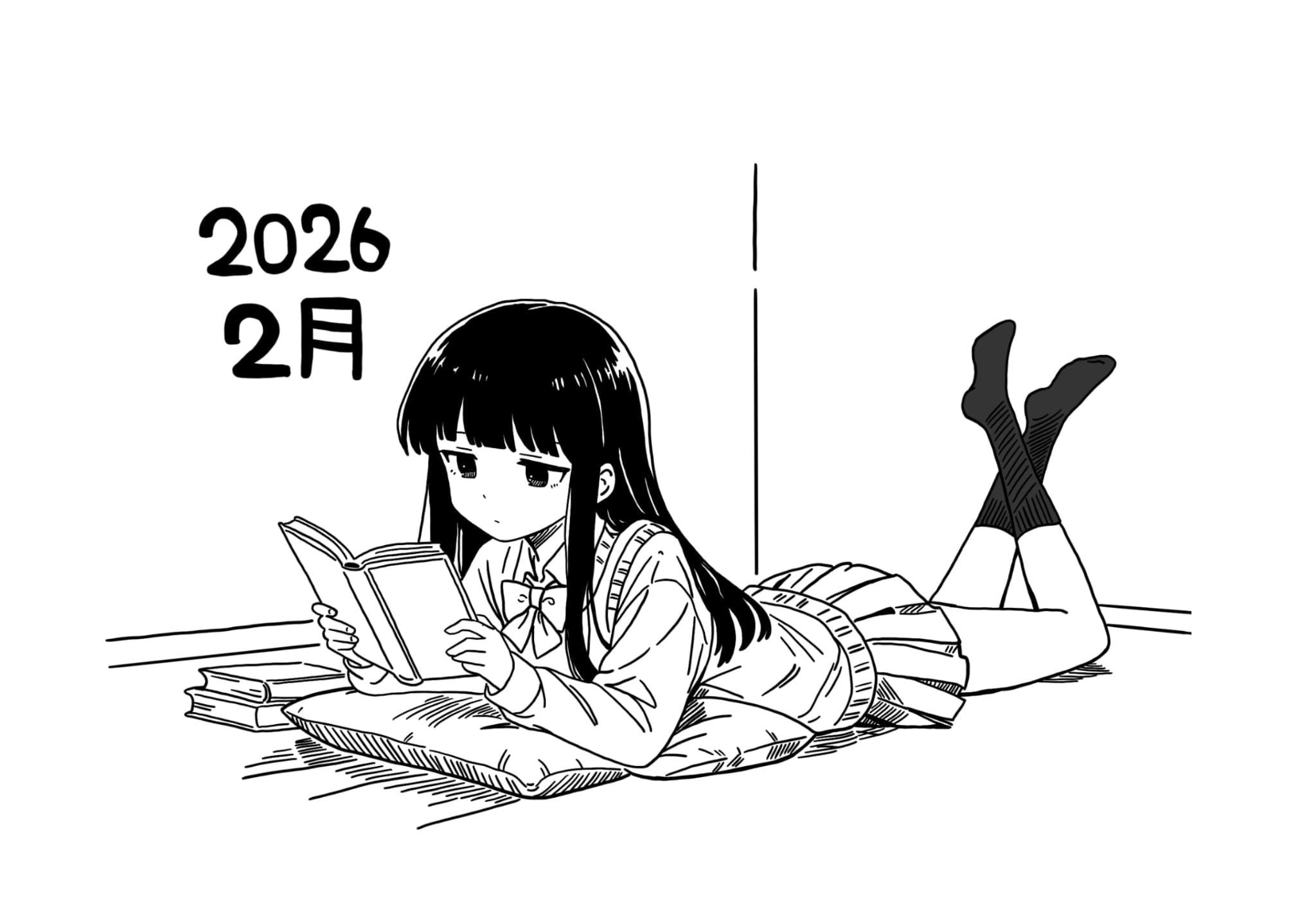江戸川乱歩の長編は意外と数が少ない。
そのせいもあって、乱歩の長編はどれがおすすめ?と聞かれると、だいたい話題が同じところに収束する。
『孤島の鬼』だ。
これは別に通ぶりたいからでも、定番だからでもない。
理由はシンプルで、この作品には乱歩が書きたかったものがほぼ全部入っているからだ。本格ミステリへの未練、怪奇趣味、同性愛的執着、異形へのまなざし、閉鎖空間、地下迷宮、そして人間関係がねじれて壊れていく感触。
しかも、どれも半端じゃない。読みながら何度も「盛りすぎじゃない?」と思う。
でも最終的に、なぜか成立している。勢いと情念で押し切られる。これぞ乱歩長編、というタイプの一作だ。
前半は本格、後半は怪奇冒険。ジャンルが壊れていく快感

江戸川乱歩『孤島の鬼』イメージイラスト 絵:四季しおり
『孤島の鬼』を語るとき、どうしても外せないのが構成の話。途中でジャンルがはっきり変わるのだ。
前半はかなり本格ミステリ寄り。東京を舞台に、密室殺人、衆人環視下の殺人、不可能犯罪的な状況が並び、探偵役もきちんと登場する。推理も提示されるし、乱歩が「ちゃんと本格を書こう」としていた気配がここでははっきり感じられる。
ところが、ある地点を境に、物語は急カーブを切る。舞台は都会から離れ、孤島へ。そこから先は、論理で整理する物語ではなくなる。地下迷宮、追跡、潜入、異形の集団、暗号解読。冒険怪奇ロマンの領域に一気に突っ込む。
この転調は冷静に考えるとかなり乱暴だ。でも個人的には、ここが一番おいしい。前半で「ミステリ的なお行儀」を覚えさせておいて、後半でそれを全部壊す。理性が通じない場所に連れていかれる感覚が最高なのだ。
これは構成が破綻しているというより、理性が敗北する物語だと思う。探偵小説的な安心感を踏み台にして、もっと不安定で気持ち悪い領域へ行く。そのジャンプの仕方が、乱歩らしさの塊になっている。
諸戸道雄というバグった存在が、この物語を歪めている
「でも、あなたは全くそんな探偵みたいなことをやったのですか。そして何か分ったのですか」
「エエ、分ったのです」諸戸はやや誇らしげであった。「若し僕の想像が誤っていなかったら、僕は犯人を知っているのです。いつだって贅察につき出すことが出来るのです。ただ残念なことには、彼がどういう訳で、あの二重の殺人を犯したかが、全く不明ですけれど」
『孤島の鬼 江戸川乱歩ベストセレクション(7)』101ページより引用
この作品の主人公は蓑浦(みのうら)だが、読後に一番印象に残るのはどう考えても諸戸道雄(もろと みちお)だ。
医学者、美青年、富豪の家系、冷静沈着、理知的。
属性だけ並べると、名探偵役にぴったりのキャラだ。でも彼は探偵として物語を収束させる存在ではない。むしろ逆で、物語を破壊する側に立っている。
彼の蓑浦への感情。ここを避けると、この作品は一気に薄くなる。諸戸の同性愛的執着は、当時としてはかなり踏み込んだ描写だが、それ以上に厄介なのは、その感情がとても生々しいことだ。本人にも制御できない。誇りと自己嫌悪が同時に存在していて、どこにも逃げ場がない。
一方の蓑浦は、強い主人公ではない。推理で事件を解決できるわけでもなく、暴力で状況を変えられるわけでもない。基本ずっと怖がって、流されて、追い詰められていく。だからこそ、諸戸の感情を受け止めきれないし、拒絶もする。その距離感が、物語を必要以上に残酷にしている。
この二人の関係は、友情でも恋愛でもなく、もっと中途半端で不安定だ。その歪さが、怪奇や事件以上にホラーとして効いてくる。
異形、閉鎖空間、迷宮。乱歩の「好き」が暴走する場所
後半の孤島パートは、乱歩の怪奇趣味がフルスロットルになる。
地下に張り巡らされた迷宮。異形の人々。外界から切り離された独自のルール。
このあたりの設定だけ並べると、ベタに見えるかもしれない。でも乱歩がやると、妙に生々しい。地下道の湿度、暗さ、音の反響。身体がどう動くかまで想像させてくる。読んでいて、頭より先に感覚が反応する。
そして重要なのは、「異形」が単なる怪物として処理されない点だ。彼らは恐怖の対象であると同時に、社会の外側に追いやられた存在でもある。乱歩はそこに、露骨な差別意識と、妙な共感を同時に書き込んだ。このアンバランスさが、作品全体の居心地の悪さを作っているのだろう。
さらに、冒頭で示される「一夜にして白髪になるほどの恐怖」。
これは物理的な現象というより、精神が壊れた痕跡の象徴だ。恐怖が体に刻まれてしまう、という感覚。このモチーフが、身体改造や変身のテーマと重なってくる。
私はまだ三十にもならぬに、濃い度の毛が、一本も残らず真白になっている。この様な不思議な人間が外にあろうか。嘗て白頭宰相と云われた人にも劣らぬ見事な綿帽子が、若い私の頭上にかぶさっているのだ。
『孤島の鬼 江戸川乱歩ベストセレクション(7)』7ページより引用
読み終えても、きれいに終わらない。だから忘れられない

確かに『孤島の鬼』は読みやすい小説ではない。現代の感覚で読むと、引っかかる表現も多いし、倫理的にアウト寄りの描写もある。
それでも、この作品は今なお読まれ続けている。
理由は簡単で、感情の熱量が異常だからだ。論理の整合性よりも、執着や恐怖や愛の重さが勝っている。そのアンバランスさが、読後に変な余韻を残す。
読み終えたあと、すっきりしない。でも妙に頭から離れない。「あの関係はあれでよかったのか」「あの選択は避けられなかったのか?」と、考えてしまう。
だから『孤島の鬼』は、乱歩長編の中でも特別扱いされる。ミステリファン的に言うなら、「乱歩の性癖と野心が限界まで詰め込まれた危険物」だ。扱いにくいけど、目を逸らせない。
この気持ち悪さと美しさが同時に残る異様な感覚。
それこそが、『孤島の鬼』という小説の正体だと思う。