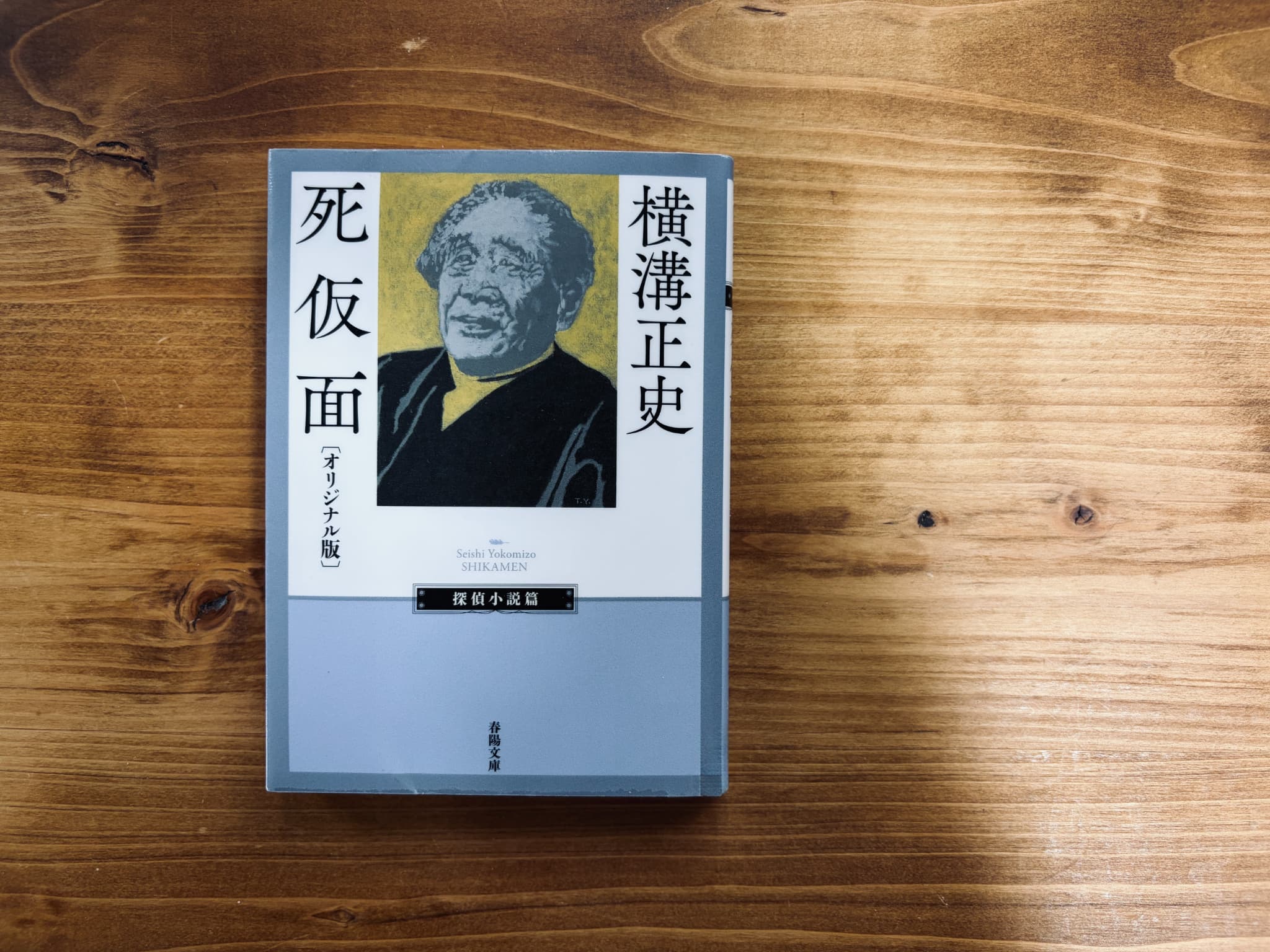ミステリ好きなら一度は経験があると思うが、タイトルだけで勝手に難易度を決めてしまうことがある。
クリスチアナ・ブランド『招かれざる客たちのビュッフェ』に収録されている『ジェミニー・クリケット事件』は、まさにそのタイプではないだろうか。響きが軽く、どこか童話じみていて、肩の力を抜いて読めそうに見える。黄金期ミステリに慣れているほど、この罠にかかりやすい。
だが、読み始めてすぐに違和感が出てくる。事件が起きない。なのに、やたらと会話が引っかかる。
登場するのは、老獪な老人と、若くて少し生意気なジャイルズ。二人のやりとりは軽妙で、ウィットも効いている。読んでいて楽しい。楽しいのだが、どこか落ち着かない。
理由は単純で、情報の出し方が妙に整理されすぎているからだ。語られていること自体は何でもないのに、「なぜ今それを言う?」という感覚が積み重なっていく。気づけばこちらは、物語を受け取る側ではなく、会話の一言一言を点検する側に回っている。
この時点で、ブランドはもう勝負を始めている。事件が起きる前から、思考を動かさせる。ミステリとしてはかなりいやらしい入り方だし、同時にものすごくフェアでもある。
ヒントは最初から置いてある。
ただ、受け取れるかどうかは別、というだけの話だ。
クリスチアナ・ブランドという、信用ならない作家

クリスチアナ・ブランドという作家は、ミステリ史の中でいつも少しだけ扱いが難しい位置にいる。
生年は1907年。英領マラヤ生まれで、インドで育ち、のちにイギリスへ渡るという経歴もあって、いかにも「帝国時代の端っこ」から出てきた作家という感じがする。
ミステリ作家としてのデビューは1941年、『ハイヒールの死』。これが重要で、時代的にはいわゆる黄金時代の真っ只中、というよりは、むしろ終盤に差しかかっている頃だ。アガサ・クリスティやカーがすでに名声を確立し、戦争を挟んでミステリの流行が心理サスペンスやリアリズム寄りに動き始めていた、ちょうどその境目に現れた。
だからブランドは、よく「遅れてきた本格派」だとか「黄金時代最後の作家」と呼ばれる。確かにその言い方はわかりやすい。閉ざされた舞台、限られた容疑者、論理による解決。使っている道具立ては、完全に古典派だ。
ただ、実際に読んでみると、そこには妙な違和感がある。形式は王道なのに、後味が妙に悪い。かわいらしく整えられたお菓子を口に入れたら、舌の奥に苦味が残るような感覚がある。
ブランドのミステリには、はっきりとした「悪意」がある。ただしそれは、露骨な暴力や残酷描写ではなく、人の判断のズレや、ちょっとした冷酷さに向けられたものだ。この感触が、彼女を単なる黄金時代フォロワーではなく、かなり信用ならない作家にしている。
コックリル警部と、「不可能」を冷ややかに扱う技術
ブランドの名前を不動のものにしたのが、コックリル警部シリーズだ。
『緑は危険』や『ジェゼベルの死』といった代表作では、病院や中世風のページェントといった舞台を使いながら、非常に凝ったトリックを披露している。
コックリル警部自身は、いかにも英国ミステリらしい名探偵だ。小柄で、少し地味で、派手な名台詞もない。その代わり、観察眼が鋭く、皮肉が効いている。どこか小鳥のような外見、という形容もよく似合う。
ただ、ブランドの凄さは、探偵キャラの魅力そのものより、やはりプロットの組み方にあると思う。彼女はジョン・ディクスン・カーと並ぶほど、不可能犯罪や密室を好んだ作家だが、そのアプローチはかなり違う。
カーが霧や怪奇趣味、オカルト的な雰囲気で「不可能」を演出するのに対して、ブランドはもっと冷たい。不可能な状況を提示しながら、そこに不思議さを盛りすぎない。あくまで現実的で、どこか意地の悪い形で「そんなはずがない」という感覚を積み上げてくる。
だからブランドの密室は、読んでいて楽しいというより、読後に奇妙な味が残るタイプが多い。論理的に解けたはずなのに、気分が晴れない。その感覚こそが、彼女の持ち味だと思う。
短編で一番怖くなる作家
『ジェミニー・クリケット事件』が書かれたのは、ブランドのキャリアがかなり円熟した時期だ。しかも長編ではなく短編。ここが重要で、ブランドは短くなればなるほど、性格が悪くなる作家だと個人的には思っている。
余計な説明を削ぎ落とし、会話と論理だけを残す。その結果、人物の感情や倫理が、むき出しの形で露出する。『ジェミニー・クリケット事件』では、まさにその状態が完成形に近い。
枠物語、安楽椅子探偵、犯人当てゲーム、不可能犯罪。どれもミステリとしては伝統的な要素だ。だが、それらを組み合わせた結果、「殺人を娯楽として語る」という構造そのものが、やたらとはっきり見えてしまう。
ここに、ブランドの「悪意の美学」がある。
派手に壊すわけではない。
ただ、少しだけズラす。
そのズレが、あとから効いてくる。
『ジェミニー・クリケット事件』は、そうしたブランドの資質が、短編という形式の中で限界まで研ぎ澄まされた一本だ。
枠物語という名の「殺人ゲーム」
「彼は自分の事務所で殺されてたんです。ドアには内側からかんぬきがかってあり、窓が割れていた。割れたガラスのふちが、いまだに小刻みにふるえてましたよ。ところが部屋は四階なんです。被害者は首を絞められ、そのうえ椅子に縛りつけられて、刺されていた。傷は真新しく、管察が部屋にとびこんだときには、まだ傷口から血が流れてた。なのに部屋にはだれもいなかった」
「なるほど、おもしろい!」
老人はその頑丈な、静脈の浮きでた手を、青年の腕にすべりこませた。
「ちょっとこの坂をのぼって、あの桑の木の下のベンチにすわろうじゃないかしきょうび、人に自慢できるほどの桑の木のある庭なんて、そうたんとはあるまい?あそこでその話をすっかり聞かせてくれ。新聞で読んだはずなんだが、忘れちまってね。このごろはなんでも忘れちまう。だから、最初から順を追って話してもらおうか」
明るい目が輝いた。「わしをテストするんだよ!ふたりでちょっとしたゲームをやろう、《指ぬき探し》のたぐいを。なんなら、《犯人探し》のゲームと言ってもいい。事件のあらましを話してくれー警察に聞かせるようなつもりで。手がかりも、証拠も!必ずしも真実でなくたっていいんだ。警察が実際に知ったときのとおりなら。わしに謎解きをさせてほしいんだよ。謎を解いて、ついでにやつらの鼻をあかしてやれるかどうか、ためしてみたいのさ……」
『招かれざる客たちのビュッフェ』199ページより引用
『ジェミニー・クリケット事件』の構造を考えるうえで、まず外せないのが「枠物語」形式だ。
物語は、事件そのものを直接描くのではなく、二人の人物の対話として進んでいく。語る側と、聞く側。その関係性が、最初からはっきりしている。
語り手はジャイルズ・カーベリー。殺された弁護士ジェミニーの養子であり、事件の当事者でもある人物だ。彼は、養父の死について、ある老人に向かって淡々と語っていく。
一方で、聞き手である老人は、名前すら持たない。彼はただ「殺人のパズルを聞かせてもらうこと」を楽しみにしている人物だ。
この構図に、ミステリ好きならピンとくるだろう。バロネス・オルツィの『隅の老人』以来続く、「安楽椅子探偵」の系譜そのものだ。事件現場に行かず、警察でもなく、与えられた情報だけで真相に迫る純粋な理性の存在。
しかもこの老人、ブランド作品ではおなじみのキャラクターでもある。EQMMに掲載された短編群に登場し続け、どこか狂言回しのようでありながら、同時に冷酷な理性の塊として振る舞う存在だ。感情に流されない。死者にも同情しない。ただ「面白いかどうか」で話を聞く。
この時点で、もう嫌な感じがしてくる。なぜなら、読んでいるこちらも、ほぼ同じ立場に置かれるからだ。
古典的なのに、手触りがまるで違う
物語の中盤に入ると、いよいよミステリらしい道具立てが揃ってくる。
振動するガラス、消えた警官、密室。
並べると、完全にクラシックな要素だ。正直、この並びを見た瞬間、「ああそういうタイプね」と思う人も多いはずだ。
ところが実際に読んでみると、その印象はかなり裏切られる。というのも、この作品では、トリックが「事件を成立させるため」に急に導入される感じがまったくない。すべてが、前半の会話や設定の延長線上にある。だから、「そう来たか」という驚きより、「そこに落ち着くのか」という納得が先に立つ。
論理の組み方も非常にクリーンだ。無駄な仮説を振り回さないし、読者を煙に巻くための説明もない。あくまで提示された条件を一つずつ整理していくだけ。その過程が楽しい。ミステリを読む醍醐味って結局ここだよな、と思わせてくれる。
長くミステリを読んでいると、「このタイプの密室は見たことがある」「この消失トリックはあれに近い」と感じる瞬間がどうしてもある。
だが『ジェミニー・クリケット事件』は、そうした既視感をうまく利用する。知っているからこそ油断し、その油断を静かにすくい取られる。
派手な演出はない。だが、論理が組み上がっていく過程そのものが、十分にスリリングだ。
犯人当てをしているのは、誰なのか
物語の中で、ジャイルズと老人ははっきりと「ゲーム」をしている。
ハント・ザ・マーダラー。
つまり、犯人当てゲームだ。
ジャイルズは、警察が得た情報、証拠、状況を順番に提示していく。老人はそれを聞きながら、「これは純粋な論理の問題だ」と言わんばかりに推理を進める。感情は挟まない。死は出来事の一部でしかない。
ここが非常に重要なポイントで、読者もまた、ほぼ完全に老人と同じ位置に立たされる。提示される情報はフェアだ。隠されてはいない。だからこちらも、自然と推理を始めてしまう。
だが、少し冷静になると、かなり居心地が悪い。人が殺されている。しかも、その死について、関係者が目の前で語っている。にもかかわらず、それをパズルとして消費している。
この構造自体が、かなり批評的だ。ミステリというジャンルが、そもそも「殺人を娯楽として扱う」形式であることを、ブランドはあえて剥き出しにしてくる。だから「殺人ゲーム」なのだろう。これは事件の話であると同時に、遊びの話でもある。
そして、気づけばこちらもそのゲームに参加している。
語り手は、本当に信用していいのか
さらに厄介なのが、語り手が事件の関係者だという点だ。ミステリをそれなりに読んできた人なら、この時点で警戒心が働く。
語り手は信用できるのか、という問題だ。
クリスティの『アクロイド殺し』以降、語り手を疑うのはもはや基本動作と言っていい。そして本作のジャイルズは、まさに疑う余地のある立場にいる。養父の死を語る当事者であり、感情や利害が絡まないはずがない。
彼は真実を語っているのか。それとも、老人を楽しませるため、あるいは自分を守るために、巧妙に物語を組み立てているのか。ブランドはこの緊張感を、あからさまに強調しない。だが、対話の端々に、微妙なズレや引っかかりを残していく。
ここでも読者は試される。
この語りを、どこまで信じるのか。
振動するガラスという、完璧すぎる密室
この作品の中核にあるのは、やはり密室殺人だ。被害者は弁護士トマス・ジェミニー。自分の事務所、四階の部屋で、椅子に縛り付けられたまま刺殺されている。
状況は完璧だ。ドアは内側から閂がかかっている。窓は割れているが、四階からの脱出は現実的ではない。
そして決定打が、「ガラスがまだ振動していた」という事実だ。警察がドアを破って踏み込んだ瞬間、割れた窓ガラスは、まだ微かに揺れていた。つまり、犯人はつい今しがたまでそこにいたことになる。
だが、部屋には誰もいない。物理的には、完全に矛盾している。
この「振動するガラス」というディテールは、本当に美しい。視覚的で、直感的で、しかも論理的だ。カーの密室講義を地で行くような構造で、密室好きにはたまらない一手になっている。
消えた警官と、「長い腕」の話
さらに話は終わらない。事件を追っていた警官が、今度は同じ手口で殺される。縛られ、刺される。しかも彼は、殺される直前、警察署に電話をかけている。
その内容が、また不気味だ。「空気の中に消えた」「長い腕が見える」。理性的な警官の口から出るとは思えない言葉が並ぶ。
ここで、事件は一気に怪談じみてくる。だがブランドは、超自然に逃げない。二つの事件をつなぐのは、あまりにも日常的な凶器──ジェミニーの机から消えたペーパーナイフだ。
事務用品が殺人の道具になり、それが不可能な状況を越えて移動していく。この「日常が少しだけズレる」感覚が、ブランドの持ち味だと思う。派手な怪異はないのに、妙に怖い。
結末が二つある、という地獄
この作品について語るとき、どうしても避けられないのが「結末が二つある」という事実だ。アメリカ版とイギリス版。どちらかが完全版で、どちらかが間違い、という単純な話ではない。両方とも、ちゃんと作品として成立している。
ここが、この作品の一番恐ろしいところだと思う。普通、結末が変われば論理が破綻する。あるいは、どちらかが明らかに弱くなる。だが『ジェミニー・クリケット事件』では、どちらの結末も論理的に通ってしまう。
つまり、どこで「真実」を確定させたかによって、物語の意味が変わってしまう。これはミステリとしては相当危険なことをやっている。探偵小説というジャンルは、基本的に「真実は一つ」という前提の上に成り立っているからだ。
ここで読者は、自分が何を信じて読んできたのかを突きつけられる。語り手の言葉か、積み重ねられた論理か、それとも自分の直感か。二つの結末は、その選択を否応なく意識させる。
しかもブランドは、これを重苦しく提示しない。あくまで軽やかに、あくまでゲームとして差し出してくる。その態度が逆に残酷だ。読み終えたあと、「あれはどっちだったんだ?」と考え始めた瞬間、この物語はまだ続いている。
ちなみに、創元推理文庫から出ている『短編ミステリの二百年6』には、アメリカ版とイギリス版の両方が収録されているので、どちらも読みたいという方はぜひ。
洗練された悪意が最後に残すもの

『ジェミニー・クリケット事件』は、過去の名作として棚に収まるタイプの作品ではない。今読んでも、かなり挑発的だ。
まず、パズルとしての完成度が高い。振動するガラス、消えた警官、密室。これらが、余計な装飾なしに、きれいに一つの解へと収束していく。その過程には、ミステリを読む喜びが詰まっている。論理が美しい、という感覚を久々に味わえる。
次に、文章と会話のキレがいい。ブランドの会話文は軽やかだが、油断すると痛いところを突いてくる。何気ない言葉の裏に、悪意や自己保身、そして人間の曖昧さが透けて見える。その冷たさが、物語に独特の後味を残す。
そして何より、この作品は「体験」として変だ。読んでいるうちに、知らないうちにゲームに参加させられている。推理しているつもりが、推理されている側に回っている。その感覚が気持ち悪くて、同時に気持ちいい。
ミステリに、ただの謎解き以上のものを求めているなら。
この作品は、今でも十分に刺さる。
ただし一つだけ言っておく。
この殺人ゲームの参加費は、安心して物語に身を委ねる、その感覚そのものだ。
それを差し出す覚悟があるなら、ぜひこのビュッフェの席に着いてほしい。