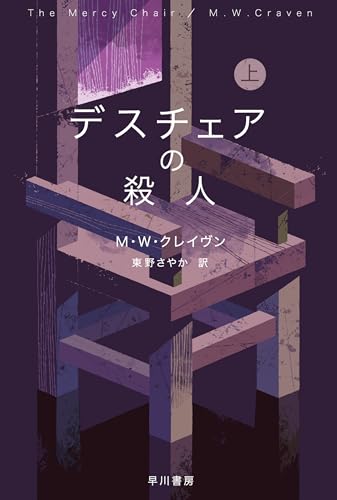ミステリというジャンルは、読者の好みに応じていろんな系統に枝分かれしている。
密室、叙述トリック、社会派、サイコスリラー……でも、いざ「今おすすめの現代クライム・フィクションを教えてくれ」と訊かれたときに、真っ先に挙げたくなるのが、M・W・クレイヴンの〈ワシントン・ポー〉シリーズだ。
今回の『デスチェアの殺人』はシリーズ6作目。シリーズもののこの位置にきて、ここまで全部盛りでありながら破綻しないのは本当にすごい。読み終わった直後、「これは文学的事件だな」と思った。
エンタメとしての完成度、人物造形の緻密さ、語りの構造の巧妙さ、舞台となるカンブリアの重み、そしてあの名コンビ。全部がちゃんと生きている。
英国推理作家協会のゴールド・ダガー賞をデビュー作でかっさらったのも納得だ。何よりも、読んでいて「この人は本物だな」と感じさせる説得力がある。軍隊、犯罪学、保護観察官。そういった著者のキャリアが、そのまま作品の骨格を形づくっている感じだ。
「フィクションなのにリアルすぎる」「リアルすぎて逆に安心できる」
そんな奇妙な感覚がずっとつきまとう。それこそが、M・W・クレイヴンの最大の魅力だと思う。
闇と光、ポーとティリーの奇跡的バランス

このシリーズの心臓部は誰がなんと言おうと、ワシントン・ポーとティリー・ブラッドショーのバディだ。犯罪捜査小説においては珍しくない組み合わせだが、この二人の関係性は、もはや一種の芸術レベルに達している。
ポーは、いわゆる「アンチヒーロー」。組織に馴染まない、だけど現場では無類に強い。陰鬱で偏屈、でも根はものすごく情が厚い。彼のキャラクターがシリーズを支える屋台骨であることは間違いない。
で、そこにぶつかってくるのがティリーだ。IQ200超、数学の天才、でも人との会話が苦手な分析官。極端に社会性に欠けているけど、そのぶんピュアで、真っ直ぐで、強い。
この対極な二人が組むことで、物語はただの暗い警察小説ではなく、ものすごく人間臭くて、愛おしいものになっていく。クレイヴンは、あえてどぎつい暴力や陰鬱な雰囲気を描く一方で、ティリーの突飛な行動やポーのあたたかさで、読者に小さなユーモアと救いを用意してくれる。
それがなかったら、とてもじゃないがこのシリーズは読んでいて辛い小説になっていたかもしれない。
でも実際は真逆だ。読むたびに「ああ、またこの二人に会えた……」という安心感すらある。
だからこそ、今回のようなポーの精神がギリギリまで追い詰められる物語は、読んでいて本当にこたえる。
あいかわらず、舞台設定の説得力がすごい
舞台はいつもどおりカンブリア州。牧歌的な自然と、恐ろしい犯罪。このギャップがこのシリーズのもう一つの魅力だ。
日本で言うなら、絵本に出てきそうな里山で連続殺人事件が起きてるようなイメージである。でもそれが妙にリアルで、怖い。そしてこの土地がただの背景じゃなくて、登場人物の心理や、物語全体のトーンにまで影響を与えてくる。
しかもクレイヴンはこの土地に実際に住んでいた人間だから、土地の描写に熱がある。観光ガイドっぽい説明じゃない。もっと、地面に足をつけた書き方だ。雨の冷たさ、石造りの家の湿気、風の強さまで肌で伝わってくる。
その手触りがあるからこそ、ストーンサークルでの焼殺、山奥の施設、湖の底に沈んだ秘密……どれもがリアリティを持って迫ってくる。風景そのものがミステリを語っている感じだ。
そして『デスチェアの殺人』——これは痛みの物語だ
さて、本題である。
『デスチェアの殺人』
タイトルからして不穏だが、中身は予想以上にヘビーだった。しかも、いつもと違う形式で始まる。ポーが精神科病院でセラピストに語るという形で、事件を回想する構成。つまり、最初から「何かがあった」ということだけが提示されていて、読者はその何かを探りながら読み進めることになる。
事件の発端は、あるカルト教団の指導者が、木に縛り付けられ、石打ちという中世の宗教的刑罰で殺されるという猟奇的な事件。まるで儀式のような手口に、捜査陣は戦慄する。
被害者の身体には、自ら刻んだとされる難解なタトゥーが残されており、その内容はティリーをして「意味は読み取れても、解読はできない」と言わしめるほどの代物。まるで数学的構造と暗号が混在したような情報の迷宮だ。
この奇怪な事件がきっかけとなり、ポーたちは15年前に起きた忌まわしい未解決事件——少女による一家惨殺という凄惨な過去へと引き戻される。裁判記録すら黒塗りだらけのこの事件には、どうにも腑に落ちない点が多すぎた。
さらに、捜査線上に浮かび上がるのが「慈悲の椅子」という都市伝説めいた存在。「それに触れた者は死を選ぶ」という話が広まり、人々は語ることすら拒絶する。やがて本当に、椅子にまつわる証言者たちが次々と自殺していく。
チームは追い詰められ、精神的にも物理的にも消耗していく。そして追い打ちをかけるように、SCASの内部に送り込まれたスパイの存在が明らかになり、組織そのものが揺らぎ始める。
ポーはセラピストに語りながら、何かを伏せている。断片的な回想、明かされない空白。そしてついに、“あの出来事”へとたどり着く。そこはあまりにも重く、深く、静かな崩壊の場だった。
この構成がずるいくらいに上手い。事件の謎と、ポーという人物の崩壊を、二重構造で描いていく。でも全部がちゃんと繋がっていく。バラバラだったピースが、気づけば一枚の不気味な絵になっているのである。
読者は、ただ推理するのではない。ポーの視線で、彼の沈黙で、すべてを体験してしまうのだ。
そしてこのシリーズのファンとして、ラストはもう、言葉にならなかった。
このシリーズを追ってよかったと心から思う

読書後は放心状態だ。
でも、これだけ重い事件を描いているのに、シリーズ全体にはどこかあたたかさがある。それはきっと、登場人物たちが本当に丁寧に描かれているからであり、読者が彼らの人生に長く寄り添ってきたからだと思う。
ミステリとして面白いのはもちろん。でもこのシリーズの本当の価値は、そこじゃない気がする。
「人は痛みにどう向き合うのか」
「正義って、ほんとにあるのか」
「信じることに意味はあるのか」
クレイヴンは、そんな問いを私たちの心にそっと置いていく。それが、派手なトリックやどんでん返しよりずっと深く残るのだ。
というわけで、『デスチェアの殺人』は、今のところシリーズ最高傑作かもしれない。というか、新作が出るたびに最高傑作を更新し続けているんじゃないか、とすら思う。
次回作がどうなるのか、今はまだ想像できない。
でもポーとティリーがまた歩き出すなら、どこまでもついていきたい。