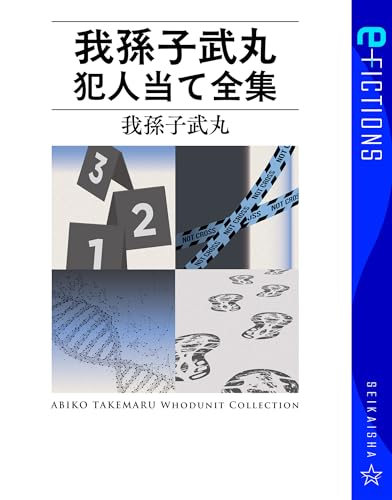まず断っておくが、この本は“読む”ものではない。“戦う”ものである。
『我孫子武丸犯人当て全集』
なんとも潔いタイトルだけど、中身はそれ以上にストイックで知的なリングだった。
相手は、あの『殺戮にいたる病』で読者の認知をぶっ壊した男であり、『かまいたちの夜』でノベルゲームの可能性を切り拓いた男。
我孫子武丸(あびこ たけまる)だ。
その彼が、冒頭でこう言い切る。
「今回はちゃんとフェアに作ってます」と。
あの最も信用できない語り手が、堂々とフェアプレイ宣言しているのだから、こちらも覚悟がいる。これは、読者と作家との間のガチの一騎打ち。犯人当てというミニマルなフォーマットで、純度100%のミステリに挑むのだ。
言ってみればこれは、「出題編と解答編のある推理クイズ」が、プロの小説家によって全力で仕立てられているようなもの。しかも、解答だけじゃなくて「この問題をどう作ったか」という裏話までついてくる。最高すぎるでしょ。こんな贅沢な体験、そうそうできるもんじゃない。
この本を読むってことは、我孫子武丸の本気を真っ向から受け止めるということだ。そしてこっちも全力で応じる。
つまりこれは、作者と読者がお互いに正面から殴り合うために用意された舞台なのである。
論理の迷宮、その構造を読む快感

本書の収録作は全部で5編。それぞれの事件が完全に独立しており、それぞれ異なる趣向とロジックで構成されている。
舞台は現代の屋敷から近未来、海辺の町までバラエティ豊か。しかし、どの作品にも共通しているのは「すべての手がかりは提示されている」という鉄のルールだ。
このルールって実はめちゃくちゃ難しい。だって、ウソはついちゃいけない。でも読者には真相を見抜かれちゃいけない。一体どうするのか?って話だが、そこを巧妙な言い換えや配置、読者心理の誘導なんかで、鮮やかに煙に巻いてくる。
ミステリってのは、こういうロジックの芸術なんだよなあ、とあらためて実感した。
各作品は「問題編」と「解決編」に分かれていて、問題編の最後で「あなたも考えてみてください」と挑発される。ページをめくる手をぐっとこらえて、自分なりの仮説を組み立てる時間こそ、この全集最大の醍醐味だ。
そして嬉しいのが、各編の最後に付いている自作解説だ。ここで我孫子武丸が、まるで答え合わせの教師のように「これはこう仕掛けました」「ここで引っかかる人が多いんですよ」と解説してくれる。この解体ショーがもう最高で、「ああ、自分はこの罠にまんまと引っかかってたな……」と苦笑する瞬間すら愛おしい。
「読み終えて終わり」じゃない。答えを知ってからがもう一段階楽しい。まるでプロの料理人がキッチンの裏側を見せてくれるような、そんな気持ちになる。
新本格という伝統と、作家としての幅
我孫子武丸は、新本格第一世代のひとりだ。綾辻行人や法月綸太郎と並び称される存在であり、そのルーツは京大ミステリ研にある。
この「ミステリ研出身」という肩書きは、実はかなり強いブランドだ。フェアプレイ至上主義、地の文に嘘はNG、提示された情報だけで解ける構造。
そんな「厳格なミステリの作法」が叩き込まれた人たちが、1980年代後半に一気にデビューして、国内ミステリをガラッと塗り替えた。そんな時代の申し子が、この全集で「犯人当て」という極限まで純化された形式に挑んでいるわけだ。
でも面白いのは、我孫子武丸ってその厳格な本格だけの人じゃないという点だ。サイコスリラーも書くし、ユーモア系もいけるし、ノベルゲームの脚本までやってのける。
この振れ幅の広さがすごい。そしてその上で、「今回はあえて縛ります」と言ってフェアな犯人当てに特化する。この引き算の美学に痺れてしまう。
読者に不安を与える『殺戮にいたる病』のような叙述トリックとは真逆のアプローチで、「誰が読んでも解けるように作りました」と堂々宣言する姿勢。
ここに作家としての誠実さと、ジャンル愛がにじみ出ていて、なんだかグッときてしまう。
推理する歓び、バレずに引っかかる愉しみ
収録作についてネタバレなしで言及するのは難しいが、印象に残ったものを少しだけ挙げてみる。
たとえば『盗まれたフィギュア』は、密室×アリバイ×オタク文化の三重奏。動機の切り口も秀逸で、なるほどそう来たかと唸らされた。事件の舞台もディテールも、全部がちゃんと考えられてる感じがあって、読みながらうれしくなる。
『記憶のアリバイ』は、近未来設定を利用した記憶の検証性にまつわる論理ミステリ。設定がSFっぽいぶん一見複雑だが、ちゃんと読めば解ける構造になっているのが見事だ。特殊設定ミステリの良さが詰まっている。
『幼すぎる目撃者』では、子供の証言をどう読み解くかが焦点となる。物理トリックではなく、言語と心理の読解力が問われる、まさに柔らかい頭が求められる作品だった。大人の理屈で突き詰めてはいけない、でもロジックは絶対にある。その匙加減が絶妙だ。
すべての作品が、単なるクイズやマジックではない。きちんと物語として成立していて、その上で論理的にも完璧に構築されている。この二重の完成度が、本当に嬉しい。
「当てる」だけじゃない、「学ぶ」ための全集
本書の構造は、「問題編」→「解決編」→「作者解説」という三段構えになっている。この最後の「作者解説」が素晴らしい。
そこでは、作者がどうやって物語を組み立てたか、どこで読者を騙そうとしたか、どんな技術的な苦労があったかまで語られている。まさに構造の開示だ。
つまりこの全集は、犯人当てという遊戯を楽しむだけでなく、ミステリというジャンルそのものを学ぶ教材としても読めるのだ。これは、知的エンタメとジャンル研究書が奇跡的に同居している構成だと思う。
最後に。
本書は、「謎を解きたい」人にとっては最高の遊び場であり、「謎を作りたい」人にとっては最高の教科書でもある。
わたしたち読者はそのどちらにもなれる。そして、どちらであっても、我孫子武丸という論理の魔術師と対等に対峙できる。
この挑戦状を受け取るかどうかはあなた次第だ。だがひとつ言えるのは、「受けてよかった」と思える極上の体験が確かにある。
こんなにも誠実で知的な読み応えをくれる作品集が、いったいどれだけあるだろうか。
そう考えると、これはもう「ミステリ好きのための祝祭」と言ってしまっていいと思うのだ。