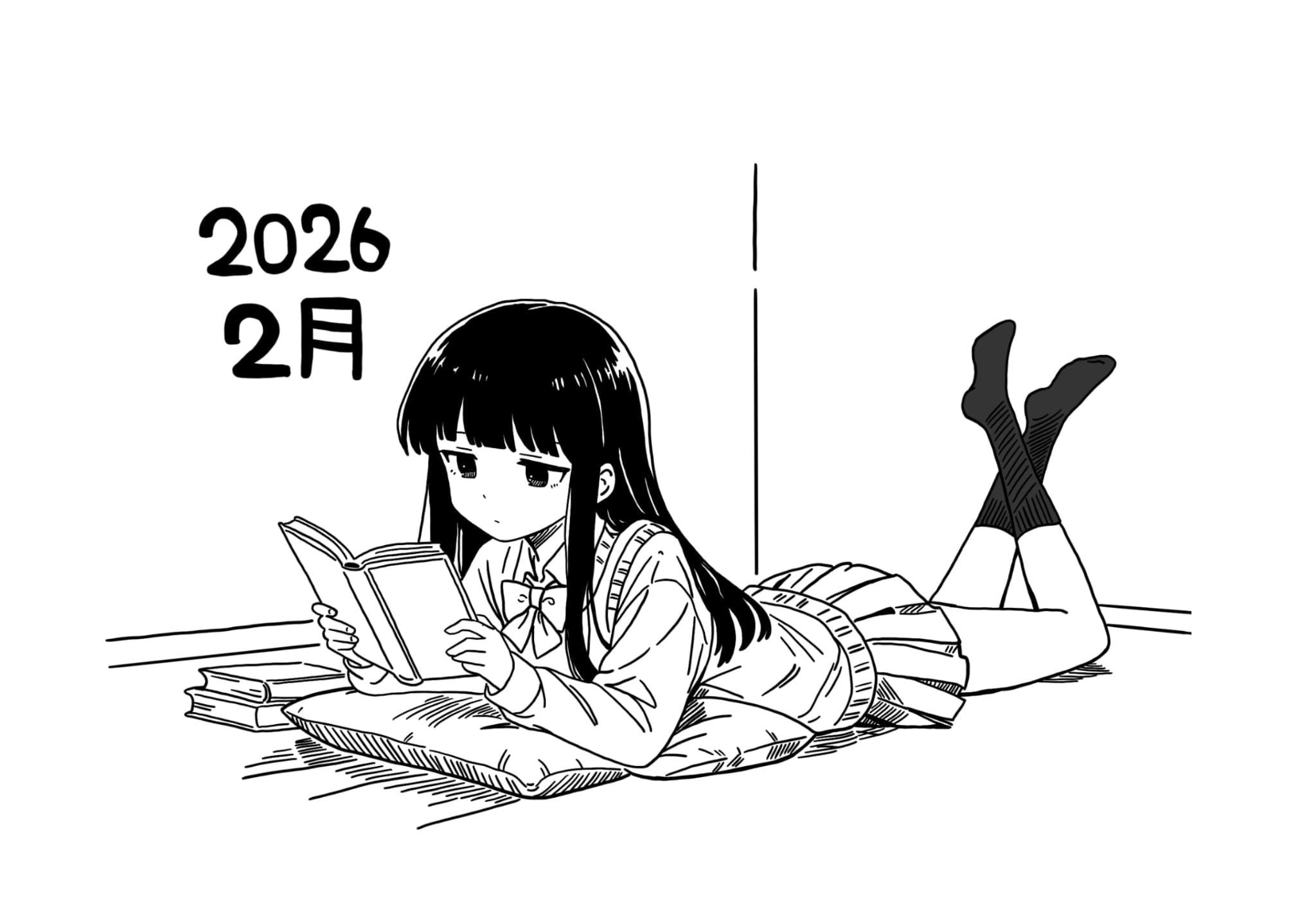今さら新しいミステリなんて、もうなかなか出てこない。
そう思っていた時期が、私にもあった。
でも2019年、相沢沙呼が『medium 霊媒探偵城塚翡翠(じょうづか ひすい)』を出してきたとき、空気が変わった。これは事件だった。完全に予想外の角度から殴ってくる、ジャンル破壊級の一作だったのだ。
「このミステリーがすごい!」2020年版第1位をはじめ、本格ミステリ・ベスト10、SRの会ミステリーベスト10、本格ミステリ大賞、Apple Booksベストミステリーまで、主要な賞を総なめにしてしまった。
読者投票系と評論家評価系、どちらも制した五冠はそうそう見ない。勢いとか流行りとかを超えて、読んだ人がちゃんと驚いて納得した結果が、この数字に表れている。
相沢沙呼といえば、デビュー作『午前零時のサンドリヨン』や『マツリカ・マジョルカ』で知られる作家で、青春小説や日常系ミステリを丁寧に書いてきた人という印象が強かった。
しかし『城塚翡翠』シリーズは、その作風を土台にしながら、ミステリとしての強度と構造の面白さを極限まで突き詰めた作品だった。ただの謎解きではない。登場人物の心理や倫理まで射程に入れたうえで、フェアでありながら容赦なく読者を騙してくるのだ。
そして、このシリーズが面白いのは、単発で終わらなかったことだ。
第1作『medium』で衝撃的などんでん返しを見せたあと、続く『invert』ではまさかの倒叙ミステリへと大きく舵を切る。しかも、形式が変わってもキャラクターはしっかり地続きで、その変化すら物語の一部として機能している。
驚かせて終わりではなく、進化させて続ける。その構造こそが、このシリーズの真骨頂だ。
この記事では、『medium』での破壊と、『invert』シリーズでの再構築という二段階の展開を軸に、《城塚翡翠(じょうづか ひすい)》という現象をご紹介したいと思う。
これは、ただの人気シリーズではない。
探偵小説というジャンルの「その先」を示してしまった作品だ。
1.すべてが伏線、すべてが罠── 『medium 霊媒探偵城塚翡翠』
ページを開いた瞬間から、罠は始まっている。
相沢沙呼『medium 霊媒探偵城塚翡翠』は、そんなタイプの小説だ。犯人が誰か、トリックがどうか、それすらも前座と感じてしまうくらい、もっと大きな何かが仕掛けられている。
とにかく一度読んでほしい……と言いたいところだが、それじゃあ解説にならないので、できるだけネタバレを避けながら紹介していく。
まずはざっくり設定から。推理作家の香月史郎は、霊媒を名乗る城塚翡翠と出会う。彼女は死者の声を聞き、犯人を視ることができる。ただしその証言には、法的な証拠能力がない。
だからこそ、香月の役割が重要になる。翡翠の語った真実を出発点に、彼は論理的に事件を組み直し、警察が動けるような証明を構築していくのだ。
この超常×ロジックという構図だけでもう面白いのに、物語の深部ではまったく別の次元のゲームが進行している。
犯人当てでは終わらない罠
本作のキモは、単なる事件の謎解きではなく、「この物語自体が何なのか」という構造にある。叙述トリックという言葉があるけれど、『medium』の場合、それが一点突破のどんでん返しではなく、物語全体を包み込む巨大な仕掛けとして機能している。
翡翠の振る舞い、香月の内面描写、服装の細かい描写、さらには物語のテンポや語りのトーンにいたるまで、すべてが緻密に設計されている。
読んでいるうちに、無意識に「こういう話なんだろう」と決めつけてしまう。その思い込みこそが、この作品最大の武器である。
言ってしまえば、これは「ミステリの常識」を逆手に取った作品だ。丁寧で誠実な語りに見せかけて、その実、足元をすくってくる。しかも悪意じゃなく、笑顔でやってくるタイプの裏切り。
しかも、再読したときに「あれは全部そうだったのか!」と悶絶するタイプ。やられた、と思うと同時に、ニヤけてしまうあの感覚。あれだ。
城塚翡翠というキャラクターの力技
この仕掛けが成立している最大の理由が、ヒロイン・城塚翡翠の存在である。彼女は霊媒としての不思議さと、少女らしい儚さと、理屈じゃ説明できない引力を兼ね備えている。そして、その魅力そのものがこの物語において非常に重要なギミックとして機能してくるのだ。
繊細で脆そうで、それでいて芯がある。そんな人物造形に説得力を与えているのが、著者・相沢沙呼の心理描写だ。しかも、あえてライトノベルっぽさを漂わせている部分がミソ。可愛さ、甘さ、ちょっとした演出過剰。それすらも罠なのだと気づいた瞬間、すべての意味が反転する。
これは、キャラクターという存在そのものを、構造上のトリックとして利用している例としてもかなり稀有だと思う。しかも、感情的なリアリティがきちんとあるから、技術的な仕掛けに見えない。
だからこそ、騙される。気づいたときにはもう手遅れだ。
とんでもなく精密なロジックと、霊視というファンタジー、そして物語に仕掛けられた罠、という構造トリック。全部をまとめてぶち込んできたのが『medium』だ。
この作品、気づけば頭の中まで占拠されている。
そういう意味では、この本はある種の悪魔なのかもしれない。
2.弱き霊媒から「知の女王」へ── 『invert 城塚翡翠倒叙集』
最初の一手が、すでにチェックメイトだった。
そんな戦慄を、物語の冒頭から味わう。
相沢沙呼『invert 城塚翡翠倒叙集』は、前作『medium』での衝撃的な結末を経て、形式もヒロインも完全に裏返った作品だ。いわゆる倒叙ミステリで、犯人が誰かは最初からわかっている。
では、何を楽しむか?
そう、「どうやって追い詰めるか」である。
殺意を秘めた知能犯たちと、探偵・城塚翡翠との頭脳ゲームが始まる。
推理は対話で仕留める時代へ
倒叙ミステリといえば『刑事コロンボ』や『古畑任三郎』を思い出す人も多いと思う。だけど、相沢沙呼はその形式にとどまらず、会話と観察の応酬による心理戦を徹底して描いてくる。
城塚翡翠の武器は、超常でも暴力でもない。観察、推理、論理、そして会話。相手の矛盾を引き出すような軽やかな尋問で、犯人の計画に潜む綻びを次々と剥がしていく。
たとえば、犯人がうっかり口にした一言。そこに宿る違和感を翡翠は絶対に見逃さない。表情のわずかな揺れ、会話のリズムの乱れ、言葉の選び方。そういった空気のノイズから真実を引きずり出してしまうのだ。
これがまた怖い。読んでいて、自分が尋問されてる気分になる。
ああ、この人には絶対にウソをつけない、と思わされるタイプの探偵がついに誕生した。
解き放たれた探偵・翡翠の本性
『medium』では、翡翠は守られる側の少女だった。儚げで傷つきやすく、超常の力に苦しむ姿が印象的だった。
しかし『invert』ではまるで別人だ。知性とウィットをまとった、自信満々の知的捕食者。相手の誤算を嗅ぎ取り、わざと泳がせて、最も効果的なタイミングで仕留める。
まるで狩人。いや、女王か。
しかも、その変貌は唐突ではない。むしろ『medium』の結末を踏まえれば、この転身は「あれを経たからこその必然」だった。心を閉ざしていた少女が、痛みとともに自分を受け入れたとき、ようやく本来の力を発揮できるようになったのだ。
だからこの倒叙形式こそが、翡翠というキャラクターが最も輝く舞台になっている。これ以上ふさわしい再出発はない。
犯人視点から始まるからこそ、読者にはすべてが見えている。アリバイもトリックも動機も全部わかっているのに、それでも翡翠の推理を追う手が止まらない。この逆説的な面白さは、倒叙ミステリだからこそ味わえる醍醐味だ。
そして何より、これは翡翠というキャラクターの覚醒を描いた物語でもある。盤面に立つ側ではなく、盤上を見下ろす側へ。知性の勝負において、もはや彼女は無敵だ。
相手がどれだけ完璧な手を打とうが、彼女の一手で全てが崩れ去る。
それが『invert』。
これは、ミステリという名のチェス盤に現れた、最強のクイーンの物語だ。
3.論理の女王に、感情の揺らぎが訪れたとき── 『invert II 覗き窓の死角 城塚翡翠』
追い詰める側だったはずの探偵が、自らの正義にぐらつく瞬間があるとしたら。それは一体どんな顔をしているのか。
『invert II 覗き窓の死角 城塚翡翠』は、倒叙ミステリという舞台装置を使いながら、その中心にいる名探偵・城塚翡翠の揺らぎをあえて描いた一作だ。
形式は変わらず倒叙。だが、見せられるのは「完璧な論破劇」ではない。むしろ、探偵が人としての顔をにじませる、苦味のある物語になっている。
事件は二つ。ひとつは山荘に閉じ込められた翡翠が、目の前にいる人物こそ犯人だと確信しながら、決定的証拠を持たないまま数日間を共に過ごすという「生者の言伝」。
そしてもうひとつが、翡翠が親しくしていた写真家が容疑者となる「覗き窓の死角」だ。後者では、なんと翡翠自身がアリバイ証人となってしまい、立場が完全に逆転する。
そこに生まれるのは、探偵としての職能と、人間としての感情の衝突だ。
倒叙を極めるどころか、突き破る
シリーズがここまで倒叙形式を徹底してくるとは思ってなかったが、今回はさらに踏み込んできた。
犯人はもちろん最初からわかっている。でも、その内面や動機、行動の細部にまで光が当てられ、事件の全体像が見えてきたと思ったところで、また別の顔が立ち上がってくる。
この「知っているはずのものが、実は見えていなかった」という構造は、倒叙形式だからこそ可能な逆転だ。
そしてその構造を活かして、相沢沙呼は「倒叙ミステリの限界」そのものに挑戦している。読者に情報を与えすぎず、かといって不誠実でもない。
そのバランスの上に成立する緻密なトリックと、深く捻れた人間関係。形式の中で自ら縛りを課しながら、それを突破する快感すらある。
完璧な探偵が、人間であること
今作最大の見どころは、なんといっても翡翠の変化だ。これまでは推理装置のような存在だった彼女が、明確に人間として描かれている。
とくに、友人が殺人の容疑者になってしまうエピソードでは、自分の感情と職業倫理の間で激しく揺れる。その姿は、これまでの翡翠像を壊すというより、ようやくその中身が見えてきた感じだ。
完全無欠の探偵ではない。間違えることもあれば、迷うこともある。それでも、真実に向き合おうとする。その誠実さが、この巻ではとても大きな意味を持ってくるのだ。
一方で、犯人たちもどこか共犯者のような顔をしている。彼らはただの悪党ではない。歪んだ正義を信じていたり、身近な誰かを守ろうとしたり、自分なりの理屈を持っている。
その行動の是非を翡翠がどう判断するか。それは事件の結末以上に、この物語の心臓になっている。
完璧なロジックに、感情の揺らぎが差し込んだとき。
探偵はただの職能ではなく、一人の人間になる。
『invert II』は、そんな危うさと美しさを抱えた探偵像を描いた、シリーズの転換点だ。
論理の女王は、傷つくことすら恐れずに、真実へ踏み込んでいく。
おわりに 城塚翡翠が書き換えた現代ミステリの地図

『城塚翡翠』シリーズがこれほどまでに圧倒的だった理由は、技巧の巧さだけじゃない。
ミステリというジャンルの語りを一度壊し、そのルールごと書き換えようとした、その姿勢自体が異例だった。しかもそれを、キャラクターの成長や感情とちゃんと結びつけて描いているから、仕掛けが終わったあとも、物語としての余韻が残る。
城塚翡翠という探偵の変化。それは、ただのキャラ付けではなく、シリーズ全体の構造とリンクした大きなテーマだった。
「真実を見抜く力」とは何か。「正しさ」と「やさしさ」は両立できるのか。そういった問いが、倒叙という形式を通して、いつの間にか自分にも向けられている気がしてくる。
形式への挑戦と、物語への誠実さ。そのどちらもを突き詰めたこのシリーズは、今の日本ミステリが到達した一つの頂点だと思う。
まだ読んでいない人は、ぜひ『medium』から刊行順に読んでみてほしい。
最初のページから、すでにすべてが仕組まれている。
その精密さと美しさに、きっと圧倒されるはずだ。