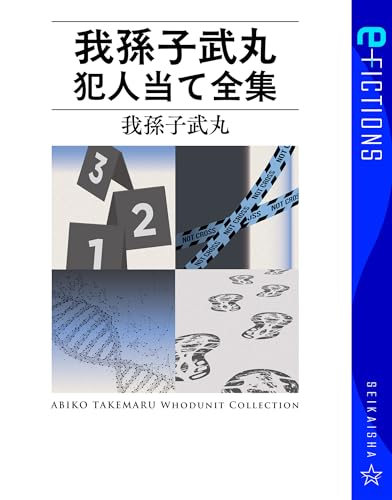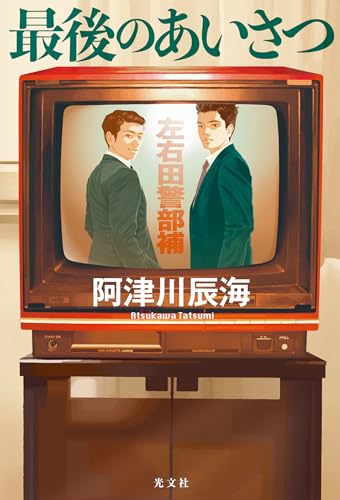四季しおり
四季しおり2025年9月に読んだ本の中から、これは面白い!と思った15冊を紹介するよー。
・2025年8月に読んで特に面白かった本17冊 – パーシヴァル・エヴェレット『ジェイムズ』ほか
・2025年7月に読んで特に面白かった本10冊 – 夜馬裕『イシナガキクエを探しています』ほか
・2025年6月に読んで特に面白かった小説7冊 – 小倉千明『嘘つきたちへ』ほか
1.作中作と現実がクロスする二重ミステリ── アンソニー・ホロヴィッツ『マーブル館殺人事件』
またホロヴィッツがやってくれた。『マーブル館殺人事件』は、作中作と現実の事件がガッチリ噛み合う、例のアレである。
メタ構造、伏線地獄、名探偵登場、意外な犯人。こんなの面白くないわけがない。
舞台に戻ってきたのは、元編集者のスーザン・ライランド。クレタ島でのホテル業を終えてロンドンに帰ってきた彼女のもとに、亡きアラン・コンウェイが生んだ名探偵〈アティカス・ピュント〉シリーズの編集の話が舞い込む。
しかし、途中までの原稿を読んだスーザンは、作者が新作に自分の家族関係を反映しているのを感じる。ということはこの作品のように、現実世界でも不審な死が存在したのだろうか?
ここからが本番。現実の殺人事件と、作中作の毒殺事件。20年前の未解決の死と、いま起こった殺人とがリンクして、スーザンが両方に首を突っ込む。しかもその作中作が、実際の事件にヒントを与えるという構造。やっぱりホロヴィッツはこういうのが天才的にうまい。
ピュントが活躍するパートは、まさにクラシカルなイギリス本格ミステリ。対してスーザン側は、現代的なスリラー風味で、毒親あり、秘密だらけの一族あり、ネットの炎上まである。時代の違いすら武器にして、二つの世界が交差する瞬間のゾクッとくる感じが最高だ。
アナグラムやら伏線回収やら、作中の細かい仕掛けも山盛りで、解いても解いてもまだ何か隠れていそうな感じがたまらない。
物語が終盤でガシャンと一つにハマる瞬間は、ホロヴィッツ作品ならではの快感だ。
二度おいしいどころじゃない、三度でも四度でもいけるミステリである。
2.鍵のかかる部屋と、裏返る真実── フリーダ・マクファデン『ハウスメイド』
屋根裏部屋の扉に鍵がかかる。しかも、外側から。
その瞬間から、ミリーの人生は「不可解な日常」へと変わっていく。
『ハウスメイド』は、人生どん底の若い女性が、裕福な家庭の住み込みメイドとして働き始めるところから始まる。だけど、そんな「救いの手」が真っ当なわけがない。雇い主の妻は常に不機嫌でヒステリック、娘は敵意むき出し、そして部屋は謎の屋根裏。それでも、夫だけは優しくて、やたらとイケメン。となれば、もう何かがおかしいのは確定だ。
この作品の凄さは、中盤で訪れる「反転」にある。語り手が変わり、視点が変わり、読者の立っていた地面ごとズレる。それまで積み上げられていた前提が、一気に裏返される感覚は、ジェットコースターの急降下に近い。そういうのに慣れている人ほど、逆にやられるタイプのやつだ。
物語の骨格は、いわゆるゴシック・ロマンスの定番。謎めいた屋敷、秘密を抱えた住人、不穏な空気。だけど、そこに現代的な家庭内スリラーのスピード感と毒気が加わって、とんでもなく引き込まれてしまう。
何より、作者が完全に「読者の裏をかく」ことを前提に物語を設計している。だからこそ、展開を予想しようとするほど、まんまと騙される仕組みになっているのだ。
最後にひとつだけ。
この家には、想像以上の秘密がある。
それを知ったとき、自分がどれだけ都合よく物語を見ていたか、痛感するはずだ。
3.読むだけじゃ終われない、ガチで勝負の一冊── 我孫子武丸『我孫子武丸犯人当て全集』
読書中に「さて、犯人は誰でしょう?」なんて聞かれたら、構えるしかない。
それも我孫子武丸が相手ならなおさらだ。
『我孫子武丸犯人当て全集』は、その名の通り「犯人当て」に特化した作品だけを集めた異色の短編集である。物語の途中で「問題編」が終了し、読者が自分の頭で推理を組み立ててから「解決編」に進むという構成。言うなれば、作者とのガチンコの論理勝負だ。
収録作は全部で11編。トリックのバリエーションも豊富で、古典的なアリバイ崩しから、コロナ禍を舞台にした最新ネタまで、時代も仕掛けもバラエティに富んでいる。テレビ番組やゲーム形式で発表された作品も含まれていて、ちょっとしたミステリ遊園地みたいな一冊だ。
ただし、この本の最大の特徴は、「全部フェアプレイ」なこと。地の文にウソなし、ミスリードはあっても反則なし。これは京都大学推理小説研究会という名門サークル仕込みの、謎解きに対する本気が貫かれているからこそ。
逆に言えば、すべての問題には必ず論理的な正解がある。読者が正しく読み取れば、犯人には辿り着けるというわけだ。
しかも、全作に我孫子本人の解説つき。トリックの裏側や構成の意図までしっかり語ってくれるので、推理が外れてもダメージが少ない(かもしれない)。ある意味で、これは解説付きの推理力診断テストでもある。
読んで終わりじゃない。考えて、疑って、論理で殴る。
読みながら脳がフル稼働するこの全集は、ミステリ好きにとって最高のエンタメである。
4.白い霧の中に潜むもの── 山口未桜『白魔の檻』
舞台は北海道の山奥。研修医と指導医がぽつんと隔絶された病院にやってくる。そこへ濃霧、地震、有毒ガス、そして死体。
はい、もう逃げ場なしである。
山口未桜『白魔の檻』は、医療×災害×本格ミステリをぎゅっと濃縮した、とんでもない密室サスペンスだ。病院の中では誰かが殺され、病院の外では毒ガスが流れ込む。人為と自然、ふたつの脅威に挟まれた動けない密室の中で、限界を超えた戦いが始まる。
何よりスゴいのは、著者自身が現役医師だという点だ。病院内の描写がとにかくリアルで、災害時の医療リソース配分や判断の重さ、医療現場の現実と限界が、事件と地続きで描かれていく。これがミステリとしても、災害小説としても成立しているのだから素晴らしい。
探偵役を務めるのは、冷静沈着でちょっと怖い医師・城崎響介。前作『禁忌の子』でも登場していた彼が、今回も論理のメスで事件を解体していく。その姿はもはや推理する外科手術だ。対する語り手の春田芽衣は、はじめは頼りない研修医だが、極限の中で成長していく。その変化もまた、読みどころのひとつ。
論理で攻めたい人にも、手に汗握るサスペンスを求める人にも刺さる一冊。とにかく息をつく暇がない。
白い霧に包まれた病院の中で、誰が、なぜ、どうやって。
答えは、霧の向こうで待っている。
5.あの刑事は、ほんとうに名探偵だったのか── 阿津川辰海『最後のあいさつ 』
あの最終回が放送されていたら、彼の人生は変わっていたのかもしれない。
『最後のあいさつ』は、テレビの中で名探偵を演じていた男が、現実でも探偵だったのか、それとも……という、いかにも阿津川辰海らしい仕掛けたっぷりの一作である。
かつて「日本で最も有名な刑事」と呼ばれた俳優・雪宗衛は、人気ドラマ『左右田警部補』の主演だった。しかし、妻殺しの容疑で逮捕され、番組は最終回目前で打ち切りに。その記者会見で雪宗はまさかの推理を披露し、別の人物の犯行を論理的に暴いてみせた。
まるで脚本通りの展開に、世間は騒然。だが、あの推理は真実だったのか? 時を経て、そっくりな手口の事件が起きたことで、過去が再び呼び起こされる。
語り手はノンフィクション作家の風見。彼の地道な取材を通して、雪宗と周囲の人々、そしてお蔵入りとなった「幻の最終回」に何が描かれていたのかが明かされていく。インタビュー形式や回想が入り混じる構成は、どこか実録ドキュメンタリーのような臨場感がある。
作中に登場するドラマ『左右田警部補』は、明らかに『相棒』のオマージュだけど、それがただのネタで終わらないところが本書のすごさだ。刑事ドラマというフィクションが、現実とどう交差し、人物の内面や社会のまなざしをどう変えていくのか。雪宗というキャラをめぐる描写には、役と現実が溶け合っていく怖さすらにじむ。
ドラマの最終回は失われた。でも、雪宗衛という謎は、まだ終わっていなかった。
6.顔のない死体が告げるもの── 櫻田智也『失われた貌』
山奥で発見されたのは、顔を潰され、歯を抜かれ、両手首を切断された遺体だった。そこまでして身元を隠そうとする意図は何なのか。
本作『失われた貌』は、この強烈なビジュアルから始まる正統派の捜査ミステリである。
物語は、ひとりの小学生が「10年前に失踪した自分の父親かもしれない」と警察に申し出るところから加速する。さらに新たな殺人も発覚し、あちこちに散らばっていた点と点が、刑事・日野の手で少しずつ繋がっていく。
この作品の真骨頂は、天才探偵のひらめきも、派手などんでん返しも使わないことだ。ひたすら聞き込み、地道に検証、コツコツと仮説を積み上げて真相へたどり着く。古き良き警察小説の伝統を、いまの時代にしっかり引き継いだ作品だ。
伏線の張り方も非常に丁寧で、些細なセリフや場面があとで効いてくる。序盤では無関係に見えたあれやこれやが、ビシッと一つの線に収束していく感覚は、まさにミステリの醍醐味。しかも、そこに人間ドラマがしっかり乗ってくるから手強い。
日野刑事はどこか不器用で、でも根っこにある「誰かを守りたい」という信念が沁みる男だ。彼の不器用さと誠実さが、複雑な事件を解くうえでの最大の武器になっていく過程がすごくいい。
最後に、タイトルの意味がふと胸に落ちる瞬間がくる。
そのとき見えてくるのは、ただの犯人探しじゃない。
人の顔、人の過去、そして、人が人を信じるということの重さだ。
7.昭和、平成、令和を駆け抜けた執念のバトン── 伏尾美紀『百年の時効』
50年前の春の夜、東京・佃島で一家三人が惨殺された。捕まったのは実行犯のひとりだけ。ほかの共犯者たちは影もつかめぬまま、事件は闇に沈んでいく。
そこから半世紀。令和になった今、関係者の変死をきっかけに、事件は再び動き出す。
『百年の時効』は、昭和・平成・令和という三つの時代を股にかけて描かれる、壮大な警察大河だ。中心となるのは、令和を生きる若手刑事・藤森菜摘。上層部の特命で、過去の未解決事件を洗い直すことになった彼女が、古い資料や証言の断片をつなぎ合わせ、かつての刑事たちの足跡をたどっていく。
昭和パートでは、ベテラン刑事・鎌田と若手の湯浅のやり取りがとにかく熱い。ぶつかり合いながらも、次第に通じ合っていく二人の姿は、警察小説の王道にして最大の見どころ。そして彼らの未練や執念が、時を超えて藤森に託される流れには、胸が熱くなる。
実在の事件や社会背景が物語の随所に織り込まれているのもポイントだ。昭和のテロや宗教問題、平成の経済スキャンダルなど、時代の空気がリアルに反映されていて、どこかノンフィクションを読んでいるような重みがある。
550ページを超える大作だが、長さを感じさせない構成の巧さが光る。張り巡らされた伏線がひとつずつ繋がっていき、ラストで「百年の時効」というタイトルの意味が明かされる瞬間には、思わずうなってしまうはずだ。
派手な爆発も、派手なアクションもない。
でもここには、刑事という職業の誇りと、物語に命を賭けた人々の魂が宿っている。
8.営業成績で命が助かる世界── 野宮有『殺し屋の営業術』
普通、殺し屋に殺されそうになったら命乞いする。でも鳥井は違った。
彼が差し出したのは、名刺とセールストーク。しかも、こう言い放った。
「ここで私を殺したら、あなたは必ず後悔します」
この時点でもう最高だ。
『殺し屋の営業術』は、トップ営業マンがひょんなことから殺し屋組織にスカウト(?)されて、命とノルマの板挟みにあいながら裏社会で成果を叩き出していく、完全にネジの外れたエンタメ小説である。でも読んでみると、これが意外と筋が通っていて笑えてゾッとしてグッとくる。
営業とはなにか? どうやって売るか? 殺しという最悪の商品に、真面目にビジネス理論を応用するこの物語、めちゃくちゃバカバカしくて、でも痛快でリアルだ。顧客の課題、競合との差別化、実行力、クロージング。全部、本気でやってる。血まみれで。
主人公の鳥井は、もともと人生に何の実感もない虚無キャラだったはずが、殺し屋稼業に足を突っ込んだ瞬間から、営業の鬼に覚醒していく。その変貌っぷりがとにかく面白いし、怖い。どこかで「人を殺すこと」より「ノルマを達成すること」のほうがヤバく見えてくるのも、本作の異常さだ。
第71回江戸川乱歩賞を「ぶっちぎりの1位」でかっさらったのも納得の内容。設定勝ちじゃなくて、ストーリーもキャラもテンポも全部ちゃんと面白い。
とにかく勢いがすごい。笑ってるうちに、いつのまにか背筋が寒くなる。
営業力で命をつなぐ男の、裏社会お仕事成長物語。
読まない理由が見つからない。
9.断罪と共感のあいだにある、静かな地獄── 辻堂ゆめ『今日未明』
「息子が父親を殺害」「恋人の連れ子が転落死」「乳児の遺体を公園に遺棄」。
どれも、見出しだけ見れば「またか」と思ってスルーしそうな事件ばかりだ。でも『今日未明』は、そんなよくあるニュースの裏側を、当事者の視点から描いていく。見出しで終わっていた誰かの人生が、ゆっくり立ち上がってくるのだ。
本作は、5つの事件を描く連作短編集。面白いのは、どの話も「報道の見出し」から始まるところだ。つまり、結果はもう最初に知らされている。そこから当事者の語りで、どうしてそんなことになったのか、その経緯が少しずつ明かされていく。いわば結末先出しスタイルのイヤミスである。
出てくる人物は、一見どうしようもない加害者ばかりだ。けど、事情を知れば印象は変わる。引きこもりだったり、誰にも頼れなかったり、追い詰められすぎていたり。もちろん犯罪は犯罪だ。でも、ただ責めるだけじゃ済まされない気持ちが、読んでるうちに出てくるのが本作の怖いところだ。
派手などんでん返しがあるわけじゃない。でも、ページをめくるたびに「うわ……そういうことだったのか」と思わされる。ひとつの事件の裏には、ちゃんと人生がある。その当たり前の事実を、嫌というほど突きつけてくる。
この作品を読み終えたあと、何気なく見ていたニュースの見え方が変わってしまう。
たった一行じゃ、人のことなんて何もわからないのだ。
10.地獄から戻った先が、また地獄だった── 櫛木理宇『悲鳴』
11年間、誘拐されて監禁されていたサチ。やっとのことで解放され、故郷の村に戻ってくる。
でもそこで待っていたのは、「よく帰ってきたね」なんかじゃなかった。陰口、嫌がらせ、同情ぶった差別、そして謎の白骨遺体。さらには「お前は偽物だ」という謎のメッセージまで。
櫛木理宇『悲鳴』は、誘拐・監禁という凄惨な事件のその後を描く物語である。普通ならハッピーエンドで終わりそうなところから始まって、帰ってきたサチが、また違う種類の地獄に引きずり込まれる。
犯人から解放されたのに、村の人間たちは彼女をちゃんと人として扱わない。ここで描かれるのは、いわゆる「二次被害」のリアルだ。
この村が、ほんとにひどい。閉鎖的で、古い価値観に染まってて、「かわいそうだね」って顔しながら、サチを傷つけまくってくる。その無自覚な悪意がたまらなくイヤだ。
しかも、ミステリとしても強烈だ。送りつけられる白骨の箱、「この骨こそ本物のサチだ」なんていう狂ったメッセージ。これは誰が、何のために仕掛けたのか。その謎を追う展開がまた重くて苦しい。
並行して描かれるのが、サチの元同級生・美幸のパート。こっちもこっちで、田舎の理不尽と戦っている。二人の人生が絡み合っていくうちに、村の奥底に隠されていた本当の闇が浮かび上がってくる。
読んでて本当にしんどい。でも、途中でやめられない。なぜなら、サチの“生きる”ってことそのものが、この物語の全てだからだ。
誰もが声をあげられるわけじゃない。
だからこそ、この物語の「悲鳴」は、ずっと耳に残る。
11.更生施設という名の地獄で、彼らは生まれ変わる── 染井為人『ひきこもり家族』
「ひきこもりをなんとかしたい」。
その一心で頼った自立支援センターが、まさかこんな地獄だとは思わなかったはずだ。
『ひきこもり家族』は、強制的に社会復帰を迫られる若者たちと、その家族の葛藤を描いた社会派サスペンスである。
更生をうたう「リヴァイブ自立支援センター」は、実態は暴力と支配による強制収容所。そこへ連行された5人の男女が、理不尽な日々に追い詰められた末、施設長を殺害してしまう。ここからが本当の物語だ。
ひきこもり問題を「個人の弱さ」や「家庭の甘さ」で片づけるような空気がいまだに残るなか、本作はその安直な図式をぶっ壊してくる。暴力で立ち直らせる? 傷を抱えたまま放り込んで、殴って脅して叫ばせて、それで更生? そんなものは回復じゃなくて、ただの破壊だ。
本作が優れているのは、施設内の視点と、施設の外で息子を案じる母親の視点を交互に描いている点だ。地獄を生きる若者と、外で苦しみ続ける親。両者の視点が交錯することで、ひきこもりという言葉の裏にある痛みが立ち上がってくる。
でもこれは、ただの悲惨な記録ではない。殺人という重すぎる秘密を共有した5人は、社会に居場所を見つけられなかった者同士で、奇妙な絆を育んでいく。血のつながりじゃない。でも、生きるために必要なつながり。
彼らは家族になっていく。社会が拒絶したその外側で。
タイトルの『ひきこもり家族』が指すのは、最初は問題を抱える家庭のことだった。でも読み終える頃には、別の意味に変わっていることに気づく。
これは、引きずり出され、居場所を失った者たちが、ゼロから作り上げた新しい家族の物語である。
12.正しさ全振りの世界で、赤ずきんが論理でぶん殴る── 青柳碧人『赤ずきん、イソップ童話で死体と出会う。』
「うさぎとかめ」が殺人事件の被害者で、「アリとキリギリス」がアリバイの伏線。
そんな世界に不時着してしまったのが、名探偵・赤ずきんだ。
今度の舞台は、あの有名なイソップ童話の世界。……のはずなのに、様子がおかしい。教訓だらけのほのぼの寓話かと思いきや、そこには「不実な者は即・氷漬け」という恐怖支配のルールが存在していた。番人イソップ、道徳をこじらせすぎである。
『赤ずきん、イソップ童話で死体と出会う。』は、童話×殺人×論理のフルコース。誰もが知ってる「うさぎとかめ」や「アリとキリギリス」の話が、赤ずきんの前ではミステリの舞台に早変わりする。競争が殺人の動機になったり、アリバイのトリックに使われたりと、元ネタの使い方がうますぎる。
もちろん今回も、赤ずきんの推理はキレッキレだ。かわいい見た目にだまされてると、例の決め台詞が炸裂する。「あなたの犯罪計画は、どうしてそんなに杜撰なの?」……これを言われたらもう、犯人は泣いて謝るしかない。
面白いのは、ただの謎解きで終わらないところだ。今回の敵・イソップは、正しさという名の暴力をふるってくる。その道徳に背いたらアウト。しかも、反論の余地なし。まるで現代社会にいる正義のフル装備おじさんみたいで、本気で怖い。
そんな世界に立ち向かう赤ずきんの武器は、魔法でも剣でもなく論理。すべてをルールと感情で押し切ろうとする世界に、冷静な推理で風穴を開けていく姿は、ちょっとスカッとするくらい格好いい。
殺人と教訓が交差する世界で、頼れるのは論理だけ。
寓話をぶった斬り、正しさを疑い、赤ずきんは今日も名推理を決めてくれる。
13.因習の村で、少女たちは神に抗った── 杉井 光『羊殺しの巫女たち』
山に囲まれた閉鎖集落・早蕨部村。
そこでは12年に一度、未の年に生まれた6人の少女が神の巫女として選ばれる。……と言えば聞こえはいいが、実態はもっとキツい。
神聖な祭りのはずが、なぜか血が流れ、人が死ぬ。そして少女たちは、ある「約束」を交わす。
「12年後、私たちでこの村を終わらせる」。
『羊殺しの巫女たち』は、1991年と2003年、2つの時間軸で進む青春ホラーミステリだ。前半では少女たちが因習の中で恐怖と疑念を募らせていき、後半では成長した彼女たちが約束を果たすため、再び村に戻ってくる。だがその帰郷を待ち構えていたかのように、またしても異様な死体が――。
本作は、まごうことなきフォークホラーだ。閉ざされた村、奇怪な儀式、口を閉ざす大人たち、不気味な神。どれもが王道だが、だからこそゾワッとくる。美しく幻想的な文体と、そこに潜む残酷描写のギャップが強烈で、読み心地はずっと不穏そのものだ。
しかもこの物語、ただ怖いだけじゃない。核心には巧妙なトリックが仕掛けられており、「ネタバレ厳禁・二度読み必須」と言われるのも納得の構成である。読了後、物語全体がまったく別の意味に変わる。その構造自体が、記憶やトラウマの再評価プロセスとシンクロしていて、めちゃくちゃ深い。
でもやっぱり一番刺さるのは、少女たちの絆だ。大人たちの支配と伝統に抗おうとする6人の想いは、まっすぐで痛々しくて、だからこそ切ない。
この作品がホラーミステリであると同時に、100%の青春小説でもあるというのは本当にその通りだ。
犠牲の上に築かれた「神聖」を、少女たちは信じなかった。
だからこそ、彼女たちの物語は美しく、そして痛いほどに悲しい。
14.フィクションを書くたびに、現実が壊れていく── 原浩『身から出た闇』
この本は、とにかくすごい。ホラー小説なのに、書いてる最中の制作過程そのものがホラーになっているのだ。
しかも、「角川ホラー文庫」編集部から執筆依頼を受けた原浩(実在)が主人公。出てくるメールも打ち合わせもリアル。これはもう、ほとんど実話だ(ようにしか思えない)。
『身から出た闇』はモキュメンタリー、つまり「ドキュメンタリー風の虚構」を使った、異常に没入感の高いメタホラーである。短編ホラーを書けば書くほど、担当編集者が次々とおかしくなっていく。まるで原稿に込められた何かが、現実を侵食していくような気味悪さが全編に漂う。
収録されている短編も粒揃いだ。「SNSアプリがやばい話」「呪われた橋」「エレベーターに閉じ込められる怪異」など、日常に潜む微細な不安が、いつのまにか取り返しのつかない闇に変わっていく。この粘りつくような恐怖が、読み終わってからもずっと頭に残る。どの話も、日常と怪異の境界が曖昧になっていく過程が恐ろしく上手い。
で、極めつけはこの構造だ。
読者自身が「恐怖を読みたがったからこそ、これが起きた」と告げられるラストのゾクッとくる気持ち悪さ。「それを求めたのはあなたでしょう?」という一文が、本当に刺さる。
ホラーを消費するという行為自体が、怪異の片棒を担ぐことなのだと突きつけられたとき、もうページを閉じても逃げられない気分になる。
読み終えて思う。
「なんで読んでしまったんだろう」
でも、怖いもの見たさでページをめくったのは自分だ。
まさに“身から出た闇”である。
15.伝承が仕掛けた「完璧な犯罪」── 原浩『蜘蛛の牢より落つるもの』
水が引いたダムの底から、村が出てくる。
それだけで怖いのに、そこはかつて集団生き埋め事件が起きた場所。さらに「比丘尼の呪い」だの「蜘蛛の災い」だの、イヤな伝承がてんこ盛りである。
原浩『蜘蛛の牢より落つるもの』は、伝奇ホラーと思わせておいて後半で一気に論理ミステリーへと舵を切る、仕掛けの効いた傑作だ。取材のため干上がった湖にやってきたフリーライター・指谷は、次々と起きる不穏な現象に翻弄される。
異様な数の蜘蛛、消える痕跡、古い言い伝え……。だが、真に恐ろしいのは「何か」ではなく「誰か」だった。
物語の空気をガラッと変えるのが、探偵役・北斗総一郎の登場だ。前作『火喰鳥を、喰う』でもおなじみの彼は、相変わらず胡散臭い。けれど、その胡散臭さを超えてくる観察力と論理が冴えわたる。超常現象の皮を一枚ずつ剥いでいく彼の推理は、まるでホラーに殴り込みをかける古典探偵のようで痛快である。
この作品の面白さは、伝承がただの雰囲気装置で終わっていないところだ。「比丘尼」や「蜘蛛」の話は、犯人たちにとっては神話ではなくトリックの部品なのだ。
土地の記憶と迷信を利用し、理不尽な呪いとして事件を煙に巻く。その計画は恐ろしく冷静で、人間の悪意と狡猾さが際立っている。
結局いちばん怖いのは、信じたくなる「怪異」のほうじゃない。
それを信じさせて、殺すために使ってくる人間のほうだ。
おわり