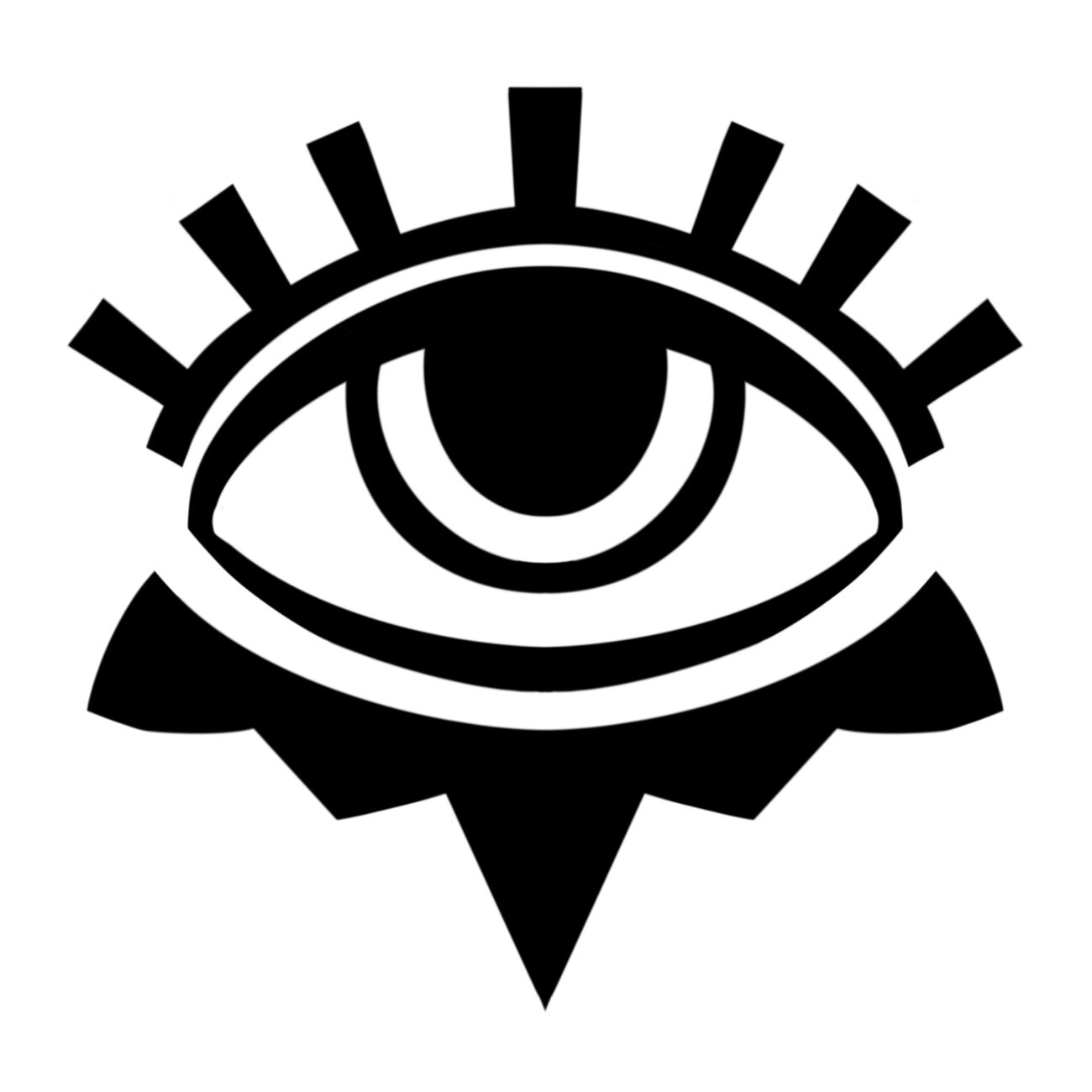「幻の作家」とも称された古泉迦十氏が、実に24年ぶりに世に送り出した本格ミステリ超大作──それが『崑崙奴』です。
2000年に第17回メフィスト賞を受賞したデビュー作『火蛾』で、文学界に鮮烈な印象を刻みつけながらも、その後は長らく沈黙を貫いてきました。今回の復帰は、多くの読者にとって、まさに待ち望んでいた出来事であると言えるでしょう。
デビュー作『火蛾』は、イスラム神秘主義という極めて特異な主題を取り上げ、それを本格ミステリの形式に見事に融合させたことで、当時大きな話題となりました。その深い思想性と高い完成度は、今なお語り継がれる作品として評価されています。しかしながら、長らく絶版状態が続いていたこともあり、古泉氏は“幻の作家”として、読者の間で神秘的な存在となっていました。
そのような中、『崑崙奴』の刊行を目前に控えて、実に23年ぶりに『火蛾』が文庫として復刊されたことは、古泉氏の作品に対する関心の高さを如実に物語っています。この復刊が新作への期待を一層高めたことは、想像に難くありません。
前作『火蛾』がイスラム世界を舞台としていたのに対し、『崑崙奴』では、舞台を古代中国・大唐帝国の都・長安へと移します。物語の核心には道教思想が深く据えられており、この大胆なテーマの転換からも、古泉氏が非常に幅広く、かつ深い学識を備えた作家であることが伝わってきます。
イスラム神秘主義から道教思想へというジャンプは、氏が単なる分野の専門家にとどまらず、より広範な人文的探究心をもつ知の探究者であることを印象づけます。
講談社の星海社FICTIONSレーベルから刊行された本作は、636ページにおよぶ大作です。その圧倒的なボリュームからも、古泉氏がこの作品にかける情熱と覚悟が伝わってくるようです。長い沈黙の果てに届けられたこの一冊は、単なる「復帰作」ではなく、現代本格ミステリの可能性を拡張する意欲作として、多くの読者に深い衝撃を与えることでしょう。
帝都を揺るがす連続猟奇殺人 ― 不可解な事件の幕開け
帝都・長安の華やかな日常を切り裂くようにして、人々の心を震撼させる連続殺人事件が発生します。
事件の様相は凄惨を極め、被害者の遺体は腹を十文字に切り裂かれ、臓腑が抜き去られた状態で発見されるという、常軌を逸したものでした。その異様な犯行手口は、単なる怨恨や物取りによる殺害とは明らかに一線を画しており、犯人の異常な精神状態や、あるいは何らかの儀式的な意味合いを強く想起させます。
やがて巷では、犯人が犠牲者の心肝を喰らっているのではないか、というおぞましい噂まで飛び交うようになり、帝都は不気味な恐怖に包まれていきます。腹を十字に切り裂き、内臓を持ち去るという残酷な手口は、偶然や激情に任せたものではなく、明確な意図に基づいた計画的犯行であることを意味しています。この描写は、物語の核心に道教思想が関与してくることを暗示する、重要な布石とも受け取れるでしょう。
この残忍で不可解な連続殺人は、絢爛たる帝都の表の顔と、その裏に潜む深い闇との対比を際立たせます。なぜ、このような惨たらしい殺人が繰り返されるのか。犯人の動機はどこにあるのか。その答えを求めて、読者は否応なく物語の渦中へと引き込まれていきます。この巨大な謎は、ページをめくる手を止めさせないほどの強烈な駆動力となり、読書体験をより一層濃密なものにしています。
事件の猟奇性は、社会全体に広がる恐怖を増幅させ、捜査当局に対しても早期解決への強い圧力を生み出します。そして、あまりにも異常なこの事件に対して、通常の捜査手法では解明が困難であるからこそ、道教のような深遠な思想体系にこそ、真相解明への鍵があるのではないか──そうした展開にも、大きな説得力が生まれてくるのです。
絢爛たる大唐帝国の都・長安 ― 物語の壮大な舞台
当時の長安は、東洋と西洋の文化が交錯する世界有数の国際都市であり、多様な民族や宗教、思想が入り混じる、活気と熱気に満ちた場所でした。本作では、この壮麗な都の姿が緻密かつ丹念な筆致で描き出されており、読者はページをめくるごとに、まるで当時の長安の喧騒の中に身を置いているかのような錯覚を覚えることでしょう。
作中では、たとえばゾロアスター教の寺院が存在していた可能性がほのめかされるなど、多文化的な側面が随所に織り込まれています。国際色豊かな都市・長安の描写は、単なる背景描写にとどまらず、物語全体の複雑さや奥行きを形づくるうえで重要な役割を果たしているように思われます。
多くの漢字や専門語が用いられているため、読み始めにはやや戸惑いを覚えるかもしれませんが、読み進めるにつれその細密な描写に引き込まれ、あたかも長安の街を探索しているかのような高揚感を味わうことができます。この漢字の多用は、おそらく読者を唐代中国という異文化世界に深く没入させるための、作者による意図的な工夫なのかもしれません。
こうした華やかさと混沌が同居する大都市・長安を舞台とすることで、物語の中で発生する事件や、登場人物たちの行動にも、当時の時代性ならではの陰影が色濃く投影されていきます。長安は、儒教・仏教・道教といった多様な宗教思想が併存し、互いに複雑に影響を与え合う独自の精神的環境を有していました。
とりわけ道教は、唐王朝によって国教として手厚く保護され、社会の精神的な基盤のひとつとして重要な位置を占めていたのです。この複雑で多層的な宗教的・文化的背景が、物語に描かれる謎に深みと広がりを与え、本作をより重厚な読み応えのある作品へと押し上げています。
道教思想の深奥へ ― 謎を彩る東洋の叡智
本作『崑崙奴』が他のミステリ作品と一線を画している最大の特色の一つは、猟奇的な連続殺人事件の謎が、中国古来の深遠な思想体系──道教思想──と密接に結びついている点にあります。
単に時代背景として道教文化が描かれているのではなく、犯行の動機、すなわちミステリにおける核心的な問いである「ホワイダニット(なぜ犯行は行われたのか)」の解明において、道教の教義や宇宙観、儀式などの要素が不可欠な構成要素として組み込まれています。
このアプローチは、従来のミステリの枠組みでは到底捉えきれない独創性を作品にもたらしており、先例のない試みとして新鮮な体験をさせてくれます。読者は事件の表層的な謎を追うだけでなく、その背後に広がる壮大な思想体系の一端に触れることになり、まさに知的冒険とも呼べる読書体験が待ち受けているのです。
犯人の動機も、西洋的な合理主義や心理学の枠内では理解し得ない、道教独自の論理に基づいているものであり、それが本作に一種の精神的な奥行きと、知的挑戦の手応えを与えています。
さらに、物語のタイトルであり、同時に事件の鍵を握る存在でもある童子の名「崑崙奴」は、唐代に成立した伝奇小説にも同名の登場人物が見られます。本作にはこの古典文学へのオマージュが随所に散りばめられており、それが物語の構造や人物関係にどのような影響を与えているのかも、読み解くうえでの大きな見どころとなっています。
もっとも、作中ではこの『崑崙奴』という伝奇物語との関連性について明確な説明がなされないため、一部の読者にとっては展開がやや唐突に映ったり、その意図を掴みかねたりする可能性もあります。しかし、あえて説明を抑制するこの手法が、逆に物語に奥行きと余白を与え、読者の知的好奇心をかき立てているとも考えられます。
西洋的な論理だけでは解き明かせない、東洋思想ならではの価値観や宇宙観。それこそが、この不可解な連続殺人事件の真相に迫るための重要な鍵です。読者は、探偵役たちと共に、道教思想の深く入り組んだ迷宮へと、一歩ずつ足を踏み入れていくことになるのです。
緻密な筆致と圧倒的な世界観 ― 読者を惹き込む古泉ワールド
古泉迦十氏の文章は、その該博な知識に裏打ちされた緻密さと圧倒的な情報量を特色としており、ときに「衒学的(ペダンティック)」とも評されるほどの濃密な語り口を持っています。登場人物たちが交わす会話には、歴史や思想、当時の風俗に関する深い考察が自然に織り込まれており、物語世界に驚くほどのリアリティと奥行きを与えているのです。
この知的な対話と独特の語り口は、京極夏彦氏の作品群を彷彿とさせ、読者を心地よい酩酊へと誘うようなレトリックの巧みさと、綿密に構築されたストーリーテリングが高く評価されています。古泉氏のもつ「衒学性」は、単なる知識の誇示にとどまらず、唐代長安という異世界的な舞台を立体的に構築し、読者をその時代精神へと導くための重要な装置として機能しているのです。
物語の舞台設定上、固有名詞や役職名などに難読漢字が多く登場するため、冒頭ではやや敷居の高さを感じる読者もいるかもしれません。しかしながら、読み進めるうちにその独特の文体やリズムに馴染み、やがて物語の奥深い世界観に自然と没入していくことでしょう。これは本作が、知識の集積にとどまらず、読者を惹きつけて離さない強靭な物語の力──すなわち、極上のエンターテインメント性を根底に備えているからに他なりません。
また、物語の導入は、主人公・裴景の友人である崔静の一見些細で不可解な行動を発端とする静かな幕開けとなっています。そのため、序盤においてはやや物語に没頭しにくいと感じる読者もいるかもしれません。しかし、最初の猟奇的な死体の発見、さらには唐代中国における食人史への考察といった衝撃的な要素が登場するあたりから、物語は一気に加速し、息をもつかせぬ展開へと突き進んでいきます。この静寂から激動への劇的なコントラストが、事件の異常性と衝撃度をより一層際立たせているのです。
そして、本作には、宗教・文化・伝説、そして当時の人々の間に根強く存在していたであろう迷信など、唐代中国を特徴づける多様な要素が物語の随所にふんだんに盛り込まれています。その結果、現代では想像しがたいような世界観のもとでしか成立し得ない、極めて独創的な推理物語が展開されていくのです。
おわりに:新たなる傑作の誕生 ― 物語の力と読後感
古泉迦十氏の『崑崙奴』は、緻密に構築された複雑な謎、その背後に広がる深遠な思索、そして個性豊かな登場人物たちの躍動が織り成す、“本格ミステリの超大作”と呼ぶにふさわしい風格を備えた作品です。道教思想や古代中国史といった専門的なテーマが物語の隅々にまで丁寧に織り込まれており、そうした知識を決して難解なままにせず、極上のエンターテインメントとして読み手に届けている筆致は、古泉氏の力量の高さを如実に示しています。
その完成度は文学界からも高く評価され、本作は第78回日本推理作家協会賞を受賞するという快挙を成し遂げました。独創性と文学性の双方において優れており、現代ミステリの中でも特異な位置にある作品と位置づけられています。深い思想性を内包しながらも、論理的な構成と意外性を失わず、ミステリとしての魅力を十全に備えている点も特筆すべき点です。
物語を読み終えたあとには、事件の意外な真相に対する驚きだけでなく、壮大な歴史絵巻を読み終えたあとのような重厚な満足感、そして知的好奇心を刺激された充実感が読者の中に深く残ります。それは、出版元・星海社が掲げるキャッチコピーにあるように、まさに「人生のカーブを切らせる」ような鮮烈な読書体験となるかもしれません。
複雑に絡み合った人間関係や伏線が、物語の中盤から終盤にかけて鮮やかに解きほぐされていくスピード感 、そして他に類を見ない独特の世界観に全身で引き込まれる体験は、まさに読書という行為ならではの醍醐味を存分に味あわせてくれます。
古泉迦十氏が24年の歳月をかけて紡ぎ出したこの物語は、長く読者の心に残り、語り継がれていくに違いありません。