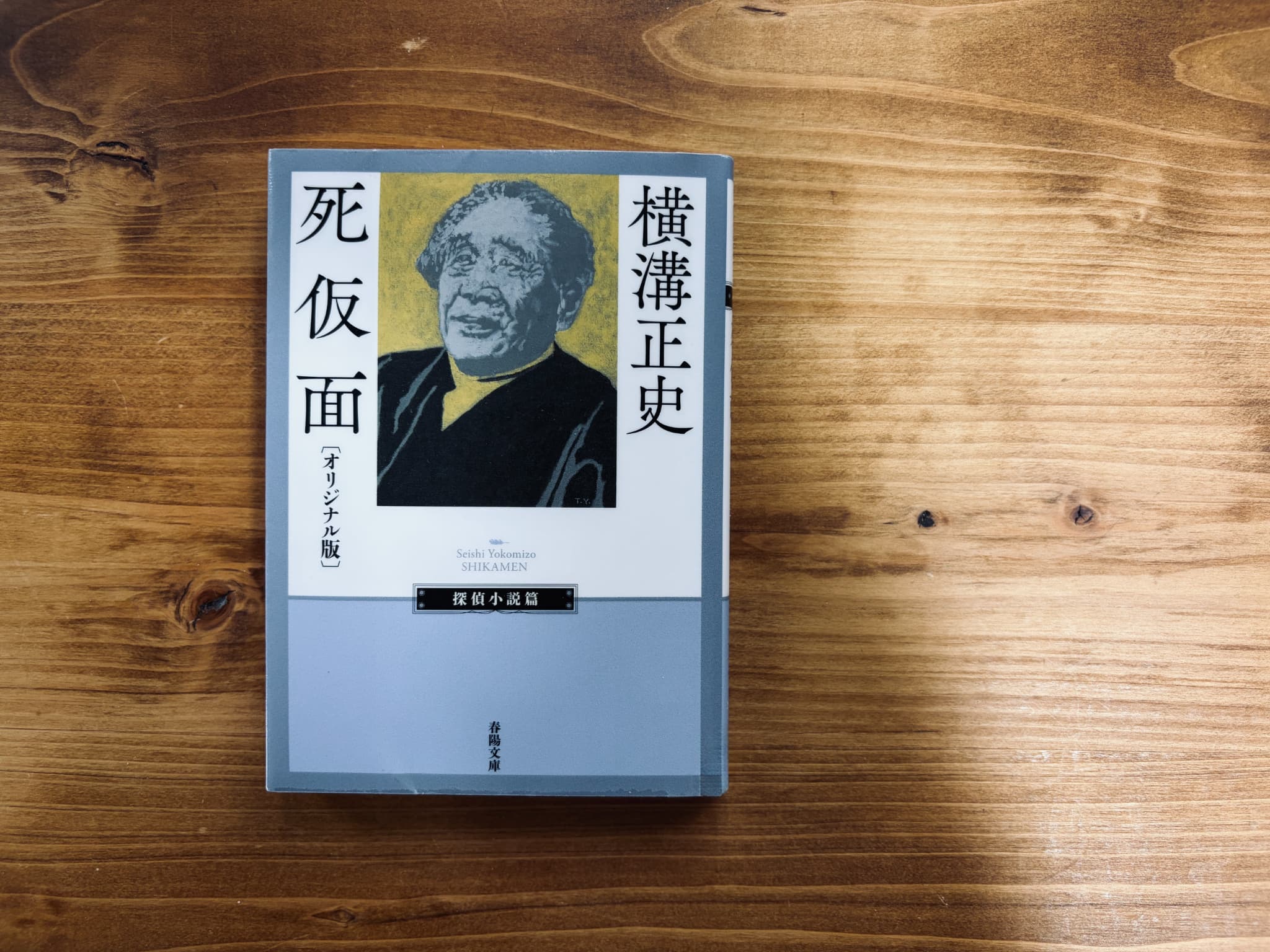江戸川乱歩。
もはや〈日本の探偵小説の開祖〉なんて堅苦しい肩書きよりも、一種の都市伝説として捉えたほうがしっくりくる。
大正末期〜昭和初期、東京がモダンになっていくほど、影も濃くなる。その影のほうにピントを合わせて、退屈と異常をごく自然に同居させてしまう。乱歩はそういう作家である。
ここで言う「退屈」は、ただヒマという意味ではない。何かが足りない、どこにも行けない、胸の奥がスカスカしてくる、あの感じだ。
乱歩の短編は、そのスカスカの底にいきなり異常が開く。覗き見たい、なり替わりたい、閉じた場所に潜り込みたい。
そういう欲望が、論理(本格)と怪奇(変格)をまたいで、するっと物語に溶ける。怖いのに、どこか気持ちいい。いや、気持ちいいからこそ怖いのだ。
というわけで今回は、乱歩短編の中でも「乱歩の顔」がはっきり出る10本をベスト10として並べる。
- 『人間椅子』
- 『押絵と旅する男』
- 『屋根裏の散歩者』
- 『D坂の殺人事件』
- 『赤い部屋』
- 『鏡地獄』
- 『目羅博士の不思議な犯罪』
- 『心理試験』
- 『人でなしの恋』
- 『芋虫』
どれも有名作ではあるが、並べて読むとただの名作集では終わらない。都市のアンニュイがどう異常に接続されるのか、乱歩の変化球がどこで本気になるのか、その手つきが見えてくる。
紹介では、あらすじは押さえつつも核心は割らない。犯人当てや種明かしに踏み込まず、作品の面白さが立ち上がるところだけをすくう。その上で、乱歩が何度も使うモチーフ──レンズ、鏡、人形、閉鎖空間──を横に並べて眺めてみたい。
乱歩は同じ道具を握り直しながら、毎回ちがう異常を作る。その再現性の高さが、いちばん怖い。
というわけで、乱歩の短編ベスト10。
退屈の底が抜ける瞬間を見ていこう。
1.『人間椅子』 ──触れた温もりの向こう側へ
ミステリ好きなら、一度は究極の密室について考えたことがあるはずだ。
でも、江戸川乱歩が1925年に発表したこの短編は、そんな概念を根底からひっくり返してくれる。
ふだん何気なく腰を下ろす椅子。
本来は安心できる場所のはずなのに、もしその内部に誰かが潜んでいるとしたら──そんな想像が、ゆっくりと現実に近づいてくる。
『人間椅子』が生む恐怖は、ありふれた日常がわずかに歪み、不現実に触れてくる種類のものだ。
視覚を捨てた男が手に入れた、生々しすぎる密着の快楽
奥様、
奥様の方では、少しも存じのない男から、突然、此様な無躾な御手紙を、差上げます罪を、幾重にもお許し下さいませ。
こんなことを申上げますと、奥様は、さぞかしびっくりなさる事で御座いましょうが、私は今、あなたの前に、私の犯して来ました、世にも不思議な罪悪を、告白しようとしているのでございます。
『人間椅子 江戸川乱歩ベストセレクション(1) 』8ページより引用
人気女流作家・佳子のもとに届いた分厚い封書。それは、ある家具職人からの長い告白文だった。
醜い容姿ゆえに孤独を抱えて生きてきた彼は、椅子作りに異常な情熱を注いでいた。ある日、製作中の肘掛け椅子の内部に人が入り込める空洞を作り、自らその中へ潜り込む。
椅子はホテルへ運ばれ、職人は内部から人々の体温や重み、衣服の擦れる音を感じ取る。夜になると外へ出て食料を得て、再び椅子へ戻る。やがて椅子は転々とし、ある高貴な家の書斎へ渡る。
手紙には、最後にその椅子に座った人物と、彼が味わった感覚が克明に綴られていた。そして、その家の主こそ、手紙を読んでいる佳子自身であることが示唆される。
読み進めるほど、いま自分が座っている椅子の中に何かがいるかもしれないという感覚が、現実味を帯びてくる。
ここからの描写が、とにかく凄まじい。視界を完全に遮断された暗黒の中で、職人が頼りにするのは触覚だけ。椅子に座る人々の体温、衣擦れの音、そして肉体の絶妙な重み。
それらを革一枚を隔ててダイレクトに感じ取ることに、彼は倒錯した喜びを見出す。
最後に待つのは安堵か、それとも……
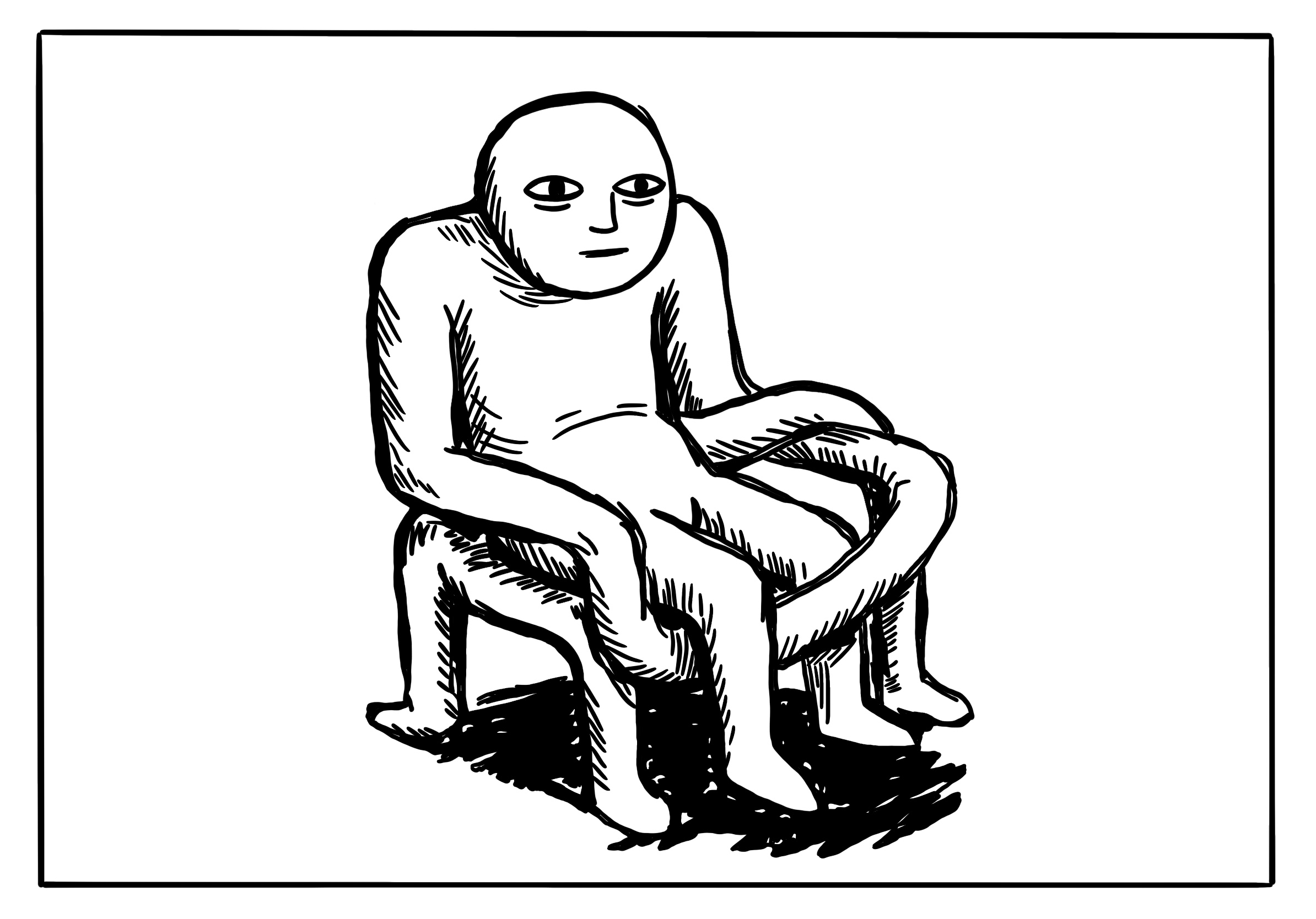
絵:四季しおり
この作品の構成で最も巧いと思うのは、読者が佳子と同じタイミングで手紙を読み進めていく点だ。
読み進めるうちに、ふと自分が今座っている椅子の感触が気になり始める。もしかしたら、この下にも誰かが潜んでいるのではないか? そんな妄想が、フィクションの枠を超えて現実を侵食してくるのだ。
視覚ではなく触れる感覚で描かれる怪奇。椅子の中という閉ざされた空間、革一枚越しに伝わる体温や重み。
その描写は生々しく、読んでいるだけで妙な実在感を伴う。この触覚中心の恐怖表現がとても好きだ。見えないからこそ想像が膨らみ、現実の椅子さえ少し違って感じられる。
乱歩は、椅子という最も身近で無害なはずの道具を、欲望と狂気の隠れ家へと塗り替えてしまった。
また、職人の孤独も印象深い。彼は誰とも繋がれず、ただ触れることでしか他者を感じられない。その歪んだ欲求には、不気味さと同時にどこか哀しさが漂う。乱歩は異常を描きながら、人間の寂しさを浮かび上がらせる。その両立が本当に見事だと思う。
構造の巧みさも際立つ。手紙形式によって、物語は読み手の現実へと入り込んでくる。封書を読み終えたあと、ふと自分の椅子を意識してしまう。この日常が侵食される感覚こそ、本作の真の怖さである。
そして、最後に用意された反転の鮮やかさ。乱歩は、読者を恐怖のどん底に突き落とした直後、ひょいと肩透かしを食らわせるような結末を提示する。だが、それで「あぁ良かった」と胸をなでおろせるだろうか?
むしろ、そんな恐ろしい物語を紡ぎ出した人間の頭の中こそが、一番底知れない闇なのではないか。そんな新たな不安を植え付けられたまま、物語は終盤へ向かう。
その余韻は長く残り、椅子というありふれた家具の印象を変えてしまう。
いま座っているその場所は、本当に空っぽなのだろうか。
一度でもこの物語を知ってしまえば、以前と同じ心持ちで椅子に深く腰掛けることは、もう二度とできない。
真実が何であれ、私たちの背中には、目に見えない誰かの視線と、温かな革の感触が刻み込まれてしまったのだから。
 四季しおり
四季しおり「いま座っている椅子の下に誰かがいる」という、想像力の毒が現実を侵食していく感覚がたまらないのだ。
2.『押絵と旅する男』 ──触れられない美だけが、永遠にそこに残る
ミステリの枠を超え、日本文学史に刻まれる「最も美しく、最も哀切な幻想譚」といえば、この短編を置いて他にない。
1929年に発表された本作は、犯人捜しの興奮ではなく、底なしの憧れが招く狂気を描いている。
乱歩の作品の中でも、この一編は少し特別だ。恐怖や異常ではなく、どこか柔らかい哀しさが底に流れている。
現実から一歩だけ外れた場所。そこにあるのは怪奇ではなく、届かないものを見つめ続ける視線だ。
押絵の中にあるもう一つの世界
蜃気楼の町・魚津からの帰路、汽車の中で「私」は奇妙な老紳士と出会う。彼が抱えていたのは黒布に包まれた額縁。
老紳士が「私」に見せてくれたのは、驚くほど精巧な押絵の額だった。そこには、真っ白な髪の老人と、振袖を着た絶世の美少女が寄り添うように描かれている。
老人は語り始める。かつて浅草の十二階(凌雲閣)から、双眼鏡で下界を覗くのが趣味だった兄の物語を。
美は永遠、時間は残酷
不思議と云えば不思議であった。だが、私の「奇妙」という意味はそれでもない。
それは、若し強て云うならば、押絵の人物が二つとも、生きていたことである。
『人間椅子 江戸川乱歩ベストセレクション(1) 』185ページより引用
この物語の面白さは、現実と幻想の境界にある。双眼鏡を逆さに覗くという単純な行為が、世界の距離感を反転させる。遠くにあるはずのものが近づき、現実の輪郭が揺らぐ。その感覚がとても美しい。
現実の尺度を失い、レンズの向こう側に魂を奪われていく感覚。それは、私たちミステリファンが、ページをめくる指を止められずに虚構の世界へ沈んでいく姿そのものではないだろうか。
そして忘れられないのが、額縁の中に並ぶ老人と少女の姿だ。芸術は時間を止めるが、人間は止まらない。この対比があまりにも切ない。
個人的に強く惹かれるのは、この作品が「逃避」を否定も肯定もしない点だ。現実から離れ、幻想へ向かう行為は弱さでもあり、同時に純粋な願いでもある。触れられないものを求め続ける姿に、どこか今の自分たちにも重なるもを感じてしまう。乱歩の中でも、ここまで透明な哀しさを湛えた作品は多くない。
蜃気楼、十二階、押絵。どれも消えゆくものの象徴だ。汽車の窓外に広がる夕闇のように、現実と夢の境界はいつのまにか溶けていく。
読み終えた後、手元に残るのは、触れれば壊れてしまいそうな、あまりに美しい絶望の余韻だ。
汽車の窓に映る自分の顔が、一瞬だけ紙のように平面的に見えたとしても、それはきっと、気のせいではない。
3.『屋根裏の散歩者』 ──異界で膨張した、退屈と覗きの果て
ミステリ好きなら、この究極の視点に一度は憧れたことがあるかもしれない。
江戸川乱歩が1925年に放った本作は、現代のストーカー犯罪やプライバシー問題を先取りしたような、背筋が凍る傑作だ。
人は退屈に耐えられない。刺激のない日常は、やがて心の奥を侵食していく。
ほんの小さな好奇心が、やがて引き返せない領域へ踏み込んでしまうこともある。
『屋根裏の散歩者』は、その静かな崩落の瞬間を、ひそやかに描き出す物語である。
天井の上から始まる異常な日常
郷田三郎は、定職も持たず仕送りで暮らす高等遊民。
すべての娯楽に飽き果て、「退屈」という重い感覚だけが彼を支配していた。友人・明智小五郎の影響で犯罪に興味を持ち、変装や尾行の真似事で刺激を得るが、それすら長くは続かない。
新たに住み始めた下宿「東栄館」で、郷田は偶然、押入れから屋根裏へ入れることを発見する。暗闇と埃に満ちた空間を這い回るうち、彼は節穴から住人たちの私生活を覗き見るという背徳的な快楽に目覚める。
「これは素敵だ」
一応屋根裏を見廻してから、三郎は思わずそうくのでした。病的な彼は、世間普通の興味にはひきつけられないで、常人には下らなく見える様な、こうした事物に、却って、云い知れぬ魅力を覚えるのです。
その日から、彼の「屋根裏の散歩」が始まりました。
『屋根裏の散歩者 江戸川乱歩ベストセレクション3』18ページより引用
誰にも見せない素顔、密やかな習慣、生活の裏側。屋根裏という異空間は、彼にとって退屈を忘れさせる遊戯場となる。
だが、その興味は次第に危険な方向へ傾く。嫌っていた同宿人・遠藤の寝顔を真上から見下ろしたとき、郷田の中で「完全犯罪」の構想が閃く。
節穴から毒薬を垂らし、眠る遠藤を殺す──ただそれだけの、冷たい計画だった。
見る者と見られる者、その転倒


絵:四季しおり
屋根裏。そこは住人たちの誰も知らない、建物の脳内のような場所だ。
郷田は埃にまみれ、蜘蛛の巣を払いながら、他人の部屋の真上を這い回る。天井の節穴から覗き見る私生活は、彼にとって最高のエンターテインメントとなった。
この作品のいちばん好きなところは、屋根裏という異様な空間の感触だ。暗闇、埃の匂い、かすかな声、節穴から漏れる光。
読み進めるうちに、まるで自分も天井の上を這っているような錯覚に包まれる。この感覚の生々しさがとてもいい。乱歩が描く空間は、ただの舞台ではなく、人の欲望そのものを映す装置になっている。
そして印象的なのは、「見る者」と「見られる者」という関係だ。天井板一枚を隔てるだけで、郷田は奇妙な全能感を手に入れる。彼の動機は怨恨でも金でもなく、ただ退屈を埋めるため。それがかえって不気味で、現実味を帯びてくる。この理由のなさこそ、本作の怖さだと思う。
明智小五郎の推理もキレッキレだ。決定的な証拠がない中で、彼は派手な証拠探しではなく、犯人の細かな習慣の変化や、被害者の性格といった心理的な足跡を辿っていく。タバコを吸わなくなった理由、あるいは吸えなくなった理由。その論理の糸が郷田の首を絞めていくプロセスは、冷徹でありながら、どこか慈悲深い。
退屈から始まった小さな逸脱は、やがて取り返しのつかない領域へ沈んでいく。天井の上で見ていたはずの世界は、いつの間にか彼自身を飲み込んでいた。
物語が残した冷ややかな感触は、今も私たちの頭上に、ひっそりと息を潜めている。
4.『D坂の殺人事件』 ──盲点のなかで、すべては完了していた
ミステリの歴史を紐解くとき、避けては通れない原点がある。
大正という時代の徒花として咲き誇った江戸川乱歩、その最高傑作の一つが本作だ。
夕暮れの坂道、古本屋の奥、わずかな違和感。乱歩の物語は、大げさな舞台よりも日常の裂け目から始まることが多い。
『D坂の殺人事件』もまた、見慣れた風景の中に潜む不可解から動き出す。何も起きていないはずの風景の中で、確かに何かが起きてしまった。
そしてここで、あの男が初めて姿を現す。
夕暮れの坂で起きた見えない犯罪
語り手の「私」は、本郷区団子坂の喫茶店「白梅軒」で奇妙な青年と出会う。長髪に着崩した浴衣、昼間から議論を好む高等遊民──後に名探偵として知られる明智小五郎である。
二人は店内から向かいの古本屋を眺めていたが、店番をしているはずの妻の姿が見えない。不審に思って店へ入ると、奥の薄暗い部屋で彼女は絞殺されていた。
完全な密室ではない。だが、見張っていたあいだ、誰も出入りしていない。裏口も閉ざされている。犯人はどこから現れ、どこへ消えたのか。
警察が行き詰まるなか、明智は独自の観察と洞察によって、見えない犯人の構造に静かに近づいていく。
ここで浮かび上がるのは、犯人が消えたのではなく、最初から認識されていなかったという逆説である。
盲点の論理と心理的密室
本作の面白さは「心理的密室」という発想にある。物理的に閉ざされた空間ではなく、人間の知覚の死角そのものが犯罪を成立させる。この発想は、当時の「日本の家は隙間だらけだから密室なんて無理だ」という常識を軽やかに裏返すものだった。
このアイデアの鮮やかさは、いま読んでも素直に面白いと思う。日本家屋の隙間や薄暗さをトリックに変えてしまうところも見事で、日本の風土から生まれた本格ミステリの原点を感じさせる。
そして個人的に好きなのは、まだ完成していない明智小五郎の姿だ。後年のスマートな名探偵ではなく、社会の外側にいる高等遊民としての彼。少し退廃的で、どこか影をまとっている。その不安定さが妙に魅力的で、名探偵が生まれる瞬間を目の前で見ているような気持ちになる。
また、古本屋という閉ざされた空間に漂う不穏な空気や、人間の暗い欲望の気配も好きなところだ。論理の奥に人間の深層がのぞく、この感触こそ乱歩らしさだと思う。
真実を暴くことは、平和な日常に戻ることではない。むしろ、世界の裂け目を見つけてしまうことなのだ。
もしもあなたが、退屈な毎日に飽き足らなくなっているのなら、ぜひこの坂道を登ってみてほしい。
ただし、そこから持ち帰るものが、見たいものだけだとは限らないけれど。



名探偵・明智小五郎の原点にして、乱歩特有の耽美な狂気が絶妙にブレンドされた一品だ。
『江戸川乱歩傑作選(新潮文庫)』『D坂の殺人事件 (角川文庫)』
5.『赤い部屋』 ──退屈は、人を殺す
すべての刺激に飽きたとき、人はどこへ向かうのか。
欲望の果てに残るのは、空虚か、それとも狂気か。
乱歩の世界では、ときに恐怖よりも「退屈」のほうが深い。刺激を失った心は、やがて異常へ向かう。
ミステリの醍醐味が知略による完全犯罪にあるとすれば、この短編はその一つの到達点だ。
1925年、乱歩が描き出したのは、あまりに不気味な秘密クラブ。深紅のカーテン、赤い絨毯、すべてが赤で統一された閉ざされた空間。
そこに集まるのは、この世のあらゆる刺激をしゃぶり尽くし、生きることに飽き果てた七人の男たち。彼らの唯一の娯楽は、蝋燭の火を囲んでとっておきの奇妙な話を披露することだった。
これは、血の色に染まった密室で繰り広げられる、最も優雅で最も邪悪な「暇つぶし」の記録である。
赤い部屋と語られる百の死
ある夜、新入会員のTが口を開く。彼は、自分が犯してきた「法に触れない殺人」について語り始める。直接手を下さず、偶然や心理を利用して人を死へ導く──いわゆるプロバビリティの犯罪である。
事故や自然死に見える形で命を奪い続け、気づけば99人も殺しているという。さらに彼は、この部屋にいる誰かを100人目に選んだと宣言する。
語りが進むにつれ、部屋の空気は変わっていく。これは現実なのか。境界が揺らぎ、疑念だけが膨らんでいく。
私は、皆さんが死刑執行のすき見を企てていられると聞いた時でさえ、少しも驚きはしませんでした。と言いますのは、私は御主人からそのお話のあったころには、もうそういうありふれた刺戟には飽き飽きしていたばかりでなく、或る世にもすばらしい遊戯、といっては少し空恐ろしい気がしますけれど、私にとっては遊戯といってもよい一つの事柄を発見して、その楽しみに夢中になっていたからです。
その遊戯というのは、突然申し上げますと、皆さんはびっくりなさるかもしれませんが……人殺しなんです。ほんとうの殺人なんです。しかも、私はその遊戯を発見してから今までに、百人に近い男や女や子供の命を、ただ退屈をまぎらす目的のためばかりに、奪ってきたのです。
『江戸川乱歩傑作選 (新潮文庫)』140ページより引用
退屈という病と、物語の毒に侵される快感
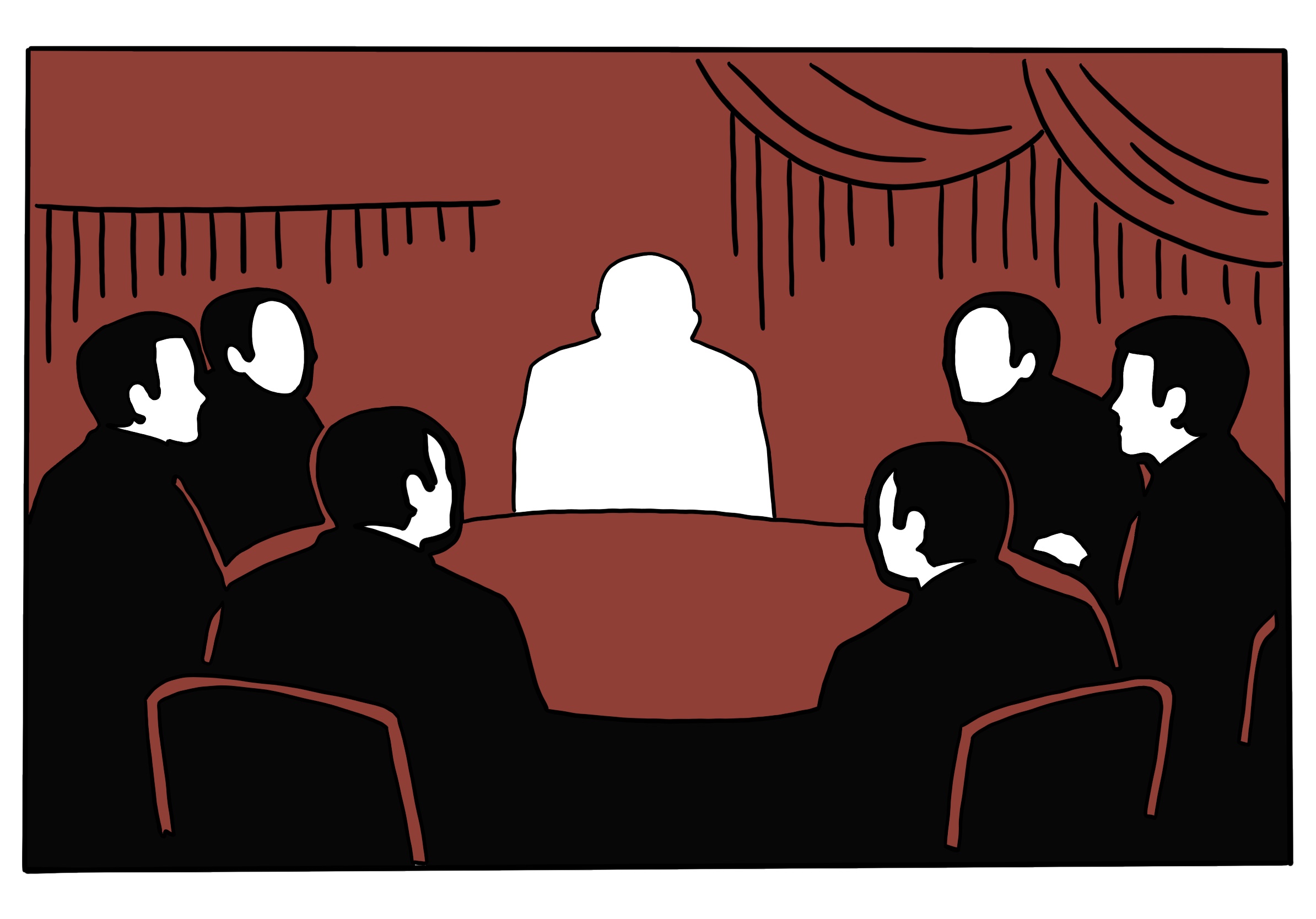
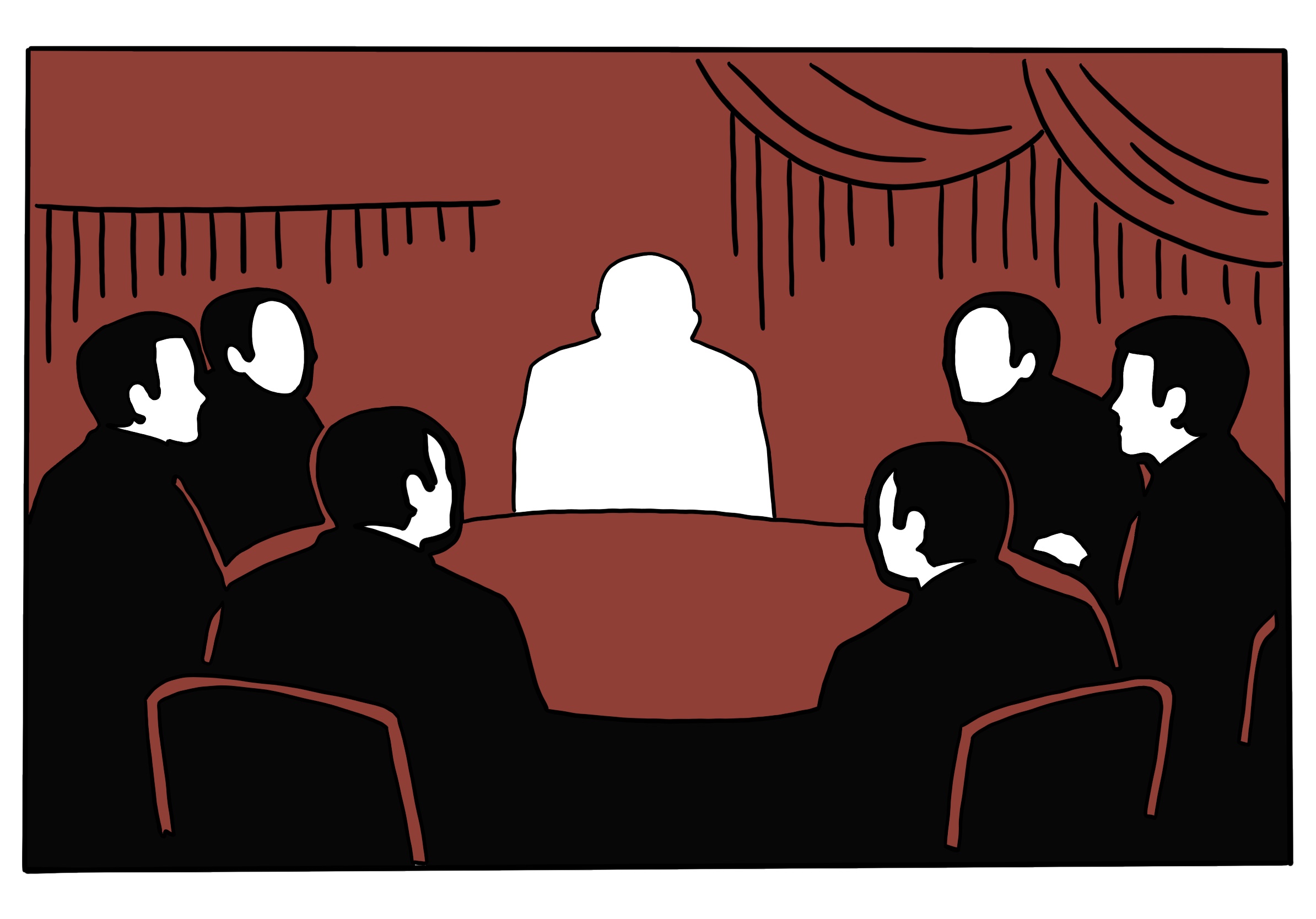
絵:四季しおり
この作品の面白さは、なんといっても「直接殺さない犯罪」という発想の鋭さだ。刃物も毒も使わず、日常に潜む偶然を操作するだけで人は死に至る。その冷たい論理が妙に現実味を帯びていて、読んでいると背筋がぞくりとする。
強く惹かれるのは、物語が語りそのものを装置にしている点だ。Tの話は淡々としているのに妙に説得力があり、真実なのか虚構なのか判別できなくなる。この曖昧さが恐怖を生む。乱歩は、言葉だけで現実を歪めることができるという事実を巧みに物語化している。
さらに、この作品には独特の虚無感がある。男たちは退屈を埋めるために狂気に近づき、その狂気さえも遊びの一部になってしまう。この空虚さがとても心に残る。刺激を求め続けた先にあるのが満足ではなく、さらに深い退屈であるという構図は、今読んでも鋭い。
そして終盤の反転。物語は単なる怪談でも犯罪告白でも終わらず、物語全体を根底からひっくり返すような、あまりに鮮やかな、そしてあまりに皮肉な仕掛け。この切れ味のよさこそ、本作の最大の魅力だ。
私たちの日常に転がっている些細な不運や偶然が、誰かの意志によって仕組まれたものではないと、どうして断言できるだろう。
赤い部屋を出たあとも、言葉だけが残る。あの告白は虚構だったのか、それとも現実だったのか。
答えはどこにもない。
ただ、退屈という病だけが、確かにそこにあった。



『赤い部屋』をオマージュした、法月綸太郎の『赤い部屋異聞』もぜひ。
6.『鏡地獄』 ──光学が招く、美しき精神の崩壊
光はまっすぐ進む。だが鏡に触れた瞬間、世界は増え、歪み、分裂する。
ひとつだったはずの像がいくつにも分かれ、やがて境界が溶けていく。
どこまでが現実で、どこからが像なのか。その区別が消えたとき、人は何を失うのだろうか。
歪んだ反射に魅入られた男の果て
でも少年時代はまだ、さほどでもなかったのですが、それが中学の上級生に進んで、物理学を教わるようになりますと、御承知の通り物理学にはレンズや鏡の理論がありますね、彼はもうあれに夢中になってしまって、その時分から、病気と言ってもいいほどの、いわばレンズ狂に変わってきたのです。
『江戸川乱歩傑作選 (新潮文庫)』247ページより引用
裕福な家庭に育った一人の男は、幼い頃からレンズやガラス、鏡といった「反射し、屈折するもの」に強く惹かれていた。
友人Kの回想によって語られる彼は、成長とともにその執着を深め、自宅の庭に実験室を建てて閉じこもるようになる。
そこには凹面鏡や凸面鏡、複雑に配置された鏡が作る歪んだ世界が広がっていた。彼はその異様な光景に陶酔し、やがて完全な鏡の世界を作ることに取り憑かれる。
レンズ越しにしか愛せぬ世界の真実
この作品が示しているのは、鏡という装置が持つ自己増幅の恐ろしさだ。鏡は現実を映すが、同時に自己を閉じ込める。像が増えるほど世界は広がるはずなのに、実際には出口が消えていく。この逆説が鋭い。
万華鏡のようにきらめく像は魅惑的だが、一歩踏み込めば逃げ場のない閉鎖空間へ変わる。その落差がとても印象に残る。視覚の快楽が、そのまま崩壊へ繋がっていく感覚が鮮烈だ。
とくに好きなのは、自己が増えすぎてしまうという発想である。無限に反射する自分、自分、自分。
視線の逃げ場がなくなったとき、人はどこまで自分を保てるのか。このテーマに引き込まれる。自己愛が極限まで膨張した先に待っているのは、充足ではなく崩壊だ。その構図の鋭さが際立っている。
また、鏡やレンズへの執着には、現実をそのまま受け入れず、歪んだ像の中に別の世界を見ようとする危うさがある。その感覚はどこか、想像力や文学の深部にも触れているみたいだ。世界を歪めて見たいという欲望。その果てにあるものを、この作品は容赦なく突きつけてくる。
映っているのは自分の姿なのに、それはもう自分ではない。鏡の奥には、そんな触れてはいけない深さがある。
私たちが毎日目にしている世界は、本当に正しい形をしているのだろうか。
あるいは、誰かが仕掛けた鏡の迷宮の中で、歪んだ像を真実だと思い込まされているだけではないか。
そんな疑念を振り払えないまま、私たちはまた、銀色の闇に魅了されていく。
7.『目羅博士の不思議な犯罪』 ──月光の下、模倣は犯罪へ変わる
乱歩の犯罪は、刃物や毒よりも知覚を狙うことがある。目に入る像、無意識の模倣、そして暗示。
『目羅博士の不思議な犯罪』が描くのは、見ているつもりの人間が、いつのまにか見せられている側へ転じる瞬間だ。
月光の下で繰り返される死
真似というものの恐ろしさがお分りですか。人間だって同じですよ。人間だって、真似をしないではいられぬ、悲しい恐ろしい宿命を持って生れているのですよ。
『人間椅子 江戸川乱歩ベストセレクション(1) 』39ページより引用
ある月夜、不忍池のほとりで探偵小説家の「私」は奇妙な男と出会う。彼は人間や動物に備わる模倣本能について語り、自らが関わった不可解な事件を打ち明ける。
舞台は丸の内のビル街。そこには、構造から窓の配置までが、向かい合うビルと寸分違わず作られた鏡像のような空間が存在していた。
その一室で、不気味な連鎖が起きる。住人が変わっても、同じ場所で、同じように首吊り自殺をする者が後を絶たないというのだ。
原因は向かいのビルに住む眼科医・目羅博士にあるらしい。
語り手の男は、この「視覚による犯罪」を暴くため、博士に罠を仕掛ける。
模倣という名の支配
「鏡をじっと見つめていると、怖くなりやしませんか。僕はあんな怖いものはないと思いますよ。なぜ怖いか。鏡の向側に、もう一人の自分がいて、猿の様に人真似をするからです」
『人間椅子 江戸川乱歩ベストセレクション(1) 』39ページより引用
この物語の核心は、人間に備わる「真似る衝動」だ。人は似たものを見ると、無意識に同じ行動をなぞろうとする。
乱歩はその心理を極端な形へ押し出し、直接手を下さない殺人という構図を作り上げた。ここにあるのは暴力ではなく、認識の操作だ。
特に印象的なのは、鏡像のように向かい合う二つのビルという舞台装置。現実と写し身、主体と影。その境界が揺らぎはじめるとき、都市空間そのものが不気味な劇場へ変わる。月光に照らされた窓、首を吊る影、人形のシルエット──視覚イメージの連鎖が強烈だ。
惹かれるのは、乱歩がここでも「眼」というテーマを突き詰めている点だ。見るはずの存在が、いつのまにか見られ、操られる側へ回る。この転倒がほんとうに怖い。
視覚は最も確かな感覚のはずなのに、それが揺らいだ瞬間、人の意思は簡単に崩れる。乱歩の心理トリックの中でも、かなり鋭い部類だと思う。
そしてもう一つ。目羅博士と語り手の関係には、どこか鏡像的な緊張がある。追う者と追われる者。光と影。どちらが主体でどちらが模倣なのか、境界は次第に曖昧になっていく。この感覚の揺らぎが、読み終えた後もムカムカと胸に残るのだ。
私たちは、自分の意志で生きていると信じている。だが、もしも窓の向こうで、自分と全く同じ姿をした誰かが、おぞましい手本を示していたとしたら。
抗いようのない衝動に身を任せてしまう恐怖は、決して物語の中だけの話ではない。
月光の下、私たちは自分の意思で動いているつもりになる。
だが、それが本当に自分の意思であると、誰が証明できようか。
『江戸川乱歩名作選(収録名は『目羅博士』に改題)』『人間椅子 江戸川乱歩ベストセレクション(1)』『江戸川乱歩全集 第8巻 目羅博士の不思議な犯罪 (光文社文庫)』
8.『心理試験』 ──完全犯罪は、頭の中で生まれ、頭の中で崩れる
ミステリファンにとって倒叙ものの醍醐味といえば、犯人がいかに完璧な計画を練り、それがどう崩されていくかを見守る興奮に尽きる。
1925年、乱歩が発表した本作は、まさにその最高峰だ。
主人公の蕗屋清一郎は、貧しいけれど頭脳明晰な大学生。彼は自らの知能を試すように、強欲な老婆を殺害し大金を奪う。
物理的なトリックではなく、人間の心理をハックすることで完全犯罪を狙う、いわば大正版『罪と罰』ともいえる物語だ。
完璧な計画、そして完璧すぎた男
そうして、いろいろと実験や推量をつづけているうちに、蕗屋はふとある考えにぶっつかった。それは、練習というものが心理試験の効果を妨げはしないか、言い換えれば、同じ質間に対しても、一回目よりは二回目が、二回目よりは三回目が、神経の反応が微弱になりはしないかということだった。つまり、慣れるということだ。
『江戸川乱歩傑作選 (新潮文庫)』116ページより引用
彼の方法は、アリバイや物理トリックではない。人間の心理の隙を突き、疑われない状況を作るという大胆なものだった。犯行は成功し、彼は何事もなかったように日常へ戻る。
この事件の注目ポイントは、タイトルにもなっている『心理試験』だ。単語への反応時間から容疑者の深層心理をあぶり出す、当時の最先端科学。
普通の人なら、事件に関する単語に動揺して反応が遅れたり、おかしな連想をしたりしてしまう。だが、蕗屋は違った。
彼はこの試験を想定し、事前に猛特訓を重ねて「犯人ではない反応」を完璧に演じ分ける準備を整えていたのだ。
すべては計算どおり──のはずだった。
しかし、そこに現れたのが我らが明智小五郎だ。彼は心理試験の結果を否定はしなかった。
ただ、蕗屋の回答データが「あまりにも完璧で、反応時間が揃いすぎている」ことに目をつけた。
理性と罪がぶつかる、もう一つの明智小五郎
本作は犯人視点で進む倒叙ミステリで、緊張感の質がとても独特だ。犯人探しではなく、どこで崩れるのかを見守る構造。その静かなプレッシャーが心地よい。
そして何より面白いのは、科学で完全犯罪を成立させようとする蕗屋と、人間の感覚でそれを見抜く明智の対比である。
明智の攻め方は、まさに心理の裏をかく真骨頂だ。屏風の絵に関する、何気ない、けれど逃げ場のない質問。論理の網が徐々に絞り込まれ、自らを選ばれた人間だと自惚れていた天才のプライドが、パラパラと崩れ落ちていく瞬間は、何度読んでもゾクゾクする。
個人的に好きなのは、「完璧であろうとするほど破綻に近づく」という構図だ。蕗屋は理性ですべてを制御しようとするが、その均一さこそが不自然さを生む。嘘をつかないことが最大の嘘になる、という逆説の鮮やかさには今読んでも痺れる。
また、明智小五郎の探偵像も魅力的だ。理論や数値をそのまま信じるのではなく、人間の微かな揺らぎを見る。その姿に、血の通った知性を感じる。
さらにこの物語には、うっすらとした倫理の影もある。自分は特別だと信じた青年の傲慢と、その理性が崩れる瞬間。そこには論理だけではない重みが残る。だからこそ、この対決はただの謎解きでは終わらない。
すべてを計算したはずの思考が、ほんのわずかな揺れで崩れていく。その瞬間、理性の光はやわらぎ、人間の重さだけが残る。
もし、あなたが自分の知能に絶対の自信を持っているのなら、一度この試験を受けてみることをお勧めする。
ただし、その答えが「あまりに完璧」にならないよう、くれぐれも気をつけて。



「嘘をつかない」という最高の防御が、最大のボロに変わる逆転劇の構成がとにかく鮮やかだ。
9.『人でなしの恋』 ──土蔵に隠された戦慄の愛執
乱歩の恋愛は、たいていどこか歪んでいる。だがこの作品の歪みは、冷たいというより哀しい。
愛が届かないのではない。最初から向けられている場所が違っていた。その事実が、ゆっくりと心を締めつけてくる。
土蔵の奥で続いていたもう一つの愛
京子は良家の青年・門野と見合い結婚をする。美しく、穏やかで、申し分のない夫。結婚生活も順調に見えた。だがある頃から、夫は夜になると寝室を抜け出し、土蔵の二階へ通うようになる。
やがて京子は、夫が誰かと語り合う声を聞く。相手は女性らしい。嫉妬と疑念に押され、彼女は夫の留守中に土蔵へ踏み込む。
そこで見つけたのは、長持の中に隠された等身大の京人形だった。
ではなぜ、あの人がそんな努力をしましたか、尤もこれらのことは、ずっとずっと後になって、やっと気づいたのではありますけれど、それには、実に恐ろしい理由があったのでございます。
『芋虫 江戸川乱歩ベストセレクション2』167ページより引用
嫉妬さえ届かない絶望の境界線
この物語の核心は、愛の対象のズレにある。人間は変わる。老いる。裏切る。だが人形は変わらない。
門野にとって人形は、拒絶せず、傷つけず、幻想をそのまま受け入れてくれる存在だった。ここにあるのは単なる異常ではなく、理想を求めすぎた愛の行き着く先である。
強く残るのは、京子の絶望だ。普通の浮気なら、相手の女を恨むことも、自分と比較して改善することもできるだろう。でも、相手は老いず、汚れず、そして決して裏切らない人形だ。
夫にとっての理想は、血の通った人間ではなく、自分の幻想を完璧に受け止めてくれる物体の中にしかなかった。京子は、人間であるというただ一点において、人形に敗北してしまう。
このピグマリオニズム(人形愛)は、乱歩が繰り返し描いてきたテーマだ。『押絵と旅する男』が異界への憧れなら、こちらは日常を侵食する隣り合わせの狂気。愛する人が、自分という存在を素通りして無機物に魂を捧げていると知ったとき、人はどれほどの孤独に突き落とされるのか。想像するだけで恐ろしい。
そして、最後の場面。これは嫉妬の爆発であると同時に、夫を現実へ引き戻そうとする最後の抵抗でもある。しかし結果は、さらに深い断絶。乱歩の恋愛はしばしば触れられないものへ向かうが、この作品ではその距離が取り返しのつかない形で露わになる。
あなたの部屋に飾られた人形や、大切にしている愛蔵品。それらは、ただそこにあるだけの無機物だろうか。
あるいは、主人が眠りにつくのを待ちわびて、密かに呼吸を始めているのではないか。
今夜、寝室を抜け出す足音が聞こえたとしても、決して後を追ってはならない。
そこには、人が決して見てはならない、異界の恋が広がっているのだから。
10.『芋虫』 ──人がただの愛の玩具に成り果てたとき
江戸川乱歩という作家の凄みを、これほどまでに叩きつけられる作品は他にないだろう。
1929年に発表された『芋虫』は、あまりに過激で残酷な設定ゆえに、かつては発禁処分という封印を食らった問題作だ。
乱歩の物語は、怪異より先に人間から始まることがある。外界を失った場所で、たった二人が向き合い続けるとき、関係はゆっくりと歪んでいく。
『芋虫』は動きの少ない物語だ。だが、その内側では確実に何かが崩れていく。
しかもその崩れ方は、あまりにも濃く、あまりにも逃げ場がない。
密室で変質していく、愛と力関係
設定は極端にシンプル。戦争で手足と声と聴覚を失った須永中尉と、その妻・時子。
舞台はほぼ密室。登場人物もほぼ二人。それだけで、世界は異様な密度を帯びる。
言葉は届かない。声も返らない。だから時子は、夫の体に指で文字を書く。皮膚を通して言葉を送る。
このやり取りが、どうしようもなく生々しい。読むはずなのに、触覚が先に立ち上がる。汗、熱、畳、肌。夏の湿り気が、そのまま二人の関係に重なっていく。
やがて、密室のバランスが崩れ始める。外では軍神の妻と称えられる時子だが、家の中では支配する側に回る。けれど彼女は冷酷なだけの存在ではない。終わりの見えない介護、閉じた生活、逃げ場のなさ。その歪みが、愛の形を少しずつ変えてしまう。
個人的に強く惹かれるのはここだ。怪奇ではなく、人間関係そのものがゆっくり壊れていく感触。乱歩の怖さは、たいていこの地点にある。
それはまるで、大きな黄色の芋虫であった。或いは時子がいつも心の中で形容していたように、いとも奇しき、畸形な肉独楽であった。それはある場合には、手足の名残の四つの肉のかたまりを(それらの尖端には、丁度手提袋の口の様に、四方から表皮が引締められて、深い皺を作り、その中心にぽッつりと、不気味な小さい窪みが出来ているのだが)その肉の突起物を、まるで芋虫の足の様に、異様に震わせて、臀部を中心にして頭と肩とで、本当に独楽と同じに、畳の上をくるくると廻るのであったから。
『芋虫 江戸川乱歩ベストセレクション2』15ページより引用
あまりに人間的な無言の抗議
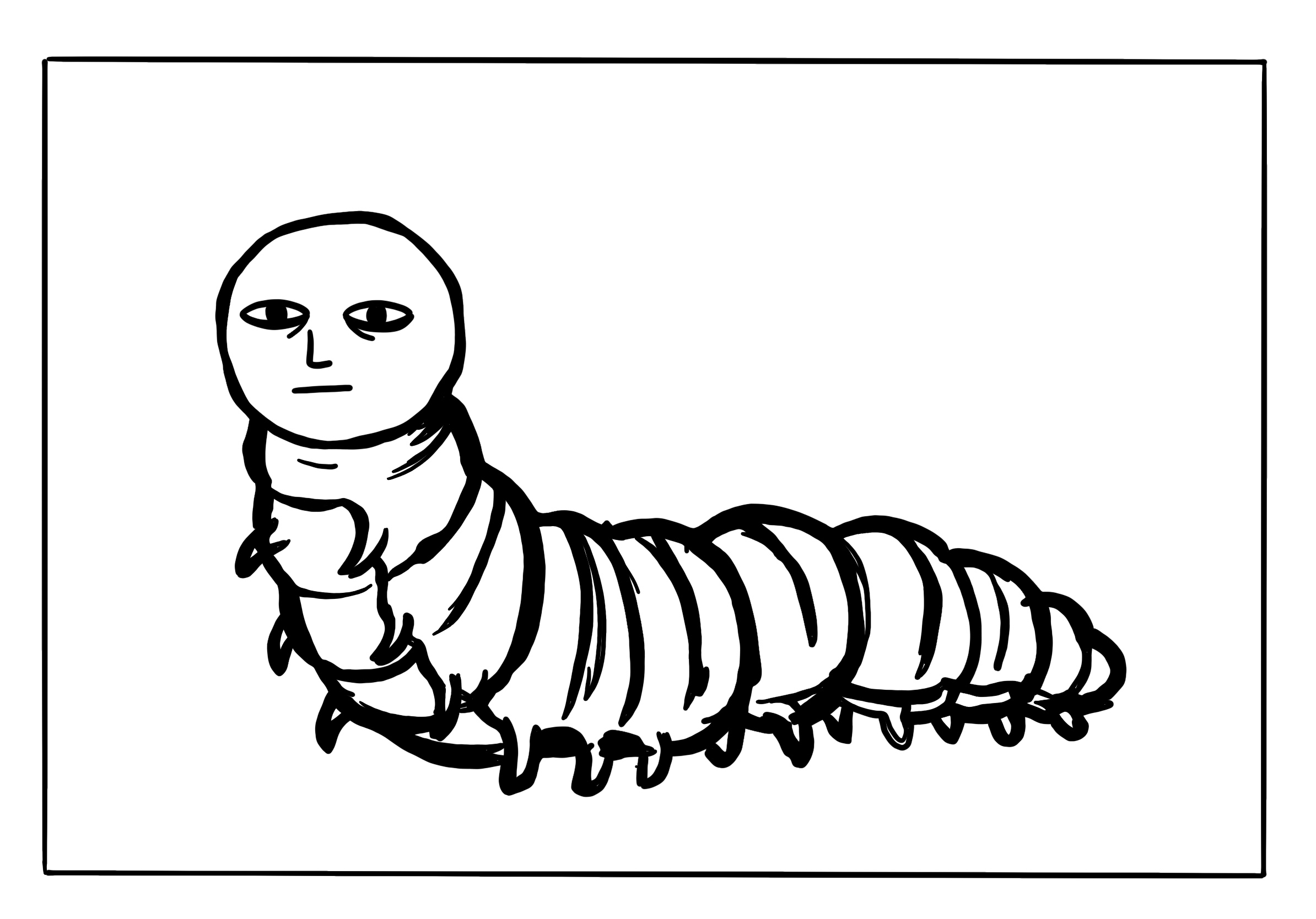
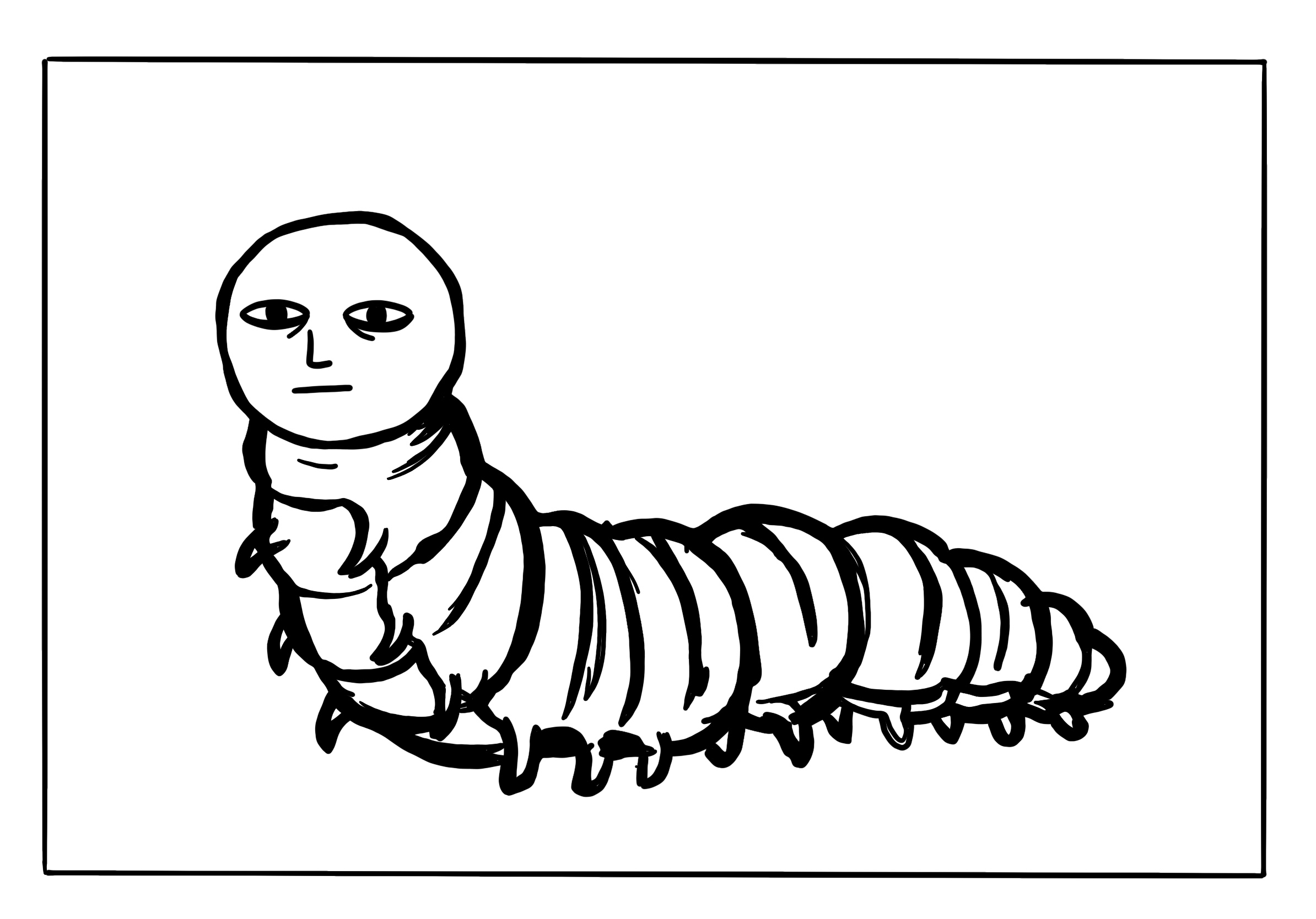
絵:四季しおり
この作品の最大の恐怖は、物理的なグロテスクさではない。外部との繋がりをすべて断たれた須永中尉が、唯一「皮膚」を通じてのみ世界と通じ合っているという、極限の触覚描写だ。
時子は夫の体に指で文字を書き、意思を伝える。声も聞こえず、表情すら乏しい夫に、皮膚の温もりや痛みを介して言葉を流し込む。
この描写が驚くほど生々しくて、読んでいるこちらの指先まで痺れるような感覚になる。密室に漂う夏の熱気、畳の匂い、そして混じり合う吐息。乱歩は、視覚以上に触覚を研ぎ澄ませることで、二人の共依存関係を浮き彫りにした。
時子は世間から「軍神の妻」として称賛されながら、家の中では夫をモノのように扱い、支配することに歪んだ快楽を見出していく。
出口のない絶望が、加害と被害の境界を曖昧にし、愛情をドロドロとした執着へと変容させていくプロセスは圧巻すぎて言葉が出ない。
そして終盤、須永中尉が見せるある選択。それは純粋すぎて、むしろ痛い。ここで物語の温度がぐっと変わる。恐怖の奥から、別の感情が立ち上がるのだ。
残酷さの底に、かすかな優しさがある。あの反転こそ、この作品の核心だと思う。
乱歩が意図したか否かに関わらず、この作品には戦争が人間から尊厳を奪い、単なる物体へと作り替えてしまうことへの強烈な皮肉が込められている。
物語の最後に見せる須永中尉の「ある決断」。それは、言葉を持たない彼が、自らの残された肉体すべてを使って放った、最初で最後の純粋な意思表示だった。
この結末を迎えたとき、気づかされる。これは単なるエログロでも怪奇小説でもない。極限状態における「人間の尊厳」と「愛の正体」を問う、あまりに哀切な人間賛歌なのだということに。
100年近い時を経てもなお、この作品が現代の介護や孤独といったテーマと響き合うのは、乱歩が時代の病理ではなく、人間の業そのものを射抜いていたからに他ならない。
触れることしかできない愛。言葉にならない感情。残るのは、奇妙な敬意のようなもの。
恐怖の奥で、人間がむき出しになるこの物語は、痛いほど人間的だ。
須永中尉が最後に選んだ道。
それは、愛する者への最大の復讐だったのか、それとも唯一残された慈悲だったのか。
その答えは、物語を読み終えたあなたの心の中にしかない。
おわりに 現実から半歩ずれた場所で


絵:四季しおり
この10作品を通して見えてくるのは、江戸川乱歩という作家が、論理と幻想のあいだを自在に行き来しながら、ずっと現実から少しだけズレた場所を探していたということだ。
ただの逃避ではない。現実を歪めて、もう一つの世界を覗き込もうとする試みである。
レンズや鏡は、そのためのスイッチだ。節穴、逆さ双眼鏡、球体鏡、向かいの窓──そこから覗いた瞬間、見慣れた風景は別の顔を見せる。日常がゆがみ、隠れていたものが浮かび上がる。乱歩の物語は、こうした視線の仕掛けで動いている。
一方で、人形や死体、閉じた空間への執着も印象的だ。変わらないもの、動かないもの、完全に支配できる小さな世界。そこには、不安定な現実や人間関係への居心地の悪さがにじんでいる。
屋根裏、椅子の中、赤い部屋……乱歩はそういう場所に、永遠のようなものを作ろうとしたのだろう。怖いのに、妙に惹かれる理由はそこにある。
そして約一世紀後のいまも、乱歩は古びない。彼が描いたのは時代の風俗ではなく、人の奥にある衝動そのものだったからだ。
退屈の怖さ、覗き見たい欲望、別の存在になりたい気分、死とエロスの引力。どれも、いまも形を変えてそこら中にある。
乱歩を読むというのは、ミステリを解くこと以上に、自分の中の見えない部屋をそっと覗く体験に近い。
うつしよは夢、夜の夢こそまこと。
──江戸川乱歩
乱歩の短編は、現実という少し退屈な夢から目を覚まし、もう一つの濃い夢を見るための入口であり続けている。