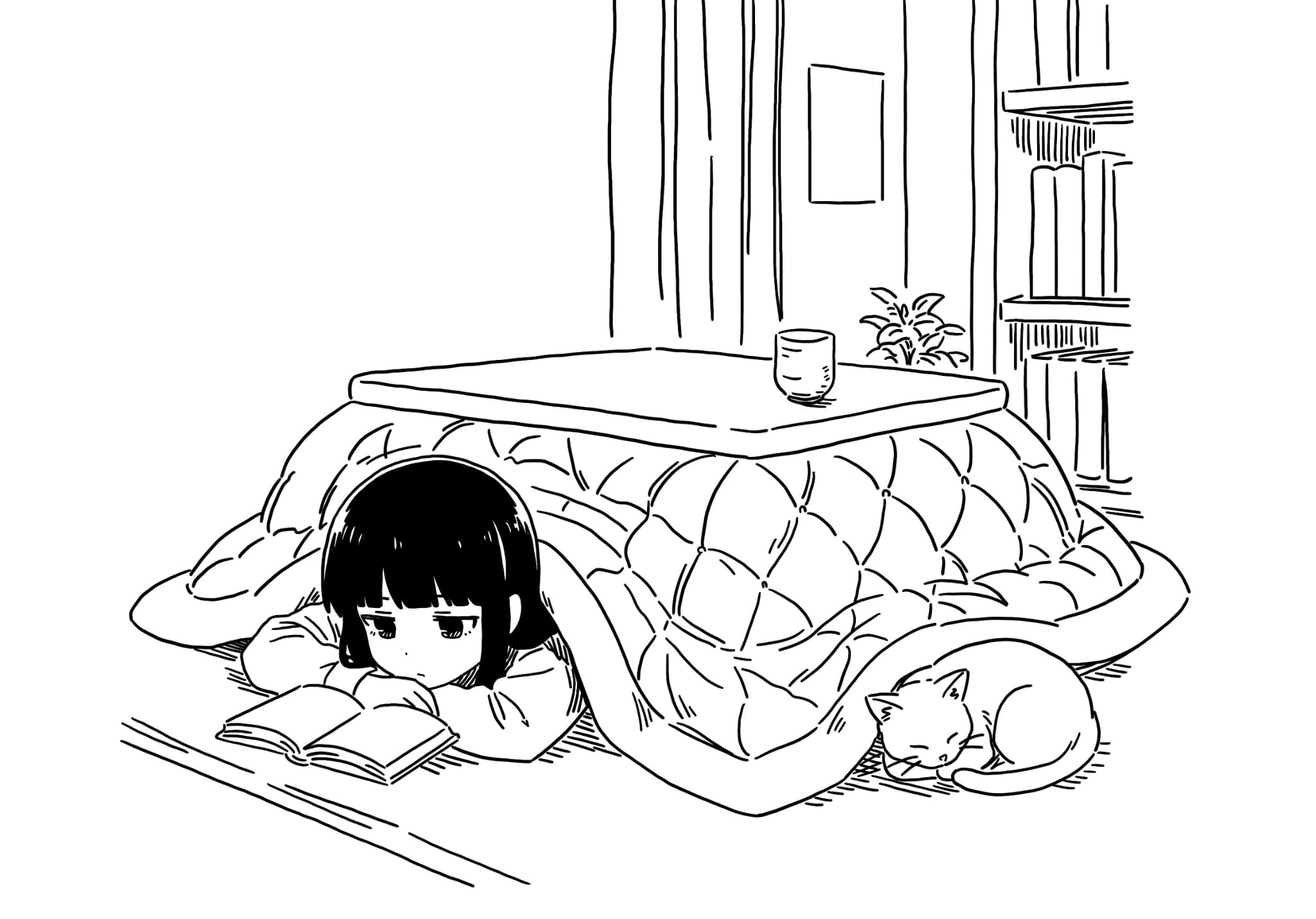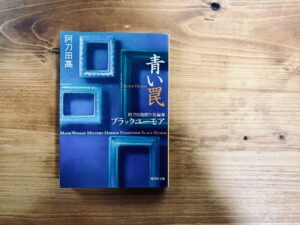2025年7月、『N・Aの扉 新装版』が刊行された。
この知らせを聞いたとき、胸の奥がざわついたのを覚えている。
「本当にあれが戻ってくるのか」──そんな気配が、ミステリファンたちの間にゆっくりと広がっていった。
この作品、もともとは1999年に新潟日報事業社という地方出版社から刊行された、かなりマニアックな一冊である。
著者は飛鳥部勝則(あすかべ かつのり)。ホラーでも本格でも幻想小説でもない、どこにもきれいに収まりきらない作風で知られ、一部の読者には熱狂的に支持されていたが、長く絶版となっていた。
古書市場では高騰し、ほとんど手に入らなかった。それが26年ぶりに再び開かれると聞いたとき、ただの復刊では済まないだろうと自然に身構えた。
しかも新装版には、装画や口絵の刷新だけでなく、別館と名づけられた追加パートが用意されていた。本書は「N・A」という名探偵をめぐる物語だが、その名が示すように、扉の向こうには幾層にも重なった空間が広がっている。
論理と幻想、作家と読者、語りと解体、そして何より「本格推理という亡霊」が静かに歩き回る空間である。
先にひとつだけ言っておきたい。
この本は「犯人当て」や「鮮やかな解決」を楽しむタイプのミステリではない。むしろ、謎が存在し続ける状態そのものを読者に体験させる構造になっている。
読み終えても、理解した手応えがほとんどない。
だが、それでいいのだと思う。それこそが、この作品の狙いなのだろう。
幽霊としてよみがえる本格推理
幽霊は幽霊でも、《本格推理の幽霊》……についての話なんです」
「本格推理?」
田村は力ない笑みを浮かべて、
「それだけでもないんですが……どこが不思議なのかよくわからないような話で、でも一種の怪談のような……本格推理小説が幽霊になって出てきたような……そんな話なんです」
『N・Aの扉 新装版』41ページより引用
『N・Aの扉』の面白さは、構造そのものにある。目次を開いた瞬間から、この本は普通の小説ではなくなる。章立てはまるで館の見取り図のようで、読書はページをめくる行為から、空間を移動する体験へと変わる。
最初に置かれている『我らに残るただ一人の女、エヴァ』は導入以上の役割を持つ。現実と虚構の境目に立たされるような感覚があり、ここから先では常識が少しずつ効かなくなる。
続く『N・Aの扉』では、ホラー作家・田村が、かつて自分が書いていた本格推理小説の記憶と向き合う。やがて『それからの孤島』へ進むころには、もうジャンルの迷宮の奥に入っている。
とくに印象的なのが「孤島」の章である。クローズド・サークルという本格ミステリの典型的な舞台が揃っているにもかかわらず、そこでは論理の快楽よりも、構造の人工性が前面に出る。美しく整った装置ほど、逆に不気味に見えてくる。この感覚が独特だ。
そして最後の『ここは私の遊び場』に至ると、それまでの世界が覆る。読み終えたはずなのに、そこが本当に出口だったのか分からない。
さらにこの新装版では〈別館〉として『変格推理の幽霊』が追加されている。これは単なる補遺ではなく、作品全体の重心を少しだけ動かす存在だ。本格の亡霊だけでなく、幻想や異常心理を重視する変格の系譜がここで浮かび上がる。
こうして本書は、「本格の亡霊を描く物語」から「ジャンルそのものの迷宮」へと、静かに姿を変えていく。
語りの奥に潜む影
この物語は単一の視点で進まない。作家・石塚と田村の対話、田村がかつて書いた小説、そしてその作品に批評を加える川合和重。三つの語りが入れ子状に重なり、現実と創作の境界が少しずつ曖昧になっていく。
川合の存在はとても印象的だ。彼は「唯一の読者」でありながら、同時に厳しい批評を加える存在でもある。彼の言葉は、読者が感じる違和感を代弁しているようでもあり、読むという行為そのものに光を当ててくる。
名探偵N・Aは、はっきりした姿を持たない。かつて存在したキャラクターであり、今はもう登場しないはずの存在である。それでも彼は亡霊として現れ、田村の創作を揺さぶる。ここにあるのは、論理と恐怖の衝突だ。
田村は現在ホラー作家である。論理ではなく、直感や混沌に惹かれる側へと移行した人物だ。しかし過去の論理の物語は消えない。この構図には、ジャンルの矛盾だけでなく、創作者の内面の揺れも重なって見える。
飛鳥部勝則という作家自身の姿が、そこにほんのりと透けているように思う。
解けなさとともに残るもの
この作品は、再読するほど理解が深まるタイプのミステリではない。
読むたびに迷宮の形がわずかに変わるような感覚がある。分かったと思った瞬間、別の影が現れるみたいだ。
何度読んでも、自分があまり前に進んでいないような気がする。理解することよりも、迷い続ける状態そのものを体験させる作品なのだろう。
この新装版には1999年と2025年、二つのあとがきが収められている。若い頃の焦燥と、現在の視点。そのあいだに流れた時間が、作品の奥行きをさらに深くしている。物語は固定されたものではなく、変化し続けるものなのだと感じさせられた。
読み終えても終わった感じがしない。むしろ、まだ中にいるような感覚が残る。
本格ミステリは死んだのか。それとも幽霊として生き続けているのか。
答えは書かれていない。
ただ一つ確かなのは、この扉は一度開けると完全には閉じないということだ。
そして気づく。外に出たつもりでも、どこかで「幽霊」がこちらを見ている。
次にページを開いた瞬間、たぶんまた迷う。
それでもいい。
この本は、迷うために読むものなのだから。