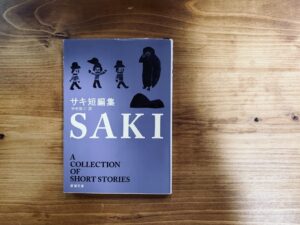島田荘司といえば、言わずと知れた新本格ミステリの開祖。
その代表作である『占星術殺人事件』や『斜め屋敷の犯罪』など、ぶっ飛んだトリックと壮大な仕掛けで読者を驚かせてきた。
でも、長編だけがすごいわけじゃない。むしろ、彼の本質がぎゅっと詰まっているのは短編かもしれない──と強く思わせてくれるのが、この『舞踏病』である。
この作品は、短編集『御手洗潔のダンス』に収められた一編で、シリーズ5作目にあたる。御手洗潔と石岡和己の名コンビが、浅草のとある古びた下宿に現れた「夜な夜な踊る老人」という奇妙な依頼に挑む。
キーワードは「狐憑き」と「大正時代の因縁」。一見、怪談めいた導入ながら、最後にはしっかりとロジックで決着をつける。そのギャップが実に心地いい。
100ページ程度の中に、奇想・論理・歴史・都市・人間ドラマといった島田ミステリの要素がすべて詰め込まれていて、読み終えたあとは本当に短編だったか?と錯覚するほどの満足感がある。
狐憑きとダンスの謎
足つきも、阿波踊りのステップを極端にしたようである。大きく高く、膝を振りあげる。体はタコのようにくねくねと蠕動する。手はもう無茶苦茶に振り廻すような印象で、狂気の発作としか見えない。
しかし何よりすごいのは、その表情だった。口を、横方向に大きくかっと開き、次の瞬間、しゅっとおちょぼ口のように閉じる。これを繰り返す。時おり下唇を突き出す。それからたまに舌もべろりと出す。それもめいっぱい出す。完全に狂気の発作だった。
『御手洗潔のダンス』収録『舞踏病』194ページより引用
とにかく、最初のつかみがうまい。物語は、陣内巌という人物が御手洗のもとに相談を持ち込むところから始まる。
彼が管理する浅草の下宿に、高額な家賃を払ってまで部屋を借りた謎の老人がいて、しかもその老人が夜になると踊り出すというのだ。
狐憑きのような様子と聞いて、普通の探偵なら「オカルトか精神疾患じゃないか」と取り合わないところだろう。
でも御手洗潔は違う。むしろこういう不思議な話にこそ食いつくタイプで、「面白い!」と身を乗り出す。狐憑き? 舞踏? なぜそんなに踊るの? そしてなんでそんな高い家賃を払ってまで、その部屋にこだわるのか? という、強烈な「なぜ?」が私たちにも突きつけられる。
さらに調査が進むと、今度は別の場所で歯科医の変死事件が発覚する。ここで一気に物語のトーンが変わり、「ただの変人の奇行」だった話が、「事件の可能性あり」に切り替わる。そして過去、大正時代に起きた事件という、まるで時空を越えるような要素が浮かび上がってくる。
現代の奇行と過去の犯罪がどう繋がるのか。これはまさに、島田作品の真骨頂。バラバラに見えていた要素が、御手洗潔という論理の魔術師の手によって一本に束ねられていくあの快感がある。
名探偵・御手洗潔の魅力が全開
この作品、ミステリとしての構造も素晴らしいのだけれど、それと同じくらいキャラ小説としての魅力も強い。とにかく御手洗潔がかっこよくて変人で愛おしいのだ。
最初からテンション高く、「踊る老人」の話に興奮しきっていて、手をすり合わせたり、肩をぴくぴくさせたりと、かなり挙動不審。でも、それが御手洗。どんな事件も知的なパズルとして捉え、そこに興奮してしまう。
いわゆる正義のためや報酬のために動いてるわけじゃない。このへん、金田一耕助やホームズともちょっと違う立ち位置にいて、彼自身が謎に対する執着の塊みたいな存在なのだ。
そして、そんな御手洗を見守り続けるのが、相棒・石岡和己。石岡は今回も、また変な事件に巻き込まれたとぼやきながらも、御手洗の行動にしっかりついていく。しかも語り手としての目線が常に常識的で、読者と同じ視点に立ってくれるのがありがたい。
さらに警察側、後亀山刑事や田崎刑事といったおなじみのキャラも健在で、彼らが「死体のある現実」を追うのに対し、御手洗が「踊る老人」という不可思議な謎を追っていく構図が面白い。
警察が見過ごすような些細な違和感を、御手洗は見逃さない。そしてそれが、実は事件の核心を突くものだったという流れが実にスマートで、何度見ても惚れ惚れする。
謎を解く快感と残る切なさの両立
本作のトリックについてはもちろん触れないが、言えるのは「すべての情報が最初から提示されている」ということ。つまり、読者が御手洗と一緒になって謎に挑めるフェアプレイ型の本格ミステリになっている。
ポイントは「なぜ踊るのか?」「なぜこの部屋なのか?」「なぜ多額の家賃を払うのか?」という、いくつものなぜが重なっていくところだ。それらを解く鍵は、空間構造・音・時間・記憶──そんな、普通の事件捜査ではあまり注目されないディテールの中に隠されている。これがまたいい。
しかし、謎がすべて解けたあとに残るのは「すごい!」だけじゃない。むしろ、そうだったのか……という、ちょっと切ない気持ちが胸に残る。狐憑きのように踊っていた老人の背後にあったもの。それは人の悲しみであり、日本という国の歴史の影であり、決してロジックだけでは割り切れない感情だったのだ。
その意味で、『舞踏病』は、幻想と論理だけでなく、「感情」と「日本の歴史」にも深く踏み込んだ物語だと思う。浅草という土地の記憶、大正と昭和の交錯、人の心に残り続ける何か。
そういうものすべてが、わずか100ページの中で見事に描かれている。
短編の名を借りた長編級の傑作

絵:四季しおり
というわけで、『舞踏病』はまさに御手洗ミステリの完成形と呼びたくなる作品だ。
構造的にはしっかり論理派。雰囲気は幻想ミステリ。なのに読後感は、なぜかしっとりと胸に残る。そして、シリーズを初めて読む人にとっても、「これが御手洗潔という探偵か」と一発で魅力が伝わる良い入口になっている。
ミステリを読み慣れている人にも、ちょっとした気分転換が欲しいときにも、この作品のような一編は嬉しい存在だ。鮮やかなロジックの心地よさと、人間くさい余情の両方が詰まっている。
御手洗潔が「踊るように推理を展開する」という意味でも、『舞踏病』はまさに彼の「ダンス」であり、読者を巻き込む旋律そのものである。
そのステップが描き出す真相の軌跡は、美しく、そしてどこか切ない。
「この世界は神の皮肉に充ち充ちているのさ。この世のあらゆる現象や行為が、すべからく「善』か「悪』と書かれたバスケットに分類できれば楽なんだけれどね」
『御手洗潔のダンス』収録『舞踏病』299ページより引用