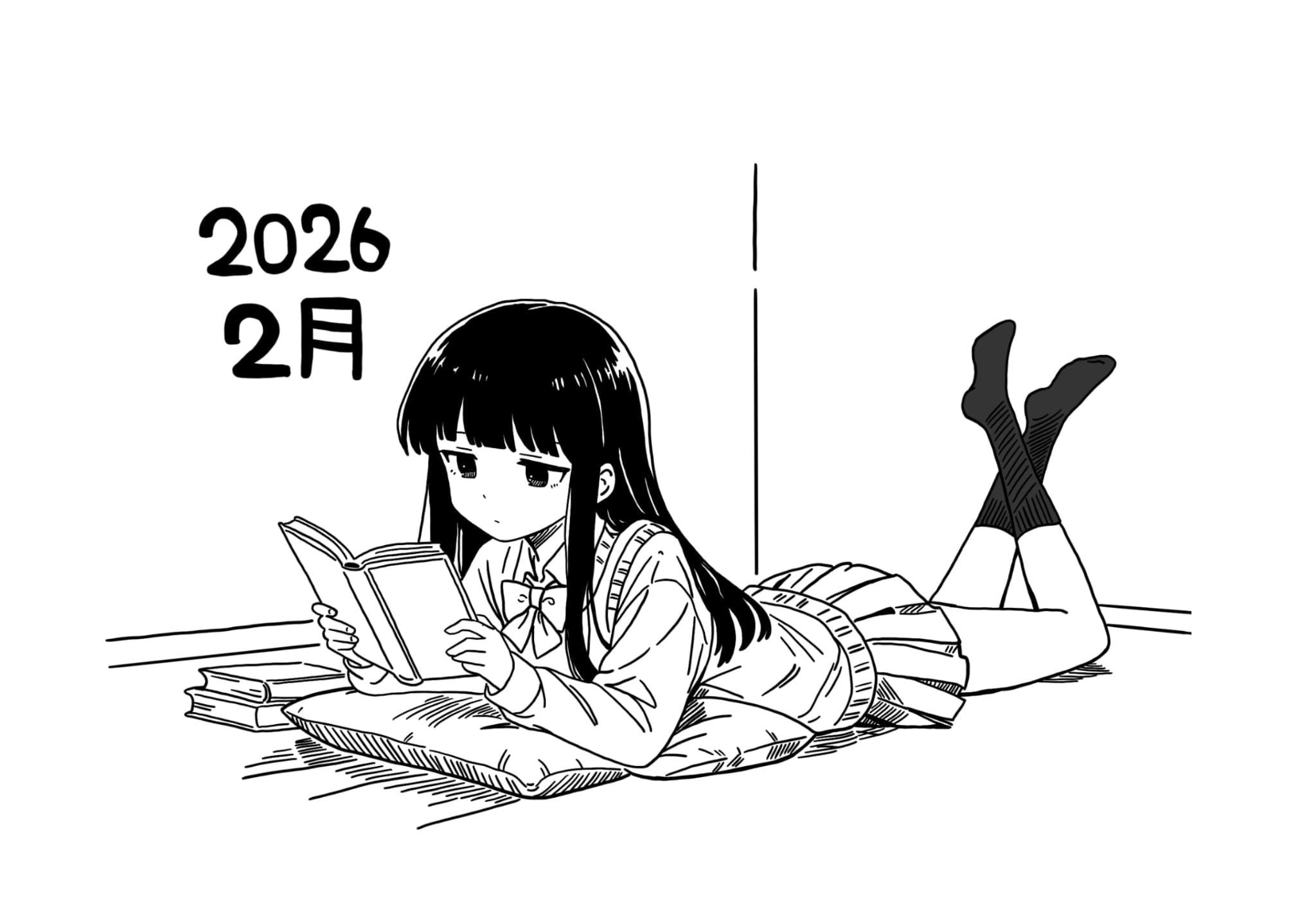四季しおり
四季しおり2025年11月に読んだ本の中から、特にこれは面白い!と思った16冊をご紹介するぞ。
・2025年10月に読んで特に面白かった本15冊 – 『本好きに捧げる英国ミステリ傑作選』ほか
・2025年9月に読んで特に面白かった本15冊 – アンソニー・ホロヴィッツ『マーブル館殺人事件』ほか
・2025年8月に読んで特に面白かった本17冊 – パーシヴァル・エヴェレット『ジェイムズ』ほか
・2025年7月に読んで特に面白かった本10冊 – 夜馬裕『イシナガキクエを探しています』ほか
・2025年6月に読んで特に面白かった小説7冊 – 小倉千明『嘘つきたちへ』ほか
1.世界は「謎」でできている── 伊坂幸太郎『さよならジャバウォック』
「夫は死んだ。死んでいる。私が殺したのだ」
そんな冒頭から始まる小説が、あんな着地するなんて、誰が予想できただろうか。
DV描写、浴室での死体、幼い息子の帰宅、そして訪ねてくる旧友……。ここだけを切り取れば、社会派サスペンスかDV被害者の再生譚と思われるかもしれない。
でも伊坂幸太郎がそんな一本調子の小説を書くはずがない。むしろこの導入は、「ここから物語は広がっていくぞ」という宣言なのだ。
読んでいくと、これはただのDVサスペンスでも、密室ミステリでもないとわかってくる。むしろ、「この先どうなるんだ?」というワクワク感に引っぱられて、どんどんページをめくってしまう類の作品だ。
混沌の中にあるリズムと再構築される世界
物語のスタート地点は、殺人を犯した「私」と、その直後にインターホン越しにやってくる謎の男・桂凍朗。この時点では完全に袋小路のような状況だが、そこからぐいっと視点が変わり、登場人物もガラリと入れ替わる。
そう、伊坂作品でおなじみの少し変な名前の人たちと、謎の二人組が登場するわけである。緊張と緩和のバランス感覚は抜群で、『グラスホッパー』や『マリアビートル』が好きな人はニヤリとするはずだ。
どこに向かっているのかまるで見えない展開なのに、読んでいてまったくストレスがない。むしろ「何が何だかわからない」こと自体が楽しい。「まあ伊坂幸太郎だし、ちゃんとオチるでしょ」という謎の信頼を持ってついていく。それこそがこの作品の肝だ。
タイトルの「ジャバウォック」は、キャロルの『鏡の国のアリス』に出てくる怪物。意味深だが、たぶんこの作品でジャバウォックが象徴しているのは、理不尽とか混沌とか、そういうもの全般なんじゃないかと思う。現実にある名状しがたい不安、それと物語的カオス。それが読み進めるにつれて、どんどん形を変えていく。
それにしても、最後の一手には本当に驚かされた。伊坂幸太郎本人が「ネタバレしないで」と呼びかけているぐらいなので、何も知らずに読むのが正解だ。というか、途中まで「これどう終わるんだ?」と思っていたのに、終盤で一気に全てがつながる快感が押し寄せてくる。再読したくなるタイプのやつだ。
名台詞も、音楽のモチーフも、寓話っぽい仕掛けも、伊坂印がてんこ盛り。それでも決してくどくない。むしろ、全部がピタッと収まる瞬間がちゃんと用意されているあたり、「結局、伊坂幸太郎なんだよなあ!」と歓喜した。
「読者を信頼する作家」である伊坂幸太郎は、いつだってフェアで、いつだって自由だ。『さよならジャバウォック』は、その集大成にして再出発のような一冊だった。
ページをめくるたびに、世界がちょっとだけ信じられる気がする。
だから、私は伊坂幸太郎を読み続ける。
それはたぶん、謎の向こうにちゃんと「希望」が待っていると、どこかで知っているからだ。
2.Jホラー×ゲームノベライズの極限融合── 黒史郎『サイレントヒルf』
日本のホラーは、なぜか湿っている。そんな漠然としたイメージがある。畳のにおい、曇ったガラス、ぬかるんだ山道、誰もいない集落。
黒史郎が手がけた『サイレントヒルf』は、そんな湿度の高い恐怖をこれでもかと凝縮した一冊である。そしてそれが、あの『サイレントヒル』シリーズの新たな形として現れた、というのが本作の面白さだ。
舞台は1960年代の日本。山に囲まれた田舎町・戎ヶ丘を襲う霧、そして現れる何か。主人公の女子高生・雛子は、ありふれた家庭のいさかいから外に飛び出し、やがて恐怖の裏世界に足を踏み入れていく。
──ここまでは王道のJホラーだが、本作が異色なのはその表現の方向性にある。
湿度と花弁と臓物が同居するノベライズ
キーワードは、「美しくて、おぞましい」。
原作ゲームでも提示されていたこのテーマが、小説版では徹底的に追求されている。咲き乱れる花のように開いた臓器、不自然にねじれた身体、病的なまでに繊細な心理描写。黒史郎らしい怪談的語り口が、ゲームのビジュアルに負けない読ませるグロテスクを生み出している。
しかもこの原作ゲームのシナリオは、あの竜騎士07が担当している。閉鎖的な村社会、疑心と祟り、誰にも頼れない絶望感。『ひぐらしのなく頃に』を思わせる要素がふんだんに盛り込まれつつ、ノベライズでは雛子の内面がさらに深く掘り下げられており、「ゲームでは見えなかったもの」が見えてくる構造になっている。
分岐型ストーリーを小説に落とし込み、読むサイレントヒルとしての満足度はかなり高い。
注目したいのは、時代設定である。なぜ1960年代なのか? これは単なるレトロ演出ではない。当時の日本が抱えていた近代化に置き去りにされた集落という空気が、サイレントヒル本来のテーマ──罪、贖罪、内面世界の具現化──と完璧にマッチしている。
閉鎖された町で少女が直面するのは、異形のクリーチャーだけでなく、「何も言わずに監視してくる社会の目」でもある。
ゲーム原作×Jホラーという異色の掛け合わせを、ここまで自然に、そして不穏にまとめ上げた作品は珍しい。ノベライズという枠を超えて、これは一つの文学的ホラー体験として記憶に残る。
はたして、霧の向こうにあるのは、化け物か、それとも自分自身か。
3.それは「ゲーム」なんかじゃ済まされない── 橘玲『HACK(ハック)』
「欠陥があるから、ハックする」──そう言い切る主人公の姿勢に、しびれてしまった。金融の知識とハッキング技術を武器に、税制度すら裏をかく。
しかしそのゲームは、いつの間にか国家と国家がぶつかるサイバー戦争の渦に飲み込まれていく。
橘玲11年ぶりの小説『HACK』は、スリル満点のサスペンスであると同時に、今を生きる私たちの「世界の見え方」を考え直す、思考実験のような一冊だ。
現実とフィクションの境界線を曖昧にするスリラー
物語の主人公は、天才ハッカーの樹生。仮想通貨で得た利益をバンコクでの優雅な暮らしに変えた彼は、ある日「沈没男」と名乗る謎の情報屋から仕事を持ちかけられる。
詐欺や強盗の資金を暗号資産でロンダリングせよ──気まぐれで請けたその依頼は、日本の公安調査庁、北朝鮮の国家ハッカー「ラザルス」、そして伝説のハッカー「HAL」まで巻き込む、地政学的な戦争の始まりだった。
面白かったのは、なんといっても現実社会への鋭すぎる切り込みだ。米大統領選、ロシア・ウクライナ戦争、北朝鮮の暗号資産略奪といった時事ネタが、リアルすぎる熱量で組み込まれている。
これらが単なる背景でなく、物語の根幹にある「マネーと権力の脆弱な関係」として機能しているのがすごい。橘玲の著作を読んだことがある人なら、「あの知識がフィクションに活きてる!」と唸るはずだ。
そして、ハッキング描写のガチっぷりにも驚かされる。ゼロデイ攻撃、暗号化通信、TORとSignal、パケット解析……単語だけで頭が痛くなるが、読み進めるほどに、「守る側はすべての穴を塞ぐ必要があり、攻める側は一つで足りる」という不条理が、恐怖として染み込んでくる。
とはいえ本作は、ただのテクノスリラーに終わらない。暗号資産を巡る「光と影」を、樹生というキャラクターの視点から描いている点が深い。国家の規制を逃れた自由な通貨としての理想と、それがテロや独裁国家の資金源になる現実。
そのアンビバレンスを提示しながら、物語は最後にこう語りかけてくる──「果たして私たちは、どちらの未来を選ぶべきなのか?」と。
読み終えたあと、思わずスマホのパスワードをもう一段階強くしたくなる。
そんな現実に食い込んでくるフィクション、それが『HACK』である。
4.時間は過ぎるのではなく、還ってくる── 小池真理子『ウロボロスの環』
終わったはずの感情が、ある日ふいに戻ってくることがある。
忘れたと思っていた痛みが、何の前触れもなく蘇る瞬間がある。
小池真理子『ウロボロスの環』は、そうした戻ってくる時間に取り憑かれた人々の、長い長い心の記録である。
物語は1989年、主人公・彩和と俊輔の結婚披露の場面から始まる。若くして夫を亡くし、幼い娘と生きてきた彩和にとって、再婚は安らぎと未来を意味するはずだった。
だがそれは、時間の環(リング)の出発点でしかなかった。
過去は死なない。たとえ葬ったつもりでも
彩和は、夫・俊輔が抱えるある「秘密」に直面する。法律的な問題ではない。けれど、人間として、夫婦としての根幹を揺るがすほどの何かである。
この作品は、その秘密の暴露をスリリングに描くというより、その後の「時間の経過」そのものを描いている。幸福が徐々にひび割れていく過程、感情の変化を観察し続けるような緻密さで。
注目したいのは、この作品が1100枚という長編である理由だ。タイトルにある「ウロボロス」とは、自らの尾を食む蛇。つまり、終わりと始まりが接続された循環を意味する。過去の記憶が、まるで亡霊のように現在を侵食する構造。
喜びも悲しみも、時間を超えて繰り返される。そして私自身もまた、登場人物たちと一緒に「終わらない感情の迷路」に閉じ込められてしまった。
もう一つの特徴は、まるで舞台劇のように限定された空間と人数で展開される室内劇のような語りである。日常の中のささいな視線、黙り込んだ沈黙、何でもない言葉の奥に潜む異変の兆し。派手な展開はないのに、読んでいて背中が冷えるような感覚が持続する。この緊張感の出し方は、もはや職人芸と呼んでいい。
そして何より怖いのは、すべてが「ありそう」なことだという点だ。カルトも殺人も出てこない。それでも、自分にも覚えがあるような些細な不安が積み重なっていき、「人間ってこうやって壊れるんだな」と思わされる。恐怖は外側からではなく、内側から滲み出てくるのである。
だからこそ、読後にじんとくる。派手な山場も、劇的などんでん返しもない。それでも、この物語は確かに人生そのものを描いていた。
時間は過ぎていくのではない。
私たちの中を、何度も何度も、還ってくるのだ。
5.謎が人生を変える物語── 梓崎優『狼少年ABC』
長かった。新刊が出るまで、12年。けれど読めばすぐにわかる。
「梓崎優は、やっぱりすごい」
そう呟きたくなる帰還作が、この『狼少年ABC』である。
ミステリであり、青春小説であり、人生のひとコマをまるごと差し出してくるような切なさのある全4編。どの話にも共通しているのは、「謎を解くことが、人生の分岐点になる」という一点だ。
ミステリは、心を暴き、明日を変える
表題作『狼少年ABC』は、カナダの原生林にぽつんと建つ観察小屋が舞台。日本人大学生3人が、狼の生態調査という名目で滞在している。だが、調査そっちのけで繰り広げられるのは、延々と続く駄弁り。
これがめっぽう面白い。『水曜どうでしょう』みたいなゆるさと、密室劇的な緊張感が同居する空間で、ふとした一言からとある過去の謎が浮上し、会話の延長線上で推理合戦が始まる。
この一編だけでも十分に濃密だが、本作の真価は収録作すべてに共通する「謎が人間の核心に触れる構造」にある。
『美しい雪の物語』では、ハワイ島を舞台に11歳の少女が叔父の秘密に向き合い、『重力と飛翔』では写真に隠された違和感が高校生の記憶を揺さぶる。そして『スプリング・ハズ・カム』では、タイムカプセルから見つかった犯行声明が、かつての春をもう一度現在へ呼び戻す。
どれも事件のスケールは小さい。でも、謎を解くという行為が、登場人物たちの人生に決定的な変化をもたらす。この視点の導入こそ、梓崎優の本領だろう。彼のミステリでは、推理は単なる遊びではない。自分の傷に気づき、他人の苦しみを理解し、そしてほんの少しだけ前を向くための「手段」として位置づけられている。
また、どの話も舞台は異国や旅先など非日常的だが、描かれる感情はきわめて身近で普遍的だ。後悔とか、寂しさとか、もう戻れない時間への思いとか。そのギャップが物語全体に心地よい浮遊感をもたらしている。
12年の空白を経てなお、この作家はまったくブランクを感じさせない。むしろ、「これを読むために12年待った」とすら言える出来栄えだった。
謎は、過去を照らすだけでなく、未来の選び方すら変えてしまう。
本作は、そのことを力強く証明している。
6.そこに故郷があるとして、誰のものなのか── 小川哲『火星の女王』
火星が舞台のSFと聞いて、赤い砂漠や孤独な宇宙飛行士を思い浮かべる人は多いかもしれない。
でも小川哲が描く火星は、それとはまるで違う。そこには、リアルすぎる社会と、移民問題、分断、そして自分がどこに属しているのかという切実なテーマがある。
『地図と拳』で歴史とアイデンティティの問題に踏み込んだ著者が、今度は宇宙という遠い舞台で、またもとんでもない物語を見せてくれた。
火星で生まれた少女と、未来の見えない現実
時代は2125年。人類が火星に定住してから40年が経ち、火星はもう未知のフロンティアではなく、普通に人が暮らす生活圏になっている。そんな場所を舞台に、物語は複数の視点から語られる。中でも特に印象的なのが、火星で生まれ育ち、視覚障害を持つ少女・リリの存在だ。
彼女は地球を見たことがない。けれど「行ってみたい」と夢見ている。ただ、そのためには自分の身体そのものを変えなければならない。火星の重力に最適化された身体では、地球の重力に耐えられないのだ。リリが通う人工重力施設は、そのまま「二つの故郷に引き裂かれる」ことの象徴でもある。
この設定だけでも相当面白いのだが、小川哲はここにしっかりと現実の社会課題を織り込んでくる。火星生まれの人々と、地球から来た移民テランとの断絶。政治的緊張、自治警察と独立派の対立、地球外生命体を探す科学者の執念……すべてが複雑に絡み合い、単なるSFではなく、ガチの社会小説になっている。
さらに面白いのは、視覚障害のあるリリの視点描写だ。火星の風や音、気圧の変化、床の感触。そうした視覚以外の感覚で描かれる世界は、逆に圧倒的な臨場感を持って迫ってくる。映像化ありきの作品が増える中で、これはむしろ映像化が難しい感情を真正面から描こうとしているように思う。
火星という遠い星の話のようでいて、本質的には「自分の居場所がどこにもない」と感じたことがあるすべての人に刺さる話だ。小川哲の描く火星は、未来を借りた今の物語なのである。
火星は、遠い未来の話ではない。
それは、「誰の世界でもない場所」を探し続ける、すべての人間の物語なのだ。
7.密室は部屋ではなく、「家庭」だった── 葉真中顕『家族』
「家族って、なんだと思います?」
そう尋ねられて、即答できる人は少ないかもしれない。でもこの小説を読んだあとでは、どんな答えも、ひどく危うく感じられるはずだ。
葉真中顕『家族』は、フィクションの皮を被った凶器のような物語である。モチーフは「尼崎連続変死事件」。でも本作が描くのは、単なる事件の再現ではない。
家族というもっとも安全なはずの場所が、いかにして拷問と殺人の舞台になりえるか。そのメカニズムを、一つずつ暴いていく社会派クライム・ミステリーだ。
支配は、殴ることではなく、愛を歪めることから始まる
始まりは2011年11月。深夜の交番に、裸足で駆け込んできた一人の女性・奥平美乃。その証言から次々と明らかになるのは、主犯・夜戸瑠璃子が築き上げた「擬似家族」の恐るべき構造だ。
彼女はターゲットとなる家庭に入り込み、言葉と暴力と洗脳で家族の人間関係をズタズタにし、互いを監視させ、最終的には殺し合わせる。まるで舞台装置のように、他人の家庭を組み換えて死を演出していく。
怖いのは、暴力そのものよりも、その過程にある。加害者はいつも瑠璃子ではない。被害者自身が、他の被害者を殺す。あるいは無視する。助けを求められても、「見なかったこと」にする。その構造が何重にも積み重なっていく。誰もが他人事だと思いたくなるが、この小説はあえてそこに踏み込む。「もし自分だったら」と問うてくるのだ。
葉真中顕の作風は、前作『ロスト・ケア』でもそうだったが、常に社会と個人の裂け目に手を突っ込む。今回も例外ではない。「警察は民事不介入」を盾に手を出せず、学校や福祉も見て見ぬふりをする。
その結果、家庭という密室は完全に孤立する。つまり、「家庭だからこそ介入できなかった」という構造こそが、最大の加害者なのだ。
そしてもう一つのポイントが、平成という時代背景である。バブル崩壊以降の不況、地域共同体の崩壊、家族の孤立化。そうした時代の空気が、瑠璃子のような寄生型の犯罪者を生み、寄生先となる弱った家族を用意してしまった。そう考えるとこの本は、この平成日本の総決算としても読める。
「家族って、なんだと思います?」
その答えは、読み終わってからでいい。
けれど一つだけ確かなのは、もう二度と、この問いに「ありきたりな言葉」で答えられなくなるということだ。
8.世界を救うのは、負けても続けるあの手の動き── 呉勝浩『アトミック・ブレイバー』
「何十回やっても勝てない。でも、もう一回やってみる」
そんな気持ちでゲームに向かい続けた夜は誰にでもあるはずだ。
でもそのもう一回が、本当に世界を救ってしまったら?
呉勝浩『アトミック・ブレイバー』は、eスポーツ×SF×国家安全保障という破天荒な設定を全力で突き抜けた、痛快すぎるエンタメ小説である。
凡人の「連打」が、世界を救う
舞台は、27年前の小型核テロ「ヴァージン・スーサイズ」以降、国民の睡眠すらアプリで管理されるようになった近未来。
主人公・堤下与太郎は、どこにでもいるような普通のサラリーマン。ある日、彼の睡眠アプリがハッキングされる。犯人は失踪中の旧友であり、かつての天才プログラマー・西丸昴。そして与太郎はいつの間にか、人気格闘ゲーム『アトミック・ブレイバー5』の改造版をプレイする羽目になる。
ただのゲームかと思いきや、その勝敗が現実世界の平和維持システムとリンクしているという展開に、さすがに笑った。しかも与太郎を狙うのは、政府機関と過激派組織の両方。コントローラーを握っていた手が、そのまま国家規模の争奪戦を引き起こす。このスケールの飛躍こそ、呉勝浩の真骨頂だ。
この本の魅力は、何より与太郎のキャラにある。彼には特別な才能も技術もない。ただ、勝てなくてもやめない。諦めずに何度でもコンティニューする。この粘りが、現代社会で軽視されがちな「無駄な努力」や「効率の悪さ」に意味を与えている。タイパ重視の時代に逆行するようなテーマ設定が、むしろ今読むべき物語にしている。
そして、ゲームと現実がつながっているという設定も、現代的だ。遠隔兵器、メタバース、リアルタイム操作……こうした技術が現実味を帯びる今、本作は「もしこの先、ゲームが現実と接続されてしまったら?」というテーマを、真正面から描いてみせる。
小説の中では、チャットログやUIが地の文に自然に組み込まれており、読みながら本当にプレイしている感覚に近づいていくのも面白い。
ジャンルを飛び越える筆力、疾走感、そしてバカバカしいほど熱い展開。呉勝浩のエンタメ変身ぶりに、いい意味で脳がバグってしまう。
この物語は、勝者の美学ではない。
何度負けてもコンティニューする人間の粘りの物語だ。
ゲームなんかに意味があるのか?
あるに決まっている。
その疑問への最高の回答が、ここにある。
9.ジャンルを背負って駆け抜けた、筒井康隆という現象── 『筒井康隆エッセイ集成 1: SFを追って』
筒井康隆といえば、奇才とか異端とか、いろいろな言葉がくっついてくる作家だ。でもこの一冊を読めば、それらのラベルを貼るだけでは到底おさまらない、とんでもない熱量と気概に圧倒されるはずである。
『SFを追って』は、彼がどれだけ本気でSFというジャンルに向き合ってきたかを記録した、いわば「筒井康隆というジャンルの始まり方」を追体験できる本だ。
収録されているのは、1960〜80年代にかけて筒井がさまざまな媒体に書き散らしたエッセイ、評論、雑感、コメント類。しかも、これまでの全集やエッセイ集では拾いきれていなかった未収録テキストを中心に構成されている。
編集を手がけたのは、ジャンル系資料発掘の第一人者・日下三蔵。読み進めるたびに「こんな貴重な文章、どこに埋まってたんだ」と驚かされた。
SFを子どもの読み物から文学へ──その戦いの記録
開幕は1963年のSF大会寄稿文。若き日の筒井康隆が、「日本のSFはここから始まる!」とばかりに情熱をぶつけている。
そこから、自作の裏話、小松左京や星新一との交流、当時の文壇の冷ややかな視線との応酬、ニューウェーブ運動への共鳴などが綴られていく。「エッセイ集」というよりは、「ジャンル創生期の実況中継」に近い。
印象的なのは、文章のトーンが軽妙なのに、根っこの部分はとにかくガチなところだ。ユーモアも飛ばすけれど、本気で怒って、本気で笑って、本気で時代と格闘している。SFという言葉がまだ信用されていなかった時代に、「これは文学だ」と言い切り、突き進んできた人の言葉には、いちいち説得力がある。
そして何より驚くのは、その視点の先見性だ。情報社会、個人の分断、虚構と現実のあいまいさ……昭和の雑誌に載っていたはずの文章が、いま読むとやたらと2025年的に感じられる。筒井康隆が未来を描いていたのではなく、人間の変わらなさを描いていたからこそ、今もリアルに響くのだろう。
この一冊には、筒井康隆の「面白い話」だけでなく、「本気でSFをやるってどういうことか」がぎっしり詰まっている。
彼はただ作品を書いていただけじゃない。ジャンルそのものを広げ、押し上げ、担いで走っていた。
それを証明する、まさに闘いと遊びの記録だ。
10.友情という名前の信仰が、目を奪っていく── 町田そのこ『彼女たちは楽園で遊ぶ』
町田そのこと聞くと、やっぱり『52ヘルツのクジラたち』とか『汝、星のごとく』のような、心に沁みる再生の物語を思い浮かべる。
でも本作『彼女たちは楽園で遊ぶ』は、読後に癒やされるタイプではない。むしろ、背筋が寒くなる。なにしろ、カルト宗教と土着信仰、そして「目を奪う怪異」の話なのだから。
とはいえ、単なる因習ホラーかといえば、そうでもない。この作品の怖さは、もっと湿っぽくて、もっと現実に近いところにある。高校生たちの間に生まれる、友情とも依存とも言い切れない関係性。信じたい物語にすがる心。
それらが、不気味な宗教の教義や儀式と結びついたとき、物語は一気に取り返しのつかない場所へと突っ込んでいく。
土着ホラー×青春群像の不安定なバランス
物語の主人公は高校2年生の凜音。夏休みのある出来事をきっかけに親友と気まずくなり、そのまま新学期を迎える。しかし、親友は学校に現れない。家を訪ねると、なぜか「売家」の札。
彼女の行方を探るうち、どうやら家族ぐるみでとある宗教団体に入信したらしいと分かる。このあたりの展開は、青春小説の体を装いながら、明らかに不穏な空気をまとっていて、読み進める手が止まらなくなる。
何より印象的なのは、凜音の動機が「友情」であることだ。誰かを救いたいと思う気持ちが、結果として恐ろしい現実を暴いていく。この構造がすごく効いていて、「ホラー」の本質が異常な他者ではなく、ふつうの私たちの側にあることを思い知らされる。
本作は、いわゆる因習ホラーの文法をしっかり踏まえている。山中にある閉鎖的な宗教施設、不気味な儀式などなど。そうした要素は、Jホラーや土着民俗ホラーの文脈を思わせるが、語り口は終始淡々としていて、キャラクターたちは等身大の現代高校生として描かれている。
だからこそ怖い。異常な世界に飲み込まれるのが、超常的なヒロインではなく、普通の子だからだ。友達のために動き、悩み、泣きながらも引き返せなくなっていく。その過程がとても丁寧に描かれている。中盤以降、仲間たちと手を組んで真相に迫っていく展開は、ミステリとしても読みごたえがある。
そしてこの作品の裏テーマは、「日常の壊れやすさ」にあると思う。ほんの少しの言葉の行き違い、家庭の問題、あるいは信じたい何かにすがる気持ち。それらが重なったとき、人は案外あっさりと奇妙な世界に足を踏み入れてしまうのかもしれない。
これは、青春×ホラーというより、青春がホラーになってしまう小説である。
友情を信じること。誰かを助けたいと思うこと。その気持ちは、時に何よりも尊い。でも同時に、もっとも危うく、もっとも痛ましい狂気にもつながる。本作は、その境界線を見せつけてくる。
そして思う。「もし自分が凜音の立場だったら」と。
怖いのは、山の中の教団ではない。
怖いのは、信じるという行為そのものだ。
11.人を食う社会が、こんなにも整然としているなんて── アグスティナ・バステリカ『肉は美し』
肉が食べられなくなった世界で、人間が合法的に「家畜」になる。
そんな設定を聞いただけで、読むのをためらう人もいるかもしれない。
実際、私もこの本の存在を知ったとき戸惑った。でも、それでもページをめくってしまったのは、「これはたぶん、人を食う話なんかじゃない」と思ったからだ。
そしてその直感は、当たりでもあり、外れでもあった。
食人ディストピアが照らす、資本主義と倫理のねじれ
舞台は近未来。動物の肉がすべて有毒化し、人類は苦渋の末に人を食べることを制度化する。人間を「頭」と呼び、食肉用に育て、解体し、流通させる社会。
人肉の精肉業者である主人公マルコスは、かつての畜産工場のノウハウを引き継ぎつつ、この異様な業界の中間管理職として日々を淡々とこなしている。
恐ろしいのは、この世界に「狂気」がないことだ。屠殺も養殖も解体も、すべてが衛生的で事務的に行われている。人を食べる、という暴力の本質は、白衣と書類と流通コードの中に隠される。感情を排した文体で、人間の処理工程を逐一描写するバステリカの手つきには、ぞっとするほどの冷静さがある。
この社会では、「頭」には声帯がない。なぜなら、声があれば、それは誰かになってしまうからだ。マルコスはそんな無言の彼女をギフトとして受け取り、自宅の納屋で飼い始める。
ここで一瞬、「ああ、反体制的な希望の物語か?」と思わせておいてからの、精神的サディズム。マルコスの感情は愛なのか、所有欲なのか、自己満足なのか。
この物語は、ただのショック小説ではない。「人間を食べるなんてひどい」と思うとき、すでに自分がどれだけ搾取する側のシステムに組み込まれているかを考えさせられてしまう。服や食料や快適さの裏側で、人間的な尊厳を奪われた誰かが沈黙している。その不均衡の上で、私たちは「善良な人間」として生きているのだ。
善悪とか倫理とか、そういう概念が薄まっていく感覚。
『肉は美し』は、人を食う話である以上に、「あなたは本当に誰も傷つけずに生きてるか?」と語りかけてくる小説だ。
正直しんどいけど、読んだあとに黙っていられない。そういうタイプの本である。
12.空中密室が回り出すとき── トム・ミード『空に浮かぶ密室』
「観覧車の上で人が撃たれた」
そんな導入だけで、もう半分勝ちなのだ。
舞台は1938年のロンドン。観覧車のてっぺん、地上から孤立したゴンドラの中で、男が射殺さる。傍らには妻。凶器は彼の足元に転がり、周囲に他人の気配はない。
どう考えても、同乗していた妻が犯人としか思えないが、彼女は無実を訴える。
では、引き金を引いたのは誰だ?
というか、銃はどこから来たのか?
演出された不条理と、繰り返される密室の罠
トム・ミード『空に浮かぶ密室』は、『死と奇術師』に続くシリーズ第2作。だが本作の狙いは明確だ──読者の予測を裏切ること。しかも、クラシカルな密室形式を踏襲しつつ、さらにひとひねりを加える形で。
まず目を引くのが、「観覧車」という密室設定だ。壁に囲まれていないのに物理的に逃げられない、という逆説的な閉鎖空間。銃声が轟くのは空中。つまり「どこから撃ったか」ではなく、「なぜそんな場所で殺したか」が鍵になる。
法廷劇の要素も効いている。被害者の妻カーラは、事件直後に容疑者とされる。弁護を務めるのは若き弁護士エドムンド・イブズ。彼が語り手を務めることで、事件の輪郭は真相を追うというより、無実を組み立てる形で立ち上がっていく。探偵の視点から推理するのではなく、法廷という時間制限のある舞台で、論理を武器に戦っていくスリルがある。
後半では二重三重の密室が登場。劇場で、楽屋で、そしてついにはイブズ自身もまた密室の中で極限状況に追い込まれていく。探偵と容疑者が入れ替わるような展開、ミスリードの伏線、その裏返しの論理構成。すべてが、密室ミステリ好きの心を刺激する仕掛けだ。
というわけで、この作品は密室マニア向けの逸品でありながら、法廷もの、倒叙、舞台劇構造、メタ的仕掛けと、複数の読み味を内包している。
タイトルに惹かれたら、もう逃げられない。
観覧車が動き出したら、最後まで乗るしかないのだ。
13.閉ざされた部屋でつくられる、こわれた愛の神話── ジャン・コクトー『恐るべきこどもたち』【再読】
ジャン・コクトー『恐るべきこどもたち』は、一見すると古典的な青春小説のようでいて、実際にはもっと恐ろしいものを描いている。
美しい姉弟が「子供部屋」と呼ばれる一室に引きこもり、自分たちだけのルールで世界を回す。こう書くと穏やかに聞こえるかもしれないが、実際はその部屋こそが、甘美で閉鎖的で、逃げ場のない牢獄なのだ。
弟のポールは、雪玉に仕込まれた石で負傷して学校に行けなくなり、姉のエリザベートと共に自宅にこもりきりになる。ふたりの関係はどんどん共依存的になり、やがてゲームと呼ばれる空想劇に耽溺し始める。
そこに友人ジェラール、そしてポールの憧れだった同級生にそっくりな少女アガートが加わったことで、密室の人間関係は一気に濁りはじめる。愛と嫉妬と支配欲がぐちゃぐちゃに絡まり合い、「大人になること」への拒絶を軸に、物語は神話的な破局へと突き進んでいく。
いま読んでこそ刺さる、推し活時代の病理
本作の魅力は、古典でありながらまったく古びていないところにある。むしろ2020年代の感覚にこそ強く響く。
ポールとエリザベートが作り上げた閉鎖空間は、現代で言えば推し活や仲間内オンリーのネットコミュニティのようなもので、そこでは共通の言語と価値観だけが絶対だ。他者は排除されるし、外の世界と接続すれば、関係性はすぐに壊れてしまう。
こうした自分たちだけの世界がもたらす安心感と、その先にある破滅の予感。この構造に、読んでいてゾワゾワした。村松潔氏による新訳は、この作品に漂う感情の湿度や緊張感を丁寧にすくい取り、会話の生々しさや神経のとがったやりとりを、するっと現代の言葉で伝えてくれる。
ポールとエリザベットの部屋は、幻想の楽園でもあるし、逃げられない監獄でもある。そして、彼らがそこに「こもる」理由が、他人には理解できないけれど、なぜかちょっとだけわかってしまう。この感覚こそが、『恐るべきこどもたち』をただの古典に終わらせない理由だ。
物語の最後に残るのは、愛か、孤独か、それとも呪いか。
彼らの閉ざされた部屋をのぞき見するような、不思議な感覚が胸に刺さってくる。
14.闇の中でしか語れない歴史がある── マリアーナ・エンリケス『秘儀』
マリアーナ・エンリケスの『秘儀』は、ホラーの皮をかぶったラテンアメリカの歴史小説であり、親子のロードノベルであり、血と闇と愛にまみれた文学的怪物である。
物語の主軸は、霊媒フアンと、その息子ガスパルの逃避行。時代は1980年代、アルゼンチンの軍事独裁政権のただ中。そんな時代に、不死を求めるオカルト教団から逃れようとするこの親子に、平穏なんてあるわけがない。
父・フアンは、強大な闇と繋がる能力を持つ男。教団の命令で儀式を行い、血まみれの死者を大量生産してきた。その代償として命は削られ、残された時間はわずか。そんな彼が何より恐れているのは、息子が自分と同じ道を歩まされることだ。
だからこそ、逃げる。命が尽きる前に、何としてでも息子を自由にしたいと願って。
血まみれの青春小説、そして愛の呪い
本作のすごさは、これがホラーだけじゃないところだ。
後半では息子ガスパルの視点で物語が動き始め、舞台はロンドン、そして再びアルゼンチンへと移っていく。彼の青春には音楽があって、友情があって、恋もある。でもその背後には、常に父の遺産が影のようにつきまとっている。
ガスパルに力があるのか? 本当に闇とつながってしまうのか? そして、父・フアンのあのやり方は正しかったのか? 答えは明言されない。でも、登場人物たちの痛みと葛藤は、ページの端から滲み出てくる。
とくに印象的なのは、愛の描き方だ。フアンは息子を愛している。命がけで守りたい。でもその愛は、時に暴力的で、呪いのようでもある。だから読んでいるほうも息子の視点で苦しみながら、父の側の愛も理解してしまう。この構造がめちゃくちゃ切ない。
ジャンルでいえばホラー。けれどその奥には、語られなかった歴史のトラウマが眠っている。エログロ、拷問、オカルト、政治、青春、音楽──どれもが無理やりに詰め込まれているはずなのに、不思議とすべてが物語として機能しているのがすごい。
『秘儀』は、死者の声を聞くための物語である。
そして、それを聞く覚悟がある人にとっては、一生忘れられない体験になる。かなり疲れるけど、読んでよかった作品だった。
15.ブラックユーモアで読み解く独裁社会の解体劇── ミハイル・ブルガーコフ『巨匠とマルガリータ』【再読】
ロシア文学と聞いて、「難しそう」と身構えてしまう人もいるかもしれない。でも、ブルガーコフの『巨匠とマルガリータ』は、そんなイメージをきれいに裏切ってくれる。
舞台はモスクワ。全体主義のど真ん中。なのに、そこへ突如やってくるのは「黒魔術の教授」と名乗る悪魔ヴォランドと、巨大な黒猫ベゲモートをはじめとした従者たち。こいつらがやらかすのが、もうめちゃくちゃで痛快だ。
偉そうな作家や役人が黒魔術ショーで正体を暴かれ、観客たちはカオスの渦に。しかも彼らの登場がただのドタバタで終わらないのがこの作品の面白いところで、同時に「巨匠」と呼ばれる男と、彼を愛する女性マルガリータの物語も進行する。
検閲に潰され、世間から消された作家を救うため、彼女は悪魔と手を組んで魔女に変身。全裸で空を飛び、死者の舞踏会のホステスまで務める。
ここだけ読んだら、どんなジャンルかわからないが、これ全部がちゃんとつながっていくのがすごい。
恐怖と笑いが同居する、芸術と自由のファンタジー
『巨匠とマルガリータ』は、政治風刺・文学論・超自然ファンタジーが同時進行するトンデモ構成の物語でありながら、ちゃんと芯がある。悪魔たちのいたずらは、実は当時のソ連の特権階級や社会の欺瞞をぶった切るものだ。
作家がキャビアを食べ、秘密警察の影に怯える中で、悪魔のほうがむしろ理知的で誠実というブラックジョーク。これは、笑えるようで笑えない。
中でも強烈なのは、マルガリータの飛翔シーンと、ヴォランドが語る「原稿は燃えない」という台詞。これは、どんな圧政の下でも、本物の芸術や表現は決して消えないというブルガーコフからのメッセージだ。
実際この作品は、ブルガーコフの死後に未亡人が隠し持っていた原稿から出版され、今も読み継がれている。彼の原稿は、確かに燃えなかった。
悪魔がやってきて暴れる話、というよりも、むしろ悪魔を借りて「この世界の狂気」を可視化しようとした作品だ。ソ連の全体主義をユーモアと幻想でぶっ叩いたこの小説は、時代も国境も飛び越えてくる。まさに「芸術の力ってこういうことだよな」と感じさせてくれる一冊だ。
読み終えたあと、空を飛びながら呟いてみたくなる。
「原稿は、燃えない」
そして、きっとその声は、どこかで悪魔にも届いている。
16.難しそうなあの本に、生活者の目で挑む楽しさ── 津村記久子『やりなおし世界文学』
「世界文学」と聞くと、ギャツビー、カラマーゾフ、赤と黒……と、知ってるけど読んでない、もしくは途中で投げたタイトルが頭にずらりと並ぶ。
そして、どこかで自分は「教養が足りないのでは?」という罪悪感に包まれる。そんな人にこそ刺さるのが、この『やりなおし世界文学』だ。
津村記久子がすごいのは、これらの古典に対して、学者でも文芸評論家でもなく、「生活者」の目で向き合っているところだ。
例えば『宝島』に出てくる主人公の少年ジム・ホーキンズ。子どもの頃に読んだときは「同年代の子どもがいなくて寂しすぎる」という感想だったそうだが、大人になって再読すると、これは船乗り社会でのサバイバルや労働、組織論の話に見えてくるという。
この視点のブレ、あるいは読みの「進化」を、あえて恥じずに記録していくスタイルが本書の持ち味だ。
「誤読」こそが面白い!文豪にツッコみ、読者を救うブックガイド
『カラマーゾフの兄弟』を全巻読破したようなマッチョな感想は、ここにはない。むしろ、登場人物の悩みには「水でも飲んでぼんやりしてな!」と声をかけ、ギャツビーの自己演出には「男性用スキンケア用品のようだ」と斬り込む。
こうした語り口は一見ラフだが、実は古典を「神棚から引きずり下ろして、自分のそばに置く」行為なのだ。
タイトルの「やりなおし」は、ただの再読ではない。一度距離を置いたものに、年齢や生活環境が変わった後で「今の自分の目」で向き合うこと。つまり、過去の読書を正さなくていいし、理解を完璧にする必要もない。
何度でも読み直せるし、途中で挫折しても構わない。そうやって、教養に対するハードルを壊しながら、自分に合う読み方を見つけていくプロセスそのものが、この本の核心だ。
文豪が並ぶ世界文学の棚の前で立ち尽くしてしまう人にとって、津村記久子の『やりなおし世界文学』は、最高の案内人になるだろう。
「名作とは、つまらなかったら閉じてもいい」と言ってくれるガイドが、どれほど心強いか。
世界文学は、いつだってこっちのタイミングで、やりなおしていいのである。
関連記事