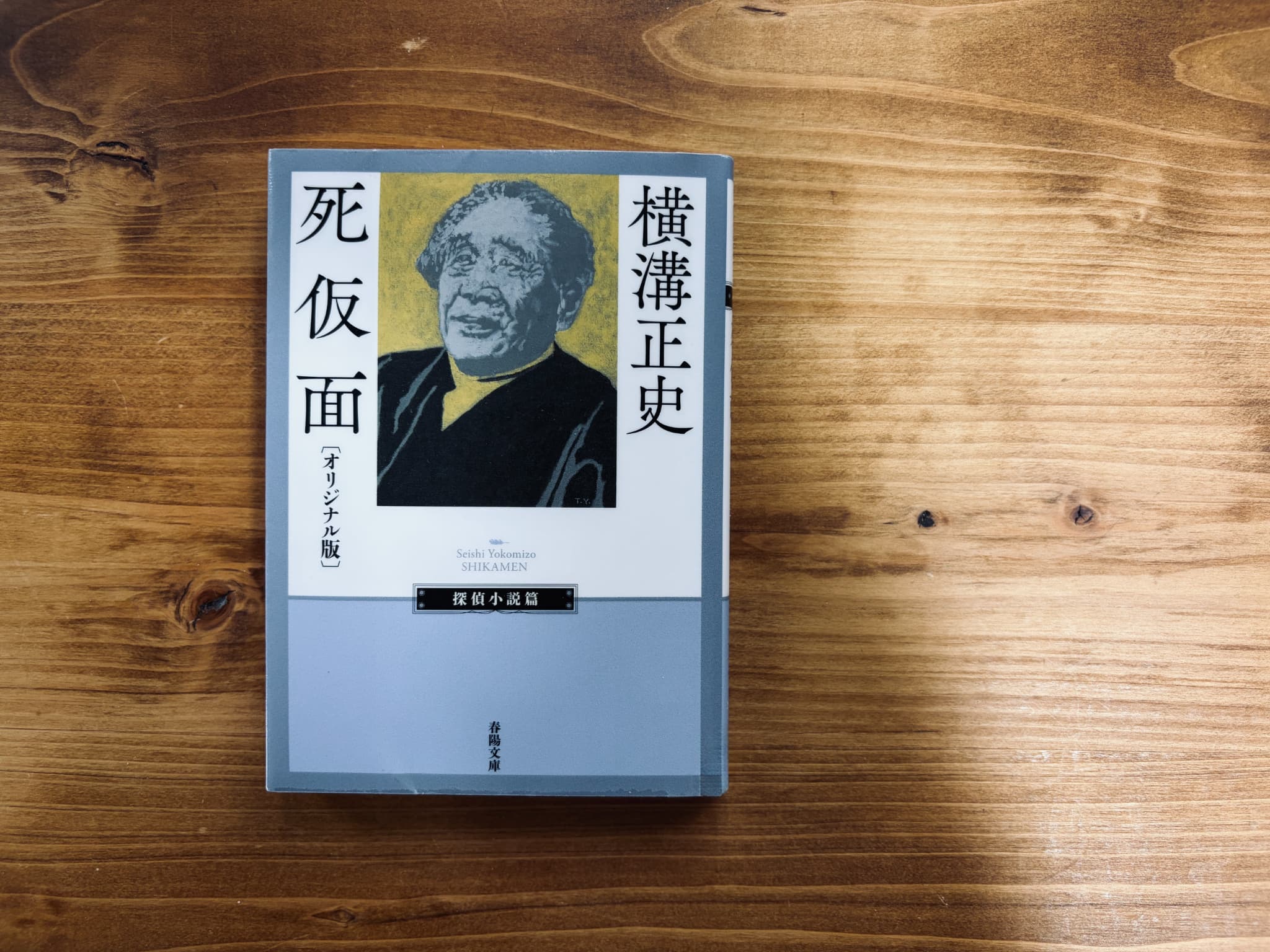この『遠海事件〜佐藤誠はなぜ首を切断したのか?〜』というタイトルを目にしてまず胸に生まれるのは、強い興味と抑えられない期待だ。
通常のミステリが、犯人は誰か、どうやったかを競い合うのに対し、本作は冒頭から「犯人は佐藤誠であり、彼は首を切った」という動かしがたい事実を提示してくる。
犯人はわかっている。では、なぜこんなにも面白いのか。
その理由は、本作がタイトル通り「なぜ首を切断したのか」という一点にすべてを集中させているからだ。
最初から出口は見えている。
けれど、その奥行きが異様に深いのだ。
感情を搭載しない、職業人としての殺人鬼
まず第一に、佐藤誠が告白した殺人は全部で八十六件である。
この数字は証言記録として残っている。さらに付け加えるなら、彼はすべての殺人を思い出せた自信はないと満らしており、この数字は上方修正の可能性を持っている。
『遠海事件:佐藤誠はなぜ首を切断したのか?』4ページより引用
まず認めておくべき事実がある。佐藤誠という男は、本質的な意味で私たちが住む世界の住人ではないということだ。
もちろん、物理的には存在している。遠海市の書店で、誰よりも正確に在庫を管理し、客の注文を過不足なく処理し、同僚からも信頼される、目立たないが有能な労働者として、彼は確かに社会に溶け込んでいる。
だが彼の精神構造を覗き込んだとき、そこに倫理や共感、罪悪感といった感情が根本から欠落していることに気づかされる。
86件という殺害件数。普通ならそこには、歪んだ愉悦か、せめて何かしらの昂ぶりがにじむはずだ。だが彼の語りは驚くほど平坦で、感情の波がほとんど存在しない。
殺人と隠滅は、ただのタスク処理。チェックリストの項目を順に消していく作業と大差がない。
多くのミステリにおいて、シリアルキラーは衝動や情念の象徴として描かれる。だが佐藤誠は違う。返品不可の重量物をバックヤードに運び適切に処理する行為と、人間をこの世から消去する行為は、彼の内部では同質の業務に分類されている。
この「職業人としての殺人鬼」という特異な造形。これこそが、従来のホラーやサスペンスが描き続けてきた、カリスマ性や情念に満ちた犯人像に対する、詠坂流の最も痛烈なアンチテーゼなのだろう。
彼は殺人に快楽を見出しているわけではない。ただ、障害物があれば取り除き、その過程を完璧に遂行することに、職人的な矜持を持っている。
この温度の低さこそが、まず異様なのだ。
なぜ首を切ったのかという、常識では説明できない謎
それを踏まえてなお、遠海事件は佐藤誠の犯罪の中でも特異なものと言える。理由は色々あげられるが、頷きやすいものは二つ。
ひとつは彼自身が事件を通報し、屍体の発見者となっていること。
もうひとつは屍体の首だけを切断したことだ。
『遠海事件:佐藤誠はなぜ首を切断したのか?』70ページより引用
さて、いよいよ本題に入ろう。
タイトルに刻まれ、思考に執拗に張り付く疑問。
なぜ、首を切断したのか。
ミステリファンであれば、死体の首を切断するという行為に対して、即座にいくつかの合理的理由を思い浮かべるはずだ。
被害者の身元を隠すため、死体を運びやすくするため、あるいは入れ替わりトリックのため……。私たちは謎を提示された瞬間、無意識に犯人の行動に物理的なメリットを求めてしまう習性がある。
だが佐藤誠には、そのどれも当てはまらない。なぜなら彼は、遺体を丸ごと発見不能な形で消去できる技術と環境を備えているからだ。
完全消去が可能な人間が、あえて一部を切断し、しかも発見される形で残す。論理的に考えれば、それは自らの完全性を破壊する致命的なエラーに等しい。
ここで思考は一度停止する。
そしてようやく気づく。私たちはずっとハウダニットの回路で考えていたのだと。
だが本作は逆転のホワイダニットである。物理的合理性ではなく、思考の合理性。
物理的な利得や既存のトリックの枠組みで「ハウダニット(いかにして)」を追求しても、この謎は絶対に解けない。
答えは、佐藤誠という男の、極めて歪んでいながらも、鋼鉄のように硬質な独自の論理の中にしかないのだ。
彼にとって、あの瞬間に首を切ることは、他のどんな選択肢よりも合理的だった。世間一般の常識が狂気と呼ぶその行動が、彼の内なる計算式においては最適解として導き出されていた。
その真相に触れたとき、文字通り一瞬停止する。
論理が物理を越える。思考が現実を上書きする。
犯罪が偶然でも衝動でもなく、考え抜いた結果として成立する瞬間に立ち会う感覚。
それこそが、新本格ミステリがここまで突き詰めてきた場所なのだろう。
すべてを理解した、その瞬間に狂気が見える
結局のところ、『遠海事件』が私たちに突きつけているのは、「人間は、果たしてどこまで『論理』だけで生きていけるのか」という、残酷なまでに純粋な話なのだと思う。
佐藤誠には、私たちがフィクションの悪役に期待してしまうような同情すべき過去も熱い情念もない。彼には逮捕されることへの恐怖もなければ、犠牲者への罪悪感も存在しない。
ただ、そこには「なぜ、その時、そうしたのか」という、一点の曇りもない完璧な理由だけがある。それはある意味、ミステリというジャンルが長年追求してきた合理性が、ついに人間性という重力を振り切って到達してしまった、美しくも冷酷な景色だ。
カタルシスや感動を求める読者には、この読後感はあまりに寒々しく、不親切なものかもしれない。
けれど、パズルの一片がピタリとはまる快感と、そのピースの形が人間の理解を超えた狂気そのものだったときの戦慄を愛する人にとって、これ以上の贅沢はない。
佐藤誠が首を切断した理由。
その答えに辿り着いたとき、ミステリにおける合理性という言葉を再定義せざるを得なくなる。
それはあまりにも冷たく、けれどどこまでも澄み渡った、狂気の論理だ。
本書の題にもあるとおり、屍体の首が切断されていたことがこの事件最大の謎であり、そう言って良ければ魅力でもあるのだろうが、それと並んで筆者が当事件を調べるきっかけとなったのはこの、どうして彼は通報したのかという問いだった。
そこにも説明はあったのだ。ほかの事件で見せた冷徹な思考とは重ね合わせられないにしても、聞けば頷ける理由が。
それはまた首切りとも密接に絡むものだった。
あたかも、よくできた推理小説のように。
『遠海事件:佐藤誠はなぜ首を切断したのか?』71ページより引用