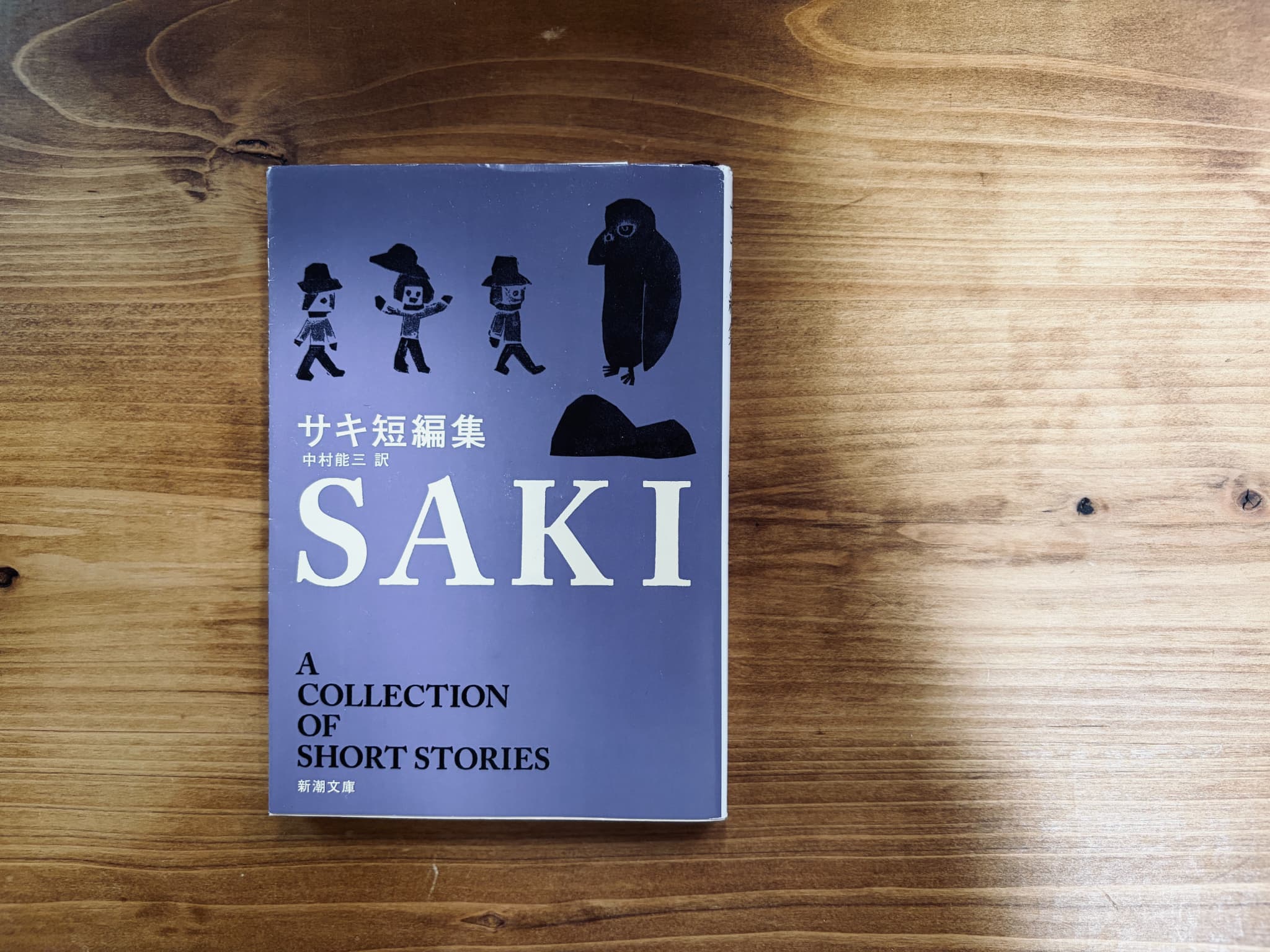森博嗣(もり ひろし)という作家を「ミステリ作家」とだけ思っている人は、おそらくあまりいない。
むしろ「森博嗣って何者なんだ……?」となる読者のほうが多いんじゃないか。元・工学部助教授という異色すぎる肩書き、毎年何冊も出す異常なペース、それでいてどこかストイックで、ひとつの思想体系みたいなものが全作品に通底している。
要するに、めちゃくちゃ変わっている。けれど、めちゃくちゃ面白い。
そんな森博嗣のデビューシリーズが、この伝説の『S&Mシリーズ』だ。
犀川創平(さいかわ そうへい)と西之園萌絵(にしのその もえ)、ふたりの名前の頭文字を取ったタイトルで、第一作はあの『すべてがFになる』。もうこの一発で、森博嗣は「理系ミステリィ」なる新ジャンルをぶち上げた。
論理で殴るタイプのミステリ。それが、森博嗣のやり口だ。
けれど、単に冷たいだけの知性じゃない。犀川と萌絵のテンポのいい掛け合いは読んでいて楽しいし、何より彼らの中に流れる微妙な温度差とか、孤独とか、感情の揺れが染みてくる。このあたりのバランス感覚が、森ミステリのすごさだと思う。
そして、このシリーズの魅力を語る上で絶対に外せないのが、真賀田四季(まがた しき)。天才にして狂気の工学博士。初登場の段階でとんでもないインパクトを残し、以降の作品でもずっと深い影を落としてくる。
彼女の存在が、物語に「ただの謎解き」では済まされない緊張感を与えている。そして、彼女を通して「人間とは」「知性とは」みたいな、底なし沼みたいなテーマに引きずり込まれていくのだ。
そう、『S&Mシリーズ』は単なる事件解決ものじゃない。人間心理、世界の見え方、現実の構造。そんな抽象的で根源的なテーマを、めちゃくちゃ自然な形で突きつけてくる。そこに物語としての面白さがきっちり融合していて、だからこそ抜群に強い。
森博嗣の「理系」というバックボーンは、ガジェット的な小道具を生むだけじゃない。登場人物の思考回路、物事の捉え方、文章のテンポや構造にまで、全部しみこんでいる。
ミステリを「問題→解決」の流れで読むのではなくて、「世界の構造そのものをどう認識するか」というところから攻めてくる。これはもう、ただのジャンル小説じゃない。
あと細かいけれど、「ミステリィ」という表記にも注目したい。これは単なる言い換えではなくて、あきらかにジャンルに対する距離の取り方が出ている。従来のミステリーとは違う、という明確な線引き。そこにも作家としての美学がにじみ出ている。
つまり『S&Mシリーズ』は、思索と構築によって立ち上がる文学的建築物でありながら、エンタメとしても強度がある。そんな奇跡的なバランスの上に成立しているシリーズなのだ。
S&Mシリーズの読む順番と作品紹介(ネタバレなし)
『S&Mシリーズ』を最大限楽しみたいなら、やっぱり刊行順に読むのがベストだ。
そのほうが、キャラたちの成長や関係性の変化がちゃんと見えてくるし、シリーズ全体に通底するテーマの深化も、より鮮明に伝わってくる。
というわけで、ここからは『S&Mシリーズ』全10作を、ネタバレなしでざっくり紹介していく。
構えず読んでくれてOKだ。
| No. | 邦題 | 英題 | ノベルス版初出年 (参考) | 惹句 (キャッチフレーズ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | すべてがFになる | THE PERFECT INSIDER | 1996年 | 孤島の天才博士、密室の惨劇。犀川と萌絵、最初の事件。 |
| 2 | 冷たい密室と博士たち | DOCTORS IN ISOLATED ROOM | 1996年 | 極低温実験室の二重密室。大学という日常に潜む、凍てつく殺意。 |
| 3 | 笑わない数学者 | MATHEMATICAL GOODBYE | 1996年 | 消えるオリオン像、連続殺人。天才数学者の館に隠された、歪な論理。 |
| 4 | 詩的私的ジャック | JACK THE POETICAL PRIVATE | 1997年 | ロック歌手の歌詞に見立てられた連続殺人。密室と奇妙な傷、事件の真相は詩の中に? |
| 5 | 封印再度 | WHO INSIDE | 1997年 | 五十年越しの謎、曰く付きの家宝。二つの死を結ぶ、封印された真実。 |
| 6 | 幻惑の死と使途 | ILLUSION ACTS LIKE MAGIC | 1997年 | 天才奇術師、衆人環視の死と消失。奇数章で語られる、幻惑のトリック。 |
| 7 | 夏のレプリカ | REPLACEABLE SUMMER | 1998年 | 親友の家族が仮面の男に誘拐される。偶数章で明かされる、夏の日の哀しい記憶。 |
| 8 | 今はもうない | SWITCH BACK | 1998年 | 嵐の山荘、隣り合う密室での連続死。映画が映すのは、過ぎ去りし日の幻影か。 |
| 9 | 数奇にして模型 | NUMERICAL MODELS | 1998年 | 模型交換会での首なし死体。二つの密室殺人、交錯する容疑者たち。 |
| 10 | 有限と微小のパン | THE PERFECT OUTSIDER | 1998年 | ハイテクテーマパークでの新たな事件。シリーズ最終章、再び相見える真賀田四季。 |
各巻は単体でもしっかり楽しめる本格ミステリとして成立しているけど、やはり通しで読むことで見えてくるものがある。
犀川と萌絵の関係の微妙な変化、萌絵自身の精神的な成長、そして真賀田四季という存在をめぐる大きな物語のピースが少しずつ繋がっていくのだ。そうして、シリーズ全体が一つの巨大な構造物として立ち上がってくる。
とくに『すべてがFになる』と最終巻『有限と微小のパン』における真賀田四季の描かれ方は、その構造の核心を鋭く突いてくる。
このふたつの巻だけでも、シリーズが何を問いかけていたのかがはっきり見えてくるはずだ。
1.静謐なる思索の迷宮── 『すべてがFになる』
孤島を旅する犀川研究室のメンバー。
島には、優秀な研究者が集まる「真賀田研究所」があり、天才工学博士・真賀田四季が隔離された生活を送る。
研究所を訪れた一行は、その彼女の部屋から、ウエディングドレスをまとい、両手両足が切断された死体を発見する。
密室で行われた殺人事件に、大学助教授の犀川創平と女子大生の西之園萌絵が挑む。
真賀田四季の圧倒的な存在感と、狂気の天才ぶりに注目
森博嗣のデビュー作『すべてがFになる』は、単なるミステリではない。考えることを楽しむ人のために作られた、精密に組み上げられた装置だ。
殺人が起き、探偵が謎を追う。構図はおなじみのミステリだが、その進行はやたら整然としていて、冷たく、理知的で、妙に美しい。血や激情よりも、数式と論理で構成された物語。読み手はテンションが上がるというより、どんどん思索の深みに引き込まれていく感じになる。
この作品のユニークさは、プログラミングという概念が物語にどっぷり組み込まれているところだ。犯行計画すらコードとして表現されていて、当時としてはかなり異質だったはず。初出は1996年。まだWindows95が出たばかりで、ネットも一部のマニアが触ってる程度の時代。
そんな時代に、仮想と現実、情報と肉体、数理と感情の境界を問いかけるミステリを世に出した森博嗣は、やっぱり相当変わっている。
そして何よりこの作品で外せないのが、真賀田四季の存在だ。登場シーンは決して多くないが、その影響力は絶大。彼女は「天才と狂気は紙一重」という決まり文句すら超えてくる。人間の姿をしているのに、思考の構造は限りなくAIに近い。でも、どこか空虚で、言葉にならない感情の残り香みたいなものをまとっている。それがまた妙に惹きつけられる。
登場人物たちの会話も、ただの事件処理では終わらない。それぞれの価値観や思想がにじみ出ていて、対話そのものがひとつの思索装置のように働いている。森博嗣の筆は、論理と詩のあいだを行き来しながら、読み手の意識を深い場所へ連れていく。
この作品は後に、ドラマ化やアニメ化、漫画化もされた。でも、どれだけ形を変えても、原作小説の本質だけは変わらない。感情の波から距離をとったまま、奥底で光るなにかがある。それは深海に沈んだ真珠のように、読んだあとも胸のどこかでぼんやり輝き続けるのだ。
『すべてがFになる』は、シリーズの中でもインパクトが強めの小説だ。そして、その冷徹さの奥にある思想と、論理の奥に潜む哲学こそが、最大の魅力である。
読み終わったとき、部屋の灯りを落としながら、なにか答えの出ない謎を抱えている自分に気づくはずだ。
その謎は、「F」のように。
言葉にならないまま、ずっと心の奥で点滅を続ける。
2.密室の温度、心の融点── 『冷たい密室と博士たち』
「すべてがFになる」から1年後、犀川と萌絵のコンビが所属する大学の、低温実験室で起こる密室殺人。
実験室で学生2人の死体、ダクトスペースでは腐乱死体が発見され、たまたま訪れていた2人が巻き込まれる。
実質上のデビュー作。前作から一転、王道のミステリー
『冷たい密室と博士たち』は、前作『すべてがFになる』に続くシリーズ第二作。
しかし実は、これが最初に書かれた一作目だった。デビュー作にしては地味すぎる、という理由で順番が入れ替わったという話が残っている。
だがこの作品こそ、森博嗣という作家が持っている深く沈む力をじっくり証明してみせた一冊でもある。
今回は、前作のような狂気の天才や極端に閉ざされた空間は登場しない。舞台は大学の研究施設。リアル寄りだが、それでもやっぱりどこか現実離れした知の世界だ。
トリックは二重にも三重にも折り重なっている。その裏側では、登場人物たちの感情がにじんでいる。憧れ、嫉妬、あいまいな想い。それらが論理の隙間からふと顔を出して、物語全体にうっすらと色を差す。
犀川と萌絵のコンビも、ここでまた魅力を増してくる。知性の鎧で距離をとる犀川と、鋭敏な感受性でまっすぐ飛び込んでくる萌絵。ふたりの会話には、皮肉と軽妙さが入り交じっているが、その裏に少しずつ信頼が積もっていく。
恋ではない。でも友情以上に踏み込んでいる。まるで凍った湖を渡るような危ういバランスが、読んでいてたまらなく緊張感を生む。
そして今作では、ついに命がふたりを襲う。ただの事件処理じゃない。論理では片づけられない局面で、ふたりはむき出しの感情に晒されることになる。
犀川の決断、萌絵の叫び。そこにあるのは知性ではなく、もっと根っこのところにあるものだ。「誰かを守りたい」という思い。それだけがすべてを動かしていく。
『冷たい密室と博士たち』は、パズルとしての完成度も高いけれど、それ以上に人間の揺れや感情の機微がちゃんと描かれている。
構築されたプロットのなかで、ふと漏れ出すにおいのようなもの。それが読後、胸に残る。
そして前作以上に、読み終えたあとでふたりの姿が記憶にこびりつくのだ。
「大切な誰かのために、自分の命を差し出せるか?」
そのテーマは、単なるドラマチックな設定では終わらない。
理性と衝動、論理と願い、冷たさと温もり。そのあいだを揺れ動く人間の在りようが、浮かび上がってくる。
森博嗣は、この作品でこそ、そんな感情の輪郭を一番くっきり描いてみせたのかもしれない。
3.沈黙する館と、記号たちの夢── 『笑わない数学者』
「三ツ星館」には、著名な数学者である天王寺翔蔵博士が住む。自宅で開いたクリスマスパーティで、大きなオリオン像を消してみせる博士。
翌日、オリオン像が現れ、同時に2つの死体も発見される。
館の謎と殺人事件のトリックに、犀川と萌絵のコンビが挑む。
ラストにゾワッとさせられる、森博嗣初の館もの
数学者は笑わない。この言葉には妙にひんやりした響きがある。
感情を捨てて、ただ真理だけを見つめる者の孤高。もしくは、世界に背を向けて沈み込んだ知性の影。
森博嗣『笑わない数学者』は、そんな沈黙する天才から幕を開けるロジック重視の館ミステリだ。
舞台となるのは、山奥に佇む三ツ星館。ガラスと曲線に包まれた異形の建築は、まるで現実の物理法則を一度忘れさせるかのような、端正で不安定な存在感を放っている。
そこに集うのは、かつて名を馳せた数学者・天王寺翔蔵と、その周囲に渦巻く人間模様。知的プライドと嫉妬、皮肉と打算が交差するこの場に、ただならぬ気配が充満していく。
作品の核となるのは、博士が発した「内側と外側」というテーマだ。最初は哲学ごっこのようにも思えるが、読み進めるほどに、この館そのものの構造や人々の関係性までもが、その言葉に絡め取られていく。
空間の認識がずれていく感覚。人間の境界が曖昧になる不安。そのうえで起こるのが、一件の殺人事件だ。さらに、館を象徴するように置かれていたオリオン像が忽然と姿を消す。二つの出来事は、別々のようでいて、どこかで強く結びついている。謎が絡み合ううち、読者自身も思考のフレームを何度もずらされていくことになる。
これはパズルであり、神話であり、知性の限界に挑む読書体験だ。
もちろん、犀川と萌絵のコンビも健在。クールで皮肉屋の犀川と、真っ直ぐで感情表現が豊かな萌絵。この二人のやり取りには、理性と直感が同居している。飄々とした会話の裏に、微かな緊張と優しさがにじんでいる。互いの心に踏み込むようで踏み込まない、絶妙な距離感。それがこのシリーズの魅力でもある。
物語が進むにつれて、人間関係のほころびと、空間の歪みと、論理の綻びが重なり合っていく。そして、すべてが解けたと思ったその瞬間、読者の足元からそっと引き抜かれる一片の真実。
きれいに組み上げたはずの論理が、決定的に崩れていくあの感覚。そこで描かれるのは、冷たい合理性と、そこにひそむどうしようもない人間の弱さだ。知を求める者の哀しみすら感じさせる。
森博嗣が描く「館もの」は、ただの密室殺人劇じゃない。そこには空間・概念・感情がひとつの構造物として立ち上がってくる手触りがある。『笑わない数学者』は、その中でも特に、思考することの苦しみと快楽が交錯する作品である。
読後に残るのは、「線とはどこに引かれるのか」という感覚的なテーマと、自分の居場所が一瞬ぼやけて見えるような不安。
誰が内にいて、誰が外にいるのか。
そもそもその境界は、本当に存在していたのか。
そんなことを、ふと考えさせられてしまう。それがこの作品の魔力だ。
4.静寂のなかの旋律、ある殺意の詩学── 『詩的私的ジャック』
週に1回、別の女子大へ講義に赴くことになった犀川。
その初日、密室のログハウスで全裸の女子大生が殺害される。
その後も、歌の歌詞に沿って行われる連続殺人と、操作線上に浮かぶ人気ロック歌手。
彼の担任である犀川は、否応なく事件に巻き込まれていく。
歌詞に沿って行われる連続殺人と、急接近するコンビ
『詩的私的ジャック』は、S&Mシリーズ第4作にして、シリーズ中でもかなり詩情寄りな異色作だ。タイトルの時点ですでに意味深だが、内容も負けていない。
今回の舞台では、すべての殺人が密室で行われる。そして、現場には妙な文字列とともに、歌の歌詞がリンクして残される。この設定だけで、もう読者の思考はぐらつく。事件の輪郭がどんどんあいまいになっていくのに、描写は端正で整っている。そのズレがいい。
だけど、この作品のキモは「どうやって殺したか」ではない。むしろ重要なのは、「なぜ殺したか」のほうだ。その動機には、合理性や計算では届かない、ぽっかり空いた感情の断片が絡んでくる。
本作では、シリーズの核である犀川と萌絵のコンビにも変化が訪れる。前半、犀川はほぼ姿を見せない。代わりに前面に出るのは萌絵だ。警察と関わりながら、自分の足で調べ、考え、ぶつかっていく。彼女の動きにはこれまで以上の鋭さと脆さが同居している。
萌絵の視点を通して見えるのは、事件そのものだけじゃない。そこにいる人間たちの些細な仕草、言葉にならない感情の重なり。そういった見えづらい揺らぎの集積が、読み手にじんわりと効いてくる。
そして物語が後半に差し掛かるころ、沈黙していた犀川が再登場する。彼は相変わらず大げさなことは言わない。けれど、その佇まいと目線の奥にある何かが、読者にも萌絵にも、不思議と安定感をもたらす。
そこから、推理は一気に駆け上がっていく。
感情を超えて論理が走り出す。けれど最終的に突き当たるのは、説明しきれない想いのかたちだった。
犯行の動機は、整理された動機というより、詩的で私的な混沌だった。
そう、まさにこの作品のタイトルそのものだ。
『詩的私的ジャック』という言葉には、整合性のないものたちが強引につなぎ合わされているような違和感がある。だけどその違和感こそが、この事件の本質に近い。
シリーズ通して登場してきた犀川と萌絵の関係性も、本作でまた一段階深まっていく。距離を保っていたふたりのあいだに、ほんの少しだけ温度のようなものが入り込む。それははっきりとした変化ではないけれど、何かが確実に動き出した手応えがある。
読み終えたあと、あなたは気づくかもしれない。
これはただの密室殺人ではなかったことに。
それは誰かの心が放った、言葉にならない詩。
殺意の形をした、哀しみの告白だったのだと。
5.瓢のなかの時間、あるいは再び封じられるもの── 『封印再度』
50年前、家宝「天地の瓢」と「無我の匣」を残し、密室で果てた日本画家。
その死と家宝の謎は説かれないまま、時は過ぎていた。そして現代、今度はその息子が死体で見つかる。
2人の自殺と不思議な家宝に、犀川と萌絵のコンビはどう立ち向かうのか。
親子2代にわたる不審な自殺と、目が離せない2人の関係
S&Mシリーズの第5作にあたるこの作品は、もともとシリーズ完結編として構想されていた一冊だった。
だがデビュー作に『すべてがFになる』が選ばれたことで構成が変わり、シリーズはさらにその先へと続いていくことになる。だからこそこの作品には、節目のような重みと、終わりに向かうような雰囲気が漂っている。
今回のキーアイテムは、「天地の瓢」という奇妙な家宝。そこには「無我の匣」の鍵が封じられているらしいが、どう見ても物理的に取り出せない構造になっている。これがそのまま、「取り出せない密室」という形で物語に深く関わってくる。
密室といえば、これまでもS&Mシリーズの定番だったが、本作ではその意味合いがグッと抽象的になる。
「どうやって密室を作ったのか」ではなく、「なぜこの世界はそういう形で閉じられているのか」。
そんな思考に引っ張られる構成になっている。哲学っぽく見えるが、ちゃんとロジックで読ませてくるあたりが森博嗣らしい。
とはいえ、この作品は理屈だけじゃない。特に印象的なのは、西之園萌絵の感情の揺れだ。そしてそれに動揺する犀川。あのいつもクールな彼が、明確には語らずとも、確実に何かを揺らがせているのだ。
タイトルの『封印再度』が意味するものは、物語が終盤に向かうにつれて徐々に明らかになっていく。読み終えたとき、初めて「そういうことだったのか」と腑に落ちる瞬間がやってくる。
それは意外性というより、納得感だ。そして、なぜこの作品がシリーズの中でもとくに愛されているのか、その理由もはっきり見えてくる。
知性と感情、閉鎖と解放、理屈と衝動。本作はそのどれにも偏らず、ちょうど境界のあたりを歩き続けている。
登場人物たちは事件と向き合いながら、それぞれが胸の奥にしまっていたものとも対峙していく。それは読者にとっても同じで、普段は見ないふりをしていた感情の匣が、ふと開いてしまうような感覚を残す。
再び封じるもの。それは真相かもしれないし、言葉にならなかった気持ちかもしれない。
そしてきっと、それは次の物語への入口でもある。
本来ここで終わっていたはずのシリーズは、この一冊を越えて、さらにその先へと続いていく。
『封印再度』は、終わりではない。むしろ、そこから始まる章の予感に満ちた作品なのだ。
6.奇術と真実のあいだに漂うもの── 『幻惑の死と使途』
「どんな密室でも抜け出してみせよう」日本で最も有名な天才マジシャン有里匠幻が、脱出マジックのさなか、衆人環視のもとで殺害される。
さらに霊柩車から消える匠幻の遺体。その後、周囲の人物も次々と殺害されていく。この怪事件に、犀川と萌絵のコンビはどう推理するのか。
何が真実で何が幻惑なのか?美しきイリュージョン殺人
魔法とは、目をごまかす技術のことだ。
でも、心をごまかすのはいつも、目じゃなくて想いのほうだったりする。
『幻惑の死と使途』は、S&Mシリーズ第6作。これまでの密室推しから少し距離を置き、マジックというあいまいな現象を軸に据えた、シリーズでもやや異色な一冊だ。
とはいえ、森博嗣らしい構成の美しさや知的なゾクゾク感は健在。むしろ密室なき密室ミステリとして、見事に新たな領域を切り拓いている。
物語は、まるで舞台袖からそっと覗いているような感覚で始まる。消えるもの、入れ替わるもの、ありえないものが現れる。そうした違和感の連続が、やがて一つの死へと結びついていく。目の前で何かが進行しているのに、真実がつかめない。その感じがずっと続く。まるで観客としてマジックショーを見せられているような構成だ。
事件自体ももちろん魅力的だが、それと同じくらい丁寧に描かれるのが、登場人物たちの心の軌跡だ。とくに今回は、シリーズ初期から登場してきた西之園萌絵の変化に目を奪われる。
彼女はもう、犀川の背中を追いかけるだけの存在ではない。推理のキレ、他人への洞察、そして感情の揺れ。すべてが以前よりも深く、鋭く、そしてどこか危うい。その成長ぶりに、長くシリーズを追ってきた読者なら、ぐっとくるはずだ。
構造上の仕掛けも面白い。本作は章番号がすべて奇数。これは、次作『夏のレプリカ』と“対”になっていることを暗示する構造だ。
まるで片翼だけの構造体を読まされているような手触り。読後には「続きが必要だ」と強く感じさせられる。このあたりのメタ構成も、森ミステリらしさがにじむポイントだ。
ページ数は500超え。それでもテンポが良く、ページをめくる手が止まらない。物理的な密室は存在しないのに、読者の思考はどんどん閉じ込められていく。この見えない密室の構築こそ、森博嗣の真骨頂だろう。
そして極めつけは、あとがきに登場する引田天功。最後の最後まで、この物語は一つの演目として読者の前に提示される。すべてが奇術であり、仕掛けであり、そして、どこかに本物の感情が紛れ込んでいるのだ。
『幻惑の死と使途』は、単なる推理小説ではない。
それは、構造と感情と未来の予感をひとつの舞台に詰め込んだ、精密で美しい上演である。
本を閉じたあと、ふと世界の見え方が変わるかもしれない。
現実と幻想の境界が、すこし曖昧に感じられるかもしれない。
そして。
あなた自身も気づかぬうちに、誰かの使途になっていたのかもしれない。
7.夏という幻影、記憶というレプリカ── 『夏のレプリカ』
西之園萌絵の親友、簑沢杜萌の一家全員が仮面の男に拉致される。
誘拐犯の一人は逃走するが、射殺されて発見。そして盲目の兄が行方不明に……。
前作『幻惑の死と使途』と同時期に起こった事件が、杜萌の視点で描かれる。
シリーズ異色作。親友の視点で描かれる事件と、悲しきチェスシーン
夏という季節には、なぜか記憶をきれいに見せかける力がある。
強い日差し、蝉の声、長く伸びる影。全部がどこか懐かしく、でも輪郭がぼやけていて、つかんだと思った瞬間にすり抜けていく。
『夏のレプリカ』は、そんな「記憶の不確かさ」と「人の輪郭の揺らぎ」を描いた、シリーズでも異色の一冊である。
S&Mシリーズ第7作。本作は、前作『幻惑の死と使途』と対になっている。あちらが奇数章で構成されていたのに対し、こちらは偶数章だけ。時間軸を共有しながら、視点を変えることで物語の見え方そのものが変わる構造になっている。
この2冊を並べて読むと、「同じ出来事でも見え方は全然違うんだな」と、作品全体が大きな立体パズルになっていることに気づかされる。
語り手は、西之園萌絵の親友・簑沢杜萌(みのさわ ともえ)。これまで脇役だった彼女が、ここで初めてメインを張る。描かれるのは、誘拐殺人と失踪をめぐる陰影の濃い事件。とはいえ、本作の本質は謎解きそのものじゃない。登場人物の内面、関係性、そしてふとした違和感の積み重ねが、この物語をかたち作っている。
いつものように犀川と萌絵が中心にいるわけではない。ふたりは今回はあくまで背景にいる存在として描かれる。代わりに前に出てくるのが、人と人との距離感、感情のすれ違い、そして喪失の感覚だ。論理で割り切れない部分に光が当てられる。
語り手である杜萌には、影のような柔らかさがある。彼女の視線を通すことで、これまでにはなかった萌絵の横顔が見えてくる。普段はまっすぐで理知的な萌絵の、その奥にある孤独や弱さ、そして口にされない想い。それを、親友というポジションから受け止めていく杜萌のまなざしが切ない。
特に終盤は印象的だ。ゆるやかに進んできた感情の流れが、ある場面で一気にせり上がってくる。チェスのシーンで交わされる萌絵と杜萌のやり取りには、言葉では語られない何かが詰まっている。事件の真相よりも、ふたりのあいだに通ったもののほうが、ずっと重みを持って響いてくるのだ。
理系ミステリ的なガジェットは控えめだが、構造の美しさは変わらず健在。章の構成、時間軸のズレ、視点の転換。すべてが仕掛けとして効いていて、小説という形式そのものを使った実験のようでもある。
『夏のレプリカ』というタイトルもすごく好きだ。
レプリカとは、複製されたもの。でも、この物語に出てくるのは決して完璧なコピーじゃない。どこかに歪みやズレを抱えたまま、それでも残っていく記憶。人の心に刻まれるのは、そういう不完全なものなのかもしれない。
できれば前作『幻惑の死と使途』と交互に読み進めてみてほしい。ふたつの作品が並んで初めて立ち上がる景色がある。
あのとき、誰がどこにいたのか。なぜ、あの言葉が生まれたのか。その重なり方が、読後の味わいを何倍にも深くしてくれる。
派手な事件や鮮やかなトリックはない。
けれど、読み終えたあとに残るのは、確かに何かを受け取ったという実感だ。
それは夏の記憶のようにやわらかく、でも心の奥をそっと締めつける。
8.消えたものと、残された記憶のかたち── 『今はもうない』
嵐の夜、避暑地の別荘。電話も通じない中、隣り合わせる映写室と鑑賞室でそれぞれ一人ずつ、美人姉妹の死体が発見される。
密室状態の現場では、スクリーンに映画が投影されたままだった。
物語はエモーショナルに進んでいく。
叙情的に進行する物語。シリーズナンバーワンとの声も
「今は、もうない。」
たったひとこと。でも、その言葉が示しているのは過去だけじゃない。
それは存在そのものがぐらりと揺れるような、ある種の不確かさをも含んでいる。
S&Mシリーズ第8作『今はもうない』は、シリーズの中でも群を抜いて完成された一冊であり、多くの読者が口をそろえて「最高傑作」と推す作品だ。
森博嗣といえば、構造の美しさと冷徹な論理性のなかに、ふいに差し込まれる感情のにおいが魅力のひとつでもあるが、本作はそのバランスが驚くほど研ぎ澄まされている。
密室トリック、ズレた時間軸、配置された登場人物、言葉の使い方と使わなかった部分。すべてが整っているのに、読み進めるうちに違和感が積もっていく。
ロジックはきれいに並んでいるのに、なぜか足りないと感じるあの感覚。登場人物の何気ない仕草や視線のズレ。時間が進んでいるようで、どこかで止まっているような浮遊感。
この「何か変だ」という感じこそが、本作最大の仕掛けである。
一見すると、精緻に作られた王道ミステリのように見える。けれど読み終えたとき、それが見せかけだったことに気づくのだ。
ある登場人物のたった一言。それによって、それまで読んできたすべてが裏返る。事件の構図、人間関係、発された言葉、その意味。すべてが折り紙のようにぱたりと裏返り、まったく別の地図が姿を現す。
この反転は、ただのトリックでは終わらない。驚きと同時に、妙な納得がやってくる。読者は、自分の見ていたものがいかに狭かったか、視点の置き方ひとつで世界がどう変わるかを思い知らされる。これぞ森博嗣、これぞS&Mシリーズとしか言いようがない。
タイトル『今はもうない』の意味も、読後にようやく本当のかたちで浮かび上がってくる。そこにあるのは、ただの喪失じゃない。すでに消えたものへの敬意であり、それを想い続ける者のささやかな祈りだ。
この作品を最大限味わいたいなら、やはり第1作『すべてがFになる』から順番に読んでほしい。
なぜなら『今はもうない』は、単体でも完成されたミステリでありながら、シリーズを通して積み上げてきた時間と関係性があってこそ、真価を発揮する結晶のような一冊だからだ。
犀川と萌絵は、もはや探偵と助手ではない。ふたりのあいだに流れる空気、ためらい、言葉選び、長い沈黙。そういうものすべてが、この作品でついにひとつの地点にたどり着く。だが、それは断絶ではなく、ここまで来たという通過点として描かれている。
読み終わっても、ページを閉じることができず、ずっと頭の中で同じ言葉がリフレインするはずだ。
「今は、もうない。」
でもその言葉の奥に、“たしかにあった”という残響がかすかに残っていることにも気づく。
それこそが、『今はもうない』という作品が持つ最大の魔法であり、森博嗣という作家が仕掛けた、いちばん優しいトリックなのだ。
9.模型の街で動き出す真実── 『数奇にして模型』
模型イベントの会場で、首のないモデルの遺体が発見される。現場は密室で、横には他の殺人事件の容疑者が、後頭部を叩かれ昏倒していた。
単純かと思われた事件は複雑になっていく。
シリーズで一番猟奇的な犯行に、犀川と萌絵のコンビが対峙する。
シリーズ史上最難解の謎。キャラ総出演と2つの密室
精巧に作られた模型には、作り手のこだわりと世界のミニチュアが詰まっている。
本作『数奇にして模型』は、まさにそんな模型のような小説だ。閉じられた空間のなかに、時間と記憶と論理がびっしり詰め込まれている。
S&Mシリーズもいよいよ第9作目。舞台は原点にして中枢、那古野の街。前作『幻惑の死と使途』『夏のレプリカ』が内面寄りの作品だったぶん、本作はガッツリ本流回帰してきた印象だ。しかもボリュームは約700ページ。だが、読む手はまったく止まらない。
たった一週間の出来事をこれだけ濃密に描いているにもかかわらず、まったく長さを感じさせないのは、やはり森博嗣の手腕によるところが大きい。キャラのやり取りのキレ、セリフの妙、テンポの良さ、事件の配置。すべてが絶妙に絡み合って、読み心地の良いリズムを作っている。
今回は古典的なふたつの密室殺人が軸。模型のように整えられた空間に、いったい何が起こったのかを解き明かす。この構図が、本作の全体テーマとも重なっていて実に面白い。
しかも、過去作からの登場人物たちが続々と再登場してくるのも嬉しいポイント。シリーズを追ってきた読者にはたまらない顔ぶれ総出演である。そのうえ、新キャラたちも個性的でいい味を出してくる。事件の緊張感と、会話劇の軽妙さがうまく拮抗していて、700ページに飽きがこない。
犀川は今回、珍しく積極的に動く。いつもの飄々スタイルは維持しつつも、事件に対して深く関与していく姿に、知的な熱を感じさせる。この、あえて動く犀川が見られるのも、終盤に近づいたシリーズだからこそだ。
萌絵はいつもどおり直感と情熱で事件に突っ込んでいく。ただ、それが彼女の強さであり、同時に危うさでもある。毎度のことながらギリギリまで踏み込むところが彼女らしいし、犀川とのやり取りに滲む信頼関係は、シリーズの積み重ねのご褒美でもある。
そして注目したいのが模型というモチーフだ。作中で語られるフィギュアや縮尺世界の話は、単なる趣味語りじゃない。それは世界を観察し、構築し、理解するためのアプローチとして、小説全体に深く関わっている。
森博嗣にとって模型は、物語のテーマであり、視点そのものなのだ。
終盤には、作者の過去を明かすようなあとがきが挿し込まれていて、シリーズ全体の裏側を垣間見るような感覚も味わえる。物語の外側に、もうひとつの模型が提示されてくるわけだ。
『数奇にして模型』は、構造、感情、論理、空間、あらゆる要素が模型のように組み上げられた大作である。
探偵行為とは、誰かの心を組み立て直すことでもある。
過去を並べ直し、再構築し、見つめ直す。それこそがこの作品で語られている探偵の本質だ。
さあ、いよいよ次は最終作。
長く続いたこのシリーズが、どんな最後のパーツを嵌めてくるのか。
この模型の完成図がどんな姿をしているのか。
その目で、ぜひ確かめてほしい。
10.永遠のなかの微小なるものへ── 『有限と微小のパン』
日本最大のソフトメーカ-「ナノクラフト」が経営する、長崎のテーマパーク。
ゼミの先遣隊として友人たちと訪れた萌絵は、謎の死体消失事件と密室殺人に遭遇する。事件の影には、あの真賀田四季博士が…。
S&Mシリーズのラスト作品。
真賀田四季博士、再降臨。現実と虚構。シリーズラストにふさわしい完成度
最後のページを閉じたあと、目を伏せたくなることがある。
それは、ただ物語が終わったからではない。
長く身を置いていた世界が、確かにどこかへ消えていったという実感のせいだ。
『有限と微小のパン』は、S&Mシリーズ最終巻にして、圧倒的な密度とスケールを誇る集大成だ。
全10作、論理と感情、現実と仮構、密室と対話、あらゆる対立項のあいだを往復しながら築き上げられてきたこの世界は、ここでいよいよ完結という名の変化点を迎える。
ページ数は900近く。なのに読んでいて長いと感じない。むしろ、もっと居ていたくなる。そんな場所になっている。
そしてやっぱり登場するのが、真賀田四季だ。『すべてがFになる』であれだけのインパクトを残した彼女が、最終巻でもなお、その存在感で物語を支配する。言葉は少ない。けれど、一言ごとに重みがある。哲学と皮肉と人間の本質が、ためらいもなくぶつけられてくるのだ。
今回の事件は、もはやトリックとか密室のレベルじゃない。構造そのものが読者の足元を揺らしにかかってくる。読み進めるうちに、自分が何を信じていたのか、どこまでを理解していたのか、だんだん怪しくなってくる。
でもその混乱すら、設計された混乱なのだ。
章の冒頭に過去作からの引用が並ぶ構成も、シリーズ読者にとってはたまらない演出だ。あのときのセリフ、あの場面の言葉が、ここにきてまた新たな意味を持ち始める。そうやって、読者の記憶すらもこの物語の部品として回収されていく。
そして、この作品が1998年に書かれたという事実。VR、人工知能、アンドロイド……いま読んでもまったく古びていないどころか、今こそリアルに響いてくるテーマが山ほど詰まっている。
森博嗣は、技術を描いているのではない。現実のかたちが変わっていく様子を、物語というフォーマットで追いかけているのだ。それは今、私たちが日々触れているSNSやAI、バーチャルな人間関係と、地続きの話でもある。
そして、ラスト。
真賀田四季の行く先、犀川と萌絵の関係。シリーズを通して積み上げられてきたものすべてに、ある種の区切りが訪れる。
だが、それは終わりではない。バッサリと切られることも、過剰に回収されることもない。むしろ、答えというより、そのまま置かれるものがあるだけだ。
明快な整理ではなく、手触りの残る余白。論理では届かない、でも確かにあると感じさせる何かが、ぽつんと残る。
シリーズを通して描かれてきた有限な世界のなかで、微小な希望のようなものが、ふっと灯る。
それは知性と感情のあいだに差し出された、たったひとつのパン。誰かと分け合える、ささやかで意味深い、最後のピースだ。
『有限と微小のパン』は、壮大な構造の記憶よりも、ふたりの何気ない会話、まなざし、そしてわずかな理解が心に残る作品である。
シリーズという模型の、最後のパーツがぴたりとはまった瞬間。
その音はとても小さいけれど、忘れがたい響きがある。
忘れえぬ二人 – 知性と魅力の交錯
『S&Mシリーズ』の核となるのは、間違いなく犀川創平と西之園萌絵という、忘れがたい魅力を持つ二人組だ。
犀川創平 (さいかわ そうへい)

国立N大学工学部建築学科の助教授・犀川創平。
S&Mシリーズを語るうえで、彼の存在は欠かせない。探偵でも刑事でもない。けれど、なぜか事件は彼のまわりに寄ってくる。しかもかなりの確率で、死体付きで。
彼の特徴をひとことで言うなら、「徹底した論理主義者」だ。感情に流されることがなく、常に冷静で、どこか超然とした空気をまとっている。無駄な動きはしないし、必要以上の関与もしない。それでも事件が起きると、ものの見方や発言に漂う独特の知性と観察眼で、するすると核心に近づいていく。
しかも、この人のセリフがまたクセモノだ。ただのうんちくかと思えば、そこに哲学が混じっている。ちょっと皮肉っぽくて、ユーモアもあって、無味乾燥な理屈では終わらせない。言葉の端々に「世界はこう見るべきだ」という、彼なりの世界認識がにじんでいる。このあたりが、読んでいてたまらなく面白い。
犀川は、萌絵と一緒にいることで事件に巻き込まれることが多い。が、彼自身が「解決したがっている」わけではない。必要とされれば手を貸す、という程度のスタンスだ。だがその距離感こそが、彼の魅力でもある。深入りしない。なのに、要所でしっかり踏み込む。
他人に対しては、どこか無関心に見えることも多い。余計なことは言わないし、感情的なやりとりにはほぼ参加しない。誰とでも一歩引いたまま接しているように見える。この冷めた態度を「冷酷」と感じる人がいても、正直、仕方ないと思う。
けれど、シリーズを読み進めていくと見えてくるのが、その仮面の奥だ。
感情を持たないのではない。むしろ、表に出すのが不器用すぎるだけだ。特に西之園萌絵に対しては、何度も「もう完全に気にかけてるじゃん」という場面が出てくる。でも犀川は、言葉で言わない。態度でもあまり見せない。たまにちょっとした仕草や、セリフの行間で、それがふっと伝わってくる。
それがまた、たまらなく良い。
犀川は理性と沈黙のあいだで生きている。でも、その生き方は決して冷たいものではない。むしろ、人との距離をきちんと測りながらも、必要なときには確実に「そこにいる」。そして、言葉にならないままに誰かを気にかけている。
そういうところにこそ、人間らしさが宿っているのだと思う。
知性の仮面の下に、静かに隠された不器用なやさしさと、ほんの少しの孤独。
それが犀川創平という人物の、最大の魅力である。
西之園萌絵 (にしのその もえ)

犀川の研究室にいる学生、西之園萌絵。
お嬢様でありながら、抜群の知性と観察力、そしてちょっとおかしいくらいの計算力を持っている。見た目は涼しげだが、中身はかなり熱い。好奇心と行動力で事件を引き寄せまくる、いわば「シリーズ最大のトリガー」である。
冷静に見えて、実はめちゃくちゃ感情で動くタイプ。でもその感情は、本人にもよくわかってなかったりする。とくに犀川に対しては、尊敬と憧れと恋愛未満の何かが入り混じっていて、そのバランスがずっと揺れている。そこがたまらなく良い。
シリーズを追っていくとわかるのは、彼女の成長がちゃんと描かれているということだ。最初はどこか危なっかしいが、話を重ねるごとに、事件に対する向き合い方や、自分の考え方が少しずつ変わっていく。誰かの影じゃなく、自分の足で動いて、自分の頭で考えるようになっていく。
そして大事なのは、彼女がただの探偵の相棒じゃないということだ。物語の内側から空気を動かし、事件を引き起こし、人間関係に火をつけるのは、たいてい彼女の言動である。
推理ものに出てくるヒロインというのは受け身になりがちだが、萌絵はむしろ真逆。ど真ん中から話を転がしていく。
感情と思考、衝動と論理。
そのせめぎ合いのなかで動き続ける西之園萌絵という存在こそが、S&Mシリーズのもうひとつの主役なのである。
犀川と萌絵の会話、それはS&Mシリーズの心臓部だ
S&Mシリーズを語るうえで外せないのが、犀川と萌絵のやりとりだ。
このふたり、事件の合間に交わす掛け合いがとにかく絶妙で、どの巻でも必ずひとつは「おっ」とニヤついてしまうセリフがある。
軽妙でありながら、ただのギャグや息抜きで終わらない。会話の中に伏線や核心が潜んでることも多くて、気を抜いてると後から「そういうことか!」となる。そういう仕込みのうまさも、森博嗣作品ならではだ。
そしてこのふたりの関係性がまた、もどかしい。くっつきそうでくっつかない。でも明らかに他人とは違う距離感。
恋と呼ぶにはストレートすぎないし、友情にしては近すぎる。理性と感情がぎりぎり拮抗してる状態で物語がずっと進むもんだから、こっちの読み手のほうが勝手に緊張してくる。
ただ、そういうピリッとした関係性が、あの難解な理屈や謎解きをちょうどよく中和してくれる。クールで抽象度の高い話が続いても、ふたりの会話が入るだけでスッと読みやすくなるし、なによりキャラとしての魅力が増していく。
殺人事件の真っ只中でも、ふと交わされるひと言が救いになっていたりする。読者にとっても、犀川にとっても。
シリーズを重ねるごとに、萌絵の変化も見逃せない。最初はちょっと感情が先走るところもあったが、話が進むにつれて、思考の深さや視野の広さがどんどん増してくる。犀川に投げかける言葉も、ただの好意や憧れではなくて、対話になってきている感じがある。この成長こそが、S&Mシリーズを読み続ける面白さのひとつだ。
それに、萌絵は単なる助手じゃない。ワトソン役に収まるようなキャラじゃないのだ。彼女自身がバリバリ推理して動いて、物語を前に進めていく。犀川と視点が違うからこそ、見えてくるものも違うし、ふたりが揃ってこそ事件が解けていくって構図がしっかり成立している。
この対等に近いパートナー感が、本作を古典的な探偵小説の枠からグッと現代に引き寄せているのだ。
論理だけでも、感情だけでもダメ。
ふたりの掛け合いがあるからこそ、あの物語世界に奥行きが出てくる。だからこそ、シリーズ全体の温度みたいなものも、あの会話が作っているのだと思う。
冷え冷えの密室理論や殺人ロジックの裏で、ふたりが交わす短いセリフこそが、このシリーズの灯りなのだ。
森博嗣がもたらした、理系ミステリィという革命
森博嗣が『S&Mシリーズ』でやったことは、まさにジャンルの地殻変動だった。
爆発音のような衝撃じゃない。もっと深く、もっと静かに、脳の内側から広がってくる知の地震だったのだ。
このシリーズで確立された「理系ミステリィ」は、工学・数学・情報科学といった分野の知見を、謎解きの根幹に直接組み込んでいる。
しかも驚くべきはその先見性。たとえば1998年の段階で、普通にPCを使ったトリックが描かれていたりする。そのあとも、VR、人工知能、仮想現実……そういった当時の未来技術が、ただの背景じゃなく、物語の論理そのものとして登場するのだ。
しかもそれが浮かない。ちゃんと今ある現実の地続きとして描かれているから怖い。森博嗣は、科学を装飾として使っていない。それは小道具じゃなくて、認識の方法として使っている。読んでるうちにこっちの思考の回路すらアップデートされていく感じがあるのだ。
このシリーズを読んでいて感じる快感は、やっぱり論理が組み上がる瞬間だろう。物語の中に置かれたピースが、あるタイミングでぴたりと噛み合う。そのときに訪れるのは、どかんと感情が揺さぶられるというより、ひやりと知性が震えるような感覚だ。
もちろん、数式や専門用語などもちょくちょく出てくる。でも、そこに抵抗感はあまりない。
なぜなら、犀川と萌絵の会話がいい意味で人間的だからだ。知的なのだけど、ときにちょっとふざけていて、でも核心は外さない。このウィットとロジックのバランス感覚が、読み心地を軽やかにしてくれている。
森ミステリのもうひとつの特徴が、「動機を重視しない」という姿勢だ。
普通の推理小説なら、「なぜ殺したか」に比重がかかることが多い。
でも森博嗣の場合は違う。「どうしてそんなトリックが可能だったのか」。
ここに最大のエネルギーが注がれている。
人の心は変わる。でも、物理法則や論理体系は変わらない。感情はぐらつくけど、数式は裏切らない。森のミステリィは、そういう揺るぎない地盤の上に立っている。
そしてその硬質な地盤の上に、感情の断片や生の手触りをポツポツと置いていく。この距離感が、また最高なのだ。
そして何よりも語っておきたいのは、森博嗣の未来感覚。ネットワーク社会、バーチャルの自己、AIと倫理。それらを20年以上前に小説に組み込んでいたという事実が、とんでもない。
それは単なる時代の先取りじゃない。「テクノロジーが、人間の存在そのものをどう変えていくのか」という問いと向き合っていたということだ。科学と倫理、現実と仮想、論理と感情。その交差点に物語を置いて、世界の輪郭を描いてみせた。
『S&Mシリーズ』は、謎解き小説ではある。
だがそれと同時に、知性そのものを描く物語でもある。
読者に突きつけてくるのは、ただの殺人事件じゃない。
「知とはなにか」
「人間は、どこまで世界を理解できるのか」
「わかった気になるという感覚は、どこまで信用できるのか」
そんなメタな感覚すら引きずり出されてしまう。
読み終えたときに残るのは、事件が解決したという満足ではなく、思考を一周して戻ってきたという知的な余熱だ。
『S&Mシリーズ』が突きつけてくるのは、謎ではなく「世界の輪郭」そのものだ
S&Mシリーズを読み進めていくと、ある段階で気づく。
この物語は、ただの推理小説じゃない。
密室トリックや殺人事件を通じて描かれているのは、もっと根源的な「世界のありよう」そのものなのだ。
たとえば、「意識とは何か」「自我とはどこから始まるのか」「他者と自己の境界はどこか」。
そんなテーマが、事件や会話、あるいは犀川の何気ないひと言のなかに、さらっと差し込まれてくる。押しつけがましくはない。だが気づいたら、いつのまにか思考の沼に引きずり込まれている。
そして、そこに必ずいるのが真賀田四季だ。
彼女はこのシリーズの中心でありながら、中心にいるふうをして中心にはいない。姿を現さなくても、物語全体を覆ってしまうほどの圧倒的な存在感。工学博士という肩書きはただの入口で、彼女の思考そのものが、「世界をどう定義するか」という主題にダイレクトに繋がっている。
シリーズを通して彼女に投げかけられる「彼女は一体何者なのか」という謎は、単なるキャラ考察ではない。それは、「人間とは何か」というテーマへの哲学的ダイブだ。
森博嗣の文体はよく「淡々としている」と言われる。でも実際には、論理を極限まで研ぎ澄ませたからこそ生まれる透明感があるだけだ。
そこには確かに熱がある。だがその熱は、燃え上がるような炎じゃない。まるで、知性の奥底で静かにくすぶる炉のような温度だ。
この文体があるからこそ、読者の内側に余白が生まれる。犀川のモノローグも、萌絵との対話も、単なる事件解決を超えて「人間そのもの」に迫っていく。この哲学×ロジックのハイブリッド感が、S&Mシリーズの最大の強みだ。
しかも森作品では、「感情より論理」「なぜよりどうして」が優先される。犯人の内面にフォーカスせず、あくまで「どうやって可能だったか」に主眼がある。
ここがまた、いかにも理系的でたまらない。人間の心はぐらつく。けれど論理は崩れない。森のミステリは、そんな揺るがないものへの信頼でできている。
そして、すべてのテーマは、結局のところ真賀田四季に帰ってくる。
天才とは何か。
常識とは誰の基準か。
倫理とは、本当に「絶対的な正しさ」なのか。
彼女を理解しようとすることは、作品世界の内と外、つまり“わたしたち”の側と“彼女”の側の違いに向き合うことでもある。
それは恐ろしく深い試みだ。だけど、それに惹かれずにはいられない。
S&Mシリーズは、読み終えた瞬間に完結するような小説ではない。
思考が止まらなくなってからが、本番だ。
S&Mシリーズの色褪せぬ魅力
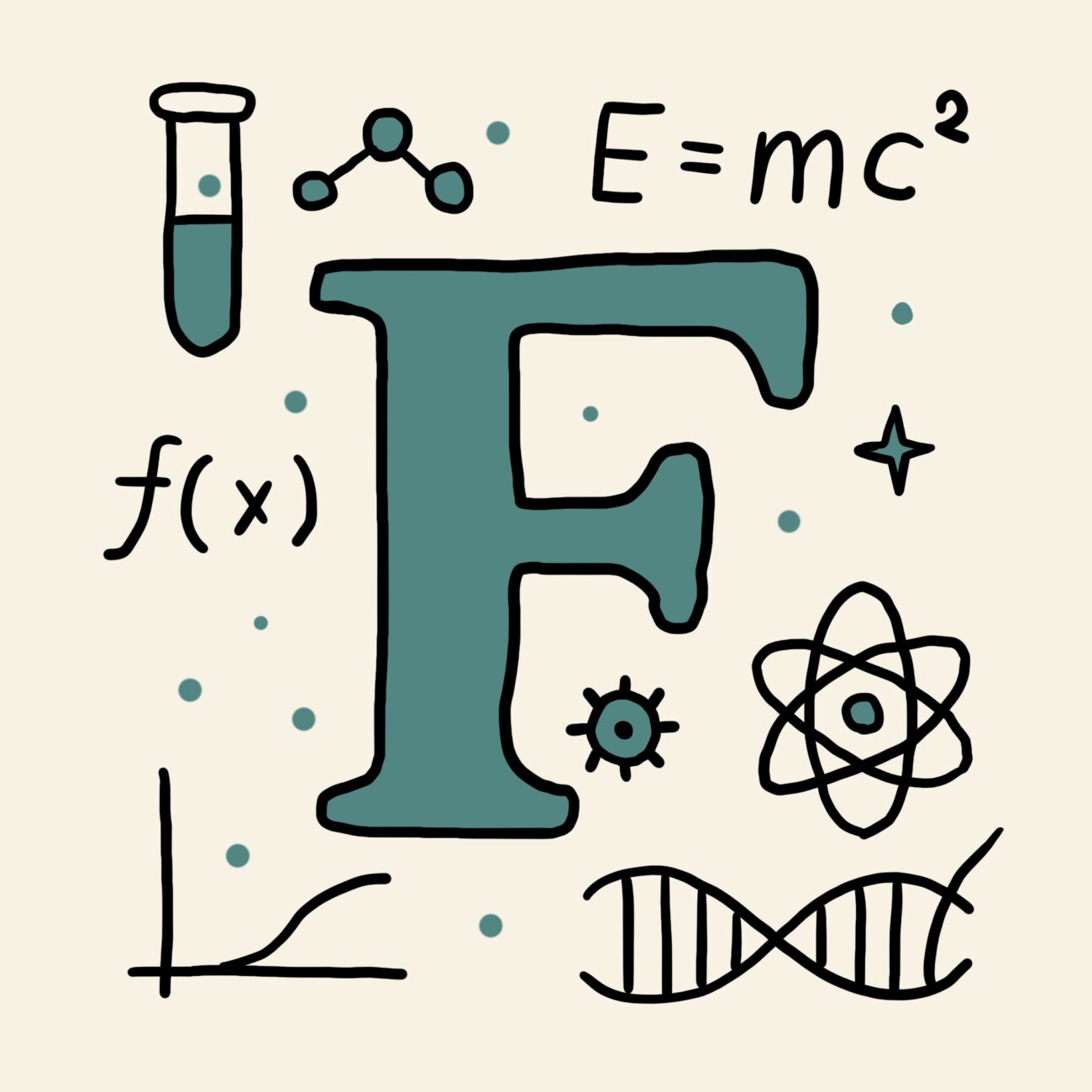
森博嗣の『S&Mシリーズ』が今もなお読まれ続けている理由。
そりゃもう、謎解きの面白さだけじゃなく、シリーズ全体に張り巡らされた知のネットワークの深さと美しさに尽きる。
まず、犀川&萌絵のコンビがいい。知的でクール、でもどこか人間くさくて軽妙な掛け合い。このふたりの距離感、「くっつきそうで絶対くっつかない」あの感じにやられた人は少なくない。
恋とも友情ともつかない、だけど確かな信頼が積み重なっていくのがいいのだ。そのやりとりの中に、さらっと哲学があったり、トリックの伏線を張ってきたりするのもズルい。
そして、いわゆる「理系ミステリィ」。これがただのフックじゃない。本当に科学と論理の骨格で事件が組まれている。物理とかプログラムとかVRとかAIとか、そういう知識が物語の土台にしっかり根を張っている。
しかも、「いつかこうなるかも」ではなくて、「いやほぼ今でしょ」というレベルのリアルさだ。現実と地続きのテクノロジーが、違和感なくストーリーに溶け込んでくるのが、ほんとうにすごい。
そして、読んでいると、ふと立ち止まりたくなる場面が何度もある。
たとえば、「自我とは?」「意識とは?」「人間って世界をどうやって理解してるんだ?」みたいな話だ。それが誰かのモノローグや何気ない会話の中にひっそり潜んでいる。このシリーズは、感情で揺さぶってくるのではなくて、理性の深いところを刺激してくるのだ。
そして、絶対に外せないのが、真賀田四季。このキャラは本当にとんでもない。登場シーンは少ないのに、全作にでっかい影を落としてくる。倫理観がバグってる系の天才なのだけど、恐ろしく魅力的で、シリーズ全体の謎もテーマも、最終的にはこの人が中心にいる。正直、彼女を理解したいと思った瞬間から、もう森博嗣ワールドの住人になっていると思っていい。
そして何より、森博嗣の文章。
「淡々としている」とよく言われるけれど、あれは感情を過剰に演出しないだけで、むしろ熱はこもっているのだ。
必要なことしか言わないのに、その必要な一言が刺さる。
メモりたくなるセリフが絶対どこかで出てくるので、準備しておいたほうがいい。
こんな人にこそ刺さるシリーズだ
- 複雑でロジカルな謎解きを愛するミステリ好き
- テクノロジーと人間の関係性に思索の興味がある読者
- 会話劇に知的な緊張感と余白を求める人
- 感情より論理、爆発より沈黙に惹かれるタイプ
- シリーズ全体で構築される世界観の美学を味わいたい人
『S&Mシリーズ』は、単体でも魅力的だけれど、全10作を通して読むことで立ち上がる物語構造の全貌こそが最大の報酬だ。
一冊ごとに異なる事件を描きながら、シリーズ全体で何かを深く掘っている感覚。
それは、森博嗣の創作世界の基盤であり、後の『Vシリーズ』『Gシリーズ』『四季シリーズ』へとつながる巨大な思索宇宙の起点である。
決して万人受けを狙わない。
だけど、ハマる人にはとことん突き刺さる。
読者の知性と感性の芯を試しにくる。
そして試された側は、なぜか嬉しくなる。
そんなシリーズが、他にどれだけあるだろうか。
『S&Mシリーズ』は間違いなく、日本ミステリ史の中で、異次元の座標に立っている。