本格ミステリというジャンルは、長い時間をかけて「論理」という名の鋼鉄の骨格を鍛え上げてきた。
誰がやったのか、どうやったのか。整然と積み上げられた手がかりが、やがてひとつの真相へ収束する。
その美しさに魅せられてきたひとりの人間として、私はこの形式を何度も何度も愛してきた。
そして、2020年代のミステリは、明らかに別の方向へ進み始めている。犯人当ての快感だけではなく、物語そのものに翻弄される体験へと軸足が移っている。
そんな流れの中で出会ったのが、五条紀夫『流血マルチバース』だった。
読み終えた感想を一言で言うなら、これはミステリであり、迷宮であり、そして体験だった。
活字の海に投げ込まれた多世界の爆弾

著者の五条紀夫といえば、デビュー作『クローズドサスペンスヘブン』で死後の世界を舞台にし、前作『私はチクワに殺されます』ではチクワの穴から死に様が見えるという、一見すると正気を疑いたくなるような設定を、驚くほど精密なロジックで本格ミステリへと昇華させてきた稀代のトリックスター。
その彼が今回挑んだのは、なんと「マルチバース(多元宇宙論)」だ。アメコミ映画でおなじみのあの概念を、あえて活字の、しかもクローズドサークルミステリに真っ向から持ち込むという暴挙に出たわけである。
500ページを超える圧倒的なボリューム、そして「ルート分岐」というゲーム的な構造。ミステリファンが愛してやまない本格の美学を、彼は一度バラバラに解体し、見たこともない異形の怪物として再構築してみせた。
王道の孤島、なのに足元から世界が崩れていく
物語の舞台は、太平洋上に浮かぶ無人島「龍穴島」。 海霧に閉ざされ、過去の火山噴火で打ち捨てられた廃墟の島。
そこには「旧日本軍の財宝」が眠っているという……この「ミステリ好きなら100回は見た」ような完璧で最高な舞台装置。横溝正史の『獄門島』や『悪霊島』を彷彿とさせる、土俗的で陰鬱な空気が全編に漂っている。
主人公の菊田耕一は、記憶喪失の妹・紗枝を守りながら、一癖も二癖もある乗客たちと共にこの島へ上陸する。この島は単なる孤島ではない。風水で言う「龍穴」、つまり「気が噴出する場所」であり、並行世界が交差する特異点だ。
そして、ある世界線では生きている人物が、別の世界線では無残な死体として発見される、という設定が導入された瞬間、それまで築き上げてきた推理の土台は音を立てて崩れ去った。
ミステリにおいて「死」は唯一無二の確定事項であるはずなのに、本作ではその前提すらも「可能性の一つ」に過ぎなくなる。この眩暈のような不確定性こそが、本作が放つ第一の毒である。
分岐する因果、あるいは重なり合う三つの地獄
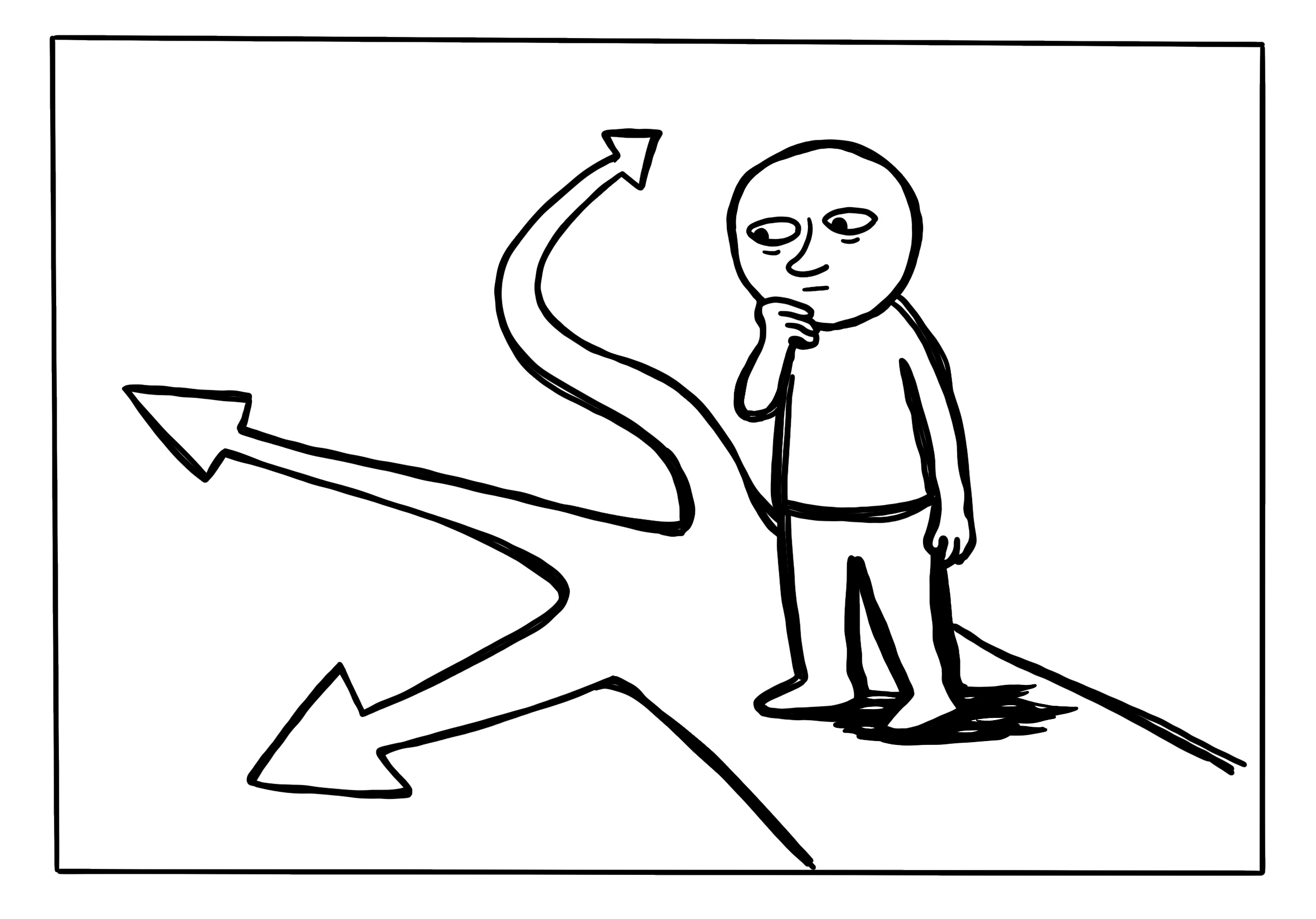
本作が面白いのは、物語の構造そのものにある。
読者の読み進め方や作中の主人公の選択によって、物語は「Aルート」「Bルート」「Cルート」の三つに分岐する。
これはゲームブックや、かつて熱中したサウンドノベル『かまいたちの夜』のような手法を、小説という媒体に完璧に落とし込んだものだ。だが、これは単なるマルチエンドの類ではない。
各ルートは物語の結末が異なるだけでなく、ジャンルそのものが変容するという点で極めて実験的だ。
Aルートにおいて展開されるのは、ミステリファンを唸らせる「見立て殺人」。島に伝わる四首の短歌になぞらえて、凄惨な死体が次々と演出されていく。
ここでは探偵役の論理的推理や物理的な証拠の積み上げが重視され、横溝正史的な情緒とジョン・ディクスン・カー的な不可能犯罪の論理が見事に融合している。ここで正統なミステリを堪能し、「この世界は論理で解明できるはずだ」という安心感を得た。
しかし、その安心感は他ルートの存在によって脆くも崩れ去る。
一転してBルートでは、物語は「デスゲーム」の様相を呈する。登場人物たちの間の信頼関係は崩壊し、互いが互いを殺し合う極限の心理戦が繰り広げられる。ここでは論理よりも生存本能や狂気が支配的となり、サスペンスフルな展開はページをめくる手を止めさせない。
そしてCルートは、AとBの背後にある「世界の構造」そのものに迫るルートである。なぜ世界は分岐するのか、龍穴島とは何なのか。このルートではミステリの枠組みを超えたSF的な要素が爆発する。
すごいのは、AルートやBルートで得られた情報が、このCルートにおいて全く別の意味を持って再構成される点だ。
情報の断片が頭の中で渦巻き、それらが終盤に向けて一点に収束していく瞬間のカタルシスは、直線的な物語では決して味わえない爆発力を持っていた。
活字という名のデバイスが引き起こす認知的酩酊
『流血マルチバース』を読み終えたいま確信しているのは、これが単なる特殊設定ミステリの流行に乗った一冊ではないということ。
これは、小説というメディアが持つ語りの力を、構造のレベルから再定義しようとする革命だ。
活字という、一見すると古いデバイス。そこに「マルチバース」と「ルート分岐」という概念を流し込むことで、五条紀夫は映像やゲームでは決して到達できない、純粋に知的な、そして身体的な「没入体験」を作り出した。
情報の断片がルートを超えて繋がり、頭の中でカチリと音を立ててパズルが完成する。その瞬間に放出されるドーパミンは、私たちが物語を必要とする根源的な理由を思い出させてくれる。
もし、この現実がたった一つの宇宙でないのなら。
もし、この文章を読んでいるあなたも、別の世界では全く異なる感想を抱いているのだとしたら。
そんな不敵な想像を誘うこの作品は、間違いなく近年のミステリシーンを象徴する一冊だ。
この迷宮の出口に立って、今もなお龍穴島から吹き付ける霧の感触を肌に感じている。
真実とは、観測者がいて初めて確定するものだ。
ならば、あなたという観測者がこの本を開いた時、そこにはどんな世界が立ち上がるのだろうか。
それを確かめる唯一の方法は、ただ、その表紙をめくること、それだけである。



















