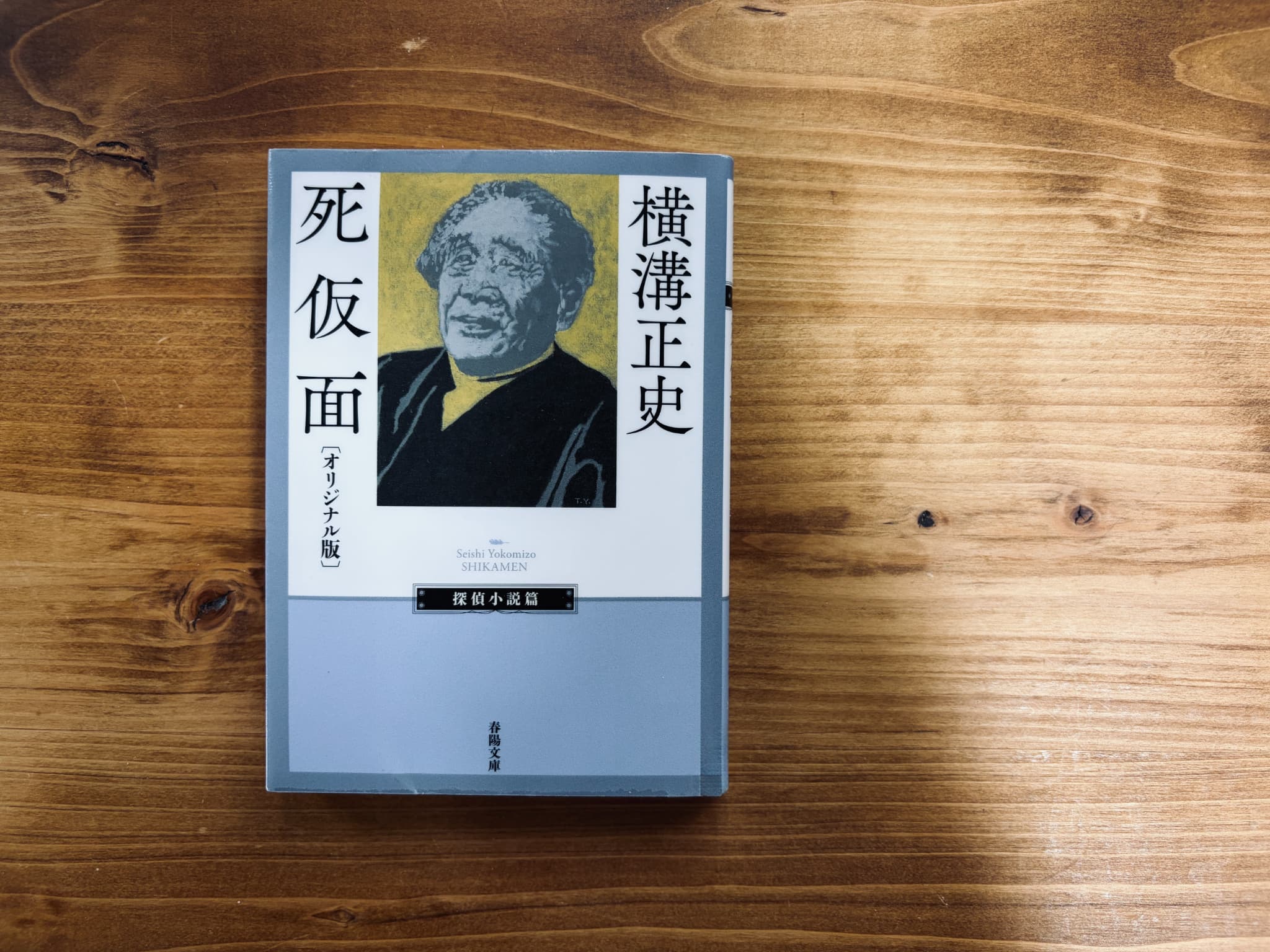怪談でもない、ホラーでもない、かといって純文学でもサスペンスでもない。
けれど、読み終えたあと、ふと視界の隅に影がよぎるような、そんな短編小説がある。
分類不能で、どこにも収まらず、それゆえに妙に印象に残る。
このジャンルには、かつて日本の評論家たちが名づけた「奇妙な味」という、まるでワインの香りのような名前が与えられている。呼び名からして曖昧だけれど、それがまた、このジャンルの本質をよく表している。
たとえば、ロアルド・ダールのように、日常の裏側にブラックな毒をひそませた作家。あるいはサキのように、優雅な文体でえげつない結末を差し出してくる作家。
あるいは、ロバート・エイクマンやシャーリイ・ジャクスンのように、不安そのものを構造として物語に埋め込む作家。
彼らが手がける短編のほとんどは、幽霊も出ないし、血も飛び散らない。でも読み終えたあとに、妙なざわつきと微かな吐き気が胸の奥に残る。これはもう、味としか言いようがない。
この「奇妙な味」は、主に三つの方向性に分けて語ることができる……と私は思っている。
ひとつは、サキに代表される「風刺と皮肉」の路線。
ふたつめは、エイクマンに象徴される「存在の曖昧さと説明拒否」。
みっつめは、ロアルド・ダールやショートショートの名手たちが追求した「構造美とどんでん返しの妙」。
それぞれ味の系統は違えど、なんだか説明のつかない不安や、世界のほころびを垣間見たような違和感は共通している。
この記事では、そんな分類不能な短編ばかりを30作品、世界中から厳選してご紹介したい。
ちょっとした隙間時間に読めるボリュームながら、脳内にこびりつく読後感はどれも一級品。
読んで「怖かった」というより「おかしかった」「変だった」「後味が悪い」と感じたら、あなたはもう立派な奇妙な味の愛好家である。
それでは、ようこそ。
不条理と美学がねじれあった、短編の迷宮へ。
1.サキ『けだものと超けだもの (白水Uブックス)』
もし、奇妙な味の原点を探したいなら、ヘクター・ヒュー・マンロー、つまりサキを避けて通るわけにはいかない。
名前は知らなくても、イギリスの短編でいちばん辛辣で笑える作家といえば、この人だろう。
「人間よりマシなけだもの」と「けだもの以下の人間」。そのあいだをぬるりと泳ぐのが、サキの傑作短編集『けだものと超けだもの』だ。
動物と人間の立場が逆転したり、子供が大人を翻弄したり。秩序や常識なんてものは、ここではとことん軽く扱われる。舞台はエドワード朝のイギリス、上流階級のサロンや田舎屋敷。外見と体裁ばかり重んじる、なんとも気取った大人たちの世界である。
でも、そこに子供や動物といった理屈が通じない存在が入り込むと、空気が一変する。無垢そうな子供が見事に人をだまし、ちょっとした会話のすれ違いが地獄の入り口になり、優雅な日常が崩れていく。
短いのに、最後の一行でビンタを食らったような気分にさせられるような話ばかりだ。
子供と動物が暴き出す、上品な社会のあやしさ
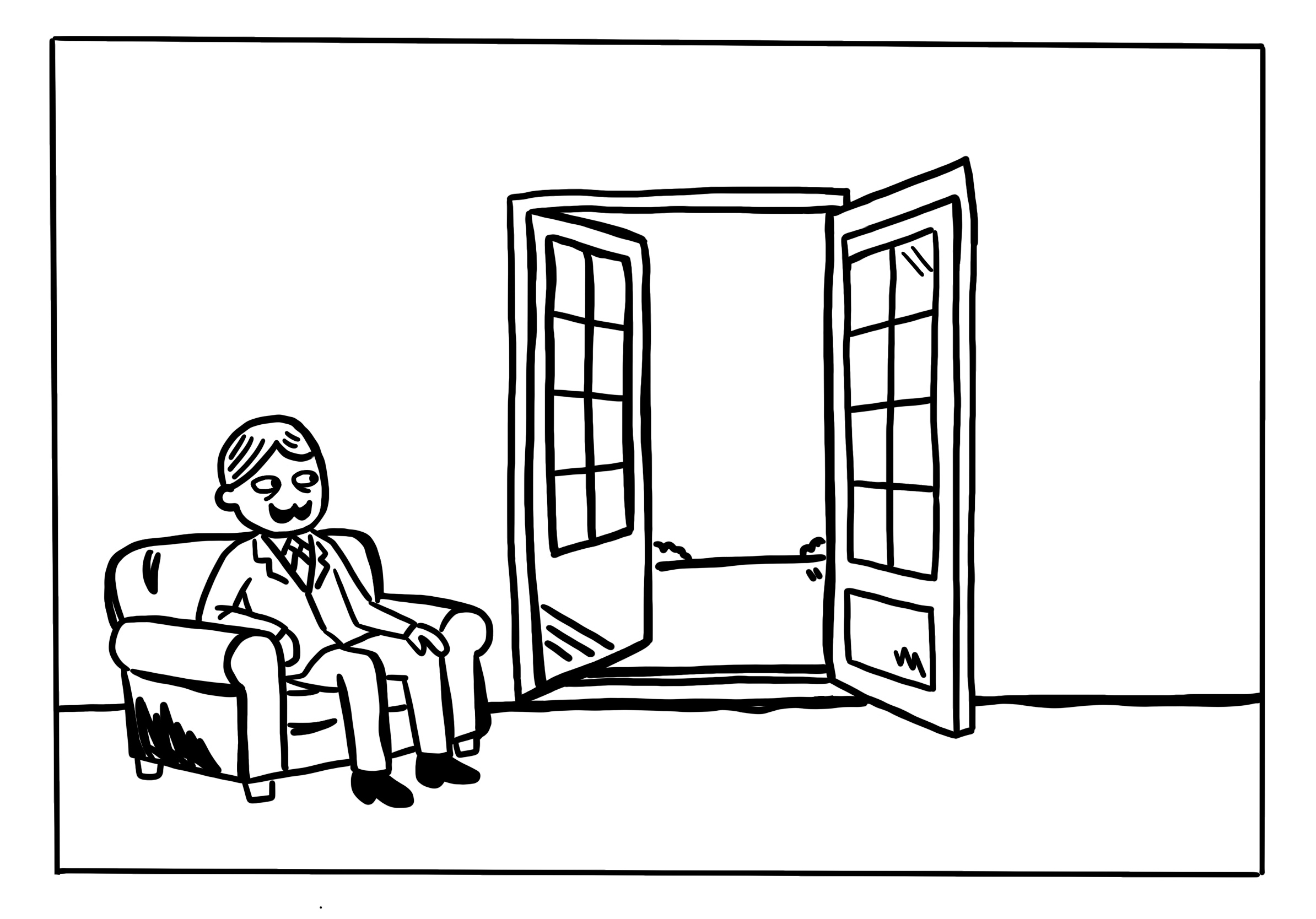
サキの得意技は、偽善的な大人社会を無邪気な存在が壊す構造だ。
たとえばサキの代表作である『開けっぱなしの窓』(あるいは『開いた窓』)。
療養のために田舎に来た神経質な男が、少女から「3年前に死んだ男たちが帰ってくるかも」なんて話を聞かされる。
まさかそんな……と思っていたら、窓の外に本当に男たちの姿が。パニックを起こして逃げ出した彼に対して、少女はしれっと「犬が苦手らしいわ」と後始末まで完璧。語った内容が本当かどうかなんて関係ない。大事なのは、その場の空気を支配できるかどうかだ。
同じ構造が『お話上手』にもある。うるさい子供たちにおとなしくさせようと、叔母さんは「良い子が報われるお話」を語るが、まったくウケない。そこへ現れた独身男性が語るのは、毒のあるブラックな話。子供たちは夢中になる。
正しさはつまらない。彼らの世界では、面白さこそが正義なのだ。
理不尽?
「いや、自然ってそういうものでしょう?」というサキの声が聞こえてきそうな冷たさがある。
どの話も2〜3ページの短さながら、読み終えたあとには妙な満足感が残る。笑ったはずなのに、なんだかチクリと刺さる。それがサキの奇妙な味だ。洗練されたユーモアと毒の効いた言葉、そしてどこか優雅な残酷さ。
大人たちが築いた秩序が、子供や動物たちの正直すぎる本能に壊されていくのを見ていると、どこかスカッとする。だけど少し怖くもなる。
サキはそんな複雑な感情を、ひと言も無駄にせずにやってのける。まさに、けだものより怖いのは、知性と笑顔で包んだ毒だ。
笑ったあとに、なんだか血の味がする。
それが、サキの「けだものたち」が放つ、本物の牙である。
2.英国紳士は嘘と毒を嗜む── 『サキ短編集』
「短編は毒が効いていてこそ」
そんな信条があるなら、この一冊はまさに古典にして最前線。この『サキ短編集』はまさにそんな毒入りキャンディみたいな本だ。
イギリスで20世紀初頭に活躍したサキ(H.H.マンロー)は、オー・ヘンリーと並び称される短編作家だけれど、作風はもっと冷たくて、残酷で、笑いに黒さがある。
嘘は芸術、悪意は洗練
このに収録された21編には、ユーモアと残酷が絶妙なバランスで同居している。
代表作『開いた窓』では、神経衰弱の男が少女の巧妙な作り話に翻弄されるし、『おせっかい』では敵同士だった男ふたりが倒木の下で和解するも、最後にやってくるのは救助隊じゃなくて……という皮肉たっぷりのオチが待っている。
どの話も短いのに、最後の一撃が強烈。まるで掌編版のイヤミスというか、数ページで精神にパンチを食らわせてくる感じだ。
サキの短編に通底するのは、大人の都合や上品な社会規範への冷笑だ。上流階級やちゃんとした大人のふるまいが、子どもや動物、あるいは自然の力でひっくり返される展開が多くて、どこかスカッとする。やってることはかなりえぐいのに、妙にスタイリッシュなのも特徴的だ。
そしてなにより、短編としての完成度がとにかく高い。無駄のない描写、会話文の鋭さ、意図的にずらされた情報の配置。星新一、筒井康隆、阿刀田高など、後の日本の短編作家たちもサキに影響を受けたと言われている。
短いけれど、ずっと後を引く。そういう一撃を、これでもかと並べてくるのがこの本だ。
『開いた窓』の向こうにいたのは幽霊ではなかった。
だがそこに映っていた、ものすごく人間的な悪意の気配は、むしろ幽霊以上にぞっとするのだ。
3.その一手に、ゾクリとする快感を── ロアルド・ダール『あなたに似た人』
ロアルド・ダールといえば『チャーリーとチョコレート工場』などで知られる児童文学の大家だが、真に恐ろしいのはむしろその短編小説の世界である。
『あなたに似た人』は、彼のブラックユーモア短編の代表作を収めた初期の傑作集。タイトルがすでに挑発的で好きだ。
ここに出てくるのは、どこにでもいそうな普通の人たち。しかし、その誰にでも似ている人間たちが、ふとしたきっかけで異常な欲望や狂気に堕ちていく。そこがたまらなく面白い。
笑いながら指を落とす、ブラックの快楽
冒頭から賭けにまつわる短編が続くが、どれも尋常ではない。たとえば『味』ではワインの銘柄当てが高じて、なんと娘の結婚相手まで賭けの対象になる。
『南から来た男』では「ライターを10回連続で着火できるかどうか」で、賞品はキャデラック、失敗すれば小指が消えるというヤバすぎる条件が提示される。ドキドキするが、笑っていいのか怖がるべきか、読みながら自分の感情が混線してくる。
中でも名作『おとなしい凶器』は見逃せない。冷凍の羊肉で夫を撲殺してしまう主婦。その計算高さには、うっかり拍手したくなる。ツイストの妙、ブラックな笑い、そして倫理の地滑り。どれを取っても完成度が高く、短編というフォーマットの中にギュッと毒が詰められている。
他にも『皮膚』『首』『プールでひと泳ぎ』など、どこか一線を越えてしまった人々が、思いもよらぬ形で結末を迎える。しかもどの話にも共通するのは、「こういう人いそう」と思わせるリアリティの存在だ。特別な怪物は出てこない。出てくるのは、あなたに似た誰かであり、もしかするとあなた自身かもしれない。
ロアルド・ダールの短編を読むと、人間が持つどうしようもない弱さやズルさ、そして突発的な狂気が、どれも「ありうるもの」として描かれていることに驚く。優雅な文章と皮肉な語り口が、こうしたダークな内容をかえって魅力的に見せるから困る。
この短編集は、短編ミステリの入門としても最適だけれど、そう簡単に読み流せるものではない。一度読めば、あなたもきっと奇妙な笑いの味を覚えてしまう。
気をつけた方がいい。
なぜなら、あなたもきっと、どこかで誰かに「似た人」だからだ。
4.その口づけは、背徳の刃である── ロアルド・ダール『キス・キス』
ロアルド・ダールの短編小説集。
『キス・キス』というタイトルに惹かれて手に取ると、まず裏切られる。
いや、正確には「期待を斜め上に超えて裏切られる」のだ。
1960年に刊行されたこの短編集は、ロアルド・ダールが短編作家として最も鋭利だった時期の傑作群であり、愛と優しさの衣をかぶった毒が、どこまでも鮮やかに神経を焼いてくる。
ここに詰まっているのは、愛のささやきではなく、復讐の囁き。甘い接吻ではなく、毒を塗った牙による致死量のキスである。
愛と狂気が紙一重で交わる場所
たとえば傑作として名高い『女主人』では、田舎町の下宿に泊まった若者が、やけに親切でお茶好きな女主人に出迎えられる。
その優しさはどこか過剰で、部屋には数年前に行方不明になったはずの青年の名が記されている。彼らはまだ「上の階にいる」と彼女は言い、剥製趣味を嬉々として語るが……気づいてしまった瞬間には、もう遅い。
他にも、死んだ夫の脳と片目だけを生かし、好き放題に振る舞う妻を描いた『ウィリアムとメアリイ』、夫がエレベーターに閉じ込められているのを知りながら、6週間のパリ旅行に出かける『天国への登り道』など、愛と結婚という制度がいかに歪み、地獄へと化すかを軽やかに描いてみせる。
どの物語も、読んでいてにやりとさせられるが、その笑いは明らかに「背筋を冷たくなぞるタイプ」の笑いである。
面白いのは、これらの作品の多くで女性が主導権を握っていることだ。家庭という舞台で男を料理するのは、鍋でも包丁でもなく、精神的圧迫や沈黙、あるいは笑顔という名の刃物である。
ロアルド・ダールが女性を恐れていたのか、それとも社会の抑圧された怒りを女性に託したのかはさておき、この短編集では女性たちは容赦がない。そしてそれが、どこか快い。
身体の変容や曖昧な境界を扱った作品も強烈だ。『ローヤルゼリー』では、蜂の成分であるローヤルゼリーを与えられ続けた赤ん坊を描く奇譚。『豚』では、料理の才能に恵まれた少年が、料理の本を書くために都会へ出るが……まさかの結末。これらの話に通底するのは、「人間とは何か」というテーマであり、そこには冷笑と哀れみが同居している。
『キス・キス』は、『あなたに似た人』よりも一段階毒が濃く、救いのない皮肉が際立つ一冊だ。とはいえ、この毒は決して不快なものではない。
むしろ、それが自分の皮膚にも少し沁み込んでいることに気づいたとき、ニヤリと笑ってしまうような、そんな恐ろしくも魅力的な短編集である。
タイトルの「キス」が意味するのは、愛の証か、あるいは絶望の始まりか。
ページをめくったその先で、あなただけの口づけが待っている。
5.幽霊のいない怪談が切り拓いた不気味の未来── ロバート・エイクマン『奥の部屋』
「何が怖かったのか、うまく説明できない」
そんな読後感をこれほど上品に突きつけてくる作家は、エイクマンをおいて他にいない。
『奥の部屋』は、古典的な怪談のように幽霊や化け物を明確に提示しない。にもかかわらず、読んでいる最中から胃の奥あたりに妙な圧がかかってくる。しかもその恐怖は、決してクライマックスで爆発したりしない。
代わりに、曖昧で象徴的なシーン、説明不能な登場人物の行動、意味ありげなのに何も明かされない結末が、何重にもレイヤーを重ねてくる。
気づけば、どこに着地したのかよく分からないまま、不穏な印象だけがくっきりと残る。いわばこれは「着地しないホラー」だ。
恐怖の輪郭を失わせる技術
特に印象的なのは、収録作『学友』や『髪を束ねて』などに見られる、語られない部分の使い方だ。
エイクマンは、物語を語ることで恐怖を喚起するのではなく、語らなさを操作することで、見る側の想像力そのものを不安定にする。モンスターを直接見せるのではなく、「何かがいたような気がする」と思わせたまま終わらせる。その手つきがとにかくうまい。
そして何よりも、エイクマンの恐怖は「この世界の論理が通用しない場所が、確実にどこかにある」という感覚を呼び起こす。その場所は廃屋でも心霊スポットでもなく、ありふれた建物や日常の裏に紛れて存在している。まるで自分の日常のすぐ隣に、説明不可能な別の人生が重なっているような気持ちにさせられるのだ。
こうした手法は、一見するとオチがない話に思える。しかしそれは、スッキリと片が付くことが前提の物語構造に毒された見方である。むしろ、解釈不能であること自体が、エイクマンの意図なのだ。
エイクマンの物語には、どこか幻想的な匂いすらある。美しい風景、落ち着いた会話、詩のような象徴性。だが、その美しさは常に不穏と隣り合わせで、ラストに向かうにつれて空気が濁っていく。
特別な事件が起きるわけではないのに、なぜか何かが壊れてしまったような感触だけが残る。感情ではなく、構造そのものを狂わせるホラー。だからこそ、読む側は気づかぬうちに巻き込まれていく。
恐怖の出どころは、目に見える何かではなく、知覚と理解のズレにある。言い換えれば、「分からないまま進んでしまった」という感覚こそが、最大の恐怖なのだ。
エイクマンの短編は、その意味で怪談というより経験に近い。得体の知れない不安を、説明も救いもないまま渡してくる、極めて厄介な文学体験。きれいに終わらないことこそが美徳であり、その未完性の中に、ぞっとするような真実が顔を出す。
安心できる物語から一歩踏み出したい人にとって、『奥の部屋』はまさに「こっち側へようこそ」と囁く一冊だ。
ここで起きたことは、理解できなくていい。
理解できないまま、通過してしまったこと自体が問題なのだから。
6.正気な人々が石を投げる── シャーリイ・ジャクスン『くじ』
シャーリイ・ジャクスンの描く恐怖は、いわゆる幽霊屋敷ではなく、ごく普通の家庭や郊外のコミュニティといった、安心できそうな場所にこそ巣食っている。
その点で彼女は、現代のホラー作家たち、スティーヴン・キングやポール・トレンブレイの先駆けであり、いわばアメリカン・ゴシックを再定義した存在だ。
特に短編集『くじ』は、彼女の恐怖のエッセンスが凝縮された代表作である。
「くじ」とは、つまり石を持つこと
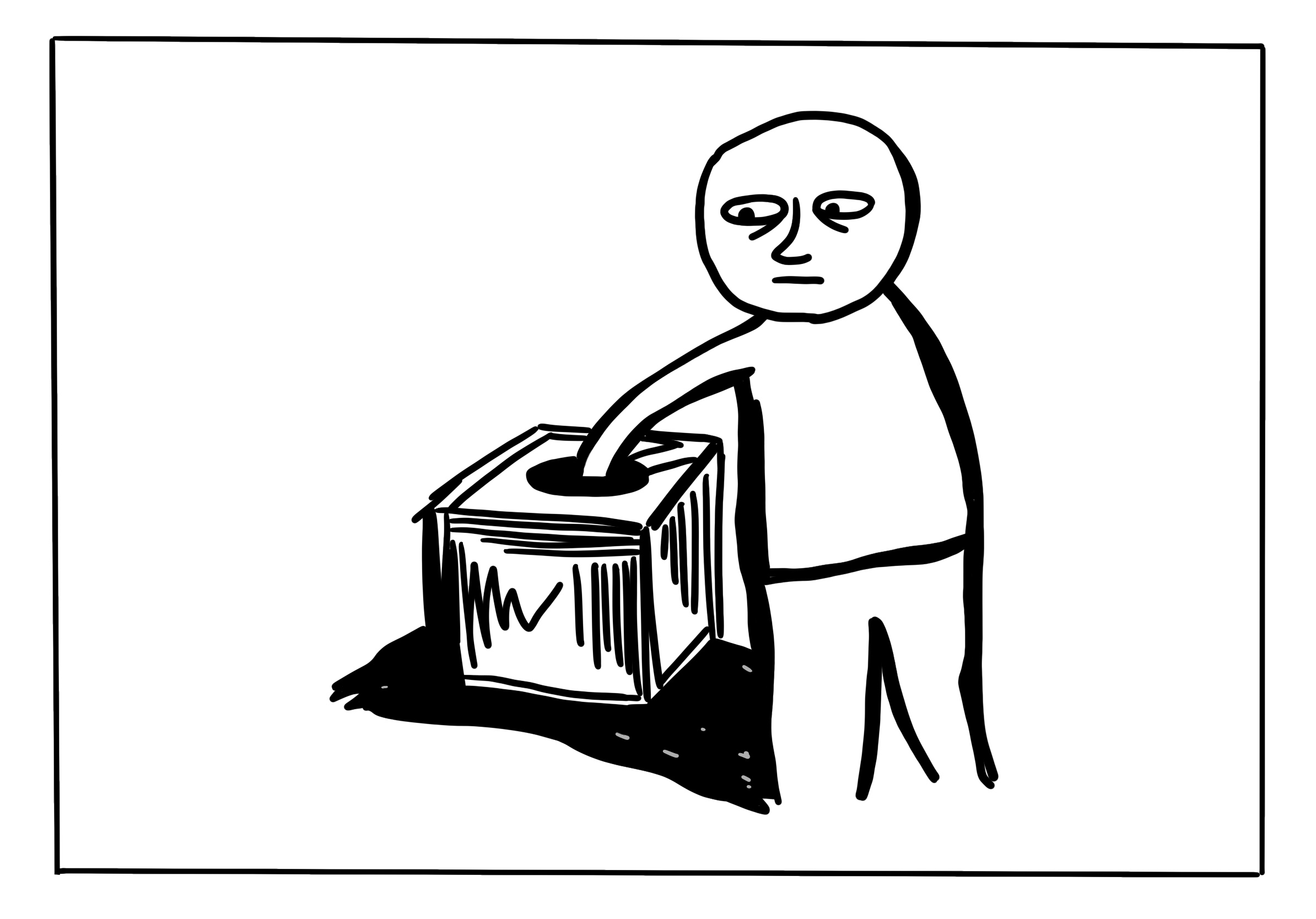
表題作『くじ』は、戦後の『ニューヨーカー』誌に掲載され、当時の読者から怒りの手紙が殺到したという伝説的短編だ。
300人ほどの小さな村で、毎年恒例の「くじ引き」が行われる。和やかな雰囲気の中で事務的に儀式が進み、「当たり」を引いたハッチンスン夫人はその場で村人たち(家族すら含めて)に石を投げつけられる。
これは豊作を願う人身御供の儀式だが、ジャクスンが描くのは儀式そのものよりも、それが日常として受け入れられているという異常さだ。誰もが淡々と、真顔で、石を手に取る。恐ろしいのは血でも狂気でもなく、「誰も疑問を持たない」という集団心理の冷たさだ。
このような、どこか乾いた社会批評は他の作品にも貫かれている。『魔性の恋人』では、結婚式の日に現れない婚約者追って街を彷徨う女性が、次第に自分の存在そのものに疑念を抱き始める。彼女が探していたのは本当に「彼」なのか、それとも「自分自身」だったのか。
『歯』でも、都会の喧騒と痛み止めの副作用が交錯するなか、主人公の自己認識が崩れていく。こうした不安感は、スリラーというより都市伝説のような気味の悪さに近い。
ジャクスンの恐怖は、目を覆いたくなるような描写ではなく、気づいたらもう逃げられないという構造にこそある。特に印象的なのは、彼女が家庭や共同体といった、信頼の象徴のような空間を、徐々に崩壊させていく手腕だ。家族、隣人、母と子……それらが、ある時から別の顔を見せ始める。
『くじ』がいまだに語り継がれるのは、石を投げる側が怪物として描かれていないからだ。
彼らはただ、順番を守り、役割を果たし、空気を乱さない。
そう考えると、ジャクスンの恐怖はいつも決まった場所に現れる。
会話が滞りなく進み、手順が共有され、誰も立ち止まらない場所だ。
その感覚に一度気づいてしまうと、日常の中にある当たり前が、ほんの少し重く見えはじめる。
7.ちょっと変な人が世界をねじ曲げる── オーガスト・ダーレス『ジョージおじさん』
クトゥルー神話の整理人、みたいな扱いをされがちなオーガスト・ダーレスだが、実のところ彼が本領を発揮していたのは、宇宙的恐怖ではない。
湿った風の吹くウィスコンシンの片田舎、日暮れどきに草むらを通りかかると感じる背後の気配、あの肌に近い怖さを書かせたら、彼は一級だった。
短編集『ジョージおじさん』は、そんなダーレスの「幽霊たちの優しさ」に満ちた一冊である。死者は恨みを晴らすためにではなく、子どもや弱者を守るために帰ってくる。
しかもその方法が、古典的なポルターガイストから視界の隅で揺れるカーテン、忘れられた眼鏡まで、いちいち丁寧で美しい。
ゴーストが主役の家庭内サスペンス
たとえば表題作『ジョージおじさん』は、孤児の少女が遺産目当ての親戚に殺されそうになるという、やけに直球の展開から始まる。だが読者は、早い段階で「この子には幽霊の味方がいる」ことを知る。しかもそれが、亡きジョージおじさん。誰に頼まれたでもなく、成仏せずに残っていたらしい。
悪人たちが行動を起こすたび、何かが落ち、棚が倒れ、階段から足を滑らせ……と、事故が自然すぎて逆に怖い。でも、どこか痛快なのだ。ダーレスの幽霊は、倫理的にちゃんとした動機で動く。恐怖というより、「早く来てくれてよかった」と思える類の存在である。
『B十七号鉄橋の男』や『黒猫バルー』では、舞台はあくまで日常。町や村、ありふれた橋やカフェといった場所で、ふとしたズレが起こる。そして、そのズレの原因となるのが、ちょっとだけ異様な人物たちなのだ。彼らは何も叫んだり襲ってきたりしない。ただ、そこにいる。それだけで空気が妙になる。
このちょっとだけ、という匙加減がうまい。ホラーでもファンタジーでもサスペンスでもない。でも全部に少しずつ足を突っ込んでいるような感触。しかも、どの作品もオチを派手に決めるわけではない。何かが起きて、何かがズレて、終わる。その余白がむしろ良いのだ。
いわゆる「ラヴクラフト神話」のダーレスとは違う、人間のために働く霊たちを描いたこの短編集は、どこか安心できる怖さがある。しかもそれは、最後まで人を見捨てないやさしさに支えられている。
だからこそ、ページを閉じたあとも、ふと夜道で後ろを振り返ったり、冷蔵庫の裏を覗き込んだりするとき、そこに「誰かが見守っているかもしれない」と思わせてくれるのだ。
それが、ジョージおじさんである保証はないにせよ。
8.現実を捻じ曲げる技術── レイ・ヴクサヴィッチ『月の部屋で会いましょう』
「なんだこれ?」と思いつつページを繰り、「そういう話か」と気づいた頃にはもう引き返せない。
でも、それこそがレイ・ヴクサヴィッチの世界では自然なのだ。奇妙すぎて笑ってしまう。笑った後、ちょっと胸が痛くなる。そんな作品集が、この『月の部屋で会いましょう』である。
ヴクサヴィッチはSFでもホラーでも文学でもある作家だ。いや、ジャンルに属するというより、すべてのジャンルの皮を一枚ずつ剥ぎ取って、奇妙な何かに仕立ててしまう人である。
収録作はいずれもショートショートのように短い。だが、その一編一編が、まるで宇宙の法則をほんの5ミリずらしたような違和感をもたらす。
形式破りの優しいねじれ
まず驚くのが、ジャンルの溶け方である。SFっぽい話もあれば、寓話じみたものもあるし、どこか詩のような断片的な構成もある。
だが共通しているのは、ほんの少し現実のルールが違う世界が、やけに生々しい感情と結びついていることだ。
たとえば、記憶を保存できるUSBのような装置が当たり前になった世界で、人間関係の崩壊がどんなかたちで起きるのか。あるいは、夢の中でしか会えない恋人との別れ方。どれもアイデアは一見派手ではないが、文章の温度が変で、読み進めるうちに現実そのものがふわっとずれてくる感覚がある。
このズレの扱いがとにかくうまい。設定そのものが奇抜である必要はない。むしろ、「ありそうで、なさそうで、やっぱりないかも」くらいの距離感にこそ、彼の腕が光る。ヴクサヴィッチの〈変〉は決して押しつけがましくなく、むしろ優しい。そしてそれが、なおさら不穏なのだ。
さらに彼の作品は、オチがない。いや、あるのだけど、たいていの場合、意味を決めないまま終わる。これを物足りないと思うか、魅力だと思うかは好みによる。
ただ、世界が断定されないまま、ふわふわと浮いた状態で話が終わるのは、まさに現代的な不安のかたちそのものだと思う。
ヴクサヴィッチの作品を読んでいると、どこかで「現実はひとつじゃない」「言葉だけでは説明できないことがある」と、腑に落ちてしまう。
その不思議な説得力が、この短編集の一番の魔法なのかもしれない。
9.何かがおかしい、それが面白い── 『街角の書店 (18の奇妙な物語) 』
このアンソロジーを読み始めると、頭が少し変になる。
タイトルは『街角の書店』。編者は中村融。
ジャンルは一応「奇妙な味」とされているが、読めば読むほど「ジャンルって何だっけ?」という気分になってくる。
恐怖でもミステリでもSFでもファンタジーでもあるけれど、全部なんだかズレている。むしろ、そのズレこそが本作の核である。
想像力の暴走が現実を侵食する
まず表題作の『街角の書店』からしておかしい。作家である主人公が、まだ構想しかしていない小説を、偶然立ち寄った書店の棚で見つけてしまう。
もちろんその小説は未完成なのに、完成品としてそこにある。このパラドックスが生む不安と焦燥、そしてありえなさの妙な説得力。たまらない。
他にも、テリー・カーの『試金石』では、意味の分からないモノが最後まで意味不明のまま終わる。そしてそれがむしろ納得感を持ってしまう不思議。
ジョン・スタインベックの『M街七番地の出来事』なんかは、意思を持つガムが登場する。もはや真顔で読み進めることすら困難だが、話としての完成度が高いからこそ笑っていいのか怖がっていいのか分からなくなる。
さらに、フリッツ・ライバーの『アダムズ氏の邪悪の園』では、魔術によって女性の身体を植物として復元するという、エロスとグロテスクの隙間をすり抜ける怪奇譚が待っている。
このアンソロジーの凄いところは、ジャンルの枠を完全にスルーしているのに、なぜか全体に統一感があることだ。
その正体は、おそらく「世界のルールがおかしい」という感覚だろう。ルールそのものがひっくり返るのではなく、あくまで日常の手触りを保ったまま、何かが食い違う。しかも登場人物たちは基本的にその異常に気づかない。だからこそ怖いし、笑える。
この短編集を通して感じるのは、奇妙さが明確なオチや説明によってもたらされるのではなく、むしろ不明瞭さ、不完全さ、余白の多さによって増幅されているということだ。それぞれの話が、世界のどこかにありそうで、でも絶対にない場所に導いてくれる。
おかしな話というのは、ただ奇をてらったネタではなく、世界を裏から覗く装置でもある。『街角の書店』は、その装置のスイッチをまとめて押してくれる一冊だ。
気づけば、自分の暮らす日常にすら、変なノイズが混じっているような気がしてくる。
10.ジャンルの迷宮で味を探す── 『夜の夢見の川』
「いったい何を読まされてるんだ?」という感覚がずっとついてくる。しかも悪くない。そんな摩訶不思議なアンソロジーが『夜の夢見の川』である。
前作『街角の書店』に続く、「奇妙な味」短編集の第二弾。編者はもちろん中村融。今回もまた、何ともカテゴライズしづらい短編ばかりを掻き集めてきた。
不安定さそのものがテーマ
まず注目したいのは、編者の構成意図が明確に「幅のある読後感」に向けられている点だ。
つまり、ほんわかする話もあれば、ズシンと沈むような物語もある。それらを並列に配置しているので、読み進めるにつれて気分が上がったり下がったりを繰り返す。読書という行為が、感情のジェットコースター状態になるのだ。
収録作には、G・K・チェスタトンのユーモラスで寓意的な一編『怒りの歩道』があれば、シオドア・スタージョンの『心臓』のようなじっとりした物語もある。とどめにロバート・エイクマンの『剣』が控えており、これがまた余韻の濃い技巧作。読後、何かを掴んだ気にもなるが、実は何も掴めていない。そこがいい。
編者はあえて、作者の意図が読み取りにくい作品を混ぜてきている。たとえばクリストファー・ファウラーの『麻酔』のような作品は、読み終わったあと、首をかしげながらもどこか惹かれている自分に気づかされる。この「わかりそうでわからない」感覚を抱えながらページをめくる行為そのものが、この本の醍醐味だ。
また、今回収められた短編の多くは、作者がSF作家であるにもかかわらず、舞台がほぼ現実世界という点も面白い。これはつまり、舞台装置ではなく感覚のズレによって奇妙さを演出しているということだ。
あくまで見慣れた世界が歪む。その微細な違いに気づいたとき、「なんか嫌だな……でも好きかも」となる。
このアンソロジーは、短編という形式のもつ未決定性を徹底的に活かしている。何かが終わったようで、何も終わっていない。ちゃんと完結しているのに、ずっと尾を引く。そんな不思議な味わいの一冊だ。
ひとつだけ確かなのは、このシリーズは、続けば続くほど癖になりそうということ。はやく続編を出してほしい。
11.サンドイッチに殺意を塗りたくる── ロード・ダンセイニ『二壜の調味料』
名探偵が鮮やかに事件を解決した……はずなのに、なぜかスッキリしない。
そんな気分を味わいたいなら、この一冊を勧めたい。
英国幻想文学の巨匠ロード・ダンセイニが、ミステリ界に放った異色の短編集『二壜の調味料』。
論理とユーモアとグロテスクが、絶妙な割合でブレンドされた、苦い後味を持つ奇妙な味ミステリの逸品である。
ミステリなのに、論理が不安にさせる
語り手は、調味料のセールスマンをしているスメザーズ。そして謎を解くのは、彼の同居人である青年リンリー。彼はいわゆるホームズ型の天才探偵だが、その推理のキレ味は、読んでいてむしろ怖くなるレベルだ。
表題作では、ある失踪事件の背後にある恐るべき真相を、ほぼ「二壜の調味料」という証拠だけで導き出してしまう。見事な論理。でも、ひとつも気持ちよくない。
江戸川乱歩が絶賛したこの一編。事件の全貌が明かされた瞬間、論理的には完全な解決なのに、なんとも言えないイヤな気配が喉元に残る。これがたまらないのだ。しかも犯人は、その後のシリーズ作品にも再登場する。別人として、別の犯罪を犯して。それがまたサラッと描かれているので、逆にぞっとする。
この短編集は、クラシックなディテクションの形式を踏まえつつ、読者の倫理感覚を試すような実験性を持っている。探偵リンリーは常に正しい。でも、その正しさが、常識や良識とはどこか歪んでいる。
結果として、「犯人が誰か」よりも、「この結末に納得してしまっていいのか?」という感覚に揺さぶられるのだ。
奇妙な味とは、サンドイッチのマスタードが血の香りだったようなものかもしれない。
『二壜の調味料』は、名探偵の論理が導く最悪の結論を、ユーモアの皮をかぶせて差し出してくる。
笑っていいのか、震えるべきか。
その判断をまるっと押しつけてくるあたり、実に悪趣味で……最高だ。
12.なぜ、あの部屋だけは落ち着かないのか── 『居心地の悪い部屋』
この短編集を読んでからというもの、エレベーターの中で隣に立つ人の目が、少し長く合っただけで怖い。
あるいは、休憩室で「新しい人が入ったらしい」と誰かが言った瞬間、喉の奥に何か詰まるような違和感を覚える。
そう、『居心地の悪い部屋』に登場するのは、そんなふうに現実のスキマから滲んでくる不安な短編ばかりだ。
この本は、翻訳家・岸本佐知子が英米の短編から「違和感だけが主役の作品」を12編選んだもの。奇妙な味、スリップストリーム、ニュー・ウィアード、ポストカフカ的現代文学……呼び名はなんでもいい。
とにかくこのアンソロジーは、日常が一歩ずつ別の論理に侵されていく、その過程をとても静かに、とても鋭く描いている。
居心地の悪さは、今そこにいる部屋にこそ潜んでいる

たとえば、ブライアン・エヴンソン『ヘベはジャリを殺す』は、二人の男が部屋にいて、片方は裸で、瞼が縫われている。
理由は全くわからない。説明の一切を削ぎ落とした文体で、人の意志や暴力がまるで物理法則のように働く世界を描いている。ひとつの出来事がすべてを支配し、登場人物たちは機械の歯車のように配置されていく。
ダニエル・オロズコ『オリエンテーション』は、入社初日の説明を聞いているだけなのに、語られる同僚の裏の顔がどんどん壊れていく。その淡々とした語りが逆に恐ろしく、この会社で何かが決定的にズレているという感覚が抜けない。
そして、ジョイス・キャロル・オーツ『やあ!やってるかい!』は、何でもないような挨拶の裏に、言葉のすれ違いと精神の断絶を仕込んだ掌編。職場や家庭といった逃げられない空間にこそ、真のホラーはあるのだと示してくる。
この本の恐怖は、「悪意を持った何か」ではなく、「日常の枠組みがゆっくり壊れていく過程」そのものである。説明がない。なぜそうなるのかも語られない。ただ、気がつけば、壁のひび割れが空へと続いていた……そんな読後感がたまらない。
目を凝らせば、どこかでこの短編集のようなことが起きている気がする。職場で、家庭で、電車の中で。
『居心地の悪い部屋』が描くのは、ファンタジーでもホラーでもない。
今まさにあなたが座っているその部屋で、もう始まっている物語なのだ。
居心地が悪いのは、部屋か、それとも自分か。
気づいたときには、もう遅い。
13.笑っても、どこか不安になる── セス・フリード『大いなる不満』
世界はよくできている。
たいていの人は、そう思いたがる。
でも、たまにいるのだ。世界のしくみに納得してないやつが。
なぜか人生のどこを切り取っても、噛み合わなさがついてくる。
そんな感覚を、セス・フリードは短編小説のかたちで徹底的にコメディ化し、しかも笑えないほどリアルに仕上げてきた。
不条理は、どこまで構築できるか?
『大いなる不満』に収められた物語たちは、いずれも「現実に似ているが、何かが極端に狂っている世界」を舞台にしている。学校や職場、家族や恋愛、いずれも日常生活でなじみのあるテーマなのに、その前提がどこかおかしい。
たとえば、ある組織の管理ルールが常軌を逸していたり、感情の表現方法が異様に制度化されていたり、そもそも登場人物たちの思考様式が、人間とは思えないほど機械的で粘着質だったりする。
でも、肝心なのは、彼らがその異常を「異常だと思っていない」ところだ。セス・フリードのユーモアはここにある。
世界はもう狂っている。でも人々は、その狂気にちゃんと順応してしまっている。あくまで誠実に、時に真面目すぎるほど真面目に、どうにか適応しようとしていくのだ。
つまりこの短編集は、奇抜な設定を並べたカタログではない。合理性の暴走を描いた、風刺と哲学と喜劇の融合体である。滑稽で不快で、哀しくて、笑いながら心を削られる。ダールやカフカの系譜にありつつ、フリードはそれをよりポップに、より過激に加速させている。
収録作のどれもが、オチや結末よりも「その状況でどう生きるか」という姿勢にフォーカスしているのも特徴的だ。設定が奇妙でも、そこで人間たちが迷いながら適応しようとするプロセスが、意外なほど共感を呼ぶ。そこにはシステム社会における正しさや承認欲求といった、現代人の苦しみがじかに響いているのだ。
笑える。でも、それだけじゃ終われない。ページを閉じても、不思議なざらつきが手のひらに残る。
セス・フリードの奇妙な味は、現実のほうがよほど奇妙であるということを、やんわりと、でもしっかりと突きつけてくる。
14.暗黒の喜劇、あるいは病んだ魂の手触り── モーリス・ルヴェル『夜鳥』
この短編集を読むと、「人間とはここまで病めるのか」と苦笑いしたくなる。
モーリス・ルヴェル『夜鳥』は、20世紀初頭のパリを舞台に、人間の裏側、それもかなり深くて暗い部分を鮮やかに描き出した怪作ぞろいの短編集だ。
どの話も短くスパッと終わるのに、残るものはやたら濃い。江戸川乱歩や夢野久作も夢中になったという逸話が残っている。
倫理のスイッチが切れる瞬間
この作品集に出てくる登場人物たちは、とにかく普通じゃない。
たとえば『或る精神異常者』。快楽を味わい尽くした金持ちが、今度は人の死にざまを観ることに生きがいを見出し、毎日同じ曲芸師のパフォーマンスを見に通い続ける。
書いてて怖くなるが、これをやたら淡々と、どこか洒脱なタッチで語ってくるのがルヴェルのすごいところだ。
他にも、乞食が偶然の誤解で一瞬だけ金持ちになってしまう話や、浮気中の人妻が麻酔中にうっかり名前を口走ってしまう話など、ちょっとしたきっかけで倫理や理性がどこかへ吹き飛ぶ瞬間を、抜群のタイミングで切り取ってくる。
しかも怖いのは、それらの動機が意外と理解できてしまうことだ。ほんの少しの好奇心、見栄、勘違い、焦り。我々にも心当たりのある感情が、ひとつずつ地雷を踏んでいく。気がつけば、ページの向こうでは誰かが破滅している。
ルヴェルの文章は極端にあっさりしてる。でも、そのぶん結末の衝撃が倍増する。読んでいて「そこで終わるのか!」と手が止まる。長々と説明しない潔さが、この作家の最大の武器なのだと思う。
「短くてイヤな話が読みたいんだけど」なんてリクエストされたら、迷わずこの本をすすめる。読んだあと、気まずそうな顔になるか、やたら笑うか、どっちに転ぶかはその人次第。
でも、その反応を見たくなるくらいには、この作品には中毒性がある。
ルヴェルが描くのは、私たちのすぐ隣にある異常の匂い。
そのことに、ページの向こうで気づかされるのだ。
15.ポストと蛇と、名もなき奇蹟── A.E.コッパード『郵便局と蛇』
奇妙な味というジャンルを語るとき、どうしても忘れがたい名前がある。
A.E.コッパード。
この作家の作品に触れたとき、「怖くないのに、なぜか胸の奥がぞわぞわする」という、説明のつかない感触が残る。
彼の短編集『郵便局と蛇』には、そんな体験がぎっしり詰まっている。
日常の風景の裏側にある、よろしくないもの
コッパードは、1920年代〜30年代の英国で活躍した遅咲きの短篇作家だ。デビューは遅く、師と仰ぐ作家もなく、文壇の流行とは距離を置いた。
その結果、彼の作風はジャンルをまたぎ、ユーモア、幻想、怪奇、田園叙景が混ざり合い、まさに「つかみどころがない」ものとなった。
たとえば表題作『郵便局と蛇』では、田舎町の郵便局を訪れた「ぼく」が、局長から奇妙な話を聞くだけ、という実にシンプルな筋立てだ。だが、その中に潜むのは、神話的な謎の存在、そして世界がどこかで終わりかけているかもしれないという感覚。日常が、すこしだけ現実から浮いている。そんな違和感が染みてくる名作だ。
他にも、『若く美しい柳』では、電信柱と柳の木の愛情という、荒唐無稽なのにやたら哀しい物語が描かれる。なんの冗談かと思いきや、読後には不思議な切なさが残る。こうした寓意的な手法も、コッパードの得意技だ。
彼の文章はどれも美しい。けれど、その美しさはどこか儚く、不穏だ。心地よいリズムのなかに、いつ崩れてもおかしくない緊張が潜んでいる。どこかで「よろしくないもの」が待ち構えている気配。こうした構造が、まさに詩的怪談としての魅力を持っている。
ホラーでもない、SFでもない、純文学とも言いきれない。それでも読めば読むほど、この作家にしか描けない風景が、たしかに存在している。
A.E.コッパードは、そんな境界に棲む語り手として、いま改めて読み返されるべき作家だと思う。
そして『郵便局と蛇』は、その入口としてふさわしい一冊である。
なぜなら、そこには世界の外れから届いた、宛先不明の物語が詰まっているのだから。
16.世界が終わらないという絶望、あるいは希望── ケイト・アトキンソン『世界が終わるわけではなく』
タイトルを見てほっとしたなら、それはもう罠にかかっている。
ケイト・アトキンソンの短編集『世界が終わるわけではなく』は、言ってみれば「終わらない世界で、壊れていく内面」を淡々と描いた物語集だ。
つまり、地球は明日も回るけれど、あなたの心は今日限りかもしれない……そんな予感に満ちた12の物語が並んでいる。
舞台は基本的に現代の英国。しかし、その日常の中に、ぽっかりと非現実が混ざり込んでくる。たとえば、巨大化する猫。ドッペルゲンガーとの二重生活。時空の歪み。
だが、これらの不思議は、あくまで比喩や皮膚感覚として機能していて、「これはファンタジーです」とは一切名乗らない。気がつくと、登場人物たちは現実と非現実の裂け目に立たされ、そのまま立ち尽くすしかなくなっている。
ささいなことが、全部伏線
アトキンソンの真骨頂は、「このくらいのこと、誰でも経験あるよね?」という顔をして、微笑みながら壊してくるところにある。
登場人物たちは基本的に普通の人だ。買い物をして、仕事に悩み、過去を後悔している。けれどふとした瞬間に、それって本当に普通か?という違和感が立ち上がる。たとえば、姉妹の微妙な関係性が、実は人生を大きく狂わせていたり、何気ない台詞の裏に10年前のトラウマが潜んでいたり。
この本は純文学と見せかけて、かなりミステリ的な構造をしている。すべての短編が連作のようにつながっていて、再読するたびに「この人ここにもいたのか」と気づかされる仕掛けもある。
サスペンスというより伏線文学というべきか。アトキンソンは、事件を起こさずに謎を残す達人である。
この短編集の読後感は、どこか不思議な心地よさがある。救われたのか絶望したのか、はっきりとはわからない。でも確かに言えるのは、「世界が終わらない」という事実には、安心と同じくらい絶望も詰まっているということだ。
生きてる限り何かは続いていく。よくも悪くも。
アトキンソンの短篇は、その続いていくもののなかにある、見落とされがちな奇跡と崩壊を、そっと差し出してくる。
17.日常が軋む音を聞け── ミック・ジャクソン『10の奇妙な物語』
奇妙な話といえば、化け物だの呪いだのを思い浮かべる人もいるだろう。
でも、ミック・ジャクソンの奇妙さはもっと日常寄りで、もっと嫌らしい。気づいたときには足元に染み込んでいるタイプのやつだ。
この本に登場するのは、ほんの少しだけ現実からズレた人たちである。海辺で溺死体を保存しようとするピアース姉妹。壊れた蝶の羽を修理する少年。洞窟に隠者を雇う一家。
字面だけ見るとトンデモ話だが、読み進むうちに「いや、これ普通にありえるのでは?」と錯覚してしまう。そこがジャクソンの怖いところだ。
不気味さは、奇人ではなく社会のほうに潜んでいる
この短編集の面白さは、変なことをしているのが登場人物だけではない、という点にある。むしろ奇妙なのは、彼らを取り巻く社会のほうだ。
『隠者求む』で洞窟に隠者を住まさせる富裕層のセンスは、笑えるようで笑えない。これは階級社会の奇妙な悪習であり、人間を所有物として扱う感覚をそのまま突きつけてくる。
『蝶の修理屋』や『骨集めの娘』も、表面的には偏執的な子どもたちの物語だが、背景には壊れた世界の穴を塞ぎたいという焦りがある。彼らの執着は異常に見えるが、そこには社会との折り合いがつかなくなった者の必死さが滲んでいる。
ジャクソンはこうした人間の歪みを、淡々とした文体で描く。お涙ちょうだいも盛り上げもない。けれど、それが逆に効いてくる。ひとつひとつの奇行が、妙にリアルな重みを持ち始めるのだ。
そして気づくと、作品全体から漂ってくるのは孤独と所有の影だ。誰かを留めたい。何かを抱えていたい。しかし、その気持ちは少し間違えると、他者を壊す方向へ転がっていく。ピアース姉妹の行動はまさにその象徴であり、恐ろしくも切ない。
どの話も突飛に見えて、実はやけにリアルだ。だからこそ、この本を読み終えたときに残るのは、変な夢を見たような感覚ではなく、「今のこの部屋がなんだか落ち着かない」という現実の方だったりする。
つまり、怖いのは物語ではなく、いま私たちが暮らしているこの世界そのもの。
そう気づいたとき、ジャクソンの狙い通り、あなたの中にも奇妙な物語が芽を出すのだ。
18.それは美食か、狂気か── スタンリイ・エリン『特別料理』
誰にでも、「人生で一度は食べてみたいもの」があると思う。
高級レストランの隠しメニュー、口コミでしか伝わらない裏メニュー、あるいは、門外不出の家族のレシピ。
それがもし、「人には言えない食材」でできていたら? という恐ろしい発想を、これ以上なく洗練された手つきで提供してくれるのが、スタンリイ・エリンの傑作『特別料理』である。
格式の裏にある、閉ざされた味覚の地獄
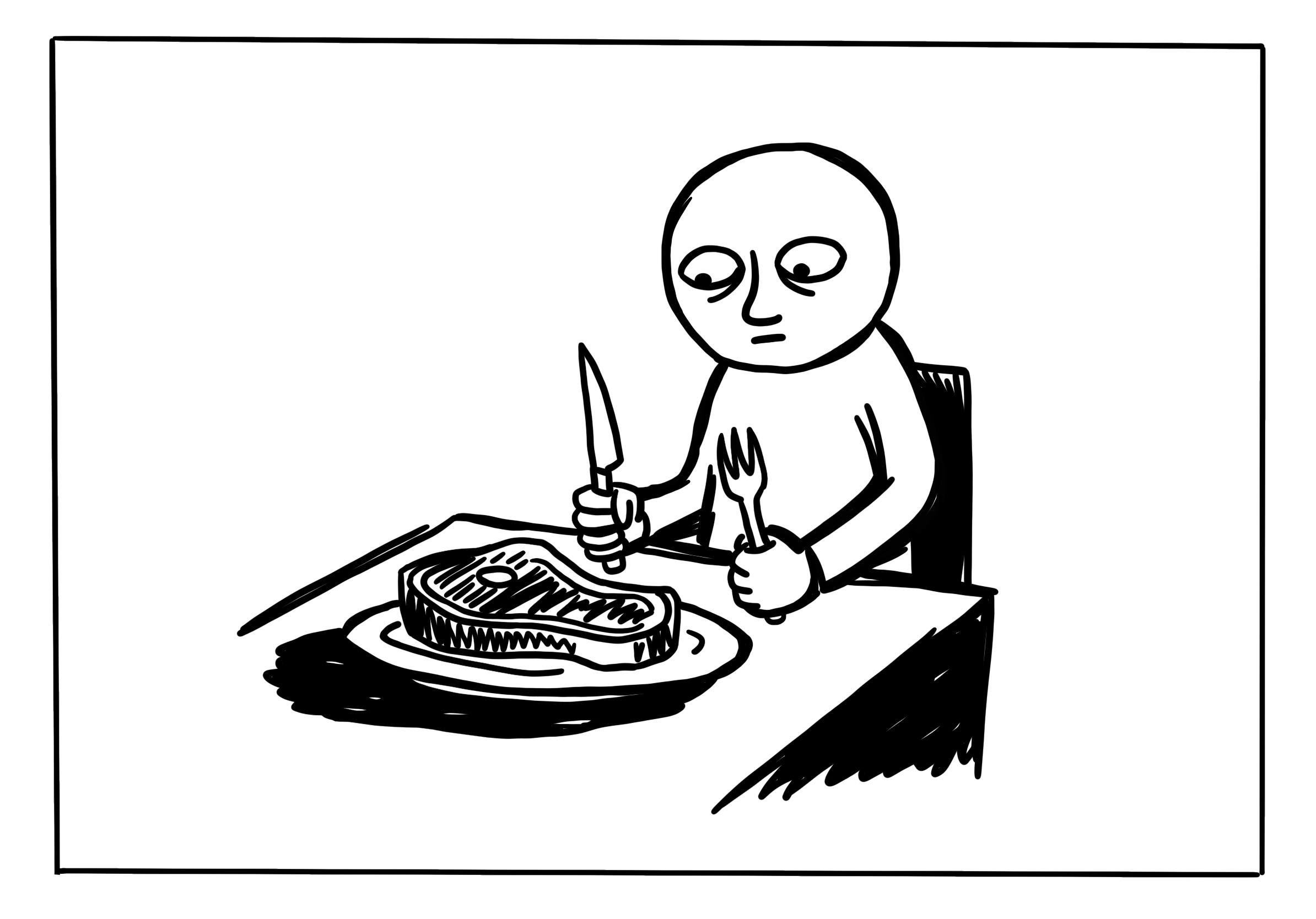
物語の舞台は、都市の片隅にひっそりと佇む会員制の名店スビローズ。ここは、常連客しか入れず、料理もコースのみ、何よりその「特別料理」は誰もが熱狂する究極の一皿とされている。
ただし、その正体は秘中の秘。主人公の青年は、この特別な店に魅了されるあまり、「あの料理」の秘密に迫ろうとする。その結果が、何を意味するのかも知らずに。
本作の凄みは、「特別料理」の正体を、ほとんど説明らしい説明なしに読者に悟らせてしまう巧さにある。語りはあくまで穏やか。陰惨な描写は避けられている。にもかかわらず、真相に辿り着いた瞬間、背筋が凍る。
「あっ」と思ったときにはもう遅い。じめじめした恐怖ではなく、最後の1ページで突然ひっくり返される、いわば落とし穴型の恐怖である。
しかもその恐怖が、どこかユーモラスですらあるのが厄介だ。あの上品な常連たちが、まるで秘密結社のようにその一皿を崇めているのが、恐ろしくて可笑しい。そしてなにより、本当にその料理が美味しそうに思えてしまうのが恐ろしい。
エリンはここで、美食、儀式、権威、そして排他的な共同体が孕む危うさを冷徹に描いている。この短編は、ちょっとした秘密の共有が、いかに簡単に倫理のグラウンドラインを越えさせるかを教えてくれる見本市だ。
しかもその境界は、決して明確な一線などではなく、香ばしくソテーされた香りのように曖昧で、誘惑的に漂ってくる。
この短編を読んだあとは、「美食」という言葉の裏に、薄く鋭いナイフが潜んでいるように感じてしまう。
誰が何を食べているのか、そしてそれが本当に食べていいものなのか。
エリンはそんな残酷な疑念を、銀のフォークで優雅に突き刺してくる。
19.「わたし」は本当に「わたし」なのか── ブライアン・エヴンソン『遁走状態』
恐怖とは、何かが襲ってくるところから始まる。そう思っていた時期が、私にもあった。
でもブライアン・エヴンソンの短編集『遁走状態』に触れると、認識が崩れる。というか、そもそも認識そのものが敵なのだ。
この本に収められた19編は、幽霊も怪物も出てこない。だがページをめくるたび、「これは現実なんだろうか?」「いま語っている私は本当に存在しているのか?」という疑念が広がっていく。
世界が壊れてるのか、自分が壊れてるのか
表題作『遁走状態』では、記憶と言語がぐずぐずと溶けていく。語り手は追跡者でありながら、いつの間にか対象と同一化し、アイデンティティの境界が曖昧になっていく。
その語りには説得力がある。だが同時に、あらゆる一文が不穏なのだ。信用してはいけない、と頭では思う。でも、他に頼れるものがない。
『マダー・タング』では、舌が勝手に言葉を紡ぎ出す。自分の言語が、自分を裏切る。こうなると、言葉とは武器ではなくウイルスだ。ベケット的な絶望と、バロウズ的な暴走が共存する、強烈な身体ホラーでもある。
エヴンソンが描く恐怖は、何かが襲ってくる類ではない。もっと根深くて、内側からくるやつだ。自分の体、自分の言葉、自分の記憶。それらがある日突然、自分のものじゃなくなる。
「これって自分が思ってるだけで、世界は全然別のふうに動いているのでは?」みたいな、世界との接続エラーみたいな感覚が全編に漂っている。
しかもこの人、文章がやけに淡々としている。だからこそ、その「おかしさ」が際立つ。壊れかけた現実を、まるでそれが当たり前かのように語るので、読んでいる側の頭がおかしくなってくる。まるで現実がゆっくりと悪夢にすり替わっていく感じだ。読んでいて息が詰まるのに、なぜか目が離せない。
いわゆる奇妙な味や不条理小説に慣れているつもりでも、この本は効く。なんなら、効きすぎて読み終わったあとしばらく放心してしまう。
なぜなら、ここで描かれている「遁走」は、ある意味、誰にでも起こりうるからだ。
自分が何者か、なぜここにいるのか、その答えを持たないまま、ただ逃げるしかない人の姿。
それは、どこかで現代社会に生きる私たちの姿そのものでもある。
結局、この短編集で描かれているのは、自分という単位の脆さだ。自分を構成していると思っていた「記憶」「言語」「感覚」がどれも揺らいでいく。しかもそれは、爆発的にではなく、ゆるやかに起こるのだ。
最終的には、「おそらくこうだったんじゃないか?」という希望的観測だけが、物語をつなぎとめる。だが、そのつなぎ方すら信じられない。
だからこそ、この作品集は恐ろしい。
正体不明のなにかが襲ってくるのではなく、理解できるはずの世界が、なめらかに理解不能へとすり替わっていく。
そう、怖いのはこの世界そのものではなく、世界を見ているはずの自分なのだ。
20.架空の劇場、実在する迷宮── フェリぺ・アルファウ『ロコス亭』
小説の中でキャラが勝手に動き出す。
そんな冗談のような設定を、冗談じゃなく本気で突き詰めたのがフェリペ・アルファウの『ロコス亭』だ。
1936年という時代にこんなメタな構造をやってのけていたなんて、ちょっと信じがたい。
舞台はスペイン・トレドの片隅にある「ロコス亭」。ここに集うのは、作者に物語として採用されるのを待っている人々だ。
つまり、彼らはまだキャラクターになりきれていない、登場前の登場人物たち。ただの酔狂かと思いきや、ページが進むにつれてこの狂気は加速していく。
ここは物語の待合室、あるいは反乱の発火点
ひとつの話で死んだ人物が、別の話ではぬけぬけと再登場。しかも別の役柄で。作者が「こいつは前に退場したはずなんだけど……」と弁解するも、キャラクターたちは完全に無視して勝手に話を進めていく。
アイデンティティを持たない男、指紋に支配される一族、金持ちの乞食……といったエピソードはどれもユーモラスなのに、じっくりと実存の根本を突いてくる。自分は誰か? 他人に認識されなければ、存在していないのと同じでは? というテーマが、脱線ギャグのふりをして刺さってくる。
この小説に、いわゆる筋はない。というか、あってもキャラたちが壊す。構成は連作短編集のようでいて、実際は迷宮的に絡み合っている。
気を抜いていると、前の話でチラッと出た人物が裏で別の事件を動かしていたことが判明したりする。いやもう、油断も隙もない。
そんな混沌の中でも軸となっているのが、「物語の中で生きるとはどういうことか」という視点だ。登場人物は、作者に操られる存在であることに自覚的で、ときには逆らい、脱走し、挙げ句の果てには物語の外へ逃げようとする。
こうなってくると、もはや書かれていることが虚構なのかどうかすら怪しくなってくる。
カルヴィーノやポール・オースターが登場する何十年も前に、すでにアルファウはこうしたポストモダン的仕掛けを作品化していた。再評価されたのは1980年代。むしろ遅すぎた再発見と言っていい。
というか、1936年にこれを書いてしまったという事実が、いちばんのフィクションなんじゃないだろうか。
あまりにも早く、あまりにも自由すぎた。
後の時代が「実験小説」と呼ぶことになる遊び場を、アルファウはすでに荒らし尽くしていた。
『ロコス亭』は、その痕跡そのものだ。
21.願いは叶う。ただし、代償を支払う覚悟があるなら── ジョン・コリア『炎のなかの絵』
奇妙な短編を愛する人にとって、ジョン・コリアの名前は避けて通れない。
毒のあるユーモア、完璧な構成、そして上品な語り。
こう書くと「怖くないのか?」と思われるかもしれないが、逆である。
コリアの物語が恐ろしいのは、誰もがマナーを守ったまま人を地獄へ突き落とすからだ。
ユーモアで飾った人間の業と欲望
コリアの短編は、どれも異様なまでに完成度が高い。冒頭の一文から結末の一行まで、まったく隙がないのだ。
『夢判断』では、高層ビルを一階ずつ落下する夢を見る男が登場するが、この奇抜な設定が最後に〈ある部屋〉と接続した瞬間、すべてが収束する快感に襲われる。
『雨の土曜日』は、とんでもなく冷酷な家族ドラマである。娘が殺人を犯した。父親は彼女を守るため、無関係な男を犠牲にする計画を立てる。口調は終始穏やか。でもその論理の背後にあるものは、社会性を完全に脱ぎ捨てた血縁という本能だ。悪魔なんか出てこない。でも、これほど悪魔的な人はいない。
一方、『クリスマスに帰る』では、逆にちょっとした運命のいたずらが恐ろしいまでの皮肉を引き起こす。完璧に殺害を隠し通したと思っていた夫が、最後に妻の用意した計画によって崩される。その仕掛けは、道徳的でも教訓的でもない。むしろユーモアのある遊びに近く、ぞっとするほどスタイリッシュだ。
そして表題作『炎のなかの絵』では、悪魔との契約がテーマになるが、コリアの描く悪魔はやたらと理知的で、交渉の手続きも完璧。怖いのは、願いが叶うことの代償ではなく、それが当然の流れとして描かれる点にある。
そう、この世界はすでに地獄なのだ。
全体を通して見えてくるのは、人間の欲望やエゴが上品な衣装を着て堂々と振る舞っている姿だ。だからこそ、この作品群は「ブラックユーモア」と呼ばれる。笑っていいのか迷う。けれど、笑ってしまう。そのあとで、背中がすうっと冷える。
魔法、悪魔、奇跡……そうした超常的要素が出てくることもあるが、それはファンタジーの飾りではない。むしろそれらは、人の願望に対する物差しだ。
「こうなったらいいのに」と、私たちが思うその瞬間、コリアは言う。
「じゃあ、叶えてあげよう。ただし、それで本当に幸せになれるかどうかは、別の話だけどね」と。
22.その壁をこえて、手にしたものは── マルセル・エイメ『壁抜け男』
パリの街角に、壁を抜ける男がいた。なんて話、普通なら笑い飛ばして終わりだ。
だがマルセル・エイメの手にかかると、その突飛な設定はむしろリアルさを帯びてくる。
『壁抜け男』は、奇妙でユーモラスで、それでいて哲学的な味わいを残す、まさに奇妙な味の傑作である。
主人公デュティユルは、書類仕事に追われる地味な役人。彼がある日突然「壁を通り抜ける能力」に目覚めるところから物語は始まる。
最初は頭痛の副作用かと心配し、真面目に医者にかかるほど慎重な男だが、じきにその力を使って世の中の煩わしさをショートカットしはじめる。
通勤の混雑も、恋の障害も、上司の権威も、全部壁ごとすり抜けてしまえ。そうして彼は、ついには銀行まで抜けてしまう。
壁の向こうにあったのは、本当の自由か?
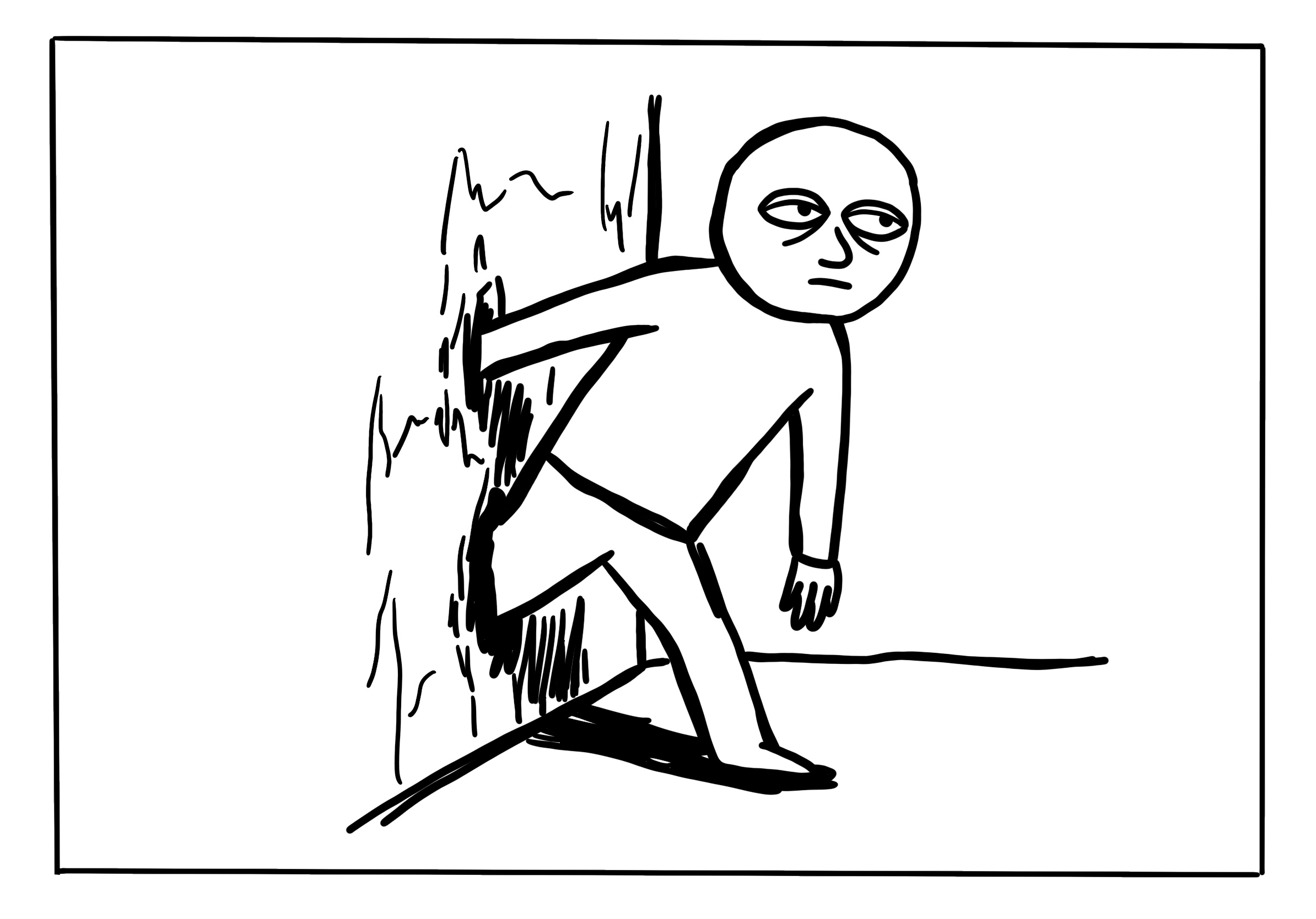
この設定だけでもかなりワクワクするのだが、エイメはここで「能力もの」のお約束をひっくり返してくる。
力を得たデュティユールがヒーローになるわけでも、世界を変えるわけでもない。彼が向かった先は、ほんの少し便利で、ほんの少しスリリングな日常。それがだんだん逸脱し、やがて破滅の気配をまとい始める。
エイメの語り口は、驚くほど淡々としている。壁を抜ける瞬間も、変に派手な演出はなく、まるで「ちょっと散歩してきた」くらいのノリで描かれる。だがその乾いたユーモアの背後にあるのは、自由と逸脱の本質に対するテーマだ。
どんなに壁をすり抜けても、人間は自分の欲望や愛や孤独までは超えられない。むしろ自由を得たことで、それらに直面させられてしまう。
それにしても、パリの風景とこの話の相性の良さよ。日常と幻想の接点が、モンマルトルの石畳やアパートの階段室にしっくりはまる。おそらくこれは、エイメの優しさと意地悪さが、どちらも街の匂いを知っているからだろう。
もしあなたが今、仕事に疲れ、誰かに腹を立て、人生の壁をすり抜けてしまいたいと思っているなら、この本を読むといい。
ただし気をつけてほしい。
壁を抜けるのは簡単でも、戻ってこれるかどうかは、別の話だ。
23.一発で世界をひっくり返す── フレドリック・ブラウン『さあ、気ちがいになりなさい』
短編小説の本当の怖さを知りたいなら、フレドリック・ブラウンに手を出すべきだ。
長編じゃない。どれだけページ数を重ねた作品よりも、彼のたった数行のオチのほうが、よっぽど精神にくる。
この『さあ、気ちがいになりなさい』は、そんな破壊力だけで構成された、まさに短編集の核爆弾だ。
内容はいたってシンプル。極端に短いショートショートが40編以上、次から次へと詰め込まれている。それぞれにオチがあり、ジャンルもバラバラ。SF、ミステリ、ブラックユーモア、そして不条理。
ところが、読んでいくうちに気づくのだ。どれもこれも、最初は普通の話として進んでいるのに、ラストの一文で常識が180度ひっくり返される。そしてそれが毎回、キレッキレに決まるから恐ろしい。
気ちがいになりなさい、なんてタイトルを見て身構えたくなった人もいると思う。だが、その警戒心は大正解だ。
フレドリック・ブラウンは、私たちが想像する不条理の数歩先を、鼻歌まじりで歩いていく作家である。
気ちがいになれ、と囁く短編たちの魔力
収録作のバリエーションは広い。精神病院を舞台に狂気の裏側を覗かせる表題作『さあ、気ちがいになりなさい』。二人の男が駅の待合室で、互いを殺人犯と疑い合う心理戦『ぶっそうなやつら』。
地球上で最後に残った男が、ただひとり部屋のなかにすわっていたら、ドアにノックの音が……という、わずか2行から始まる伝説の掌編『ノック』。どれも構造はシンプルだが、転がし方が尋常ではない。
特に表題作は、読み進めるにつれてこちら側とあちら側の境界が崩れていく感覚に陥る。監視されているかもしれない。自分以外は演技をしているのかもしれない。そうした考えを、ブラウンは淡々と、しかし逃げ場のない論理で突きつけてくる。パラノイアの論理がこんなにも説得力を持って迫ってくる作品は、他に思い当たらない。
一方、『ぶっそうなやつら』では、殺人鬼がどちらなのか最後までわからないまま、緊張がぐいぐい引き伸ばされる。頭の中だけで繰り広げられる推理と恐怖。そのオチには、思わずニヤリとするしかない。このブラックな反転こそ、星新一が影響を受けたというのも納得の芸風である。
ただ、ブラウンの魅力は笑える狂気だけではない。『みどりの星へ』では、荒れ果てた惑星に取り残された男の孤独と希望、そしてラストに訪れるひどく切ない真実が描かれる。
救われたのか、それとも全てが皮肉だったのか。その「にやりと笑ってから殴る」ような感触が、ブラウンの真骨頂だ。
何もかもお見通しのような冷めた目線と、幼い子どもみたいな悪戯心が同居している。そのくせ、ラストでちょっと胸を締め付けてくる。その塩梅が絶妙なのである。
短編ミステリ、SF、ホラー、ショートショート。どれが好きな人にも刺さるし、逆にどれも当てはまらない何かを求めている人には、なおさら危険で魅力的な一冊だ。
いや、ブラウンの場合、ひとつの棚に収まってもらっては困る。棚ごと壊して、「どうぞこちらへ」と誘ってくるタイプの作家なのだから。
最後の一文でひっくり返されたい?
それも、繰り返し、容赦なく?
だったらこの本を読めばいい。
でも、くれぐれも、気ちがいになる覚悟だけはしておいてほしい。
24.非論理の爆弾が降ってくる── エトガル・ケレット『突然ノックの音が』
エトガル・ケレットの作品を読んでいると、日常というものがいかに脆いかを思い知らされる。
鍵をかけたつもりの世界に、唐突にノックの音が響き、それだけで現実がぐらつく。
気づけば、こちら側とあちら側の区別はとっくに曖昧になっているみたいに。
短くて、奇妙で、切実な38の物語
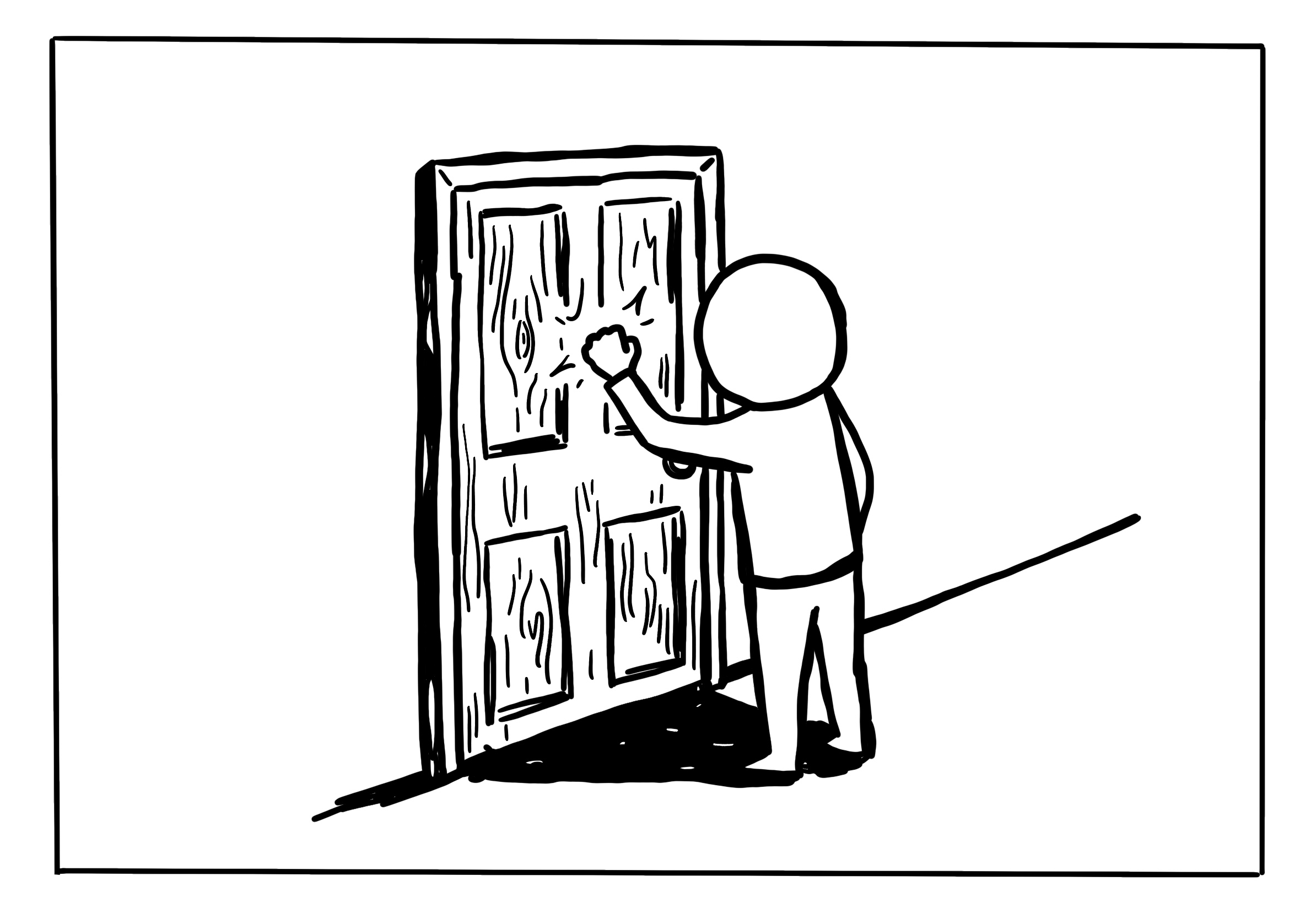
『突然ノックの音が』は、わずか数ページで世界を裏返すような38の短編から成る本だ。
冒頭の表題作では、作家の家に銃を持った男たちが押し入り、「今の俺たちの話を書け」と要求してくる。フィクションと現実の境界が揺さぶられ、語ること自体が暴力に対するサバイバルになる。
他にも、『嘘の国』では過去に吐いた嘘が空間として存在していたり、『金魚』では三つの願いをくれる金魚と暮らす男が、最後のひとつをどうしても使えずにいる。切なさとユーモアが同居し、どこか既視感すらあるのは、これらの物語が荒唐無稽でありながら人間の本質を突いているからだ。
ケレットの物語には、幽霊も怪物も出てこない。しかし、変わった人たちがいる。そしてその変人たちは、隣人かもしれないし、もしかすると自分自身かもしれない。社会的孤立や言葉の不全、愛されたいのにうまく伝わらないもどかしさが、奇妙なアイデアを通して立ち上がってくる。
面白いのは、ケレットがどんな突拍子もない設定でも、決して奇をてらった印象にならないことだ。むしろ、荒唐無稽であればあるほど、そこに潜む寂しさや切実さが濃くなる。この絶妙なバランス感覚こそが、ケレットの真骨頂である。
この本に収められた物語たちは、まるで突然のノックのように、こちらの日常の奥に亀裂を入れてくる。
笑ったと思ったら、いつの間にか心がひりついている。
それこそが、ケレットの魔法なのだ。
25.熊の不在が語るもの── ミック・ジャクソン『こうしてイギリスから熊がいなくなりました』
ミック・ジャクソンの書く奇妙な話は、笑って済ませるにはどこか引っかかるものがある。
この『こうしてイギリスから熊がいなくなりました』もそうだ。表向きは、かつてイギリスに存在したという様々な熊たちの記録を並べた奇書のように見える。
だが、その語り口の奥には、社会への皮肉、歴史への懐疑、そして人間という存在の滑稽さが詰まっている。
架空の熊たちが暴いていく、人間社会のかたち
この本に登場する熊たちは、どれも想像の産物……のはずなのだが、不思議な説得力がある。
「罪食い熊」は、死者の罪を代わりに背負わされた存在。「下水熊」は、ヴィクトリア朝ロンドンで下水道の清掃に駆り出されたという労働者のメタファー。中には「市民熊」のように、人間社会に同化しようとしたものもいる。
ひとつひとつの物語は、まるで民俗誌か自然誌のように淡々と語られる。けれど、そこに滲むのは、野生が人間社会によって都合よく扱われ、捻じ曲げられ、やがて消されていく過程への哀しみと皮肉だ。
熊というモチーフを借りて語られているのは、実のところ、人間社会の他者へのまなざしそのものではないかと思えてくる。
面白いのは、史実とフィクションの境界線がほとんど見えなくなっているところだ。たとえば「ベア・ベイティング(熊いじめ)」は本当に存在した残虐な娯楽だし、熊がサーカスで芸をしていたというのも実際の話。
なのに下水熊や罪食い熊といった荒唐無稽な存在が、それらと同じトーンで描かれていると、だんだん「あり得たかもしれない」と思えてくる。これは、嘘を本物に見せるための精密な語りの技術でもある。
この本が語っているのは、熊の話に見せかけた「私たちが何を失ってきたか」の物語だ。それは野生かもしれないし、共感かもしれない。あるいは、違う存在と一緒にこの世界を生きていく想像力そのものなのかもしれない。
真面目にふざけている、あるいはふざけながら核心を突いてくる。これはただの冗談ではない。正しく語られた作り話が、こんなにも説得力を持つんだということを、見せつけてくる。
熊がいたかどうかよりも、「そういう歴史があったと信じてしまうこと」こそが、この作品のいちばんの恐怖であり、魅力でもあるのだ。
26.奇想がほじくる、家族と孤独のかたち── 地球の中心までトンネルを掘る
ケヴィン・ウィルソンの短編集『地球の中心までトンネルを掘る』は、一見ふざけたようなタイトルを冠しながら、内容はまっすぐに胸を撃ってくる。
登場するのは、どこか壊れたようで、それでも懸命に何かと繋がろうとする人々。そこには現実からの逃走もあるが、同時に必死の抵抗もある。
奇抜な設定の奥にある、切実な感情
たとえば表題作。大学卒業後の若者たちが、裏庭から本気で地球の中心に向かってトンネルを掘り出す。現実逃避と言えばそれまでだが、実際には「外に出られない」「どこにも行きたくない」という気持ちが、まるごと地中に沈んでいる。
就職もせず、誰にも迷惑をかけず、それでも世界に不適合なまま時間が進んでいくあの感覚。ウィルソンはそれを、ふざけているようで絶妙に真面目なトーンで描く。
『替え玉』は、亡くなった祖母の代役を派遣するという、嘘みたいなビジネスに就いた女性の話。偽りの関係に本物の愛情が混ざり始めたとき、彼女は「自分が誰なのか」を見失っていく。他人にとっての理想の存在を演じ続けるうちに、自分の内側は空っぽになってしまう。その怖さと、どこか心地よい諦めが同居している。
そして『発火点』。両親が自然発火で死んだ青年が、自分もいつか燃え尽きるのではと怯えるなか生きていく話。くだらないように見えて、なんだか泣けてくる。
ウィルソンの物語は、派手な仕掛けに見えて、実は登場人物たちの居場所のなさを丁寧に描いている。誰もが少しずつ壊れていて、誰かとつながろうとして、でもそれがうまくいかない。その不器用さはとても現代的で、あちこちで息苦しくなっているこの社会の空気を、やわらかく吸い取ってくれているようでもある。
ラストの一行にすべてが詰まっている、というタイプの短編ではない。むしろゆっくりと、気づけば自分も地面の奥深くに連れていかれているような読後感だ。
それは暗くもあるけれど、決して絶望的ではない。なぜならこの本の登場人物たちは、少なくとも自分の逃げ場を見つけているからだ。
そしてそれは、いまこの世界で生きるために必要な、とても大切な技術なのかもしれない。
笑える。でも泣ける。ケヴィン・ウィルソンの短編には、そんな感情の混ざり合いがある。
奇妙な味とは本来、後味の悪さをともなう読書体験を指すけれど、この本に関して言えば、少し違う。
どこか遠くに消えてしまった心の居場所を、奇想というスコップで必死に掘り起こす。
そんな優しさと愚直さが、このトンネルの底にはちゃんと詰まっているのだ。
それって、けっこう泣けることなんじゃないだろうか。
27.消えていく人たちの文学── イム・ソヌ『光っていません』
これは、「光ることができなかった人たち」の物語だ。
夢も希望も、自分らしさも、努力すらも、いつの間にか削れていく。誰からも見えなくなっていく。そんな感覚に覚えがある人なら、きっとこの本に心を掴まれるはずだ。
イム・ソヌの短編集『光っていません』は、一見地味だが、ものすごく鋭い。派手な事件も、わかりやすい奇跡もない。だが読んでいるうちに、世界の輪郭がいつの間にかゆがんでいく。
この奇妙な読後感は、ホラーでもファンタジーでもない。むしろ、現実の中でひそやかに進行する透明化の物語なのだ。
社会という透明な地獄
この作品集に収められた短編には、はっきりとした怪異やホラーはない。でも、じつはそれがいちばん怖い。
舞台は現代の韓国。過労と孤独がデフォルトになったような都市社会の中で、登場人物たちはごく自然に存在感を失っていく。
たとえば、事故で眠り続ける恋人を見舞う〈私〉の前に、なぜか自分の幽霊が現れる(『幽霊の心で』)。あるいは、人間をクラゲに変える変異体が出現し、仕事を失った私はクラゲ志願者のサポート業に就く(『光っていません』)。
また、演劇で芽が出ず代役業をしていた〈あたし〉が、ある男の冬眠の準備に付き合わされる話もある(『冬眠する男』)。どれも現実のすぐ隣にあるようで、どこか壊れている。
この短編集に出てくるのは、どこにでもいる普通の人たちだ。就職に失敗した若者、家庭と仕事の板挟みに疲れた女性。誰もが頑張っているし、まっとうに生きている。でも、気づけば少しずつ社会の輪から外れていく。声は届かず、姿も見えなくなり、やがて「光っていない」と言われてしまう。
この「光を失う」という表現がうまい。単に目立たないとか暗いとかいう意味じゃない。「存在していないことにされる」ことの比喩なのだ。
社会という巨大なシステムが、光っていない人を照らさず、記録にも残さない。それって、じつはものすごく怖いことだと思う。
誰もが発光することを求められるこの社会で、光れなかった人たちの姿を、イム・ソヌは確かな手つきで描いている。
そして気がつくと、こう思っている自分がいる。
「自分はいま、ちゃんと見えているだろうか?」と。
28.仮面の下に宿るのは── ヒュー・ウォルポール『銀の仮面』
恐怖とは、必ずしも血や悲鳴から生まれるわけではない。
相手があくまで礼儀正しく、敬意すら払ってくる存在であった場合、人はその脅威に気づくのが遅れる。
ヒュー・ウォルポールの短編『銀の仮面』は、そんな暴力なき侵略の恐ろしさを描いた、まぎれもない怪作である。
善意につけ込む寄生者たち
主人公は、ロンドンに住む中年女性ソニア。財産もあり、品もあり、孤独を静かに受け入れて暮らしている。その彼女が、ある日道端で倒れていた青年を助けるところから物語は始まる。
青年は美術に詳しく、言葉遣いも丁寧で、最初はソニアの生活に癒しの風を運んでくる。しかし、彼の家族と称する不気味な一団が屋敷にやってきたあたりから空気は変わっていく。
彼らは暴力を振るうわけでもなく、むしろ感謝と敬意をもってソニアに接する。だがそのぶん、断る理由を見つけにくい。なにせ、可哀想な人々を追い出す冷たい人間にはなりたくないのだ。この「断れない」構造が地獄の入口である。
ウォルポールが描くのは、完全に理詰めの恐怖だ。悪人らしい行動を取らず、あくまで居るだけの他人たちがソニアの屋敷を占領し、ついには彼女自身の尊厳と存在意義をも奪っていく。仮面のように美しい青年の顔。断るべきタイミングを逃した善意。それらが物語の奥深くで腐敗していく。
『銀の仮面』は、いわゆる怪奇を期待して読むと、拍子抜けするかもしれない。だがこれは、読後にゆっくり効いてくるタイプの毒だ。江戸川乱歩は、これを「奇妙な味」の傑作として推した。読んでいるうちに、自分の生活にもこんな侵入を許してしまいそうな、得体の知れない不安が忍び寄る。
もはや誰が悪いとも言い切れない構造の中で、ソニアだけが徐々に物扱いされていく。この皮肉と静けさこそが、この本の怖さの源だ。
ホラーでもサスペンスでもない。でも、読んでしまった以上、どこかに自分の居場所が侵されるような感覚が残る。それがこの作品の本質であり、「奇妙な味」というジャンルの真骨頂でもある。
恐怖とは、忘れたつもりの何かが、何十年も経ってからドアをノックしてくることだ。
その音が聞こえてきた時、人は笑って仮面を被り続けられるだろうか。
29.短さゆえの残酷さ── 阿刀田高『ナポレオン狂』
人というのは、あっけないほど簡単に狂うものだ。
しかも、妙に理屈が通っているからやっかいである。
阿刀田高の短編集『ナポレオン狂』は、そんな人間の滑稽で恐ろしい一面を、短い物語の中にぎゅっと詰め込んだブラックユーモアの宝庫だ。
普通が崩れる音を楽しむ
表題作『ナポレオン狂』では、ナポレオンの遺品を集め続ける男が登場する。彼はあくまで静かで上品な人物だが、その執着は常軌を逸している。
しかも彼の前に現れるのは、「自分こそナポレオンの生まれ変わりだ」と信じて疑わない別の狂人。この時点で、まともなのはもう読んでいるこっちだけかもしれない。二人のナポレオンを愛しすぎた男たちの邂逅は、やがてブラックでシュールな悲劇へと転がり落ちていく。あくまで淡々と、だが確実に。
この作品集の魅力は、誰にでも起こりうるような歪みが、常識を侵食していくところにある。『来訪者』では、家庭に突如現れる過去の影が日常を塗り替えていく。
思い当たる節はないのに、相手の語る話はどこかリアルで、不安が少しずつ形になってくる。それでも、誰も取り乱さず、声を荒らげず、ただ粛々とズレた現実が展開していくのが、阿刀田流の恐怖演出である。
阿刀田高の短編は、どれも長くはない。文体もシンプルで癖がなく、読み進めるのはとても軽やかだ。しかしラスト一行で、それまでの全てがひっくり返る。
その爽快さ、あるいは絶望感。読んでしまったあとで「うわ」と声を漏らすあの瞬間のために、全編が組み立てられているといってもいい。
これは、サキの毒や、ブラウンの論理的ツイストに通じるものがあるけれど、阿刀田高はそこに日本人らしい感情の襞を持ち込んでいる。人間関係の微妙な距離、建前と本音、名誉や見栄、劣等感。そうした小さな心の揺らぎが、狂気へとつながっていく。
ラストのページをめくるたびに、「うまいな」と唸らされる。奇抜さではなく構成で驚かせてくるあたりが、ミステリ好きにも刺さるポイントだ。
この短編集には、派手な恐怖や残虐な描写はほとんどない。でも、本を閉じたあとも、ずっと心に引っかかる何かが残る。
それこそが、奇妙な味の真骨頂。
そして阿刀田高は、それを完璧なまでに操る名手である。
30.それは何かおかしい話ではなく、なぜか胸に残る話だった── 五木寛之の『奇妙な味の物語』
「奇妙な味」と言われて思い浮かぶのは、どんでん返しの衝撃、皮肉の効いたオチ、笑えるのに背筋が寒くなる話。そんな作品たちだろう。
サキ、ロアルド・ダール、フレドリック・ブラウン……いずれも短い話の中で見事に読者を裏切る名手たちである。でも、五木寛之の『奇妙な味の物語』は、そうしたラインとは少し毛色が違う。
もっとしっとりとしていて、言葉を選ぶなら、「深い」のだ。
しかし、五木寛之が自ら編んだこの『奇妙な味の物語』は、そうした技術的な話法とは違う地点に立っている。
この短編集に収められた作品たちは、どれも不思議な読後感を持っている。けれどそれは、決して派手なトリックや意地悪なオチのせいではない。むしろ逆だ。
五木寛之は、何気ない旅の途中や異国の片隅に、不可解な出来事や奇妙な偶然をすっと差し込んでくる。しかもその描写には湿度があり、まるで運命に出会ったような、でも説明のつかない気持ちのざらつきが残るのだ。
トリックではなく、無常が味を決める
阿刀田高が論理的な驚きで魅せるなら、五木は「なぜかそうなるほかなかった気がする」という納得で押し切るタイプだ。たとえば、ある出会いが不思議な偶然に彩られていても、五木作品の世界では「人生ってそういうものだから」と飲み込まれていく。
五木寛之にとって奇妙な味とは、日常のふとしたズレから現れる不可解さではなく、「人生というものの、どうしようもなさ」の一断面なのだ。
異国の港町や、夜行列車、古びた喫茶店。そうした場面設定とともに、人間の欲望や後悔が浮かび上がる。言葉は少ないが、確実に胸の奥に何かを残していく。
この短編集を読むと、「なるほど、奇妙な味とはこういうものだったか」と考え直したくなる。怖くないのに忘れられない。驚きがないのに強く残る。そんな感触を、五木寛之は見事に物語へと進化させている。
テクニックではなく、生きてきた人間の重さで語られる奇妙な話たち。
読んでいて、自分の人生にも、あの奇妙な味はすでに滲んでいたのかもしれない。そんな気すらしてくるのだ。
おわりに 恐怖でも感動でもない、名前のつかない後味

こうして見てくると、「奇妙な味」というジャンルは、実にバリエーション豊かで、しかも一筋縄ではいかない。
どの作品も短編という器の中で、限られた語数だからこそできる、余白の演出に心血を注いでいる。
明確な説明を拒み、わざと結末を曖昧にする。正義も悪も提示せず、読み手にモヤモヤだけを投げてくる。そういうタイプの作品群である。
でも、それこそが「奇妙な味」の最大の魅力だ。
すべてを説明されて納得した気になるよりも、何かが引っかかったまま数日間ずっと考え続けてしまう。そんな読書体験のほうが、よほど脳に残る。
怖くもないのに怖い、オチがあるようでない、笑っていいのか不快になるべきか判然としない……そういう作品たちが、まるで小骨のように心のどこかに刺さってくる。
この記事でご紹介した30作品は、20世紀以降の短編小説が到達したひとつの頂点であると同時に、「普通の小説では物足りない」と感じ始めた人にとっての、最高に刺激的な通過儀礼でもある。
もしあなたがこの不穏なジャンルに足を踏み入れてしまったなら、もう戻れないかもしれない。
でも、それも悪くないと思う。
だって、このおかしな世界の味を覚えてしまったら、ふつうの話じゃ物足りなくなるのだから。
さて、次はどんな短編があなたの現実をぐらつかせるだろうか。
「奇妙な味」の世界は、今日も笑いながらあなたの常識を裏切る準備をしている。