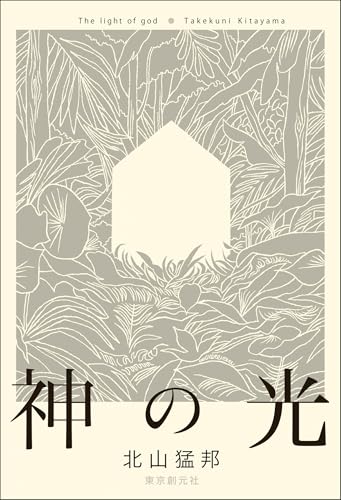北山猛邦の短編集『神の光』を読み始めてすぐ、これは単なる不可能犯罪ではないことをすぐに思い知らされる。
タイトルが象徴するように、本書の全編を貫いているのは「神の視点」と「人間の限界」、そして「建造物の消失」という極めて抽象的で、かつ物理的な主題だ。
普通なら死体が消えるとか、犯人が消えるというのが不可能犯罪だろう。だがこの本は違う。「建物」が、あるいは「街」が、現実からまるごと消えてしまう。
そんなスケールの謎を本格ミステリとして成立させるには、もはや技巧だけでは足りない。読者の認識そのものを揺さぶる論理の演出が必要になる。
そしてその挑戦に、北山猛邦は見事に成功している。しかも5つの短編すべてにおいて、舞台も作風も違うのに、すべてが「建物の消失」という一点で見事に接続しているのだ。
スケールでかすぎて笑ってしまうけど、ちゃんと論理で殴ってくるのがほんとに恐ろしい。
戦場、砂漠、夢。5つの消失をたどる旅

この短編集は、はっきり言ってトンデモない。なぜなら、どの話も「普通はそんなもの消えないだろ」という建物が、本当に消えてしまうからだ。
そして、それぞれの作品は見事にトーンも構成も違う。簡単に5作品の魅力をまとめてみる。
『一九四一年のモーゼル』
舞台は第二次大戦下、狙撃兵が遠くからスコープで監視していた「館」が消える。いきなりロマンのかたまりみたいな導入だが、読み進めるうちに背筋が寒くなる。
これは物理トリックというより、戦争という極限状況の中で、「見たものが真実とは限らない」という本格ミステリの根源的恐怖を体験させてくれる。スコープ越しの視野という制限付きの視界がトリックの鍵になるあたり、本当に上手い。
戦場というリアルな緊張感が、ミステリと融合しているからこそ、謎も嘘もリアルに見えてくる。私たちもまた、狙撃兵と同じようにフレームの外を見落としてしまうのだ。
さらに言えば、この作品では「誰が嘘をついているか」ではなく、「自分の目がいかに騙されるか」という点が主題になっている。つまり、トリックの肝は情報の欠落そのもの。私もまた一緒に銃を構えていたのだと気づくと、少し怖くなった。
『神の光』
表題作。これは、砂漠に現れた幻の街が翌日まるごと消えていたという、壮大なスケールの話。だが北山猛邦はここで「巨大な仕掛けは、小さな積み重ねから成る」という原則を守り抜く。
奇跡のように思える街の消失も、読み終えるころには「あ、そういうことか」と膝を打たされる。神話的なタイトルにふさわしい、知性の奇跡。
情報の断片が全部つながった瞬間の爽快感は、まさに「ミステリ読んでてよかった」と思える瞬間だ。派手なのに地に足がついている。あのバランス感覚はすごい。
しかもこの話、街の消失という派手な謎を扱いながら、視点はあくまで一人の男のささやかな行動にフォーカスしている。その地味さの中にある必然が、全体をリアルにしているのだ。これぞ北山流スケールマジック。
『未完成月光 Unfinished Moonshine』
これはもう、ポーへのラブレターである。
ある日、友人から手渡されたのは、「エドガー・アラン・ポーが遺した未完の原稿」だという代物。その中には、とある家が消えたという話が描かれていて、その謎を現代の人物が解くというメタ構造のミステリ。
幻想的で哀愁のある筆致と、ガッツリ論理で決着をつける終盤の快感が両立していて、「知的で美しい」という表現がこれほど似合う話は珍しい。
あと、雰囲気が抜群にいい。古い紙の匂いまでしてきそうな空気感。トリックよりも空気で酔える作品でもある。
注目すべきは、「未完成」というキーワードがそのまま構造にも効いているところだ。語られなかった部分、断絶された時間、それが逆に想像力をかき立てる。完成しないからこそ残る余白。その余白の中に、きっちりとした解答が隠れている。
『藤色の鶴』
ひとつのトリックで、異なる時代に起きた三つの消失事件を解き明かすという、完全に実験的な構成。これがすごく面白い。
ミステリの「トリック」という概念そのものを文体と構造で遊んでいる感じで、視点がどんどんズラされていく。読後は、短編という形式の可能性を改めて思い知る。
どれも別の話なのに、どこか響き合っているのが不思議だ。そして同じトリックでここまで印象を変えられるのか、という驚き。
しかも、読む側が「どこで見破るか」を試されているような、対話的な仕掛けになっている。三つの話を読み終えてから、もう一度最初に戻って読み直したくなる構成。気づけば、物語ではなく仕掛けの演出を味わっている自分がいる。
『シンクロニシティ・セレナーデ』
現実と夢の世界で、同時に小屋が消えるという、もはや幻想と現実の境界線が溶け合うような話。北山猛邦が「内面の建築」というテーマに踏み込み始めた記念碑的な一編だと思う。
もはや消えるのは建物ではなく、記憶とか心になっていく。全体を締めくくるにふさわしい、静かなラストだった。
夢の中とリンクしてるトリックというだけでワクワクするが、読後はふわっとした感情が残る。トリックと詩情の混ぜ方がうますぎた。
これまでの作品がガチガチの物理トリックで攻めてきた分、この一編が心理・幻想寄りなのがいいアクセントになっている。ある意味で「読む人の感受性」によって印象がまるで変わるのではないか。個人的には、この方向性でもっと書いてほしいなと思った。
北山猛邦というジャンル職人

「物理の北山」という異名があるように、北山猛邦はトリックメーカーとして有名だ。でも、ここまで読んでわかるのは、彼が単なるトリック職人じゃないということだ。
彼の書く物語には、いつも建物がある。それも、どこか現実離れした幻想的な建築物。それが「アリス・ミラー城」だったり「時計館」だったり「密室船」だったり、今回は「街」や「小屋」だったりする。彼の小説における建築は、単なる舞台装置ではない。むしろ、記憶や制度、秩序、そして人間の認識そのものを象徴している。
それが消える、というのはつまり、「私たちが信じていた現実が崩れる」ということに他ならない。
しかも彼は、その崩壊を物理トリックで説明してしまう。超常じゃない。論理で証明する。これがスゴい。ロジックと幻想が両立している。読んでいて「自分の推理が試されている……」と嬉しくなる。
あと、忘れてはならないのが彼の余韻の演出のうまさだ。オチが決まっても、すぐには手を離さない。登場人物たちの静かな感情が、ふわっと立ち上がってきて、それが「読後感」になる。これが、単なる論理パズル以上の何かを生んでいる。
構造も、技巧も、感情も全部乗せ。でもそれをうるさく見せない。あくまで丁寧に、誠実に組み上げてくるところに作家の品格を感じる。
消える建物と、消えない読後感
『神の光』は、いわゆる「トリック集」ではない。もちろん、トリックはある。しかも極上のやつが。でも、それだけじゃない。
論理と幻想。記憶と物質。現実と夢。あらゆる相反する概念が、見事に同居している。ページをめくるごとに広がっていくのは、緻密に設計された構造美であり、どこか胸を打つ哀しみでもある。
「最も頑丈な建物が、最も儚く消える」
まさにそのテーマを、小説という建築物で体現しているような作品集だ。
これは推理小説でありながら、詩のようでもある。そして知的な祝祭でありながら、しみじみと胸に残る哀しみの記録でもある。
テンポも派手さも控えめで、考えることを前提にしている。でも、「読んだ」と誇りたくなる一冊だし、「これは面白い」と誰かに語りたくなる本でもある。
そして語っているうちに、きっとまた最初から読みたくなる。再読のたびに、見え方が変わってくる。そんな読み直す喜びに満ちた、不思議な中毒性がある。
だからこそ言いたい。
ミステリ好きなら、ぜひこの建築に迷い込んでみてほしい。
そこには、知性と幻想の両方が、ちゃんとあなたを待っている。