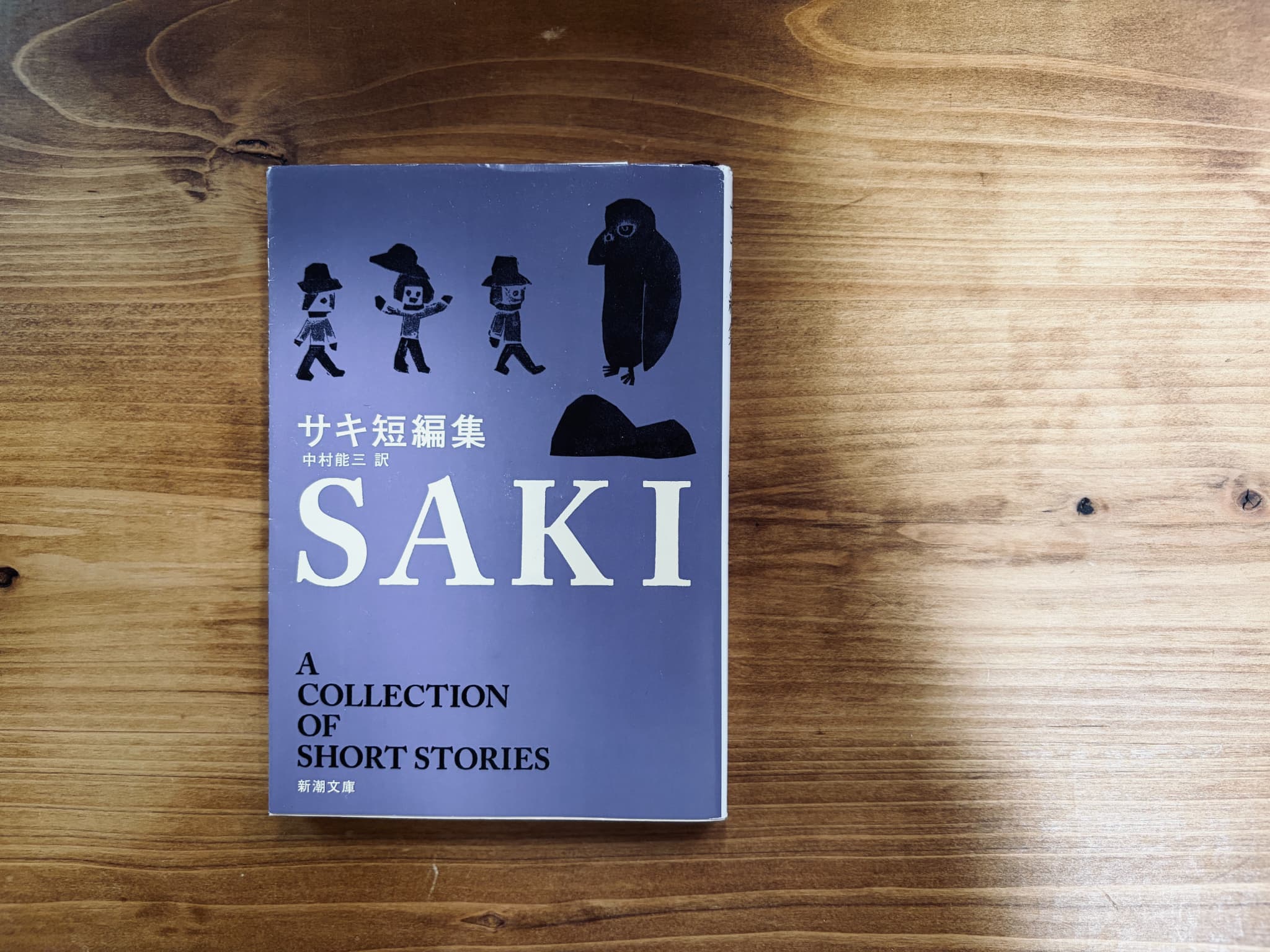「誰だ! せっかく殺したクソジジイを生き返らせたのは!?」
――これがこの物語の第一声であり、読者への宣戦布告でもある。
こんなにパンチの効いた書き出し、なかなかない。
五条紀夫の『町内会死者蘇生事件』は、タイトルも設定もぶっ飛んでる。そのくせ、読めば読むほどページをめくる手が止まらなくなるから困る。これはもう、“バカっぽいけど本気”というジャンルの傑作だ。
物語の舞台は、どこにでもありそうな田舎町・信津(しなづ)町。そこに暮らす幼なじみ三人組――健康、昇太、由佳里が主人公。
彼らが立ち上がった理由は一つ。町を牛耳る暴君・権造を抹殺することだった。権造は住職にして町内会長、なのに人間的には最悪で、セクハラ・パワハラ・モラハラをフルコンプ。まさに“老害”の化身だ。
ある夜、三人は完璧な計画のもと、酒に酔わせた権造を風呂場で沈める。
これで終わるはずだった――のに、翌朝ラジオ体操に、元気な声で「いっちにー、さんしー」と号令をかける権造が出現。殺したはずのジジイがピンピンしてる地獄。
ここから一気に物語の構造が裏返る。従来のミステリーが「誰が殺したのか(whodunit)」を問うのに対し、本作は「誰が生き返らせたのか(Who-revived-it)」という前代未聞の謎を提示する。
つまり、犯人が“蘇生犯”を探すというミステリーの大逆転が始まるのだ。
死者はよみがえる、でも24時間前にリセットされる地獄

この町には“魂玉”と呼ばれるアイテムを使った、古代から伝わる秘術が存在していて、死者を蘇らせることができる。ただし条件付きで、肉体も記憶も「死の24時間前」に戻ってしまう。
つまり、自分が殺されたことすら覚えていない。殺された本人が「え、何のこと?」とけろっとしてるわけで、殺人犯からすれば、まさに悪夢だ。
これがややこしくて、面白い。自分も一緒になって「この人は何を覚えていて、誰が知らないのか?」と混乱する。蘇った人は無自覚だし、殺した側は焦りまくりだし、蘇生した人と殺した人がまた普通に顔を合わせるのも地獄だ。しかも、魂玉は誰でも使えるわけではなく、町内の旧家にだけ継承されているという設定が、田舎の排他性を皮肉るようで味がある。
この“死が軽い世界”が何度も繰り返されるせいで、読者としても「誰が本当に死んだのか」「この死は意味があるのか」と考えさせられる。そしてそのたびにリセットされる物語は、まるでセーブとロードを繰り返すゲームのようで、読み進めるごとに“蘇生”という仕組み自体が怖くなってくる。
最初はただの設定かと思っていた蘇生のルールが、やがて「記憶を失わせる=過去の罪をなかったことにする」装置として機能しはじめる。この町は、都合の悪いことを“魂玉”でリセットしてしまう世界。なんて気味が悪いんだと思う一方で、「現実にもこういうことってあるよな」とゾクリとした。
ゆるいのにズシンとくる、五条流“哀愁のミステリー”
一貫して物語はユーモラスで、テンポも軽い。セリフも小ネタも絶妙で、何度もニヤリとした。でも、後半にかけて、だんだんと笑えなくなっていく。ある場面では、ふざけたような展開が、ふとした描写ひとつで切なさに変わる瞬間がある。
著者や編集者が語る「チルい雰囲気の中のペーソス」という言葉が、ほんとうにぴったりだ。ポンポン死んだり蘇ったりする軽快な展開に身を任せていたら、いつのまにか胸の奥に“重さ”がたまっている。
ラストに近づくにつれて、ある登場人物の選択が“取り返しのつかない何か”として読者に襲いかかってくる。まさか、こんなバカミスっぽい話で泣かされるとは。
一人ひとりのキャラが抱えている傷や諦め、そして彼らの「もう一歩だけ前に進みたい」という小さな勇気が、じわじわと染み込んでくる。笑いの裏に、しっかりと血が通ってる。その“熱”が、本書の大きな魅力だ。
「エンタメの極北」と呼びたい、一冊の熱量
五条紀夫という作家、完全に只者じゃない。『クローズドサスペンスヘブン』も良かったが、本作でその“ぶっ飛び力”と“構成力”が一気に開花した印象だ。何がすごいって、トンチキな設定でここまで感動させる技量。まさに「バカを本気でやる」凄み。
殺人犯が探偵になる作品はたまにあるけれど、「蘇生犯を追う」という設定はなかなかお目にかかれない。その異常さを、本気のエンタメとして成立させている時点で、これはもう奇跡のような小説だ。
読み終わって思ったのは、「誰かと語り合いたい本だ」ということ。設定の話、ラストの余韻、キャラの魅力――語りたいことが多すぎる。
何度でも読み返したくなるし、「このトリック、もう一回確認したい!」という衝動が止まらない。
『町内会死者蘇生事件』は、ミステリ好きならずとも、物語の“変さ”に惹かれた人に強く勧めたい一冊だ。ジャンルとしては「特殊設定ミステリ」や「バカミス」に括られがちだけれど、そこに収まらない熱と余韻がある。
軽やかに笑わせながら、最後にはズシンと胸に残る。読み終えた今も、登場人物たちの表情や台詞が頭の中に残っている。
もし「ミステリーって最近ちょっと型にはまりすぎてるな」と感じている人がいたら、ぜひこの作品を手に取ってほしい。
バカっぽく見えて、ちゃんと泣けて、そしてちゃんと面白い。こんな作品、そうそうない。