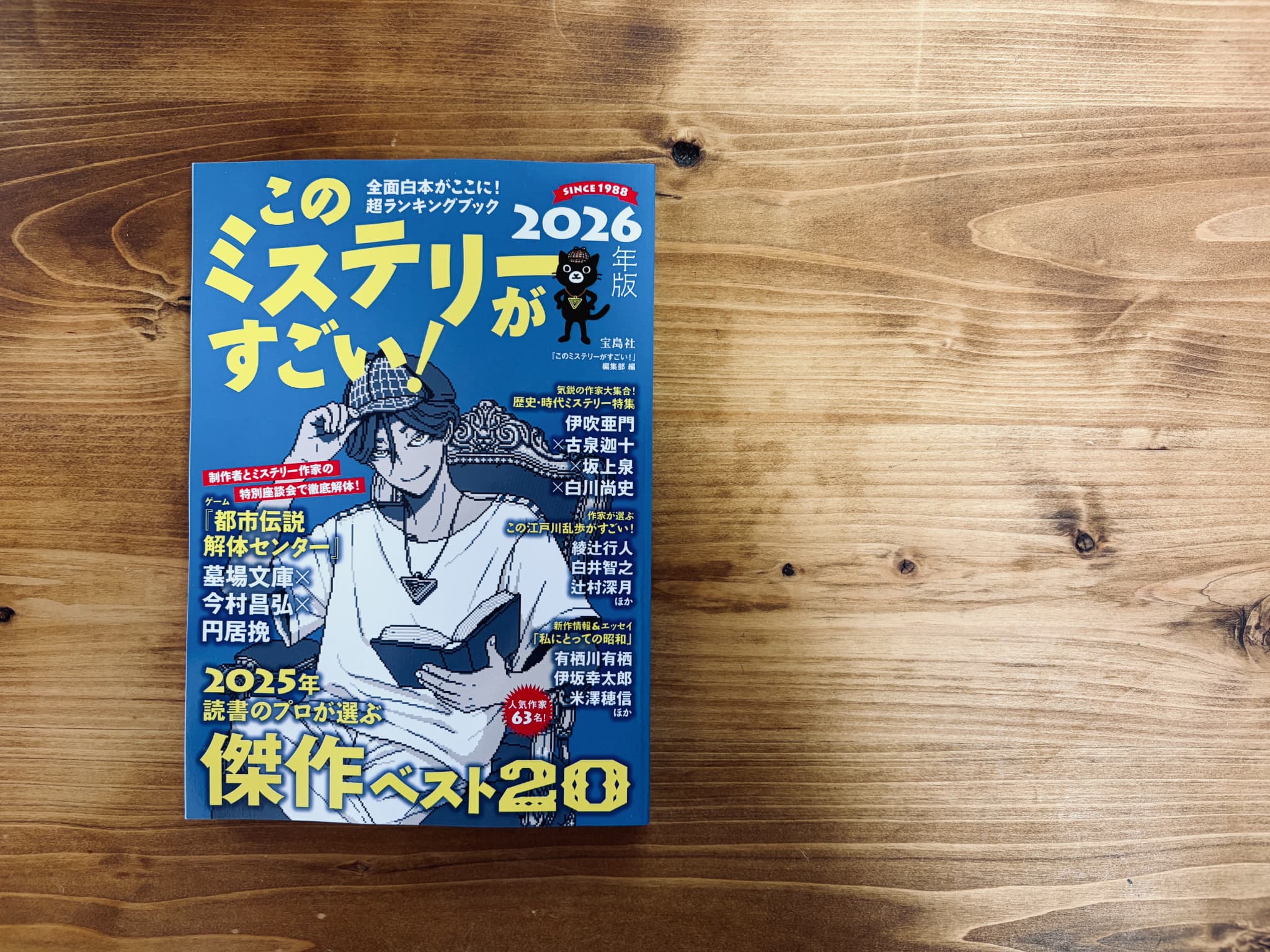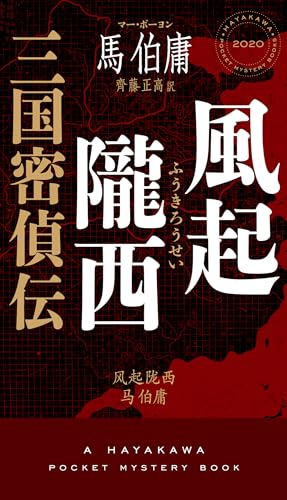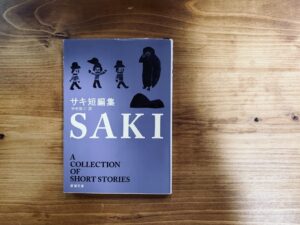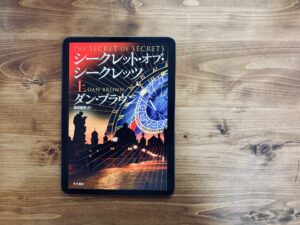「海外ミステリが熱い」
なんてセリフ、もう何度目か分からないけれど、今年のこのミスに選ばれた作品群は、ほんとうに凄かった。
アンソニー・ホロヴィッツ、M・W・クレイヴン、ホリー・ジャクソン、スチュアート・タートン、フランシス・ビーディング、S・A・コスビー、ピーター・スワンソン……豪華すぎるだろ!!!
翻訳新刊の棚に並ぶ作品が、どれもジャケ買い不可避、あらすじだけで即積み確定。そのレベルで、質もジャンルも振り幅がすごかった。
王道のフーダニット、陰鬱なノワール、社会の闇をえぐる重厚サスペンス、さらには歴史とスパイのハイブリッド系まで、今年も読めてよかったと心から言える一冊に何度も出会えた。
というわけで、『2026年版 海外編 このミステリーがすごい!』ベスト20作品をご紹介していく。
読み終わったあと、ふと本棚を見て「今年のミステリもすごかったな」とつぶやきたくなるような作品ばかりである。

【2026年版 海外編】このミステリーがすごい! 1位〜10位
| 1位 | リチャード・デミング『私立探偵マニー・ムーン』 | 義足の私立探偵ムーンが密室殺人や冤罪事件に挑む。タフガイの行動力と本格ロジックが融合し、戦後アメリカの荒さと哀愁が漂うハードボイルド短編集。 |
| 2位 | アンソニー・ホロヴィッツ『マーブル館殺人事件』 | 編集者スーザンが作中作の手稿に隠された告発を読み解く。小説世界と現実が重なり合う、メタ構造ミステリの到達点。 |
| 3位 | フリーダ・マクファデン『ハウスメイド』 | 家政婦ミリーが富豪一家の屋敷で狂気と支配の罠に落ちる。視点反転が連続し、被害者と加害者の構図が激しく揺らぐスリラー。 |
| 4位 | ウィリアム・ショー『罪の水際』 | 荒涼とした海岸で発生した殺人が投資詐欺や移民問題と結びつく。傷を負った刑事が、土地の闇と向き合う社会派警察小説。 |
| 5位 | ホリー・ジャクソン『夜明けまでに誰かが』 | RVに閉じ込められた6人が狙撃犯に脅され互いの秘密を暴く。極限の密室と心理崩壊が連鎖する、緊迫の一夜サスペンス。 |
| 6位 | M・W・クレイヴン『デスチェアの殺人』 | ポー刑事が過去の事件を語る形で進む異色構成。カルトの暗号、謎のワード〈慈悲の椅子〉、内通者の影が絡むシリーズ最大級の危機。 |
| 7位 | フランシス・ビーディング『イーストレップス連続殺人』 | 1930年代の保養地で無差別殺人が続発。誤認逮捕の悲劇を越え、真犯人の狂気が暴かれる。黄金期にして先駆的なサイコスリラー。 |
| 8位 | ジャニス・ハレット『アルパートンの天使たち』 | メールや議事録だけで教団事件の真相を追う資料ミステリ。証言の矛盾が積み上がり、取材者自身も危険に巻き込まれていく。 |
| 9位 | スチュアート・タートン『世界の終わりの最後の殺人』 | 世界滅亡前の孤島で起きた殺人。記憶が消された住民全員が容疑者となり、犯人特定が人類の命運を左右するSF本格の極北。 |
| 10位 | ジェイク・ラマー『ヴァイパーズ・ドリーム』 | 才能なき男がハーレムの麻薬取引で成り上がり、ジャズ黄金期と裏社会を生き抜く。音楽史と犯罪が交錯する哀切なノワール。 |
1位. リチャード・デミング『私立探偵マニー・ムーン』
義足の探偵が蹴破るのは、心の扉と密室の論理
古き良きハードボイルドには、いわゆる「タフガイ」が欠かせない。
でも、それがただの暴力担当で終わらないとしたらどうだろう?
義足の探偵マニー・ムーンは、まさにそんな存在だ。
銃を撃たなくても、殴り飛ばさなくても、ハードボイルドは成立する。そんな幻想をマニー・ムーンはあっさり蹴飛ばした。
片足を失った私立探偵。頑固で皮肉屋、だけどどこかユーモラスで、自らを「ミスター・ムーン」と呼ばせる一風変わった男。彼の存在そのものが、この作品集の芯を成している。
リチャード・デミングの『私立探偵マニー・ムーン』は、1948年から1951年にかけて発表された全7話を収めた中短編集であり、つい最近になってようやく日本語で読めるようになった。いわば戦後アメリカの影がぎゅっと詰まった、忘れられた名品だ。
戦後アメリカの影をまとった、もう一人のタフガイ
パルプ・マガジン全盛期の空気をまといながらも、その中身は驚くほど現代的。本格ミステリの構造美とハードボイルドの熱量が、違和感なく一つの器に収まっている。
最も印象的なのは、『フアレスのナイフ』という密室ミステリだ。ムーンは弁護士に呼ばれて事務所を訪れるが、待たされ続けた末に応接室へ踏み込むと、そこにはすでに死体。部屋は内側から閉ざされ、当然、外には誰もいない。
でも、ムーンはその場の状況、死体の姿勢、家具の配置、そして少しの人間観察から一気に推理を進める。暴力を振るうでもなく、目を剥くわけでもない。密室を崩すのは、拳ではなく論理だ。この話一本で、「この探偵は只者じゃない」と納得させられる。
だが、ムーンが単なる名探偵で終わらないのは、その行動の根底に「肉体」があるからだ。義足という欠損は決して弱点ではなく、むしろ武器になる。格闘中に外して投げつけたり、隠し武器を仕込んでいたりと、戦場の経験を生かした工夫が満載。
しかも、それがギャグとしても機能しているのも好きだ。例えば、警察署で署長のタバコを勝手に盗むシーンなど、ハードボイルドというより、もはやコメディの領域に足を踏み入れている。
中でもユニークなのが、ある女性容疑者の冤罪を晴らすエピソードだ。美容室の予約というちょっとした違和感から真相を突き止めていくのだからたまらない。しかもその推理が、最終的には銃撃戦へとなだれ込むという展開。安易な知的探偵ものでは終わらせず、必ず最後に火薬の匂いを残していく。
そして何より面白いのが、マニー・ムーンというキャラクターそのものの「ずらし」だ。彼は年金でのんびり暮らせたはずの元兵士でありながら、食いしん坊で服好き、美女には弱く、無茶な依頼にもつい首を突っ込む。
ハードボイルドにありがちな「ストイックな孤高の男」ではなく、なんとも人間臭い。けれど、その分、銃撃や推理に本気でぶつかる姿が際立つ。彼はただのキャラではなく、戦争と身体、そしてユーモアを背負った語るに値する過去を持った探偵なのだ。
戦後の都市風景、くすんだ喫煙室、酒と血と汗の混じる空気。そんな背景のなか、義足の探偵がゆっくりと歩き、鋭く考え、時にドスを効かせて真相に迫っていく。
拳と論理、その両方を持った男がいたことを、今だからこそ改めて知っておきたい。
『私立探偵マニー・ムーン』は、その証人である。
2位. アンソニー・ホロヴィッツ『マーブル館殺人事件』
小説の中に埋め込まれた殺意を掘り起こせ
『カササギ殺人事件』や『ヨルガオ殺人事件』でおなじみ、編集者スーザン・ライランドが主人公の作中作ミステリが、ここにきて新たな地平を見せた。
『マーブル館殺人事件』は、作家アラン・コンウェイの死後、そのシリーズを引き継ぐ若手作家エリオットが「祖母の死は殺人だった。その犯人を新作小説の中に隠した」と言い残して殺されるという、とんでもない導入から始まる。
そのエリオットが遺した原稿『ピュント最後の事件』は、1950年代のイギリスを舞台にしたクラシックな屋敷ミステリだ。
毒殺された意地悪な老婦人、遺産を巡る親族たち、探偵アティカス・ピュントの推理と、雰囲気はまるでアガサ・クリスティ。
でもこの小説は、ただのフィクションでは終わらない。
作中作と現実が交錯する、編集者スーザンの最終章
スーザンは編集者の視点でその原稿を読み解きながら、現実に起きた殺人の真相に迫っていく。作中作の台詞や設定、登場人物の名前にさえ意味がある。
これは、作家ホロヴィッツが仕掛けた「小説という形式そのものが証拠になる」メタ・ミステリの極みだ。編集者という読むプロが謎を解くという構図が、なんとも痛快でニクい。
しかも、作中では出版業界の裏側──作家の遺産ビジネス、ゴーストライター、ベストセラーの続編製造機としての出版社など──も皮肉たっぷりに描かれる。作家でもあるホロヴィッツが、内部からぶっ刺してくるような辛辣さと笑いのバランスも絶妙で、ただのミステリにとどまらない読み応えがある。
シリーズとしての完成度も高い。スーザンはこれまで、探偵でも作家でもなかった編集者という立ち位置から事件に関わってきたが、今回の彼女は過去作を踏まえたうえで、ひとつの探偵役としての覚悟を見せている。ピュントの推理と並走しながら、自分自身のやり方で謎を解く姿にはグッとくるものがあった。
そして終盤、作中作でのピュントの推理が現実の事件にリンクする瞬間。これがまた鮮やかだ。謎が解けるだけでなく、「これはあれのことだったのか!」と腑に落ちる気持ちよさが後から効いてくる。
『カササギ殺人事件』で仕掛けた作中作トリックを、ここまで洗練させて、しかも三作目でも飽きさせないのは本当にすごい。文字通り、「物語を読むことが命を救う」ような展開まで描いてしまうホロヴィッツの執念に拍手を!
もはやシリーズの完結編と呼んでも差し支えない仕上がりである。
スーザン・ライランドの、これが最後の事件になるのか、それともまだ仕掛けがあるのか──真相は、もちろん本文の中に。
3位. フリーダ・マクファデン『ハウスメイド』
脳外科医が放つ、読む人間監禁装置
最初に言っておくけれど、『ハウスメイド』は文学的な香りを漂わせるタイプのスリラーではない。
繊細な心理描写や文章の美しさを求めるつもりなら、別の棚を探すべきだろう。
でも、寝不足になってでも読み進めてしまうような「ページをめくる爆走感」が欲しいなら、迷わずこのドアを開けていい。
前科あり・無職・住む場所もないミリーに舞い込んだのは、豪邸に住むセレブ家族の住み込み家政婦というあまりに出来すぎた仕事。条件は最高、だけど様子がおかしい。
面接中から漂う不穏さ、雇い主の奥さんの気まぐれすぎる態度、そして部屋の鍵はなぜか外側にだけ付いている。
そんな違和感が積み重なりながらも、ミリーはその家に住み込むことになる。家の中は閉鎖空間で、人物は少人数、部屋はきっちり分断されていて、まるで舞台劇のようなミニマル構成だ。
だがその分、視線や言葉、沈黙の一つひとつが効いてくる。ミステリ好きとしては、この閉じた環境で「何が始まるか」を感じるだけでニヤけてしまう。
鍵がかかるのは、部屋か、それとも感情か
構造は三部構成。特に中盤の視点切り替えには驚かされた。よくある二重構造……と思わせておいて、読み手の把握していた「事実」が根こそぎ転覆されるタイプの展開だ。
一度裏返された物語を、再びどう組み直すかのプロセスが非常に面白い。伏線と再解釈が交錯し、思考が追いつく前に物語は次の局面に進んでいく。
文章は平明で、やや荒削りにすら感じるかもしれない。比喩や心理描写の工夫といった技巧に凝ってはいないが、逆に言えば全ページが「展開」のために存在している。冗長さはゼロ。次から次へと「それアリか?」という展開が押し寄せるが、説得力はある。なぜならこの小説を書いたのは、現役の脳外科医だからだ。
フリーダ・マクファデンという作者は、脳損傷の専門家でもある。脳や記憶、感情の扱いに長けたプロが、サイコロジカルなトリックを仕込む。しかも、これが彼女にとって「ダークすぎてお蔵入りしていた作品」だという。その背景だけでも、作品のトーンと一致するものがある。
出版当時からBookTokなどSNSを中心に爆発的に広がり、全世界で累計何百万部という規模で売れまくったのも頷ける話だ。
細部のリアリティには多少の強引さもある。キャラの行動が雑に見える場面もある。でも、その勢いと展開力で押し切ってしまうあたり、『ハウスメイド』は極めて現代的なエンタメ小説だと思う。
3時間あれば読了できる。短い章、軽い文体、限定空間。そして怒涛のどんでん返し。今の「読むスタイル」にぴたりとハマる設計である。
完璧な小説ではない。でも、完璧じゃないからこそ魅力的なタイプの物語だと思う。
スリルを純粋に楽しみたい時、頭を空っぽにして物語に没入したい時。そんな夜に、うってつけだ。
扉は開かれている。
あとは、自分で鍵をかけて中に入るだけだ。
4位. ウィリアム・ショー『罪の水際』
すべてが流れ着くその岸辺で、罪と孤独が交わる
ミステリを読むという行為には、たいてい「誰が殺した?」とか「どうやって?」という構造的な楽しみがある。
でも、ウィリアム・ショーの『罪の水際』は、それだけでは済まない。ここには、壊れた人間と壊れた場所とが、互いの欠けを埋め合うようにして物語を進めていく感触がある。
舞台はケント州ダンジェネス。原子力発電所が見下ろす、砂利と草と風だけが支配する土地だ。
そこに生きる人々の顔には、どこか現実に押し潰されたような影がある。主人公のアレックスもまた、警官でありながら、被害者でもある存在だ。
壊れたままで進む、警官という生き方
彼女はロンドン警視庁を離れ、この海辺の町でくすぶっている。理由は、トラウマ、不倫、娘との確執……つまり、積み重なった「人としての傷」だ。復職もままならないまま、彼女はふとしたきっかけから、とある事件の匂いを嗅ぎ取ってしまう。
導入部で登場するのは、結婚式に乱入し花嫁に襲い掛かろうとする女。どうやら彼女には、何か重大な過去があるらしい。そこから、ユーニス夫妻の惨殺事件が連鎖する。
現場に残された血文字、地元の名士だったはずの被害者、表向きは静穏な町を覆う「何かがおかしい」雰囲気。こうして複数の事件が重なり合い、見えない線で結びついていく過程は、実に手堅い。
でも、この小説の面白さは、プロットの巧妙さよりも、「なぜ人は壊れるのか」「どこまで堕ちて、どこで踏みとどまるのか」という、個々の登場人物が背負う地層の厚みにある。犯人探しだけで進む話なら、もっと短く、もっと派手に仕上げられていたはずだ。しかし、ショーが描きたいのは、ミステリという形式のなかでしか語れない人間たちの居場所である。
たとえば、投資詐欺にすべてを失った老夫婦。あるいは、国外から来てこの土地で働き、搾取され、名前さえ知られぬまま姿を消す移民たち。そして、警察という組織に所属しながら、心の傷を抱え、マニュアル通りに生きられない者たち。
誰もがどこかで一度はつまずき、そこから戻ってこれずにいる。アレックスもその一人だ。彼女は名探偵ではない。ただ、まだ諦めきれない警官として、事件と向き合っているだけだ。
物語の終盤、アレックスはある選択を迫られる。それは法と人情の間にある、常に揺れ動く正義のグレーゾーンだ。警察官としての矜持と、一人の人間としての感情。そのあいだで彼女が出す答えは、事件の解決以上に、深く胸に残る。
『罪の水際』は、海のような小説だ。表面は穏やかで、しかし底には複雑な流れと暗い渦がある。
人が人として生きていくために何を背負い、何を捨てるのか。
その声に正解はなく、それでも誰かが波打ち際に立っている。
アレックスのように。
誰かのために、あるいは自分のために。
生き残るために。
5位. ホリー・ジャクソン『夜明けまでに誰かが』
逃げ場のない8時間、正義はどこへ消えた?
「クローズド・サークル」という言葉がある。
外の世界から隔絶された空間で事件が起こる、ミステリの定番だ。でも、この作品がすごいのは、その密室が究極に狭いという点にある。
ホリー・ジャクソン『夜明けまでに誰かが』は、キャンピングカーという極小の密室を舞台に、若者たちの関係がひと晩かけて崩壊していく姿を、容赦なく描ききっている。
高校生6人が春休みに出かけたロードトリップ。途中でタイヤが撃たれ、燃料タンクが破壊され、通信手段も失われ、キャンピングカーはそのまま罠の中に取り残される。
そして真夜中、無線越しに語りかけてくるスナイパーの声。
「この中の一人が秘密を隠している。それを明かさなければ、朝までに全員殺す」
ありがちなデスゲームか?と思ったら甘い。犯人は姿を見せず、ただ情報を要求するだけ。誰も殺されないまま、時間だけが進んでいく。
けれど、キャンピングカーの中では何かがどんどん壊れていく。友情、信頼、自己像。そしてその先にある「正しさ」の境界まで。
密室の先にあったのは、正義の崩壊だった
中心人物のレッドは、母親の死を抱えて生きる少女。語り手である彼女の視点は繊細で、時に不安定だが、観察力にかけては鋭い。
そんな彼女と対照的なのが、リーダー格オリヴァーの存在だ。初めは冷静なまとめ役だった彼が、徐々に支配者へと変貌していくプロセスがこの作品のキモになっている。
「正義」を口にしながら、自分だけが助かる道を選び、仲間を犠牲にしようとする。外にいる狙撃者以上に、内部のオリヴァーの存在がグロテスクに見えてくるのは、現実でも似た構図を何度も見てきたからかもしれない。
ホリー・ジャクソンは元々、プロットの緻密さと構成力に定評のある作家だ。『自由研究には向かない殺人』では、伏線回収の鮮やかさと、構成の巧妙さに唸らされた。
この『夜明けまでに誰かが』も、その技巧は健在で、ラストには認識をひっくり返すようなどんでん返しが待っている。
しかも、そのどんでん返しは単に「犯人はこいつだった!」という種類のものではない。むしろ、「今まで見ていた物語の意味そのものが変わる」というレベルのやつだ。
誰が死ぬのか?という単純なミステリ的な面白さはもちろんあるけれど、それ以上に重要なのは、「なぜその人が死んだのか」であり、「誰がその死に手を貸したのか」である。
これはサバイバルゲームではなく、人間の倫理が、集団の中でどれほど脆く崩れるかを描いたドラマだ。誰か一人を吊し上げることの気持ちよさ、その場の空気で誰かを悪に仕立て上げてしまうことの恐ろしさ。
そして、それを止めるためには何が必要だったのか。ラストに待っているのは、ほろ苦く、後味の重い結末だ。
血が飛び散るようなグロさはない。でもこの作品が突きつけてくるのは、もっと現実的な恐怖だ。
誰かが銃を構えていなくても、人は集団の中で簡単に凶器になってしまう。
そんな地獄の一夜が、ここに。
6位. M・W・クレイヴン『デスチェアの殺人』
語ることの重さが、捜査の構造そのものを変える
ミステリというジャンルはいろいろあるけれど、「今、海外ミステリでどれが一番アツい?」と聞かれたら、真っ先に挙げたくなるのがこの〈ワシントン・ポー〉シリーズである。
『デスチェアの殺人』はその第6作。毎回思うのだけど、よくもまあ、これだけの完成度を更新し続けられるものだ。読了後、しばらく呆然とした。これはもう、文学ではなく事件だ。
エンタメとして面白いのはもちろん。けれどそれ以上に、語りの構造や人物造形、舞台の重み、そして何よりあの名バディ、ポーとティリーの存在がシリーズをただの警察小説にとどまらない深さへと引き上げている。
これは、クレイヴン自身が歩んできた人生とキャリアが、作品の地盤になっているからこその説得力だと思う。
暗さと優しさ、ポーとティリーの化学反応
ポーとティリーの関係性は、このシリーズ最大の武器である。組織に馴染めない不器用な男と、天才的な知性を持ちながら社会性に欠ける分析官。
相棒というより、もはや家族に近い。ポーの荒っぽさや陰鬱さも、ティリーがいることで軟着陸できるし、ティリーの突飛な言動も、ポーが拾ってくれる。
本作では、そんな二人の信頼関係に、これまでで一番深い陰が落ちる。ポーは精神的にかなり追い詰められており、序盤からセラピストとの会話という異色の形式で物語が進んでいく。
そう、「なにかあった」ことだけが最初に提示されているのだ。
物語の舞台は、いつものようにイングランド北西部のカンブリア。クレイヴンはこの土地をただの背景にはしない。雨や石造りの家、湿気、風の冷たさまで描写し尽くす。だからこそ、山中の施設、湖底の秘密、焼かれた遺体……そうした描写が重く染みてくる。
事件の発端は、カルト教団のリーダーが「石打ち刑」で処刑されるという、ショッキングなものだ。中世の宗教的刑罰を再現したような手口に、ティリーですら震える。そして、そこから紐解かれていくのは、15年前の未解決事件、謎の言葉「慈悲の椅子」、そして「それに触れた者は死ぬ」という都市伝説のような噂だ。
話が進むにつれ、ポーは身体的にも精神的にも追い詰められていく。彼があの出来事を語り始めたとき、すべてのパズルが一気に形になる。この構成は本当に見事だった。
重い話だ。けれど不思議なことに、ページを閉じたあと、また二人に会いたくなってしまう。それは、このシリーズが「人間」を描いているからだと思う。単なる事件解決ものではなく、生きる痛みや倫理、信頼、希望みたいなものが、しっかり根を張っている。
構造の実験、キャラクターの深化、テーマの重さ。どれをとっても次の一歩に進んでいた。
シリーズがここまで来たことに驚くと同時に、この先に進めるのか?という不安もよぎる。
だが、ポーとティリーなら、きっとその先の闇にも踏み込んでいくはずだ。
7位. フランシス・ビーディング『イーストレップス連続殺人』
死は歩いてやってくる、1931年の予言的スリラー
「黄金時代ミステリ」と聞いて連想するものは、エキセントリックな探偵と優雅な推理劇だろう。でも、1931年に発表されたこの『イーストレップス連続殺人』は、そうした常識を静かに裏切る。
当時としては異例の「名探偵不在」「群像劇形式」「連続殺人」という構成、しかも殺害手段は突如現れてこめかみを一突き。見せ場はひたすら唐突に訪れ、去っていく。つまりこの作品は、時代を半世紀ほど先取りしていたのだ。
物語の舞台は、イギリス・ノーフォーク州の保養地イーストレップス。観光地のイメージにそぐわぬ猟奇的連続殺人が起き、町は報道と噂に飲み込まれていく。
名探偵はいない。あるのは、パニックと狂気の町だけ
犯人像は不明、手口は共通、動機は不明、被害者も無作為。こんな時代に「シリアルキラー」という言葉が使われていれば、間違いなく貼りつけられていたであろう犯行スタイルだ。
現場には推理の余地はあれど、名探偵の登場はない。代わりに描かれるのは、警察、新聞記者、町の人々、それぞれの混乱と失策、憶測の連鎖である。
この作品の凄みは、中盤に訪れる誤認逮捕の展開だ。浮上する容疑者は、不倫のアリバイを隠していたために状況証拠を積み重ねられ、死刑を宣告される。物語的にはここで一旦幕が下りるかに見える。
ところが、事件はまだ終わっていない。容疑者の逮捕後も、同様の手口による殺人が発生するのだ。警察は模倣犯の可能性を疑うが、実際に待っていたのは、より根源的で不気味な本物の犯人だった。
ここで注目したいのは、ビーディングが描く「狂気」の正体である。犯人の人物像は、1931年という時代にしては恐ろしく現代的だ。本作の終盤では、動機の論理がどこかに置き去りにされ、純粋な暴力性と異常な執着だけが浮かび上がってくる。
いわば、サイコパスの概念がまだ一般的でなかった時代に、明確にその姿を活写してしまう先見性があったのだ。のちの『ABC殺人事件』や『羊たちの沈黙』に通じる、冷たい暴力性がそこにはある。
また、本作の構成はかなり映像的だ。群像劇としての配置、場面転換のスピード、犯行場面の描写は、今日のテレビドラマや犯罪映画を想起させる。名探偵不在ゆえに、視点がコロコロと切り替わり、真相に迫る神の目線が存在しない。その不安定さこそが、事件をよりリアルに、そして不気味に際立たせている。
復刊された今、ようやくこの作品は正しく評価される段階に来たのかもしれない。名探偵に頼らない、論理も倫理も崩れていく町の描写、そして戦慄のラストまで突き抜けるスピード感。これが1931年に書かれていたのか、と思わず二度見したくなるはずだ。
事件の謎解き以上に、社会全体が「犯人を作り出していく」過程そのものが恐ろしい。そしてその構造は、現在の報道犯罪モノにも色濃く残っている。
要するにこれは、当時として異端なのではなく、今だからこそ最先端に見えるミステリだったということだ。
死は歩いてやってくる。
イーストレップスの町を、そして今この時代をも。
8位. ジャニス・ハレット『アルパートンの天使たち』
カルト、陰謀、そして資料が暴く真実の地層
ジャニス・ハレットのミステリを読むとき、もはや登場人物やストーリーラインといった枠組みだけでは足りない。
本作『アルパートンの天使たち』は、最初から最後までひたすら資料。メール、議事録、取材メモ、チャット、音声文字起こし──つまり、登場人物が「何を語ったか」ではなく、「何を記録に残したか」が大部分を構成している。
だからこそ、物語の中で最も信用ならないのは、常に文字である。そしてその曖昧さこそが、本作最大の武器だ。
物語は、18年前に起きたカルト教団〈アルパートンの天使〉の集団死事件から始まる。現場には、信者たちの遺体と、生き残った赤ん坊。彼らは赤ん坊を反キリストだと信じていた……というのが、当時の報道だった。
誰かが仕組んだ真実を、誰が再構築するのか
2020年代の現在、作家アマンダ・ベイリーはその赤ん坊が18歳になったという噂を聞きつけ、彼女なりの方法で取材を開始する。ただしこの取材、完全にゲームである。ライバル作家オリヴァーも同じテーマを狙っており、どちらが先に本を出すかの競争が展開される。
最初は気軽な出版ネタにすぎなかった。しかし、取材が進むにつれ、アマンダは不可解な矛盾に気づき始める。
「そもそも、この事件の公式見解、全部おかしくない?」
本作は「資料ミステリ」と呼ばれる形式に属する。つまり、全編が記録文書で進行するスタイルだが、ハレットの手にかかるとそれはただのギミックではない。断片を並べた結果、かえって読者はアマンダより多くの情報を得ることになる。
なぜなら、彼女が読み落とした小さな矛盾、記憶違い、嘘の影に気づくのは、すべて読者側──いや、ここではむしろ「記録を検証する第三者」と言ったほうが正確だろう。
事件の真相は、オカルトでも神秘でもない。そこにあるのは、人間の利害と欲望である。特に、アマンダとオリヴァーという二人の作家が、それぞれの視点と都合で資料を読もうとする姿が面白い。
彼らは真実に近づこうとしながらも、それを売れる本に加工しようとする。資料は素材でしかなく、解釈こそが武器。そしてその解釈が暴走したとき、関係者が次々と事故死していく。偶然か、それとも……。
タイトルにもなっている「天使たち」という言葉の使われ方がまた絶妙だ。天使は守護でもあり、破壊でもある。本作のなかで「天使」は、信仰の対象であると同時に、口実としても使われる。善意と悪意の境目は曖昧だ。
一見被害者に見える人物が、最も暴力的な選択をしていたり、その逆もある。関係者の証言がすべて残っているのに、「誰も真実を語っていない」という倒錯こそが、本作の核心だ。
最後まで読めば、タイトルの意味も、過去と現在のつながりも、最初に見えていた地図が全く役に立たないことも理解できる。だがそれでも、確かに全てのピースは揃っている。正しい順序で見れば、全貌は浮かび上がるのだ。
ハレットは「証拠だけで真実に到達できるか?」という実験を通じて、物語の外側にいる私たちにまで揺さぶりをかけてくる。
『アルパートンの天使たち』は、カルトを扱いながらも神秘には逃げない。むしろ、言葉と記録がいかにして人間を追い詰め、物語を構築し、そして時に破壊するのかを描いたメタミステリである。
そして最終的に明かされるのは、天使なんかじゃない、「人間」のあまりに人間らしい顔なのだ。
9位. スチュアート・タートン『世界の終わりの最後の殺人』
人類滅亡まで46時間、記憶喪失の島で誰が嘘をついているのか?
スチュアート・タートンという作家の何がすごいかって、読者の脳をねじることに一切遠慮がない点である。
『イヴリン嬢は七回殺される』では時間ループと人格転移をミステリの土台にしてみせたが、今回の『世界の終わりの最後の殺人』では、なんと「世界の終末」と「記憶の喪失」を組み合わせ、そこに殺人事件をぶち込んできた。
普通はどれかひとつを主軸にすれば十分だと思うのに、彼は全部のせでくる。
舞台は、有毒な黒い霧によって人類が死滅したあとの世界。唯一の希望は、バリアで守られた小さな島。そこではAI〈エービイ〉の管理のもと、122人の島民と3人の科学者が、平穏無事なコミュニティを築いていた。
この殺人を解かなければ、世界は終わる
だが、ある日その一角で事件が起きる。科学者ニエマの死が引き金となり、島を覆っていたバリアが48時間で解除されることが判明。つまり、殺人犯が見つからなければ、残された人類も全滅する。
そこに、さらにとんでもない条件が加わる。島民全員の記憶から、「事件当夜の数時間分」がごっそり消されていたのだ。容疑者は全員、動機もアリバイも思い出せない。記憶を失った探偵が、記憶を失った容疑者を取り調べる。この設定だけで、もう勝ちだ。
探偵役を務めるのは、島のはみ出し者エモリー。彼は、記憶という最大の証拠を欠いた状況の中で、住民の証言、監視記録、バリアシステムの残滓などを手がかりに、残された時間との戦いに挑む。
進めば進むほど、この島の理想郷の正体が明るみに出てくる。そこには、60歳以上になると問答無用で消される定年制度、同一人物のクローンを次々と育てる人体リサイクル計画、そしてAIの善意による独裁が存在していた。
つまり、この物語の核心は「誰が殺したか」だけではなく、「なぜこんな社会が許されているのか」「誰が本当の支配者なのか」という構造的な謎にまで踏み込んでいる。しかも、すべての要素がミステリとして機能しているから驚きだ。
トリックはフェアで、伏線は綿密。でも同時に、語られるテーマは思いのほか重い。管理された平和、記憶とアイデンティティ、AIの倫理、そして人間が選ぶべき最期の在り方。
ジャンルで言えば、SF、ディストピア、終末小説、クローズド・サークル、記憶ミステリ、倫理スリラーの全部に足を突っ込んでいる。それでも物語が破綻しないのは、タートンの構成力とアイデアの熱量によるものだろう。
「記憶を奪われた人間は、自分の罪にどう向き合うのか?」
「殺人犯がひとりの命を奪った結果、逆に世界全体が助かるとしたら?」
この小説は、そんな厄介な矛盾を突きつけてくる。そしてその先にあるのは、単なるどんでん返しではない。
これは、記憶が風化する未来で、それでもなお人間であることを選ぶかどうかの物語である。
10位. 『ヴァイパーズ・ドリーム』
演奏できないってだけで夢は終わるのか?
ジャズとノワール。その組み合わせを聞いただけで、夜の匂いがしてくる。
ジェイク・ラマーの『ヴァイパーズ・ドリーム』は、まさにそんな一冊だ。
舞台は1930年代から60年代のハーレム、主人公はトランペッターになれなかった男、クライド・ヴァイパー・モートン。
彼は音楽の才能に恵まれなかった代わりに、薬と金と人脈でジャズを裏から仕切るようになる。
音楽になれなかった男のノワール神話
物語は1961年、クライドが三度目の殺しをやらかしたあとから始まる。逃げる猶予は3時間。その間に彼が思い出すのは、自分が音楽に憧れて都会に出てきた、若き日の話だ。
でも、彼には決定的に足りないものがあった。音楽センス。それでもハーレムで生きていくには、何かを売らなきゃならない。彼が選んだのは、大麻だった。
売りながら、彼は見た。才能あるやつらが破れていく姿を。マイルス・デイヴィスやセロニアス・モンクが現れ、チャーリー・パーカーが堕ちていく。その傍らでクライドは、演奏できない分、支え、時に利用し、そして支配する側にまわっていく。演奏できなくても、ジャズを愛し、ジャズに取り憑かれた男の、裏からのクロニクルだ。
面白いのは、クライドが単なる悪人ではないところだ。彼は演奏家を潰しもするが、同時に守りもする。演奏はできなくても、彼なりのやり方でジャズに参加しようとした結果がこれなのだ。なんとも歪んだ愛し方ではあるけれど。
この小説、実在の人物もばんばん出てくる。ニカ男爵夫人の屋敷「キャット・ハウス」での逃亡劇から始まり、マイルス、モンク、バードたちとの絡みが濃厚に描かれる。フィクションのクライドが、あたかも本当にその時代にいたように思えるのは、このリアルさがあるからだ。
ジャズの進化とハーレムの変貌が、ノワールの空気と重なる感じもいい。スウィングからビバップ、ハード・バップへ。音楽のテンポが上がるにつれて、街もどんどん危なくなっていく。
クライド自身も、どこまでが守りたかったものか、どこからが堕ちた結果か、だんだんわからなくなっていく。その迷いこそが、物語の切なさにつながってくるのだ。
『ヴァイパーズ・ドリーム』は、音楽に恋して、破れて、それでもそこに居続けようとした男の話である。
夢は叶わなかった。でも、全然終わっていない。
どんな手を使ってでも、ジャズのそばにいたいと思った彼の姿は、哀しくて、どこかかっこいい。
11位〜20位
| 11位 | マシュー・リチャードソン『スパイたちの遺灰』 | 冷戦と現代が交錯し、歴史学者が元MI6伝説の女スパイの遺稿に潜む国家規模の秘密へ迫る。虚実を攪乱する極上の諜報スリラー。 |
| 12位 | 馬伯庸『風起隴西 三国密偵伝』 | 三国志の裏で繰り広げられた情報戦を、小人物の視点と現代的な諜報組織論で描く。裏切りと信義が交錯する歴史スパイミステリ。 |
| 13位 | フェリックス・フランシス『覚悟』 | 娘を誘拐された元騎手シッド・ハレーが、競馬界の八百長と巨大な陰謀に挑む。不屈のヒーローが復活する、熱量みなぎるスリラー。 |
| 14位 | ベンジャミン・スティーヴンソン『真犯人はこの列車のなかにいる』 | 豪華列車で作家たちが殺人事件に巻き込まれる。ミステリの「お約束」を武器にしたメタ構造とフェアな謎解きが光る快作。 |
| 15位 | ジョン・ブロウンロウ『エージェント17』 | 世界最強の殺し屋17が先代16と対峙し、組織の闇に迫る。映画的スピード感と父子神話が融合したアクション・スリラー。 |
| 16位 | ピーター・スワンソン『9人はなぜ殺される』 | 無関係な9人の名が書かれた封筒から殺人が始まる。現代版『そして誰もいなくなった』として、理不尽な暴力の恐怖を描く。 |
| 17位 | チェスター・ハイムズ『逃げろ逃げろ逃げろ!』 | 白人刑事に追われる黒人青年の逃走劇を通し、警察権力と人種差別の病理を剥き出しにする。半世紀越えで甦った怒りのノワール。 |
| 18位 | S・A・コスビー『闇より暗き我が祈り』 | 腐敗した南部の町で牧師の死を追う元海兵隊員。暴力と贖罪が渦巻くサザン・ノワールの原点として荒々しい熱量が迸る。 |
| 19位 | マシュー・ブレイク『眠れるアンナ・O』 | 昏睡状態の少女が二人殺害事件の容疑者となり、睡眠専門家が真相へ迫る。無意識と責任の境界を問う法廷サスペンス。 |
| 20位 | ジョー・ネスボ『失墜の王国』 | 山間の村で再会した兄弟の秘密が連鎖的に破滅を招く。愛と裏切りが渦巻く北欧ノワールで、家族の闇を粘着質に描く長編。 |
11位. マシュー・リチャードソン『スパイたちの遺灰』
燃えたはずの過去が、今を焼き尽くす
スパイ小説に求めるものが、派手なアクションや陰謀劇だけじゃないなら、この作品はかなり刺さるはずだ。
マシュー・リチャードソンの『スパイたちの遺灰』は、ただの諜報サスペンスではない。記憶と記録、真実と虚構、そういうややこしい境界を、煙のようにぼかしてくる「歴史改変スリラー」である。
主人公はマックス・アーチャー。ロンドンでくすぶる歴史学者で、元スパイ志望。今は大学で講義をしつつ、昇進にも私生活にも行き詰まっている。そんな彼の前に、伝説の元スパイ、スカーレット・キングが現れる。
記憶と記録、そのどっちが本物か
彼女はかつてMI6でソ連課を率いた切れ者で、90歳を超えた今、自分の死後に公開されるはずだった回顧録をなぜか生前のうちにマックスに託そうとする。
その文書には、ただの暴露では済まない爆弾級の情報が詰まっていた。過去の裏切りだけじゃない。今の世界の秩序にすら影を落としかねないレベルの国家の裏側が書かれている。結果、マックスは殺人容疑をかけられ、逃亡しながら謎を追う羽目になってしまう。
この小説の仕掛けは、時系列のクロス構造にもある。現在のロンドン、冷戦下のウィーンやモスクワ、90年代のバルト三国。過去と現在を行き来しながら、少しずつ真相の断片が集まっていく。それはあくまで断片でしかないけれど、スカーレットの記憶と、マックスの史料が合わさることで、見えてくるものがある。
とくに面白かったのは、語られなかった記憶の方が、むしろ歴史の本質をついてくるという逆説だ。記録というものは、誰かが都合よく残したものであって、決して中立なものではない。スカーレットの語りは、その記録に火をつける役割を果たしていく。
スパイ小説としても申し分ない。頭脳戦と逃走劇、古い因縁と新たな裏切りが交差し、ぐいぐい読ませる。『ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ』の重厚さに、『007』のアクションを少しだけ足したようなバランスだ。しかもロシアの現実の事件も組み込まれていて、フィクションとリアルの間を何度も行ったり来たりさせられる。
そしてタイトルにある「遺灰」。これは単なる比喩じゃない。燃え尽きたと思われていた過去が、灰の中から再び火を噴く──そんな意味合いを持っている。
たとえ誰かがすべてを燃やそうとしたとしても、言葉は、記憶は、消えない。
12位. 馬伯庸『風起隴西 三国密偵伝』
スパイの視点から見た、もうひとつの三国志
もし『三国志』という物語を、戦場の正面からではなく、影でうごめく情報機関の視点から描いたらどうなるのか。
馬伯庸の『風起隴西』は、まさにその実験を真正面からやってのけた歴史ミステリである。
物語の起点は、史実として有名な「街亭の敗北」。蜀の馬謖が防衛線を崩壊させ、諸葛亮が「泣いて馬謖を斬る」場面だ。
この一幕の裏に、じつは魏のスパイによる情報工作があったとしたら……? という仮説を軸に展開される。
時は西暦228年、諸葛亮が仕掛けた第一次北伐が失敗した直後。だが失敗の原因は本当に馬謖の戦略ミスだったのか?
本作では、蜀の諜報機関「司聞曹」が魏に送り込んだ伝説のスパイ「白帝」=陳恭の情報が、なぜか敵に漏れていたことで戦局が狂ったとする。
つまり、内部に裏切り者がいるということだ。
名もなき情報将たちが歴史を動かす
その調査を命じられるのが、防諜担当の荀詡。白帝とは義兄弟という間柄だが、任務は彼を粛清すること。にもかかわらず、荀詡は陳恭の潔白を信じ、二人で真の裏切り者「燭龍」の正体に迫っていく。
一度疑われたスパイが味方にも敵にも命を狙われる、という展開はスパイ小説としてはかなり王道だが、舞台が三国志というのがたまらない。
本作の面白さは、いわゆる英雄たちをメインに据えず、歴史に名前の残らない情報将たちを主人公にしているところにある。暗号、偽装、通信経路の遮断、内部抗争……時代劇というより、現代スパイサスペンスに近いテンションだ。組織内での責任のなすりつけ合いや、命令の意味をめぐる葛藤も、生々しいリアリティを持って描かれている。
そして、あくまで言葉と信頼と推測で戦うこの作品は、剣も矢も飛ばないのに手に汗握る。力づくではどうにもならない局面を、信じるか疑うかで切り抜ける頭脳戦の数々が、むしろ戦闘シーンよりも緊迫感を生んでいるのがすごい。
なお、本作は2022年に中国で実写ドラマ化されていて、映像作品のほうも非常に高い評価を得ている。ドラマではややロマンス色が強めに出ていたが、原作はあくまでスパイとスパイの頭脳バトルに徹している。
三国志といえば武将たちの豪快な駆け引きを想像しがちだが、その陰で命を張って働いていた影のプロフェッショナルたちの視点は、思いのほか新鮮で、濃密で、胸に刺さる。
スパイもの、組織内サスペンス、三国志、どれか一つでも好きなら刺さる可能性は高い。
これは知略と信念の物語だ。
派手さではなく、静かな炎を抱えた男たちの戦いに、しっかりと引き込まれる。
13位. フェリックス・フランシス『覚悟』
もう一度義手をはめる理由があるとき
ディック・フランシスの代表作といえば、競馬界を舞台にしたハードボイルドミステリだ。
その魂をそのまま受け継いだのが、息子フェリックス・フランシスである。
『覚悟』(原題:Refusal)は、そんなフランシス・ブランドの伝統を踏まえつつ、より個人的で感情的なテーマへと踏み込んだ作品だ。
主役はもちろん、元障害騎手にして名探偵のシッド・ハレー。かつて左手を失い、義手を武器に数々の事件を解決してきた男である。今では探偵業を引退し、妻と娘と静かに暮らしていた──はずだった。
正義と家族のあいだで揺れる、引退探偵の決断
だが、「競馬界に八百長がある」として持ち込まれた依頼を断った翌日、依頼人が死亡。その直後、正体不明の男から脅迫が届く。
しかもまだ調査に着手もしていないというのに。こうして、平穏な生活はあっけなく壊れ、ついには娘が誘拐される事態へと転がっていく。
ここでハレーは、再び義手を装着する。これは職業復帰以上の意味を持つ行為だ。家族のために、かつて捨てた戦場に戻る。その決断の重みこそが、邦題『覚悟』の本質だろう。
本作の魅力は、そんなハレーの葛藤にある。かつての彼は「己の正義」で動いていたが、今回は「守りたい存在」がある。そのせいで、かえって正義と倫理のラインが揺らぐ。相手の言いなりになるわけにはいかない。だが、拒めば娘が危ない。このジレンマが物語を引っ張っていく。
アクションや推理もしっかり面白いが、いちばん熱いのは、再び戦う決意を固めたシッドの姿である。年齢を重ね、弱さや迷いを抱えながらも、それでも彼は立ち上がる。守るために。
フェリックス・フランシスは、父の名作を単に引き継いだだけではない。そこに新たな情動を持ち込んだことで、シッド・ハレーは再び「現代のヒーロー」として蘇った。
タイトル『覚悟』が意味するのは、敵に立ち向かう強さだけではない。
守るべきもののために、弱さを抱えたまま立ち上がる勇気そのものなのだ。
14位. ベンジャミン・スティーヴンソン『真犯人はこの列車のなかにいる』
全員ミステリ作家、全員容疑者。舞台は走る密室
前作『ぼくの家族はみんな誰かを殺してる』でメタミステリ界に旋風を巻き起こしたベンジャミン・スティーヴンソンが、さらに大胆な一手を放ってきた。
今回の舞台は、オーストラリアを縦断する豪華列車ザ・ガン。乗客は、ミステリ作家、エージェント、批評家、出版社の人間……とにかく「殺人の専門家」だらけ。
そんな密室空間で、案の定、誰かが殺される。
ルールを知り尽くした奴らの「犯人当て」
探偵役を務めるのは、自作の犯罪実録本で一発当てた自称作家アーネスト・カニンガム。だがこの男、推理は得意でも人間関係はポンコツ。
捜査そっちのけで恋人との関係に悩み、証拠よりセリフ回しに気を取られ、挙げ句の果てには「犯人の名前は本書に135回出てきます」と自爆気味なメタ発言をかます始末。
それでもこの物語が抜群に面白いのは、登場人物たちが全員ミステリに精通している点だ。殺人を伏線として読み、ノックスの十戒を逆手に取り、アリバイの裏に二重三重の罠を仕掛ける。もはやこれは「ジャンル内戦争」と言っても過言ではない。
スティーヴンソンは、そんな知的格闘をユーモアと風刺たっぷりに描きながら、ちゃんとロジックとフェアプレイで着地させてくるから見事だ。
舞台となる「走る密室」も絶妙で、オーストラリアの荒野を滑る列車の中で起こる連続殺人は、クラシックな香りと新しさが見事にブレンドされている。アガサ・クリスティのファンも、新本格派も、ミステリオタクも、それぞれ違う角度から楽しめる構造だ。
「犯人の名前は135回登場する」と言われたら、そりゃ探したくなる。でも、この列車では「誰が犯人か」よりも、「どう仕掛けたか」「なぜそれをやったのか」にこそ、ニヤリとさせられる仕掛けが詰まっている。
そして気づく。メタという言葉すら、この作品ではただのギミックに過ぎない。
これは、犯人当てという遊びそのものを、最高に贅沢に、そして愉快にやりきった現代ミステリの祭典だ。
15位. ジョン・ブロウンロウ『エージェント17』
そのコードネームは、殺して継ぐ
『エージェント17』というタイトルにピンときた人は、たぶん既に最高の殺し屋エンタメを嗅ぎつけている。
タイトルからして只事じゃないが、本書は中身もやっぱり只事じゃない。
CWAスティール・ダガー賞を受賞した本作は、「読むアクション映画」という言葉がしっくりくる。書いたのは脚本家のジョン・ブロウンロウ。
映像で叩き上げられた感覚がそのまま文章に落とし込まれていて、最初の数ページで一気に掴まれる。
世界最高の殺し屋、その継承制度は殺るか殺られるか
主人公のコードネームは17。西側のどこかにある秘密機関が管理する、選ばれし暗殺者のナンバリングシステムで、現役最強の殺し屋だけに与えられる称号である。
そしてこの称号は、前任者を殺すことでしか手に入らない。つまり17は16を殺して今ここにいる……というわけではなく、16は例外で、失踪したことになっていた。
ところが、17に与えられた任務は、この16を見つけ出して始末すること。16は偽名でアメリカに潜伏し、小説なんぞ書きながらひっそり暮らしているという。
しかし話はそう単純ではない。16は「組織の裏側」に気づいたがゆえに逃げたのだという。17は迷う。任務を果たすのか、それともこの謎めいた先代と手を組むのか。
アクションはとにかくキレッキレだ。冒頭のベルリンでの作戦から、60ページに及ぶ銃撃と追跡の応酬。だが、それ以上に面白いのが、17と16の関係性である。敬意と殺意、共闘と対立。その揺らぎが全体に緊張感を与えている。これは単なるスパイvsスパイの話じゃない。「自分がこれから何になるのか」をめぐる、アイデンティティの物語でもある。
文章は映像的で、余計な修飾はゼロ。カット割りがそのまま浮かぶような構成で、まさに「映画を読んでいる」感覚。情報の開示のテンポも見事で、設定の複雑さに足を取られることなく、ラストまで一気に持っていかれる。
殺して継ぐという過激な設定を出発点にしつつ、しっかりと心理劇としての深みを持たせている点が秀逸だ。プロフェッショナルとしての矜持と、人間としての葛藤。その狭間で揺れる男の物語は、スリラーでありながら、どこか詩的な響きすら帯びている。
殺すことでしか継げない称号なんて設定は、ある意味でマンガ的だ。しかし、それをここまで骨太なテーマと絡めて成立させてしまう力量は、本当に見事としか言いようがない。
シリーズ化も予定されているようで、17のこれからがどう描かれるのか、ますます楽しみである。次も確実に撃ち抜いてくれるはずだ。
16位. ピーター・スワンソン『9人はなぜ殺される』
バラバラに殺されていく、その理由はどこにあるのか?
ある日、9人の男女に差出人不明の封筒が届く。中には、彼ら自身を含む9つの名前が並んだリストだけ。
差出人も、脅迫文もなし。ただ名前が並んでいる。その意味はすぐに明らかになる。リストの名前はひとり、またひとりと死んでいくのだ。
これだけで、『そして誰もいなくなった』を思い出す人も多いだろう。実際、ピーター・スワンソンはこの名作に真正面からオマージュを捧げつつ、まったく別の角度から「なぜ殺されるのか」という深層に踏み込んでいく。
群像劇としての構成はクリスティ的だが、そのトーンはより現代的で、よりパーソナルで、より容赦がない。
リストと理不尽のサスペンス
本作では、9人それぞれの視点が入れ替わりながら、少しずつ死が忍び寄ってくる。FBI捜査官、リゾートの老人、売れない若者、教師、人妻。それぞれに過去があり、秘密がある。
でも、それが殺される理由になるのかは最後までわからない。そこにあるのは、法では裁けない曖昧な過去と、どこかに潜む強烈な執念だけだ。
殺人の順番に法則はない。殺害方法もバラバラ。しかも、犯人の動機は論理的でも正義的でもない。ただの復讐でもなく、狂気でもなく、言ってしまえばとても個人的で、ひどく一方的な動機だ。だからこそ、厄介で怖い。
スワンソンはこの「理不尽な動機」を物語の最奥に据えることで、犯罪小説にありがちな「秩序ある真相」から故意に逸脱している。結果として描かれるのは、「誰が悪かったのか」ではなく、「人はどこで間違えるのか」という、もっと見えづらいグラデーションだ。
『9人はなぜ殺される』は、確かに古典へのオマージュである。だがその構造はむしろ、クリスティのフォーマットを使って現代の不安と暴力を再定義しようとする挑戦でもある。
被害者たちは「悪人」ではない。ただ、「あのとき、あの選択をしてしまった」人たちだ。
ラストに待つどんでん返しも、衝撃というよりは納得に近い。そう、あらかじめ決まっていた運命だったかのように、すべてが収束していく。この冷酷な整合性は、スワンソン作品ならではの怖さでもある。
結局、殺意は合理性よりも執念から生まれる。
そして、リストに名前がある。それだけで十分。
逃げ場のない恐怖とは、まさにそういうものだ。
17位. チェスター・ハイムズ『逃げろ逃げろ逃げろ!』
撃たれたのは、希望だったかもしれない
チェスター・ハイムズといえば「墓掘りジョーンズ&棺桶エド」シリーズが有名だが、この作品はあのシリーズとはまったく違う。1959年に書かれた社会派ノワールで、いま読むと「これはまだ終わってない話だな」と思わされる。
物語は、酔っ払った白人警官ウォーカーが、ハーレムの食堂で黒人店員を射殺するところから始まる。理由なんてない。ただの八つ当たりだ。そこでたまたま働いていた若者ジミー・ジョンソンは、現場から命からがら逃げ出す。
だが、そこからが地獄の始まりだった。ウォーカーはジミーを警官殺しに仕立てあげ、自分の罪をすべて塗り替えようとする。
追う者と追われる者、そして見えない檻の正体
ジミーは、警察にも世間にも助けを求められない。逃げるしかない。恋人リンダに支えられながら、ニューヨークという巨大な迷路を必死に駆け抜ける。
でも、そこは単なる街じゃない。肌の色によって行ける場所と行けない場所が分かれている。逃げ場なんて、はじめから存在しないに等しい。
ウォーカーはただの悪徳警官じゃない。やつは本物のサイコパスだ。殺しにも罪悪感がないし、目的のためなら何でもやる。けれど、もっと恐ろしいのは、そんな彼が「正義の執行者」として扱われる社会のほうだ。バッジ一つで殺人が合法になる、そういう仕組みがこの物語の真の悪である。
この小説は、今だからこそ意味がある。ジミーが走る姿は、もう遠い過去の話ではない。彼が逃げていたものは、2020年代の今も形を変えて生き残っている。復刊された意味があるし、その怒りや悲しみは、まだ終わっていない。
最後のページを閉じたとき、自分の中にあったはずの正義や秩序が、ぐらりと揺れるのがわかる。
それは、ハイムズが仕掛けた一発の銃声よりも、ずっと深く響く衝撃だ。
ジミーの逃走は、過去の物語ではない。あの走りは、今も続いている。
少なくとも、この社会が「逃げなければならない誰か」を生み出し続けている限りは。
18位. S・A・コスビー『闇より暗き我が祈り』
祈るように拳を握る、その痛みと贖いの道
南部ノワールには、独特の熱と重さがある。土の匂いと汗と血が混じり合い、正義も倫理も境界線がゆらぐ。
その渦中に立つのが、本作『闇より暗き我が祈り』の主人公ネイサン・ウェイメイカーだ。
のちに『黒き荒野の果て』『頬に哀しみを刻め』で名を馳せるS・A・コスビーの記念すべきデビュー作にして、その後の作風すべての原点がここに詰まっている。
境界に生きる男の、怒りと孤独と再起の物語
舞台はヴァージニア州の田舎町。ネイサンは黒人の母と白人の父を持つバイレイシャルの元警官。今は従兄弟の葬儀屋で働きながら、穏やかなようでどこか鬱屈した日々を送っていた。
そんな彼のもとに、地元でカリスマ的人気を誇っていた牧師の不審死に関する調査依頼が舞い込む。
調査を始めると、牧師の裏の顔が次々と明らかになる。ギャングとの繋がり、隠された金、そしてスキャンダラスな過去。やがて牧師の娘であり、今はポルノスターとなったリサが帰郷し、ネイサンは彼女とも危うい関係に足を踏み入れる。
やがて彼は、幼馴染で今はアウトローな存在となったスカンクと再会し、二人で町の裏側へと切り込んでいく。腐敗した保安官、見えない圧力、そして自分自身の過去。そのすべてと、真正面からぶつかることになる。
この物語の魅力は、なんといってもネイサンの「中間者」としての視点だ。肌の色、立場、過去。彼はどこにも完全には属せない。だがだからこそ、見えるものがある。法の外と内、暴力と慈しみ、正義と保身。その境界線の上で揺れながら、それでも拳を握る姿が、胸に響いてくる。
葬儀屋という静謐な場所と、血なまぐさい抗争のコントラストも効いている。死に向き合う時間と、生きるための闘争。その両方を抱えながら、ネイサンは何かを見つけようともがく。
正直、後年の作品に比べると少し粗さもある。けれど、それ以上に熱と勢いがある。「とにかく今、この物語を書きたかったんだろうな」という、作家の衝動がビシビシ伝わってくるのだ。
暴力は容赦ないし、感情の揺れもごまかさない。善悪なんて曖昧なものだと分かっていながら、それでもネイサンは真っ当な道を選ぼうとする。そんな人間の足掻きが、この作品には詰まっている。
そして、この物語はまだ始まりにすぎない。コスビーがどこまで行くのか。
その一歩目として、このデビュー作はあまりにも誠実だ。
19位. マシュー・ブレイク『眠れるアンナ・O』
現代の眠り姫は、本当に無実なのか?
「眠ってる間に人を殺したら、それは有罪なのか?」
そんな無理ゲーみたいな状況を本気で扱ったのが、この『眠れるアンナ・O』。2025年の話題作にして、世界中の出版社がこぞって翻訳権を取りに走った注目のサスペンスだ。
事件の主役はアンナ・オグルヴィ。4年前、親友2人を刺殺した容疑で現場にいた彼女は、血まみれのナイフを手にしたまま、その場で昏睡状態に陥る。それ以来、彼女はずっと目を覚ましていない。
診断名は「生存放棄症候群」。簡単に言えば、自分の存在を放棄するかのように眠り続ける、現代の眠れる森の美女である。
眠ったままの容疑者と、裁判のありえない依頼
でも、殺人が事実なら裁判は必要だ。そこで登場するのが、睡眠犯罪の専門家ベン。司法省に呼び出され、「アンナを目覚めさせて、裁判にかけてほしい」と無茶ぶりされる。
ベンはアビーと呼ばれる高級睡眠クリニックで、アンナの深層心理にアクセスしようとするが、彼女の過去にはいろんなものが絡まりまくっていた。
とくに彼女の日記に出てくる「患者X」という存在が曲者で、そこからベンの過去ともリンクして、事態はますますややこしくなっていく。
眠っているあいだに本当に何があったのか? そもそも、彼女は本当に無意識だったのか?
この作品の面白さは、「無意識下の犯罪は責任を問えるのか」という、心理と法のギリギリを突いてくるところだ。加えて、ベンの語りはどこまで信じていいのか怪しいし、アンナの視点も信用できない。
語りの構造自体が巧妙な罠になっていて、終盤にはしっかりどんでん返しも仕掛けてくる。
エンタメとしてスピード感はあるし、テーマは哲学的。でも難しすぎず、ちゃんと「面白さ」に回収されてるのがうまい。
眠りの奥底に何が潜んでいたのか。
最後のページまで、その謎は眠らせてくれない。
20位. ジョー・ネスボ『失墜の王国』
この兄弟は、互いを救わない。
ジョー・ネスボといえば「ハリー・ホーレ」シリーズの印象が強いけれど、この『失墜の王国』ははそこから大きく離れた、地に足のついた血の物語だ。刑事ものの枠を外れ、村社会と家族の歪んだ関係を描いたノワールである。
舞台はノルウェーの山奥。自然に閉ざされた小さな村に帰ってきた弟と、村に残り続けた兄。このふたりの関係が、最後までねばっこく、重く、そして逃れようのないほど濃密に描かれていく。
兄・ロイはガソリンスタンドを営み、両親の残した農場──かつて「王国」と呼ばれていた土地──を守っている。弟・カールは海外から美しい妻シャノンを連れて帰郷し、「村を豊かにする」という大義名分を掲げて巨大なスパ・ホテルの建設計画を持ち込む。
が、そこにあるのは純粋な郷土愛ではなく、綿密に練られた計画の匂いだ。
雪に閉ざされた村で、ゆっくり崩れていく家族という神話
本作の軸は、この兄弟の関係に尽きる。彼らの過去には、両親の死をめぐる決して語れない出来事がある。
そしてカールの帰還をきっかけに、それがゆっくりと暴かれていく。新たな事件も起きて、物語はサスペンスとしての輪郭を強めていくが、真に怖いのは「身内だからこそ生まれる地獄」である。
ロイの語りが全編を貫いており、警察や探偵のような「外からの視点」は一切ない。だからこそ、語られないことの重みや、内面のずしりとした感情がじかに伝わってくる。この語りの不確かさが、ネスボらしい不穏さを醸し出しているのだ。
ネスボは、兄弟の絆を単なる愛としてではなく、共依存や共犯関係として描いている。その息苦しさが、寒々しい雪山の風景とうまく噛み合い、読んでいて逃げ場のなさを感じさせる構成だ。とくに後半にかけては、ノワールとしての完成度が一気に高まっていく。
続編を匂わせる描写もあるが、この1冊だけでも十分に濃い。希望も救いも安易には差し出されない。そこにあるのは、血のつながりという呪縛にどうしようもなく絡め取られた男たちの物語だ。
誰が善人で、誰が悪人かなんて簡単には決められない。
その複雑さこそが、この王国の本質である。
おわりに

以上、全20作品を並べてみてあらためて実感するのは、いまの海外ミステリは「ジャンルを越えること」と「過去を再び使いこなすこと」に全力を注いでいるということだ。
スパイ小説が歴史小説になり、心理劇が法廷サスペンスと混ざり合い、古典ミステリの骨格に現代の病理が肉付けされる。
どれも一筋縄ではいかない。けれど、そのひとひねりがあるからこそ夢中になってしまう。
今年の翻訳ミステリも、やっぱりすごかった。
そして、これからもこのジャンルは、世界の混沌を物語の中に書き写していくのだと思う。
謎を解くことは、世界を見つめ直すことと、きっとどこかでつながっているのだから。
国内編はこちら