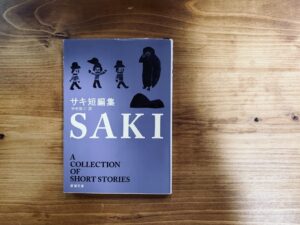短編小説というのは、気づけば中毒になっている。
たった数ページで始まり、いつの間にか転がり、最後の数行で「そう来たか!」と頭を抱える。
これは最高の娯楽だ。ミステリを読む人間として、このひっくり返される感じには本当に抗えない。
そういう「読んでる途中には気づかないけれど、最後で全部がひっくり返る」という爽快な体験をほぼ芸術の域まで高めたのがオー・ヘンリーである。古典作家という肩書きが先に来るが、改めて読んでみると、ものすごく現役なのだ。
特に角川文庫の新訳版『オー・ヘンリー傑作集1 賢者の贈り物』(訳・越前敏弥)は、まるで2020年代の読者に向けて書かれたかのような読み心地になっている。
作家オー・ヘンリーという二重生活者と、400万人のニューヨーク

オー・ヘンリーの人生について話し始めると、それだけで一冊の冒険譚になりそうだ。牧場、薬局、銀行勤務、横領容疑、逃亡、収監、そしてニューヨークでの文筆生活へ。
華々しい作家デビューの裏に、どうしようもなく荒れた現実が広がっている。そのギャップこそ、作品のユーモアの背後に漂うほろ苦さを作っているのだと思う。
特にニューヨークに移ってからの彼は、まさに街の語り部だった。上流階級のわずか400人が幅を利かせていた時代に、彼が目を向けたのはその外側に生きる400万人の名もなき人々である。
ショップガール、浮浪者、下宿の老紳士、デパート勤めの女性、仕事に追われる仲買人。彼らは歴史の年表の片隅にすら残らないが、オー・ヘンリーにとっては物語の主人公だった。彼は、そういう人々の小さな物語を描き続けた。
だからこそ、彼のニューヨークはいつも息苦しいほどリアルで、溜息と笑いと偶然の魔法が同居している。地下鉄の騒音も、アパートの寒さも、冬の風も、すべてが物語の燃料になっているのだ。
短編16編の構造を追いながら読む楽しみ
収録されている16編は、どれも短いのに構造がぎゅっと詰まっている。
導入の巧みさ、登場人物の立ち位置、価値観の反転、都市生活の観察。それらがページごとに積み重なり、最後のひと押しで全部ひっくり返る。
『賢者の贈り物』
言わずと知れた、世界で一番有名なクリスマス短編。あまりにも有名すぎて説明が難しいのだが、越前訳だと貧しい夫婦の生活が妙にリアルで痛切なのが印象的である。
1ドル87セントという金額が、数字以上の重みを持つ。だからこそ、あの贈り物が単なる美談ではなく、ふたりの生き方そのものに感じられてくる。
『警官と讃美歌』
ホームレスのソーピーが、冬越えのために逮捕されようと頑張るという奇妙な前提から始まる。普通なら逮捕されないようにするのが物語の動機だが、ここでは逆である。
その逆さまの価値観が、物語全体を軽やかなコメディにしつつ、最後のシーンでとんでもなく胸に迫ってくる。教会から聞こえてくるオルガンの音が、ソーピーの心のどこか深い部分に灯りをともすあの瞬間は、何度読んでも美しい。
『忙しい株式仲買人のロマンス』
ウォール街の狂騒を追いながら、仕事に没頭しすぎた男の忘却をユーモラスに描く。人間は極度の集中状態にいると、本当に大切なことをすっぽり落としてしまう。
ラストでようやくその落ちた何かが明かされるのだが、その哀しさと滑稽さが同時に押し寄せる。
『緑のドア』
偶然で始まるロマンス短編の最高峰。きっかけは完全に即物的な理由なのに、読後はなぜか心が温かいという奇跡の構造。
偶然という名の軽妙な装置が、読み手に「世界はまだ驚きに満ちている」と思わせてくれる。結末の明かし方は非常に即物的なのに、不思議と夢が壊れない。ここにオー・ヘンリーのすごさが凝縮されている。
『振り子』
人間の反省は長続きしない問題を、数ページで完璧に描いた作品。ラスト一文の破壊力がすごい。
孤独に触れた瞬間は心が動くのに、日常に戻った途端その誓いが霧散してしまう。あの最後の一文は、本当に人間の弱さと可愛さを一撃で言い当てている。
ほかにも、身分詐称系三部作とも言いたくなる、『洒落男の失敗』『桃源郷のはかなき客』『自動車を待たせて』の三編も好きだ。いずれも嘘が嘘を呼び、立場のねじれが物語を動かしていく。
嘘と虚栄がたしかに物語を歪ませるはずなのに、オー・ヘンリーはそこで人間を責めたりしない。むしろ、そうした小さな見栄や夢にこそ、都市で生きる人間の可愛らしさが宿ると言わんばかりだ。
このほかの作品も、それぞれにオー・ヘンリーらしい仕掛けがあり、読み返すほど新たな発見がある。短編の構造を楽しむ読み方をするなら、この16編は格好の教材になるはずだ。
新訳が古典を現在にしてしまう

この新訳版でまず驚くのは、100年以上前の物語なのに、会話や描写がすんなり頭に入ってくる点だ。
古い翻訳だと、どうしても文語調のにおいが残ったり、語尾のニュアンスが固く感じたりすることがある。しかしこの新訳は、原文の軽やかさやユーモアを、現代日本語で自然に再現している。
特に『警官と讃美歌』の独白部分や、『賢者の贈り物』のデラの感情の揺れは、今の読み手がそのまま自分の言葉として理解できるようになっている。オー・ヘンリーの持ち味であるおしゃべりな語り口が損なわれていないのが嬉しい。
作品の舞台が1900年代初頭であることを忘れさせるわけではない。ちゃんと当時の空気が伝わってくるのだが、それでも古典を読んでいるという距離感がない。短編に必要な速度感が、現代語で維持されているからなのだと思う。
いまオー・ヘンリーを読むと、なぜこんなに面白いのか
今も昔も、どんでん返しもののミステリや映画が人気だが、その源流がここにあると改めて感じる。オー・ヘンリーのツイストは、ただ驚かせるための仕掛けではなく、価値観をぐっと裏返すための装置だ。
逮捕されることが幸福になる世界。
贈り物が無駄になることが愛の証になる夫婦。
金の力でロマンスが支えられる父と息子。
偶然の出会いに運命を見いだす青年。
こうして並べてみると、彼の反転はいつも人間の価値観の根本を刺激してくる。この価値観の揺さぶりこそが、古さとは無縁の普遍性を生んでいるのだと思う。
そしてもうひとつ。現代の社会に根強く残る格差や孤立の問題と、オー・ヘンリーが描いた持たざる人々の姿が驚くほど重なって見える。
貧しさを悲劇だけとして描かず、その中のユーモアやしたたかな明るさを拾い上げるまなざしが、今読むと逆に新鮮なのだ。
これは「古典の名作集」ではなく、完全に今の本だ
『オー・ヘンリー傑作集1 賢者の贈り物』は、越前敏弥という訳者の手を経て、100年前の短編が21世紀の短編として蘇った一冊である。
読み始めればわかるが、そこに古めかしさはほとんどない。ニューヨークの街角の喧騒も、貧しいアパートの空気も、恋の淡い予感も、すべてが生々しくて、すぐ隣で起きているように感じられる。
16編を読み切る頃には、人間の愚かさと愛おしさがないまぜになった、なんとも言えない温度が胸に残るはずだ。ソーピーの一瞬の改心も、若夫婦のプレゼントも、虚勢を張る男女の夢のような時間も──全部ひっくるめて、オー・ヘンリーの短編は「いま読むべき物語」として輝いている。
古典を読むというより、最新の短編集を手に取るつもりで。そんな感覚でこの本を開くと、きっと驚くほどしっくりくる。
ニューヨークの片隅にあった物語が、時間を越えてゆっくりこちらへ染みてくるようなその感覚が、なんとも心地いいのだ。