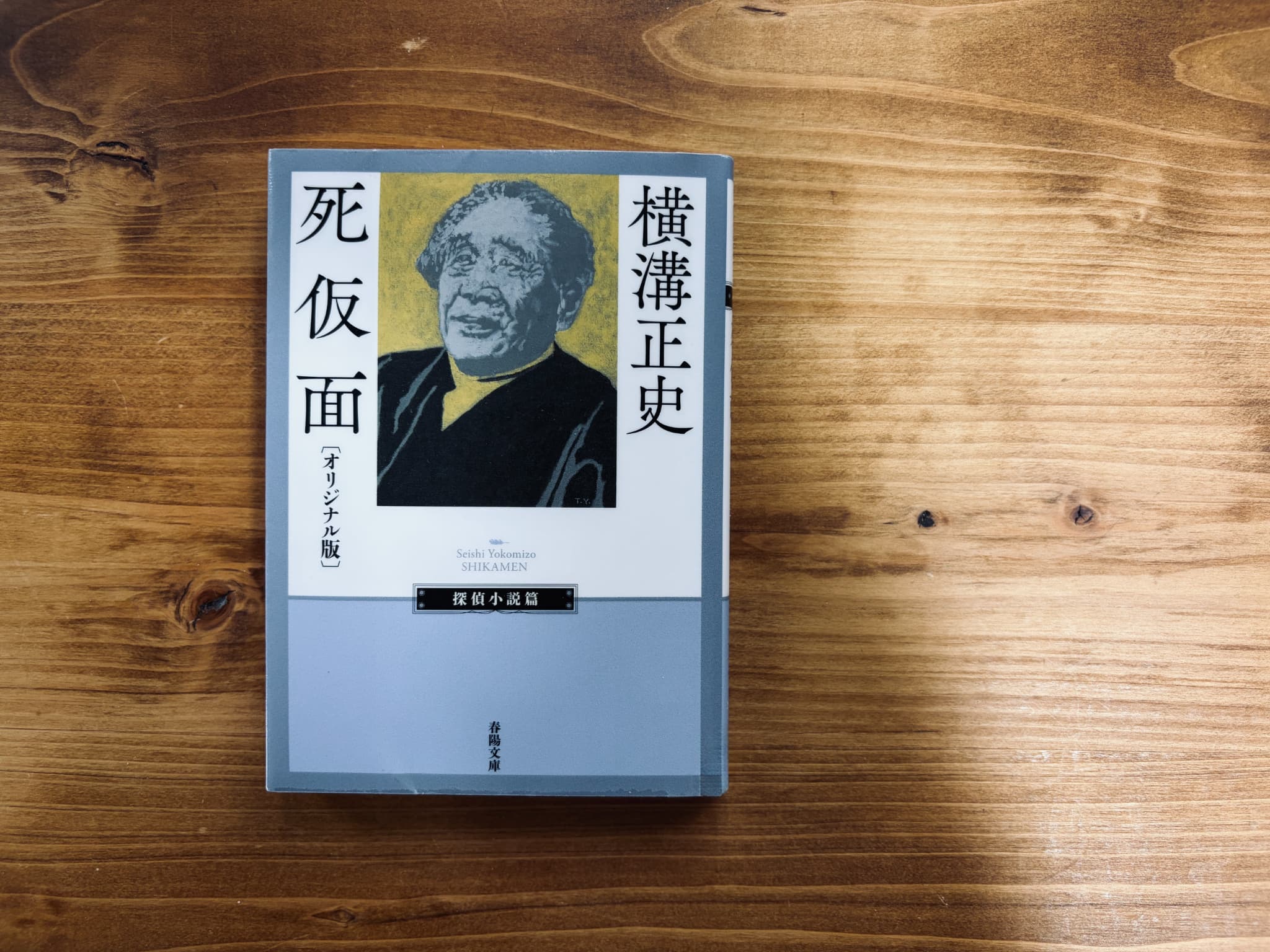スティーヴン・キングのデビュー50周年を記念して刊行された『コロラド・キッド 他二篇』は、いわば「読まれずにいたキング」を一気に解き放った作品集だ。
長らく国内では読めなかった「幻」の中篇群をまとめ、日本オリジナルの文庫版としてリリースされたのがこの一冊。
内容はというと、表題作『コロラド・キッド』、ゴーストホラーの短編『ライディング・ザ・ブレット』、そして本邦初訳の『浮かびゆく男』。それぞれがまるで違うジャンルの顔をしているのに、読み終えたあとにふと胸に残るざらつきと温度は、たしかにキングその人の筆によるものだった。
この本は単なる再録でも寄せ集めでもない。それぞれが出版当時に話題を呼び、あるいは読者の戸惑いを買った作品であり、まさにこのタイミングで並べられることで、「キングとは何か?」というテーマに答えようとする構成になっている。
恐怖から始まり、謎へと向かい、やがて昇天へと至る。まるで自分自身の変遷が、三篇の順番に反映されているかのようだ。
各作品を順に読みながら、それぞれが何を語ろうとしていたのかをじっくり見ていきたい。
ミステリとしての裏切り、ホラーとしての痛み、寓話としての祈り──そのすべてが、キングの半世紀にわたる物語人生の一断面なのだから。
『ライディング・ザ・ブレット』── 自分を裏切る気持ち悪いホラー

『ライディング・ザ・ブレット』は、いかにもキングらしいホラー……に見せかけた、ある種の心理スリラーだ。
内容はシンプル。大学生のアランが、脳卒中で倒れた母のもとへ向かう途中、ヒッチハイクで拾われた車の中で「ある選択」を迫られる。自分が死ぬか、母が死ぬか。そんな無茶苦茶な問いに、咄嗟に彼は「母を連れて行け!」と叫んでしまう。
生存本能に任せた裏切り。その選択は、実際に母の命を奪いはしなかったが、彼の心に深く根を下ろす。死よりも重い、後悔という名の呪いとして。
この作品は、明らかに気持ち悪い。幽霊の不気味さよりも、もっと根深い人間の弱さにホラーがある。
死の使者として現れるスタウブは、どこか古典的な恐怖の顔をしているが、それ以上に恐ろしいのは、自分がその提案に「乗ってしまった」瞬間のアラン自身なのだ。キングはいつだって、化け物よりも人間のほうが怖いことをよく知っている。
『ライディング・ザ・ブレット』は、いま読むとむしろしみじみとする話かもしれない。若さの軽率、親への未熟な愛、死への素朴な恐怖──それらがごちゃごちゃに混ざりあって、正しさも救いも見つからない。だからこそ、ここには確かな真実の震えがある。
『コロラド・キッド』── 最後に残るのは、壊れた心のあたたかさ
そして、『コロラド・キッド』である。
かつて『ダークタワー』シリーズのノベルティとして抽選で配布された非売品、という幻の作品。それが読める。神。
内容も、ミステリ好きとしてはかなり面白い一手だ。
いちおう「未解決事件を語る話」なのだが、核心の謎が解かれない。この作品は、そもそもミステリにおける「解決」の意味そのものを考え直そうとする構造になっている。ある意味ではメタ・ミステリであり、語りの小説であり、文学するキングの一面が最もよく出ているように思う。
舞台はメイン州の離島。二人の老記者が、若いインターンに向けて語るのは、過去にその島で起きた「コロラド・キッド事件」だ。
何が起きたのか、どこまでわかっていて、なにがわかっていないのか。読み進めるほどに、むしろわからなさだけが際立ってくる。そもそもこの謎は解けるのか?
面白いのは、老記者たちが「ミステリとは、すべてが解明される話じゃない」と堂々と言い切るところである。そんなことをミステリでやってしまっていいのか? と思う人もいるだろう。でも、それこそがコロラド・キッドなのだ。
情報過多の時代に、「わからないまま終わる物語」を提示することの勇気。その潔さと苦味が、この作品には詰まっている。キングはここで、物語のカタルシスよりも、読者が立ち止まって「なぜ語られたのか」を考えることを求めている。
語りの伝達。記憶の継承。これもまた、物語の役割なのだ。
『浮かびゆく男』── これは、怪異じゃない。たましいの現象論だ

最後に紹介するのは、2018年の『浮かびゆく男』。これは初の邦訳で、今回の文庫でようやく読めた作品だった。
体重計に乗るたびに数字が減っていく。食べても減る。着込んでも減る。筋トレしても変わらない。にもかかわらず、外見はまったく変わらない。
この奇妙な現象が示すのは、ただ一つ。
「主人公の身体は、重力から解き放たれつつある」──ということ。
これだけ聞くと、昔のキング作品『痩せゆく男』のパラレル的な話かと思うが、まったく違う。怖くない。むしろ優しい物語だ。
ただのSFかと思いきや、そこから広がっていくのは、とても地に足のついた、そして心に沁みる人間ドラマである。スコットという男が、自らの終わりを予感しながら、同時に和解と連帯をつくり出していく。
彼の浮遊は、社会の分断を乗り越える象徴となり、ラストの夜空への浮上は、もはや死ではなく上昇なのだ。
これは、キング作品の中でも異色でありながら、たしかにキングらしい物語である。かつて『痩せゆく男』で体重減少が呪いだったキングは、ここではそれを「祝福」に変えてしまった。
恐怖ではなく、癒しの寓話。物理的な軽さが、精神的な自由を意味するなんて、なんとも詩的ではないか。
キングという作家がホラーの枠にとどまらず、やがて物語そのものになっていった──そんな歩みの最果てのような作品である。
キングとは、「解けなさ」を描く語り手である
三篇を通して思ったこと。それは、スティーヴン・キングという作家が「謎を解く」人ではなく、「謎と共に生きる人間の姿」を描く語り手なのだということだ。
『ライディング・ザ・ブレット』では、自分自身の中に潜む恐怖や罪悪感と向き合う。
『コロラド・キッド』では、解けない謎を語り続けることの意味を教えてくれる。
『浮かびゆく男』では、理解を超えた出来事の中に、優しさや連帯を見出していく。
いずれも「不可解なもの」との関係性を描いているのだ。そしてそこにこそ、キングの物語の魔法がある。
50年にわたって、化け物を描き、怪奇を語り、恐怖を生んできたキングが、今や描いているのは、「人はなぜ語るのか」というもっと根本的なテーマなのかもしれない。
そう考えると、この『コロラド・キッド 他二篇』は、「スティーヴン・キング入門」であり「キング思想の精髄」でもある。
ミステリ好きにも、ホラー好きにも、文学好きにも刺さる言葉と謎の宝箱のような一冊だ。
何より、読み終わった後に「人間って、そんなに完璧じゃないけど、そこが面白いよね」と思えるようになる。
謎を完全に解かなくても、生きていける。
選択を間違えても、それを抱えていけばいい。
重力から解放されなくても、気持ちを軽くすることはできる。
それが、この本のいちばん素敵なところだと思う。