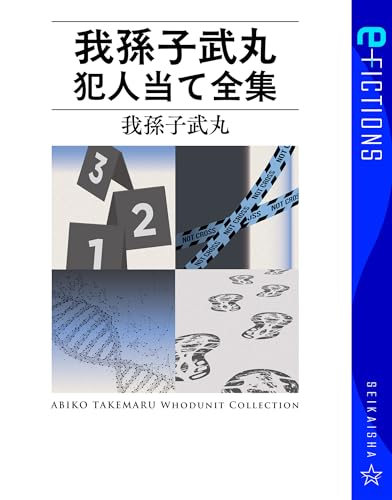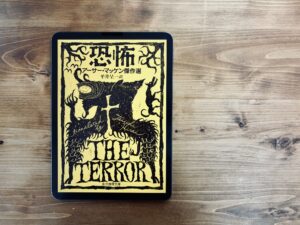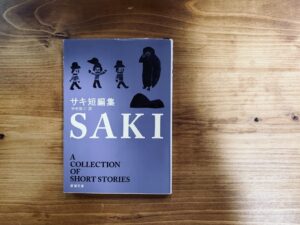2025年もミステリ漬けの一年だった!
新刊も旧作も、国内も海外も、長編も短編も、手あたり次第に読みまくったけれど、それでも「まだ足りない!」と叫びながら年末を迎えている。
本格ミステリ、イヤミス、警察小説、ホラーミステリ、特殊設定系……今年もジャンルの幅はさらに広がり、読めば読むほどミステリーの奥行きにうなされた。
「こんな構造思いつかないだろ」「そう来るか!」と深夜に唸り、早朝にため息をつき、何冊も布教したくなる傑作と出会った。
というわけで今回は、『2025年に刊行されたミステリー小説』の中から、特に面白かった53作品をセレクトしてご紹介したい。
有名無名は関係なし。とにかく「読んだ自分がテンション上がったかどうか」を基準にしているので、かなり偏ってるかもしれないが、それも含めて楽しんでほしい。
この1年、最高だったミステリたちに感謝と愛を込めて。
1.麻根重次『千年のフーダニット』
──時間を閉じた未来の密室で、論理と進化が交錯する
1000年後の未来で目を覚ましたとき、仲間のひとりはすでに死んでいた。
この一文だけで心をつかまれる。
『赤の女王の殺人』でデビューした麻根重次の第2作『千年のフーダニット』は、いわゆる「時間SF×本格ミステリ」の枠に収まりながらも、予想を大きく裏切ってくる科学の怪作である。
まず、舞台設定からすでに面白すぎる。1000年のコールドスリープ実験に選ばれた7人が未来で目覚める。しかしその中の1人が、ポッドの中でミイラとなって発見される。時刻表も使えなければ、目撃証言も期待できない。
なにせ、事件は1000年間誰の目にも触れずに密閉されていたのだから。この時間そのものを密室とする発想が、まず新しい。
このやりようがない状況で、誰が、どうやって、なぜ殺したのか。ミステリ好きとして、こんな設定をスルーするわけにはいかない。
進化生物学が導くSFミステリの地平
だが、本作が真にユニークなのは、ここから先だ。フーダニット(誰が?)に見せかけておいて、物語の核心はホワイダニット(なぜ?)にある。
犯人が何を思って行動したかではなく、どのような動機が、あるいは執念が、その犯罪を必然としたのか。
作者は進化生物学出身。なるほど、と思わせられるのが、時間を扱う手つきの丁寧さだ。物理トリックもロジックも、無理なく、でも大胆。単に未来を舞台にするのではなく、人類がこの1000年でどう変わったのかが、事件の背景にがっつり絡んでくる。
ミイラ化した仲間、顔のない死体、そして人類史上のとある分岐点。すべてがリンクした瞬間、ここまで考えてたのか…!とため息が出る。
しかも、学術的すぎず、ストーリーはあくまでサスペンスとしてテンポよく進むのもありがたい。このバランス感覚が絶妙で、読んでいてまったく息切れしない。
最終的に明かされる犯人は、意外性というより論理の果てに自然と立ち上がってくる存在であり、その動機には戦慄すら覚える。人間の欲望と進化の方向性が、ここまでスムーズにミステリに落とし込まれている作品は珍しい。
そして何より、これはちゃんと本格ミステリなのだ。ちゃんと伏線があり、ヒントがあり、ロジックで解ける。
SF設定に寄りかからない潔さ。科学を使っても、ご都合主義にはならない。
これは、ミステリに対するリスペクトの表れであり、麻根重次という作家の最高の心意気だ。
1000年の密室で暴かれるのは、人類そのものの罪。
 悠木由良
悠木由良生物学を武器にした新しいフーダニット。ここに、SFミステリの次世代がある。
2.梓崎優『狼少年ABC』
──論理と感情が交錯する、奇跡の4編
梓崎優が帰ってきた。それだけでもう感無量だが、届けてくれたのがこの『狼少年ABC』というのだから、本当にうれしい。
これは全4編の短編集で、どれも青春のきらめきと、ちょっとした傷、そしてミステリらしい小さな謎に満ちている。
たとえば表題作の『狼少年ABC』。舞台はカナダの森の中、大学生3人が狼の調査をしているのだけど、退屈な時間のなかで会話が転がり、ある人物の嘘が暴かれていく。
最初はただの雑談っぽいのに、気づけば推理ゲームが始まり、最後には関係性がガラッと変わってしまう。その変化が、地味だけどものすごく効いてくる。
推理は、青春の選択をあぶり出す装置だ
梓崎作品は、謎解きがただの事件解決では終わらない。真相にたどり着いた瞬間、登場人物たちの関係が崩れたり、逆に深まったりする。謎を解くこと=人生の分岐点、という構図が本当に巧い。
『狼少年ABC』の魅力はここにある。トリックや密室や犯人当てといったミステリ的快楽は確かにあるが、それ以上に、登場人物たちの心の機微や関係の変化が繊細に描かれていて、それが謎とぴったり噛み合っているのだ。
舞台設定がかなりグローバルなのも面白い。カナダ、ハワイ、日本。普通なら「非日常のミステリ」になりそうな場所なのに、そこで描かれるのはきわめて日常的な葛藤ばかりだ。
「家族」「友達」「未来」「後悔」──そんなテーマを、異国の空気感に包んで描くことで、逆にユニバーサルな切実さが際立っている。
特に好きなのは『スプリング・ハズ・カム』。卒業を控えた中学生たちの間で交わされる何気ない会話と、埋められたタイムカプセル。
そこから出てきた犯行声明と過去のいじめが交錯する中で、誰がどんな選択をしたのかが明かされていく。
謎が解ける瞬間よりも、そのあとに訪れる沈黙のほうが重く響いてくるようなミステリだ。
『叫びと祈り』から時間は流れたが、梓崎優は変わっていない。
いや、変わらないまま深まった。
再びこの声が届くようになったことを、心からうれしく思う。
エモい青春とロジカルな推理の両立、それが12年ぶりのこの一冊に詰まっている。



謎を解いてしまったら、もう昔には戻れない。その切なさこそが梓崎優の本質だ。
3.我孫子武丸『我孫子武丸犯人当て全集』
──フェアプレイの原点に帰れ
『我孫子武丸犯人当て全集』は、その名のとおり、我孫子武丸が長年書き溜めてきた犯人当て短編を集めたもの。
タイトルだけ見ると地味そうだけれど、開いてみると「犯人は誰か?」というシンプルなルールが、これほど濃密で頭を使わせてくるのかと驚かされる。
収録作は『盗まれたフィギュア』『完全無欠のアリバイ』『記憶のアリバイ』『漂流者』『幼すぎる目撃者』。
すべてが「問題編→解決編」という形式で、問題編を読み終えた時点で答えを推理できるようになっている。
京都大学推理小説研究会の遺伝子が息づく、フェアプレイの標本箱
我孫子作品の元ネタになっているのが、彼が所属していた京都大学推理小説研究会の厳格なルール。
要するに、「地の文に嘘は書かない」「論理で解けなきゃ意味がない」「偶然やひらめきに頼るのは禁止」という、ガチガチのフェアプレイ仕様だ。
最近はキャラ重視・心理重視のミステリも多いけれど、こういうガチ推理一本勝負を読むと、逆に新鮮に感じられる。
「なぜそれを使わなかったのか」というシンプルな謎に、消去法と状況証拠、犯人心理までを織り込んで詰めていく過程が実にスリリングで、論理好きにはたまらない快感だ。
この手の犯人当て短編は、今ではあまり見かけないジャンルになってしまったけれど、本書を読むと「こういうミステリもちゃんと面白い」と素直に思える。
論理だけで戦うパズルのような物語。それでいて、我孫子武丸らしい軽妙な語りや、意外と人間味のある動機づけもあり、硬すぎず読みやすい。
なにより、手ごたえのある謎がきっちりと用意されていて、きちんと解かれる。そこがいいのだ。
推理したくなる気持ちに火をつける、ワクワクする心に直撃の短編集。



これぞ、犯人当ての醍醐味。地味だけど、めちゃくちゃ頭を使わされるミステリの良心。
4.野島夕照『片翼のイカロス』
──空飛ぶ富豪とヘリの衝突。バカミスを超える真剣勝負
空を飛ぶことを夢見た男が、本当に空を飛び、ヘリコプターと衝突して死んだ。
この一文を読んで「はいバカミスね」と即断するのは早い。『片翼のイカロス』は、その不条理な導入に反して、異様なまでに真面目なロジックの解体ショーである。
第16回ばらのまち福山ミステリー文学新人賞優秀作に選ばれたこの作品、著者はなんと現役の保険会社社長。しかも1962年生まれ。
そんなビジネス畑から突如現れた新人が描くのは、空を飛んでヘリとぶつかった富豪の謎だ。
物理法則への反逆から始まる、真面目すぎる珍奇
舞台は巨大一族が住む洋館、探偵役は新人メイドの麻琴。とにかく情報量が多い。
家系図は20名超、登場人物はくせ者揃い、テーマには寄生性双生児、脳死出産、遺産相続、秘匿された恋愛関係と重いネタがずらり。なのにこの物語、たったの268ページで完結している。とんでもない密度である。
いわゆるバカミスとは、荒唐無稽な仕掛けやトリックで笑わせるジャンルだが、本作は笑いに逃げない。むしろそのバカバカしさをガチで論理的に解きほぐしてみせる。「空を飛んだ? 本気で言ってるの?」という前提に、真正面から突っ込む潔さ、大好きだ。
しかも島田荘司の選評にもある通り、この作品は御手洗シリーズへの明確なリスペクトと対話を感じさせる構造を持っている。「奇想×物理トリック×大真面目」の方程式は、ある意味で新本格の伝統そのものだ。
さらに注目したいのは、語り口の軽快さだ。ラノベ風のテンポと会話文、メイド探偵の視点によるツッコミの効いた文体が、トリックの重さやテーマの暗さを中和している。
読後感はどこか爽やかですらある。なんだこの設定……と思いながらページをめくる手が止まらず、最後には「まさかそれで理屈が通るとは……」と呆気に取られる。まさに奇想が天を動かすタイプの一作だ。
新人作家らしからぬ完成度の高さと、奇抜さをねじ伏せるロジックの腕力。
これを読まずに「最近の本格は元気がない」なんて言ってはいけない。
空を飛んで死ぬというバカ設定に、ロジックで真っ向勝負。これは立派な本格だ。



バカミス? いいえ、これはガチミスです。
5.櫻田智也『失われた貌』
──顔のない死体が照らし出す、ささやかな人生のかけら
山奥の川べりで見つかった男の死体は、顔も、指紋も、歯型すらも消されていた。
警察官の執念をもってしても、身元特定が困難なその遺体。しかし「これは父かもしれない」と訴えに来た少年の登場から、物語はゆっくりと歯車を回し始める。
櫻田智也の初長編『失われた貌』は、警察小説のフォーマットを借りながら、本格ミステリのロジックと、人間模様の繊細さが高次元で絡み合った一作だ。
主人公は、新任係長の日野雪彦。出世街道から外れ、胃薬を抱えて地味な現場を踏み続ける、どこにでもいそうな中年刑事である。けれど、そんな日野の地に足の着いた視線こそが、バラバラだった事件の断片を繋ぎはじめる。
誰もが見落とした断片が、やがて全体像を描き出す
物語は、ひとつの殺人事件を軸にしながら、「不審者の声かけ」「ゴミの不法投棄」「古びたアパートでの変死」など、小さな事件や雑音のような出来事を丁寧に拾い上げていく。
序盤では何気ないやりとりに見えた会話、同僚とのささやかな食事、家庭での軽口。そのどれもが後に意味を持ちはじめ、ラストでは怒涛のような伏線回収につながっていく。この構成力は本当に素晴らしい。
大げさなどんでん返しがあるわけではない。ただ、小さなパズルのピースが音を立てて収まっていく感触がある。
そして面白いのは、やはり「動機(ホワイダニット)」の扱いだ。なぜ死体は「顔」を失ったのか。なぜ徹底的に身元を消さなければならなかったのか。
その理由に辿り着いたとき、物語はミステリから、ひとつの人間の生と死、関係性の物語へと変貌する。暴力や悪意ではない、別のベクトルの理由がそこにあるのだ。
終盤、日野がかけるある人物への言葉は、事件の解決以上に深く刺さる。それは警察官の言葉であると同時に、人間としての誠実さのにじむひとことだ。
謎が解けたあとに残るものが、事件のスッキリ感ではなく、どこかあたたかくて、少し寂しい気持ちなのがこの作品らしい。
謎を解いたのは論理。でも救ったのは、思いやりだった。



論理の積み上げが、なぜか人の温かさに変わる。そんなマジックだ。
6.森バジル『探偵小石は恋しない』
──恋は、証拠にならない。でも、トリックにはなる。
タイトルと表紙だけ見ると、軽妙なラブコメ調の探偵ものかと思う。
依頼の9割が不倫調査、探偵は恋をしない、事務所の面々はどこかポンコツ……とくれば、よくあるゆる系キャラミスだと油断するのも無理はない。
でも、森バジル『探偵小石は恋しない』はそんな表層を見事にひっくり返す。これは恋と視線をめぐる、精緻なトリックの塊なのだ。
主人公の探偵・小石には、恋をしている人の胸から赤い矢印が見えるという能力がある。恋の向きが見えるという、ややファンタジーめいた設定だが、使い道は非常に地味。
証拠は押さえられなくても、誰が誰に好意を持っているかが視える──それだけで不倫調査は驚くほど効率化される。
だが、この矢印が万能な真実の鏡ではないことが、物語を大きくかき乱していく。
日常ミステリの皮をかぶった認識の罠
小石と助手の蓮杖。二人の探偵コンビは、典型的なボケとツッコミのように見える。しかし、物語の後半で判明するのは、認識そのものが揺らいでいたという事実だ。
作中で描かれる些細なことがの断片が、絶妙にフェイクとヒントの両方を担っていたと気づかされたとき、その伏線回収は爽快のひとこと。
そして何より見事なのは、恋の矢印という便利すぎるギミックが、最後に裏返される点だ。恋している誰かが、誰に向けていたのか。それを読み違えると、探偵すらも嘘をついてしまう。
タイトルの『探偵小石は恋しない』は、アロマンティック的な自己定義に見えて、実は終盤にかけて多重の意味を持ちはじめる。
恋しないことは強さなのか、それともただの自己防衛なのか。観察者としての冷静さと、当事者になれない寂しさ。そのどちらでもあるからこそ、このタイトルは読後に深く刺さる。
この作品が描くのは実のところ、愛が絡むとミステリは途端に複雑になるという真理だ。
不倫も片思いも執着も、すべてが感情という矛盾と欲望の塊で、証拠は出てこないけれど、確かに人を動かしてしまう。
恋の向きが見えるという能力は、便利なようで不完全だ。
なぜなら、見えているのは感情であって、覚悟ではないからだ。
そのズレを突きつけられたとき、この物語は一気に色を変える。
ラブコメ風の顔をした論理の爆弾。



恋と謎が交差する、破壊力抜群のトリックをぜひ。
7.彩藤アザミ『正しい世界の壊しかた:最果ての果ての殺人』
──幻想世界の崩壊。
イバラに囲まれた閉ざされた村ドルノは、私有財産も争いもなく、みんなで子どもを育て、預言者に従って暮らす理想郷。
その村で育った少女・未明は、ある日、外の世界から迷い込んできた瀕死の少年キフカを助けてしまう。
彼は、貧困も暴力もある現実を語るが、未明にとってそれはまるで異世界の話。やがて村の精神的支柱である「一世さま」が密室状態で殺される事件が起き、村は動揺。
疑いの目は唯一の異分子=キフカへと向けられるが、それをきっかけに、正しいと信じられてきたこの世界の綻びが一気にあらわになっていく。
ユートピアに隠されたディストピアの刃
この物語が面白いのは、ファンタジーの衣を着つつ、ちゃんと本格ミステリであることだ。幻想的な設定はただの装飾じゃなく、世界のルールそのものがロジックとして物語に組み込まれている。
「眠りの御業」「イバラの迷宮」といった不思議な要素も、実は緻密に仕掛けられたトリックのピース。中盤まではどこか寓話めいているが、真相が見えてくると、一気にジャンルが裏返るのだ。
主人公・未明が正しい世界にひびが入るたびに揺れる心は、ミステリの謎解きと並行して、成長物語としても効いている。良い人たちの集まりだった村が、外の価値観にさらされることでむき出しにする排他性や恐怖。それらが一気に爆発する終盤の展開には、ディストピアもの特有の絶望と解放の両方が詰まっている。
結末は、世界の構造そのものがガラリとひっくり返る鮮やかな反転。タイトルに込められた意味が、読後にずしりと響いてくる。
M・ナイト・シャマランの映画『ヴィレッジ』や、貴志祐介『新世界より』に心惹かれた人なら間違いなく刺さる、幻想と論理のハイブリッド作品だ。
美しい仮面を剥がした先にあるのは、残酷な現実と、確かなまなざし。



世界観まるごとがトリック。これぞ幻想ミステリの真骨頂。
8.笠井潔『夜と霧の誘拐』
──これは謎解き小説の皮を被った思索の迷宮だ
笠井潔『夜と霧の誘拐』は、シリーズファンにとってはおなじみ、矢吹駆とナディアのコンビが活躍する本格ミステリ……というよりは、ミステリの枠を借りた、超重量級の思想小説に近い。
ページ数も厚ければ中身もギュウギュウ。ミステリ好きとしては、この読むのに体力がいる感じにワクワクしてしまう。
舞台は1978年のパリ。かつて『哲学者の密室』で事件が起きたダッソー家で、ふたたび新たな事件が幕を開ける。今回は「間違えられた誘拐」と「学院長の射殺」という二つの事件が同日に発生。
これだけでもおいしいのに、そこに絡んでくるのが、矢吹らしいズレと二重化のトリック。しかもこのズレは、ただの時間差とかじゃなく、認識や視点のズレにまで踏み込んでくる。
ズレて、重なって、爆発する。哲学とミステリの二重奏
さらに面白いのが、この事件群の背景にハンナ・アーレントを思わせるユダヤ人女性哲学者・カウフマンが登場し、矢吹と真っ向から「絶対悪とは何か」について哲学バトルを繰り広げるところだ。
アイヒマン裁判やパレスチナ問題まで出てくるあたり、さすが笠井潔、容赦がない。だが、それがいい。
もちろん、ミステリとしてのキモもしっかり押さえてある。誘拐と殺人の時間の仕掛けは、時刻表トリックの現代版とも言える精密さだし、終盤のあの真相には、おおっと声が出た。
物理的にもガチガチのトリック、観念的にもヘビーな哲学という、ダブルで胃にくる内容だが、その分読み応えは抜群。
ページ数も内容も重たい。だが、それに見合うだけの報酬がちゃんと用意されている。矢吹駆の謎解きとは、世界そのものの構造を疑い直す行為なのだ。
それが、このシリーズの核心であり、『夜と霧の誘拐』はその精度と射程において、現時点での最高到達点である。
知と論理が交差する異端の鈍器本。



事件は常に二つある。そのズレこそが真実を語るのだ。
9.北山猛邦『神の光』
── 消えゆくもののロマンを描く、物理トリックと哀しみの融合
北山猛邦の短編集『神の光』は、巨大なものの消失という、とびきり視覚的でロマンチックなテーマに挑んだ作品集である。
城、街、山小屋、神社、そして夢の中の館──消える対象はそれぞれ異なるが、どの物語も共通して、物理トリックの魅力とそこに込められた感情の温度差に驚かされる。
収録作は5編。戦時下のレニングラードを舞台に、狙撃手のスコープの中にあった館が屋敷が一夜にして消える『一九四一年のモーゼル』。ラスベガスで大勝ちした男が目を覚ますと、街ごと消えていた『神の光』。
ポーの未完作と重なるように山小屋が消える『未完成月光』、ひとつのトリックで異なる時代に起きた三つの消失事件を解き明かす『藤色の鶴』、そして夢の中で皆が同じ館の崩壊を体験する『シンクロニシティ・セレナーデ』。
どれもタイトルからして詩的だが、中身は意外なほど硬派な本格ミステリである。
見えなくなっただけなのか、それとも世界がごっそり消えたのか
北山猛邦といえば、「物理トリックの魔術師」とも呼ばれる作家だが、本作ではその技巧がただのパズルにとどまらず、過去や人の想いと結びついて物語全体を温めている。
たとえば『神の光』では、ギャンブルに取り憑かれた男の栄光と没落が、まるで蜃気楼のように描かれる。砂漠の幻に街が消えるという奇想天外な発想は、驚きだけでなく、どこか切なさすら呼び起こす。
『一九四一年のモーゼル』もまた、消さなければならなかった人々の選択が胸に迫る。ミステリである以上、トリックの種明かしはあるのだけれど、それを知ってなお「それでもこうするしかなかったのか」と感じさせる余韻が残る。北山作品の持ち味は、まさにこの感情を帯びた理屈だ。
そして極めつけは、ラストを飾る『シンクロニシティ・セレナーデ』。人々が同時に共有する夢、それも館が崩れるという現象を、きっちりロジックで解明してしまうのだからすごい。
幻想のような題材を、合理の土俵で鮮やかに決着させるセンス。こんなの北山猛邦にしかできない。
消えるのは物理的な対象だけじゃない。記憶、過去、そして大切な何かも、そっと見えなくなっていく。



ステリでありながら、どこか詩的。物理と幻想の境界を曖昧にする短編集だ。
10.『●●にいたる病』
──あの衝撃から35年、狂気と叙述のDNAを受け継ぐ者たち
我孫子武丸のデビュー作『殺戮にいたる病』が世に出て35年。
それを記念して企画されたこのアンソロジー『●●にいたる病』は、タイトルのとおり、現代の作家たちがそれぞれの「病」を描く短編集だ。
集まったメンバーは、叙述トリックの名手からホラーの最前線を走る作家までバラエティ豊か。
その結果、「狂気」「欺瞞」「執着」といったテーマが、各作家ならではの切り口で描かれている。
「いたる病」の新しいかたち
たとえば我孫子武丸本人の『切断にいたる病』は、ど真ん中のセルフオマージュ。グロさとブラックな笑いが絶妙に絡み合い、原点にして今なお現役な筆の冴えを感じさせる。
神永学の『欲動にいたる病』は、学生の恋愛と殺意が紙一重でつながる青春スリラー。恋が引き金になる衝動を、ストレートに、そして怖く描いている。
背筋『怪談にいたる病』は、ネット怪談好きにはたまらない一本。前半の淡々とした語りから、後半でゾワッとくる感覚は、まさに効いてくるタイプの怪談だ。
真梨幸子の『コンコルドにいたる病』は、作家の苦悩とイヤミスの真骨頂が炸裂。叙述トリックを依頼された作家が、どこまでも沈んでいく様がリアルで笑えない。創作の闇、深い。
矢樹純『拡散にいたる病』は、因習とネットが絡み合う呪いのメディアミックス。設定が濃くていい。情報の伝播と穢れの拡散が重なって、読み終えたあと効いてくる。
そして歌野晶午の『しあわせにいたらぬ病』。唯一タイトルが反転形になっているのが象徴的で、内容も相当きつい。老女の死を巡るこの話、途中まで見えていた構図がラストでひっくり返され、冷たいものが残る。歌野晶午らしい叙述の妙味がしっかりある。
全体として、このアンソロジーは『殺戮にいたる病』が切り開いた狂気とミスリードの文学が、時を経てどう深化し、ジャンルを越えて広がったかを体感できる一冊だ。
しかも、ただの追悼企画やパロディではない。
ミステリとホラーの境界線があいまいになった今こそ、この系譜が必要なんじゃないかと思うのだ。
狂気と叙述を武器に、35年の進化を見せつけたオールスターメンバー。



「病」にいたる、それぞれの地獄。それでも読みたくなる中毒性。
11.山口未桜『白魔の檻』
──ガスと霧の二重密室
北海道の山奥にある小さな病院。そこで起きたのは、ただの殺人事件ではなかった。
舞台は過疎地の「更冠病院」。主人公の研修医・春田芽衣と、論理重視の指導医・城崎響介は、地域医療実習の一環でこの地を訪れる。
しかし到着直後、大地震と濃霧が発生。さらに火山性の硫化水素ガスが立ち込め、病院は外界と完全に遮断されてしまう。いわば〈毒ガス密室〉である。
冷徹な医師探偵と、命の重さをめぐる倫理
その密室の中で、首を切断された遺体が見つかる。生存者は87名。
病院という場で起きた殺人に加え、階下から刻一刻と上がってくるガスにより、生存可能エリアは徐々に狭まり、緊張感は増す一方。サバイバル×本格ミステリ、しかも医療の現場という、他にない組み合わせが本作の大きな武器である。
とくに面白かったのは、この「硫化水素」という動く密室の設定だ。階層ごとに安全圏が減っていくため、犯人の行動範囲やアリバイがリアルタイムで変動する。まさに沈みゆく船のような状況で、探偵役の城崎は冷静な頭脳を駆使して事件の真相に迫っていく。
そんな彼もまた、ただのロジックマシンではない。命を扱う医師としての葛藤を抱えており、誰を助けるべきかという究極の選択を迫られる瞬間もある。
合理と情、探偵と医師。その狭間に立つ彼の姿に心を揺さぶられた。
この作品に漂うのは、絶望ではない。むしろ、それでも命を救おうとする意志の物語だ。
閉ざされた空間で暴かれるのは、人の弱さだけじゃない。
ギリギリの状況でも、誰かを守ろうとする心が、かすかに光を放っている。
動く密室と命の天秤が、冷静さの奥にある激情を炙り出す。



ガスが迫るなか、真相と倫理の酸欠ギリギリまで追い詰めてくる。
12.衣刀信吾『午前零時の評議室』
──閉じ込められた裁判員たちが挑む、本当にあったら怖い法廷スリラー
裁判員に選ばれた7人が、謎の密室に閉じ込められる。
午前零時までに正しい評決を出さなければ、全員死ぬ。
『午前零時の評議室』は、そんなデスゲーム設定の皮をかぶった、極めてリアルな法廷ミステリである。
著者は元・日弁連副会長という本物の弁護士。だからこそ、本作に漂うリアリティは尋常ではない。登場人物たちは裁判の素人ながらも、議論を重ねるごとに証拠や合理的推論に基づいた「本物の評議」へと至っていく。
過激な導入とは裏腹に、展開は驚くほど地に足がついており、むしろ『12人の怒れる男』に近い空気感すらある。
デスゲーム×裁判員制度=プロシージャル本格
さらに面白いのが、もう一つの軸である外側の捜査パートだ。ベテラン弁護士・羽水が調査を進める中で浮かび上がるのは、ある被害者が「片方の靴下だけを失っていた」という些細な謎。
この違和感を見逃さず、事件全体を覆す鍵として機能させていく展開は、まさにプロの手腕。終盤もひっくり返しの連続で、その手があったか!と思わせるロジカルな構成が好きだ。
ありがちなキャッチー設定頼みではない。むしろ、デスゲームというジャンルを逆手に取って、法的手続きの重要性や、司法制度が抱えるリアルな葛藤を浮き彫りにしている点が、本作の真骨頂だと思う。
登場人物たちの思考はきわめて論理的で、誰かの感情に流されるのではなく、あくまで証拠と矛盾が突破口を開くのだ。
ラストまできっちり引っ張り、しかも終わってからもう一度最初を読み直したくなる伏線の張り方も鮮やか。
現役弁護士が放った、法廷ミステリの新しいスタンダードだ。
リアルさが桁違い。論理の重みが命を懸けた議論に変わる瞬間を見逃すな。



デスゲームの仮面をかぶった、ガチの司法ミステリだ。
13.織守きょうや『ライアーハウスの殺人』
──犯人が失敗するところから始まる倒叙ミステリ
『ライアーハウスの殺人』は、犯人視点で描く倒叙ミステリなのに、犯人の殺人計画が最初からうまくいかないという、斜め上の発想から組み立てられた作品だ。
舞台は孤島の館、登場人物は全員クセ者、しかも全員が何かしらの嘘をついている。つまり、「館もの」「クローズド・サークル」「倒叙ミステリ」「全員嘘つき」が合体した、なんとも欲張りな構造である。
主人公の彩莉は、かつて自作小説をネットで酷評され、偽の新人賞受賞通知まで送りつけられた過去を持つ。その恨みを晴らすため、加害者たちを孤島の来鴉館に呼び寄せ、自作小説のトリックそのままに殺人を再現しようとするのだが、いざ決行という朝、殺す予定のターゲットがすでに死んでいる。
しかも自分はやっていない。この時点で、計画は完全に崩壊。
復讐どころか、自分が狙われる側かもしれないという疑念とともに、彩莉のドタバタ推理劇が始まる。
嘘とコントとどんでん返しの密室劇
犯人なのにヘマばかりする彩莉が、とにかく愛おしい。PCに殺人計画を保存してたり、隠し通路の鍵をかけ忘れたり、メイドに喋っちゃいけないことをうっかり話しちゃったり。
どう考えても抜けすぎてるけれど、そのポンコツっぷりが逆にテンポのよさにつながっていて、笑えてサクサク読める。
そして何より面白いのが、登場人物が全員なにかしら嘘をついてるという構造だ。刑事役、霊能者役、メイド役……みんなそれぞれ役割を演じているのだが、その裏に別の目的や素性が隠れていたりする。
嘘の層が何枚も重なっていて、「誰が、どの段階で、どこまで嘘をついてるのか」を考えるだけでも楽しい。
作中で展開されるトリックは、彩莉がかつてネットで酷評された自作小説の内容そのまま。つまり、自分の過去と向き合う形で犯行に踏み切っているわけで、その構図自体がすでにちょっと切ない。
登場人物それぞれが嘘をつき、その嘘が二重三重に絡み合い、事実の輪郭があいまいになっていく。
犯人も被害者も何者かを演じている以上、最後に暴かれるのはトリックだけでなく、人間の本性そのものだ。
「倒叙」「館」「全員嘘つき」──好きなワードがあるなら、ぜひ一読を。



ミステリでやれることは、まだまだある。そんな挑戦を、肩の力を抜いて楽しめる一作だ。
14.小倉千明『嘘つきたちへ』
──思い出話のはずが、喉の奥に苦い後味を残す
同級生3人が集まって、居酒屋で昔話。そんなありふれた再会から始まるのが、表題作『嘘つきたちへ』だ。
小学校時代の王様のような少年・翔貴の事故死について語るうちに、あれ?と思う違和感が少しずつ積もっていく。記憶が食い違い、誰かが何かを隠している気配が濃くなっていく。
それでも話は進み、やがて「本当はどうだったのか」が顔を出しはじめる。その瞬間、さっきまでの懐かしさが一気に引っくり返るのだ。
あの頃の話をしようか。でも、本当にあったことだけを。
全部で5編。それぞれテーマもトーンも違うけれど、どれも「語られること」と「隠されていること」のズレを軸にしているのが面白い。
生放送中のラジオ番組に爆弾みたいなメールが届く『このラジオは終わらせない』、赤い糸が見える能力を持つ女性の話『赤い糸を暴く』、学校の保健室で起きた地味だけど謎めいた事件『保健室のホームズ』など、バリエーションは豊富。でも根っこではどれも、言葉のすき間にあるものが大事な鍵を握っている。
語り手が何を語るかじゃなく、語らないか。あるいは、語っているようでズレているか。このズレの仕込み方がうまい。
だから、ただのどんでん返しとかラスト一行では終わらない。「あれ?」「もしかして」「そういうことか!」とあとから効いてくる感覚がある。
正統派ミステリの型をなぞっているようで、その型の裏側にある感情や弱さにまで踏み込んでいるのが本作の強みだ。しかも、それをひとつのトーンにまとめず、短編ごとにまったく違うアプローチで見せてくる。
人間の怖さ、弱さ、そしてずるさ。
それを浮き彫りにしてしまうのは、いつだって自分のためについた小さな嘘なのだろう。
過去は捏造できる。
心を守るために、人は平気で記憶を塗り替えるのだ。
信頼できない語り手が5パターンで襲いかかる、新時代型・短編連作ミステリ。



記憶は都合よくできている。その事実に、どこかでゾッとするのだ。
15.岡本好貴『電報予告殺人事件』
──モールス信号が鳴らす、死のカウントダウン
19世紀末のロンドン。スチームと煤煙のなか、電報が世界を結びはじめた時代に、本作の舞台はある。
岡本好貴『電報予告殺人事件』は、鮎川哲也賞を受賞したデビュー作ながら、世界観も謎解きもとびきり緻密な歴史ミステリだ。
主人公は、中央電信局に勤める女性電信士ローラ・テンパートン。ある夜、局長室で仕事中だった彼女は、ちょっと目を離した隙に局長の死体を発見する。現場は密室。容疑者は、さっき彼女が案内したばかりの青年。
だが事件はそれだけでは終わらない。翌日、警察署に届いた電報には、新たな殺人の予告が記されていた。
通信が遅かった時代にしか生まれないトリック
この物語の最大の仕掛けは、〈電報〉そのもの。
現代のLINEやメールと違って、当時は手打ちのモールス信号、物理的な中継、配達時間の遅れ──そんな「通信のラグ」こそが犯人の武器になる。
モールスの打ち間違いや、通信記録の改ざんも含めて、情報伝達そのものがトリックの一部として成立しているのが楽しい。
ローラというキャラクターの描き方も魅力的だ。男性中心の社会でプロとして働き、自分の職業に誇りを持っている。そんな彼女が直面するのは、事件だけじゃない。
仕事と人生のバランス、家族との距離、そして恋愛の機微。お堅い本格ミステリでありながら、しっかり今の空気も吸っている。
そして終盤、何気ない一言が意味を変える瞬間が訪れる。世界が一気にひっくり返る、あの感覚。
鮎川哲也賞の名にふさわしい、王道ど真ん中の構成だ。
ガジェットで押すか、ロジックで攻めるか、キャラで読ませるか。
この一冊は、それを全部やってのけた。
通信の時代だからこそ成立した、レトロで斬新なタイムトリックミステリ。



電報=遅れて届く情報が、事件の鍵を握るという発想が天才すぎる。
16.塩田武士『踊りつかれて』
──正義は誰のものか。
ブログに投稿されたのは、ネット中傷の加害者を名指しで告発する文章。
そしてそこには、彼らの名前や住所、勤務先までもが詳細に書き込まれていた。
これは報復か?それとも正義か?
塩田武士『踊りつかれて』は、そんなギリギリのテーマを軸に、SNS社会の歪みを描き出す長編サスペンスである。
曝露されたのは加害者だけじゃない
暴かれる側に同情の余地はないのかもしれない。だが、その加害者たちに制裁を下したのが、被害者を支えていた音楽プロデューサーだと知ったとき、話はややこしくなる。
彼のやり方は完全にアウトだ。でも、その怒りや哀しみがどこから来ているのかが見えてくるにつれ、簡単には断罪できないものが胸に残る。
物語の軸は現代の事件だが、その根っこには昭和の芸能界がある。伝説の歌姫・奥田美月。彼女をめぐる光と影。中森明菜を思わせる造形、ヒット曲の誕生秘話、テレビの裏側──その描写がいちいちリアルで、取材の丁寧さが伝わってくる。芸能界の過去を知る人にはたまらない空気感がある。
そしてラストあるのは、心にズンとくる言葉の数々だ。暴かれたのは加害者の個人情報だけじゃない。復讐者の過去、芸人の苦悩、そして世間の無自覚な暴力性。
誰もが被害者にも加害者にもなり得る社会で、言葉の重みがどれだけ人を追い詰めるかを、まっすぐ描いている。
タイトルの『踊りつかれて』が意味を変える瞬間、胸に残るのはひとすじの願いに近いものだ。
ネット中傷と昭和歌謡が交差する、重くて鮮やかな言葉の物語。



復讐と正義の境界をグラグラ揺らしながら、最後には人間愛に着地する。ずるいくらい巧い。
17.芦沢央『嘘と隣人』
──人は、どれくらいの嘘なら許せるのか
定年退職した元刑事・平良正太郎は、特別な事件に巻き込まれるわけでも、大きな陰謀に立ち向かうわけでもない。
舞台は団地、隣人、ママ友、地域の祭り。けれど彼の周囲には、日常の皮をかぶった、ちょっとした異変が転がっている。
芦沢央『嘘と隣人』は、そんな一見ささやかなご近所トラブルを出発点に、人の弱さやずるさ、そして嘘の本質に迫っていく連作短編集だ。
元刑事のご近所相談が映し出す、人間の複雑な闇
ストーカー気味の元夫に怯える女性。理想の暮らしを手に入れたはずが、マンションの転落事故に巻き込まれる一家。技能実習生の失踪と地域の祭りの騒動。痴漢冤罪と夫婦間の秘密。そして、SNSでの誹謗中傷をめぐる表題作。
どの話もちょっとした違和感から始まり、気づけばその奥にある深い業へと引きずり込まれていく。正太郎の推理は地味だが確実で、事件そのものよりも、人間の言動のほころびを丁寧に拾っていくタイプだ。
この作品の特に好きなところは、物語が解決したあとにも残る妙な後味である。誰が嘘をついていたのか、なぜ黙っていたのか。
正太郎の言葉によって真実は明らかになるが、その真実が登場人物たちの救いになるとは限らない。中には、知らないままのほうが幸せだったと思わされる話もある。
イヤミスという言葉では片づけられない余韻。それは、物語に描かれる嘘のほとんどが悪意ではなく、保身や思いやりのつもりでつかれたものだからだ。
だからこそ、自分の周囲にも似たような空気を感じた瞬間、ゾクリとする。
真相が明かされた後のやるせなさまで含めて、完成された一冊。



日常に紛れ込んだ小さなズレが、やがて決定的な破綻を生む。その描写があまりに巧みだ。
18.五条紀夫『町内会死者蘇生事件』
──生き返らないでください、もう一度殺すのが面倒なんです
とんでもないタイトルだが、中身はかなり本格的。
五条紀夫『町内会死者蘇生事件』は、笑わせにきているように見えて、実のところはロジックに支えられた極めて精緻な特殊設定ミステリである。
舞台は田舎町・信津町。青年団に所属する幼なじみ3人組が、町内会長にして地元の寺の住職・権造を殺害する完全犯罪を実行する……まではよくあるドタバタ劇だが、事件はそこで終わらない。
なんとこの町には「死後24時間以内にある処置を施すと蘇生する」という秘術が存在しており、死んだはずの権造がピンピンしてラジオ体操に出てくる。
不条理設定を本格ミステリの装置に変える仕掛け
この時点でギャグとしか思えないが、設定の作り込みが半端ではない。
「蘇生すると死ぬ前の24時間の記憶を失う」「蘇生には時間制限がある」など、ルールがきっちり整備されており、その条件下で巻き起こる蘇生阻止戦がまさに頭脳戦となる。
殺人を繰り返すわけでも、単純に逃げるわけでもない。誰が蘇生したのかを探る逆ミステリ的な構造と、どうやって蘇生を止めるかというサスペンスが絶妙に絡み合っている。
さらに面白いのは、この荒唐無稽な設定を使って切実さを浮かび上がらせてくる点だ。なぜ権造は何度も蘇るのか。誰が、なぜ、そんな面倒なことをしてまで蘇生させようとするのか。
物語が進むにつれ、コメディの裏にある人間関係の複雑さや、失いたくないという感情の重みが顔を出す。そして迎える終盤、「世界一優しい殺人犯」という言葉に込められた意味が明かされる瞬間には、不意打ちのような感動がやってくる。
章タイトルのパロディやメタ構造など遊び心も満載で、形式面でも飽きさせない。前作『クローズドサスペンスヘブン』同様、五条紀夫はふざけているようで、めちゃくちゃ真剣な書き手であることがよくわかる。
笑って読んでいたら、いつの間にか胸を締めつけられているから不思議だ。
笑ってるうちに泣かされる、変化球ど真ん中の傑作特殊設定ミステリ。



殺したいほど憎い相手と、それでも生きていてほしい誰かが、同じ人物になる不条理。
19.三津田信三『寿ぐ嫁首 怪民研に於ける記録と推理』
──呪いか、トリックか。首のない死体が導く二重の謎
山奥の旧家、謎の婚礼儀式、そして首のない死体。
三津田信三『寿ぐ嫁首』は、そんな王道ホラー風の出だしから一気に引き込んでくる長編ミステリである。
舞台は奈良の山間部にある皿来家。大学生の瞳星愛は、友人・唄子に頼まれて婚礼の介添人として村を訪れるが、そこで待っていたのは「嫁首様」と呼ばれる不気味な山神の伝説と、儀式の最中に起きる首なし殺人事件だった。
しかも現場は密室。さらに村に伝わる数え唄になぞらえた連続殺人が始まり、事件はどんどん怪異めいていく。
土着伝承、数え唄、密室。全部盛りの本格怪異ミステリ
けれどもこの作品、見た目はホラーでも中身はしっかりロジカル。数え唄を使った見立て殺人というガジェットは横溝正史ばりだが、三津田信三はそこでひとひねりしてくる。
ただ唄に沿って殺しているわけじゃない。むしろ唄を信じ込ませることそのものが仕掛けになっていて、その思い込みにまんまとハマらされる。ここに来て「そうくるか!」と唸る人も多いはずだ。
そして後半、探偵役の天弓馬人が登場してからは推理パートが一気に加速する。証拠の解釈を積み上げながら、少しずつ真相に迫っていく展開は、まさに本格ミステリの醍醐味。
返しに次ぐ返しが入り乱れ、どこに着地するのか最後まで予測がつかない。このあたり、読んでいてかなり熱くなる。
もちろんすべてが論理で説明されるわけではない。擬音が不気味すぎる怪異描写や、物理的な偶然にはツッコミどころもある。ただ、それも含めて三津田作品の味だ。
すべてを解明しきったはずなのに、どこかに本物の怪異が残っているような気配が消えない。理屈で割り切れない部分が、逆に物語を深くしている。
ホラーとしても、ミステリとしても、ちゃんと怖くてちゃんと面白い。
見立ての構造、密室トリック、土俗的伝承。どれか一つでも好きなら、この作品はかなり刺さるはずだ。
怪異の顔をした論理パズルを、真正面から殴り合いにいく。
その力技に、しばらく興奮が冷めない。
唄に従って殺されるんじゃない。唄を信じ込ませるために人は死ぬ。その転換が鮮やか。



怪異とロジック、両方とも本気でやってるのが最高だ。
20.貫井徳郎『不等辺五角形』
──友情という名の図形は、最初から歪んでいた
誰が嘘をついているのか、ではなく、誰の真実がもっとも歪んでいるのか。
貫井徳郎『不等辺五角形』は、そんな心理の迷宮を描く意欲作である。マレーシアのインターナショナルスクールで育った5人の幼馴染たちが、30歳を目前に再会を果たす。
しかしその夜、メンバーのひとり・雛乃が殺害される。そして犯人として自首したのは、グループ内で最も穏やかで恋愛に淡泊だったはずの梨愛だった。
記憶と感情のズレが生む、五人の主観ミステリ
物語は、「あの夜に何があったのか」を、残された4人がそれぞれ弁護士に語る独白形式で進んでいく。でも彼らの証言は、誰ひとり同じではない。重成は冷静で客観的な語りを装うが、感情のこじれがにじみ出る。
夏澄は自身を中心に話を構築し、聡也は自分の記憶に過剰な確信を持つ。そして誰の視点からもよく見えていなかった梨愛だけが、すべての証言の死角となる。
5人の関係は、かつての仲良しグループのように見えて、実際はとっくにバランスを失っていた。タイトルが示す『不等辺五角形』とは、そのまま彼らの関係性を示している。誰かが一方的に好意を抱き、誰かが見下し、誰かが距離を取り、誰かが疎外されるのだ。
クライマックスでは、ついに梨愛の視点による独白が始まる。その瞬間、これまでの証言が音を立てて裏返る。
ミステリとしてのどんでん返しというよりも、「その感情を誰も気づいていなかったのか」という人間関係の再定義だ。犯行の動機が、決して劇的でも納得づくでもないからこそ、そのつまらなさが逆にリアルで苦い。
人は他人のことを見ているようで、まるで見ていない。
そして、自分のこともまた、都合のいいようにしか語れない。
この本はそうした主観の闘いが、どんなトリックよりも厄介で、どんな密室よりも深いと教えてくれる。
人間関係は対称じゃない。その非対称こそが、悲劇の引き金になる。



誰かが嘘をついているわけじゃない。でも、その本当は、全部ズレている。
21.水見はがね『朝からブルマンの男』
──論理がほぐす、日常と青春のほつれ目
毎週、決まった曜日に来ては、2000円もするブルーマウンテンを頼んで、しかめっ面で残していく男がいる。
なぜ高いコーヒーを頼んで、わざわざ半分も残すのか? そんな疑問から物語は始まる。
舞台は、桜戸大学のミステリ研究会。部員はたったの二人、1年の冬木志亜と、2年の葉山緑里。
表題作を含む5編の短編からなるこの連作集は、日常の謎ミステリとして、北村薫や米澤穂信の系譜に連なりつつ、現代の空気感をしっかりまとっている。
不機嫌な常連客は、何を隠していたのか?
本作の魅力はなんといっても、変な行動の裏に潜む論理の美しさだ。
例えば冒頭の『朝からブルマンの男』の真相は、意外なほど筋の通ったものだった。変な行動には変な理由がある。だがそれが、筋の通った必然として解き明かされる瞬間は、地味ながら強い快感がある。
加えて、物語の背景に広がるのは、青春期特有のモヤモヤだ。部活動というゆるやかな共同体の中で、志亜は緑里との距離感に悩み、時には自分の存在意義にまで踏み込む。
最終話『きみはリービッヒ』では、その関係性に一つの答えが提示されるが、それはあまりにも静かでささやかなものだ。友情でも恋でもない、だけど確かな結びつき。その曖昧さこそ、大学時代の人間関係のリアルに近い。
収録作のバリエーションも面白い。『学生寮の幽霊』では立ち退き問題を、『受験の朝のドッペルゲンガー』では心理トリックを、『ウミガメのごはん』では、なぜ金曜日の夕食だけ味が落ちるのか?という謎を扱うなど、舞台は地味でも謎の幅は広い。
しかもそれぞれが、どこか寂しさをまとっているのがいい。学生たちが生きている今この瞬間が、謎と一緒にきちんと描かれている。
謎を解くことでしか手の届かない距離や、打ち明けられない気持ちがある。
だからこそ、この物語は、少しずつ成長していく志亜の青春の記録でもあるのだ。
謎をほどくたびに、人の輪郭がくっきりしていく。



論理は冷たい。でも、その使い方はあたたかいのだ。
22.潮谷験『名探偵再び』
──幽霊×学園×論理パズル!ありえない設定を本格に変える
死んだ名探偵の霊と交信して事件を解く。
字面だけ見れば冗談みたいだけれど、『名探偵再び』はそこから本格ミステリの地平をグイッとこじ開けてみせた。
著者・潮谷験は『スイッチ 悪意の実験』や『時空犯』などでも、SF的な舞台設定と論理の共存に果敢に挑んできたが、本作ではとうとう幽霊を探偵にしてしまった。にもかかわらず、ちゃんとフェアで論理的なのがすごい。
主人公は名探偵・時夜遊の甥である高校生・翔。探偵の素養ゼロ、だが承認欲求は一人前。伝説の名探偵を親族に持つという肩書だけでチヤホヤされたいという身も蓋もない理由で、女子校の学園事件に首を突っ込む。
ところが、いざ事件に巻き込まれて命の危機に瀕したところ、30年前に滝に落ちて死んだはずの名探偵・遊の霊が登場。以来、翔は滝壺で幽霊の遊と交信し、現場の情報を伝えて推理してもらうという幽霊安楽椅子探偵スタイルを確立する。
ホームズ×ギャグ×ガジェット=新時代の脱力ミステリ
時夜遊という名前からして分かるように、本作は明確にシャーロック・ホームズのパスティーシュを意識している。滝=ライヘンバッハ、巨悪M=モリアーティ、さらには新聞連載形式など、設定から演出に至るまであらゆる要素にホームズオマージュが仕込まれている。
ただし、トーンは極めて軽妙。探偵は死んでいるし、助手はポンコツ。にもかかわらず、事件はきっちり論理で解決される。このギャップがとても良いのだ。
たとえば、学園内で発生する毒物未遂事件、写真消失事件、密室状況などは、パッと見では無理筋に思える。だが、遊の霊が披露する推理は意外にもオーソドックスで、現代的な道具や人間関係を前提とした今の論理で成立している。
これは明らかに「幽霊という設定をギャグで終わらせず、きちんとミステリに落とし込もうとする著者の意地だ。
そして何より、本作で最も好きなのは、終盤にかけてのガラリとトーンが変わるあの展開だ。ぬるま湯のコメディかと思っていたら、いつのまにか足元の水位が上がってきていて、気づけばしっかりと事件の意味に向き合わされている。
軽さの裏に、硬質な構成がちゃんと埋まっている。これは並のミステリパロディでは到達できない。
そんなバカな、が成立してしまう異能ミステリ。



死んだ名探偵と事件を解くという無茶を、本気の論理でやり切る、超真面目な挑戦状である。
23.若竹七海『まぐさ桶の犬』
──それでも葉村晶は、今日も理不尽な暴力と向き合っている
またか、と思わず笑ってしまうほど、葉村晶は今回も不運だ。
車に轢かれかける、変な依頼が舞い込む、闇の過去がざくざく出てくる。それでも彼女は引き受ける。バイト探偵として、ミステリ書店の売り子として、そして一人の人間として、誰にも任せられない面倒な謎をこつこつと拾い集めていく。
『まぐさ桶の犬』は、約5年ぶりとなる葉村晶シリーズの長編であり、そのタフネスと諦念、そしてスモールスケールな日常のなかに潜む悪意を、これまで以上に濃密に描き出している。
傷だらけの探偵が歩む、ハードボイルドの現在地
葉村晶は、ハードボイルド探偵の系譜に連なりつつも、その身体は脆く、メンタルも決して鋼ではない。風邪を引けば寝込むし、怪我もするし、ひとりでコンビニ弁当を食べるような生活をしている。
それでも、逃げない。面倒だから、嫌いだから、気乗りしないから。そういう理由では済まされない何かに、彼女は突き動かされてしまう。これはもはや、探偵の業としか言いようがない。
事件そのものは大仰ではない。派手なトリックがあるわけでもないし、警察と激突するような展開もない。ただ、登場人物たちの心の奥にある、他人の幸福が許せないという感情が、日常の裂け目を広げていく。
タイトルの『まぐさ桶の犬』とは、まさにその象徴だ。これは「自分は食べないのに、他人にも食べさせない」存在を指す寓話由来の言葉だが、この作品ではまさに、人の幸福や安寧を邪魔する見えない悪意を象徴している。
人の心に巣食う、厄介でどうしようもない業。その描写は容赦がなく、それでいて、どこか悲しみが滲むのだ。
若竹七海の長編は、どれも構成が緻密だが、この本も例外ではない。
短編作家としての腕が光る、伏線の積み上げと回収の巧さ。序盤の何気ない食事会が、後半のクライマックスに直結する流れは見事で、地味なはずの展開が、気づけば全貌を露わにしていく。
個人的に、今作の見どころは葉村晶の限界のなかでの踏ん張りにある。
スーパーヒーローではない。
むしろ疲れていて、いつもどこか痛めていて、それでも少しだけ前に進もうとする。
この姿勢にこそ、現代のハードボイルドのリアリティがあると思うのだ。
暴力は減らないし、人間はわかりあえない。だからこそ、探偵は立ち上がる。不器用でも。



歯を食いしばって生きてる人のための、地に足のついたハードボイルドの名品。
24.古泉迦十『崑崙奴』
──幻のメフィスト作家、24年ぶりの帰還作
メフィスト賞受賞作『火蛾』で読者を煙に巻き、そのまま煙のように消えてしまった古泉迦十が、なんと24年ぶりに戻ってきた。
しかも舞台は8世紀の中国・長安。猟奇殺人、異形の奴隷、内臓を奪う犯人、神仙思想、道教、幻術、民族文化……とにかく濃い。読み始めて5ページで、すごいのが来たと確信した。
物語は、十文字に腹を裂かれた死体が発見される事件から始まる。都では「肝を喰う魔物」の噂が広がり、人々の不安は頂点に達する。
やがて捜査線上に現れるのが崑崙奴(こんろんど)という黒い肌をもつ奴隷たち。人間なのか仙人なのか、そもそも実在するのか。謎が謎を呼ぶ。
世界観の暴力に酔いながら読む、知と幻想のハイブリッド
唐代を舞台にしたフィクションは多くあれど、ここまでの情報密度とリアリティで殴りかかってくる作品は珍しい。
官僚制度、異民族の交流、薬学、風俗、道教の実践、葬送文化、シルクロードの影響……すべてがミステリの伏線として機能していて、歴史資料集を読み込んでる気分にすらなる。
でも安心してほしい。ちゃんと面白い。いや、めちゃくちゃ面白い。
幻惑的な雰囲気はあるが、前作よりはずっと読みやすい。そしてなにより、謎解きがガチである。歴史と呪術のヴェールを一枚一枚はがしていく快感は、本格ミステリのそれそのものだ。
読んでいて何度も感じたのは、「これは本格か? ホラーか? 歴史冒険譚か? いや、全部か!」という混乱。
だが、その境界のなさこそが古泉作品の真骨頂なのだと思う。しかも今回は読者を突き放す感じではなく、ちゃんと誘い込んでくれる。
唐代を選んだ理由も絶妙だ。多民族国家でありながら、神秘と現実が共存していたあの時代は、本格と幻想の両立にはうってつけの舞台装置だ。
これが「いま唐代で起こっている事件」なのだと信じ込ませる説得力。架空と現実、歴史と伝承の境が曖昧になる感覚。
古泉迦十という作家の復活が、単なる話題ではなく事件であることを、本作は証明している。
歴史・宗教・幻想・論理、その全部を燃料にしてミステリとして走りきる、異次元の一作。まさに、書かれたこと自体が事件。



こんなにも重く、奇妙で、情報が詰まりすぎた本格が、ちゃんと面白いってどういうこと?
25.真梨幸子『フジコの十ヶ条』
──拡散する悪意のミーム
「第一条 邪魔な人間は消せ」「第六条 周りはみな敵だと思え」──。
それが伝説の殺人鬼フジコが残したという、謎の成功法則だった。いかにも怪しげな都市伝説めいたこの「十ヶ条」は、なぜかSNSで拡散され、自己啓発セミナーの教材としても使われ始める。
怖いのは、それがただのジョークでは終わらず、現実の殺人や失踪事件とリンクしていくことだ。
自己啓発パロディとしてのイヤミス
主人公・米井富士子は、かつて「殺人鬼フジコ」の事件を追っていた過去を持ち、名前までフジコと重なる女性。現在は地味な日々を送りながらも、DIYと愛猫ヨツバに癒やされる日常にそこそこ満足していた。
しかし、ふとしたきっかけから「フジコの十ヶ条」関連の不審死に巻き込まれ、次第に過去と現在がねじれながら絡み合っていく。
本作が突きつけてくるのは、〈悪意は伝染する〉という不穏な現実だ。殺人鬼という個の恐怖よりも、その思考がミームとして拡散し、誰もが〈加害者になりうる〉構図が気味悪い。
人を操り、搾取し、踏み台にしてでも成功を目指せ──そんな十ヶ条が、現代の競争社会で実際に「使えそう」に見えてしまう皮肉は、痛烈な風刺でもある。
しかもこの物語、誰ひとり信用できない。富士子自身も含め、登場人物たちはみな、都合のいい嘘と歪んだ記憶で自分を守っている。ときに被害者を装い、ときに無自覚な加害者となる彼らの語り。真梨幸子お得意の「信頼できない語り手」という構造が、今回も抜群に冴えている。
極めつけは、「フジコの十ヶ条」そのものが、実は社会のあるあるを悪魔的に言語化したものである点だ。
ポジティブな自己啓発の裏返しに潜む攻撃性や冷酷さを、ここまであけすけに提示してくると、笑っていられなくなる。
なんだか「あなたもフジコの中の一人じゃないのか?」と言われているようで、すごく嫌なのだ。
背中を押すのは天使か悪魔か。成功哲学の顔をした地獄。



共感したらアウト。それがこの物語のルールである。
26.阿津川辰海『最後のあいさつ』
──探偵は演じるもの? それとも、なりきるもの?
30年前、国民的刑事ドラマ『左右田警部補』の最終回を目前にして、主演俳優・雪宗衛が妻殺しの容疑で逮捕される事件が起きた。
けれど彼は、まるでドラマのキャラそのままに振る舞い、記者会見で推理ショーを展開。真犯人として連続殺人鬼「流星4号」の名を挙げ、自らの無罪を証明してみせる。
まるでドラマの探偵がそのまま現実に出てきたかのように。
世間はそのパフォーマンスに騒然となり、雪宗は一躍名探偵として祭り上げられるが、その後はメディアから姿を消す。そして現在、再び同じ手口の殺人が起こり、ノンフィクション作家・風見が調査に乗り出す。
鍵を握るのは、放送されなかった幻の最終回「最後のあいさつ」だ。
フィクションと現実の境界で踊る名優探偵
この作品の肝は、「雪宗は本物の名探偵だったのか? それとも名演技だったのか?」という曖昧さだ。登場時の仕草や口調は、『相棒』の杉下右京を思わせるし、その徹底ぶりには不気味さすらある。
けれど一方で、彼の演技が人の命を救ったのも事実。虚構の中に生きた男が、現実の事件すらコントロールしてしまう構図がなんともスリリングだ。
そして、事件の真相に迫るうちに見えてくるのは、人生そのものを演じる覚悟と、その代償である。雪宗は探偵を演じたのではなく、「最後まで探偵であろうとした」。
そこには計算を超えた狂気と、悲しさと、ほんの少しの希望がある。
終盤、あの最終回の真実が明かされた瞬間、ただの謎解きが一気に劇的なラストへと変貌する。
これは、探偵小説という舞台に捧げられた、ひとつの熱演だった。
推理劇を最後まで演じきった俳優=探偵の美学が刺さる。



役者が探偵を演じるのではなく、探偵として生きることの重さと危うさを描いた異色作だ。
27.藤崎翔『オリエンド鈍行殺人事件』
──笑いとミステリの境界で
ミステリは殺人事件を解き明かすものだ。そんな常識を、これほど愉快に裏切る作品はそうない。
藤崎翔『オリエンド鈍行殺人事件』は、アガサ・クリスティの傑作パロディを皮切りに、ブラックな笑いとぬるりとした人間関係を見せつけてくる短編集だ。
著者は元芸人という異色の経歴を持つだけあって、構成やツッコミのタイミングが絶妙。その笑いの裏に、現代人の孤独や見栄、自意識といったちいさな痛みが潜んでいるのが、ただのコメディでは終わらない理由でもある。
殺人事件どころじゃない人たちの、どうでもいい秘密と生き様
表題作『オリエンド鈍行殺人事件』は、土砂崩れで孤立したローカル列車というクローズド・サークルで殺人が発生する……という筋書きまでは本格ミステリの王道だ。
でも、肝心の乗客たちは、事件の真相よりも自分たちの不倫や過去の黒歴史のほうが気になる様子。どこかズレた会話の応酬にクスクス笑っていると、ラストで予想もしない真相が顔を出す。その落差が心地いい。
その他の短編も粒ぞろいだ。『タイムスリップ・リアリティ』では、亡き親友を救うために過去に戻った男を描くが、ラストにはビターな展開が待っている。タイムリープもの特有の感動へ向かわないあたりが、この作家らしい意地の悪さであり魅力だ。
これらの物語に通底しているのは、「真相はいつだって人間のしょうもなさにある」という信念だ。藤崎作品のトリックは決して奇抜ではないが、どれも人間関係の裏にある卑小な欲望や、自己防衛のための嘘を巧みに浮かび上がらせる。謎解きが最終目的なのではなく、あくまで人間を見るための手段として機能している点が面白い。
読後、殺人事件のことはほぼ覚えていないのに、登場人物たちのズレたやりとりやしょうもない自白だけが記憶に残っている。それがこの短編集の正体であり、真の魅力だ。
ミステリ好きなら笑えるし、そうでなくても「こんな人が近くにいるかもしれない」と思わされる。そんな等身大のブラック・コメディだ。
脱力感の先にある真相は、意外と毒が強め。



殺人事件なんてどうでもいいと思えるほど、人間の小さな恥が面白すぎる。
28.伏尾美紀『百年の時効』
──昭和から令和へ、刑事たちの執念がつなぐ50年
刑事たちが、50年越しでひとつの未解決事件を追い続ける。それだけでグッとくる設定だが、『百年の時効』はそれだけじゃない。
昭和、平成、令和という三つの時代をまたいで、捜査の方法も、警察という組織の在り方も、登場人物の世代交代までもが物語に織り込まれている。これはもう、ほぼ警察大河だ。
始まりは1974年の佃島。一家が日本刀で惨殺され、犯人は4人とされるも逮捕されたのはひとりだけ。事件は迷宮入りし、残りの3人は行方知れずのまま時代は流れる。
50年後、変死体と共に発見された刀と「警察の皆様へ」という封筒が再び過去を呼び戻し、捜査が動き出す。
三つの時代と一本の未解決事件がつくる警察の歴史
昭和パートでは、聞き込みと直感が命の昭和の刑事たちが、熱いバディっぷりを見せてくれる。平成になると、科学捜査の波に組織が揺れ、地下鉄サリン事件や震災といった歴史が空気を変えていく。
そして令和では、若手刑事・藤森菜摘が、最新技術を駆使して遺留品を掘り起こし、1年限定の再捜査チームで過去に挑む。刑事たちが代わっても、事件にかける想いや執念がちゃんと引き継がれていくのがアツい。
そして、この事件は単なる殺人事件ではない。そこには満州引き揚げや身元の乗っ取り、宗教団体の影、テロの芽といった、戦後史の闇がずっしり詰まっている。
「百年」というタイトルも、単なる時効を指しているわけじゃない。これは国家レベルの過去清算でもあるのだ。
最終的に、この本が描くのは法と情のせめぎ合いだ。データと制度だけでは割り切れない何かが、人の手と足で掘り返されていく。
そして、令和の刑事が最後に見出すものは、「誰が」よりも「なぜ」に近い形の真相だ。
そのとき、真に終わるのは事件か、あるいは刑事たちの戦いか。
刑事たちの執念が時代を超えてつながっていく、圧巻の警察ミステリ。



未解決の裏には、いつだって未整理の歴史がある。
29.野宮有『殺し屋の営業術』
── 営業ノルマと殺しの請負が交差するとき
トップ営業マンが、殺し屋に捕まり、営業を始める。
そんなバカな話が、信じられないほどスリリングで論理的に展開していく。
第71回江戸川乱歩賞を受賞した『殺し屋の営業術』は、ビジネス小説と犯罪ノワールの意外な化学反応が楽しい、異色のエンタメ小説である。
主人公の鳥井一樹は、完全歩合制で18年間トップを走り続けた営業マン。スーツの下には誇りと疲弊、そして空っぽの心が詰まっている。
そんな彼が、ある日営業先でとんでもない場面に遭遇する。
営業マン vs 殺し屋!命をかけたノルマ達成ミッション
顧客は皆殺し、犯人は中年と金髪の殺し屋コンビ、そして鳥井はその場で拘束される。ここで逃げるでも泣き叫ぶでもなく、彼が取った行動がすごい。
「ここで私を殺したら、あなたは必ず後悔します」
「あなたは幸運です。私を雇いませんか? この命に代えて、あなたを救って差し上げます」
まさかの殺しの営業を提案し、その場を切り抜ける。
条件は、2週間で2億円分の殺しを受注してくること。
この物語の面白さは、ビジネス書に出てきそうな営業テクニックが、裏社会でも異様にうまく機能してしまうところだ。ドア・イン・ザ・フェイス、イエス・セット、クロージングのタイミングまでばっちり決めてくる。
相手が殺し屋だろうと、ヤクザだろうと、営業のロジックは刺さるのだ。鳥井は殺人請負業界を市場と捉え、競合分析から価格交渉、納期管理まで持ち出して、どんどん仕事を取ってくる。
やがて彼は、生き延びるための営業ではなく、自分の意思でその世界にどっぷり入り込んでいく。血の匂いにも慣れ、死体処理すら「CS(顧客満足度)」の一環と考えるようになる。その変貌ぶりは、「有能な人間が制度の歪みと手を組んだときの恐ろしさ」を象徴しているようだ。
笑っていいのか、怖がるべきなのか。そんなギリギリの感情の上を綱渡りしながら、鳥井は一人のサラリーマンから魔王へと成長していく。
この本は、「社会に適応すること」と「怪物になること」が紙一重であることを、皮肉と笑いと恐怖で突きつけてくる。
営業スキルで裏社会を無双する、新感覚ブラックエンタメ。



ビジネス書を読んだあとに読むと、笑えるけど背筋が寒くなる。
30.有栖川有栖『濱地健三郎の奇かる事件簿』
──幽霊は、ただのノイズじゃない。
幽霊が見える探偵と聞くと、「そういうオカルト系ね」と思うかもしれない。でも、有栖川有栖がそれをやるとなると話は別だ。
『濱地健三郎の奇かる事件簿』は、あの火村英生シリーズの論理派・有栖川有栖が、幽霊という要素をどうミステリに組み込むかを本気で追求してきた、そんなシリーズの第4弾である。
探偵・濱地健三郎は、南新宿のくたびれたビルで開業していて、ただの心霊探偵じゃない。幽霊の現れた理由や去れない事情に向き合いながら、きっちり理屈で事件を解き明かす。
助手の志摩ユリエも霊感がちょっとずつ開花してきて、いいコンビ感を出してきた。心霊現象とロジックのハイブリッド捜査が、いよいよ板についてきた感じだ。
怪異に理屈で立ち向かう、幽霊探偵シリーズの到達点
収録作の中でも、『黒猫と旅する女』が特に良かった。江戸川乱歩の『押絵と旅する男』を下敷きに、旅先で出会った黒猫連れの美女が登場する。
この話は、ホラーというより切なさでくる。トリック云々より、なんでこの人は黒猫と一緒にいるのか?という理由がすごくいい。
他にも、『湯煙に浮かぶ背中』は温泉宿でのほんのり怪談系、『目撃証言』は死者の視点を通して事件の本質が明かされていくという、地味ながら上手い構造の短編もある。霊を証人として扱う発想が良い。
霊能×ロジックというのは本来相性悪そうだけど、ここではちゃんと合っている。
そして、どの話にも共通しているのは、「幽霊=怖い」じゃなくて、「幽霊=未解決の物語」というスタンス。現象の背後にある人の感情や因果を、濱地たちは解き明かしていく。
祓うのではなくて、ほどく。
これはもはや、霊を救う探偵の物語だ。
ホラーでもサスペンスでもない、まったく新しい共感型ミステリ。



幽霊は怖くない。ただ、話を聞いてほしいだけなのだ。
31.杉井光『羊殺しの巫女たち』
──祭りは終わらない。
杉井光『羊殺しの巫女たち』は、ひとことで言えば「横溝正史&スティーヴン・キング」である。横溝とキング、どっちも大好きな私にとって最高の一冊だった。
12年に一度、「おひつじ様」と呼ばれる神を迎える儀式が行われる村・早蕨部(さわらべ)を舞台に、巫女として選ばれた少女たちの過去と現在を交錯させながら描く因習ホラー×青春ミステリだ。
物語は1991年と2003年、二つの時間軸を行き来する構成となっている。91年、12歳の少女たちは、「おひつじ様」を殺すという盟約を交わした。
そして03年、24歳になった彼女たちは村に帰還する。しかし新たな死体と、あの存在の再来が始まってしまう。
因習村ミステリ×スティーヴン・キングという異種交配
この構造は明らかに『IT/イット』へのオマージュだ。あの町に戻った「ルーザーズ・クラブ」と同様、少女たちはもう一度だけ戦うために村を訪れる。
ただし本作にペニーワイズはいない。その代わりにあるのは、もっとねっとりした土着の闇と、女の子たちのやりきれない過去である。
本作のミステリ的な主軸は、「おひつじ様」とは何か、そして少女たちの中にいるもうひとりの存在は誰か、という点にある。実体を持つ怪異としての羊、その象徴性、そしてネーミングに仕込まれた仕掛けが、物語の底にメルヘン的な切なさを残す。
だが、それ以上に印象的なのは、村の男たちが守ろうとする祭りの構造だ。本作では外部の名探偵は現れない。過去に傷を負った当事者たち、すなわち元巫女たち自身が、自ら村の仕組みに引導を渡しにくる。
これはミステリやホラーの枠を越えて、構造的な暴力に抗う物語でもある。
解決編で明かされる真相は、確かに驚きがある。だがそれ以上に残るのは、「何を守り、何を終わらせるのか」という決断の重さだ。
風習が人を支配するのではなく、人が風習を壊していい。
そのことを、この物語は血と泥で証明してみせた。
「IT×八つ墓村」を、女性たちの手で書き換えた衝撃作。



古典ホラーの骨組みを使いながら、これは明らかに今の物語である。
32.飛鳥部勝則『ラミア虐殺』
──吹雪の山荘×怪獣大戦争=???
2003年に単行本で刊行されて以降、長らく幻となっていた『ラミア虐殺』が、2025年に文庫化された。
しかも、同年には15年ぶりの新作『抹殺ゴスゴッズ』も登場して、飛鳥部勝則リバイバルの波が一気に加速。その一角を担うのが、ゴシック×異能×論理という飛鳥部節全開の『ラミア虐殺』だ。
舞台は雪に閉ざされた山荘。探偵・杉崎は、謎の少女・美夜に雇われて護衛として屋敷を訪れる。電話は通じず、外部との連絡も遮断されたお決まりのシチュエーション──と思いきや、そこにいるのはただの人間じゃない。
異能力者や怪物たちがひしめく異形のクローズド・サークルが出来上がっている。
変格ミステリの牙が剥かれるとき
一見すれば、ノックスの十戒もフェアプレイ原則も蹴り飛ばした反則ミステリに見える。
でも飛鳥部勝則は、それをむしろ武器にしてくる。怪異が前提の世界であっても論理と構造はちゃんと機能するんだ、というのを見せてくれるのがこの作品の強みだ。
「背徳の本格(インモラル・パズラー)」というジャンル名がぴったりなこの作品。怪物たちのバトルがド派手に展開されるのだが、そこで終わらない。
その背後にはきっちりとした論理の網が張られていて、まさかの真相を冷たく突きつけてくる。派手な見た目に惑わされそうになるが、しっかり本格ミステリしてる構造が逆に恐ろしいのだ。
飛鳥部作品らしく、美術や視覚的なこだわりも健在。今回の文庫化では鈴木康士の装画や書店限定特典のアクリルプレートなど、作品世界がビジュアル面でも強化されているのが嬉しい。
ジャンルを軽々と越えていくその語り口は、「涅槃ミステリ」なんて呼ばれるのも納得。ミステリとホラーと異能バトルがひとつに溶け合って、こんなミステリありかよ!と思いながらもページをめくる手が止まらない。
ミステリとホラーとバトルが融け合い、最終的にジャンルの輪郭そのものが溶解する。
それは危険で、けれど抗えない吸引力を持っている。
怪物たちの乱舞の裏で、冷ややかな論理が牙をむく。ミステリとは何か、を考え直す危険な快作。



超常ありでもフェアプレイ成立。飛鳥部流・変格の極北である。
33.飛鳥部勝則『抹殺ゴスゴッズ』
──怪神と怪人が交差する、「虚構=現実」の論理地獄
手にずっしりとのしかかる、全656ページの長編。久々の飛鳥部勝則の新作は、物理的にも精神的にも「覚悟して読め」と言わんばかりの一冊だ。
『抹殺ゴスゴッズ』は、平成と令和というふたつの時代を行き来しながら、父と子の物語を描く。父・利根正也は昭和の終わりに金山の廃坑で起きた密室殺人に関わり、怪人蠱毒王と対峙する。
一方の息子・詩郎は令和の現代、空想で作り出した「怪神コドクオ」がなぜか現実に干渉を始め、自分の創作が他者に影響を及ぼしてしまう事態に巻き込まれていく。
美術と密室と神話がレンガで殴りかかってくる
いきなり謎の神と怪人が出てくるが、これはあくまで装置であり、飛鳥部勝則が本当に描きたいのは「人が作り出す虚構」と「その虚構が現実に干渉してくる仕組み」だ。
つまりこれは、メタフィクションであると同時に、極めてロジカルなアンチ・ミステリなのだ。
前半は正直重い。ゴシック趣味、美術史、精神分析、サディズム的暴力、膨大な比喩と引用と講釈がこれでもかと詰め込まれていて、読み進めるにはある程度の忍耐が求められる。でも、それらはすべて終盤の伏線として機能しているのだ。
平成編と令和編がある一点で交差したとき、バラバラに見えた美術論と怪人譚と妄想の神話が、一気に論理の重力で吸い寄せられ、整合していくカタルシスは壮絶。
特に面白かったのは、「怪神コドクオ」や「怪人蠱毒王」といった虚構の存在が、いかにして作中でリアルな殺人と結びついていくのか、あるいはその逆か、という構造の処理である。
このあたりの倒錯ぶりは、清涼院流水や舞城王太郎にも通じるが、飛鳥部勝則は一歩も譲らない強靭な論理でねじ伏せてくる。
カルト的人気を誇りながら長らく沈黙していた飛鳥部勝則が、これほどまでに自分のすべてを注ぎ込んできたという事実だけでお腹いっぱい。
乱歩や中井英夫が好きな人、あるいは論理で虚構を乗りこなしたいタイプのミステリファンには必読の迷宮だ。
美術、神話、妄想、密室。全てが論理で繋がる、飛鳥部版「神話的本格」。



「怪人が本当にいたとして、殺せますか?」という問いが、論理で答えられる衝撃。
34.新名智『霊感インテグレーション』
──祟りとバグの境界線を、コードで超えていけ
幽霊がサーバーに棲みついたら、誰がバグレポートを書くのか?
『虚魚』で横溝正史ミステリ&ホラー大賞を受賞した新名智の最新作『霊感インテグレーション』は、「オカルト×テクノロジー」という異色のジャンルを本気で突き詰めた現代的怪異譚だ。
舞台はピーエム・ソリューションズという、どこかで聞いたような名前のITベンチャー。曰く付きのシステムやアプリ、呪われたUX改善案件(?)など、一般企業が手を出さない怪異案件専門の請負集団である。
主人公の多々良数季は、死にたくても死ねない一族の末裔。でも、彼女の戦場は除霊ではない。ターミナルとコードエディタとGitHubである。
ITベンチャーが呪いをデバッグする時代
登場する怪異がまずすごい。祟るAPI、瞑想すると発狂するアプリ、勝手に人を呼ぶプッシュ通知霊──それらに多々良たちは、霊媒でも神主でもなく、仕様書とデバッグログで対峙していく。
ロジックで祟りを可視化し、サーバーログから怨念のアクセスを検出する。そんなのアリか? と思いつつ読んでいると、アリだと納得させてくる構造力がこの作品のすごさだ。
何が面白いって、呪いもアルゴリズムも一般人にとっては同じブラックボックスである、という発想だ。どちらも仕組みが分からないから怖く、不可視の力で人を不幸にする。
新名は、祟りをエモーショナルに語るのではなく、「仕様です」と言い切る。オカルトとITがここまで自然に溶け合う物語は珍しい。
テック業界に身を置く人ならニヤリとする場面も多いが、そうでない人には若干難解に映る用語や構造もある。しかしそれ以上に、今っぽさとこの時代ならではの恐怖を鮮やかに捉えた、現代ミステリとしての切れ味が光る。
幽霊が見える時代から、幽霊をインタフェース越しに扱う時代へ。それをリアルに想像させてくれる小説だ。
もし自分の使っているアプリが、やたら挙動不審だったら。
その原因が、設計ミスではなく成仏してない何かだったら。
次にエラーが出たとき、ちょっとだけこの小説を思い出してしまう。
それはつまり、もう十分に呪われているということだ。
怪異は霊障か、それとも仕様か。現代の恐怖の実装を描いた野心作。



幽霊より怖いのは、仕様が未定のまま走り出す開発案件だ。
35.南海遊『パンドラブレイン 亜魂島殺人(格)事件』
──人格が可変なら、犯人は誰と呼べるのか
これはもはやミステリなのか、SFなのか、それともゲームなのか。
南海遊『パンドラブレイン 亜魂島殺人(格)事件』は、そんなジャンルの境界線をあえて飛び越えることで、特殊設定ミステリの新しい地平を切り開いた一作である。
舞台は孤島、発生するのは密室殺人、そして導入されるのは人格移植を可能にする脳科学装置パンドラブレイン。
ひとことで言えば、すべてがやりすぎなのに、なぜか論理が破綻していない。そのギリギリの綱渡りが、想像以上にスリリングだ。
人格殺人本格ミステリ
基本構造は、大学のミステリ研究会の学生たちが、かつて未解決となった「亜魂島連続密室殺人事件」を検証すべく現地を訪れ、そこで新たな連続殺人に巻き込まれるというもの。
ここまではクラシックな事件の再演だが、本作の核は身体と人格が一致しない状況が平然と起こりうる点にある。
「誰が殺したか」ではなく「誰の人格がどの身体に宿っていたか」が鍵になるため、アリバイも目撃証言もすべて不確実になる。この情報のズレこそが、本作のロジックの燃料だ。
とりわけ面白いのは、首なし死体という古典ギミックの再解釈だ。単に身元隠しではなく、「脳=人格の器」がどこにあるかを攪乱する行為として描かれている。
つまり首がないとは人格の不在を意味し、視覚トリックではなくアイデンティティ・トリックとして機能するのだ。こんな発想はなかなか見れない。
パンドラとは、災厄をまき散らす者であると同時に、最後に希望を残す存在でもある。
その希望が推理なのか、自我なのか、それとも新しい世界のルールなのか。
それを決めるのは、最後まで読み切った人の解釈次第だ。
犯人の名前ではなく、中身の人格を推理せよ。



これは人格で読み解く格闘系本格ミステリだ。
36.酒本歩『ひとつ屋根の下の殺人』
──ここが大事、と太字で叫んでいたのに。
これはちょっとズルいくらい新しい。
酒本歩『ひとつ屋根の下の殺人』は、伏線をゴシック体で強調表示するという、普通ならやってはいけないメタな仕掛けを堂々と正面から使ってくる。
その時点でかなり攻めているのだが、それが単なるトリック遊びでは終わらないのが本作のすごいところだ。
物語の主人公は高校生の可奈。寝たきりの祖父と二人暮らしで、バイトと介護に追われる日々。ある日帰宅すると、隣人の女性から「おじいさんは殺されたのよ」と告げられる。
第一発見者は彼女で、可奈の家には警察が入り、状況は一気に非日常へと転がっていく。
太字、貧困、隣人、そして、ひとつ屋根
けれどこの物語は、突飛な殺人事件のインパクトではなく、なぜ可奈の生活がここまで追い詰められていたのかという、もっと根深い問題にフォーカスしていく。
そしてその核心に、太字というギミックが噛み合ってくる。
「ここがヒントだよ」と読者に向けて強調される太字。読んでいる側も、つい「これはミステリの手がかりだな」と思い、太字を拾っていく。
しかし、そこに描かれているのは可奈のしんどすぎる日常だったりするわけで。本当にちゃんと見てた?と小説のほうから逆に問われている気分になる。
つまり、「これは伏線です」とわざわざ強調されていた言葉が、実は別の意味で使われていた、という仕掛けになっているのだ。
この作品は、トリックや伏線の巧さももちろんだが、テーマがとにかく重い。
太字の伏線は、読み返せばすべて「そういう意味だったのか…」と膝を打つタイプの仕掛けだが、その奥にあるのは、ケアされない子ども、見て見ぬふりをされる貧困のリアルだ。
一緒に暮らしているはずなのに、気づかれないことがある。
同じ屋根の下でも、救われないままの日々がある。
この小説は、その事実をメタな遊びで包み込みながら、逃がさず置いていく。
見えすぎるミステリは、かえって盲点になる。



伏線の使い方が倫理そのものになっている構造に注目。
37.伊坂幸太郎 『さよならジャバウォック』
──主婦の独白から始まる物語
「夫は死んだ。死んでいる。私が殺したのだ」
伊坂幸太郎のデビュー25周年記念作『さよならジャバウォック』は、最初の一行からインパクト抜群だ。この衝撃の独白から、物語はあっという間に加速する。
主人公・量子は、かつては優しかった夫が、結婚後に別人のように変わってしまい、日常的な暴力に追い詰められていく。そしてある日、ついに殺してしまう。
その後、現れたのが大学時代の後輩・桂凍朗。再会からわずか2週間後、いきなり彼が家にやってきて「量子さん、問題が起きていますよね? 中に入れてください」などと言う。
25年かけてたどり着いた怪物との決着戦
なぜ彼が来たのか? どうしてすべてを見抜いたような顔をしているのか? 桂は量子に助言するでもなく説教するでもなく、いきなり死体処理の旅に付き合いはじめる。
桂は一見頼りないようで、やたら勘が鋭い。通報もしない、慰めもしない、ただ量子を連れ出し、奇妙な逃避行へと導く。
タイトルの「ジャバウォック」は、ルイス・キャロルの詩に登場する不定形の怪物。本作ではそれが、理不尽な暴力や、変貌する人間の本性、さらには自分の中に潜む何かを象徴しているように見える。
そして桂凍朗というトリックスターの存在が、物語に絶妙なバランス感を与えている。飄々としてるのに何かを隠している。敵なのか味方なのか、最後まで掴ませない。
彼の正体と、物語を通して張り巡らされた伏線が、終盤にかけて一気に回収される瞬間は、伊坂ファンならずとも「そうきたか!」と唸るはず。会話、しぐさ、小道具、そのすべてがあとでピースとなってはまり込む展開は本当に爽快だ。
バイオレンスあり、ユーモアあり、でも最後に残るのは希望。
25年走り続けてきた作家が、これまで描いてきた人の強さと変わることの可能性を、しっかりと提示してくれている。
軽やかで深い、伊坂流「怪物退治」の完成形。



変わるのは、世界じゃなくて自分だった。
38.クリスチアナ・ブランド他『本好きに捧げる英国ミステリ傑作選』
── 書物がトリガーになるとき、事件はページの外でも起きている
本と殺人。
この取り合わせにニヤッとする人には、たまらないアンソロジーだ。
編者は、英国クラシック・ミステリ復興の立役者マーティン・エドワーズ。『大英図書館クライム・クラシックス』の監修でおなじみの人で、今回のテーマはずばり「ビブリオ・ミステリ」──つまり、本そのものが事件に関わる物語たちである。
収録されているのは、1930〜60年代あたりの英国ミステリ作家による短篇16作。クリスチアナ・ブランドやA・A・ミルン、ナイオ・マーシュ、フィリップ・マクドナルドなど、知る人ぞ知る(あるいはちょっとマニアックな)名前が並ぶ。
本に取り憑かれた人たちの、可笑しくもゾッとする短編集
なかでも私が一番好きなのは、ブランドの『拝啓、編集者様』。ひたすら手紙形式で進むのだが、読み進めるにつれて、書き手のヤバさが浮き上がってくる。信頼できない語りの極致で、最後に「そういうことか」と背筋がひやっとした。
A・A・ミルンの『荒っぽいゲーム』も面白い。気が利いててテンポもよくて、最後の落とし方がまた見事。『くまのプーさん』で有名な彼が、実はこんな手練れのミステリを書いていたとは。
この本が面白いのは、単に本を舞台にするだけじゃなくて、本というモノそのものへの執着がテーマになっている点だ。毒が仕込まれたページとか、原稿の誤植に隠されたメッセージとか、ちょっとしたフェティッシュさすらある。
現代みたいにデータが主役の時代に、紙の手触りとかページの匂いなどが、こんなにも事件性を持つというのがなんだかうれしい。
本を愛しすぎたがゆえに人を殺してしまう人たちの、どうしようもなさと人間くささ。ブラックだけど、どこか笑えて、妙に胸に残る。
本に関わる仕事をしてる人や、蔵書に囲まれて暮らしてる人には、思い当たる節がありすぎるかもしれない。
活字と殺意が同じページに詰まっている、という倒錯が心地よい。



紙の本への偏愛が、ここまで人を狂わせるとは。怖いけど、わかる気もする。
39.ジャニス・ハレット『アルパートンの天使たち』
──ファイルの海に沈んだ真実を拾い上げろ
メール、チャット、通話記録、インタビューの書き起こし。この小説には普通の文章がまったく出てこない。でもそこが面白い。
ジャニス・ハレットはデビュー作『ポピーのためにできること』で、モダン書簡体ミステリの新境地を切り開いた作家だけれど、『アルパートンの天使たち』ではそのスタイルに加えて、トゥルークライムというジャンルそのものへの批評までぶっこんできた。
事件の舞台は、ロンドン郊外で起きた怪しすぎるカルト集団「アルパートンの天使たち」の集団死。信者たちはある赤ん坊を反キリストだと決めつけ、儀式殺人を計画。しかし母親が通報し、計画は未遂に。
教団は壊滅し、母子は行方不明に。それから18年後。この赤ん坊こそが鍵だと信じて、売れっ子ノンフィクション作家たちが動き出す。
書簡体で暴かれる、18年前のカルト事件
主人公は、かつてベストセラーを出したトゥルークライム作家アマンダ。だが今やすっかり落ち目。汚名返上を狙って、18年前の事件を追うことになる。
ところがライバルのオリバーも同じネタで動いていて、バチバチに火花を散らしながら、時には手を組むハメにも。
この二人、どっちも自己中心的で、自分の本を売ることしか考えてない。でも、彼らが取材を通して得た情報は、すべて文書として作中に並べられる。地の文はない。あるのは当人たちのメールや録音だけ。
つまり、私たち読者はその大量のファイルから真実を拾い集めるしかない。しかも、その語り手たちが平気で嘘をつくからタチが悪い。
唯一信頼できそうなのが、アマンダの助手エリー。文字起こし担当の彼女が時おり挟むぼそっとしたコメントが、めちゃくちゃ鋭い。このモブっぽい存在が実は核心を突いているあたり、かなり面白い構造になっている。
この物語、実はミステリの皮をかぶったメディア批判でもある。作家たちが追いかけているのは事件の真相ではなくて、売れる物語だ。誰かのトラウマを掘り返して、血でページを染めるような仕事。
それをビジネスとして割り切るアマンダと、カルトに感化されて暴走するオリバー。どっちがマシか、という話でもない。怖いのは、両方リアルにいそうなところだ。
物語の終盤では、過去の事件の裏側にある思わぬ真実が明かされるのだが、それもまた文書の行間からしか見えてこない。
誰かが「これが真相です」と断言してくれることはない。
でもそれがいい。
この作品の醍醐味は、断片的な証言や資料から、自分なりの見え方を作っていく過程にあるのだから。
資料のすき間に転がってるひとことが、どれだけ重いかに気づいた時、この作品の本当の恐ろしさがわかる。



「物語の裏側にある編集作業まで丸ごとミステリにしてしまう」という離れ業。これは、読むという行為そのものを揺さぶってくる本である。
40.フリーダ・マクファデン『ハウスメイド』
──反転する支配構造
家を持たない元受刑者のミリーが、郊外の豪邸で住み込み家政婦として雇われた──という出だしは、一見ラッキーに見える。
けれど、与えられた部屋が外から鍵がかかる屋根裏部屋だった時点で、何かがおかしい。
雇い主であるニーナは美しくて情緒不安定、ミリーに嫌がらせを繰り返す。一方の夫アンドリューは優しくて魅力的……と思いきや、物語は一気に裏返る。
TikTok世代のドメスティック・ノワール
この小説、序盤の印象を信じて読み進めていると、第二部で思いっきりひっくり返される。語り手が切り替わった瞬間、そこにいたのはまったく別の顔をした人物だった。
暴力と支配の構造、そしてガスライティングの恐怖。すべてがひとつずつ組み立てられたピースとして再配置され、優しさが仮面にすぎなかったことが明らかになる。
そしてなにより、ミリーがただの巻き込まれ系ヒロインじゃないのがこの作品の面白さだ。怒りを内に抱えた彼女は、アンドリューのような人間を真正面から叩き潰せる毒。
追い詰められた彼女が毒をもって毒を制す構図を逆転させていく終盤は、まさにエンタメ小説の醍醐味。めちゃくちゃスカッとする。
短くテンポの良い章、次が気になる終わり方、感情のジェットコースター。こうした設計の巧さも、本作がTikTokで話題となった理由だろう。
内容は過激でも、展開は読みやすく、気がつけば最後まで駆け抜けてしまう。
鍵付きの屋根裏部屋が、最後にはいちばん熱い舞台になる。



やられっぱなしじゃ終わらない。家政婦、反撃開始。
41.ホリー・ジャクソン『夜明けまでに誰かが』
──動く密室で暴かれるのは、秘密だけじゃない
春休みのロードトリップを楽しむはずだった6人の若者が、RV(大型キャンピングカー)の中で突如として人質に変わる。
原因は、謎のスナイパーによる襲撃。夜明けまでの8時間、「お前たちの中に罪を隠している者がいる。その秘密を暴け」と告げられた彼らは、密室の中で疑心と怒号をぶつけ合いながら、1人また1人と壊れていく。
本作は、『自由研究には向かない殺人』で知られるホリー・ジャクソンの最新サバイバル・サスペンス。最大の特徴は、移動するRVを舞台にした閉鎖空間ミステリであること。
そして、その舞台装置を成立させているのが、一歩外に出れば狙撃されるというシンプルで強烈なルールだ。
若者たちの友情と疑念が崩壊していく、極限の8時間
カーテンの隙間から覗く赤いレーザーポインター、逃げ場のない空間、疑い合う仲間たち。状況は典型的だが、語りの巧さが抜群なので、まったく古さを感じさせない。
中心にいるのは、主人公・レッドと、支配的なリーダー・オリヴァー。このオリヴァーという男がとにかく癪に障る。状況を仕切りたがるくせに、自分の立場を守るためには平気で他人を犠牲にする。グループの秩序を保つはずの存在が、実は一番不安定な爆弾だったという構造は、この手の群像劇の見せ場だ。
物語が進むにつれて「こいつの末路が見たい」という負の感情が加速していくのだが、その感情が物語を牽引するエンジンとして作用しているのも上手い。
もう一つの軸が、レッドという語り手の存在。彼女は何かを隠している。その秘密は事件の核心に関わるもので、終盤でのカミングアウトが物語の印象を一変させる。
狙撃手の動機や、グループ内の裏切りも含めて、YA(ヤングアダルト)向けとは思えない濃度の人間ドラマだ。
ジャクソンは今回も、若者たちがそれぞれの正義と罪を抱えながら、限られた時間の中で何を選び何を守るか、を描いてみせた。
誰が生き残り、誰が沈むか。読んでいる側の価値観もまた、試されている。
死なないと信じていた関係ほど、いとも簡単に壊れるのだ。
閉鎖空間で試されるのは、記憶ではなく覚悟。



出るも地獄、黙るも地獄。なら、何を晒す?
42.ジェフリー・ディーヴァー『スパイダー・ゲーム』
──蜘蛛のタトゥーは、ネットの闇に仕掛けられた罠のサイン
『スパイダー・ゲーム』は、どんでん返しの魔術師ジェフリー・ディーヴァーと、元FBI捜査官のイザベラ・マルドナードという異色コンビによる、新シリーズの第1作だ。
国家安全保障省(DHS)の捜査官カーメン・サンチェスと、元ハッカーのジェイク・ヘロン。正反対の立場と性格を持つふたりが、連続殺人犯「スパイダー」の正体に迫っていく。
サンチェスは規則第一のプロフェッショナル。ヘロンは一度逮捕された過去を持ちながら、今はセキュリティの専門家として大学で教えている変わり者。
このふたりが手を組むこと自体が、すでにドラマの火種となっており、どこか『ホームズ&ワトソン』の現代版のような空気をまとっている。
アナログとサイバーのいいとこ取り捜査劇
現場に残されたのは、不気味な蜘蛛のタトゥーとごくわずかな痕跡だけ。従来の捜査では太刀打ちできないタイプの事件に、アナログの捜査とデジタルのハッキング的アプローチが組み合わさっていく様子は、新鮮かつ説得力がある。
ヘロンのソーシャルエンジニアリング(人間関係を使った情報収集術)も、今っぽい見どころのひとつだ。
そしてもちろん、これはディーヴァーの作品である。となれば、ただの手がかり追跡劇で終わるはずもない。中盤から終盤にかけて、犯人視点で語られる情報の裏がひっくり返されるあたりの展開は、もう「これぞディーヴァー!」としか言いようがない。
実は○○だった、という仕掛けが何重にも畳み込まれており、正直ページを戻って再確認したくなった箇所もある。提示された事実が、実は全然違った意味を持っていたと分かったときの快感は、やっぱり健在だ。
タイトルにある「スパイダー」は、単なる記号ではない。ネットワーク社会に潜む目に見えない罠そのものであり、今の時代ならではのサスペンスに仕上がっている。
ベテラン作家ふたりによるハイブリッド型の警察小説。
こんなの、シリーズ化に期待が高まるしかない。
ルールとアウトローが手を組む、新時代の探偵劇。



物理証拠×ハッキングで挑む、令和のホームズ&ワトソンだ。
43.アンソニー・ホロヴィッツ『マーブル館殺人事件』
──フィクションが現実を告発する、最後の推理劇
シリーズ第3作にして、ついに「アティカス・ピュント最後の事件」。だが、もちろんホロヴィッツがそんな直球タイトルを素直に使うはずがない。
『マーブル館殺人事件』は、作中作と現実パートが緊密に交錯するメタミステリの極北であり、名探偵の死を通して、フィクションと現実の境界線を溶かしていく実験作でもある。
舞台は現代ロンドンと、劇中劇としての1950年代フランス。スーザン・ライランドは、亡き作家アラン・コンウェイが生み出した人気探偵シリーズの続編企画を引き受けることになる。
だが、その新作原稿『ピュント最後の事件』には、ある意図が隠されていた。著者はアランではなく、20年前に祖母の不可解な死を体験した青年・エリオット。
彼はこの小説に、とあるメッセージを忍び込ませていた。
二重構造の迷宮に仕掛けられた真実の鍵
今回の作中作は、黄金時代の香り漂うクラシカルなフーダニット。
南仏の別荘、毒殺、遺産相続……まるでアガサ・クリスティの再来かと思わせる舞台設定だが、その筋立ての中に、アナグラムや暗号といった現実の手がかりが潜り込んでいる。
ここが恐ろしく巧妙だ。あたかもミステリ小説という形式そのものが、現実の罪を裁く法廷になっているような構造である。
そして忘れてはならないのが、アティカス・ピュントの幕引きである。彼は虚構の名探偵でありながら、スーザンにとって、いや、読者にとってもすでに本物の探偵になっていた。
その彼が作中で別れを告げる瞬間、いわば探偵としての役目を終える場面は、驚くほど感情的で、穏やかで、そして美しい。むしろ、ピュントの論理や信念は、スーザンの中にしっかりと根を下ろし、彼女自身が新たな探偵として歩み始める決意につながっていく。
虚構が現実を暴き、現実が虚構を更新していく。
この入れ子構造の中で、シリーズは一つの終幕を迎えるが、それが本当に終わりなのかどうかは、まだ誰にもわからない。
物語は終わるが、虚構と真実の関係は、まだ終わらない。



これはミステリではなく、ミステリという形式を使った裁判だ。
44.ベンジャミン・スティーヴンソン『真犯人はこの列車のなかにいる』
──豪華列車で繰り広げられるメタ・ミステリの祝祭
前作『ぼくの家族はみんな誰かを殺してる』で「フェアプレイ宣言」+「読者への挑戦」+「信頼できる語り手(とされる主人公)」という超メタ構造で話題をさらったベンジャミン・スティーヴンソン。
二作目となる『真犯人はこの列車のなかにいる』では、舞台を密室列車に移し、よりストレートに黄金時代ミステリの文法を脱構築してみせた。
今回の主役は再び、アーネスト・カニンガム。駆け出しのミステリー作家の彼が、作家フェスティバル開催中の大陸横断列車に乗り込むところから物語は始まる。
ここまでは設定がメタなだけだが、そこに本物の殺人が起き、列車が完全なクローズド・サークルと化したとき、物語の密度が一気に変わる。
犯人はこの中にいる。
だが容疑者は全員、プロのミステリ作家──というのが、本作最大のアイディアだ。
ミステリ作家同士の騙し合いが意味するもの
登場する作家たちは、それぞれ法医学スリラー、心理サスペンス、文芸ミステリなどのジャンルを代表していて、事件に対して各自の作家的アプローチで挑んでくる。
このジャンルによる捜査の視点の違いが、ただの設定にとどまらず、物語全体を批評的に読み解く鍵になっているのが面白い。
たとえば、死体の状況から証拠をいじる法医学派、犯人像を物語的に再構成しようとする文芸派など、彼らの言動自体がジャンルのパロディになっており、ある種のジャンル批評ミステリとしても読める。この構造だけで、正直ミステリ好きとしてはたまらない。
そして当然、主人公アーネストもただの語り手では終わらない。彼が読者に向かって語りかけてくる語りのクセそのものが、作品全体の仕掛けに密接に絡んでくるからだ。
本作の肝は、もちろんどんでん返しの部分にある。あまりにも軽妙でユーモラスな語りに慣れていると、つい油断してしまうが、ふとした言い回し、細かな記述、なんなら句読点の位置すら伏線になっているあたり、ディテールの張り方は異様に緻密だ。
そして何より最も面白かったのは、読者の記憶を試すような構成である。つまり、登場人物や設定のどこまで覚えていたかが、そのまま読後の衝撃に直結する。
「油断していた!」と思わせられるポイントがいくつもあり、まさに読者を推理のゲームに巻き込む設計の巧みさに唸らされた。
鉄道という古典的舞台に、ジャンル批評、語りの仕掛け、作家の業を詰め込んだ、まさに今読むべきメタ・ミステリ。



犯人は列車のなかにいる。だが、語り手が何を見せ、何を隠しているかにも目を凝らすべし。
45.フランシス・ビーディング 『イーストレップス連続殺人』
──その町の誰もが怪しく、そして誰もが被害者になりうる
1931年に発表されたこの作品が、実に90年を経てようやく邦訳されたという事実だけでも、ミステリ好きとしては胸が熱くなる。
舞台は、イギリス東部の保養地イーストレップス。いかにも事件が似合わなそうなのどかな田舎町に、突如として現れた連続殺人犯。その犯行は冷酷で、しかも妙に規則的。事件が増えるたび、町の空気はひたひたと不穏になっていく。
被害者たちに共通点は見られない。警察はやがて、一人の男を犯人として突き止め、裁判を経て事態は収束……したかに見えた。
だがもちろん、物語はそこで終わらない。
多視点×群像劇×法廷ドラマ
この作品が面白いのは、フーダニットとしての基本を押さえながら、誰もが語り手であるような群像構成をとっているところだ。
被害者の家族、警察、新聞記者、貴族の屋敷で働く人間、過去を持つ容疑者──どこかで聞いたようなパーツではあるが、それらが驚くほど自然に、しかも無駄なく噛み合っていく。複数の人物の視点のズレや勘違いが、読者の推理を巧妙に撹乱してくるあたりも実に上手い。
そして後半では、法廷サスペンスとしての顔も見せる。容疑者エルドリッジの過去と現在が交錯し、社会がいかにして犯人を作り上げてしまうかという冤罪モチーフまで絡んでくる。1930年代の小説とは思えないほど、今読むからこそ刺さるテーマがそこにはある。
一番驚いたのは、やはり終盤の展開だ。序盤からちゃんと伏線が張られていたのに、まんまと誤導されていた。あの正体、あの動機。古典ミステリでここまで犯人像に深く切り込む作品は、そんなに多くない。
アガサ・クリスティに例えるなら、あの作品と肩を並べてもいいかも──そう思えるくらいのツイストが待っている。
90年越しの邦訳ということで、古くささを心配する人もいるかもしれない。でも、ミステリにおける人の心の暗部や社会の偏見は、実はちっとも古びていない。
むしろ今の感性だからこそ刺さるタイプの作品だ。
古典でありながら、犯人を記号で終わらせない。
この一点だけでも、この作品が今になって評価される理由は十分すぎる。
英国古典ミステリの隠れた牙。



容疑者を知っているということが、真実を遠ざける。その感覚を、ぜひ体感してほしい。
46.ピーター・スワンソン『9人はなぜ殺される』
──クリスティを下敷きにした、現代的サスペンスの地雷原
『そして誰もいなくなった』に強く影響を受けた作品は山ほどあるが、その中でもスワンソンのこの一作は、ある意味で最も大胆な再演だと思う。
舞台は孤島でも館でもなく、アメリカ全土。誰もが自由に動けるはずの世界で、名前だけを並べた謎のリストが届き、そこに載った9人が一人ずつ殺されていく。
クローズド・サークルの設定がまったくないのに、そこにいる誰もが逃げられない。あるのは名前が書かれただけの紙という、極めて抽象的な選ばれし者の感覚。
それが逆に不気味さを増している。章ごとに視点が切り替わり、次々に死が迫る構成は非常にテンポがよく、むさぼるように読んでしまうタイプの作品だ。
模倣ではなく、変奏としての巧妙さ
この作品の評価を分けるのは、おそらく終盤で明かされる犯人の動機だと思う。あえて詳細は避けるけれど、これがどうにも理不尽で、正義というよりは私怨や逆恨みに近く映る。
でもそれこそがスワンソンの狙いなのだと思う。正義の名のもとに罪人を裁くクリスティ的ロジックとは違い、ここにあるのはもっと歪んだ倫理感で、現在の無差別犯罪や偏った復讐劇を思わせる。筋が通っていないからこそ、逆にリアルに感じる瞬間もあった。
犯人の正体や生存者の処理、そして物語の幕引きに至るまで、本作はかなり意図的に原典を外すことで個性を確立している。読んでいて思ったのは、これはリメイクではなく、明確に別の地平を狙って書かれた変奏曲だということだ。
スリラーとしてのスピード感は抜群だし、構造的な仕掛けも巧み。なにより、クリスティ作品の影を引きずりながら、まったく異なる後味を残してくるのが面白い。
スワンソンは、読者の予想を裏切ることで、ジャンルの記憶そのものに逆らってみせた。そのチャレンジ精神に拍手を送りたい。
クリスティの名作を知っているほど、ズラしの構成にニヤリとさせられる一作。



構成は古典、味つけは現代。ミステリの形を借りた不条理スリラーの快作だ。
47.ジャック・ケッチャム『冬の子 ジャック・ケッチャム短篇傑作選』
──怖いだけじゃ終わらない。
ジャック・ケッチャムと聞くと、「グロい」だったり「エグい」だったり、まずはそういう言葉が浮かんでくる。
しかしこの短篇傑作選は、そういうイメージだけで読み始めるとちょっと面食らう。いやもちろん、暴力もトラウマもたっぷり出てくる。でも、なんというか……その奥にある人間がやけに鮮明なのだ。
たとえば表題作の『冬の子』。あの伝説の食人ホラー『オフシーズン』のスピンオフということで、予想通りの地獄展開ではある。
彼らはただの化け物じゃなく、家族を守り、飢えに抗って、冬を生き延びようとする生きものとして描かれている。
気づけば、彼らにうっすら共感してしまってる自分がいるのが恐ろしい。
ケッチャムが見つめる人間の奥底
とはいえ、本書の魅力はその幅広さだ。『箱』なんてもう、名作ホラー短篇の代表格だし(ブラム・ストーカー賞受賞)、怖さの見せ方が巧妙すぎる。
なにが入ってるかは教えてくれない。でも、それがわからないからこそ怖い。こういう見せない恐怖を描けるのもケッチャムの凄みだ。
かと思えば、『永遠に』では猫と人間の切ない絆を描いてくる。やってることは完全に文芸。なのに、ちゃんとケッチャムの作品だとわかるのが不思議だ。静かな、やさしさに満ちたラストに、むしろぞっとするくらい心をつかまれる。
編者の金子浩氏の手腕も光っていて、ただのホラー短篇集じゃなく、ケッチャムという作家の全貌を見せる構成になっているのがうれしい。
暴力の向こうにいる人間、残酷さと一緒にあるやさしさ、壊れかけた日常と、かすかな希望──そんな多面体のケッチャムを一冊で味わえる贅沢。
怖いけどそれだけじゃない、というのは、こういう作品のためにある言葉なのかもしれない。
血も涙もある短篇集。ケッチャムが描くのは、人間の底だった。



怖さの幅が広すぎて、むしろ愛おしくなってくる一冊。グロと詩情が見事に共存している。
48.ドナルド・E・ウェストレイク『うしろにご用心!』
──失敗してなんぼ、それがドートマンダー式
ドナルド・E・ウェストレイクのドートマンダーものは、いわば犯罪コメディの金字塔である。
『うしろにご用心!』もその例に漏れず、完璧なはずの強奪計画が、いつものように予期せぬ方向にズレていく。
しかも今回は、ヤマの最中に行きつけのバーがマフィアに乗っ取られるという、わけのわからない事態まで発生するのだから、ただの泥棒話では済まされない。
狙いは、高級ペントハウスに眠る大富豪プレストンの美術品。でもプレストン本人は、借金や元妻から逃げて南の島に長期逃亡中。計画自体はシンプルだった。
なのに、ニューヨークとカリブ海でそれぞれ厄介ごとが同時進行し、ドートマンダーたちはあっちでもこっちでも大混乱に巻き込まれる羽目になる。
バーが戦場、島は罠、そして仲間はいつも通り
本作では、二つの舞台が絶妙に交差する。凍えるNYの街角と、陰謀が渦巻く灼熱の島。交互に描かれるプロットが次第に接近し、最後には思わぬ形で結びつく構成は実に気持ちいい。
そして何より楽しいのは、いつものチームだ。ケルプの軽妙さ、タイニーの頼もしさ(と見た目のインパクト)、そして何かと不器用なドートマンダー。
彼らの掛け合いは、シリーズもののシットコムを観ているような安定感がある。真剣なはずの強盗計画が、なぜこうも滑稽に転がっていくのか。もはやジャンルとして確立されている。
計画は綿密、タイミングもバッチリ。でも実行すると、なぜか全部ズレる。それがドートマンダーの宿命だ。普通なら絶望するような状況も、この男にかかれば妙に笑えるのが不思議でならない。
ドートマンダーものの面白さは、何度も失敗して、それでも諦めずに何かをやってのける姿にある。もはや強奪は目的ではなく、「いかにしてうまくやろうとしたのにうまくいかなかったか」という結果の積み重ねの芸術だ。
ドートマンダーは決して世界一不運な泥棒などではない。単に、世界一運に期待してない泥棒なのである。
ウェストレイクの筆は今回も絶好調で、皮肉もチラつきつつ、しかし根本には「人間ってしょうがないなぁ」というぬるいまなざしがある。
その懐の深さが、何度でもこのシリーズに戻ってきたくなる理由だと思う。
どう転んでもうまくいかないのに、なぜか癖になるドートマンダー・ワールドの中毒性。



こんな泥棒たちなら、友達になってみたい。
49.M・W・クレイヴン『デスチェアの殺人』
──ポーの心が砕ける音が聞こえる。シリーズ最暗部、突入
『デスチェアの殺人』は、シリーズ第6作にして異例の幕開けを迎える。
セラピー室で語られるポーの回想から物語はスタートし、彼が精神的にどれほど追い詰められているかが最初から明かされるのだ。
つまり今回の読みどころは「誰が犯人か」だけでなく、「この事件でポーに何が起きたのか」という視点がもう一つ加わっているところにある。
物語の軸となるのは〈慈悲の椅子〉と、旧約聖書のような石打ちによる処刑死体。そこに登場するのが、カルト団体。危険な香りしかしないが、案の定、信仰と暴力がねじれ合った異様な事件が待っている。
なぜポーは壊れたのか? 回想が紐解く最悪の事件
今回の事件では、「コンバージョン・セラピー(矯正治療)」という現代社会でも問題視されるテーマにまで踏み込んでいる。
改心させる、救ってやる。そんな言葉で正当化される恐怖の数々。しかも、それが組織ぐるみで行われている。
〈慈悲の椅子〉は、まさにその象徴だ。優しさの仮面をかぶった存在。ここまであからさまに人間の尊厳を踏みにじるものが登場すると、読んでいてゾッとする。それでも物語を追ってしまうのは、ポーとティリーがどんな真相に辿り着くのかを見届けたくなるからだ。
シリーズおなじみのポーとティリーの掛け合いは健在だが、今回面白いのが第三の男ライナス(通称スヌーピー)の存在である。
監査官として送り込まれた彼は、一見ギャグ要員のようでいて、最終的には意外な活躍を見せる。この男、最初は完全に空気を読めない邪魔者なのだが、思わぬタイミングで物語を支える存在になるのが面白い。
そして、論理で武装したティリーが狂信という論理外の相手とぶつかる場面には、彼女のこれまでにない感情の揺らぎも見える。この成長と葛藤がまたいいのだ。
正しさとは時に、いちばん残酷な拷問になる。その現実に、ポーたちが全身でぶつかる。



シリーズ屈指の重さ。だが、手放せない濃度だった。
50.スティーヴン・キング『フェアリー・テイル』
──老犬と少年が歩む、血と魔法のおとぎ話
スティーヴン・キングの『フェアリー・テイル』は、そのタイトルとは裏腹に、甘ったるい童話などではない。
グリム童話のように残酷で、ラヴクラフトのように不穏で、それでいてチャーリーと愛犬レイダーの物語は、骨の髄まで温かい。
ファンタジー×ホラーというキングらしい組み合わせの中で、この作品が描くのは、少年が愛するもののために世界を越えるという、きわめてシンプルな動機から始まる成長の物語である。
物語の導入は現実的だ。母を亡くし、父はアルコール依存。チャーリーはすでに人生の不条理と向き合っている。だからこそ、偏屈な老人ボウディッチと出会い、老犬レイダーと心を通わせていく過程が、ありふれたヒーロー譚よりもはるかに響いてくる。
ダークファンタジーの皮を被った、痛みと優しさの冒険譚
異世界〈エンピス〉へ旅立つ動機が、世界を救うことではなく、愛犬を救うことなのが何よりいい。この物語の中心にあるのは、壮大な魔法ではなく、個人的な愛情と責任なのだ。
そしてキングはここでも容赦がない。エンピスの風景は幻想的というより病的で、どこかが壊れている。おとぎ話の骨格を借りながら、その肉付けは毒気に満ちている。魔法の日時計といったアイテムは確かにファンタジーの道具立てだが、それらが放つのは夢ではなく代償の匂いである。
印象的だったのは、チャーリーが語る力を得ていく描写だ。彼は剣を振るわず、勇者として称えられるわけでもない。
だが、物語を聞き、話し、他者の心に火を灯す力を通じて、少年は世界を変えていく。これこそが、キングが物語そのものに託した信念の現れだろう。
個人的に推したいのは、レーダーの存在感だ。魔法で若返る犬なんて、普通はご都合主義だが、本作ではその奇跡に泣かされる。
老い、死、喪失、そして奇跡。
それらが犬と少年の間に差し込まれたとき、キングの筆はホラーでもファンタジーでもなく、紛れもなく文学になっている。
これは恐怖の王様が語る、最も美しくて血なまぐさい童話である。



世界の終わりより老犬の命のほうが、よっぽどリアルで切実なのだ。
51.セレステ・イング『密やかな炎』
──完璧なはずの街にくすぶる、小さな火種たち
オハイオ州にある計画都市・シェイカー・ハイツ。きちんと整備された街並みに、教育熱心な住人たち。
規則を守れば平穏に暮らせる、そんな理想の街で、ある日突然、リチャードソン家の豪邸が全焼する。犯人とされたのは、四人きょうだいの末娘・イジー。けれど、彼女はどこにもいない。
物語はそこから11ヶ月前へとさかのぼり、なぜその家が燃えることになったのかが語られていく。
母性がぶつかり合うユートピアの裏側
この家の持ち主・エレナが貸し出していた家にやってきたのが、写真家のミアと娘のパール。リチャードソン家とミア親子は、真逆の価値観を持ちながらも、子ども同士の交流を通じてしだいに距離を縮めていく。
だが、ある中国系移民の女性と白人夫婦による赤ちゃんの親権争いをきっかけに、街は一気に分断される。そしてミアの過去と、リチャードソン家のひずみも、少しずつ明るみに出ていく。
この作品の肝は、母であることに関わるいろんな立場が丁寧に描かれている点だ。子どもに最善を尽くしたい一心で抑圧してしまう母、芸術と生活のバランスに悩む母、赤ん坊を迎えたくて必死の夫婦、貧困のなかで手放した娘を思い続ける実母……。
どれもが間違っていないからこそ、ぶつかり合ったときに生まれる火花がまぶしい。
タイトルの『密やかな炎』は、燃えた家のことだけじゃない。それぞれの胸の奥でくすぶっていた感情、疑念、怒り、あきらめ──そうした火種がいつの間にか広がって、ついには街全体を巻き込んでいく。その描き方がとてもスムーズで、どこを切ってもドラマが詰まっている。
正義とは、子育てとは、幸せとは。
エレナとミアという真逆の母親像を軸に、価値観を揺さぶる疑問を何度も投げかけてくる。派手な謎解きやトリックはなくても、火がつく理由がわかったとき、心の中に残るのは一種の切なさと納得。
ラストで明かされる、火を放った本当の理由は、誰にとっても他人事ではない。
いい母親の形なんて、誰にも決められない。それでも、火花はどうしても散ってしまう。



燃やしたのは誰かじゃない。燃えざるを得なかった、それぞれの理由があるのだ。
52.スチュアート・タートン『世界の終わりの最後の殺人』
──記憶が消されても、真実は残る。終末世界で最後の殺人を解け
スチュアート・タートンの新作が、特殊設定ミステリの限界をまたしても更新してきた。
『イヴリン嬢は七回殺される』でタイムループ×人格転移を使い倒した彼が、今回挑んだのは「終末世界×本格ミステリ」という無茶なハイブリッド。だが、タートンにかかればそれが成立してしまうから面白い。
舞台は、謎の霧によって地球がほぼ壊滅してしまった90年後の未来。唯一生き残ったギリシャの孤島には122人の村人と3人の科学者がいて、彼らはAI〈エービイ〉によって徹底管理された社会で暮らしている。
外からの接触は一切なし。だがその平和は、長老のひとり・ニエマの死によって一気に崩壊する。彼女の死によって島を守っていた防壁システムがダウンし、世界を覆う霧が迫り来る。
タイムリミットは92時間。そして事件当夜の記憶は、全島民からAIによって削除されてしまっていた。
消された記憶、閉ざされた世界
この設定だけでもう勝ちなのだが、そこに「誰が殺したのか本人すら覚えていない」という爆弾を重ねてくる。
探偵役を務めるのは、他の村人たちとは違って現状に疑問を抱く、好奇心と理性を併せ持つエモリー。彼女が限られた記憶の断片とAIの残したデータを頼りに、事態の真相とシステムの矛盾を突いていく。
本作の面白さは、単に犯人を探すだけではない。「自分の罪を忘れた人間は、責任を取ったことになるのか?」「多数の命を守るために少数を切り捨てていいのか?」といった倫理のジレンマが、物語の根幹に据えられている。
しかもそれをエンタメの枠をはみ出さずに描き切る筆力。ずるい。
本格ミステリとしての構成も抜群で、エモリーの視点に加え、AIアビの冷徹なロジックや、断片化された記憶のパズルが巧みに織り込まれていく。
特に島民の正体が明かされた瞬間、ミステリの前提そのものがひっくり返る感覚は快感でしかない。
物語の舞台がギリシャというのも象徴的だ。
かつて文明が始まった場所で、今また新たな再生の物語が始まろうとしている。
終末SFとしての絶望感と、本格ミステリの快感。その両方を限界まで引き上げたタートンの執念が詰まっている。



記憶が消えても、倫理は残る。そのジレンマにこそ、この作品の核心がある。
53.エイミー・チュア『獄門橋』
──その橋の向こうにあるのは、名家の誇りか、アメリカの闇か
エイミー・チュアと聞けば、厳格な教育論や文化論を思い浮かべる人も多いと思う。だが本作『獄門橋』で彼女は、堂々たる歴史ノワール・ミステリの書き手としてジャンルに殴り込んできた。
しかも舞台は1944年のカリフォルニア。ホテルで始まる暗殺事件、名家の呪われた過去、自己の出自に揺れる刑事。構図としてはクラシックだが、その内実は現代的な鋭さに満ちている。
主人公サリバンは、一見すると優秀で分別のある白人刑事だが、その正体はメキシコ系とユダヤ系の混血であり、白人社会で生き抜くために名前もアイデンティティも偽っている。つまりパッシングの中で苦悩する男である。
この複層的な人物設定がすでに強い。そして彼が捜査するのは、富豪一族の娘たちと、10年前の少女の転落死が絡む怪事件。クレアモントホテルという密室的な舞台設定と、戦時下アメリカという不穏な時代背景が、見事に交錯する。
ノワール歴史、差別、そして亡霊
この本の面白さは、単に殺人の動機を追うだけでは終わらないところにある。チュアはこの物語で、「パッシング=偽りの生」に潜む恐怖と痛みを描いた。
サリバンの自己否定的な内面は、差別に対する静かな抵抗でもあり、同時に彼自身の倫理を蝕んでもいる。職務を果たすためには、自分を偽り続けなければならない。この葛藤が捜査線と共鳴し、重層的なドラマを生んでいる。
さらには、10年前に亡くなった少女の亡霊のような存在が、今もホテルを彷徨っているという噂まで登場。もちろんホラーではないが、歴史という亡霊がいかに現在を呪縛しているか、という点で、これはまぎれもないゴースト・ストーリーである。
構成面でもかなり攻めている。老女の供述書がインサートされ、家族の歴史と狂気が露わになっていく構図は、ゴシック小説のそれだ。
でも文体や語りはレイモンド・チャンドラーを思わせる硬派なノワール。この組み合わせがとにかく効いている。
個人的ではあるけど、歴史の闇と個人の闇を同時に描いた点に、ジェイムズ・エルロイ『ブラック・ダリア』に通じる力強さを感じた。
語られなかった歴史を描いたゴシック・ノワールの傑作。



ミステリとしても読み応え十分だが、本作が本当に暴いているのは、国家の偽装と、個人の偽装が重なる場所である。
ホラー作品も少し紹介


今年はホラー小説もけっこう読んだ。
むしろ、気づいたら「怖い話を読みたい周期」が何度も来ていて、気になる新刊は片っ端から追いかけていた気がする。
結論を言うと、今年はホラーも当たり年だった。
怖いだけじゃなくて、構造が凝ってる作品、ジャンルを横断してくる作品、設定で勝負してくる作品、とにかくバリエーションが豊富で、こんな地獄の描き方があるのかと笑ってしまった。
というわけで、この勢いのまま、ミステリと隣接しつつもまた違った刺激をくれた今年のホラー作品たちも、ここで少しだけご紹介しておきたい。
1.夜馬裕『イシナガキクエを探しています』
──その名前を検索した瞬間から、呪いが始まる
『イシナガキクエを探しています』は、テレビ東京のフェイクドキュメンタリー番組(TXQ FICTION)をベースに書籍化された一冊だ……なんて説明するとありふれて聞こえるが、これは次元が違う。
QRコードで動画や音声にアクセスできる仕掛け、関係者が番組の前後で次々と不審死していく展開、何より物語の外側にまで染み出してくるような不気味さ。モキュメンタリー・ホラーの文脈で語るには、この作品はあまりにも本気だ。
ぐっと来たのは、映像がもたらす「リアルすぎる違和感」だ。わざと解像度の悪い素材を見せたり、録音がブツ切れだったり、そういう粗さが逆にリアルに見えてしまう。
スマホで再生するノイズ混じりの音声に、ぞっとしたのは私だけじゃないはずだ。
テレビ発ホラーが、本の中でも続いていた
話の発端は、1969年に失踪した謎の女性・イシナガキクエを探してほしい、という一人の老人の依頼だった。そこにTVクルーが乗っかり、公開捜査番組が作られる。
だが、写真は顔が写っておらず、提供された証拠もいまいち信用ならない。さらに、番組の放送前に依頼主が焼身自殺。もうこの時点で何かがおかしいのは明白だ。
追跡調査をしていた元AD(語り手の妹)も後に変死体で発見される。しかも彼女が遺したテキストや録音が、紙面上に散りばめられている。その記録がゾワゾワと物語を侵食していく構成が、とても嫌で、好きなのだ。
そして最大の恐怖は、スマホでリンク先を開いた瞬間に訪れる。これは本当にフィクションなのか?と思わせる演出が巧妙すぎるのだ。しかも、終盤ではこの呪いが次に伝播する可能性を示唆するようなラストが待っている。
ホラーとしても完成度が高いけれど、それ以上にこれは視る側の倫理や、トゥルークライム的消費の暴力性を突いてくる一作でもある。
探してはいけない、知ってはいけない、けれども、目が離せない。
そんな現代型ホラーの罠に、まんまとハマってしまった。
モキュメンタリー×紙書籍×QRコード。現代ホラーの最前線にして、禁忌の入り口。



QRコードの先にあるのは、次の犠牲者としてのあなた自身かもしれない。
2.三浦晴海『なぜ「あしか汁」のことを話してはいけないのか』
──情報が呪いになる時代の、ネット発ホラーの進化形
Web小説投稿サイト「カクヨム」発の話題作、『なぜ「あしか汁」のことを話してはいけないのか』。
一見ナンセンスなタイトルに惹かれて読んでみたら、思ったより遥かに深くて、怖くて、面白かった。これはもはや、単なるネットミーム系ホラーじゃない。
ジャンルとしては「検索してはいけない言葉」系の系譜に連なる。例えば「くねくね」や「八尺様」といった都市伝説の系譜も感じるけれど、本作が新しかったのは、意味不明な言葉に理不尽な死が付随してくる、その感染力だ。
曰く、「あしか汁」「十三本数」「アカマシ、マカマシ、アトナシ」──これらの言葉を調べたり、話したりした人間は、次々と謎の死や発狂に見舞われる。
語り手は著者自身の名前を冠した「三浦晴海」。死んだ大叔父の日記に記された奇妙な文字列に引っかかり、軽い気持ちで調査を始めたのが運の尽きだった。協力者は次々と死に、情報を深掘れば深掘るほど、真実がこちらの精神を削ってくる。
怪異の正体は呪いではない。悪意のある意志すら存在しない。ただ、情報がそこにあり、触れる者を巻き込んでいくだけ、という冷ややかな無機質さにゾッとさせられた。
言葉が暴く、歴史と記憶の断層
物語が後半に入ると、単なるナンセンスホラーかと思っていた「あしか汁」が暗い歴史とつながっていく。意味を持たないと思っていた記号に、途端に歴史的な重みが宿ってしまうこの瞬間はかなり恐ろしい。
そして本作最大の仕掛けは、読者もまた巻き込まれているという構造だ。「この本を読んでくれた方が、無事であることを祈ります」という語り手の言葉は、明らかに警告として機能している。
つまり、私たちが「あしか汁」の文字列を目にした瞬間から、もう話してしまっているわけだ。
従来の怪談が、恨みや呪いといった人間の感情に由来していたのに対し、本作は感情や動機を持たないただのデータが災厄をもたらす。
それが、今のネット時代にふさわしい恐怖の形に見えてしまう。
自分が触れたことで、次の誰かに飛び火する。
この拡散性の高さもまた、恐怖そのものだ。
「知らなきゃよかった」が本当に機能する、現代型情報ホラーの傑作。



意味のないはずの言葉が、歴史と死を引き寄せてくる。読後、確実に検索したくなくなる。
3.斉砂波人『堕ちた儀式の記録』
──フィールドワークが地獄の入口になるとき
こんな村に行かなければよかった系のフォーク・ホラーが盛り上がりを見せる中で、この作品は群を抜いて異質だった。
斉砂波人『堕ちた儀式の記録』は、民俗学的なフィールドノートの形式を模したモキュメンタリーでありながら、その情報の断片から立ち上がってくるのは、単なる田舎の怪異ではなく、科学とオカルトが癒着した不気味な知の闇である。
構成は二つの集落をめぐるレポート。東北の瀧来集落では、少女を囲んで男たちが無言で数珠を回す雨乞いの儀式が行われ、儀式後には少女が決まって失踪する。
民俗学×フォーク・ホラー=知ることの恐怖
四国の高山集落では、「オハチヒラキ」と呼ばれる霊力覚醒の禁忌儀式があり、これがどう考えても脳の何かを開いている気配を漂わせている。
どちらの儀式も現地大学生の手記やメモ、インタビューの断片として提示され、読者は断片から真相を読み解かされる構造だ。
こういう資料系ホラーにありがちな嘘っぽさが少ないのは、用語選びや地域描写のリアリティが異様に高いからだろう。さらにゾワッとしたのは、これらの儀式がファフロツキーズやロボトミーといった実在の科学現象・医療技術とつながっていく点である。
つまり、土着の奇習だと思っていたものが、国家規模の実験や人体制御のシステムと地続きかもしれない……という嫌な気づき。東北と四国、離れた地にある二つの村の儀式が根っこでつながっていたとき、自分の知っている日本の風土が、まるで別のものに見えてくる。
読み終えたときに全貌は明かされない。しかし、それがいい。
謎を解明するというより、未解決のまま胸に引っかかる歯車の欠片だけを残していくような読後感。
ネット上で考察が飛び交っているのも納得だし、何より「あの描写のあれってやっぱりそういうことだったのか……?」と後から気づかされる作りが最高だ。
ホラーというより報告書。怖いのは怪異ではなく、記録された事実の方だった。



資料形式を用いた日本版『ミッドサマー』。科学と民俗が手を結ぶ瞬間の、得体の知れない嫌さが最高だった。
4.藍上央理『完璧な家族の作り方』
── 呪いが家から広がる、ファウンド・フッテージ系ホラーの新機軸
この本はただのフィクションじゃない。そんな気配が、ページをめくる前から漂ってくる。
なんせ「noteで発表された新人賞作品を、作者の目的のために出版した」などという、現実とリンクした設定が施されている。しかもその目的というのが、ざっくり言えば「呪いの拡散」だ。読んだ時点で、もう巻き込まれているということになる。
舞台は北九州のボロ家。「虎ロープの家」と呼ばれる廃墟で、一家心中とその後の殺人事件が起きた場所だ。ここにまつわる怪異を描くため、作中にはさまざまなテキストが差し込まれている。
幼い筆致の手記、関係者の音声記録、取材メモや怪談まで、ジャンルの異なる断片がコラージュされており、ホラー小説というよりモキュメンタリードキュメントのような読み味を生む。
読んでいくうちにわかるのは、「この家に何があったのか」ではなく、「なぜ完璧な家族が呪いとして立ち上がったのか」が焦点になっていることだ。
写真という呪物と、家族の圧力
この本の最大の衝撃は、巻末に掲載された家族写真の存在だ。ぼやけた表情、不気味な構図。内容そのものも怖いが、それが実際に本に挿し込まれているという事実が、嫌でもリアルを侵食してくる。
これはもう、視覚的な呪物だ。作中でも「捨てても戻ってくる」「完璧な家族になれと強要してくる」といった性質を持っており、読者にもその呪いが波及する形になっている。
「太郎くんは優しい子」とか「お父さんは頑張っている」みたいな、家族内の理想像を押しつける言葉が、作品の随所に染みこんでいる。
つまりこの作品に出てくる怪異は、家そのものというより、完璧な家庭を演じなければならないという圧力そのものなのだ。
そしてそれを託された写真が、自分の本棚にそっと居座る──これが本作のいちばん怖い仕掛けである。
読むことが参加になる、次世代型ホラーの到達点。



ただの小説ではない。見るな、という警告ごと、すべてが仕掛けだ。
5.上條一輝『ポルターガイストの囚人』
──科学で怪異を解き明かす探偵たちの帰還
上條一輝の『ポルターガイストの囚人』は、あしや超常現象調査シリーズの第2作。
前作『深淵のテレパス』で「霊なんていない、あるのは現象だ!」と言わんばかりに論理で怪異を解き明かしたこのシリーズは、今回もそのスタイルは健在である。
主人公コンビの芦屋晴子と越野草太は、いわば論理探偵×科学調査員。除霊も呪文も使わない。ただ現象を観察し、仮説を立て、トライ&エラーで解明していく。
その姿勢はまるで自然科学のフィールドワークであり、今回も怖がらせる前にまず「観測」なのが面白い。
鳴る襖、落ちる遺影、映る影。ホラーの定番を分析する快感
舞台は、俳優・東城彰吾の実家。彼の身に降りかかる怪異は、クラシックなポルターガイストのオンパレード。
襖が勝手に開く、遺影が落ちる、こけしが動く、鏡に黒い何かが映る……どれも「そういうのあるよね」と思いつつ、上條はそこに物理法則をねじ込んでくる。
「この振動は電磁波か?」「鏡の角度は?」「家の構造上、風の通り道は?」と、芦屋たちはガチで分析しながら進む。怖がらせながらも理屈が通ってしまうのが本シリーズの快感であり、本作もその期待にきっちり応えてくれる。
ただし、今回の恐怖はその先にある。一連の怪異は論理で封じた。これで終わり……と思いきや、まさかの展開。ここで一気に空気が変わる。ロジックで整えたパズルに、ホラーの理不尽が割り込んでくるのだ。
ここで物語は、謎解きから侵食へと転じる。観測者だった芦屋と越野の周囲にも異変が起き始め、論理のフィールドが崩されていく。
安全圏など存在しない。
解決は、決して救済じゃない。
むしろ扉を開けてしまったのでは? という疑念が残るのだ。
芦屋&越野コンビの掛け合いも良い感じにこなれてきて、シリーズとしての安定感が光る一作。



探偵の推理が終わっても、ホラーは終わらない。そこに本作の恐怖がある。
6.岡崎隼人『書店怪談』
──本の世界で起きているのは、ただの怪異じゃない
これは本当に嫌な意味で刺さるモキュメンタリーだ。
『書店怪談』というタイトルから、ある程度の怖さは想像していたつもりだったが、まさかここまで本屋という空間が侵食されていくとは思っていなかった。
岡崎隼人は、メフィスト賞デビュー組の中でもかなりストイックな作風の印象があったが、本作ではがっつりメタフィクションに振り切ってきた。
主人公は作家・岡崎隼人。担当編集者と一緒に「書店にまつわる実話怪談」を集める企画が立ち上がる。……で、そうして完成した本が『書店怪談』。
つまり、いま手にしているこの本が呪われた本ということになる。
この入れ子構造だけでも勝ちだ。
書店が舞台というだけでゾクゾクしてしまう人へ
書店というのは、ふだんは安心できる場所として思い込んでいたはずなのに、本作の中では完全に恐怖の発信源として描かれている。
たとえば、書店員のエプロンの紐が、作業中にいつのまにか解けている。異界の子供が棚の間に立っている。レジカウンターに盛り塩がされている。「時間だよ」という謎の声が聞こえる。……どれもこれも地味なのに、やけにリアルで、気づくと背筋が冷えてくる。
この怪談たちが、最初はバラバラのようでいて、同じ何かに結びついていく構成が実にいやらしい。
しかも、それを集めている担当編集者の精神が少しずつ変調をきたしていくあたり、「これはもうホラーというより編集という名の儀式じゃないか?」という気分になる。この編集=怪異の媒介という発想がめちゃくちゃ好みだった。
そしてリアルな実在地名。岡山、実在の書店、実名に近い描写……これが効いている。もはや怖い話を読んでいるというより、現実の地層の下にある何かに触れてしまったような居心地の悪さがある。
これは、ホラー小説というより「呪術書」に近い感触なのでは?とすら思ってしまった。
書店にいるはずのない誰かが、背表紙越しにこちらを見てくる。そんな視線を想像してしまう作品。



編集者が集めるたびに、怪異が増えていくという恐怖のロジックが秀逸。
7.原浩『身から出た闇』
──呪術的編集システムが暴走するメタホラー
「この本ができあがるまでに、編集者が二人消えています」
ホラー作品の帯にはよくある誇張表現かと思いきや、『身から出た闇』においては、その帯すら作品構造に組み込まれた呪いの一部になっている。この攻め方は、かなり新しい。
著者は『火喰鳥を、喰う』で一躍注目された原浩。今回の新作は、本人名義の小説でありながら、その「原浩」自身が主人公として登場し、角川ホラー文庫の編集部と実際に短編集を編もうとするところから話が始まる。
しかも、短編を書いて提出するたびに、編集者が休職したり、失踪したり、どんどんいなくなっていく。書いている側もヤバいが、編集する側もヤバい。
つまり、作品を完成させようとする編集作業そのものが呪術なのだ。
フィクションが現実を壊していく
短編集は『トゥルージー』『裏の橋を渡る』『らくがき』など、どれも現代的かつ社会的な不安をベースにしたホラーばかり。
特に『トゥルージー』はスマホとSNSが命綱になっている若者文化を背景に、見てはいけないものがスクリーン越しに忍び寄ってくる感覚が恐ろしい。現代のホラーがどこに潜んでいるかを熟知している作者だと感じた。
そして面白いのは、これらの短編が単体で怖いだけでなく、原稿を提出したら担当者が消えるという実録パートとシームレスにつながってくるところだ。作品そのものが何かを呼び寄せる装置として機能しているのだ。ここが本当にうまい。
物語の外側すら怪異に飲み込まれていく。書籍のあらすじに「これは著者の強硬な意向により挿入されました」という文言があるあたりで、もう完全にフィクションの仮面は剥がれている。
本を読むという行為そのものが、封印を解く行為になってしまっているのだ。
タイトルの『身から出た闇』という言葉が、作者だけでなく、それでも手に取ってしまった人すべてに向けられている気がしてくる。
ちょっとした好奇心や興味が、自分の闇を招いてしまう。
そんな後味の悪さと背筋の寒さを、読み終わったあとも引きずる作品だ。
書き手だけでなく、編集者も読者も飲み込まれていくホラー。



編集という行為が、そのまま呪術になってしまうというアイディアに完全にやられた。
8.矢樹純『或る集落の●』
──因習村ホラーの最終形態、ついに紙で降臨
矢樹純が2015年に個人出版で発表し、一部マニアの間で「とんでもないのが出た」と密かに語り継がれていた幻の怪作『或る集落の●』が、ついに講談社から商業出版された。
『撮ってはいけない家』で一気にメジャーに躍り出た著者が、それ以前に書き上げていたこの連作集は、民俗ホラー×身体ホラー×メタホラーを見事に融合させた、因習村ホラーの決定版と言っていい。
舞台は東北の山中にある架空の寒村「P集落」。タイトルの「●(まる)」は、その集落が祀る何かの名を伏せるための記号だ。
呼んではいけない、書いてはいけない、知ってしまってはいけない。そんな存在が村の根底に横たわっている。
七つの怪談で構成されるP集落の地獄
この本は短編集という形式を取りながらも、すべての物語が「P集落」という異界に集束していく。
収録作は『べらの社』『うず山の猿』『がんべの兄弟』『まるの童子』『密室の獣』『天神がえり』『拡散にいたる病』の全七篇。どれも独立した話のようでいて、読み進めるごとに「これは同じ村の、同じ呪いのバリエーションなのでは?」という違和感が積もっていく構成が秀逸だ。
『べらの社』では、社に参拝した姉が徐々に人ではない何かに変貌していく。明確な描写は避けつつも、表情の乖離、言葉の使い方、足音の違和感といった細部で異常がにじむ描写はさすが。『うず山の猿』では、病気の治療のために、どんな病も治す猿がいるという集落に閉じ込められた「私」を悪夢が襲う。
明らかに因果があるのに、それを説明しようとする者がいない。沈黙が支配する村の気配が、皮膚感覚で迫ってくる。
個人的にもっともゾッとしたのは『まるの童子』だ。神の声を聞くため、幼い子供を社に閉じ込める風習。儀式のあと、戻ってきたその子は同じ顔をしているのに、何かが違う。完全にチェンジリング系の恐怖でありながら、描写があまりに淡々としていて、かえって冷える。
そして、最後の『拡散にいたる病』で、この連作の意味が大きく変わる。この怪談群が、どこからともなく集められ、盗作され、流布され、どこかで新たな村のモデルとして再利用されている。
つまり、物語の中で「P集落」の怪異は、すでに外部へと漏れ出しているのだ。
書籍として出版されることそのものが、感染を広げる儀式のように感じられる構造は、岡崎隼人『書店怪談』や藍上央理『完璧な家族の作り方』にも通じる現代ホラーの拡散性を意識しているように思う。
タイトルに「集落」とあると、ある程度の定番を想像してしまうが、本作はその定番に対するメタ的な更新を含んでいる。
もはや村は閉鎖されていない。
言葉にした瞬間、物語にした瞬間、それはどこへでも行ける。
そして、それが手元にあるこの本なのだ。
封印していた怪異を、出版というかたちで解き放ったような一冊。



どこかにある村の話ではない。どこにでも現れるかもしれない村の話だ。
9.ジャニス・プーン『ハンニバル・レクター博士の優雅なお料理教室』
──恐怖を美食へ変える、禁断のレシピブック
ジャニス・プーンによる『ハンニバル・レクター博士の優雅なお料理教室』は、マッツ・ミケルセン主演のTVシリーズ『HANNIBAL』の公式レシピ集である。
とはいえ、いわゆるタイアップ本の枠には収まらない。そこに並ぶレシピは「心臓のタルタルのタルト」「仔羊の睾丸のフライ」「肺とテンダーロインの赤ワインソース煮」など、あまりにも悪趣味すれすれの品々ばかり。
だが、完成された盛り付けの美しさと、極めて高い調理技術、そしてレクター博士の哲学に基づいた一皿一皿には、驚くほどの優雅さが宿っている。
ここで扱われているのは、もちろん本物の人肉ではない。豚、仔羊、レバー、キノコといった代替食材を巧みに使い、「人肉に見えるが違う」料理を作ることで、あくまでドラマ的な演出としての食人を成立させている。
その意味で本書は、食文化とフィクションの結節点にある異色のアートブックでもある。
カニバリズムとガストロノミーが交差する場所
この書籍が想定している読者層は明確だ。『HANNIBAL』という耽美で暴力的で詩的なシリーズに魅了されたファン、通称「ファンニバル(Fannibal)」である。
レクター博士のキャラクター性──知性、美意識、そして冷酷な捕食性──を、味覚という感覚領域から再体験するためのツールとして、この本は機能している。
実際、ジャニス・プーンの語り口は、愛と敬意に満ちている。「これは人肉ではありません」「レクター博士のように、献身と洗練をもって調理してください」といった文言は、単なる冗談に見えて、ちゃんと作品世界へのリスペクトと節度があるのだ。
危うさを演出しつつも、一線は越えない。そのバランス感覚こそが、この本の持つ危険な魅力を成立させている。
特に良かったのは、料理を美的演出として扱う視点だ。ジャニス・プーンは、キッチンを舞台に、料理人を芸術家として描く。
レクター博士にとって料理とは、ただの生存手段ではない。それは芸術であり、コミュニケーションであり、究極的には支配の道具である。
この本を手にすれば、彼の美学を安全に体験できる。そこが重要だ。
つまりこの本は、「悪」の表現がもつ二重性、嫌悪と魅了を、極めて優雅にデザインし直した装置である。
ホラーのファンブックとしても、異色の料理書としても成立してしまうこの企画力とデザインセンス。最高でしょ。
見るだけでも満足できるが、料理としてもちゃんと再現可能。鍋の中で生まれるレクター的世界を味わいたい人向け。



これは、キッチンで楽しむ「芸術としての食人」だ。美しさと悪趣味のギリギリを攻める美食ホラーの完成形である。
おわりに
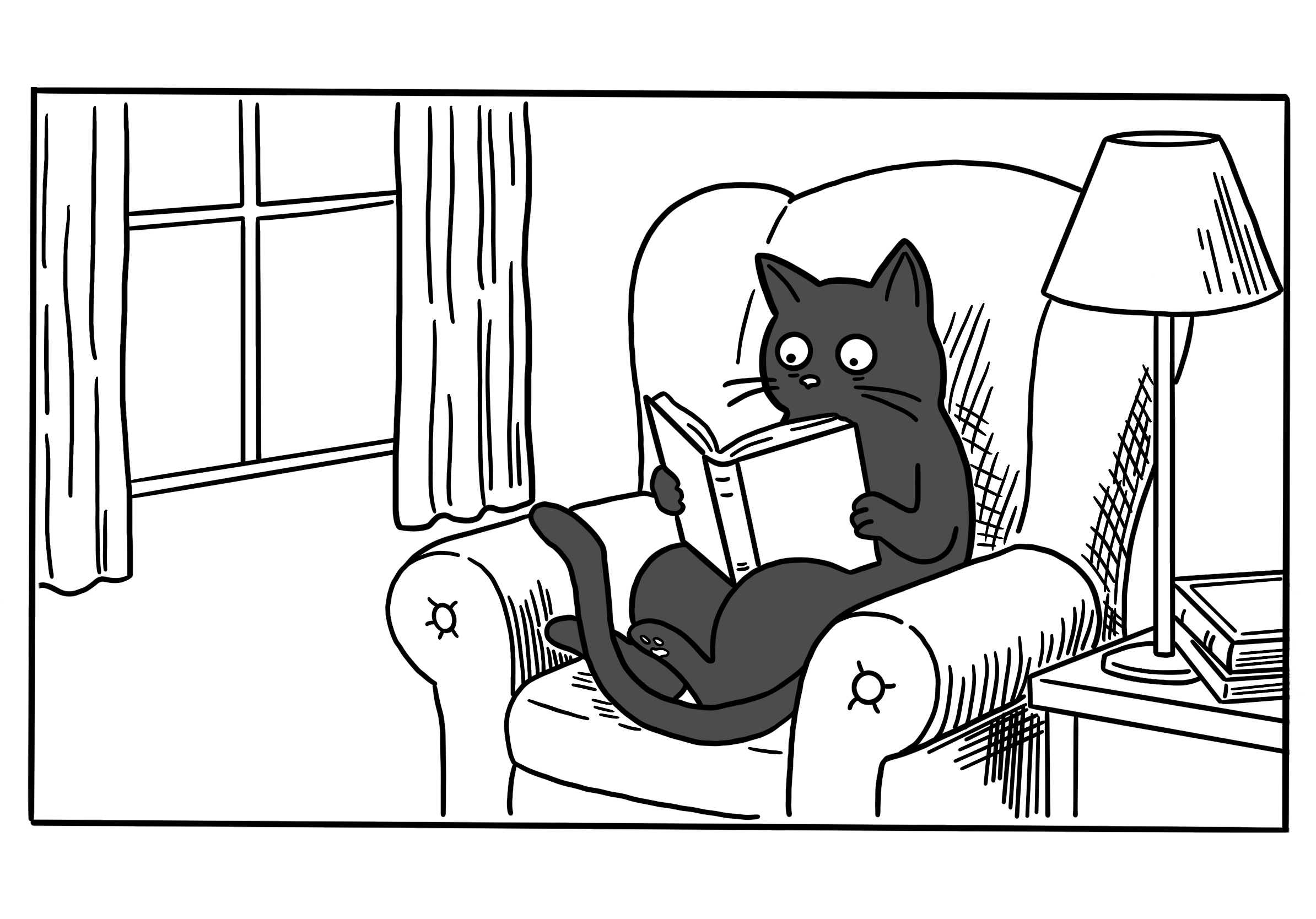
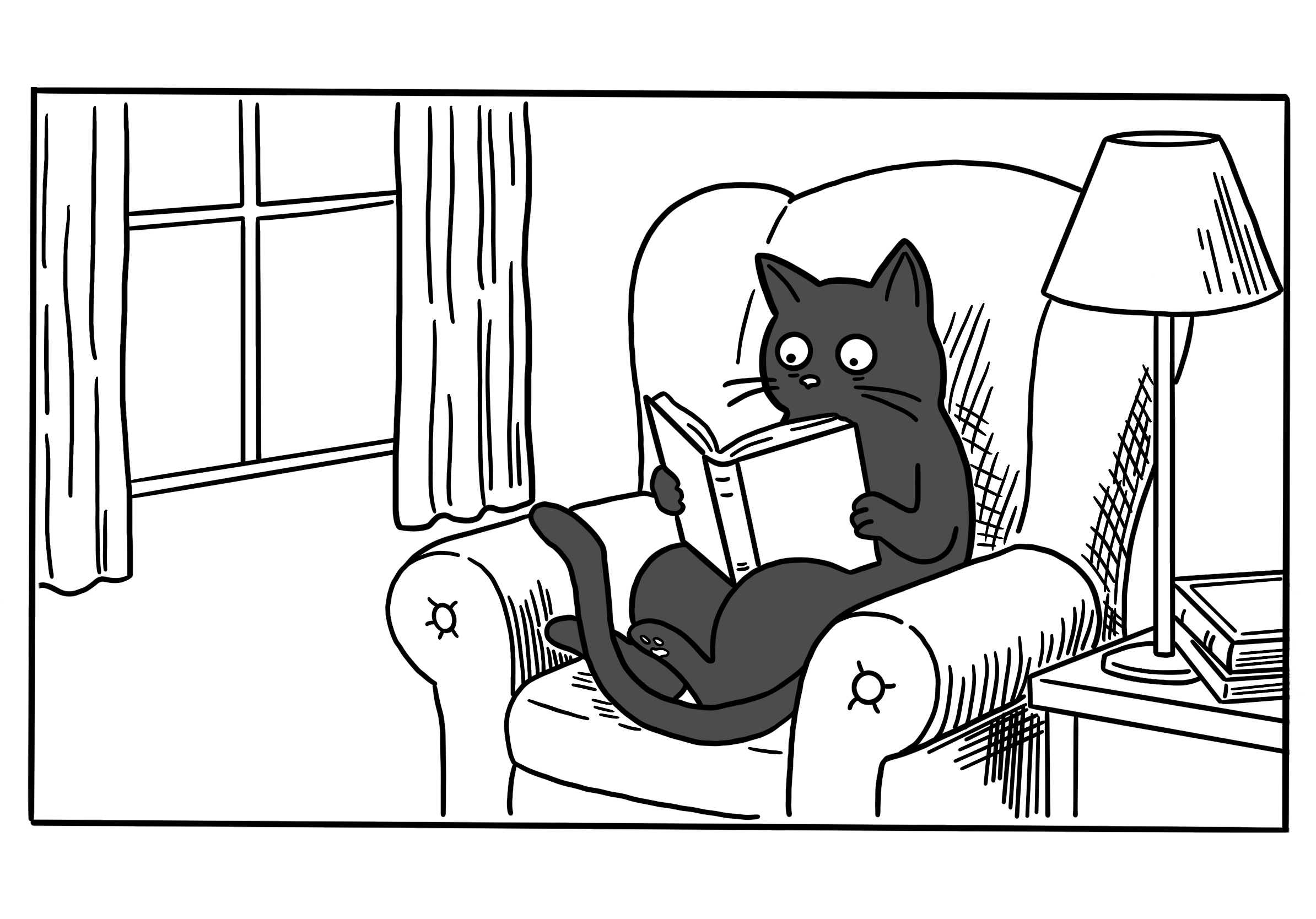
面白かった!
もうそれに尽きる。
緻密なロジック、予想を裏切る構成、ジャンルの枠を越える挑戦。それぞれの作品が、それぞれのやり方で面白さの限界を更新していたように思う。
ミステリーはまだまだ進化しているし、読み手の私たちも、いつまでも鍛えられ続けるばかりである。
今回ご紹介した53作品は、そんな修行のなかで特に心に残った作品たちだ。偏愛と勢いと少しの理屈で選んだけれど、どれも推したい気持ちに嘘はない。
どれもこれも、今すぐ誰かに語りたくなる傑作揃いだった。
来年もどんなトンデモトリックや破天荒探偵に出会えるのか、いまから楽しみで仕方がない。
来年もまた、知らない名探偵や新しい密室、とんでもないトリックのミステリに出会えますように。