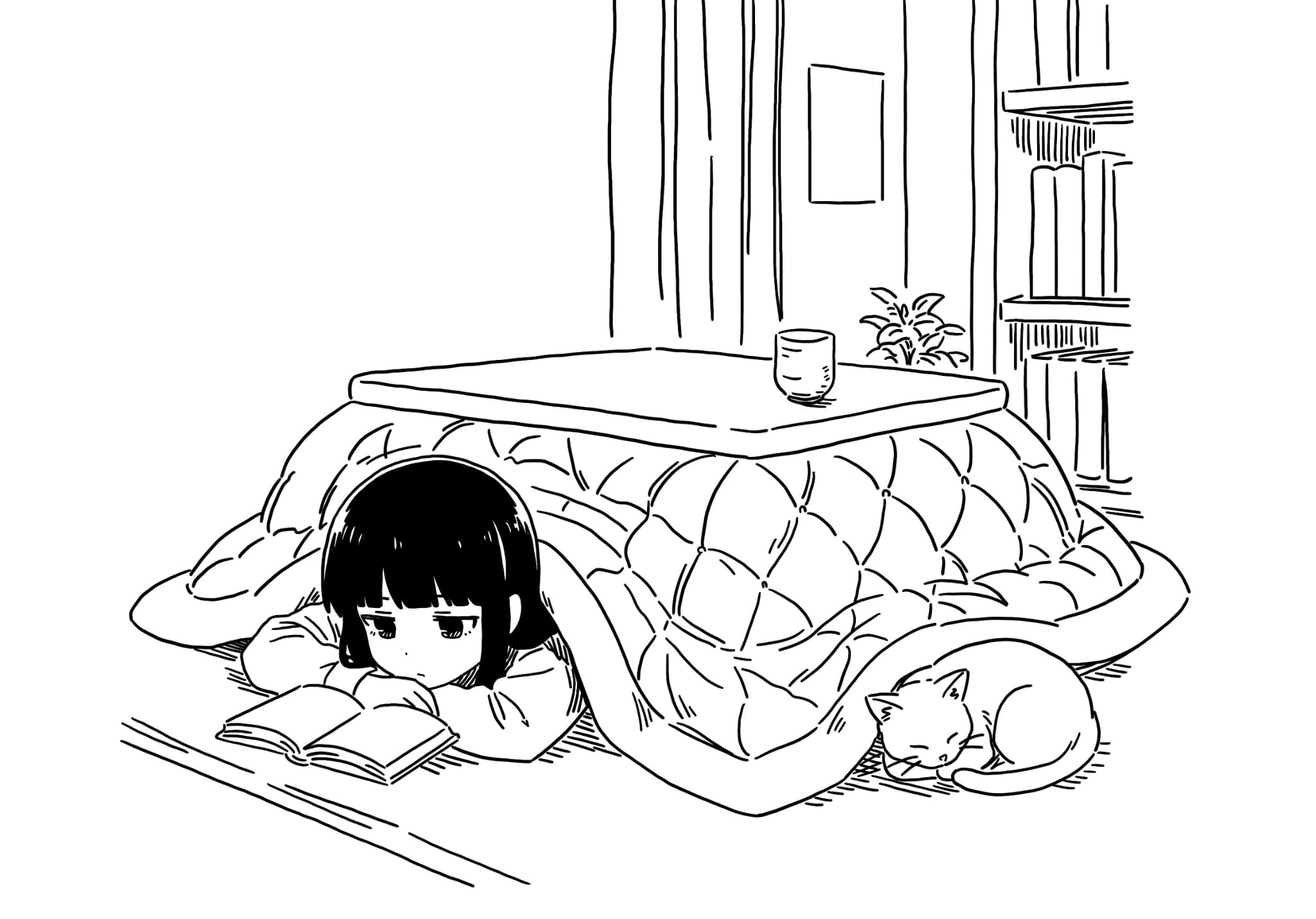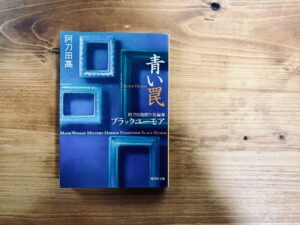四季しおり
四季しおり2025年10月に読んだ本の中から、特にこれは面白い!と思った15冊を紹介するぞ。
・2025年9月に読んで特に面白かった本15冊 – アンソニー・ホロヴィッツ『マーブル館殺人事件』ほか
・2025年8月に読んで特に面白かった本17冊 – パーシヴァル・エヴェレット『ジェイムズ』ほか
・2025年7月に読んで特に面白かった本10冊 – 夜馬裕『イシナガキクエを探しています』ほか
・2025年6月に読んで特に面白かった小説7冊 – 小倉千明『嘘つきたちへ』ほか
ベンジャミン・スティーヴンソン『真犯人はこの列車のなかにいる』
乗客全員、ミステリ作家。嘘つきしかいない密室へようこそ
「本書には、あらゆる形を含めて、犯人の名前はここから135回出てくることを前もって知らせておこう」
そんなとんでもない約束から始まるこの物語。語り手は駆け出しのミステリ作家アーネスト・カニンガム。
彼は、オーストラリア推理作家協会の50周年記念イベントに招待されるが、気がつけば舞台は、走る列車の中で起きた密室殺人。乗り合わせたのは全員が小説家。しかもひと癖もふた癖もある人たち。プロットを練り、アリバイをでっちあげ、嘘をつくことにかけては全員がプロ。
そんな列車の中で第二の殺人まで発生し、アーネストはついに決断する。「これはもう、ミステリのルールで解決するしかない」と。
これはトリックではなく、ゲームだ
この小説の何がすごいって、メタフィクションであることを最初から隠さないことだ。語り手アーネストは「双子は出てきません」「超常現象は禁止です」なんてことを宣言してから物語を始める。
つまりこれは、ミステリの黄金時代が築き上げたフェアプレイのルールを、あらかじめ読者と共有したうえでの知的な腕試しというわけだ。
しかも、ただの古典オマージュじゃない。たしかに『オリエント急行殺人事件』っぽい要素は満載だ。走る密室、容疑者だらけ、誰も信じられない。
でもこの作品は、そこに現代的なユーモアとメタ視点をぶっこんでくる。たとえば、語り手が「この展開、読者に怒られないかな」なんてつぶやいたりする。そんなのズルいに決まってる。けど、最高に面白い。
しかもこの物語、読み終えたあとで「ルールを全部守ってるのに、なぜか裏切られた」なんて感じになる。それは作者が、読者がミステリのルールを知っていることすら想定して、その上をいってくるからだ。
これは、トリックではなくゲームなのだ。「騙された!」じゃなくて「やられた!」と思わせる、その爽快感がたまらない。
ミステリに慣れた人ほど楽しく、初心者には少しクセ強め。でも、この乗客全員作家という密室劇は、ただの列車旅じゃ終わらない。あなたも、135回登場する「犯人の名前」を数えながら、このゲームに参加してみてほしい。
ルールは全部提示済み。なのに裏切られる。こんなミステリに出会えたことに、感謝。
『本好きに捧げる英国ミステリ傑作選』
本のための、本による、本をめぐる殺人
本が出てくるミステリに弱い。
それも、「探偵が本好き」とか「図書館で人が殺される」とか、そんなざっくりしたものではなくて、「本そのもの」がトリックや動機のど真ん中に関わってくるようなやつ。つまり、いわゆるビブリオミステリである。
この『本好きに捧げる英国ミステリ傑作選』は、そんなフェチ心に真正面から応えてくれる短編集だ。編者はマーティン・エドワーズ。
現代英国ミステリ界の顔役にして、黄金時代のミステリ再評価プロジェクトの立役者。彼が選んだ16編には、紙とインクと謎がぎっしり詰まっている。
英国ミステリ黄金時代の読書殺人事件コレクション
収録作はどれも「本」が主役。たとえば、盗まれた蔵書の中に奇妙な書き込みが残されていたり、人気作家がアリバイトリックを仕込むために新作原稿を悪用したり、あるいは単なる誤配の依頼状が殺意の引き金になったりと、とにかく紙の上で事件が転がる。
そして、登場人物は当然ながらみんな本に関わる人間たちだ。作家、書店主、編集者、コレクター、亡霊のような司書まで、紙と活字に取り憑かれたような面々が次々に出てくる。
作風も多彩だ。ニコラス・ブレイクやマイケル・イネスのような洒落っ気の効いたフーダニットから、クリスチアナ・ブランドの毒気あるブラックユーモア、さらにはヴィクター・カニングによる作家の「キャラ」崩壊スリラーまで。
とりわけエドマンド・クリスピンの『きみが執筆で忙しいのはわかってるけれど、ちょっとお邪魔してもかまわないだろうって思ったんだ』は、ある意味で書くことの地獄を描いたメタミステリであり、本好きというより「書く人間」が読んだら震える一編だ。
編者エドワーズの狙いは明快だ。これは「本というモノ」にまつわる物語であり、同時に「本を愛する人間」の暴走と妄執を描くアンソロジーでもある。しかも、単なる懐古趣味では終わらない。大英図書館が主導するクライム・クラシックス企画として、本書は過去の傑作を現代に再提示するプロジェクトの一環でもある。
選ばれた作品たちは、奇抜なトリックよりも、物語と本と人間の関係性に焦点を当てたものばかり。だからこそ、ミステリとしても文学としても読ませる力がある。
つまりこれは、ミステリ好きが「本好き」を拗らせた果ての一冊というわけだ。古本屋の棚で偶然見つけた希少本みたいな味わいが、ページのすみずみにまで宿っている。
読めばきっと、思うはずだ。
「本の中で殺されるなんて、本望じゃないか」と。
ジェフリー・ディーヴァー『スパイダー・ゲーム』
新コンビが挑む、サイバー時代の獲物狩り
殺人現場に現れるのは、蜘蛛のタトゥーを持つ謎の男。しかもそいつは、ただの殺人鬼じゃない。高性能な技術をバックに、人も情報もすり抜けていく、完全に今風の「怪物」だ。
その獲物を追うのが、現場主義の連邦捜査官カーメン・サンチェスと、安楽椅子からネット空間を制する諮問探偵ジェイク・ヘロン。真逆すぎるふたりがぶつかりながらも、南カリフォルニアを舞台にサイバー×殺人の迷宮に突っ込んでいく。
ディーヴァー節炸裂、でもどこか新しい
どこか既視感があるコンビ構成だ。 そう、あのライム&サックスを思い出すかもしれない。でもここでのヘロンは、動かないが傲慢ではないし、サンチェスも全然サブキャラじゃない。
むしろこのふたり、互いに自分の正しさを譲らず、まるで火花を散らすように対立しながらも、次第に機能していくのが面白い。ディーヴァーお得意の「ひっくり返し」も健在で、どのページからも油断できない感じがうれしい。
さらに、サイバー空間が戦場になることで、物語のスケールも変わってくる。ハッキング、情報攪乱、データの海に潜む犯人の影。もうこれは、探偵小説というよりサスペンス・アクションの粋に達している。スピード感はNetflixドラマ級、だが謎解きの快感はしっかり残っているあたり、さすがの手際だ。
この『スパイダー・ゲーム』は、新シリーズの一作目にして、すでに名刺代わり以上の完成度。共著に名を連ねたイザベラ・マルドナードのリアリティ重視の描写もいいアクセントになっていて、「ディーヴァー×現場経験者」という組み合わせの可能性を感じさせる。
新コンビ、ハイテク犯罪、頭脳と行動の二重奏。次も追いたくなる要素しかない。クラシックな警察小説が好きな人も、最先端サイバー犯罪スリラーが好みの人も、まずはこの獲物狩りに乗ってみるのがいいと思う。
『●●にいたる病』
変奏する狂気、拡散する病
「〜にいたる病」ときたら、ミステリ好きはもう条件反射であの一冊を思い出すだろう。そう、『殺戮にいたる病』。言わずと知れた日本サイコサスペンスの金字塔だ。
本書『●●にいたる病』は、そんな我孫子武丸の代表作に対する全力のオマージュであり、現代作家たちによる異常なリスペクト合戦である。
参加しているのは6名。神永学、矢樹純、背筋、真梨幸子、歌野晶午、そして我孫子武丸本人。お題は共通で、「●●にいたる病」。つまり、●●に何を入れるかは作家次第。その解釈の幅が、このアンソロジーを一気に面白くしている。
「殺戮」はもう過去のものなのか?
我孫子本人による『切断にいたる病』は、原作に最も近い不快で血まみれな一編。だが他の作家たちは、あえて外しにくる。
たとえば神永学の『欲動にいたる病』は、若者の歪んだ共依存と執着を淡々と描く。背筋は『怪談』を、矢樹純は『拡散』というワードで、物語そのものが感染する仕組みを構築。いずれも現代的な不穏さをまとっていて、いわば「ポスト殺戮」の世界観だ。
個人的に刺さったのは歌野晶午の『しあわせにいたらぬ病』。タイトルからして不穏だが、内容もやっぱり最悪だった。殺意が病として伝播していくというよりは、絶望の再生産という感じで、社会の構造そのものをぶった斬っている。ある意味、本書で一番ヤバい。
この本のすごさは、過去の怪物的作品にただ乗っかるのではなくて、そこから派生した「病」を、それぞれの作家が今の言葉で語っている点だ。初読時にトラウマになったあの衝撃を、別の角度から、別の温度で、また体験させてくれる。
「殺戮」はもはやゴールではない。時代が変わり、狂気のかたちも変わったのだ。6人の作家が描いたこの病の変奏曲は、我孫子武丸の遺伝子がどれだけ広く深く感染しているかを見せつける。
というか、みんな感染済みだったわけだ。
めでたく、手遅れである。
藤崎翔『オリエンド鈍行殺人事件』
殺人事件なのに笑えてしまうのはなぜか?
殺人事件が起きた。でも誰も推理しない。いや、一応しようとはするのだが、誰も名探偵ではない。結果、容疑者たちが犯人を探すどころか、なぜか自分たちの恋愛や人間関係を語り出し、事件とは無関係な悩みだけが解決していく。
それが表題作『オリエンド鈍行殺人事件』の大筋だ。アガサ・クリスティーのあの名作のパロディなのに、こんな展開でいいのか? いや、それでこそ本作の真骨頂である。
謎解きはどこへ? ミステリが日常に溶ける瞬間
元お笑い芸人という異色の経歴を持つ藤崎翔が描くのは、ミステリの仮面をかぶった人生の小ネタ集である。列車という密室設定は、通常なら論理的パズルの温床になるはずだが、ここではむしろ人間関係の圧力鍋となってしまう。
殺人事件をきっかけに、乗客たちは勝手に自己紹介を始め、暴露合戦を繰り広げ、最終的には事件そっちのけで人生相談大会に突入する。これがもう、バカバカしくて愛おしい。
収録された短編のどれもが、ツッコミどころ満載な展開で笑わせてくるのに、最後には意外な感動や余韻を残すのがずるい。とりわけ『勇者たちのオフ』や『ファーブル昆虫記を読んで』あたりは、オチの切れ味と後味の良さで印象に残る佳作だ。ミステリにおけるオチの概念を、笑いと驚きの両面で見せるセンスは抜群である。
藤崎翔の描くミステリは、謎を解く快感よりも、その途中で繰り広げられる人間模様に重きがある。言ってしまえば「コントの延長にあるミステリ」だ。それでいて、ちゃんとトリックも伏線もあるから驚きがある。その絶妙なバランスがいい。
『オリエンド鈍行殺人事件』は、ミステリのフォーマットを使って、まったく別のジャンルの面白さを生み出している。こんなにくだらなくて、こんなに面白い。殺人事件が起きているのに、なんだかほっこりする。
このズレとユーモアがたまらない、まさにジャンルの外側でミステリを遊び倒す一冊だ。
青柳碧人『クワトロ・フォルマッジ』
ピザと秘密と4人の視点
殺人事件の舞台になるのが、丘の上にぽつんと建つピザ屋。すでにその時点でミステリ心をくすぐられるが、さらにその事件の真相に迫るために必要なのが「4人の従業員の視点を4回繰り返して読む」ことだと知ったら、ちょっと面白そうだと思わないだろうか。
しかもその4人、なにやらそれぞれ秘密を抱えていて、ピザのようにトロけるどころか、内部はけっこうドロドロしている。
物語は、ある夜の突然死から始まる。客がピザを食べた直後にバタリ。警察が乗り込んでくる中、店内に残された4人の従業員たちは、それぞれの時間軸と立場で事件前夜の出来事を回想していく。
視点が変われば、事件も変わる
面白いのは、この作品が「繰り返し」で退屈させるどころか、逆に繰り返しによってどんどん情報の裏面を開示してくるところだ。ある視点では怪しく見えた言動が、別の視点では納得できる理由がある。
逆に善人に見えたあの人が、他の章では驚きの一面をさらけ出す。これが4回繰り返されるわけだから、同じピザでも具が変われば味がまるで違う、みたいな妙味がある。
視点人物のうちの一人が、いい意味で「何も知らない系」なのもポイントだ。全体の中で彼だけが異常にピュアすぎて、逆に他の3人の黒さが引き立つというか、こういうバランス感覚が青柳作品らしい。軽妙な会話とテンポ感、ちょいちょい挟まれる小ネタのようなユーモアも健在で、全体的にはライトなコメディミステリに仕上がっている。
事件そのものの謎解きは意外なほどシンプルだ。どちらかというと、本作の醍醐味は「人間関係のズレ」や「主観の食い違い」にある。誰が犯人か、というより「誰が何を知っていて、何を知らず、どう勘違いしているか」を探っていくゲーム。
つまりこれは、ピザ屋を舞台にした群像劇であり、多視点による心理のミステリであり、職場ドラマでもあるのだ。4種類のチーズが溶け合ってできた『クワトロ・フォルマッジ』というタイトルが、見事にこの作品の構造そのものを語っている。
トリック重視じゃないが、構成の妙とキャラの面白さで引っ張るタイプの変化球ミステリが好きなら、間違いなく楽しめる一作だ。
川瀬七緒『18マイルの境界線 法医昆虫学捜査官』
虫が語る、もう一つの真実
死体に群がるハエやウジが、事件の真相を語る。そんな風変わりな設定にピンと来たなら、このシリーズはど真ん中だ。
主人公は赤堀涼子。常識よりも虫に従う、変わり者の法医昆虫学者である。彼女が相手にするのは、証拠を徹底的に隠された遺体。歯も髪も指紋も潰された身元不明の死体が、ゴルフ場の藪とスクラップヤードで立て続けに発見されるところから物語は始まる。
捜査線上にはっきりした物証はない。だが、遺体に集まった虫たちは知っている。いつ、どこで、どうやって死んだかを。赤堀はその声なき証言を読み解き、人間たちの欺瞞をバッサリ切り裂いていく。
グロテスクと知性の絶妙なブレンド
本作の何がすごいかと言えば、題材の攻めっぷりだ。警察小説に科学捜査を絡めた作品は山ほどあるが、「虫」を主役に据えてここまでやるのはかなり珍しい。しかもハエやウジの種類、成長速度、気温や環境条件を使って死亡時刻を割り出すというガチ理系の推理が、物語に深みと説得力を与えている。
赤堀涼子というキャラもかなり個性的だ。人間相手にはちょっとズレた対応を見せるが、虫の扱いは誰よりも真剣。それが逆に好感度を高くしている。研究オタク系ヒロインの中でも、この「生々しさ」と「実務能力の高さ」のバランスはかなり絶妙である。
リアルすぎる死体描写と虫の描写は人を選ぶかもしれないが、それも含めてシリーズの味だ。むしろ、「ここまで描くか」という潔さが、本作を他の科学捜査ものと一線を画す理由になっている。
人間は嘘をつくが、虫はつかない。赤堀の捜査は、そんな自然界の法則に寄り添いながら、死者の真実を拾い上げていく。グロいし臭いし地味。でも、その先にある「納得」の感覚はやめられない。
昆虫好きでなくとも、ロジック重視のミステリ好きなら刺さること間違いなし。新しい証人のかたちを、ぜひ。
中山七里『バンクハザードにようこそ』
詐欺で正義をブチかませ!中山七里流・逆転バンクエンタメ
友人を殺された元・天才詐欺師が、悪徳銀行をターゲットに復活する。この一文だけでワクワクする人にはドンピシャの作品である。
主人公・東雲は司法書士というお堅い仕事の裏で、誰にも知られず詐欺師としての顔を持っていた。そんな彼のもとに届いたのが、親友・燎原の自殺の報せ。だが真相は、巨大銀行による捏造と冤罪。
怒りのスイッチが入った東雲は、封印していた才能を再起動。銀行を地獄に叩き落とす、華麗なコンゲームが幕を開ける。
毎回スカッと決まる詐欺パズル
詐欺と聞いて身構えるなかれ。本作の東雲は、腐った大企業に正義の制裁を下す清々しい悪党なのだ。不動産詐欺に未公開株、インサイダー取引……ありとあらゆる手法で敵を出し抜く。
そのやり口が実にスマートで、読みながら「よし、そこだ!」と叫びたくなるようなキメの連続。各部署を1話ずつ潰していくテンポも心地よく、まるで痛快な復讐劇の連ドラを見ている気分になる。
東雲は犯罪者であると同時に、読んでる側が感情移入できるアンチヒーローとしてしっかり立っている。仲間たちとの掛け合いもテンポよく、重たいテーマを扱いつつも、作品全体には軽快さと抜群の読みやすさがある。そこに加えて、しっかり中山七里お得意のどんでん返しも完備しているのだから最高だ。
敵となるのは、個人ではなく「銀行」という巨大な組織。これがまた絶妙だ。スーツで固めた偉そうな奴らを、詐欺という違法スキルでひっくり返していく姿に、無力感を覚えがちな現代人はきっとニヤリとする。大きなものに抗う痛快さとは、やっぱり物語の強力な燃料だ。
「正義は法の中にある」と信じたい。でも現実は、法の外でしか裁けない悪もいる。本作は、そんなギャップを軽やかに、そして痛快にぶち破ってみせる。詐欺師による銀行クラッシュ劇、ぜひその一撃を目撃してほしい。
はやせ やすひろ『ヤバい実家』
「血」と「家」にまつわる、逃げられない話
「家が怖い」なんて話は昔から山ほどあるが、本作『ヤバい実家』の怖さは格が違う。これは「家」の話というより、「血筋」の話。もっと言えば、どれだけ逃げても付きまとう、自分の出身に関するホラーである。
この本は、YouTubeチャンネル「都市ボーイズ」のメンバー・はやせやすひろ氏の体験と取材に基づいたエピソードを、小説家・クダマツヒロシが再構築した怪談集だ。
見たら死ぬ手鏡、何百年も怪異が続く家系、逃げても引っ越しても終わらない不吉な何か。そういった怪談が、実話ベースで淡々と語られていく。
実話怪談と物語のあいだで揺れる
この本の面白さは、単に怖い話を並べるだけで終わっていないところだ。主人公は、本人をモデルにした「怪異ハンター・はやせ」。でもこれはドキュメンタリーじゃなく、あくまでフィクションとして書かれている。つまり、本人の実体験をベースにしながらも、もう一人の「語り手としてのはやせ」がいるわけだ。
この構造が不思議な揺らぎを生んでいて、リアルと物語の境目がどんどん曖昧になっていく。YouTuberの話を別の作家が小説として語るというのは、ある意味すごく現代的なやり方だし、それ自体がひとつの実験的ホラーと言ってもいい。
家にまつわる呪い、呪物、奇怪な因習。それらはどれも古くさい題材に思えるかもしれないが、そこに「SNS時代の怪異」の切り口が差し込まれることで、一気にアップデートされている。
主人公が心霊スポットに赴く理由も、動画のため、調査のため、承認のためと多層的。迷信を疑いつつも惹かれてしまう感覚、科学とオカルトの狭間で揺れる視線。そのバランス感覚が絶妙だ。
「家からは逃げられても、血からは逃げられない」
この一文にゾッときたなら、本書のターゲットに間違いない。これは怖い話のふりをした、家族とアイデンティティにまつわる物語でもある。
実家が怖いのは、心霊現象だけじゃない。そんな現代的なヤバさを、丁寧かつ不気味にすくい上げている。
綿原 芹『うたかたの娘』
その美しさは、本当に彼女のものだったのか?
人魚伝説をベースに、幻想と記憶と語りの迷宮を描いた綿原芹の『うたかたの娘』は、ひとことで言えば「怪しくて切なくて、でもどこか刺さる」作品だ。
舞台は若狭の港町、そして語り手は「僕」。誰に語っているのかすら曖昧な語りのなかで、彼は高校時代の同級生・水嶋との記憶を少しずつ、まるで古い貝殻を拾い上げるように語っていく。
彼女は美しかった。そして言ったのだ。
「私、人魚かもしれん」
そこから始まる物語は、ファンタジーでもホラーでも青春小説でもあるのに、どれにもきれいには収まらない。記憶というフィルターを通して語られる水嶋は、現実にいたのか、それとも幻想にすぎなかったのか。語りの不確かさが、彼女の存在そのものを揺らがせる。
美しさと視線の物語
『うたかたの娘』は4つの連作短編から構成されていて、各話ごとに語り手が変わる。視点が変わるたびに、水嶋という存在の像が少しずつズレていくのが面白い。第3話『へしむれる』は特に強烈で、選考委員が絶賛したのも納得の異様さだった。
ただの人魚伝説じゃない。この物語が真正面から描いているのは、他人の目線に奪われる「美しさ」という呪いだ。水嶋の美貌は、彼女のアイデンティティを形成するどころか、彼女自身を「物語られる存在」へと変えてしまう。
語り手たちは、彼女を語ることで彼女を定義してしまう。まるで人魚の肉が「食べられる」ことで力を与えるように、美しさは他者に消費されてしまうのだ。
幻想と現実が混ざり合う海辺の町で、記憶が語られ、歪み、そしてまた語られる。『うたかたの娘』は、ジャンルを超えた異色作として、その独自の構造とモチーフによって強烈な読後感を残した。
人魚は誰だったのか?
そして、彼女の物語は本当に彼女のものだったのか?
語られた時点で、もう手遅れなのかもしれない。
芦沢央『おまえレベルの話はしてない』
夢は手に入れた瞬間から、呪いになる
将棋にすべてを賭けた男たちの物語、と聞いて「熱い青春物語」を想像したら痛い目に遭う。
芦沢央のこの小説は、その真逆を突き進むアンチ青春小説だ。タイトルからして刺々しいが、中身も容赦がない。奨励会というプロ棋士養成の世界で交差した、二人の男の業と執着がじっくりと描かれていく。
芝と大島、どちらも26歳。かつては同じ夢を見ていたが、今はまったく別の場所にいる。芝はプロ棋士になったが不調続きで心身ともにボロボロ。一方の大島は夢を諦めて弁護士になり、社会的には成功している。
しかし、将棋を捨てた後悔と嫉妬が、いまだに胸の奥に澱のように沈んでいる。この二人、勝った側も負けた側も全然幸せじゃないってところが、何とも苦い。
才能が奪うもの、夢が壊すもの
構成は前半・芝、後半・大島と視点が分かれている。芝パートでは、夢を叶えた人間がその夢に潰される様を、息詰まるようなリアルさで追っていく。大島パートでは、夢から逃げた人間が「未練」という名の鉄格子に囚われていることが明かされる。
この対比が強烈だ。「夢を追い続けること」も「夢を諦めること」も、どちらも救いじゃない。しかもそれを描く筆致がとにかく鋭い。他人の不幸に優越感を抱いた瞬間の自己嫌悪とか、嫌な感情の描写がやけにうまい。
本作の面白さは、「夢=美しい」という前提をぶっ壊してくるところにある。青春や努力を肯定しないわけではない。しかし、それらが人をどれだけ傷つけ、蝕んでいくかを描く視線が徹底している。将棋界という極端な世界の話ではあるが、夢と現実のギャップに苦しんだことのある人には、いやでも刺さる内容だ。
タイトルの『おまえレベルの話はしてない』は、登場人物の捻じれたプライドを象徴するセリフだが、同時に「どの立場にも逃げ場なんてない」という皮肉も滲んでいる。
夢を追っても、夢を捨てても、結局は自分自身と向き合わなきゃならない。この物語、将棋の勝ち負けを描いているようでいて、本当に語っているのは、「人生ってどうやって折り合いをつけるのか」ということなのかもしれない。
森バジル『探偵小石は恋しない』
その偏見ごと、きれいに裏切られる快感
どうせまた変わり者探偵と助手のコンビが、日常の謎をテンポよく解いていくライト寄りのコメディミステリだろう。
そんな風に思って読み始めたら最後、その思い込みこそが作者の最大の武器である。
森バジル『探偵小石は恋しない』は、近年の新作本格ミステリの中でもトップクラスに「うまい」作品だった。
主人公・小石はミステリオタクで、恋愛に無関心。なのに浮気調査が病的に得意という皮肉な体質の持ち主で、探偵事務所にやってくる依頼の大半は色恋沙汰ばかり。
助手の蓮杖との軽快なやりとりと、あっさりした日常ミステリ風の構成が続くのだが……終盤、すべてがひっくり返る。物語全体が、読む側の目の曇りを見越して仕掛けられた超精密な罠だったと気づいたときには、もう後戻りできない。
騙されたくて読むミステリ
小石と蓮杖の関係性をはじめ、章ごとに展開される浮気調査の数々は、最初こそ軽く読めるように見える。だがその裏では、細かい伏線とテーマが着実に積み上がっている。
作者が仕掛けるのは、社会的ステレオタイプへの批評だけではない。読者のジャンル慣れや犯人当ての勘そのものを逆手にとる、メタ的で、挑発的な構造なのだ。
何気ない一文、キャラの言動、視点の置き方。それら全部が後から効いてくる。気づいたときには、「やられた……」と、しばし放心。トリックに慣れてる人間ほどハマるタイプの仕掛けで、「再読必須」と言われるのも納得の構成だ。
ポップで読みやすいのに、テーマは骨太。伏線は緻密で、トリックは本格派。そして何よりも、ミステリを読める自分がいかに容易く騙されるかを、自覚させてくれる一冊だ。
『探偵小石は恋しない』
そのタイトルすらも、あらゆる思い込みへの反逆である。ミステリを読み慣れているなら、なおさら騙されてほしい。
そして、騙されたことに気づいたとき、きっと笑てしまう。
木爾チレン『神に愛されていた』
その愛は、崇拝という名の毒だった
小説家が小説家に殺意を抱く。しかもその動機が「崇拝」だったとしたら?
木爾チレン『神に愛されていた』は、作家と作家がぶつかる物語である。嫉妬と崇拝、愛と殺意。その境界線を限界まで曖昧にしながら、芸術家の心を容赦なく剥き出しにしていく。読んでいて胸が苦しくなるし、正直かなり怖い。でも、めちゃくちゃ面白い。
物語は、東山冴理という元天才作家が30年ぶりに口を開くところから始まる。ある編集者がやってきて、こう問うのだ。
「あなたが筆を折ったのは、白川天音が原因では?」
二つの視点で崩される真実
そこから語られるのは、あまりに眩しい後輩にすべてを奪われ、嫉妬にまみれた冴理の凄絶な半生。しかし、それは物語の半分にすぎなかった。
この小説、二部構成でまるごと印象がひっくり返る。前半は冴理の視点。出るわ出るわ、天音への恨みつらみ。「成功も恋人も執筆意欲も全部奪われた!」と、怒涛の勢いで語られる。その感情が痛いほど伝わってくるから、読んでいて天音を「悪役」にしたくなる。
ところが後半、語り手が天音に変わると一気に空気が変わる。タイトルの『神に愛されていた』は皮肉であり、真実でもある。冴理は天音という神に愛されていたし、天音もまた、神に選ばれたがゆえに滅びた。
愛と芸術の混ざり合う地獄のような世界で、二人はたしかに神に愛されていたのだ。いや、むしろ「愛されすぎた」のかもしれない。
エヴァ・ドーラン『終着点』
時間が逆流するサスペンス
この小説、やってくれた。殺人事件が起きて、それを隠蔽するところから物語が始まる。しかも、そこから先が「順行」と「逆行」の二本立てだ。
モリーという活動家の視点は未来へ向かって進み、エラという若い活動家の視点は過去へと巻き戻されていく。この構成が実にスリリングで、のめり込んでしまう。
事件は単純。集合住宅で男が死ぬ。エラが正当防衛を主張し、モリーがそれを信じて死体を隠す。この冒頭の「共犯成立」の瞬間から、物語は一気に緊張感を帯びていく。そして同時に、何かがおかしいというモリーの疑念も徐々に強まっていく。
時間を操る構成の妙
この小説の真骨頂は、なんといってもその構造にある。モリーの視点では、罪の重さとエラへの疑念が膨らんでいく。一方、エラの視点では「この事件に至るまでの一年間」が巻き戻されていき、彼女の行動と周囲の男たちとの関係性が明らかになっていく。
読者は誰が死んだのかすら明かされないまま、複数の被害者候補を前にして揺さぶられ続けるのだ。視点が進むほど真相が見えてくるのではなく、逆にズレが露わになっていくというのが面白い。
社会派サスペンスとしても優れていて、背景にはジェントリフィケーション、政治運動の表と裏、そして草の根活動の限界と腐敗が描かれる。だからこそ、エラとモリーの信頼がどれだけ危ういものだったかが効いてくる。世代も信条も違う二人の関係は、シスターフッドというにはいささか辛辣で、ほとんど師弟関係の崩壊ドラマに近い。
タイトルの『終着点』が意味するのは、事件の真相ではない。むしろ、SNS時代の活動家にとっての「自己イメージの崩壊」を意味している。
過去からの逆行によって明かされていくのは、若者の理想ではなく、その理想を守るためについた嘘。そして、年長者が信じていた正義の薄っぺらさである。
構造トリックと社会批評ががっつり噛み合った本格派。最後にたどり着く終着点には、想像以上に冷たい現実が待っている。
M・C・ビートン『アガサ・レーズンと月夜に消えた男』
探偵業より恋を取る?
コージーミステリといえば、ティーカップ片手に庭仕事、村人とのおしゃべり、時にはお菓子作り。
そんなイメージを根こそぎ吹き飛ばすのがこの作品。タイトル通りの月夜の殺人も気になるが、それ以上に爆発的な魅力を放つのが、主人公アガサ・レーズンのキャラだ。
物語の冒頭、アガサは探偵業を一時休業して、村にやってきたイケメン庭師ジョージの心を射止めようと躍起になっている。何せ村中の女性がライバルという状況。勝負をかけたアガサは、自ら舞踏会を主催するという大暴れっぷりを見せる。
だが当日、ジョージは現れず、彼の遺体が血まみれで見つかることに。悲しみよりも怒りが勝っていそうなアガサは、すぐさま探偵としてのスイッチをオン。舞踏会が殺人事件の幕開けになってしまう。
コージーっぽいのに、まったくコージーじゃない
コージーミステリにありがちな「心優しきおばあちゃん探偵像」とは真逆の存在、それがアガサ・レーズンだ。元PR会社の敏腕経営者であり、村に移住しても都会の毒気がまったく抜けていない。
無礼、虚栄心強め、料理は下手、恋愛にはがっつき気味。それでもなぜか憎めない。というか、だからこそ面白い。こういうキャラが村人たちとやり合うから、コージーミステリのテンプレがガンガン壊れていく。
本作の魅力は、殺人事件の謎解きと同じくらい、アガサと村社会のあいだに生まれる摩擦にある。誰とでもぶつかり、恋はこじらせ、事件には首を突っ込む。完璧からはほど遠いが、意志の強さと変な正義感で毎回なんとかしちゃうのが痛快だ。
つまりこのシリーズは、ジャンルのフォーマットを踏まえたうえで、そのお約束を軽く踏み倒していく。アガサ・レーズンは、コージーミステリの世界に殴り込んできた異分子であり、同時にこのジャンルを新鮮に生まれ変わらせた立役者でもある。
だから本作は、定番の型に飽きた人にも、むしろ型の魅力を知るためにも、どちらの立場からでも楽しめるという絶妙なバランスを持っている。
そう、これはコージーだけど、まったく「ぬるくない」ミステリなのだ。
関連記事